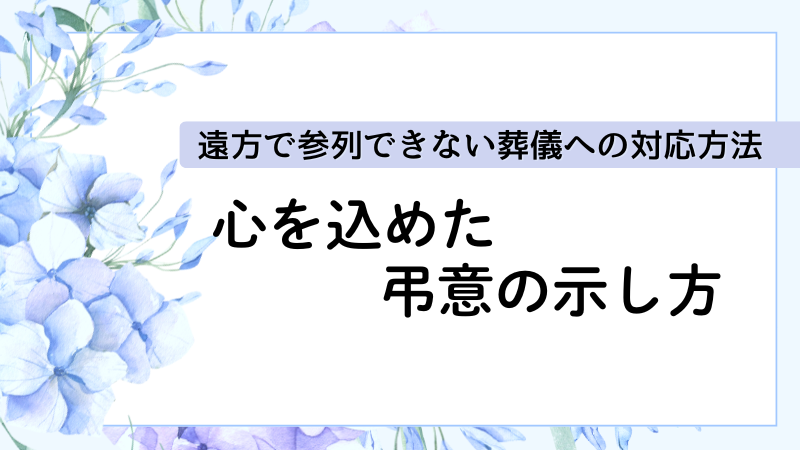大切な方の訃報を受けたものの、遠方にいて葬儀に参列できないという状況は誰にでも起こりうることです。参列したい気持ちがあるからこそ、どのように弔意を示せばよいのか悩む方も多いでしょう。
本記事では、距離や時間の制約がある中でも、心を込めてお別れの気持ちを伝える方法をご紹介します。
目次
弔電による弔意の表現

弔電(お悔やみ電報)は、遠方から弔意を示す最も一般的で確実な方法です。適切な文面と送るタイミングを知ることで、故人や遺族に対する敬意を表現できます。
ここでは弔電の基本的な送り方と注意点について詳しく解説します。
弔電の基本と仕組み
弔電は故人への最後のお別れの気持ちを文字にして伝える重要な手段です。電話やインターネットで申し込みを行い、指定した場所に電報を配達してもらうサービスです。通夜または葬儀の開始前に届くよう手配することが基本です。
弔電には様々な種類があり、シンプルなものから花や装飾が付いた豪華なものまで選べます。近年では、VeryCardのような専門サービスも登場し、利用者の選択肢が広がっています。料金や配達方法、デザインなどに違いがあるため、状況に応じて最適なサービスを選ぶことが大切です。
 弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
VeryCardのサービス内容
VeryCardは弔電専門のサービスを展開しており、豊富なデザインと文面が特徴です。オンラインで24時間申し込みが可能で、全国即日配達に対応しています。台紙のデザインが充実しており、故人との関係性に応じて適切なものを選べます。
また、宗教に配慮した文面を選べるため、失礼のない弔電を送ることができます。料金体系が明確で、追加料金の心配なく利用できる点も利用者にとってメリットです。
 格安弔電で評判!VERY CARDの特徴と使い方、文例、サービス比較(ベリーカード)
格安弔電で評判!VERY CARDの特徴と使い方、文例、サービス比較(ベリーカード)
NTT電報との違い
NTT電報サービスは、長年にわたり弔電の定番として親しまれてきましたが、現在では大幅にサービスが向上しています。「D-MAIL」というオンライン申込みサービスにより、24時間いつでもインターネットから申込みが可能になりました。午後2時までの申込み完了で全国当日配達に対応し、緊急時にも安心して利用できます。
料金面でも大きなメリットがあり、D-MAILでオンライン申し込みをすると、115番の電話申込みよりも440円お得になります。料金は台紙料金にメッセージ料を加算する仕組みで、必要最小限の費用で弔電を送ることができます。会員登録すると発信履歴の管理や電話料金との合算払いも可能です。
 NTT東日本・NTT西日本の弔電の送り方・申し込みの方法:「115」「D-MAIL」
NTT東日本・NTT西日本の弔電の送り方・申し込みの方法:「115」「D-MAIL」
一方、VeryCardなどの専門サービスは、より多様な選択肢を提供する新しいスタイルの弔電サービスです。490文字までのメッセージ込みの定額料金制が特徴で、文字数を気にせずに心のこもった文面を作成できます。台紙のデザインも豊富で、故人との関係性に応じて適切なものを選べます。
両者それぞれに特徴があり、確実性と実績を重視する場合は伝統あるNTTサービス、デザインの豊富さや定額料金制を重視する場合はVeryCardを選ぶなど、ニーズに応じて使い分けることが大切です。
心のこもった文面の作り方
弔電の文面は故人との関係性と宗教に配慮して選ぶことが最も大切です。「御逝去」「御冥福」は仏教用語のため、キリスト教や神道では使用を避けます。無宗教の場合や宗教が不明な場合は、「お悔やみ申し上げます」「謹んでお悔やみ申し上げます」といった一般的な表現が適切です。
文面作成時は「重ね重ね」「たびたび」「再三」などの忌み言葉を避け、故人への感謝の気持ちを込めることが大切です。長すぎる文面は避け、簡潔で心のこもった内容にまとめましょう。
定型文を基に、故人との関係性に応じて少しアレンジを加えることで、より個人的な弔意を表現できます。
確実に届けるための準備
弔電の送付先は、葬儀会場または喪主の自宅に指定します。会場がわからない場合は、葬儀社に確認することもできます。宛名は喪主の名前が分かる場合は「〇〇様」、不明な場合は「〇〇家ご遺族様」とします。差出人名は関係性が分かるよう、会社名や肩書きも併記することが大切です。
配達時間は通夜または葬儀の開始2時間前までに届くよう手配するのが理想です。当日の朝に届くよう前日に申し込むか、確実性を重視する場合は2日前に申し込むことをお勧めします。また、会場の受付時間を確認し、確実に受け取ってもらえるタイミングで配達されるよう配慮しましょう。
オンライン参加による弔問

近年、オンラインでの葬儀参列という新しい選択肢が登場しています。しかし、特に年配の方にとっては、技術的な不安だけでなく、心理的な抵抗感も大きな課題となっています。
ここでは、このような心理的なハードルを理解しながら、オンライン参加の意義について考えてみましょう。
葬儀に対する価値観の違い
多くの年配の方にとって、葬儀は「直接足を運び、故人の前で手を合わせるもの」という価値観が根強く残っています。長年にわたって培われてきた葬儀への向き合い方は、単なる習慣を超えて、故人への敬意を示す重要な行為として認識されています。そのため、画面越しでの参列は、本当の意味での「お別れ」ではないと感じる方も少なくありません。
このような価値観の違いは、決して間違いではありません。長い歴史の中で培われてきた葬儀の形式には、故人への敬意や遺族への配慮が込められており、それらを大切にする気持ちは尊重されるべきです。
新しい技術との間に生じるギャップは、単なる慣れの問題ではなく、葬儀に対する根本的な考え方の違いです。
オンライン参加への不安
オンライン参加において、多くの年配の方が感じる最大の違和感は、「画面越しでは故人への敬意が十分に伝わらないのではないか」という不安です。直接お焼香をあげることもできず、故人の顔を間近で見ることもできない状況では、本当にお別れができたのか疑問に感じるのは自然なことです。
また、葬儀の最中に技術的なトラブルが発生した場合、「故人に対して失礼にあたるのではないか」という心配も生じます。画面が固まったり、音声が途切れたりすることで、大切な瞬間を逃してしまう可能性があることも負担になります。
これらの不安は、故人への深い愛情と敬意の表れでもあります。
PC・スマホ操作と場の共有への課題

年配の方にとって、オンライン参加への抵抗感は技術的な不安だけではありません。スマートフォンやパソコンの操作に不慣れなことに加え、「機械に頼ることで、故人への気持ちが薄れてしまうのではないか」という心理的な抵抗もあります。これは、人生の大切な場面でデジタル技術に頼ることへの違和感です。
さらにオンライン環境では、他の参列者と静かな空間を共有したり、会場全体の厳粛な雰囲気を感じたりすることが困難です。葬儀特有の「場の空気」を体感できないことで、参列した実感が得られにくく、「本当に故人とのお別れができたのか」という疑問が残ることも少なくありません。
周囲のサポートと段階的な慣れが必要
一方で、遠方での生活や健康上の理由など、やむを得ない状況では、オンライン参加が唯一の参列方法となる場合もあります。このような状況において、「参列できないよりはオンラインでも参加したい」という気持ちを抱く年配の方も増えています。完璧ではなくても、故人との最後の時間を共有できることの価値を理解し始めている方も多いです。
家族や親しい人からのサポートを受けながら、段階的にオンライン参加に慣れていくことで、心理的なハードルは徐々に低くなっていきます。初回は戸惑いを感じても故人の姿を画面越しでも見ることができ、最後の言葉を聞くことができたという実感が、次第に「これも一つの参列の形だ」という理解につながることがあります。
香典や供花の手配方法

弔電やオンライン参加以外にも、香典や供花を贈ることで弔意を表現できます。適切な金額や手配方法を知ることで、遺族に対する心遣いを示せます。
ここでは、遠方からでも可能な香典や供花の手配について解説します。
香典の基本的なマナー
香典は、故人への供養の気持ちと遺族への経済的な支援を兼ねた大切な慣習です。金額は故人との関係性や自身の立場によって決まりますが、一般的には3,000円から10,000円程度が相場です。親族の場合はより多額になることもあります。
香典袋の選び方も大切で、故人の宗教に合わせて選ぶ必要があります。仏教の場合は「御霊前」「御仏前」、神道の場合は「御玉串料」、キリスト教の場合は「御花料」などが適切です。宗教が不明な場合は「御霊前」を選ぶのが無難です。
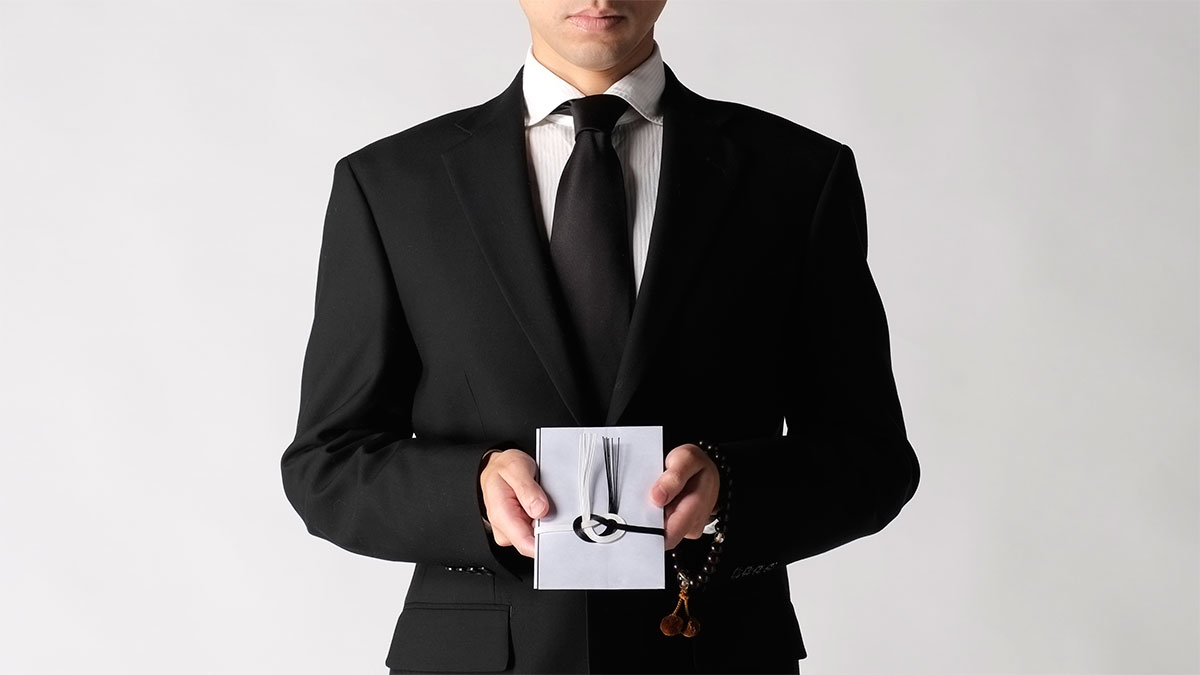 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
現金書留による香典の送り方
遠方から香典を送る場合は、現金書留を利用するのが一般的です。香典袋に現金を入れ、さらに現金書留用の封筒に入れて郵送します。送り先は葬儀会場または喪主の自宅になりますが、事前に遺族に確認することをお勧めします。
現金書留には簡単な手紙を添えることができます。お悔やみの言葉と、参列できないことへのお詫びを記載しましょう。「この度は御愁傷様でございました」「遠方のため参列できず申し訳ございません」といった内容が適切です。
参考 書留日本郵便株式会社供花の注文と手配方法
供花は故人への供養と会場の装飾を兼ねた弔意の表現方法です。葬儀社に直接連絡して手配するのが最も確実で、会場の雰囲気に合った花を選んでもらえます。費用は10,000円から30,000円程度が一般的で、花の種類や大きさによって異なります。
インターネットを通じて供花を注文できるサービスも増えています。花キューピットやイーフローラなどの全国展開している花屋のネットワークサービス、楽天市場やAmazonといったオンラインモールの供花サービス、葬儀社と提携しているオンライン花屋などがあります。
これらのオンラインサービスは24時間申し込みが可能で、当日配達に対応している業者もあります。ただし、葬儀会場によっては外部からの供花を受け付けない場合もあるため、事前に確認することが大切です。
供物の選び方と送り方
供花以外にも、線香や果物などの供物を贈ることも可能です。線香は日持ちがよく、故人の供養に長期間使用できるため喜ばれる品物です。果物の場合は、りんごやオレンジなどの日持ちするものを選びましょう。
供物も現金書留と同様に、宅配便で送ることができます。ただし、生花や生果物は日持ちの問題があるため、葬儀の前日または当日に届くよう手配することが大切です。のし紙は「御供」と記載し、差出人の名前を明記します。
後日弔問に訪れる際のマナー

葬儀に参列できなかった場合、後日弔問に訪れて弔意を表現することができます。ここでは、適切なタイミングとマナーについて解説します。
弔問に伺う最適なタイミング
後日弔問は、一般的に四十九日法要までに行うのが適切です。ただし、葬儀直後は遺族が忙しく、精神的にも疲れているため、少し時間を置いてから訪問する配慮が必要です。一週間から一ヶ月程度の間に訪問するのが理想です。
訪問前には必ず遺族に連絡を取り、都合の良い日時を確認しましょう。突然の訪問は遺族に負担をかけます。電話での連絡が基本ですが、メールやメッセージでも構いません。
短時間での訪問を心がけ、長居は避けることが大切です。
 葬儀に出れない!後から知った!葬儀後のお悔やみの仕方(弔電・香典・後日弔問)
葬儀に出れない!後から知った!葬儀後のお悔やみの仕方(弔電・香典・後日弔問)
弔問時の服装と持参するもの
後日弔問の際は、地味な色の服装を着用します。喪服である必要はありませんが、黒やグレーなどの落ち着いた色合いの服装が適切です。アクセサリーは控えめにし、派手な装飾は避けましょう。
持参品として香典や供物、お菓子などを用意します。香典は葬儀で渡せなかった場合に持参し、金額は葬儀の際と同程度が適切です。お菓子は日持ちするものを選び、のし紙には「御供」と記載します。花を持参する場合は、仏花や供花として適切なものを選びましょう。
弔問時の挨拶と過ごし方
弔問時の挨拶は簡潔で心のこもったものにしましょう。「この度はご愁傷さまでした」「お忙しい中、時間をいただきありがとうございます」といった言葉が適切です。故人との思い出話をする場合は、明るい思い出を中心に短時間で話すようにします。
仏壇がある場合は、お参りをさせていただくことを申し出ます。線香をあげる際は、遺族の案内に従って行いましょう。宗派によって作法が異なるため、分からない場合は遺族に尋ねることも大切です。
滞在時間は30分から1時間程度に留め、遺族の負担にならないよう配慮します。
弔問を控えた方がよい場合
遺族が弔問を遠慮している場合や、故人の遺志により弔問を受け付けていない場合は、無理に訪問することは避けましょう。また、遺族が引っ越しをしている場合や、連絡が取れない場合も弔問は控えるべきです。弔意を示したい気持ちは尊重されるべきですが、故人や遺族の気持ちを尊重し、無理のない範囲で対応することが大切です。
感染症が流行している時期や、自身の体調が優れない場合も弔問は控えるべきです。遺族の健康を考慮し、別の方法で弔意を示すことを検討しましょう。無理をして訪問することは、かえって迷惑をかけることになります。
まとめ

遠方で葬儀に参列できない状況は、誰にでも起こりうることです。そのような時でも、弔意を示す方法はたくさんあります。弔電、オンライン参加、香典や供花の手配、後日弔問など、それぞれが故人への想いを伝える大切な手段です。
何より大切なのは、故人への敬意と遺族への配慮を忘れないことです。新しい技術による方法も昔からの方法も、どちらも有効な選択肢です。参列できない状況でも、気持ちは必ず伝わります。心を込めて選んだ方法で、故人との最後のお別れを大切にしてください。