余命を宣告されることは、人生で最も辛く衝撃的な出来事の一つです。突然「残された時間が限られている」と告げられれば、本人もご家族も大きな不安や悲しみに襲われるでしょう。それでも、限られた時間をどう過ごすか、そして旅立ちの後の準備をしておくことは、残りの人生を有意義にし、ご自身と周囲の人々の負担を軽くする助けになります。この記事では、余命を宣告されたご本人が死の前に準備しておくべきことを、実用的かつ寄り添いの視点で6つにまとめました。どれもすぐに始められることばかりです。無理のない範囲で少しずつ取り組んでみましょう。
目次
1. 財産の整理と相続の準備
限られた時間の中でまず取り組みたいのは、財産の整理です。自分の財産状況を把握し、残された家族が相続手続きをスムーズに行えるよう準備しておきましょう。
-
預貯金・口座の整理: 口座が複数ある場合は主要な銀行口座にまとめ、不要な口座は解約することを検討します。ネット銀行を利用している場合は、IDやパスワードも分かるように記録しておきましょう。口座を整理しておくことで、亡くなった後の相続手続きの手間を減らせます。
-
保険証券や重要書類のまとめ: 加入中の生命保険や医療保険の証券、不動産の権利書などは一箇所にまとめて保管し、家族にも場所を伝えておきます。いざというとき必要な書類がすぐ見つかれば、残された家族の負担が軽減されるでしょう。
-
資産の名義と現金化: 名義変更していない不動産(土地・建物)があれば、生前のうちに現所有者に変更しておきます。また、有価証券や株式など運用資産があり、相続発生後に相続税支払いのため現金が不足しそうな場合は、事前に一部を現金化しておくことも検討してください。納税資金を用意しておけば、家族が慌てずに済みます。
-
財産目録の作成: 自身の財産を一覧できる財産目録を作りましょう。預貯金や不動産だけでなく、負債(借入金や未払いの税金等)があればそれも含め、全体像を明確にします。財産目録は市販のエンディングノートを活用しても良いでしょう。
加えて、相続のための法的準備も大切です。具体的には遺言書の作成を検討しましょう。遺言書というと「自分には大した財産がないから必要ない」「家族仲が良いから揉めないはず」と思うかもしれません。しかし遺言書には、財産額の多少にかかわらず遺産分割の手続きを円滑にし、相続争いを未然に防ぐ効果があります。特に以下のようなケースに当てはまる方は、公正証書による遺言書を用意しておくことが望ましいです。
-
法定相続人以外に財産を譲りたい人がいる場合(お世話になった方や内縁のパートナーなど)
-
相続人の中に認知症の方や行方不明の方がいる場合
-
再婚しており、前妻・後妻との子どもがいる場合 など
遺言書は自筆証書遺言(自分で全文を書く)と公正証書遺言(公証人役場で作成)の2種類があります。エンディングノートに遺産の希望を書き残しても法的効力はないため、正式な遺言書として残すことが重要です。遺言書があれば、残された家族は家庭裁判所での検認や相続手続きがスムーズになり、精神的負担も軽くなります。
また、財産が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は相続税対策も考えておきましょう。例えば、生前にできる節税策の一つに生前贈与があります。相続人やその配偶者以外の方(お孫さんやお嫁さんなど)に毎年110万円まで贈与することで、贈与分を相続財産から減らすことができます。この金額内であれば贈与税が非課税になるうえ、亡くなる前3年以内の贈与でも相続財産に加算されないため有効です。ただし、贈与を受けた方が相続で生命保険金を受け取る場合など一部例外もあるため注意が必要です。まとまった資産があり専門的な対策が必要な場合は、税理士など専門家に相談すると安心です。
■関連記事
 【節税】相続税を大幅に安くする鍵は相続人の数にあり!相続人を増やす方法と注意点を解説| 国税OB 税理士 秋山清成
【節税】相続税を大幅に安くする鍵は相続人の数にあり!相続人を増やす方法と注意点を解説| 国税OB 税理士 秋山清成
2. エンディングノートの活用方法と重要性
エンディングノートに大切な情報や想いを書き残しておけば、残された家族が迷ったときの道しるべとなります。
自分の想いや希望をまとめて書き残せるエンディングノートは、終活における心強いツールです。エンディングノートとは、医療・介護の希望や財産の情報、葬儀の要望など、人生の最期について伝えておきたいことを自由に記録しておくノートのことです。法的な書式が定まっている遺言書とは異なり、エンディングノートには決まった形式はありません。市販の専用ノートを使っても良いですし、手持ちのノートに自分の言葉で綴っても構いません。大切なのは、「自分が亡くなった後に家族が必要とする情報」や「自分の気持ち・メッセージ」をわかりやすく残しておくことです。
エンディングノートに書いておきたい主な項目は次の通りです。
-
基本的な本人情報(氏名、住所、生年月日)
-
家族・親族の一覧(配偶者や子ども、兄弟姉妹などの氏名・住所・連絡先)
-
主治医・かかりつけ病院の連絡先
-
延命治療についての希望(胃ろうや人工呼吸器の装着を望むかなど)
-
葬儀に関する希望(葬儀の規模や形式、喪主を誰にお願いしたいか、宗教・宗派の希望など)
-
財産・保険に関する情報と連絡先(預貯金口座、証券口座、不動産、保険契約先などの一覧)
-
通帳や印鑑、権利証など重要書類の保管場所
-
お世話になった方々へのメッセージ(家族や友人への感謝の言葉、伝言など)
上記は一例ですが、最低限これだけは伝えたいという内容を盛り込んでおくと、残された家族にとって大きな助けとなるでしょう。たとえば延命措置について本人の希望が分かっていれば、いざという時にご家族が判断に迷わずに済みますし、葬儀の希望が書いてあれば「どんな形で送りたいのか」と家族が悩まずに済みます。財産の所在や各種連絡先がまとまっていれば、相続手続きや各種解約手続きもスムーズに進むでしょう。
エンディングノートは思いついたときに少しずつ書き進めていくことをおすすめします。残された時間がまだあるうちに、体調の良い日を見計らって少しずつ項目を埋めてみましょう。最初から完璧に仕上げる必要はありません。一度書いた内容も後で訂正・追加できますので、気軽に始めてみてください。終活の定番とも言えるエンディングノートですが、書き進める過程自体が気持ちの整理にもつながるかもしれません。自分の人生を振り返り、大切な人たちのことを思い浮かべながら書く時間は、きっと残りの人生をより悔いなく過ごす一助となるでしょう。
なお、繰り返しになりますがエンディングノートは法的な効力を持ちません。財産の分け方など相続に関する希望を書くこと自体は問題ありませんが、それだけでは法律上の遺言書とはならない点に注意しましょう。あくまで家族へのメッセージや情報共有の手段として活用し、正式な遺産分割の指定は前述のように遺言書で行うようにしてください。
3. 心の整理(後悔を減らし感謝を伝える)
余命を告げられたとき、胸中には様々な心残りや「やり残したこと」が思い浮かぶかもしれません。「もっと○○しておけばよかった」「あの人にまだ伝えていないことがある」といった後悔の念が出てくるのは当然のことです。限られた時間を後悔の少ないものにするために、今からでもできることがないか考えてみましょう。
やりたかったことに挑戦する

「いつかやりたいと思って先延ばしにしていたこと」はありませんか?残された時間で叶えられる範囲で、ぜひやりたいことに挑戦してみましょう。例えば、体調が比較的安定しているのであれば短期間の旅行に出てみるのも一つです。「人生で一度は行ってみたかった場所」に日帰りや一泊で出かけてみたり、難しければ近場で好きな風景を見に行くのも良いでしょう。医師の許可を取り、無理のない範囲であれば、数日程度の旅行は可能なケースもあります。他にも、「最後に美味しいものを思い切り味わいたい」と好きな料理を楽しむ方もいます。闘病中は食事制限をしていた方も、余命がわずかと分かった時には「もう体のことは気にせず好きな物を食べたい」という思いを持つこともあるでしょう。食べる喜びや行きたい所へ行く喜びは、生きている今だからこそ味わえる大切な時間です。それを家族や友人と共に実現することで、かけがえのない思い出を作ることができます。そうした思い出は、やがて訪れる別れの時に自分や家族の悲しみを和らげ、心に温かく残る財産となるでしょう。
ただし、大切なのは「やりたいことを全てやらなければいけない」と自分を追い込まないことです。体調や気力には日々波がありますから、その日の状態に合わせて無理のない範囲でできることから取り組んでみてください。例えば調子が良ければ外出してみる、難しければ自宅で映画を見るなど、小さなことで構いません。周囲も「何とかして叶えてあげなきゃ」と焦る必要はありません。大切なのは本人の気持ちに寄り添うこと。やりたいことを一緒に考え、可能な範囲でかなえていく――その過程自体が、本人の人生の最期に寄り添う時間になるのです。そうした時間を持つことで、ご本人にとってもご家族にとっても「できる限り悔いの残らない時間を過ごせた」という安心感につながるでしょう。
大切な人との関係を見直す

心残りを減らすために、人間関係の整理も大切です。もし「謝りたい相手」や「伝えたい思いがある人」がいるなら、この機会に連絡を取ってみてはいかがでしょうか。直接会うのが難しくても、電話や手紙でも構いません。「あの時はごめんなさい」「あなたのおかげで幸せでした」――伝えそびれていた謝意や感謝の気持ちを伝えることで、長年のわだかまりが解けることもあります。それは相手の心を軽くすると同時に、自分自身の心の重荷が下りるきっかけにもなるでしょう。実際、余命がわずかと分かった方の中には「大切な人にきちんとお礼を伝えたい」という願いを持つ方が多いといいます。
たとえば、昔お世話になった恩師や親友に久しぶりに連絡を取るのも良いでしょう。「急に会いに行って迷惑では…」「病状を知られて心配をかけたくない」と悩むかもしれません。そんな時は、「あなたに伝えたい感謝があるから会いたい」と正直に思いを伝えてみてください。「自分の人生を楽しいものにしてくれた」「お世話になったのでお礼が言いたい」といった気持ちを事前に伝えておけば、相手も安心して会いに来てくれるでしょう。実際に会えたときは、決して沈痛な雰囲気になる必要はありません。できるだけ笑顔で楽しいひとときを過ごすことを心がけましょう。面と向かって「ありがとう」を伝え、互いに笑顔で語り合えれば、きっと心残りが薄らいでいくはずです。きちんとお礼が言えたという事実は、ご自身にとっても大きな安心となり、最期の時を穏やかな気持ちで迎える助けになるでしょう。
専門家の力を借りる
心の整理には時間がかかりますし、一人ではどうにもならない不安や恐怖もあります。もし気持ちが不安定で眠れない、不安で押しつぶされそうだと感じるときは、専門家のサポートを受けることも検討してください。主治医や看護師に相談すれば、医療ソーシャルワーカーや臨床心理士、緩和ケアの担当者などにつないでもらえる場合があります。また、がん相談支援センターや地域のホスピスなどには心理カウンセラーが在籍していることもあります。カウンセラーや精神科医に話を聞いてもらうことで、孤独や恐怖が和らぎ、残された時間をどう過ごすか前向きに考えられるようになるかもしれません。「心のケアはプロに任せていい」と割り切り、抱え込まないことも大事です。周囲の家族や友人にも気持ちを打ち明け、適度に感情を共有してください。悲しみや不安を一人で抱え込まず、人の支えを借りながら、少しずつ心の平穏を取り戻していきましょう。
4. 家族・友人へのメッセージの残し方
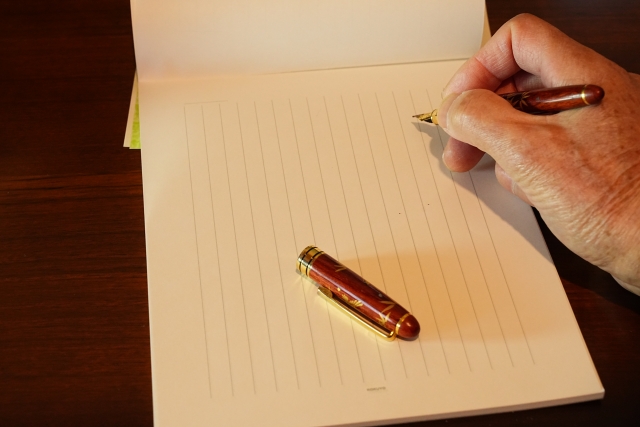
自分に万一のことがあった後、残された大切な人たちにメッセージを残しておきたいと思うのは自然な感情です。面と向かって伝える時間がもう十分にない場合でも、手紙やビデオメッセージといった形で思いを託すことができます。
メッセージを伝える方法に決まりはありません。口頭で直接伝えてもいいですし、後で読んでもらう手紙に書いて残すのも良いでしょう。最近ではスマートフォンで手軽にビデオレターを撮影することもできます。実際、多くの余命わずかな方が家族や恋人、恩師や友人に「最後のメッセージを伝えたい」と望んでおり、その手段として手紙を書いたりビデオレターを準備するケースも多いようです。
伝える内容は自由ですが、普段なかなか面と向かって言えない感謝の気持ちや、心配をかけたことへのお詫び、そして「愛しています」「幸せになってね」などの想いを綴る方が多いようです。これまで言えずにいた本音を手紙に書くことで、自分の心の中のモヤモヤが晴れ、清々しい気持ちになれるかもしれません。メッセージを残すことは自分自身の心の整理にもつながるのです。
手紙を書く場合は、一人ひとり宛てに別々の手紙を用意するのも良いでしょう。便箋に丁寧に書かれた手紙は、受け取った相手にとって一生の宝物になります。何度でも読み返すことができるため、相手が寂しいときや励ましが欲しいときに、あなたの言葉が支えとなるでしょう。ビデオレターであれば、あなたの声や表情とともに思いを届けることができます。お子さんやご家族に向けて、「◯◯のときはこうしなさい」「ずっとあなたの幸せを願っているよ」といったメッセージを動画で残しておけば、きっと後で大きな支えとなるはずです。最近ではビデオレターの作成サービスを提供している会社もあり、プロの手を借りてしっかりした映像を残すこともできます。そこまで本格的でなくても、スマホで自撮りした簡単な動画でも十分気持ちは伝わります。
メッセージは今の自分の気持ちを素直に伝えることが何より大切です。長さや形式にとらわれず、「ありがとう」「ごめんね」「愛している」といった短い言葉でも構いません。伝えたい相手一人ひとりの顔を思い浮かべながら言葉を綴ってみてください。こうしたメッセージを用意しておくこと自体、お金もほとんどかからず体力的な負担も少ない手軽な取り組みです。体調が許すうちに少しずつ準備しておけば、万一伝えきれないままになってしまった…という後悔を減らすことができるでしょう。
残した手紙や動画は、信頼できる家族や友人に託しておいたり、エンディングノートに「〇〇に預けてある」と保管場所を記しておくと安心です。最近は、亡くなった後に預けた手紙を届けてくれるサービスなどもあります。いざというとき確実に相手の手元に届くよう、工夫しておきましょう。あなたからのメッセージは、きっと皆さんの心に生き続ける何よりの贈り物になります。
5. 葬儀の準備(内容・費用・規模の考え方)
自分の葬儀について考えるのは勇気がいるかもしれません。しかし、生前に葬儀の希望や方針を決めておくことは、残される家族への最後の気遣いでもあります。どのような形で見送ってほしいかを伝えておけば、いざというとき家族が迷わずに済み、あなた自身も安心して最期を迎えられるでしょう。
葬儀の内容・規模を決める
まず決めておきたいのは、葬儀の規模や形式です。葬儀の規模とは参列者の範囲や人数のことで、一般葬(親族以外も幅広く会葬者を迎える従来型の葬儀)にするのか、家族葬(親族中心の少人数葬)にするのか、それともごく近親者のみで見送る密葬や直葬(火葬式)にするのか、といった選択があります。一般的に、参列者の人数や葬儀の規模が小さいほど、費用の負担も軽くなります。葬儀形式別に見ると、直葬(火葬式)、一日葬、家族葬、一般葬の順で費用は安くなる傾向です。最近では「自分の葬儀はできるだけ簡素にしたい」と考える方も増えており、ご自身の交友関係や希望に応じて無理のない規模を選ぶことが大切です。例えば高齢で友人知人も少ない場合は、形式にこだわらず身内だけで見送ってもらう形でも十分でしょう。
葬儀の内容についても希望があればまとめておきましょう。宗教者(お坊さんや神父など)にお経やお祈りをお願いするか、無宗教でお別れ会のような形にするか、遺影写真はこれを使ってほしい、好きだった音楽を流してほしい、といった具体的なリクエストもあれば書き残します。特に宗教的な儀式の有無は費用や段取りにも大きく関わるため重要です。昨今は無宗教葬や音楽葬なども増えていますので、自分らしい送り方を遠慮なく伝えておきましょう。
葬儀費用と節約のポイント
葬儀の費用相場は地域や内容によって差がありますが、日本では一般的に数十万円から数百万円と幅があります。民間の調査では全国平均で約100~120万円程度とも言われます。しかし、家族葬や直葬など小規模な葬儀にすれば費用を大きく抑えることも可能です。例えば火葬のみを行う直葬プランであれば20万円以下という例もありますし、通夜を省略して告別式と火葬だけ行う一日葬も、一般葬に比べ割安な傾向にあります。
費用を抑える工夫としては、葬儀社の選び方も重要です。時間に余裕がある今のうちに、インターネットや資料請求で複数の葬儀社のプランを比較しておくと安心です。「もしものとき」に備えて事前に相談や見積もりを取っておけば、いざというとき慌てずに済みます。葬儀社によってセットプランの内容や含まれるサービスが異なるため、価格だけでなく何にいくらかかるのかを確認しておくことも大切です。例えば式場費や火葬料だけでなく、飲食接待費(通夜振る舞い・精進落とし)や返礼品、お布施など付随費用も含めた総額を意識しておきましょう。事前にある程度予算感を家族で共有しておけば、万一の場合に「費用が思ったより高額で困る」という事態を避けられます。
さらに、公的補助や保険の確認も忘れずに。自治体によっては葬祭費の給付制度があり、国民健康保険加入者が亡くなった場合に葬祭費(葬儀費用)の一部が支給されることがあります。また、すでに加入している生命保険の中に葬儀費用特約が付いていないか確認しましょう。生前に保険会社に連絡しておけば、給付条件など教えてもらえます。
「小さなお葬式」の早割(事前相談割引)情報
葬儀費用を抑える選択肢の一つに、定額低価格の葬儀プランを提供している専門サービスの利用があります。例えば全国対応の葬儀社「小さなお葬式」では、直葬・家族葬など小規模葬儀のプランを明瞭な料金で提供しています。同社の特徴は、事前に無料の資料請求をしておくだけで全ての葬儀プランが一律5万円割引になる点です。資料請求者限定の割引価格が適用されるため、興味がある方は早めに取り寄せておくとよいでしょう。例えば火葬式プランなら割引後の料金は176,000円(税込)となるなど、非常にリーズナブルに葬儀を執り行うことが可能です。生前相談をしておけば、葬儀の段取りや希望も具体的に決めておけるため、当日のご家族の負担も軽減できます。もちろんどの葬儀社を使うかは自由ですが、このような事前相談サービスや早割制度を上手に活用しておくと経済的にも安心です。
葬儀についてはエンディングノートにも希望の概要を記しておきましょう。【どんな規模で、誰に連絡して、どこで送りたいか】などを書いておけば、細かな手配は家族がするとしても基本方針が伝わります。「葬儀は家族だけで静かに」「○○は呼んでほしい」「○○式で送ってほしい」といった希望があれば遠慮なく残しておいてください。それがご自身の安心にもつながり、残された家族にとっても「望んだ形で送り出せた」という心の支えになるはずです。
6. おわりに:残された時間を自分らしく生きるために
余命を宣告された直後は、未来への恐怖や無念さで頭がいっぱいになることでしょう。しかし、人生の最期をどう迎えるかは、ある程度自分の手で準備し、選択していくことができます。ここまで述べてきたように、財産や情報の整理を行い、想いを形にして伝えておくことは、決して「死の準備」だけではなく「残りの人生を充実させる準備」でもあります。
大切なのは、一人で抱え込まないことです。準備の途中でつらくなったら、遠慮なく周りの助けを借りてください。家族と一緒にエンディングノートを書いてみたり、思い出話をしながら手紙を綴ったりするのも良いでしょう。専門家の力を借りることも恐れないでください。あなたを支えたいと願っている人は、きっと身近にたくさんいます。
限られた時間だからこそ、今この瞬間を大切にしてください。準備をしつつも、残された日々で感じる風の音や陽の光、食事の味、そして何より家族や友人との語らいを味わいましょう。苦しい中で準備を進めるあなたの姿は、周囲に深い愛情と勇気を伝えているはずです。最後まであなたらしく生きること、それ自体が何よりのメッセージになります。
あなたが心から望む形で人生の幕を閉じ、そしてご家族も「悔いのない見送りができた」と思えるように――この記事の内容が少しでもお役に立てば幸いです。残された時間が穏やかで意味のある日々となることを、心より願っています。







