生前葬とは、本人が元気なうちに親しい人たちと感謝を伝え合うための場です。死後の葬儀では伝えにくい思いを、自分の言葉で届けられるのが特徴です。最近では還暦や定年などの節目に合わせて開かれることも多く、形式にとらわれない自由な会として広まりつつあります。
この記事では、生前葬の基本的な流れや演出の工夫、費用の目安、家族や宗教への配慮まで、準備に役立つ情報をわかりやすく解説します。
目次
生前葬がもたらす「安心感」

従来「お葬式は死後の行事」とされてきましたが、生前葬は生きているうちに自分の言葉で感謝を伝えられるのが魅力です。また、本人の意思や希望を反映できるため、納得のいくかたちで人生の節目を迎えられるでしょう。
たとえば還暦や定年といった区切りのタイミングに、家族や親しい人たちと静かに心を交わす場を設けることで「最期を迎える心の準備」もできます。また、残された家族や友人に前向きな気持ちを残せるのは、大きなメリットです。
-
感謝を直接伝えられる
家族・友人・恩師など、大切な人に元気なうちに感謝の言葉を伝えられます。 -
家族の負担を減らせる
葬儀の方針や内容を本人が決めることで、遺された家族の手間や負担を軽くできます。 -
自分らしい形を選べる
趣味や思い出の品、音楽などを取り入れ、自分らしい雰囲気で行えます。 -
心の整理ができる
将来への不安を整理し、心構えをするきっかけになります。
自身の寿命は誰にも分かりません。だからこそ生前に準備を進めておくことで、本人も家族も安心感が得られるでしょう。
 生前葬とは?メリット・デメリットから有名人の事例、準備の流れまで徹底解説
生前葬とは?メリット・デメリットから有名人の事例、準備の流れまで徹底解説
企画の流れと基本準備

生前葬を計画する際は、「何のために」「いつ」「どこで」「誰を呼び」「どう進めるか」を順に整理していくとスムーズです。ここでは、生前葬の主な流れを紹介します。あくまで一例ですので、状況に応じて柔軟に調整していきましょう。
1. 目的とコンセプトを決める
まずは生前葬の目的を明確にします。家族への感謝・長寿祝い・人生の節目など、意図がはっきりすると式の雰囲気や進行内容が自然と決まります。
「思い出を静かに振り返る会」や「趣味仲間との集まり」など、具体的なイメージを持つことが大切です。目的がはっきりすると、招待する人や会場も決めやすくなります。
2. 日時と会場を決める
体調に無理のない時期を選ぶのが基本です。還暦や退職後などの節目に合わせる人もいれば、引越しや生活の変化に合わせる例もあります。季節や天候、招待客の都合も考慮すると、全員が参加しやすい日程になります。
会場は自宅・公民館・レストラン・ホテルなどから、規模や希望に合う場所を選びます。事前に見学し、設備や動線を確認しておくと安心です。バリアフリーやアクセスの良さもチェックポイントです。
3. 招待客の検討と家族への相談
誰を招くかをリストにし、家族や友人、仕事の関係者などを整理します。人数によって会場や進行も変わるため、優先順位をつけて調整しましょう。小規模でも親しい人たちとの時間が充実していれば、温かな会になります。
生前葬に対する受け止め方は人それぞれなので、特に家族や親族には趣旨を早めに伝え、協力を得ておくことが大切です。反対意見が出る可能性もあるため、丁寧な説明と対話が欠かせません。
4. 形式を選ぶ
無宗教の自由な形式にするか、宗教儀式を含めるかを検討します。仏教やキリスト教などの宗教儀式を希望する場合は、事前に寺院や教会に相談をしましょう。
近年は宗教色を控え、感謝の会として進行する形式も増えています。宗教にとらわれず、自由に感謝や想いを伝えるスタイルが喜ばれているようです。
5. 予算を立てる
会場費・飲食・映像や演出・記念品など、費用の内訳を書き出して目安を立てます。全体で20万円〜50万円程度が一般的ですが、規模や内容で上下します。
事前に予算の上限を決めておくと、無理のない範囲でプランを組み立てられます。予算に合わせて内容を調整し、必要に応じて専門業者から見積もりを取ると安心です。
6. プログラムを組む
開会あいさつ・映像上映・メッセージ紹介・歓談・閉会あいさつなど、大まかな流れを考えます。進行は本人が務めることもできますが、友人や司会者に依頼してもよいでしょう。
時間配分に余裕を持たせることで、参加者もリラックスして過ごせます。また、プログラムは書き出して配布すると、参加者も流れを把握しやすくなります。
招待客の範囲と案内のコツ

生前葬では「誰を呼ぶか」によって会の雰囲気が決まります。招待するのは、感謝を伝えたい相手に絞るのが基本です。
案内状やメールには「元気なうちにお礼を伝えたく、ささやかな会を開くことにしました」など、趣旨を簡潔に伝えると相手も安心しやすくなります。大切な方には、電話や対面で直接説明するのもよい方法です。
招待客を選ぶポイントは、次の通りです。
-
本当に感謝を伝えたい人を優先する
数よりも気持ちを届けたい相手を大切に考えます。 -
優先順位をつけてリスト化する
家族、旧友、恩師などをグループごとに整理し、人数を調整します。 -
趣旨を案内状に明記する
「元気なうちにお礼を伝えたくて企画しました」と一言添えると伝わりやすくなります。 -
強制しない呼びかけにする
「ご都合が合えばぜひお越しください」といった柔らかな表現が適しています。 -
香典は辞退し、会費制を明記する
香典はお断りし、飲食代などは1〜2万円程度の会費制とするのが一般的です。
参加を強く求めず、都合の合わない方には、後日写真や動画などで雰囲気を共有すると丁寧です。招待は、相手の立場に配慮して行うことが大切です。
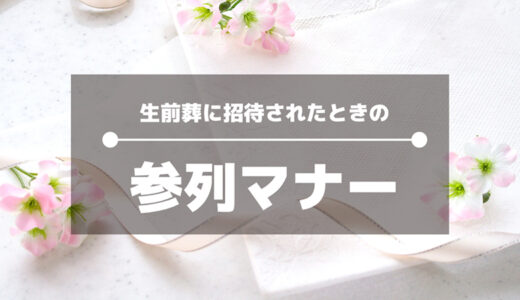 生前葬に招待されたら?知っておきたい参列マナー完全ガイド
生前葬に招待されたら?知っておきたい参列マナー完全ガイド
演出アイデアと当日の進行例

生前葬だからこそ実現できる自由度の高い演出を取り入れましょう。派手ではなく、静かに心に残る工夫がおすすめです。
-
思い出映像の上映
幼少期から現在までの写真や動画をスライド形式で静かに鑑賞。 -
好きな音楽のBGM
生演奏やセレクトした楽曲を背景に流し、しっとりした雰囲気を演出。 -
手紙朗読タイム
参加者から預かったメッセージを本人や司会が静かに読み上げる。 -
小規模な余興
ギター弾き語りや短いスピーチなど、程よい長さで温かな余韻を残す。
スライド上映では写真にちょっとしたコメントを付け、映像にナレーションを重ねると、自分の想いが伝わりやすくなります。手紙朗読の時間を設ける場合は事前に参加者からメッセージを募り、当日に本人または司会が丁寧に読み上げると場が引き締まります。
-
開会のあいさつ(本人または司会)
-
思い出スライド上映
-
家族・友人からのメッセージ朗読
-
歓談・軽食タイム
-
閉会の言葉(本人から感謝を込めて)
演出を盛り込みすぎると息切れするので、「開会」「メイン演出」「歓談」「閉会」の4部構成に絞ると準備も進めやすいでしょう。
演出の合間には歓談時間を多めに取り、参加者同士がゆったり交流できるよう配慮すると、落ち着いた会になります。
費用相場と予算調整のポイント

生前葬の費用は、規模や演出内容で大きく変わります。会場費・飲食代・招待状・記念品代など、項目ごとに洗い出して見積もりを取りましょう。
費用の目安
以下は、生前葬の規模ごとに想定される費用のおおよその目安です。
| 規模 | 費用相場 | 内容の例 |
|---|---|---|
| 家族中心の小規模な会 | 20〜30万円程度 | 自宅や公民館で開催、招待客10名程度、軽食やお茶の提供など |
| レストランを貸切 | 50〜80万円程度 | 少人数でも料理をしっかり楽しめる形式、装飾や映像演出などを追加 |
| ホテルの宴会場を利用 | 80〜100万円超 | 大人数対応、司会者・生演奏・記念品などを含む本格的な会の開催 |
実際の費用は会場の立地や設備、招待人数、料理内容などによって上下します。費用を見積もる際には、自身の希望と優先順位を明確にしながら、無理のない範囲で予算を組み立てていくことが大切です。
予算を抑える工夫
予算を抑える方法としては、公共施設の利用や自宅での開催により会場費を減らし、招待人数を絞ることが効果的です。また、招待状やスライド映像を自作すれば、業者への依頼費を抑えつつ個性も出せます。
ただし、節約を優先しすぎると、本来伝えたかったことが薄れてしまう場合もあります。とくに大切にしたい部分には適切に予算をあて、全体のバランスを取ることが大切です。自分らしさを大切にしながら、家族に負担を残さない範囲で計画しましょう。
生前葬実施のタイミング

生前葬を行う時期に決まりはありませんが、体力や気力に余裕があるうちに準備することが大切です。還暦や古希、定年退職といった人生の節目に合わせて開かれることが多く、引越しや趣味の引退など、生活の変化に合わせて行うケースもあります。
また、余命の告知を受けた場合は、体調が安定しているうちに早めに準備を始めましょう。
- 還暦・古希など長寿の節目
- 定年退職後の区切りとして
- 引越しや趣味の引退など生活環境の変化をきっかけに
- 余命宣告を受けた場合(体調が安定しているうちに)
「まだ早いかもしれない」と感じる時期でも、元気なうちに準備や計画を始めると安心です。思い立った時が適切なタイミングと考えるのも、自分らしい最期を迎えるための第一歩と言えるでしょう。
また、生前葬は終活を始めるきっかけにもなります。たとえば残された家族への負担を減らすために「お墓の見直し」や「墓じまい」を考える方も増えています。
 墓じまいの進め方 ~費用や改葬手続き、親族への説明ポイント~
墓じまいの進め方 ~費用や改葬手続き、親族への説明ポイント~
近年は「わたしたちの墓じまい![]() 」のような離檀代行サービスの活用も広がっており、墓じまいの手続きや移転もスムーズに進められます。お墓の継承者がおらず、無縁墓となってしまう不安がある方はぜひ検討してみてください。
」のような離檀代行サービスの活用も広がっており、墓じまいの手続きや移転もスムーズに進められます。お墓の継承者がおらず、無縁墓となってしまう不安がある方はぜひ検討してみてください。
宗教・親族の理解とトラブル回避策

生前葬を進める際は、宗教的な考え方や親族の受け止め方に配慮することが大切です。「生きているうちに葬儀をするのは縁起が悪い」と感じる人もいるため、事前に丁寧に説明して理解を得ておく必要があります。
主な課題と対策
親族の中には、生前葬の意義をすぐに理解できない方もいます。とくに高齢の方や、地域のしきたりを重視する家庭では反対の声が出ることもあります。
-
家族の不安・抵抗感の解消
「縁起が悪い」といった意見がある場合は会の目的を説明し、「感謝の集い」など柔らかい名称に変更するなどの工夫すると受け入れられやすくなります。 -
寺院や教会への相談
仏教やキリスト教など、宗派によって受け止め方が異なります。事前に寺院や教会へ相談し、進め方について確認しておくと安心です。 -
亡くなった後の対応を共有
生前葬を行っても、亡くなった後には火葬や納骨といった手続きが必要です。遺族との間であらかじめ方針を共有しておくと、混乱を防げます。希望があれば、エンディングノートや遺言書に記しておくとより確実です。
亡くなった後の葬儀について不安な親族がいる場合は、あらかじめ葬儀サービスを検討しておくのもひとつの方法です。たとえば「小さなお葬式」では火葬式や家族葬など多様なプランが用意されており、事前相談も無料で受けられます。
生前葬と合わせて備えておくことで、遺族の負担を大きく減らすことができるでしょう。
否定的な意見があってもすぐに説得しようとせず、時間をかけて話し合うことが大切です。「無理に出席しなくてもよい」と伝えるなど、相手の立場を尊重する姿勢が信頼につながります。
当日の雰囲気づくり
参列者の中には、緊張や戸惑いを感じる方もいます。当日は落ち着いた進行と穏やかな言葉がけを意識し、温かい雰囲気を保つことが大切です。
たとえ本人や司会者が冒頭で会の趣旨を説明し、「今日は明るい気持ちで過ごしていただければ嬉しいです」とひとこと添えるだけで、参加者も安心して過ごせます。
自分と周囲の歩幅をそろえる
生前葬は、本人の意志で進める前向きな取り組みですが、家族や親族、宗教的な背景との調和も重要です。誰か一人の意見を優先しすぎることなく、関係者それぞれの立場を尊重しながら調整していくことが、後悔のない準備につながります。
自分の気持ちと周囲の気持ちの歩幅をそろえながら、落ち着いて進めていくことがポイントです。
最後まで自分らしく

生前葬は、人生を静かに振り返り、感謝を伝える機会です。大切なのは演出の派手さではなく、自分の言葉や思いを伝えることです。
準備には時間と労力がかかりますが、それによって本人も家族も気持ちを整えることができます。無理のない形で計画を進め、自分らしい最期の時間を迎えましょう。








