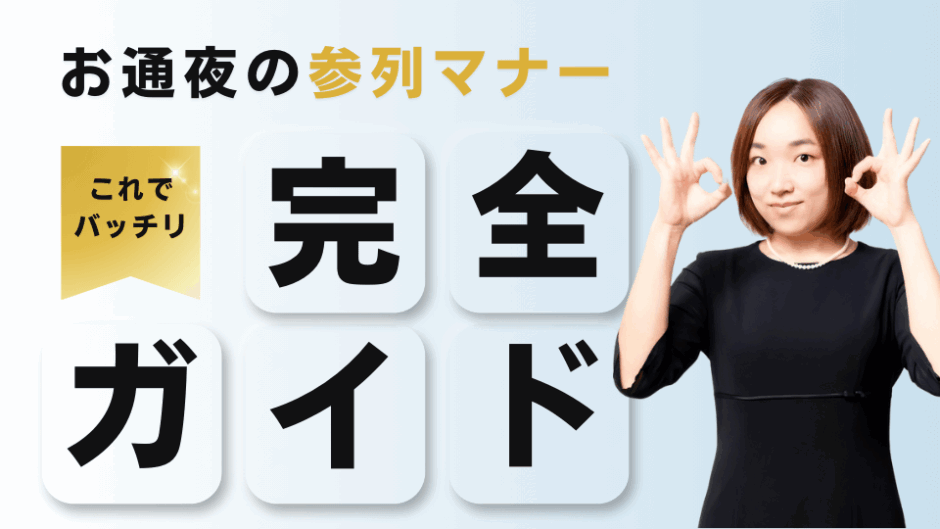おさるくん
おさるくん
目次
お通夜の意味と目的
お通夜とは、故人と最後の別れをするために葬儀の前夜に行われる儀式です。本来は家族や親しい人々が故人に寄り添い夜通し明かす「通夜」が起源で、故人を見守り冥福を祈る意味がありました。現在では形式が簡略化され、一般的には葬儀・告別式の前夜に夕方から夜にかけて1~2時間程度行われることが多いです。お通夜は、日中の正式な告別式とは異なり、比較的自由に参加しやすい場であり、仕事帰りでも駆けつけやすい時間帯に設定されることが一般的です。
お通夜は故人とゆかりのある人が集い、故人との最後の時間を共有する場です。僧侶による読経(宗教的な儀式)が行われ、参列者は焼香をして故人の冥福を祈ります。また、お通夜には正式な招待状がなくても参列できる場合が多く、「誰でも比較的気軽に参加できる最後のお別れの場」として位置付けられています。一方で翌日に行われる葬儀・告別式は、故人との正式な別れの儀式であり、より厳粛で格式ばった雰囲気になります。お通夜が故人と親しい人々によるインフォーマルな集いであるのに対し、葬儀・告別式は親族や限られた参列者が集まる正式な式典という違いがあります。
お通夜はいつ行われるのか?

お通夜は故人が亡くなった当日または翌日夜に行われることがほとんどで、葬儀・告別式の前日にあたります。開始時間は一般的に18~19時頃から始まるケースが多く、仕事終わりでも間に合うよう夕方以降に設定されます。所要時間は読経などの儀式部分が約1時間程度、その後に遺族が参列者に軽い食事や飲み物をふるまう「通夜振る舞い」が1時間程度という流れが一般的です。したがって、参列者としては合計で約2時間ほどを見ておくと良いでしょう。
葬儀・告別式はいつ行われるのか?
なお、葬儀・告別式は通常お通夜の翌日の日中(午前~午後)に執り行われます。ただし六曜(暦)の「友引」にあたる日は葬儀を避ける習慣が昔からあり、「友引」に重なった場合は日程をずらして葬儀・告別式を行うこともあります(「友引に葬儀を行うと故人が友を冥土に引き連れてしまう」といった忌み言葉に由来する風習です)。一方、お通夜は友引でも前夜であれば実施される場合が多いです。
現代のお通夜
現代では、お通夜自体の形も少しずつ変化しています。かつては夜通し行われるものだった通夜も、現在では参列者が一定の時間で帰宅し、遺族のみで夜を明かす形式も一般的です。そのため「半通夜」といって、儀式自体は1時間ほどで終え、参列者は通夜振る舞いの後に早めにおいとまし、遺族のみで故人と夜を過ごす形を取ることも増えています。形が簡略化されても、お通夜は故人との最後の別れを告げる大切な時間であることに変わりはありません。
お通夜に参列する人・しない人 ~誰が出席すべき?迷った時は
「葬儀・告別式に出席するならお通夜にも出なければいけないのだろうか?」と悩む方もいますが、必ずしも両方に参列する必要はありません。現代では仕事や距離の都合でお通夜か葬儀のどちらか一方のみ参列する人も多いです。では、どのような場合にお通夜へ参列すべきか、判断のポイントを解説します。
故人との関係が深い場合やお世話になった間柄である場合
この場合はできるだけお通夜に参列することを考えましょう。たとえば親族や親しい友人であれば当然参列すべきですし、かつてお世話になった上司や恩人などの場合も、最後のお別れに行くのが望ましいでしょう。明確なルールがあるわけではありませんが、「少しでもお悔やみの気持ちを伝えたい」「手を合わせたい」という気持ちがあるなら、参列を前向きに検討してください。
顔見知り程度の知人で関係が浅い場合
この場合は参列すべきか悩むこともあります。その場合でも、故人や遺族に対してお悔やみの気持ちが少しでもあるなら、お通夜に出向いて手を合わせることは決して失礼にはあたりません。お通夜は基本的に誰でも参列できる場ですので、「場違いではないか」と過度に心配する必要はないでしょう。ただし、故人と直接の面識がなく遺族ともほとんど交流がないような場合は、無理にお通夜へ行かず心の中で弔意を示すか、後日弔電やお花を送るなど別の形で気持ちを伝える方法もあります。
友人・知人の家族が亡くなられた場合
その友人・知人を支えるために参列するケースもあります。直接故人と面識がなくても、親しい友人がご家族を亡くされたのであれば、「お悔やみを伝えたい」「励ましてあげたい」という気持ちからお通夜に駆けつけることもあるでしょう。大切な人を亡くして深く悲しんでいる遺族に、そっと寄り添ってあげることもお通夜に参列する大きな意義の一つです。
仕事関係の人(上司・同僚・取引先など)が亡くなられた場合
会社や所属先の方針・慣例をまず確認しましょう。職場によっては有志で弔問団を送ったり、代表者のみが参列したりと決まりがあることがあります。一般的には、親しくしていた同僚や上司であればお通夜だけ参列することも多いです。会社として弔意を示す場合は、上司や代表者が会社名義の供花や弔電を送るケースもあります。また、会社の代表として参列するのであれば葬儀まで出席することもありますが、通常は仕事関係者はお通夜のみで失礼するケースが一般的でしょう。
親族の場合
葬儀への参列はもちろんですが、遠方に住んでいるなどどうしても都合がつかない場合を除き、お通夜から参加するのが丁寧です。特に故人が三親等以内の親族(祖父母、叔父叔母、甥姪など)であれば、できる限りお通夜にも顔を出すことが望ましいでしょう。
お通夜の出席に関する常識
お通夜の出席について「自分は出席してもいいのか?」「どうしても出席できない時はどうしたらいい?」という疑問を解決していきます。
お通夜の案内がなくても参列していい?
訃報は時として直接ではなく、人づてに聞くこともあります。遺族から正式な案内や連絡を受けていない場合でも、参列してよいかどうか迷いますよね。一般的には、故人や遺族と面識・つながりがあるならお通夜に参列することに問題はありません。
ただし、可能であれば、遺族や関係者に連絡を取り、お通夜の日程や場所を確認した上で「参列しても大丈夫か」うかがってみると確実です。突然訪問して遺族を驚かせてしまうより、事前に意向を確認できれば安心でしょう。
家族葬と言われた場合は参列しないほうがいい?
最近増えている家族葬(家族やごく近親者のみで執り行う葬儀)の場合、基本的には参列は遠慮するのがマナーです。もし訃報の際に「今回は家族葬で執り行います」と案内された場合は、遺族の意向で一般の弔問客をお呼びしないという意味ですので、お通夜・葬儀ともに参列は控えましょう。この場合、後日改めて弔電を送ったり、お花や御供物を届けたりするのが一般的です。どうしても直接お悔やみを伝えたい場合は、四十九日法要の後など落ち着いた時期に訪問の機会をうかがうと良いでしょう。
訃報を受け取った際には、その葬儀の形式(一般葬か家族葬か)について情報がないか注意して確認してみてください。もし家族葬であれば、遺族の負担にならないよう弔問は自粛することがマナーとなります。
お通夜に出席できない時はどうすればいい?
お通夜や葬儀は突然に予定されるため、「どうしても都合がつかず参列できない」ということも起こりえます。では、やむを得ずお通夜に行けない場合はどのように弔意を示せばよいのでしょうか。
まず考えられるのは弔電を送ることです。弔電とは、故人を悼む気持ちを綴ったお悔やみの電報のことで、参列できない場合によく利用されます。NTTや郵便局、ネットから手配でき、葬儀会場へ直接送ることが可能です。弔電には「お悔やみ申し上げます」といった定型文のほか、故人との思い出や感謝を書くこともできます。
 格安弔電で評判!VERY CARDの特徴と使い方、文例、サービス比較(ベリーカード)
格安弔電で評判!VERY CARDの特徴と使い方、文例、サービス比較(ベリーカード)
また、供花をお送りする方法もあります。供花とは葬儀式場に飾る花輪や生花のことで、故人への哀悼の意を表します。供花を送る場合も、葬儀社や生花店に依頼して葬儀会場に届けてもらいます。供花料は相場がありますので、事前に葬儀社などに問い合わせると安心です。
 お葬式の花の種類と贈るときのマナー「供花・枕花・一本花・花輪・献花」の違いとは
お葬式の花の種類と贈るときのマナー「供花・枕花・一本花・花輪・献花」の違いとは
そして、香典を後日届けるという方法もあります。たとえば葬儀に出席できない場合でも、別途香典を現金書留で郵送したり、あとで遺族に直接お渡ししたりすることで気持ちを伝えられます(香典については後述します)。その際、お悔やみの手紙を添えると丁寧です。
 葬儀に出れない!後から知った!葬儀後のお悔やみの仕方(弔電・香典・後日弔問)
葬儀に出れない!後から知った!葬儀後のお悔やみの仕方(弔電・香典・後日弔問)
このように、直接参列できなくても弔意を示す手段はいくつかあります。大切なのは「故人を悼む気持ちを形にすること」です。何も連絡しないままでいるより、できる範囲で気持ちを伝えることで、遺族にとっても「きちんとしてくれたのだな」と感じてもらえるでしょう。
一番の悩みどころ「恥をかかないためのお通夜の服装」

お通夜に参列する際、「どんな服装で行けば失礼にならないか」は多くの人の悩みどころです。お通夜の服装マナーについて押さえておきましょう。
基本は黒の喪服かダークスーツ
現在では、お通夜でも基本は喪服(黒のフォーマルウェア)で参列するのが一般的です。昔は「通夜は平服で」といって普段着で駆け付ける風習もありましたが、現代では通夜もほとんど葬儀と同様に正装で臨む人が多くなりました。そのため、黒のスーツやワンピースなど喪服に準ずる服装で参列すればまず間違いありません。
とはいえ、訃報は突然入るものです。急に連絡を受けて喪服の準備が間に合わない場合もあるでしょう。そのような時は、地味な色合いのスーツや控えめな服装であれば参列可能です。男性であればダークグレーや濃紺のスーツに黒または地味なネクタイを締める、女性であれば黒に近い落ち着いた色味のスーツやワンピースを着用する、といった対応でも構いません。要は、派手さを避けた落ち着いた服装であればマナー違反にはならないということです。
また、服装に関して押さえておきたい基本原則として、「遺族の喪服の格より目立たないようにする」という考え方があります。遺族は通常正式な喪服(男性ならモーニングや黒スーツ、女性なら黒無地の喪服)を着用されています。参列者はそれより控えめな格好を心がけ、遺族と同等かそれ以下の格式にとどめるのが無難です(もちろん平服すぎてもいけませんが、遺族より華美にならないことが大事です)。
男性の服装マナー
男性の場合、黒のスーツに白シャツ、黒ネクタイが基本スタイルです。靴下や靴、ベルトもすべて黒で統一し、派手なデザインのものは避けましょう。ネクタイピンやカフスなどのアクセサリー類も付けないか、つけても目立たないシンプルなものにとどめます(可能なら外しておくのが望ましいです)。時計をする場合は、光沢の強い派手なものは避け、シンプルなデザインのものにします(電子音やアラームは事前に切っておきましょう)。
髪型は清潔感のあるよう整え、無精髭は剃って臨みます。強い香水や整髪料の匂いも控えめにし、全体的に目立たず清潔な印象になるよう心がけてください。
女性の服装マナー

女性も基本は黒無地のスーツやワンピース、アンサンブルなど喪服が望ましいです。スカートの場合は膝が隠れる丈のものを選び、胸元や肌の露出が少ないデザインにします。袖もできれば長め(五分~七分袖以上)が適切です。パンツスーツでも構いませんが、やはり黒無地で体のラインが出すぎない上品なものを選びましょう。
靴は黒のパンプスが基本です(光沢のある素材やエナメルは避けます)。ヒールは高すぎず低め~中くらいのもの(3~5cm程度)で、つま先も露出しないデザインが望ましいです。ストッキングは肌色ではなく黒の無地を着用します(柄物やラメ入りはNGです)。
女性のアクセサリーは極力シンプルにします。結婚指輪程度なら問題ありませんが、その他の指輪やブレスレット、派手なイヤリング・ネックレスは控えましょう。ただし真珠のネックレスは喪の場で許容される数少ないアクセサリーです(涙の象徴とも言われ、一連のシンプルな真珠ネックレスは慣例的によく用いられます)。真珠以外の宝石やキラキラ光る装飾品は付けないようにします。
また、バッグや小物類も黒で統一します。ハンドバッグは黒無地で金具が目立たないデザインのものを持ち、中身もハンカチ(白黒や無地のもの)や数珠(念珠。宗派によりますが持っている場合)、香典など必要最低限のものに留めます。派手な柄物のハンカチや目立つ色のスマホケースなど、細かいところまで派手にならないよう注意します。
メイクについても、ナチュラルメイクを心がけます。濃すぎるアイメイクや派手な口紅は避け、控えめで落ち着いた印象になるようにします。マニキュアもできれば落として、素の状態か透明・ベージュ系に整えておくと良いでしょう(急な場合で落とせないときは目立たないように心がけます)。
髪色・喪章などその他のポイント
近年では髪を染めている方も多いですが、髪色について過度に心配する必要はありません。昔は「茶髪の場合は黒染めスプレーで黒くするべき」と言われることもありましたが、現代では茶髪程度であればさほど問題視されなくなっています。無理に染め直す必要はないでしょう。ただし、遺族世代の感覚によっては派手な髪色に驚かれる可能性もありますので、気になる場合は一時的にトーンダウンするか、まとめ髪にして露出を抑えるなど工夫すると安心です。
喪章(黒いリボンや腕章)については、通常遺族や葬儀関係者が身につけるものです。一般の参列者が「喪服代わり」に喪章をつける必要は基本的にありません。まれに「平服で参列する場合は喪章をつけた方がよいか?」という疑問がありますが、喪章はあくまで遺族側が喪に服していることを示す目印のようなものですので、一般参列者は着用しなくて大丈夫です。それよりも全体の服装トーンを黒やダークカラーで統一し、静かな身だしなみに整えることの方がずっと重要です。
最後に、服装とは少し離れますが携帯電話などの電源は必ず切っておくようにしましょう。着信音や通知音が式の最中に鳴ると非常に無作法です。マナーモードではなく電源OFFが基本です。また、会場ではお静かに、礼を失しないよう言動にも気をつけることが大前提となります。
 おさるくん
おさるくん
 葬儀や法事で恥をかかないための服装・喪服・持ち物のマナーまとめ
葬儀や法事で恥をかかないための服装・喪服・持ち物のマナーまとめ
数珠については必ずしも必要ではありませんが、詳しく知りたい方は下記の記事をお読みください。
 お葬式で使う『数珠』の基礎知識:意味・マナーから選び方まで
お葬式で使う『数珠』の基礎知識:意味・マナーから選び方まで
お通夜における香典について

お通夜や葬儀に参列する際には「香典」を持参するのが一般的です。香典とは、故人への供養の気持ちとしてお供えする現金のことで、葬儀費用の一部を助ける意味合いも持っています。ここでは香典の準備や渡し方のマナーについて説明します。
お通夜に持参?それとも告別式に持参?
お通夜にも告別式にも参列する場合はどちらに香典を持参するのが正しいのでしょうか?
答えはいずれかに持参するということになります。
参列する最初の機会に一度だけ渡せばOKです。一般的にはお通夜で先に渡すことが多いです。お通夜に参列したならその場で香典を出し、翌日の葬儀では香典を改めて持っていく必要はありません。ただし、訃報を受けて急いで駆け付けたお通夜の場合、香典の用意が間に合わないこともあります。そのような場合は無理にお通夜で渡さず、翌日の葬儀に持参してお渡ししても問題ありません。逆にお通夜には行けず葬儀のみ参列するなら、葬儀の日に受付で香典をお渡しすれば大丈夫です。要は重複せずタイミングがずれても構いませんので、自分が最初に参列できるタイミングで香典を持参すると覚えておきましょう。
香典の相場は?
香典の金額は故人との関係性によって異なりますが、一般的な相場を参考にしましょう。たとえば会社の上司・同僚や知人レベルであれば5,000円程度、友人や恩人であれば5,000円~1万円、叔父叔母・祖父母などの親族であれば1万円~3万円程度、両親や兄弟といったごく近い親族なら3万円以上包むこともあります。地域の習慣や周囲との兼ね合いもありますので、心配であれば周りの人に相談したりインターネットで相場を調べたりすると良いでしょう。
金額について一つ注意したいのは、「4」や「9」の数字を避けることです。「4=死」「9=苦」を連想させるため、日本では不吉な数字とされています。そのため香典も4,000円や9,000円といった金額は避け、5,000円や1万円などキリのよい額にするのが一般的です。どうしても新札しか手元にない場合は、一度折り目をつけるなどして「新札ではない」状態にして包む配慮もあります。
香典袋について
市販の香典袋は白い袋に黒白や銀色の水引(結び紐)が印刷または掛けられたものです。水引が印刷された略式タイプは主に1万円以内の場合、5,000円以上包む場合は実際に水引がかかっている正式タイプを使うなど、金額や格式に応じたものを選びます。迷ったら黒白の水引が印刷された一般的な香典袋で問題ありません。
香典袋の書き方
表書き(袋表面中央上部)には宗教に応じた文言を書きます。仏式のお通夜・葬儀であれば「御霊前」(または「御香典」)と書くのが一般的です(キリスト教式なら「御花料」、神式なら「玉串料」など異なる表書きになりますが、仏式がほとんどでしょう)。
表書きは毛筆か筆ペンで薄墨を使って書きます。薄墨を使うのは「急な悲報に駆け付けたためインクが十分でない(涙でにじんだ)」という弔事特有の慣習によるものです。最近では薄墨タイプの筆ペンも市販されています。表書きの下部には自分の氏名をフルネームで記入します。
中袋(香典袋に中包みがある場合)には金額と住所氏名を記入します。金額は漢数字(「壱」「弐」「参」など)で書くのが正式です。例えば5,000円なら「金伍仟円」、1万円なら「金壱萬円」と記します。中袋の表に金額、裏に住所氏名を書く欄があるので、これも薄墨の筆ペンで書きます。
香典の持参の仕方
準備した香典袋は袱紗と呼ばれる布に包んで持参します。袱紗は紫や灰色、深緑など地味な色のものを用います。香典袋を袱紗に包んで持参することで、財布から直接取り出すよりも丁寧であり、また香典袋が汚れたり折れたりするのを防ぐ役割もあります。袱紗がない場合は風呂敷や清潔なハンカチで代用しても構いません。
香典の渡し方
会場に着いたら、まず受付で記帳(芳名帳への名前記入)と香典の受け渡しを行います。受付が設けられていない場合は、遺族や係の人に直接お渡しする形になることもありますが、一般的なお通夜では受付があります。
袱紗に包んだ香典袋は、受付のテーブルの前で袱紗から静かに取り出します。取り出す際、自分から見て文字が逆さま(受付の方から読める向き)になるように持ち替えます。そして受付係の人に表書きが相手から読める向きで両手で差し出して渡します。このときに小さな声で「この度はご愁傷様です」「心ばかりですがお納めください」など、一言お悔やみの言葉を添えると丁寧です。受付の方(多くは葬儀社スタッフや親族の代表の方)が「ありがとうございます」と受け取ったら、お辞儀をして一礼しましょう。
その後、芳名帳に自分の名前・住所などを記帳します。芳名帳は香典をいただいた方を遺族が把握するためのものです。住所を書く欄がある場合は略さず正式に書きます。会社関係で参列している場合は会社名・所属も書き添えると親切です。
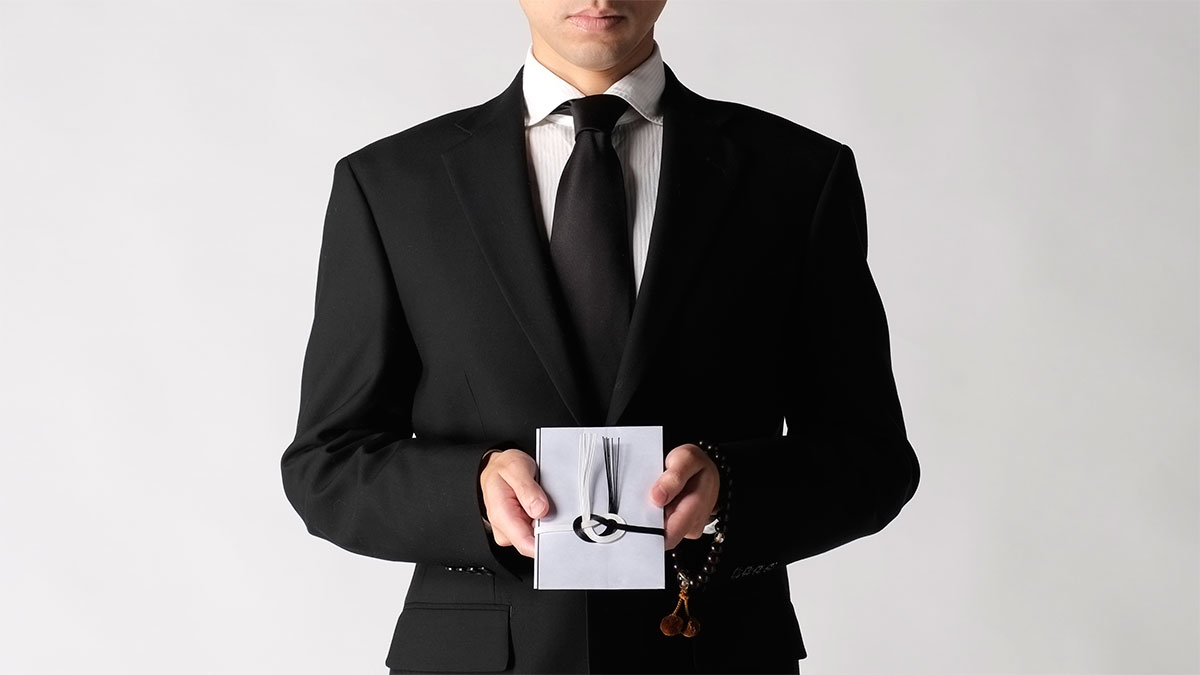 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
お通夜当日の流れと参列マナー

最後に、実際にお通夜当日の流れと、その各場面でのマナーについて説明します。受付を済ませてから退席するまで、一連の所作を押さえておけば落ち着いて行動できるでしょう。
到着~受付のマナー
お通夜の開始時刻までには会場に到着するのが理想です。開始の10~15分前には着けるよう、余裕をもって出発しましょう。万一仕事の都合などで開始時刻に間に合わなくても、遅れて参列することは可能です。お通夜は突然のお知らせで開催されるものなので、開始後30分~1時間程度の遅刻であれば途中から静かに参列しても失礼にはあたりません。ただし遅れて到着した場合は、進行の妨げにならないよう静かに会場に入りましょう。もし読経の真っ最中であれば、入口付近で合掌して一礼し、区切りの良いタイミングまで後方で待機する配慮も必要です。
会場に着いたら、まず受付で香典を渡し、芳名帳に記帳します。受付でお悔やみの言葉を伝え、案内に従って会場内へ進みます。多くの場合、受付で紙の会葬御礼(葬儀社や遺族からのお礼品や礼状)が手渡されますので、受け取ったら自分のバッグにしまっておきます。
読経〜焼香の手順とマナー

式場に入ったら、葬儀スタッフや係の人の誘導に従って着席します。席順は遺族・親族が前方、一般弔問客は後方が基本ですが、指定される場合は指示に従いましょう。定刻になると僧侶によるお経(読経)が始まり、厳かな雰囲気の中で式が進行します。
読経の途中または終了後に、参列者による焼香の時間があります。焼香とは、香を焚いて手を合わせる仏教の弔いの作法です。会場前方に焼香台(香炉)が設置されており、順番に立ち上がってお焼香を行います。係の合図や僧侶のお経の区切りなどで「ではお焼香をお願いします」と促されますので、自分の順番が来るまで席で待ちましょう。焼香は通常、親族など前列から順に行い、その後一般参列者へと移ります。列ごとに案内されるか、自由に席から立って列を作る形になります。
自分の番が来たら席を立ち、焼香台へ進みます。前の人との間隔を保ち、歩くときは静かに一礼しながら進みましょう。では、焼香の一般的な手順を示します。
①遺族・親族に一例する:遺族席が近くにある場合は遺族に一礼してから香炉の前に進みます。
②遺影・祭壇に一礼する: 焼香台の手前まで進んだら、まず故人の遺影や祭壇に向かって軽く一礼し、合掌します。
③焼香を一回目行う: 焼香台の前に立ったら、香炉のそばにある抹香(粉末状のお香)を指でつまみます。右手の親指、人差し指、中指の三本で一つまみ取り、目の高さくらいまで持ち上げます(目の高さ近くまで持ち上げて故人への敬意を表します)。
④香をくべる: つまんだ抹香を香炉に静かにくべます。香炉の上で指をひねるようにして抹香を落とし入れます。炎が出ている場合でも直接火に触れないよう気をつけながら落とします。
⑤焼香を二~三回繰り返す: 一般的な宗派では、この抹香をつまんでくべる動作を2~3回繰り返すことが多いです(地域や宗派によって回数は異なりますが、わからない場合は前の方にならってください)。例えば3回行う場合、同じ動作をもう二度繰り返します。
焼香の所作が終わったら、両手を胸の前で合わせて合掌し、数秒間静かに祈ります。心の中で故人へのお悔やみや冥福を祈りましょう。
⑥一礼して退く: 合掌を終えたら一礼し、静かに焼香台から下がります。後ろに下がってから体の向きを変え、遺族の方にも一例します。その後、自席に戻ります。
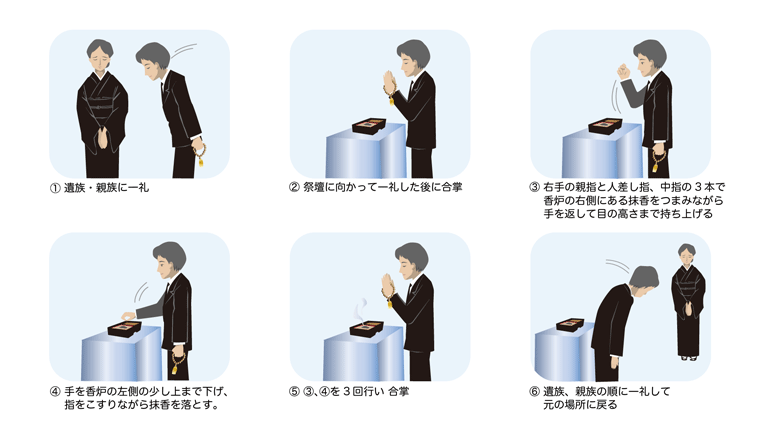
動画でお焼香の作法をみてみよう!
お焼香についてさらに詳しく知りたいときは下記の記事をお読みください。
 知っておきたい焼香マナー | 作法・仕方・やり方、回数など
知っておきたい焼香マナー | 作法・仕方・やり方、回数など
遺族へのお悔やみの挨拶
お焼香が終わり、席に戻った後は僧侶のお経が締めくくられ、葬儀委員長や遺族代表の挨拶が簡単に行われて、お通夜の式自体は終了となります。式が終わったら、可能であれば遺族に直接お悔やみの言葉をかけるようにしましょう。
遺族の方々は式の終わりか、もしくは通夜振る舞いの席で、参列者一人ひとりに挨拶をされることが多いです。タイミングとしては、焼香後に遺族席の前を通る際に一言声をかけるか、後ほど食事の場で改めて声をかけるか、どちらでも構いません。
お悔やみの言葉としては、「この度はご愁傷様でございます」がよく使われる丁寧な表現です。少し改まった言い方になりますが、お通夜や葬儀の場では定型句として頻繁に用いられます。他にも「心よりお悔やみ申し上げます」という表現も一般的です。どちらも深い哀悼の意を表す正式な言葉です。
しかし、人によってはあまりに形式ばった表現は口に出しにくいと感じるかもしれません。その場合は、もう少し自分の気持ちを込めた言葉で伝えても問題ありません。例えば「本当に急なことで驚きました。さぞお力落としのことと存じます」や「○○さん(故人)には生前大変お世話になりまして…心から残念でなりません」など、故人や遺族に対する気持ちを率直に伝えるのも良いでしょう。大切なのは、遺族をいたわり、悲しみに寄り添う気持ちを示すことです。
声をかける際には、沈痛な面持ちと落ち着いた声のトーンで、あまり長々と話しすぎないようにします。遺族側も多くの方と挨拶を交わしている最中ですので、手短に気持ちを伝えたら軽く一礼し、「どうかお身体を大切にしてください」など相手を気遣う言葉を添えて切り上げましょう。避けたほうが良いのは、「頑張ってください」「元気を出して」などの言葉です。悪気はなくても、深い悲しみの中にいる遺族にとって「頑張れ」「元気を出せ」は酷な場合があります。代わりに「落ち着かれましたら何でもお手伝いしますので」など、寄り添う姿勢を示す言葉の方が適切です。
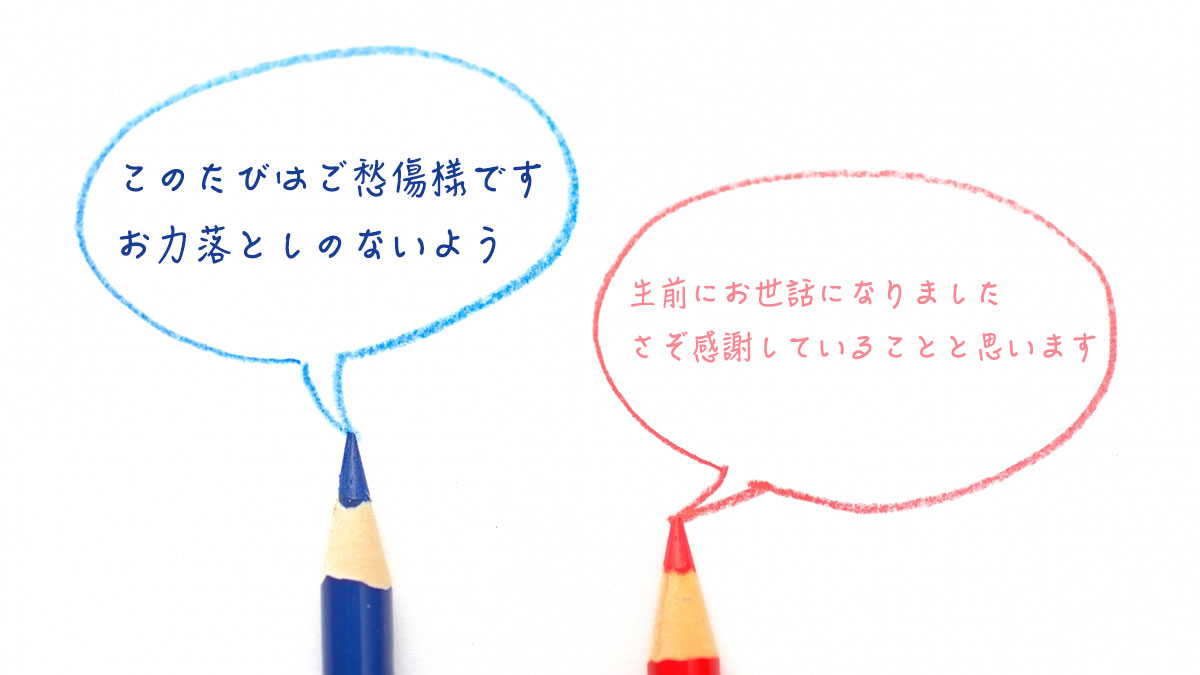 お悔やみの言葉 例文集 | メールやLINEにも対応【保存版】
お悔やみの言葉 例文集 | メールやLINEにも対応【保存版】
 おさるくん
おさるくん
通夜振る舞いでのマナー

お通夜の式が終わると、会場や別室で通夜振る舞いと呼ばれる席が設けられるのが一般的です。通夜振る舞いとは、遺族が参列者に対してお礼として軽い食事や飲み物を振る舞う場のことです。寿司やサンドイッチ、おにぎりなどの料理や、お酒・お茶が用意され、参列者同士や遺族を交えて故人の思い出を語り合う時間となります。
通夜振る舞いに招かれたら、できるだけ断らずに少しでも頂くのがマナーです。悲しみの場で飲食…と尻込みするかもしれませんが、通夜振る舞いは故人の供養の意味も込められています。遠慮して何も口にしないのは、せっかく用意してくださった遺族の厚意を無にすることになりかねません。食欲がない場合でも、せめて箸を付けて一口二口何かを食べる、乾杯ではなくてもお茶やお水を一口飲むなど、形式的にでも一度は手を付けるようにしましょう。もちろん空腹であれば召し上がって問題ありませんが、あまり長居して食べ過ぎるのも控えめにします。
地域によっては、通夜振る舞いの料理を折詰めにして持ち帰ってもらう習慣のところもあります。その場合も、声をかけていただいたらお断りせず、ありがたく受け取りましょう。
お通夜からの帰り方
ある程度通夜振る舞いで時間を過ごしたら、頃合いを見て退出します。長居しすぎず、適切なタイミングで切り上げることもマナーの一つです。他の参列者がひととおりお焼香とお食事を終えて席を立ち始めたら、自分も失礼すると良いでしょう。目安として、通夜振る舞いの席では30分~1時間程度過ごしたらお開きに向かうのが一般的です。
帰る前には、遺族にひと言お声がけしましょう。席を立って遺族のところに行き、「本日はこれで失礼いたします」とお辞儀をしてお伝えします。遺族から「本日はご参列ありがとうございました」などとお礼の言葉をいただいたら、「どうかご自愛ください」「お疲れが出ませんように」といった相手を気遣う言葉を返すと丁寧です。最後にもう一度軽く頭を下げ、静かに会場を後にします。
退場の際、受付で荷物を預けていた場合は忘れずに受け取ります。また、香典返しの品(会葬御礼)をまだ受け取っていない場合は受付で受け取ります。会場出口でも遺族が見送っておられる場合がありますので、その際も一礼し、静かに退出しましょう。
外に出たらコートを着たり身支度を整えて構いません。ただし、会場内でコートを着るのはマナー違反とされていますので、建物のロビーや玄関を出てからコートを羽織るようにします。
まとめ
以上がお通夜当日の一連の流れとマナーになります。初めての参列では緊張するかもしれませんが、周囲の人の振る舞いにならい、基本的な礼儀を守れば大丈夫です。何より大切なのは故人と遺族に敬意と哀悼の意を示す気持ちです。その気持ちがあれば、多少の作法の違いは大目に見てもらえるものです。事前にマナーを理解しておけば落ち着いて行動できるでしょう。ぜひ本記事の内容を参考に、いざという時にも恥をかかない振る舞いで故人をお見送りしてください。