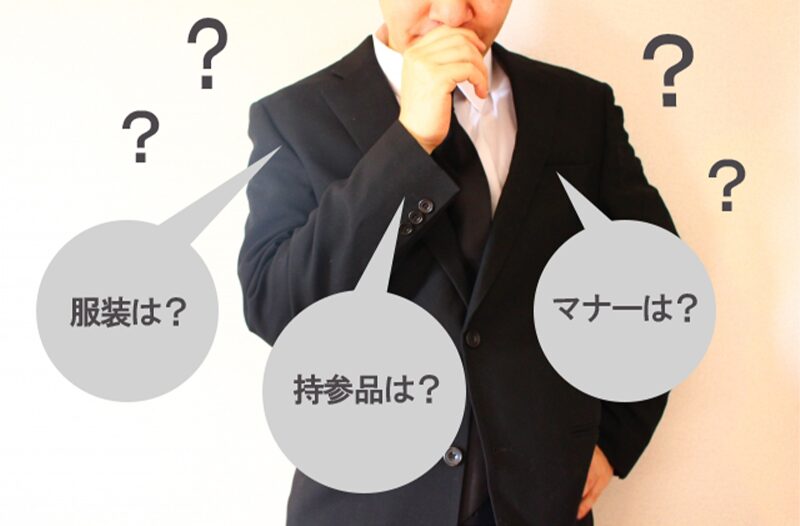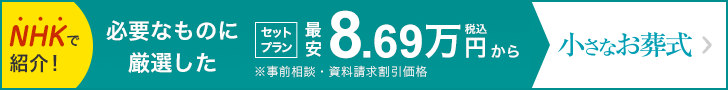大切な方の訃報を突然受け取ったとき、「すぐにでも駆けつけて弔問すべきか、それともお通夜に参列するまで待つべきか」と悩むことはないでしょうか。訃報は常に不意に訪れるものです。ご遺族のもとへ急いで駆けつけたい気持ちもある一方で、「行くべきか、行かないべきか」と迷うのは当然です。本記事では、お通夜前の弔問(正式なお通夜や葬儀より前にご遺族宅などを訪問し、お悔やみを伝えること)について、基本的な考え方や具体的なマナー・注意点をわかりやすく解説します。
お通夜前に弔問してもいい?基本的な考え方
まず押さえておきたい大前提は、「お通夜前の弔問は基本的には控えるべき」だということです。訃報を受け取った直後に駆けつけたい気持ちは理解できますが、多くの場合、ご遺族はお身内を亡くされた直後で非常に慌ただしい状況にあります。葬儀社との打ち合わせや親族への連絡などで忙しく、心の整理もついていない時期です。それに加えて、予期せぬ弔問客が訪れると「お茶の一杯でも…」とおもてなしの対応をさせてしまい、ご遺族に余計な負担をかけてしまう可能性があります。こうした理由から、一般的なマナーとしては通夜当日まで弔問は控え、お通夜や葬儀の場でお悔やみを伝えるのが基本となっているのです。
もっとも、すべてのケースで一律に「絶対に行ってはいけない」というわけではありません。故人やご遺族との関係性によっては、お通夜前に弔問することが適切・必要とされる場合もあります。以下に、どのような場合なら行ってもよいのか、逆に遠慮すべきなのか、主な判断基準をまとめます。
弔問してもよい場合
「基本的には控えるべき」とはいえ、ごく限られた近親者や特別に親しい間柄であれば、お通夜前に駆けつけて弔問してもマナー違反ではないとされています。具体的には次のようなケースです。
近親者の場合(一親等~三親等内の親族)
故人の配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹など、ごく近い親族であれば、訃報を受けてできるだけ早く駆けつけるのが一般的です。三親等(おじ・おば、甥姪、曾祖父母等)より遠い親戚であっても、生前に深い付き合いがあり普段から親しかった間柄ならば、お通夜前に伺っても不自然ではありません。特に同居のご家族や葬儀準備を担う立場の親族であれば、弔問というよりお手伝いも兼ねて早めに駆けつけることが多いでしょう。実際、親族であれば「何かお手伝いできることはありませんか?」と申し出るのが一般的です。身内としてご遺族を支える気持ちで行動すると良いでしょう。
特に親しい友人・知人の場合
血縁ではなくても、家族同然に親しかった友人や幼なじみ、恋人などの場合は、訃報に接して居ても立っても居られないこともあるでしょう。故人と家族ぐるみの深い付き合いがあったような間柄であれば、ご遺族も受け入れてくれる可能性が高く、お通夜前に伺うことも考えられます。ただしこの場合も、ご遺族が「家族だけで静かに見送りたい」と望んでいる状況であれば、そのお気持ちを最優先に配慮すべきです。相手が望んでいないのに押しかけることがないよう、相手の立場に立って判断する配慮が必要です。特別な事情があり、ご遺族から「ぜひ来てほしい」と直接連絡を受けた場合は、その意向に沿ってできるだけ速やかに駆けつけるとよいでしょう。逆にこちらに体調不良など、どうしても行けない事情がある場合は、無理をせず「申し訳ないが伺えない」旨を伝えて構いません。
ご遺族から直接訃報連絡を受けた場合
故人の近しい方(親族や親友など)には、ご遺族から直接お電話等で訃報を知らせることがあります。そのように直接連絡をもらった場合は、ご遺族側もあなたが来てくれることを想定しているケースが多いと言えます。電話を受けた際に「今から伺って大丈夫でしょうか?」と先方の都合を確かめた上で、速やかに駆けつけるとよいでしょう。もちろん、連絡を受けたからといって絶対に行かなければならないわけではありません。遠方に住んでいたり体調が優れなかったりする場合は、「すぐに伺えず申し訳ありません」とお詫びを伝え、後日改めてお悔やみに伺う、弔電や手紙を送るなど別の方法で弔意を伝える選択肢もあります。
以上のように、「ごく近しい間柄でどうしても早く駆けつけたい場合」に限って許容されると考えましょう。この範囲に当てはまらない場合は、無理にお通夜前に伺う必要はありません。では次に、むしろ弔問を控えるべきケースについて説明します。
弔問を控えるべき場合
上記に当てはまらない場合、つまりそれほど親密ではない間柄の場合や、ご遺族の状況次第では、お通夜前の弔問は控えた方が良いとされています。具体的には以下のケースが挙げられます。
会社関係の上司・同僚・取引先など
仕事上の関係者の場合、たとえ訃報を知ってショックを受けたとしても、お通夜前に個人的判断で弔問するのは控えましょう。職場の方が亡くなった場合には、通常会社としてのお悔やみ(弔電を送る、葬儀に社代表者が参列する等)を行います。個人で動く前に上司や社内の決まりを確認し、迷う場合はお通夜・葬儀に参列する形で弔意を示すのが無難です。特別にプライベートでも深い付き合いがあった場合は個人的に伺う選択もあり得ますが、「会社ではなく一個人としての弔問」であることを明確にし、周囲とも相談の上で慎重に判断しましょう。一般的には「社員の身内(親や配偶者)が亡くなった場合に同僚が葬儀まで参列する」程度であり、まして通夜前の弔問は基本的に身内だけに限られることを念頭に置いてください。
ご遺族から直接の連絡がない場合
自分にとっては大切な友人でも、ご遺族側から特に訃報連絡を受けていない場合は、お通夜前に訪問するのは控えるのがマナーです。訃報を知ってすぐにでも駆けつけたい気持ちがあっても、こちらから「お悔やみに行きたい」と申し出るのは一般的にマナー違反とされています。ご遺族にはご遺族の事情がありますし、前述の通り突然訪ねられると対応の負担が大きいからです。どうしても気になる場合でも自分から先走って押しかけることは避け、まずはお通夜や葬儀の日程を待って正式に参列するようにしましょう。なお、地域によっては近所の方が率先して弔問に訪れる習慣がある場合もありますが、その際も事前にご遺族の意向を確認するのが礼儀です。ご遺族側が「今は遠慮してほしい」と言えば、素直に引き下がりましょう。
ご遺族が弔問を遠慮している場合
訃報の連絡や訃報広告に「ご弔問はご遠慮ください」などの注記があることがあります。これはご遺族が弔問客を迎える心の余裕がない、あるいは家族だけで静かに送りたいというお気持ちの表れです。このような場合は、その意向を最優先に尊重し、どんなに親しくてもお通夜前の訪問は控えましょう。弔問を申し出ても断られることがありますが、その際は潔く諦めることが大切です。無理に粘ったりしないよう注意してください。
ご遺族の悲しみを深めてしまう可能性がある場合
亡くなった状況によっては、あなたの訪問がかえってご遺族の心を乱す恐れもあります。たとえば事故や事件など予期せぬ不慮の死・急死の場合、ご遺族は大きなショックを受けています。同年代の友人であるあなたの姿を見ると、かえって「どうしてうちの子が…」と悲しみが募ってしまうことも考えられます。また、死因や最期の状況がよく分からない段階では、うかつな言動がタブーに触れる危険もあります(弔問時に亡くなる直前の様子や死因を尋ねることはご法度です)。状況が落ち着くまでは、軽率な行動は慎み、代わりに手紙でお悔やみを伝える、少し時間が経ってから改めて訪問するといった方法を選ぶ方が良い場合もあります。
自身に慶事(おめでたい行事)が控えている場合
例えば間もなく出産を控えている妊婦さんや、直近に結婚式を予定している方など、自分側にお祝い事がある状況では弔問を遠慮する方が無難です。無理をして駆けつけても、ご遺族に気を遣わせてしまったり、あなた自身も複雑な気持ちになってしまうかもしれません。また古くからの習わしで「おめでたいことと不幸ごとが重なるのは良くない」との考えもありますので、このような場合は弔問は控えても差し支えありません(その際、どうしても参列できない場合は後日改めてお悔やみの手紙を送るなど別の方法で気持ちを伝えると良いでしょう)。もし弔問に伺う場合でも、自身の慶事の話題には触れないよう十分注意してください。
その他、迷うくらいなら控える
上記いずれにも当てはまらず、「行くべきかどうか少しでも迷う」ような場合は、思い切って弔問は見送り、お通夜や葬儀に参列するようにしましょう。一般論として「かなり親密でなければ通夜前の弔問はすべきではない」のですから、少しでもためらいがある場合は行かない方が良いというのが一つの判断基準になります。「行かなかったことで非礼になるのでは…」と心配になるかもしれませんが、正式な場でお悔やみを伝える方がかえって礼儀にかなっていることも多いのです。ご遺族に負担をかけないことを第一に考え、状況に応じて適切な対応を選びましょう。
以上がお通夜前に弔問すべきかどうかの一般的な考え方です。まとめると、原則は控えるものの、身内など特別に親しい場合のみ例外的に訪問するということになります。では、実際に「弔問してもよい」と判断した場合、どのようなマナーに気を付ければいいのでしょうか?次章では、お通夜前に弔問する際の具体的なマナーや注意点について、服装・持ち物・訪問方法・言葉遣いなど項目ごとに詳しく見ていきます。
お通夜前に弔問する際のマナー

ごく親しい間柄で、「ぜひお通夜前にお悔やみに行きたい」となった場合でも、通常のお通夜や葬儀に参列する時以上に慎重なマナーへの配慮が求められます。突然の訪問はご遺族のご厚意で受け入れていただくものですから、失礼のないよう細心の注意を払いましょう。以下では、弔問時の服装や持参品、訪問の時間帯や連絡、現地での振る舞いや言葉遣いなど、知っておくべきマナーを項目別に整理します。
服装:平服で構いません
弔問に駆けつける際の服装は、喪服(正式な喪の装い)である必要はありません。むしろ突然の訃報に接して駆け付ける状況ですから、喪服を着て行くと「不幸を予期して準備していたのか」と受け取られかねず、かえって失礼にあたるケースもあります。そのため、「平服」(普段着)で問題ありません。とはいえカジュアルすぎる服や華美な装いは避け、手持ちの服の中から地味で控えめなデザイン・色合いのものを選びましょう。男性であればダーク系のスーツやジャケットにネクタイなし、女性であれば地味な色合いのブラウスやセーターにパンツなど、黒・紺・グレーなど落ち着いた色の服がおすすめです。ジーンズや派手な柄物、露出の多い服装は避けます。
女性の場合はメイクやアクセサリーも控えめにします。濃いメイクや華やかなアクセサリーは弔問の場にはふさわしくありません。結婚指輪以外のアクセサリーは外し、メイクもナチュラルに抑えましょう。また髪型にも配慮が必要です。髪の長い方は一つにまとめ、前髪もきちんと留めて清潔感を出すようにします。急な弔問では、ご遺族を心身ともに支えるサポート役に回ることもありますから、動きやすく相手に安心感を与える身だしなみが大切です。
なお、親族としてお手伝いに入るような場合はエプロンを持参していくのも良いでしょう。葬儀準備の雑務を手伝う際に役立ちます。いずれにせよ、「取り急ぎ駆け付けた」という状況に合った服装であれば失礼にはあたりません。喪服でなくてもマナー違反ではないので安心してください。
香典・持参すべきものは?
お通夜前に弔問する場合、基本的に香典(こうでん、御霊前として包む現金)は持参しません。香典は本来お通夜や葬儀の際にお渡しするものです。訃報を聞いてすぐ駆け付ける「取り急ぎの弔問」のタイミングでは、香典は後日改めてお通夜・葬儀に参列するときに持参すれば問題ありません。もしお通夜や葬儀に参列しない事情がある場合でも、弔問時に香典だけ置いていくのではなく、後日郵送するか改めて訪問するなどの方法をとる方が丁寧です。
では、お通夜前に何も手ぶらで行ってよいのかというと、基本的には手ぶらで構いません。ご遺族に気を遣わせないためにも、香典以外の手土産なども無理に用意する必要はありません。ただし、「どうしても何かお供えを持参したい」という場合は、故人が生前好きだったお菓子や果物、あるいはお花などを選ぶのも一案です。お花を持参する場合、白や淡い色の花をまとめた小さな花束が良いでしょう。なお、訃報直後にご遺体の枕元に供えるお花のことを「枕花(まくらばな)」と呼びます。枕花を正式に贈る場合は、葬儀社を通じて弔問当日に間に合うよう手配することも可能です。枕花には普通、差出人名を記した札(芳名札)は付けません。白や青を基調にした落ち着いた花を選び(あまりに明るい色合いは避ける)、費用の目安は5,000~2万円程度とされています。宗教や地域の風習によって細かな決まりがある場合もありますので、事前に葬儀社に相談したり、ご遺族に一声かけて確認すると安心です。
まとめると、香典や手土産は基本不要、持参する場合でも相手に負担をかけない気遣いが大切ということです。突然の訪問で重い品物を持って行っても、ご遺族が気を遣いますので注意しましょう。
訪問のタイミングと事前連絡
訪問のタイミング(時間帯)については、常識的に考えて深夜や早朝の弔問は避けるべきです。訃報の連絡が夜遅くにあった場合でも、その深夜に押しかけるのはマナー違反です。ご遺族も休息が必要ですし、夜分に突然訪問するのは負担になります。したがって、どうしてもその日に伺いたい場合でも夜遅く(例えば21時以降)は避け、できれば日中~夕方頃までに訪問するようにします。遠方で当日中に間に合わない場合は、無理に当夜に駆け付けず翌日お通夜の前までに伺うか、お通夜に参列する形でも問題ありません。いずれにしても、「なるべく早く駆けつける」が原則ではありますが、常識的な時間帯の範囲内で行動しましょう。
また、事前連絡は非常に重要です。たとえ親しい間柄でも、何の前触れもなく突然訪問するのは避けるべきです。訃報連絡を直接受けた場合はその電話口で訪問の可否や都合を伺えば良いですが、自分で訃報を知ったケースでは、必ず一度ご遺族に電話等で連絡を取り、「今から伺って大丈夫でしょうか?」と確認するのがマナーです。一般的には、ご遺族から直接連絡をもらっていない場合はこちらから「弔問したい」と申し出るのは控えるべきですが、どうしても行きたい特別な事情があるときは、一方的に押しかけず必ず了承を得るようにします。ご遺族にとって弔問客を迎えることが負担にならないか、迷惑にならないか、細心の配慮を払いましょう。もし「今はお気遣いなく」と辞退された場合は、すぐに諦めて引き下がることも大切です。
地域による慣習で、近所の人々が訃報を聞いてすぐお線香をあげに訪問するのが一般的な土地柄もあるようです。その場合も、「昔からの習慣だから皆行っているはず」と思い込まず、一度は遺族に問い合わせるようにしましょう。「本日は家族のみで過ごしたい」との意向があれば従います。また「〇時頃なら大丈夫です」と時間を指定されることもありますので、指示に従いましょう。とにかく遺族ファーストで、訪問のタイミングは慎重に調整することがマナーです。
訪問時のマナーと遺族への配慮
実際に弔問に伺った際は、なるべくご遺族に負担や気苦労をかけないよう心掛けます。以下、現地での主なマナーと配慮すべき点をリストアップします。
玄関先での挨拶
ご自宅に到着したらインターホンを押し、「○○と申します。突然お伺いして申し訳ありません。この度は心からお悔やみ申し上げます」等、簡潔に弔問に伺った旨とお悔やみを伝えます。玄関先では深々と一礼し、「お忙しいところ恐れ入ります」と丁重な姿勢でご遺族と言葉を交わしましょう。突然の訪問にもかかわらず迎え入れてくれたことに対する感謝とお詫びの気持ちを伝えることが大切です。
長居はしない
ご遺族の負担を減らすため、訪問時の滞在時間は必要最小限にします。故人との対面やお悔やみを述べる時間を含めても、30分~1時間以内には切り上げるのがマナーでしょう。特に深夜にかかった時間帯での訪問になった場合は、さらに短時間で切り上げます。ご遺族が「もっといてください」とおっしゃっても真に受けず、「ではそろそろ失礼いたします」と早めに辞去する方が相手への負担は少なくて済みます。決して長居をしないこと、これが大原則です。
勧められない限り控える
ご遺族宅にお邪魔した際、こちらからあれこれ自分の希望を申し出ないようにします。例えば「故人にぜひお別れしたいので会わせてください」などと、自分から対面をお願いするのはNGです(故人との対面については次節で詳しく触れます)。また、仏壇や祭壇がある場合でも、ご遺族の案内があるまでは勝手に上がり込んでお参りを始めたりしないようにしましょう。基本はすべてご遺族のペースに合わせ、相手から勧められるまで待つ姿勢が大切です。例えば上がり框(かまち)で待っていたら「どうぞ中へ」と案内される、座っていたら「どうぞお顔をご覧になりますか」と勧められる、といった具合です。それまでは控えめに待ちます。
勧められたことは遠慮しない
上記と表裏一体ですが、ご遺族側から「どうぞ○○してください」と勧められたことには素直に従うのが礼儀です。例えば座布団を勧められたら「いえ、立ったままで結構です」と辞退するのではなく、「では失礼します」と腰掛けましょう。同様に、お茶やお菓子を出された場合も、「お気遣いなく」と断るのはかえって相手に気を遣わせてしまいます。たとえ喉が通らなくても、お気持ちだけ頂戴して少し手を付ける方が良いでしょう(飲み切らなくても構いません)。これは故人との対面についても同じです。「もしよろしければお顔をご覧になりますか」と勧められたら、心の準備ができていればありがたくお受けするのがご遺族への礼儀です。逆に「見ると取り乱してしまいそう」など事情がある場合は、「申し訳ありません、あまりに悲しくて正視する自信がないので…」ときちんと理由を伝えて辞退しましょう。いずれにせよ、ご遺族の好意を無下にせず、その場で最も礼にかなった振る舞いを心掛けます。
子連れで伺わない
もし弔問者本人が小さなお子さん連れの場合、基本的にはお子さんは連れて行かない方がよいでしょう。特に、故人が子ども(ご遺族にとってお子さん)であった場合などは、自分の子を連れて行くとご遺族の心情を刺激してしまう恐れがあります。子どもは予測不能な行動をとることもあり、静かに弔問の場に居続けるのは難しい場合も多いです。やむを得ず子連れで行く必要がある場合でも、できれば玄関先でお悔やみだけ伝えて長居しないなど、特段の配慮をしてください。
遺族の方へのいたわりの言葉
弔問の際には、ご遺族に対しまずお悔やみを述べますが、その後もご遺族の心情を気遣う言葉をかけるようにしましょう。例えば「さぞお力落としのことでしょう」「さぞお寂しいことと存じます」といった一言を添えると、遺族の悲嘆に寄り添う気持ちが伝わります。「何かお手伝いできることがあれば仰ってくださいね」と付け加えるのも良いでしょう。ただし長々と話し込むのは禁物です。あくまで簡潔に、しかし心のこもった言葉で、ご遺族をいたわる気持ちを示すことが大切です。
以上が弔問時の基本マナーと配慮です。特に大切なのは「ご遺族を第一に思いやること」に尽きます。最低限のマナーさえ押さえておけば、あとは形式にとらわれすぎず、あなたの率直な気持ちを伝える方がかえって良い場合もあります。深い間柄の弔問であれば、あまり型どおりに堅苦しくするよりも、心からの言葉で気持ちを伝える方が遺族の心に響くことでしょう。
お悔やみの言葉とNG表現
弔問時にはお悔やみの言葉を述べます。多くの人は突然の訃報に対し、何と声をかければよいか迷うものです。基本的には、故人の死を悲しみ遺族を慰める気持ちを短い挨拶で伝えるのがマナーです。難しいことは言わず、シンプルで心のこもった言葉で十分ですが、避けるべき表現もあります。以下にNGとされる言葉遣いをまとめますので注意しましょう。
不幸の繰り返しを連想させる言葉
例えば「たびたび」「またまた」「重ね重ね」などの言葉は、不幸が続くことを連想させるため忌み言葉とされています。弔問の場では使わないようにしましょう。同様に「再び」「返す返す」なども避けます。お悔やみの挨拶ではこうした言葉は不要です。
直接的すぎる「死」「生存」といった表現
あまりに生々しい表現も避けます。たとえば「死亡」「死んだ」「生きていた時」など直接的な言い方はせず、「ご逝去」「お亡くなりになった」「ご生前」などの婉曲表現を用いるのが一般的です。「亡くなった」という表現自体は許容範囲ですが、できれば「ご逝去」など丁寧な語を使うとよいでしょう。
仏教でタブーとされる表現
「浮かばれない」「成仏できない」「迷う(迷っている)」といった言葉は、仏教の考えでは故人の魂が救われないことを暗示するため不適切です。「浮かばれないですね」などと遺族に言うのは避けましょう。また「供養にならない」等も同様です。仏教では死者が成仏して安らかになることを願うため、そうでない状況を連想させる言葉はNGです。
宗教に合わない表現
故人やご遺族の宗教が仏教以外(神道やキリスト教など)の場合、仏教由来の表現は慎んだ方がよいとされます。例えば「ご冥福をお祈りします」「成仏されますように」などは仏教的な言い回しです。詳しくは後述しますが、キリスト教や神道では「冥福」という概念を持たないため、本来こうした表現はふさわしくありません。宗教別のお悔やみ言葉については「4.宗教・地域による違い」で説明します。
このような忌み言葉・タブーに気を付けつつ、実際には形式にとらわれすぎずシンプルなお悔やみの言葉で気持ちを伝えるのが一番です。一般的によく用いられるお悔やみの表現としては、「この度は誠にご愁傷様でございます。心よりお悔やみ申し上げます」などがあります。「ご愁傷様です」はカジュアルな会話表現に思えますが、「この度はご愁傷様でございます。心からお悔やみ申し上げます」のように丁寧に言えば正式な場面でも使われます。ほかにも「突然のことでさぞお力落としのことと存じます」「心中お察し申し上げます」といった遺族を気遣う一言を添えるのも良いでしょう。とにかく長々と話す必要はありません。短いながらも心のこもったお悔やみの挨拶で、あなたの気持ちは十分伝わるはずです。
故人との対面をすすめられたら
弔問に伺うと、ご遺族の計らいで故人と対面させていただける場合があります。病院から自宅等にご遺体を安置している場合、白い布で覆われたご遺体の顔を見せてくださることがあります。「最後のお別れをしてください」というご厚意で勧められるものですので、もし対面を勧められたら原則としてお受けするのがマナーです(前述の通り、精神的に見るのが辛い場合は無理せず丁寧に辞退しても構いません)。ここでは、故人と対面する際の具体的な作法の流れを簡単に押さえておきましょう。
対面する際の基本的な手順は次の通りです。
1.枕元で正座し一礼する
ご遺体の安置されている場所(多くは布団やベッドの上)に近付き、枕元で跪くか正座します。そして故人に向かって静かに一礼(お辞儀)します。
2.白布が上げられたら合掌する
ご遺族が白い布を顔からそっと外してくださったら、合掌して故人の冥福を祈ります(※注意:自分から勝手に白布を取ってはいけません。必ずご遺族に任せます)。合掌の際、数珠を持っていれば左手にかけて合わせます。心の中でお別れの言葉や感謝を伝えましょう。
3.ゆっくりと下がる
お顔を拝んだ後は、合掌したままの姿勢で少し体を後方に下げます。合掌を解き、ご遺体から適度に距離をとりましょう。
4.ご遺族に一礼する
最後に振り返ってご遺族の方に向き直り、改めて深く一礼します。「この度は誠に残念でなりません」「ありがとうございました(対面させてくださって)」など、一言お礼やいたわりの言葉を述べると良いでしょう。
対面の後は、故人のお顔に対して「安らかなお顔ですね」「穏やかなお顔をされていますね」など簡潔に一言述べるのが一般的です。絶対にしてはいけないのは、死因や最期の様子について尋ねることです。「最期はどんな様子でしたか?」などと詮索するのはマナー違反ですので避けてください。あくまで故人とのお別れに集中し、ご遺族の悲しみに寄り添う態度を貫きましょう。
以上、対面の際のポイントを見てきましたが、難しく考える必要はありません。ご遺族の指示に従い、最低限の作法を守れば問題ありません。繰り返しになりますが、お通夜前の弔問はごく親しい人だけが行う特別な機会です。形式にとらわれすぎず、マナーの基本さえ押さえておけば、あとはあなたの真心が何より大切です。堅苦しくなりすぎず、しかし失礼のない態度で、故人とご遺族に向き合ってください。
直接会えない場合:電話・メールで弔意を伝えるには
お通夜前に弔問に伺うのはごく近しい場合に限られますし、遠方で駆けつけられないなど物理的に難しいケースもあるでしょう。また「今訪問するとかえって迷惑では?」と判断して見送る場合もあります。そのようなとき、電話やメールで弔意を伝える方法があります。ここでは、直接会えない場合のお悔やみの伝え方についてポイントを解説します。電話やメールでのお悔やみにはマナー上の注意点もありますので、適切な例文と合わせて確認しておきましょう
電話でお悔やみを伝えるポイント
電話で訃報を知った場合や、弔問に行けない代わりに電話でお悔やみを伝えたい場合もあるでしょう。まず前提として、訃報を電話で受けた際には落ち着いて感謝とお悔やみを述べることが大切です。電話口では相手の顔が見えない分、声のトーンにも注意して、気持ちが伝わるようゆっくり丁寧に話すようにします。
電話でお悔やみを伝える際のポイントは以下の通りです。
手短に伝える
電話では長々と話さず、簡潔にお悔やみの気持ちを伝えるようにします。相手(ご遺族)は突然のことで忙しいかもしれませんし、精神的にも負担が大きい時です。長電話は避け、「この度は突然のことでお力落としと存じます。心よりお悔やみ申し上げます」など短い挨拶で気持ちを伝えたら早めに切り上げるのがマナーです。
相手の状況を気遣う
電話の最初に「このようなお知らせをくださってありがとうございます」と訃報を知らせてくれたことへの感謝を述べ、その後「さぞお辛いことでしょう」「お疲れが出ていませんか」などと相手を思いやる言葉をかけます。自分がどんなに驚いたか、悲しいかといった話に終始するのではなく、ご遺族の心情を第一に考えた言葉を選びましょう。
聞き役に徹する
電話で訃報連絡を受けた場合、相手が話したいことを一通り話し終えるまで遮らずによく聞くことも大切です。自分から根掘り葉掘り尋ねる必要はありません。特に死因や経緯についてこちらから尋ねるのはNGです(ご遺族が自発的に話す分には聞き役に回る)。「そうでしたか…」「お気持ちお察しします…」と相槌を打ちながら静かに耳を傾け、失礼のないタイミングでお悔やみとお礼を述べて電話を終えるようにします。
最後に日程確認
可能であれば、電話を切る前にお通夜や葬儀の日程・場所などを確認させてもらいましょう。「差し支えなければ、ご葬儀の日程を教えていただけますか?」と伺い、参列の意思がある場合は「ぜひお伺いしたいと思っています」と伝えます。参列できない場合でも、「後日改めてお悔やみに伺わせてください」など今後の意向を伝えておくと良いでしょう。電話を切る際は「お忙しい中ご丁寧にありがとうございました。それでは失礼いたします」とお礼を述べて静かに受話器を置きます。
このように電話でのお悔やみは声と言葉だけで気持ちを伝える分、対面より注意が必要ですが、基本は相手を思う気持ちが伝われば十分です。くれぐれも夜遅くや早朝に電話することは避け、先方の迷惑にならない時間帯にかけるようにしましょう。
メール(LINE)で弔意を伝える場合のマナー
最近では、急な訃報で駆け付けられない場合にメールでお悔やみを伝えることも増えています。特に若い世代の友人同士などではLINE(ライン)などのメッセージアプリで連絡を取ることもあるでしょう。ただし、目上の方や正式な関係に対しては、本来はメールよりお悔やみ状(手紙)を出す方が丁寧とされています。やむを得ずメールで連絡する場合は、できるだけ礼を尽くした書き方を心がけましょう。
メールやLINEで弔意を伝える際のマナーを押さえておきます。
件名(タイトル)に配慮
ビジネスメールとは異なり、季節の挨拶や近況報告などは不要です。まず件名を一目で弔意のメールだと分かるようシンプルに書きます。「お悔やみ申し上げます(◯◯様 ご逝去に際して)」のようにすると、メールを開封する前に弔事の要件だと理解してもらえます。「◯◯様ご逝去のお知らせ」といった件名は、訃報を知らせる立場の人が使う表現なので弔問側のメールには不適切です。あくまでこちらから弔意を示すメールであることが分かる表現にしましょう。
本文は前置き不要で本題から
メール本文の書き出しでは、通常のメールにあるような時候の挨拶や相手の安否を尋ねる前置きは不要です。いきなり本題に入り、「◯◯様のご訃報に接し、驚いております。◯◯様のご冥福を心よりお祈り申し上げます。」といった形で弔意とお悔やみの言葉を述べます。自分の氏名も冒頭に名乗りとして入れておくと親切です(受信者が戸惑わないようにするため)。
本文の内容
メールでも基本的には対面や電話の場合と同様、長文にならないよう簡潔に気持ちを伝えます。「突然の訃報に接し信じられない思いです」「生前のお姿を偲び涙がこぼれました」など、自分の感じた悲しみと相手へのお悔やみを率直に書きましょう。また、「お力落としのことと存じます」「どうかお身体をご自愛ください」といった遺族を気遣う言葉も忘れずに添えます。最後は「本来であれば直接お伺いすべきところ、メールにて失礼いたします。」などとお詫びと結びの言葉で締めくくります。改まった相手には敬語を用い、友人に送る場合でも最低限の丁寧さは保ちましょう。
絵文字やスタンプはNG
LINE等で送る場合、普段は顔文字やスタンプを使っているかもしれませんが、弔意を伝えるメッセージでは一切使用しないのがマナーです。ビックリマークやハートマークなどももちろん避け、句読点も控えめにして簡潔な文章にします。メールでも同様に、デコレーションメールやカラフルな絵文字などは厳禁です。フォントや文字色も黒(または濃紺など)の標準的なもので送りましょう。
返信への配慮
相手から返信が来るかもしれませんが、返信を期待してはいけません。場合によってはご遺族がメールを見る余裕がないこともあります。返事がなくても気にせず、相手の負担にならないことを第一に考えます。返信があった場合は、一度で済むよう簡潔にお礼を伝え、それ以上のやり取りは控えましょう。
以上がメールでお悔やみを送る際のマナーです。繰り返しになりますが、正式には手紙(弔事用の便箋)で出すのが最も丁寧です。特にご年配の方や目上の方へのお悔やみは、メールより手紙の方が無難でしょう。しかし近年はコミュニケーション手段の多様化もあり、メールやLINEで伝えるケースも増えてきています。その場合でも最大限礼儀を払った文面にすることで、失礼のない気持ちの伝え方ができるでしょう。
お悔やみメッセージ例文
最後に、電話やメールで弔意を伝える際に使えるお悔やみの言葉の例文をいくつかご紹介します。状況に応じてアレンジし、参考にしてみてください(実際に使う際は形式通りではなく、自分の言葉で伝えることが大切です)。
突然の訃報に対する例文(友人・知人宛)
「このたびは突然の訃報に接し、私も大変驚いております。まだ信じられない思いで、言葉もございません。心よりお悔やみ申し上げます。」
(※驚きと深い悲しみで言葉もないという気持ちを伝える定番表現です)
目上の方のご親族が亡くなった場合(メール例文)
「◯◯様のご逝去の報に接し、謹んでお悔やみ申し上げます。生前のご厚情に心より感謝しつつ、ご冥福をお祈りいたします。◯◯様のご遺族の皆様にも、くれぐれもお力落としのないようお祈り申し上げます。」
(※丁寧な言い回しを用いたフォーマルな文例です。「ご厚情に感謝しつつ」など故人への感謝を述べると品位が感じられます)
親しい友人宛(LINEメッセージ例)
「○○(故人名)さんの訃報に今はただ驚いています。本当に信じられない気持ちでいっぱいです…。○○さんには私もたくさん良くしてもらったので、とても残念でなりません。心からご冥福をお祈りします。△△(自分の名前より)」
(※友人同士の気軽なやり取りでも、絵文字等を使わず真摯な言葉で伝えます。「…」などを用いて喪失感を表現しています)
遠方で葬儀に行けない場合(手紙の一文)
「本来であればすぐにでもお伺いし、お悔やみを申し上げるべきところ、遠方のため叶わず大変心苦しく存じます。書中にて失礼ながらお悔やみ申し上げます。」
(※直接行けない非礼を詫びる文例です。メールでも使えます。)
これらは一例ですが、共通するのは「驚きと悲しみ」「お悔やみ」「相手への気遣い」を簡潔に織り交ぜている点です。型通りでも構いませんので、状況に合わせて適切な言葉を選びましょう。大切なのは、「相手を思いやる気持ち」を真摯に伝えることです。
宗教・地域による違いと例外ケース

日本の葬儀は仏教式が大多数ですが、神道やキリスト教など他の宗教の場合や、地域の風習によって弔問に関する習慣が異なることもあります。最後に、宗教・地域による違いや知っておきたい例外的なケースについて触れておきます。
宗教や宗派によるお悔やみ表現の違い
前述の通り、仏教ではお悔やみの表現として「ご冥福をお祈りします」が広く用いられています。「冥福」とは仏教でいう冥土(死後の世界)での幸福を意味し、故人の魂の安らかさを祈る言葉です。仏教徒のご遺族であれば「心よりご冥福をお祈り申し上げます」は適切なお悔やみと言えるでしょう。一方、神道やキリスト教では「冥福」という概念がないため、本来この表現はふさわしくないとされます。できれば宗教ごとに適した言い回しに言い換える配慮が望ましいです。
神道の場合
人は亡くなると祖霊(みたま)となり家の守護神になるという考え方をします。死は不幸ではなく神として祀られることから、仏教のような「冥福」はありません。そのため「ご冥福をお祈りします」は本来避けた方が良い表現です。代わりに「ご遺族様の平安をお祈りいたします」や「安らかなご永眠をお祈り申し上げます」といった仏教色のない表現が用いられます。たとえば「◯◯様の御霊(みたま)のご平安をお祈り申し上げます」のように言う方法もあります。もっとも、現代の日本ではそこまで厳密に宗教で言葉を使い分けないことも多く、一般的な「お悔やみ申し上げます」でも大きな問題になることは少ないとも言われます。相手が特に神道を信仰していると分かっている場合は、上記のような表現にすると無難でしょう。
キリスト教の場合
キリスト教でも「冥福」は仏教的な表現なので用いません。カトリックやプロテスタントでは、人は亡くなると天国へ召されるという信仰があります。したがって「天国で○○様が安らかにお眠りになりますようお祈りいたします」などと表現すると良いでしょう。プロテスタントでは葬儀を「昇天式」「記念式典」と呼び、故人が天に召されたことを神に感謝する場とも位置付けます。あまり過度に悲嘆的なお悔やみは述べず、「○○様の天国での平安をお祈りします」「ご遺族に神の慰めがありますように」といった宗教色のある言葉を使う場合もあります。ただし、キリスト教の場合もご遺族が特に信仰深いわけでなければ、一般的な「お悔やみ申し上げます」だけでもマナー違反にはなりません。先方がクリスチャンだと分かっているなら、十字架のデザインが入った弔問カードを送る、聖書の一節を引用するなどの配慮も考えられます。
このように宗教によって捉え方や適切な言葉が多少異なります。とはいえ、弔問マナーの根幹部分(訪問する範囲や服装、香典を持たない等)はどの宗教でも基本的には共通です。宗派よりもご遺族の意向を尊重することが何より大切ですので、言葉遣いに迷ったら「お悔やみ申し上げます」など一般的な表現で気持ちを伝えつつ、もし後から「◯◯教ではこの表現は使わない」と知った場合でも深く気に病まないでください。大事なのはあなたの思いやりの心です。
地域や慣習による例外的な習慣
日本は地域によって冠婚葬祭の習慣が少しずつ異なります。お通夜前の弔問に関しても、地域のコミュニティによっては一般常識とされる行動があるかもしれません。例えば地方の一部では、近所の人や町内会の関係者が訃報を聞くとすぐに駆け付けてお線香をあげる風習が根付いている場合があります。そのような土地では、ある程度の関係者がお通夜を待たずに訪れることが想定され、ご遺族も受け入れる準備をしていることがあります。
とはいえ、その場合でもやはり基本はご遺族の意向に沿うことが大切です。たとえ地域の習慣だからといって、遠慮なく大勢で押しかけてはご遺族の負担になる可能性があります。一報聞いた自治会長さんなどがご遺族に確認を取り、近隣への連絡をすることも多いようですので、各自が勝手に訪問するのではなく取りまとめ役の指示に従う方がよいでしょう。ご遺族から「お気持ちだけ頂戴します」と遠慮された場合は、それ以上は控えます。
また、家族葬(親族とごく親しい人だけで行う葬儀)が増えている昨今では、通夜・葬儀自体に呼ばれないケースもあります。その場合、訃報を知った友人知人は弔問すべきか悩むところです。一般的にはに訪れる必要はありません。ご遺族もお呼びしなかった手前、対応に困ってしまいます。家族葬に招かれなかった人は、葬儀後に弔電を送るか、落ち着いた頃(四十九日以降など)に改めて訪問してお線香をあげさせてもらう方が適切です。実際、「葬儀後のお悔やみ(後日弔問)の仕方」については別途マナーがあり、四十九日までの忌明け前に伺う場合は香典を持参してお参りする、といった流れになります。その詳細は本記事の範囲を超えるため割愛しますが、家族葬の場合は通夜前も含め臨機応変に対応し、ご遺族の負担にならない形で弔意を示すようにしましょう。
まとめ
以上、「お通夜前の弔問」に関するマナーや注意点について解説しました。繰り返しになりますが、お通夜前に弔問に伺うケースは限られた特別な場合です。多くの方にとってはお通夜・葬儀で正式にお別れをするのが通常ですので、基本は焦らず公式の場で故人を見送り、ご遺族にお悔やみを伝えれば失礼には当たりません。どうしてもという場合のみ、今回述べたマナーを守った上で慎重に訪問を検討しましょう。大切なのは形式以上に相手を思いやる気持ちです。ご遺族のお気持ちに寄り添い、失礼のないよう心を込めて弔問してください。それが何よりの供養になることでしょう。心よりお悔やみ申し上げます。