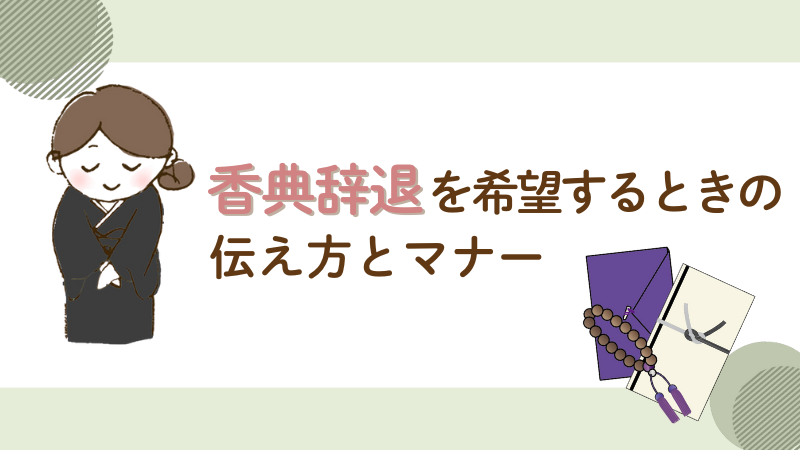近年、家族葬が主流となる中で、香典を辞退する遺族が増えています。故人との最後の時間を大切にしたい、参列者に負担をかけたくないという想いを大切にし、香典を辞退する際の正しい伝え方とマナーを知っておくことが重要です。
目次
香典辞退を選ぶ理由

近年の葬儀では、香典辞退を選択する遺族が増加しています。その背景には、遺族の負担軽減や参列者への配慮など、様々な理由があります。ここでは、香典辞退が選ばれる主な理由や背景について詳しく解説します。
約30%が香典を辞退
株式会社bloom-postが2022年11月に実施した調査[1]によると、全国の香典辞退率は約30%に達しています。
特に注目すべきは地域差で、近畿地方では約50%の方が香典辞退を選択しており、都市部ほど香典辞退の傾向が強いことが分かります。これは都市部における核家族化の進展や、地域コミュニティとの関係性の変化が影響していると考えられます。
小規模で親族中心の家族葬においては、香典辞退を選択するケースがさらに増える傾向にあります。家族葬は参列者を限定して費用を抑えやすく、そもそも香典の必要性が低くなっているという背景があります。
加えて、「参列者に気を遣わせたくない」という遺族の心情や、遺族の負担を軽減したいという意向から、香典辞退が選ばれやすくなっていると考えられます。
遺族や参列者の負担を減らしたい想いをもつ人にとって、家族葬は理想的な形といえます。たとえば「小さなお葬式」の小さな家族葬プランでは、費用を抑えながらも温かみのある葬儀を行えるのが魅力です。香典辞退にも対応しやすく、事前に費用が明確な点も安心です。
香典辞退を選ぶ3つの理由
現代の香典辞退には、主に次の理由があります。それぞれの理由について詳しく見ていきましょう。
香典返しの負担軽減
香典をいただくと、後日お礼として香典返しを用意する必要があり、品物選びや発送手配など多くの手間がかかります。
悲しみの中にある遺族にとって、これらの作業は精神的にも身体的にも大きな負担となるため、事前に辞退することで負担を軽減したいと考える方が増えています。
参列者への経済的配慮
現代では経済状況の多様化により、参列者が香典を用意することが経済的負担となる場合があります。特に家族葬のような親しい関係者で執り行う葬儀では、相手の状況を思いやり、金銭的な負担をかけたくないという優しさから香典辞退を選択する傾向があります。
家族のみでの費用負担
核家族化や個人主義の浸透により、冠婚葬祭における経済的な相互扶助の考え方が変化しています。他人に頼らず、自分たちの責任で葬儀を執り行いたいという気持ちが、香典辞退の選択につながっています。
地域による香典辞退の傾向

調査結果を見ると、住んでいる地域によって香典辞退を選ぶ人の割合に大きな違いがあることが分かります。近畿地方では約50%の方が香典辞退を選んでいるのに対し、全国平均は約30%となっており、約20ポイントもの開きがあります。
なぜこのような差が生まれるのでしょうか。その背景には、近畿地方特有の葬儀文化や社会環境の変化があります。近畿地方では家族葬を選ぶ方が全国平均よりも多く、都市部での核家族化が進んでいることも影響しています。
また、関西圏では古くから商業が発達し、実用的で合理的な考え方が根付いているため「香典の負担を軽減したい」「お返しの手間を省きたい」といった現実的な判断から香典辞退を選ぶケースが多いと考えられます。
一方で、地方では今でも地域のつながりが深く、冠婚葬祭でお互いを支え合う文化が残っています。そのため、香典辞退を選ぶ人は少ない傾向にあります。これは日本社会の価値観や人間関係のあり方が多様化する中で、葬儀のスタイルにも違いが生まれていることを示しています。
香典辞退が選ばれる背景
時代が変わるにつれて、私たちの「お別れ」の仕方も少しずつ変わってきています。香典辞退という選択は、ただ手続きを楽にしたいからではなく、「大切な人を思いやる気持ち」を表す新しい方法なのかもしれません。
昔の香典は、お金で支え合うという実際的な意味がありました。でも今は、「心の重荷を軽くしてあげたい」という気持ちが強くなっています。香典を遠慮することで、参列される方は金額を悩まずに済み、ご遺族もお返しの準備に追われることがありません。
また、香典辞退には「故人らしさを大切にしたい」という気持ちも込められています。「人様にご迷惑をおかけしたくない」と生前よく言っていた方の人柄を、最後のお別れでも大切にしてあげたいと考えるご家族が多くなっているのです。このように香典辞退は、現代の新しいお別れの形として、私たちの気持ちに寄り添ってくれる選択肢になっているのです。
香典辞退の伝え方

香典辞退を確実に伝えるためには、適切なタイミングと方法が重要です。電話、メール、案内状など、それぞれの連絡手段に応じた伝え方のポイントと具体的な文例をご紹介します。相手に失礼のないよう、丁寧で分かりやすい表現を心がけましょう。
電話での伝え方
電話で香典辞退を伝える際は、タイミングと言葉遣いに注意が必要です。電話での訃報連絡時に、葬儀の詳細とともに香典辞退の旨を伝えることが基本です。
具体的な伝え方として、まず故人の逝去を報告し、続いて葬儀の日時と場所を伝えます。その後、「故人の生前の意向で香典は受け取らない形で考えております」と明確に伝えましょう。この際、理由を「故人の遺志」とすることで、相手も理解しやすくなります。
電話では相手の反応を確認しながら、丁寧に説明することが大切です。
メールでの伝え方
メールで香典辞退を伝える場合は、件名を「訃報のお知らせ」とし、本文では簡潔かつ丁寧に伝えることが重要です。絵文字などは使用せず、できるだけシンプルに記しましょう。
また、訃報では「葬儀が滞りなく終わりますように」という祈りを込めて、読点を使用しないのが一般的です。メールの場合は読みにくくなる可能性があるため、適宜改行を入れましょう。
メールでの基本構成は以下の通りです。
- 件名:「訃報のお知らせ」
- 挨拶と逝去の報告
- 葬儀の詳細(日時・場所)
- 香典辞退の旨
- 感謝の気持ち
以下に、上記の基本構成をふまえた例文をご紹介します。
◯◯が去る◯月◯日に逝去いたしました
誠に勝手ながら生前の故人の希望により家族葬を執り行います
つきましては御香典や御供物などのお気遣いは辞退させていただきます
生前中のご厚誼に深く感謝申し上げます
香典辞退をメールで伝える際は、丁寧で簡潔な文面と形式を守りつつ、故人や遺族の意向を誠実に伝えることが大切です。
案内状・訃報通知での伝え方

書面での香典辞退は、最も正式で確実な方法です。訃報の連絡や葬儀の案内状で辞退する旨を伝えることで、参列者の準備がスムーズになります。
書面での基本構成と例文は、以下の通りです。
- 故人の逝去の報告
- 葬儀の詳細(日時・場所)
- 香典辞退の明記
- 感謝の気持ち
去る◯月◯日に永眠いたしました
葬儀につきましては故人の遺志により近親者のみで執り行います
また弔問 香典 供物 弔電に関しましても故人の遺志により固くご辞退申し上げます
故人が生前賜りましたご厚誼に深くお礼申し上げます
故人の意志を尊重した旨を丁寧に記し、参列者への配慮と感謝の気持ちを忘れずに伝えることが大切です。
職場への伝え方
仕事関係の方への香典辞退では、ビジネスマナーを踏まえた適切な対応が必要となります。訃報の連絡を入れる際に伝えることが基本です。
職場への連絡では、以下の点に注意しましょう。
- 上司への報告を最優先とする
- 香典だけでなく、供花や弔電についても辞退の意向を伝える
- 会社の規定や慣習を確認する
- 必要に応じて人事部門にも連絡する
上記の注意点をふまえた、具体的な伝え方を以下にご紹介します。
職場への香典辞退の連絡でも、礼儀を守りつつ必要な情報を簡潔に伝えましょう。
香典辞退を伝えるタイミング
香典辞退を伝えるタイミングは、訃報連絡と同時に行うことが最も効果的です。参列者の方には葬儀前に事前に伝える必要があり、参列者以外の方には訃報と一緒にお知らせします。
訃報の連絡は参列の有無を問わず、故人が亡くなってすぐに一斉に行うことが多いため、この初回の連絡時に香典辞退の意向を明確に伝えることが重要です。
弔電も辞退したい場合は、訃報連絡の際に弔電についても辞退の意向を伝えておくと良いでしょう。
香典辞退のマナーと対応方法

香典辞退を伝える場合、相手の気持ちを尊重し、失礼のないよう細心の注意を払う必要があります。適切なマナーを守ることで、故人を偲ぶ大切な時間を心穏やかに過ごすことができます。
ここでは、実際の対応方法と注意点を詳しく解説します。
香典辞退を伝える基本マナー
香典には故人を支える気持ちが込められているため、相手の気持ちを無下にしないよう丁寧に伝えることが重要です。
基本的なマナーとして、以下の点を守りましょう。
- 理由を明確に伝える(「故人の遺志」が最も適切)
- 感謝の気持ちを表現する
- 丁寧な言葉遣いを心がける
- 相手が理解しやすい説明をする
香典辞退の理由として「故人の遺志」を伝えることで、相手も納得しやすくなります。「故人がまわりの人たちに負担をかけないでほしいと申しておりましたので」という表現は、相手に配慮した適切な伝え方です。
香典を受け取ってしまった場合
香典辞退を伝えていても、当日に持参される方がいる場合があります。香典を辞退しても、それでも渡したいと申し出る人もいるため、この場合の対応はケースによってさまざまです。
以下に、受け取ってしまった場合の対応手順をご紹介します。
- 一度は丁重に辞退する
- 相手の強い意向がある場合は、周囲の目につかない場所で対応
- 感謝の気持ちを表し、例外的に受け取る
- 後日、香典返しを行う
やむを得ず受け取ることになった場合は、「ご辞退のご案内を差し上げていたにもかかわらず、お心遣いをいただき、深く恐縮しております」と謝意を示すことが大切です。
香典を渡されそうになった場合

葬儀後に香典の持参を希望された場合や、直接訪問された場合は、改めて香典辞退の意向を丁寧に伝える必要があります。香典を辞退した旨を事前に伝えたにもかかわらず香典が送られてきた場合は、改めてその意図を明確にすることが必要です。
ここでは、ケースごとの対応例をご紹介します。
- 直接持参された場合
その場で再度丁寧に辞退し、相手の気持ちに感謝を示す。 - 強くお渡ししたいと言われた場合
一度は辞退した上で、相手の意向を汲み取り例外的に受け取る。 - 郵送で送られてきた場合
電話で連絡し、事情を説明した上で対応を相談する。 - どうしても受け取れない場合
相手の了承を得てから返却手続きを行う。
香典を持参された方の気持ちを尊重し、丁寧に辞退の意向を伝えます。それでも相手が強く希望される場合は例外的に受け取り、後日香典返しを行うのがよいでしょう。
葬儀の受付での対応
葬儀当日の受付では、香典辞退の旨を明確に伝える必要があります。受付係には事前に香典辞退の方針を伝え、統一した対応をしてもらいましょう。
以下は、受付でスムーズに対応するためのポイントです。
- 「香典辞退」を見やすい位置に表示する
- 受付で係が丁寧に説明する
- 例外的に受け取る場合の対応方法を決めておく
- 供花や供物についても辞退するか決めておく
会場には参列者に向けて「香典辞退」を伝える看板などを設置し、受付係が遺族の代わりにその旨をお伝えすると円滑に進みます。
故人の関係者に配慮すべきポイント

香典辞退を選択した場合でも、様々な関係者への配慮が必要です。親族、会社関係者、地域コミュニティなど、それぞれの立場や関係性を考慮した対応方法を知っておくことで、円滑な葬儀運営が可能になります。
親族への配慮
親族への香典辞退は、特に慎重な配慮が必要です。親族間では香典のやり取りが慣習となっている場合があり、突然の香典辞退は関係に溝が生まれる可能性があります。
親族に香典辞退を伝える際は、以下の点に配慮しましょう。
- 事前に主要な親族に相談する
- 香典辞退の理由を丁寧に説明する
- 親族の意見を尊重し、柔軟に対応する
- 必要に応じて親族のみ受け取ることも検討
特に年配の親族の場合、香典は弔意を表す重要な手段と考えている方も多いため、一律の辞退ではなく、個別の対応を検討することも大切です。家族間での事前の話し合いを通じて、全員が納得できる方針を決めることが重要です。
会社関係者への対応
会社関係者への香典辞退は、職場の慣習や規定を考慮する必要があります。会社の規定などで香典を贈ることが決まっている場合もあるため、改めて確認することが重要です。
会社関係者への対応時は、以下のポイントをおさえましょう。
- 上司に事前相談する
- 人事部門へ連絡する
- 会社の香典の慣習や規定を確認する
- 同僚へ香典辞退を知らせる
会社によっては、香典・供花・弔電のセットが規定されている場合もあるため、どの項目を辞退するかも明確に伝える必要があります。また、会社全体の慶弔規定がある場合は、それに従った対応を検討することも重要です。
地域コミュニティへの配慮

地域のコミュニティでは、近所づきあいの一環として香典を持参する習慣があります。都市部・住宅地では、ご近所づきあいの希薄化や、経済的な事情を背景に香典辞退の家族葬が増加しています。
香典辞退を地域の人に伝える際は、次の点をおさえましょう。
- 自治会や町内会へ連絡する
- 近隣住民へ丁寧に周知する
- 地域の慣習を尊重した対応を心掛ける
- 必要に応じて個別に説明をする
地域によっては、香典辞退に対する理解が得られにくい場合もあるため、丁寧な説明と配慮が必要です。特に長年住んでいる地域では従来の慣習を尊重しつつ、現代的な価値観も理解してもらう努力が大切です。
香典辞退後も良好な関係を保つために
香典辞退後も、関係者と良好な関係を保つことはとても重要です。香典を辞退したことで相手に不快感を与えないよう、継続的に配慮をしましょう。
良好な関係性を保つには、次のような方法があります。
- 忌明け後、年賀状や暑中見舞いで挨拶を続ける
- 法要の際には適切な連絡を取る
- 相手の冠婚葬祭には適切に対応する
- 感謝の気持ちを忘れずに表現する
このような配慮により、感謝の気持ちを表すことが大切です。
また、香典辞退後も継続的な関係維持を心がけ、相手の気持ちを尊重した対応を続けましょう。
まとめ

現代の葬儀では、香典辞退が定着しつつあります。株式会社bloom-postの調査[1]でも明らかになったように、多くの方が遺族の負担軽減や参列者への配慮から、香典辞退を選択しています。
しかし、香典辞退をする際は相手の気持ちを尊重し、失礼のないよう細心の注意を払うことが重要です。適切な伝え方とマナーを守ることで、故人を偲ぶ大切な時間をより心穏やかに過ごすことができるでしょう。
出典