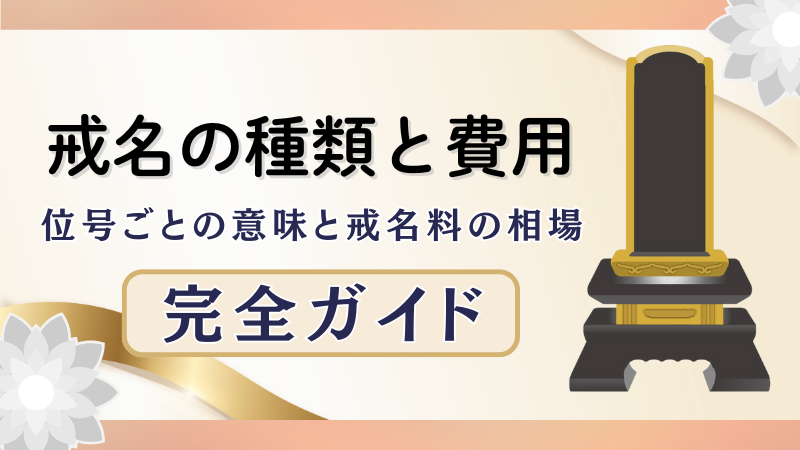戒名(かいみょう)とは、仏式の葬儀で故人に授けられる新しい名前であり、仏教徒としての証でもあります。戒名には様々な種類(位号)があり、その位号に応じて意味や授与される条件、費用相場が異なります。さらに、菩提寺の有無によって戒名授与の方法や費用が変わってくるため、注意が必要です。
本記事では戒名の種類と意味、費用の相場、菩提寺がある場合とない場合の授与方法、さらに戒名を付けないという選択肢についても詳しく解説します。
目次
戒名の位号の種類とその意味

戒名の位号には「信士・信女」「居士・大姉」「院号」などがあり、それぞれの位号には明確な意味や授与基準があります。この章では、それぞれの位号の特徴や意味について詳しく説明していきます。
信士・信女の特徴
信士(しんし)は男性、信女(しんにょ)は女性に対して授与される一般的な戒名で、仏教徒として基本的な信仰を持つ方に広く授けられます。特別な社会的功績や寺院への多大な貢献がない場合でも、日常的な信仰心が認められれば授与されるため、最も広く普及している位号です。
信士・信女という戒名は世間で最も一般的なものであり、仏教を信仰する者としての基本的な証とも言えます。また、この位号は仏教徒としての敬意を示す最も簡易的な形式であり、経済的負担が比較的軽いことも特徴です。戒名料を抑えたいという家庭や、特に格式にこだわらずにシンプルに見送りたいと考える方には最適です。
居士・大姉の特徴
居士(こじ)は男性、大姉(だいし)は女性に授与され、信士・信女よりも格式が高くなります。主に地域社会や菩提寺への貢献が顕著な場合に授与され、生前の活動や寺院に対する奉仕を評価して位号を決定します。
人格や社会的地位を重視した位号であり、家族が故人を特別に称えたいと考える場合に適しています。この位号は一定の費用負担を伴いますが、故人への尊敬や感謝を示すものとして意義深い選択となります。
院号の特徴
院号は戒名の最高位で、伝統的には貴族や皇族、武士など特別に身分の高い方に授与されました。現在では社会的功績が非常に高かった方や、寺院への多額の寄付や貢献をした方に授与されます。
戒名の最初に「院」の文字が入り、「院居士」「院大姉」「院信士」「院信女」などの形式となります。この位号は戒名料も高額となり、寺院運営を支える寄付的な意味合いも強く含まれています。
一般的には多額の戒名料を支払える家庭や、社会的名誉を特に重視する家庭で選ばれることが多いです。
戒名にかかる費用相場

戒名料は寺院から明示的に「〇〇円です」と提示されるものではなく、「お気持ち(志)で包んでください」という形で渡すのが通例です。しかし実際にはランクごとにおおよその相場が存在します。
戒名の一般的な相場目安とランクごとの違い
戒名料は「定価」ではなくお布施であるため、本来は施主(遺族)の気持ち次第とされています。実際には寺院も経験上の相場を把握しており、多くの菩提寺では過去の事例に基づく大まかな金額の目安を持っています。
檀家であれば生前から寄付やお布施の額の習慣があるため、大体の水準が暗黙的に共有されている場合もあります。しかし檀家でなく初めて依頼する寺院の場合、どの程度包めばよいか悩むことも多いでしょう。
その際は遠慮せず葬儀社や寺院に相場を確認することも大切です。「お気持ちで」と言われても、「皆さまどのくらい包まれていますか?」などと尋ねれば、参考になる金額のヒントを教えてもらえるケースもあります。
信士・信女の費用相場
信士・信女は最も一般的な位号であり、費用相場は約20~30万円です。多くの寺院でこの相場が目安とされ、一般家庭でも負担しやすい額とされています。地域や寺院によって若干の差異がありますが、一般的にはこの範囲内で収まります。
居士・大姉の費用相場
居士・大姉の場合、信士・信女よりもランクが高いため費用も上がり、約40~60万円程度が一般的な相場です。地域や寺院によっても差はありますが、この位号を選ぶ場合はそれなりの費用負担が必要です。費用は寺院への貢献や社会的評価を反映しています。
院号の費用相場
院号が付く戒名は特に高額で、費用相場は70~100万円以上になることも珍しくありません。この費用の高さは、寺院への寄付や社会的評価、特別な功績を反映しているためであり、家族が故人への敬意を強く示したい場合に選ばれます。
宗教による費用の違い
戒名料は宗派や地域によっても差が出ることがあります。浄土真宗や日蓮宗など、戒名の呼び名や構成が異なる宗派では若干相場も異なる傾向があります。
例えば浄土真宗では戒名を「法名」と呼び、戒名料のランクも「信士・信女」「居士・大姉」の2段階のみとなるため、結果的に最高額でも他宗派ほど高騰しないとも言われます。浄土真宗の法名では、信士・信女は20万円~、居士・大姉は50万円~が費用の一例です。
一方、曹洞宗や臨済宗など禅宗ではランクが細かく分かれており、院居士まで含めて4段階に及ぶため最高ランクは100万円以上と高額になる傾向があります。
日蓮宗では独自の「院信士」という中間ランクも用いられますが、こちらは30~50万円程度と比較的抑えめであるなど、宗派内のしきたりによって金額帯が異なることがあるのです。
地域による費用の違い
地域差も無視できません。都市部の寺院は檀家数が多く競争があるため戒名料相場が比較的低く、地方の寺院では檀家が少なく経営維持のため相場がやや高めに設定されているといわれています。
ただしこれは一概には言えず、同じ都道府県内でも寺院ごとに慣習が異なる場合があります。実際、「戒名料は住職によって違いがあり、地域によっても異なる」とされており、一律の基準は存在しないのが現状です。
近年は直葬や家族葬の増加など葬儀の簡素化に伴い、戒名料も全体的に下がる傾向にあるといった指摘もあります。これは経済状況や葬儀の価値観の変化で、高額な院号を希望するケースが減っているためとも考えられます。
 初めてでも迷わない!家族葬の流れと費用 丸わかりガイド
初めてでも迷わない!家族葬の流れと費用 丸わかりガイド
例えば「小さなお葬式」では、時代に合わせたシンプルで温かな葬儀プランが人気です。
中でも家族だけで落ち着いて見送れる「小さな家族葬」プランは、通夜・告別式を含んだ内容で、料金の明確さが喜ばれています。より負担を抑えたい方には、必要最低限の供養のみを行う「火葬式」プランも選べます。
戒名料が高額になりがちな理由と注意点
戒名料が時に高額になる背景には、戒名の持つ本来の意味と近世以降の歴史が影響しています。
江戸時代の檀家制度で庶民にも戒名が広まった当初、身分や寄進額によって戒名に差が付いた経緯があります。位牌に戒名を記す文化が定着すると、「立派な戒名を付けてあげたい」という遺族の思いから寺院への寄進合戦のようになった側面もありました。
 位牌の基本【種類、文字の入れ方、大きさ、その後の処分方法まで】
位牌の基本【種類、文字の入れ方、大きさ、その後の処分方法まで】
この名残で、現代でも戒名に対するお布施額は「ご志納」という建前ながら実質的にはランクに応じた相場が存在する状況です。高位の戒名ほど多額のお布施を要するのは、「故人が極楽往生できるよう厚く供養する」という考え方もありますが、現実的には寺院運営への寄付的性格も持っています
このように戒名料は半ば慣習的に定まった相場がありますが、注意したいのは無理をして高額な戒名を求めないことです。お寺によっては住職が故人の人柄や家柄から判断して位号を提案してくれる場合もありますが、最終的にランクを決めるのは遺族の意思です。先祖代々が居士号だからといって必ずしも合わせる必要はありませんし、経済的に負担が大きければ遠慮なく希望を伝えて問題ありません。最近では「戒名料を巡るトラブル」を避けるため、事前に戒名の位とお布施の目安を住職と相談する方も増えています。逆に何も聞かずに高額なお布施を包んでしまい、後で「そんなに出す必要なかったのでは…」と後悔するケースもあります。不明点は遠慮なく質問し、納得した上で戒名を授かることが大切です。
菩提寺がある場合の戒名授与方法

菩提寺がある場合の戒名授与は、住職との密接なコミュニケーションが重要になります。長年付き合いのある菩提寺だからこそ、故人の人柄や家族の要望を反映した戒名を丁寧に授与してもらうことができます。
この章では、菩提寺を通じて戒名を授けてもらう際の流れや注意点を詳しく解説します。
菩提寺での戒名授与の流れ
菩提寺がある場合は、まず葬儀の準備段階で寺院の住職と連絡を取り、故人の人柄や生前の信仰、戒名のランクや費用の希望などについて具体的に相談します。この相談をもとに住職が戒名を決定し、通夜や葬儀の際に戒名授与の儀式が行われます。
菩提寺は故人や遺族との関係が深いため、故人の性格や遺族の希望をより細やかに反映した戒名を授与することができます。また、戒名だけでなく、その後の法要や納骨なども円滑に行うことができ、家族の負担が軽減されることも特徴です。
戒名授与後は位牌を準備し、菩提寺で法要を行い納骨するのが一般的です。
事前の相談の重要性
戒名授与は、家族や故人の意向が強く反映されるため、事前の準備や相談が非常に重要です。
生前から戒名を授ける「生前戒名」という方法もあり、生前のうちに戒名を決定しておけば、遺族が葬儀時に戒名選定の負担を負うことがなくなります。また、戒名料についてもあらかじめ明確にしておくことで、後々の金銭的トラブルを防ぐことができます。
家族全員が納得できるよう、できるだけ早期に菩提寺の住職と具体的な話し合いを進めておくことをおすすめします。
菩提寺がない場合の戒名授与方法

菩提寺がない場合は戒名を授かるために、僧侶派遣サービスを利用する方法があります。このサービスを利用すると、明瞭な料金設定で安心して戒名を選ぶことができるメリットがあります。
本章では、菩提寺がない方が戒名を授けてもらうための僧侶派遣サービスの活用方法や注意点について詳しくご説明します。
僧侶派遣サービスの利用方法
菩提寺がない場合は、僧侶派遣サービスを利用することが一般的です。僧侶派遣サービスは、インターネットや葬儀社を通じて僧侶を手配できるサービスで、葬儀の際の読経や戒名授与を行ってもらうことができます。
サービスを利用する際は、故人や遺族が希望する宗派を明確にし、位号や予算をしっかり伝えることで、適切な戒名を授けることが可能になります。料金体系が明朗であることが特徴で、あらかじめ位号ごとの料金が決まっているため、予算に合わせて安心して戒名を選択することができます。
例えば、よりそう「お坊さん便」では、全国どこでも定額で僧侶を手配でき、宗派やご希望に合わせた対応が可能です。事前に料金がわかるため、安心して依頼することができます。
 初めての喪主でも安心!『よりそうお坊さん便』徹底ガイド【僧侶手配】
初めての喪主でも安心!『よりそうお坊さん便』徹底ガイド【僧侶手配】
利用にあたっての注意点
僧侶派遣サービスを利用する場合、菩提寺があるにもかかわらず無断で利用すると後のトラブルになる可能性があります。そのため、もし菩提寺が存在する場合は、必ず事前に寺院の許可を得る必要があります。
また、派遣される僧侶とは直接的な繋がりがないため、戒名を授与する際の故人の情報提供が非常に重要です。生前の人柄や趣味、信仰の深さを詳しく伝えることで、より故人にふさわしい戒名を授けることができます。
戒名を授かるには、菩提寺の住職に依頼する方法が基本ですが、昨今では僧侶派遣サービスによる戒名授与も選択肢の一つです。それぞれ費用感や手順に違いがあるものの、いずれの場合も故人の人柄を反映した戒名にしてもらえるよう、十分な情報提供と相談をすることが大切です。
戒名を付けないという選択肢

戒名を付けないで葬儀を行うという選択肢も近年増えつつあります。俗名(生前の名前)のままで葬儀を行う場合、無宗教葬や家族葬などの形式を取ることが多くなります。戒名を付けないことで、戒名料の経済的負担を軽減できるだけでなく、宗教色を抑えた自由な葬儀スタイルを実現できます。
ただ菩提寺がある場合には、戒名なしでの納骨が許可されないこともあるため、事前に寺院や親族と慎重に協議を行い理解を得ておく必要があります。また、戒名を付けない場合でも、故人への敬意や家族の想いを形にするために、位牌や納骨先、供養方法を明確に決定しておくことが望まれます。
まとめ

戒名は仏弟子となった証として故人に贈られる大切な名前であり、その文字には故人の人生や想いが託されます。一方で戒名料はランクによって大きく異なり、経済的負担も考慮しなければなりません。
大切なのは、故人や遺族が納得できる戒名を無理のない形で授かることです。菩提寺や僧侶とよく相談し、必要であれば現代のサービスも活用しながら、それぞれにふさわしい送り方を準備しておきましょう。
戒名に込められた意味を理解し、適切な選択をすることが、故人への何よりの供養となるはずです。