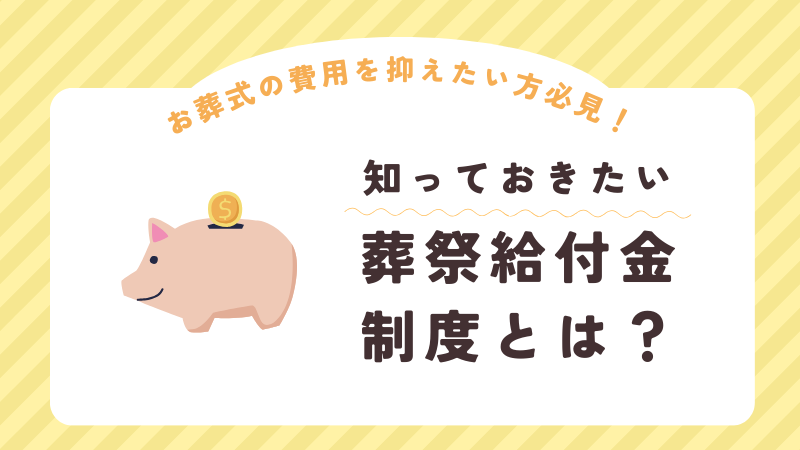親が亡くなった後、葬儀費用の負担は大きなものです。しかし、日本には葬儀後に申請することで受け取れる給付金制度があるのをご存じでしょうか?これは健康保険や共済など、故人が加入していた公的な保険制度から支給されるもので、葬儀費用の一部を補助してくれます。本記事では、2025年時点の最新情報にもとづき、全国の葬祭費・埋葬料の給付制度について、制度ごとの概要や申請条件、必要書類、申請先、期限、給付額の目安などをわかりやすくまとめました。葬儀後の手続きに不慣れな方にもわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
目次
葬祭費・埋葬料とは?制度による違いはあるの?
「葬祭費」や「埋葬料」とは、人が亡くなった際に、その葬儀(葬祭)を行った人に支給される給付金のことです。故人が加入していた保険制度によって呼び名が異なり、支給元も異なりますが、いずれも所定の手続きをすることで受け取れる公的な補助金です。
葬祭費(そうさいひ)
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合に、その保険者(市区町村や広域連合)から支給される給付金です。自治体に申請することで受け取ることができ、支給額の平均は約5万円前後となっています。自治体によって金額は多少異なり、東京都23区では7万円、その他の市町村では3~7万円程度と幅がありますが、多くの自治体が5万円と設定しています。この給付金は正式には「葬祭費補助金制度」と呼ばれることもあります。
埋葬料(まいそうりょう)
故人が会社員などで勤務先の健康保険(協会けんぽや健康保険組合)に加入していた場合、または公務員等で共済組合に加入していた場合に、その健康保険組合や共済組合から支給される給付金です。こちらも5万円前後が相場ですが、健康保険組合や共済組合によっては独自の付加給付が設けられており、10万円以上の給付になることもあります。基本的に支給額の最低ラインは法律で定められており、どの健康保険組合でも一律5万円(健康保険法第100条)と決まっています。それにプラスして組合ごとの上乗せ給付がある場合がある、というイメージです。
なお、埋葬料と葬祭費の違いは主に上記のように故人の保険種別の違いによります。いずれも故人の葬儀を行った人に支給される点では共通しています。ただし後述するように、健康保険の場合は「埋葬料」を受け取れる遺族がいない場合に、実際にかかった費用を上限として支給される「埋葬費」という制度があります。また、故人が健康保険の被扶養者(家族)であった場合には「家族埋葬料」といって、加入者(世帯主)に対して同様の給付が行われます。以下で制度ごとに詳しく見ていきましょう。
国民健康保険の葬祭費 – 自営業や退職者などが対象
まず、故人が国民健康保険(国保)に加入していた場合についてです。国民健康保険は自営業者や年金生活者、無職の方などが加入する市区町村運営の医療保険です。国保加入者が亡くなったときは、その葬式や火葬など葬祭を行った方(喪主)に対して葬祭費が支給されます。
支給額の目安
葬祭費の支給額は自治体によって定められており、多くの場合5万円です。ただし地域によって多少差があり、例えば東京都特別区は7万円に設定されています。一方、地方自治体では3~5万円程度が多い傾向です。
申請者(受給できる人)
原則として葬儀の喪主など実際に葬祭を行った人が申請・受給できます。故人と申請者の親族関係は問われません。実務上は、葬儀社の請求書で喪主として名前が記載されている人が該当します。
申請先
故人が加入していた国民健康保険を管轄する市区町村の役所(国民健康保険課など)が窓口です。故人が住民登録していた市区町村の国保担当窓口に申請しましょう。
必要書類
一般的に以下のような書類が必要となります。
-
葬祭費支給請求書: 市区町村役場で入手できる所定の申請用紙です。窓口でもらうか、自治体ホームページからダウンロードできる場合もあります。
-
故人の国民健康保険証: 紙の保険証があればそれを提出します。2024年末以降はマイナンバーカードの健康保険証利用に移行していますが、その場合も保険証情報がわかる書類の提出が求められることがあります。
-
喪主(申請者)の本人確認書類: 運転免許証やマイナンバーカードなど。
-
喪主が葬儀を行ったことが分かる書類: 例えば葬儀社の領収書(但し葬儀費用とわかるもの)や会葬御礼のハガキ、会葬者名簿などです。自治体によって細かい指定がありますが、葬儀の事実と喪主を確認できるものを用意します。
-
喪主名義の振込先がわかる通帳や口座情報。
-
死亡を証明する書類: 自治体によっては死亡診断書の写しや火葬許可証などを求める場合があります。案内に記載がなければ基本不要ですが、心配な場合は持参すると安心です。
上記は一般的な必要書類の例ですが、自治体によって異なる場合があります。申請前に自治体のホームページや窓口に問い合わせて確認しておきましょう。
申請期限
葬祭費は葬儀を行った日の翌日から起算して2年以内に申請しなければなりません。これは健康保険法上の時効期間で、2年を過ぎると原則として受け取りができなくなってしまいます。葬儀後は何かと忙しいですが、できるだけ早めに手続きするようにしましょう。
支給時期
申請から支給までは自治体にもよりますが、概ね1~2か月以内に指定口座へ振り込まれます。詳しい時期は申請時に担当者に確認してください。
注意点
葬祭費はあくまで「葬祭を行ったこと」に対する給付金です。そのため自治体によっては、火葬のみ(直葬)でお別れの会等を一切行わなかった場合は支給対象外とする場合があります。例えば遺体を火葬するだけで葬式を執り行わなかったケースなどです。近年は簡易なお別れを選ぶ方もいますが、事前に自治体へ確認し*証明できるもの(火葬許可証など)は必ず保管しておきましょう。
後期高齢者医療制度の葬祭費 – 75歳以上の方が対象
故人が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた場合も、国民健康保険と同様に葬祭費が支給されます。この制度は都道府県ごとの広域連合が運営していますが、手続き窓口は各市区町村に設けられています。
支給額の目安
後期高齢者医療の葬祭費も一律5万円としている地域が多くなっています。例えば埼玉県後期高齢者医療広域連合では「葬祭費5万円」が支給額と定められています。東京都など他の地域でも概ね5万円で全国的に足並みが揃っているようです(地域により多少の違いがある場合は各広域連合から周知されています)。
申請者
原則として葬儀の施行者(喪主)が申請できます。こちらも国保と同様で、故人との続柄は問いません。
申請先
故人がお住まいだった市区町村の後期高齢者医療担当窓口に申請します。具体的には市区町村役場の国保年金課内に後期高齢者医療係があることが多いです。広域連合(都道府県)の窓口ではなく、お住まいの市区町村で手続きできるのでご安心ください。
必要書類
基本的には国民健康保険の葬祭費と同様の書類が求められます。後期高齢者医療被保険者証、葬儀の領収書や会葬礼状など葬儀を行った証明書類、申請者の本人確認書類、振込先通帳などが必要です。自治体ごとに細かな指定がありますので、申請前に確認しましょう。
申請期限
葬祭を行った翌日から2年以内が申請期限です。国保と同じく2年を過ぎると時効で請求できなくなりますので注意してください。
支給時期
おおむね申請後1~2か月ほどで指定口座に振り込まれます。自治体によってはもっと早い場合もあります。
国民健康保険の葬祭費と後期高齢者医療の葬祭費は制度上ほぼ同じ扱いです。ただし75歳以上の方は国保ではなく後期高齢者医療制度から給付される点が異なります。75歳到達前後で制度が切り替わるため、故人の年齢によって申請先の制度を間違えないようにしましょう(市役所で確認すれば案内してもらえます)。また国民健康保険と後期高齢者医療の重複加入はありませんので、基本的にはどちらか一方の申請になります。
会社員の健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)の埋葬料
故人が現役の会社員などで健康保険(被用者保険)に加入していた場合、その健康保険から「埋葬料」が支給されます。被用者保険とは、サラリーマンやOLの方が勤務先で加入する健康保険で、「協会けんぽ」(中小企業等が加入)や各企業・業界の「健康保険組合」(組合健保)があります。これらはいずれも健康保険法に基づく制度で、給付内容もほぼ共通です。以下では両者まとめて会社員の健康保険として説明します。
支給額
健康保険の埋葬料は法律で一律5万円と定められています。したがって基本的には5万円が支給額となります。ただし、一部の健康保険組合では組合独自の付加給付として、この5万円に上乗せで独自の給付金を支給する場合があります。例えばある企業の健康保険組合では埋葬料に数万円を加算して給付するケースもあります。具体的な金額は各健康保険組合の給付内容によるため、加入していた健康保険組合の案内を確認してください。なお、全国健康保険協会(協会けんぽ)では法律どおり5万円(固定)の支給です。
申請者と「埋葬料」「埋葬費」の違い
健康保険の場合、給付を受け取れる人(申請者)が故人と生計を共にしていた遺族かどうかで扱いが変わります。基本パターンは次の2通りです。
-
故人と生計維持関係にあった遺族が葬儀を行った場合・・・その遺族に対して「埋葬料」5万円が支給されます。多くの場合、故人と同居し収入を支え合っていた配偶者や子が該当します。例えば一家の生計を支えていたお父様が亡くなり、お母様や同居のお子様が葬儀を行った場合、お母様(または子)に埋葬料5万円が給付されます。
-
故人に生計維持関係の遺族がいない場合・・・上記のような受給者がいないケースでは、実際に葬儀を執行した方に対して、かかった葬儀費用を限度に5万円までが「埋葬費」として支給されます。例えば独身で一人暮らしだった方が亡くなり、遠方に住む兄弟姉妹が葬儀を執り行った場合などが該当します。この場合は実費精算型となり、葬儀に要した費用が5万円に満たなければその額が支給額となります。
被扶養者が亡くなった場合(家族埋葬料)
故人が会社員本人ではなく、その扶養家族(被扶養者)であった場合にも給付があります。これを「家族埋葬料」といい、扶養されていた家族が亡くなったとき、健康保険の被保険者(世帯主)に5万円が支給されます。例えば会社員である娘さんの扶養に入っていたお父様が亡くなった場合、娘さんは健康保険から家族埋葬料5万円を受け取れるということです。家族埋葬料には付加給付の上乗せはなく、一律5万円です。
申請先
加入していた健康保険によって異なりますが、基本は会社経由で健康保険組合または協会けんぽ支部に申請します。在職中に亡くなった場合は、会社の総務・人事担当者に連絡すれば、必要書類の案内や「健康保険埋葬料支給申請書」の用紙をもらえます。協会けんぽ加入の場合は会社を通じて協会けんぽ都道府県支部へ、組合健保の場合はその健康保険組合へ提出します。会社を退職後に任意継続中の方が亡くなった場合などは、直接保険者に申請書を郵送することも可能です。いずれにせよまずは健康保険証の発行元に問い合わせると確実です。
必要書類
健康保険の埋葬料支給申請書(会社または保険者から入手)、故人の健康保険証(被保険者証)、事業主の証明(在職中の場合、申請書に会社の証明欄があります)、申請者の本人確認書類、振込先口座情報、そして埋葬費を請求する場合は葬儀費用の領収書等が必要です。領収書が無い場合は葬儀社の案内状や会葬礼状などでも実績を証明できます。会社員本人の死亡の場合は死亡診断書のコピー等も添付するケースがありますが、健康保険の資格喪失手続きと同時に行うことで簡略化できる場合もあります。
申請期限
健康保険の埋葬料(費)も期限は2年です。多くの場合、「亡くなった日の翌日から2年以内」に申請する必要があります。会社員が亡くなった場合、健康保険と年金の資格喪失届を5日以内に会社経由で提出する決まりがありますが、埋葬料の申請はそれよりは余裕があります。ただし忘れないようこちらも早めに手続きしておきましょう。
支給時期
協会けんぽの場合は支部にもよりますが、申請から1~2か月程度で指定の口座に振り込まれます。健康保険組合の場合も概ね同様ですが、会社の締めや書類取りまとめのタイミングによって多少異なることがあります。
注意点
在職中の方が亡くなった場合、健康保険証の返却や扶養家族の資格喪失など複数の手続きが同時に発生します。埋葬料の申請書と資格喪失届を同時に提出できると手間が一度で済みスムーズです。また、会社を通さず直接申請する場合は不備が無いよう注意しましょう。書類に不明点があれば健康保険組合や協会けんぽに問い合わせ、指示を仰ぐと安心です。
公務員など共済組合の埋葬料
故人が公務員(国家公務員・地方公務員)や私立学校の教職員など、共済組合に加入していた場合も埋葬料が支給されます。共済組合は職域ごとに分かれていますが、健康保険同様に死亡時の給付が用意されています。基本的な仕組みは健康保険の埋葬料と似ていますが、共済独自の上乗せ給付などがある点が特徴です。
支給額
共済組合の埋葬料もおおむね5万円+αです。法的な下限は健康保険と同様に5万円程度となっていますが、共済組合では組合員向けの福祉制度として追加給付があることが多く、支給額が10万円以上になるケースも少なくありません。たとえば地方公務員共済や教職員共済などでは、組合員の福利厚生の一環で葬祭補助金が別途支給される場合があります。それぞれの共済組合ごとに給付額が異なるため、詳細は加入していた共済の給付案内を確認してください。
申請者
基本的には**葬儀を執り行った方(喪主)**となります。共済の場合も生計維持関係がある遺族がいればその方、いない場合は実際に葬儀を行った方に給付されます。また組合員の被扶養者が亡くなった場合には、組合員(世帯主)に家族埋葬料が支給される点も健康保険と同様です。
申請先
故人が所属していた共済組合の窓口に申請します。在職中であれば職場を通じて手続きします。例えば地方公務員なら各自治体の共済担当課、教職員なら私学共済などに申請書を提出します。退職者で任意継続組合員の場合は、直接共済組合に連絡して手続きを行います。
必要書類
こちらも埋葬料支給申請書(共済所定の様式)、故人の共済組合員証(または健康保険証)、葬儀の領収書など葬儀を証明する書類、申請者の身分証明書、振込先口座情報などが必要です。共済組合独自の追加給付がある場合、その申請書類が別途必要なことがあります。詳細は各共済組合の案内に従ってください。
申請期限
共済組合も基本的に2年の時効期間があります。健康保険と同様、「葬祭を行った翌日から2年間」などと定められていますので、遅れないよう申請しましょう。
注意点
共済組合の場合、在職中の死亡では年金(共済年金→遺族厚生年金)や死亡退職金など複数の給付も絡んできます。また、公務員の場合は所属長への報告や公務災害との切り分けなど内部手続きも必要です。まずは所属先に連絡し、葬儀後の手続きについて指示を仰ぐと安心です。「埋葬料の申請をしたい」旨を伝えれば、しかるべき書類や手順を教えてもらえます。
なお、共済組合や船員保険など特殊な保険者でも埋葬料(葬祭料)の給付制度は共通して存在します。いずれのケースでも**「申請しなければ受給できない」**点は同じですので、忘れずに手続きを行いましょう。
【比較表】主な保険制度別・葬祭費用給付の比較
各制度ごとの葬祭費・埋葬料について、ポイントを比較表にまとめました。
| 加入していた保険制度 | 給付金の名称 (対象者) | 支給額の目安 | 申請先/窓口 | 申請期限(時効) |
|---|---|---|---|---|
| 国民健康保険(市区町村) | 葬祭費(喪主) | 多くは5万円 ※自治体により3~7万円 |
故人の住所地の市区町村役所(国保担当) | 葬儀翌日から2年以内 |
| 後期高齢者医療制度(広域連合) | 葬祭費(喪主) | 5万円(全国ほぼ共通) | 故人の住所地の市区町村役所(後期高齢者医療担当) | 葬儀翌日から2年以内 |
| 会社員の健康保険(協会けんぽ等) | 埋葬料(生計維持していた遺族) 埋葬費(上記以外の喪主) 家族埋葬料(被扶養者死亡時) |
5万円(法定給付) ※組合健保は付加給付で増額あり |
勤務先経由で健康保険組合 または協会けんぽ支部 |
死亡翌日から2年以内 |
| 公務員等の共済組合 | 埋葬料(遺族 or 喪主) 家族埋葬料(被扶養者死亡時) |
5万円+α(組合ごとに独自給付) | 所属先経由で共済組合 (退職者は直接共済へ) |
原則2年以内(組合規程による) |
※いずれの制度も請求できるのは原則1回限りで、同一の故人に対して重複して受け取ることはできません。また、死亡当時に加入していた保険から支給されます(複数の健康保険に重複加入していた場合は通常ありません)。どの制度でも申請が必要で、自動では支給されない点に注意しましょう。
手続き全般の流れと共通の注意点
最後に、葬祭費・埋葬料の申請手続きの流れと共通する注意点をまとめます。
申請手続きの流れ
1.加入保険の確認
まず故人が亡くなった時点で加入していた公的医療保険の種類を確認します。会社勤めなら健康保険、公務員なら共済、75歳以上なら後期高齢者医療、それ以外は国民健康保険というケースが一般的です。不明な場合は市区町村役場や勤務先に問い合わせましょう。
2.死亡届の提出
葬祭費とは直接関係ありませんが、故人が亡くなったら7日以内に役所へ死亡届を提出します。火葬許可証の発行を受けます(葬儀社が代行することも多いです)。この死亡届の情報に基づき保険資格の喪失処理も行われます。
3.保険証の返却
故人の健康保険証(被保険者証)を関係先に返却します。国保や後期高齢者医療なら市区町村、協会けんぽ・健康保険組合なら勤務先経由、共済なら所属先などに返します。保険証は葬祭費/埋葬料の申請時に必要になるため、返却時にコピーを取るか申請書類と一緒に提出しましょう。
4.申請書の入手
該当する保険者の葬祭費(埋葬料)支給申請書を入手します。市区町村役場や保険組合の窓口で配布しているほか、公式サイトからダウンロード可能な場合もあります。勤務先で加入の保険なら会社に用紙があることも多いです。
5.必要書類の準備
前述の各制度の項で挙げた必要書類を揃えます。共通して重要なのは、葬儀を行ったことを証明する書類と申請者の本人確認書類です。領収書や会葬礼状などは大切に保管しましょう。また振込先口座も忘れずに確認します。
6.申請書類の提出
必要事項を記入した申請書と添付書類一式を、保険者の窓口へ提出します。窓口持参のほか、郵送受付としている自治体や組合もあります。不備があると後日連絡が来て再提出となるので、記入漏れや押印漏れがないよう注意しましょう。
7.支給決定・振込
審査の上、支給が決定すると申請者名義の銀行口座に給付金が振り込まれます。振込通知が郵送されることもあります。振込までの期間は制度にもよりますが、概ね1~2か月が目安です。
共通の注意点
必ず自分で申請を
葬祭費・埋葬料は申請しないともらえません。年金のように自動振込されるものではないため、「知らずに時効が過ぎていた」ということがないようにしましょう。
期限(時効)に注意
くり返しになりますが、請求権は2年間で消滅します。2年を過ぎると原則として請求が認められなくなってしまいます。書類が揃っていなくてもまずは申請だけ済ませ、後から不足書類を提出することも可能なケースがありますので、早めの行動を心がけましょう。
給付は1回限り
葬祭費・埋葬料は一人の故人に対し一度きりの支給です。他の遺族が後から「自分も欲しい」と申し出ても追加でもらえるものではありません。代表者が申請して受け取ったら完了となります。
併給調整
基本的に故人が加入していたいずれか一つの保険からしか受け取れません。例えば在職中の会社員が75歳以上の配偶者を扶養していた場合、その配偶者が亡くなれば後期高齢者医療から葬祭費5万円が出ますが、会社員の健康保険から家族埋葬料5万円が重ねて出ることはありません(後期高齢者医療制度に加入した時点で健康保険の扶養から外れているためです)。このように重複受給はできないことを覚えておきましょう。
他の給付との関係
葬祭費・埋葬料以外にも、故人の死亡に際して受け取れるお金はいくつかあります。例えば故人が厚生年金に加入していれば遺族年金、勤務中の事故で亡くなった場合は労災保険の遺族補償や労災の葬祭給付などです。これらはそれぞれ別制度の給付金です。労災保険の葬祭料(葬祭給付)は葬祭費・埋葬料と名前は似ていますが全く別枠で、金額も「給付基礎日額の60日分 or 30日分+31万5千円の高い方」など非常に手厚く(100万円以上となるケースもあります)支給されます。対象となる方は労働基準監督署への申請も忘れずに行ってください。ただし労災から葬祭料が出る場合でも、健康保険等からの埋葬料も受給できます。労災と健康保険はそれぞれ別制度であり、併給調整の対象ではないためです。該当する場合は両方請求して構いません。
まとめ ~申請を忘れず、葬儀後の経済的負担軽減に役立てましょう~
以上、全国の主な公的保険制度における葬祭費用の給付金制度について詳しく解説しました。国民健康保険や後期高齢者医療では「葬祭費」、会社員の健康保険や共済組合では「埋葬料」という名称で、おおむね5万円程度の給付が受けられることがお分かりいただけたと思います。【葬祭費5万円】と聞くと葬儀費用全体からすれば決して大きくはありませんが、それでも**「ないよりはありがたい」実質的な支援**です。
葬儀後は何かと慌ただしく、また深い悲しみの中にいる時期でもあります。しかし、こうした公的給付金は申請しなければ受け取ることができません。せっかくの権利を逃さないためにも、本記事を参考にぜひ早めの手続きを心がけてください。役所や保険者に問い合わせれば丁寧に教えてもらえますので、不明点は抱え込まず相談しましょう。
葬祭費・埋葬料の存在は意外と知られていないため、周囲でご家族を看取った経験のある方にも教えてあげると感謝されるかもしれません。公的保険から支給されるこれらの給付金制度を上手に活用し、少しでも葬儀費用の負担軽減に役立てていただければ幸いです。