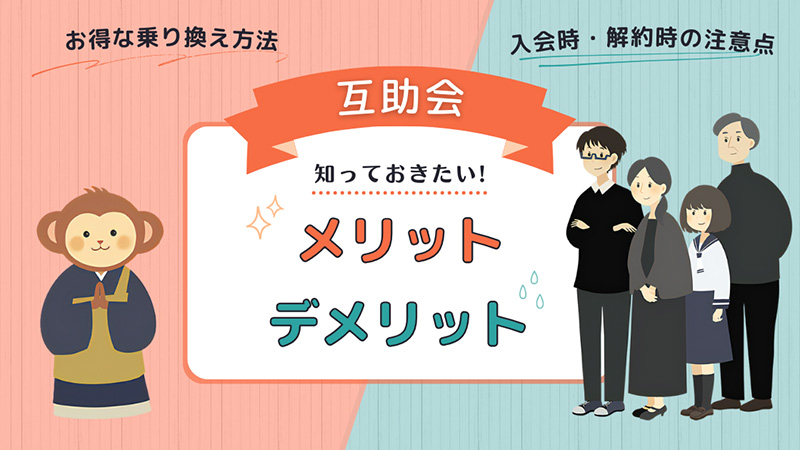冠婚葬祭の費用を前もって積み立てておける「互助会」は、結婚式やお葬式の準備として以前から利用されてきたサービスです。月々少額を積み立てていくことで、いざという時に割安な価格で式典サービスを受けられる仕組みですが、実際のメリット・デメリットや近年の業界動向については最新情報を踏まえて理解しておくことが大切です。この記事では、2025年時点の互助会の現状に基づき、その利点と欠点、解約時の注意点やトラブル事例、そして他社サービスへの乗り換えについてまでわかりやすく解説します。
互助会とはどんなサービス?
互助会(ごじょかい)は、冠婚葬祭に備えて毎月掛け金を積み立てることで、結婚式や葬儀のサービスを割引価格で受けられる前払い式の積立システムです。経済産業大臣の許可を受けた業者が運営するもので、全国に多数の互助会があります。例えば月額1,000〜5,000円程度を60〜120回払い(5年〜10年)で積み立て、合計20万〜50万円ほどのコースを完納するといったプランが一般的です。
積立金を完納すると同等額かそれ以上のサービス(例:25万円の積立で50万円相当の葬儀プラン)が受けられるのが特徴で、掛け捨ての保険と異なり将来的に自分や家族の冠婚葬祭費用に充当できます。また、多くの互助会では契約者本人以外の家族もサービスを利用できるため、一人が入会すれば家族全員に恩恵が及ぶ場合もあります。万一、積立途中で葬儀を行う必要が生じた場合でも、不足分を支払えば途中利用が可能であり、完納後は権利が半永久的に保証される互助会も多く見られます。
互助会と保険・共済の違い: 保険や共済が契約者の死亡時にお金(保険金)を給付するのに対し、互助会は積立金をサービス(葬儀施行など現物)という形で提供する点が異なります。互助会はあくまで前払いの割引サービスであり、蓄えたお金が増えるわけではありません。しかし、物価や葬儀費用が値上がりしても契約時の金額でサービスを受けられるため、将来の価格変動に備える効果もあるとされています(インフレに強い)。一方で、互助会は民間企業が運営するため経営破綻のリスクがあり、後述するように倒産時の保証範囲にも限界があります。
互助会のメリット

互助会には以下のようなメリットがあります。
まとまった葬儀費用を割安にできる
前もってコツコツ積み立てることで、大きな出費が必要な葬儀も比較的低価格で行うことができます。互助会会員向けの葬儀プランは一般価格より3〜5割程度安く設定されているケースが多く、積立額に対して受けられるサービス価値が高くなるよう設計されています(例:25万円積立で50万円相当の葬儀プラン)。このため、豪華な葬儀を予算内で実現したい人には大きな助けになります。
掛け捨てにならない安心感
互助会の掛け金は保険のように払いっぱなしで消えてしまうものではなく、最終的に自分たちの冠婚葬祭に充てられる資金になります。実際に葬儀などに利用しなかった場合でも、解約すれば積立金の一部が戻ってくる点は安心材料です(※解約時には後述の通り手数料が差し引かれます)。「何も起こらなければお金が無駄になる」といった心配が少ないのはメリットと言えるでしょう。
家族も含めて利用できる
互助会によっては契約者本人だけでなく家族全員が会員特典を受けられる場合があります。例えば親が互助会に入っていれば、子供や配偶者などが葬儀サービスを利用できるプランもあります。一家で一契約しておけば万一の際に家族内で融通が利くため、効率的な備えとなります。
全国規模のネットワーク
大手の互助会は全国に提携式場や関連会社を持っていることが多く、引っ越しをしても積立金を移管して利用可能です。実際、全国展開の互助会なら居住地が変わっても新天地の提携斎場で積立を使えるケースがあります。将来的に遠方に移り住む可能性がある人でも、大手互助会を選んでおけば安心です。
物価上昇に強い
前払いでサービスを契約している形になるため、契約後に葬儀費用の相場が上がっても契約時の内容でサービス提供が保証されます。インフレ等で葬儀一式の価格が上がっても追加負担なく当初のプランを利用できるのは、互助会ならではの利点です。将来の物価変動が読めない中で、早めに費用を確定できる安心感があります。
互助会のデメリット

一方、互助会には注意すべきデメリットや制約も存在します。
利用できる式場が限られる
互助会を利用して葬儀を行う場合、その互助会が運営・提携している斎場に基本的には限定されます。自由に好きな葬儀社や式場を選べるわけではなく、「互助会のエリア内・提携内でしか使えない」という制約があります。互助会によっては提携先が全国的に充実しているところもありますが、地域密着型でエリアが限定される互助会もあるため、入会前に対応エリアや提携式場を確認する必要があります。
葬儀費用の全てを賄えるわけではない
互助会の積立だけで葬儀代が全額まかなえるケースは多くありません。互助会がカバーするのはあくまでプラン内の費用(祭壇や棺、式場基本料など)であり、プランに含まれない項目は別途支払いとなります。例えば飲食接待費(通夜振る舞いや精進落とし)、香典返し、寺院へのお布施、火葬料などは互助会プラン外であることが一般的です。そのため、互助会に入っていても追加費用は必ず発生し、最終的な総額は積立金+追加費用となる点に注意が必要です。「積立金だけで葬儀ができる」と誤解していると、いざという時に想定外の出費に驚くことになります。
小規模葬には不向きな場合がある
互助会の葬儀プランは従来型の一般葬(中〜大規模葬)を前提に作られていることが多く、最近増えている家族葬や直葬(火葬式)など超小規模な葬儀には対応しにくい傾向があります。用意されたプランの中に希望するスタイル(例えば火葬のみのシンプルなお別れ)が無い場合もあり、自分の望む葬儀規模とプラン内容がミスマッチになるリスクがあります。「とにかく簡素に済ませたい」と考える方にとっては、互助会の大掛かりなプランではかえって割高になる可能性もあります。
解約時の手数料トラブルが多い
互助会を途中で解約する際には所定の解約手数料が差し引かれますが、この手数料が想像以上に高額でトラブルになるケースが少なくありません。多くの互助会は業界団体(全日本冠婚葬祭互助協会)の標準約款に沿っており、解約手数料は積立金の約2割前後に設定されているのが一般的だとされています。[1] 例えば50万円積み立てていた場合、解約手数料が約10万円差し引かれ、手元に戻るのは40万円程度という計算です。このように解約すると積立金の20%前後が戻ってこないため、「思ったより返金が少ない」と感じる人が多いのです。解約金を巡る消費者からの苦情・相談件数も多く、実際に裁判になった例もあります。
運営会社が倒産するリスク
互助会は民間企業が運営する前払い式サービスである以上、会社の経営破綻リスクはゼロではありません。特に近年は少子高齢化や葬儀の小規模化で会員数が減少し、業績不振に陥る互助会も増えています。法律上、互助会は受け取った前受金(積立金)の半額を供託金として国に預けて保全する義務がありますが、万一倒産した場合でも加入者に返ってくるのは積立金の半分程度にとどまる可能性が高いとされています。
状況次第では半分すら戻らないケースもあり得るため、会社選びや経営状況のチェックが重要です。実際、互助会業者の数は最盛期の1986年に415社でしたが、その後統廃合や撤退が進み2024年時点では236社まで減少しています。契約件数も2015年頃に約2,400万件だったものが、2024年には約2,128万件程度まで減少傾向にあります。[2]このような業界動向も踏まえ、加入する互助会の信頼性や規模感は事前によく確認しておきましょう。
互助会に入会・解約する際のポイントと最新動向

互助会を上手に活用するためには、入会時と解約時それぞれで押さえておきたいポイントがあります。また、近年は解約を巡るトラブルや他社サービスへの乗り換えといった動きも出ています。以下に2025年時点での注意点をまとめます。
入会前に確認しておきたいこと
プラン内容と適用範囲をチェック
提示されたプランでどこまで費用がカバーされるか(含まれない費用項目は何か)を必ず確認しましょう。特に香典返し・飲食費・寺院費用・火葬料などが別途になるケースが多いので、「積立金だけで足りるのか」「追加費用の目安」を事前に聞いておくことが大切です。また、自分が希望する葬儀の規模(直葬や家族葬など)にその互助会プランが対応しているかも確認しましょう。互助会のプランは一般葬向け中心のため、小規模葬を希望する場合はプランが合わない可能性もあります。希望に合うプランがないと感じたら、無理に入会する必要はありません。
対応エリアと提携先の規模
自分の住む地域や実家のある地域で互助会の提携斎場が十分にあるかをチェックしましょう。将来的に引っ越す可能性がある人は、全国規模で展開している互助会を選ぶと安心です。全国にネットワークを持つ互助会なら、転居先でも積立金を利用できる場合があります。逆にエリア限定の互助会だと、引っ越し先で使えず無駄になってしまうこともあり得ます。
経営の信頼性
前述の通り互助会は長期間にわたる前払い契約なので、運営会社の健全性も重要な判断材料です。全互協(互助会業界団体)加盟の大手であるか、会社の実績や財務状況はどうか、といった点を可能な範囲で調べてみましょう。口コミや評判も参考になりますが、公的機関への供託状況や事業規模(預かり資産がどれくらいあるか)も確認できるとベターです。あまりにも知名度が低い互助会や、新興で実績の乏しい会社の場合は慎重に検討しましょう。
約款と解約条件の確認
契約前に解約時のルールについてもしっかり確認しておくことが大切です。「解約する場合は手数料○○%を差し引いて返金」など約款に必ず記載がありますので、入会前に目を通しましょう。後から「こんなに引かれるの!?」と驚かないためにも、解約手数料がいくらになるかシミュレーションしておくと安心です。一般的には積立総額の約20%前後と言われますが、会社によって違いがあるかもしれません。また、解約手続きの方法(連絡先や必要書類)も事前に確認しておくとスムーズです。
解約するときの手順と注意点
基本的な解約手順
互助会を解約したい場合、まず契約者本人が互助会の窓口に電話等で解約の意思を伝えます。その後、互助会から郵送されてくる解約届(所定の書類)に必要事項を記入し返送するのが一般的な流れです。書類が受理されると、後日指定の銀行口座に積立金の残額(積立累計から解約手数料を引いた額)が払い戻されます。返金が振り込まれるまでに数週間~1ヶ月程度かかる場合があります。解約時には会員証や身分証明書のコピー提出が求められることもありますので、案内に従って手続きを進めましょう。
解約手数料の負担
上述のように、解約時には積立金の約20%前後が手数料として差し引かれることに注意が必要です。積立期間が短いほど手元に戻る割合が少なく、加入直後〜数ヶ月での解約だと返金がゼロという互助会もあります(※実際、ある互助会では「2500円を200回積立=50万円コース」を9回以内で解約すると一切返金なし、という例が報告されています)。長年積み立ててきても解約時に数万円〜十数万円が差し引かれるため、「もったいないからこのまま続けた方がいいのでは」と迷う方もいるでしょう。ただし無理に続けても使わなければ意味がないため、本当に互助会を使う見込みがない場合は早めに解約した方がトータルの損失は抑えられます。解約手数料は契約時点でルールが決まっているので、悩んだら契約書面を再確認してみてください。
解約トラブルへの対処
残念ながら、解約の際に互助会側の対応が不誠実でトラブルになるケースも報告されています。「電話がなかなか繋がらない」「解約を引き止められて話が進まない」「書類を送ったのに返金がいつまでもされない」といった相談が消費生活センター等にも寄せられています。こうした場合は経済産業省の商取引監督部署に相談することも検討しましょう。互助会業者は経産省の許可事業ですので、悪質な対応を続ける業者には行政指導が入ることもあります。実際に経産省には冠婚葬祭互助会に関する相談窓口が設置されていますので、解約に応じてもらえない・明らかにおかしな対応をされた場合は遠慮なく助けを求めてください。「泣き寝入り」する必要はありません。
解約手数料を巡る裁判事例
互助会の解約手数料の妥当性については過去に消費者団体が提訴した例があり、司法の場でも争われてきました。特に有名なのが、京都の互助会「セレマ」を相手取った訴訟で、2015年に大阪高等裁判所が「解約手数料が高すぎる部分は無効」との判決を下し確定しています。この判決では、「解約手数料として認められるのは実際に解約に伴って事業者が被る平均的な損害の範囲内のみ」と示され、具体的には毎月の振替手数料60円+通知費用14.27円程度/年しか損害は生じないと認定されました。積立総額の2割にも上る高額な解約手数料は事業者の損失を大きく超えており、不当だと判断されたわけです。この判決後、一部の互助会では解約手数料の見直しも検討されましたが、依然として平均2割程度の手数料を徴収しているケースが多いのが実情です。つまり法律上は問題が指摘されつつも、現状では高額な解約手数料が事実上容認されている状態と言えます。互助会を解約する際はこの点を踏まえ、「いくら戻ってくるのか」を冷静に計算した上で判断しましょう。
他社サービスへの乗り換えという選択肢
近年では、「互助会に入ったものの小規模なお葬式で十分なので解約したい」「積立より必要なときだけ支払うサービスに切り替えたい」というニーズから、互助会を解約して他社の葬儀サービスに乗り換える動きも増えています。その際に注目したいのが、葬儀社による「のりかえ割」キャンペーンです。
小さなお葬式の「のりかえ割」

例えば全国対応の定額葬儀サービス「小さなお葬式」では、他社互助会会員や解約者を対象に最大15万円の割引が受けられる「のりかえ割引」キャンペーンを提供しています。積立金がなくても利用できる低価格プランが特徴で、最安約16万5,000円(税込)から葬儀を行える設定になっており、互助会を解約して乗り換える人でも割引によって解約手数料の実質的な負担を減らすことができます。実際、「互助会をやめたいが手数料で損するのが嫌だ」という利用者にとって、この割引は大きな後押しとなっています。小さなお葬式以外にも、葬儀社大手の中には同様の乗り換え特典を用意しているところがありますので、現在互助会に加入中で乗り換えを検討している場合は一度相談してみると良いでしょう。「互助会に入っているから他は頼めない」ということは全くなく、むしろ他社は歓迎してくれる場合が多いのです。
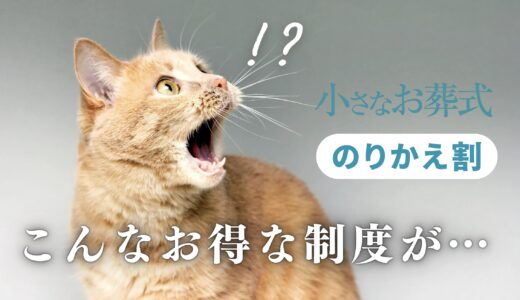 互助会からお得に乗り換え!小さなお葬式の「のりかえ割」を徹底解説
互助会からお得に乗り換え!小さなお葬式の「のりかえ割」を徹底解説
乗り換え時の注意
互助会を解約して乗り換える場合、前述の解約手数料分の目減りは避けられません。乗り換え先の割引である程度カバーできるとはいえ、積立金のうち手数料控除後の金額しか手元に戻らない点は理解しておきましょう。また、互助会によっては解約時に積立ポイントで香典返し等の商品と交換できる制度を設けている場合もあります。せっかく積み立ててきたお金が無駄になるのを少しでも避けるため、商品交換などが可能かどうか契約先に確認してみるのも一手です。その上で他社のサービス内容・価格と総合的に比較し、乗り換える価値があるか判断しましょう。近年はインターネット葬儀仲介サービス(小さなお葬式、よりそうお葬式、イオンのお葬式等)が充実しており、互助会にこだわらなくても定額で明瞭会計な葬儀プランが選べる時代になっています。自分や家族にとって最適な備え方を選ぶようにしましょう。


まとめ
互助会はうまく活用すれば葬儀費用の負担を軽減できる便利な制度ですが、2025年現在、その仕組みや業界を取り巻く状況は大きく変化しつつあります。メリットだけでなくデメリットやリスクも正しく理解し、「自分に合った葬儀の備え方とは何か」を改めて考えることが大切です。互助会に加入する場合は信頼できる企業を選び、契約内容を十分に確認しましょう。すでに加入している方で「やめた方がいいのかな?」と迷っている場合も、解約手数料や他社サービス情報を踏まえて冷静に検討してください。最終的には「安心して大切なセレモニーを迎えられること」が何より大事です。互助会もその手段の一つですが、現代では他の選択肢も増えています。ぜひ本記事の情報を参考に、後悔のないよう準備を進めていただければと思います。
脚注