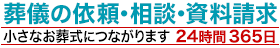この記事では、相続税の節税対策に役に立つ「生前贈与」のやり方を詳しくお伝えしていきます。
相続税の節税対策のポイントは「生前贈与」
近年は生前贈与を促進する法制度へ
贈与税は基本的に相続税に比べて基礎控除額も低く、さらに相続税と比べて税率も高くなっています。
これは贈与税はもともと相続税の課税の逃れを防ぐための補完税としての役割があるからです。
平成27年度の法改正で、相続税や贈与税の仕組みが改正されました。
要点としては、相続税の基礎控除が引き下げられたことで相続税の納税対象が広がったこと、一方で贈与税の税率構造や小規模住宅地等の特例などの範囲が広がったことなどが挙げられます。
これまでよりも相続税の対象が広がっているため、多くの人が節税対策を考えなければなりません。相続税の節税を考える上で生前贈与の仕組みをうまく利用することが重要なのです。
相続税の節税の原則は相続財産を少なくすること
相続税の最も効果的な節税方法は相続税の基礎控除額以下に相続財産を抑えることにあります。
相続税の基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数(平成27年より)です。
法定相続人が一人だった場合には3,600万円が基礎控除額、二人だった場合には4,200万円が基礎控除額になります。
遺産総額から基礎控除額を差し引いた残りの額が課税遺産総額となります。ここから個々の相続人に分配した金額に応じて以下の税率と控除が適用されます。
| 取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | – |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
相続税を節税するためには、生前贈与などをして有利な税率で財産を移動させることにより、相続財産を減らしておくことが有効と言えるでしょう。
では、相続税の節税に有効な生前贈与の仕組みについて見ていきましょう。
贈与の基本の暦年課税の仕組み
毎年110万円までは非課税で贈与できる
暦年課税は通常の贈与税の課税方式です。
1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税されます。
よって、1年間の贈与額の合計が110万円以下である場合は贈与税の申告は必要ありません。よって以下のような計算方法になります。
贈与税の課税価格=贈与財産の総額 – 基礎控除額(110万円) が課税価格の計算式になります。課税価格ごとに税率や控除額が設定されています。
1年間の贈与総額が110万円以下の場合は贈与税がかかりません。
したがって、例えば親から成人した子へ1,000万円を一度に贈与すると240万円の贈与税を納めなければなりませんが、毎年100万円の贈与を10年間継続して行えば贈与税がかからないことになります。
しかし、毎年100万円ずつ贈与を受けることが贈与者との間で約束されている場合は、1年ごとに個別の贈与が発生しているのではなく、約束した年に毎年100万円を10年間にわたって給付する定期金に関する権利の贈与を受けたものとして贈与税が課せられますので、申告が必要になります。
基礎控除額110万円を最大限に活かした節税方法は、例えば毎年120万円ずつ贈与することで毎年1万円の贈与税を納めながら財産を贈与することが可能です。
贈与税の課税価格ごとの税率と控除額
110万円を超える贈与があった場合は、基礎控除額を差し引いた残りの金額に応じた贈与税率をかけ、さらに控除額を差し引いた残りの金額が納税額になります。計算式は次の通りです。
贈与税の納税額=課税価格 × 税率 – 控除額
この時の贈与税率は一般贈与財産と特例贈与財産で控除額がさらに異なります。
特例税率は平成 27年1月から新たに導入された税率で、20歳以上の子や孫が直系尊属(父母や祖父母)から受けた贈与財産(特例贈与財産)に対しては税率を優遇する措置を追加しました。
特例贈与財産に当てはまらない場合は、これまでどおりの一般贈与税率が課税される仕組みです。
課税課価格ごとの詳しい税率は以下のテーブルをご覧ください。
| 贈与税率の区分 | 課税価格 | 200万円以下 | 300万円以下 | 400万円以下 | 600万円以下 | 1,000万円以下 | 1,500万円以下 | 3,000万円以下 | 4,500万円以下 | 4,500万円超 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般贈与財産 | 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | |
| 控除額 | – | 10万円 | 25万円 | 65万円 | 125万円 | 175万円 | 250万円 | 400万円 | ||
| 特別贈与財産 | 税率 | 10% | 15% | 20% | 30% | 40% | 45% | 50% | 55% | |
| 控除額 | – | 10万円 | 30万円 | 90万円 | 190万円 | 265万円 | 415万円 | 640万円 | ||
暦年課税の税額計算の具体例
具体例で考えてみましょう。
贈与する側と贈与を受ける側との関係性において次の3パターンの計算方法が考えられます。
- 「一般贈与財産」の計算になる場合
- 「特例贈与財産」の計算になる場合
- 「一般贈与財産」と「特例贈与財産」の両方の計算が必要な場合
一般贈与財産の計算になる場合
まず①一般贈与財産の計算になる場合です。
直系尊属以外の親族(兄弟や夫、夫の父母)や他人からの贈与や、直系尊属からの贈与を受けた年の1月1日時点で20歳未満の場合などはこの計算方法になります。
500万円の贈与総額から基礎控除額110万円を差し引いた390万円が課税価格です。
課税価格390万円に対して贈与税率20%がかかり、さらに控除額25万円を差し引いた53万円が一般贈与財産の納税金額になります。
特例贈与財産の計算になる場合
次に②特例贈与財産の計算になる場合です。
贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の子や孫が、直系尊属(父母・祖父母)から贈与を受けた場合は特例贈与財産の税率になります。
①と同じく基礎控除額を差し引いた390万円の課税価格に対して、特別贈与税率15%をかけ、さらに控除額10万円を差し引いた48.5万円が特別贈与税率の計算になります。
一般贈与財産と特例贈与財産の両方の計算になる場合
最後に一般贈与財産と特別贈与財産両方の計算が必要な場合です。
例えば、20歳以上の人が1年以内に配偶者と自分の両親両方から贈与を受けた場合です。
これは以下のような計算方式になります。
- 全ての財産を一般税率で計算した税額に占める一般贈与財産の割合に応じた税額を計算
- 全ての財産を特別税率で計算した税額に占める特別財産の割合に応じた税額
- ①と②の合計額が納付総額
100万円の一般贈与と400万円の特別贈与の合計500万円の贈与があった場合を計算してみましょう。
一般贈与財産の計算は課税価格500万円から基礎控除額を差し引いた390万円で、390万円×20%-25万円=53万円が500万円全体の一般税率です。
実際には500万円のうち100万円なので、53万円×100万円 / 500万円 = 10.6万円が全体のうち一般贈与財産の税額です。
特例贈与財産も同じように390万円×15%-10万円=48.5万円が全体の特例税率で、実際の割合は500万円のうち400万円分なので、48.5万円×400万円 / 500万円 = 38.8万円が全体のうちの特例贈与財産の税額です。
一般贈与税と特例贈与税を合計して 10.6万円 + 38.8万円= 49.4万円が贈与税額になります。
暦年贈与のポイント
暦年課税で節税をするポイントはできるだけ多くの人に長い時間をかけて贈与し続けることです。
年間110万円の基礎控除は受贈者ごとのため、例えば10人に対してそれぞれ110万円、計1100万円を贈与したとしても贈与税は発生しません。
相続発生から3年以内の贈与は相続財産に加算されるため、早期に生前贈与を済ませておくとよいと思われます。
暦年贈与で重要なことは、税務署の税務調査対策と言えます。一つは贈与とみなされないケースです。
例えば、子供の名義口座にお金を入金しているが、子供が自由にお金を使えないような状態(印鑑や通帳などを子供自信が管理していない)場合などは税務調査によって贈与とみなされない可能性が高いです。
そしてもう一つは、分割贈与のケースです。
例えば毎年100万円を10年間贈与し続けた場合、定期金に関する権利を贈与されたとみなされ、合計金額1,000万円に対する贈与税が課せられる可能性があります。
この分割贈与で定期金とみなされないためには次のような対策を講じる必要があります。
- 毎年きちんと贈与契約を交わす
- 毎年違った金額を贈与する(105万円、90万円、100万円など)
- 毎年少額でも贈与税を収める(111万円を贈与し、1,000円の贈与税を納めるなど)
こうした分割贈与はものすごく警戒されていますが、実は裁判や税務上でも争われることは少ないです。
毎年きちんと贈与契約を交わし、後で形として残るようにしておくと良いでしょう。
使いどころが難しい相続時精算課税
2,500万円までは贈与税がかからない制度
財産の贈与に関する課税方式には一般的な暦年課税のほかにも相続時精算課税の制度というものがあります。
毎年110万円の基礎控除のある暦年課税と異なり、選択してから贈与者が亡くなるまでの間に2,500万円の特別控除があるのが特徴です。
原則として60歳以上の父母・祖父母から、20歳以上の推定相続人である子・孫に対し財産を贈与した場合にどちらの課税方式にするかを選択することができます。
暦年課税は毎年110万円以下の基礎控除額がありますが、相続時精算課税制度は選択をした年以後、特別控除額2,500万円を控除した後の金額に一律20%の税率を乗じて計算します。
例えば、初年度500万円の贈与があった場合、暦年課税の場合は500万円-基礎控除110万円=390万円が課税価格となりますが、相続時精算課税の場合は500万円-特別控除2,500万円=-2,000万円で、初年度はまだ2,000万円の控除枠が残っていることになります。
この特別控除額の残額は翌年に繰り越されます。
翌年に2,500万円の贈与があった場合、前年で500万円を差し引かれているので特別控除は残り2,000万円、よって2,500万円 – 2,000万円 = 500万円が課税価格となり、20%の税率をかけた100万円がその年度の納税額となります。
特別控除を使いきっているため、以後の年度の贈与には全て20%の税率が課せられることになります。
この性質上、相続時精算課税は一度選択すると、暦年課税に変更することは不可能になります。
収益物件や値上がりする財産の贈与などにメリット
この相続時精算課税は、使いどころが難しく、一度選択すると暦年課税に戻すことは不可能となるため、この制度を利用する人も少ないのが現状です。
まず、相続時精算課税で贈与した財産については、相続時に相続財産に加算されます。
したがって、相続時精算課税それ自体では相続税の節税にはなりません。
相続時精算課税で節税効果を得るためには、収益物件を生前に贈与しておくことで、相続開始までに得られる財産を減少させたり、また、株式などは精算時ではなく贈与時の価額で評価されるため、将来的に値上がりが見込まれる財産を贈与することで相続財産の評価を下げることが可能となります。
また、相続財産にあたる財産を生前に贈与できるため、相続争いを未然に防ぐことにも繋がります。
2,500万円以上のものを贈与した場合は、以後税率20%の贈与税を納める必要がありますが、相続発生時には納めた贈与税相当額を控除することが可能です。
遺産を確実に生前に贈与しておきたい場合などには有効と言えるでしょう。
相続時精算課税のポイント
相続時精算課税は、あくまでもまとまった財産を生前に贈与するときに利用するものと捉えておいたほうが良いでしょう。
相続財産自体が少なく、子や孫への住宅購入支援などの際に利用する場合などは利用することがあるかもしれません。
申告時に相続時精算課税の申込をしないかぎりは暦年課税として申告されます。
孫に教育資金を1,500万円まで非課税で贈与できる
孫の教育資金を 1,500万円まで非課税で贈与できる制度
2013年から教育資金の一括贈与に対する非課税措置が一時的なものですが始まりました。
現在は期限を延長して平成31年3月31日までに伸ばしています。
これは祖父母から30歳までの孫に対して教育資金を一括して贈与した場合、1,500万円までは非課税とする内容になっています。
もともと扶養義務者間で必要の都度支払われる教育資金(都度贈与)は贈与税非課税でしたが、この制度は非常に大きな金額を一括して非課税で贈与可能な点でメリットが大きいと言えるでしょう。
一方で、注意点もいくつかあるので見ていきましょう。
教育資金口座を開設して教育資金にのみ使用し、使い残しがあれば贈与税が課税される
教育資金の一括贈与は現金ではなく、金融機関に子・孫(受贈者)名義の教育資金口座を開設して、その口座に一括して拠出します。
第一の注意点は教育資金口座の使い道はもちろん教育資金にのみの使用で、これは金融機関によって領収書等でチェックされます。
また、教育資金口座は対象である孫の年齢が30歳になるまでで、30歳に達するまでに使い残しの資金があった場合は、残った金額は孫への贈与とみなされ、贈与税が課せられます。(もちろん、贈与扱いされた後は使途は自由になります。)
したがって、教育資金は計画的に使い切ることが重要になります。
教育資金の中身
使途金として認められるのは教育資金で、これは「学校等に対して直接支払われる金銭」と、「学校等以外に対して直接支払われる金銭で社会通念上相当と認められるもの」です。
前者の学校等とは文字通り、学校教育法上の幼稚園、小中学校、高校から大学、大学院などの教育機関や外国の教育施設、認定こども園・保育所などを指しています。
後者の学校等以外とは、学習塾やそろばん教室、水泳教室やスポーツ活動、ピアノ・絵画などの芸術活動など、学校以外の習い事などが対象となっています。
両社に共通しているのは直接支払われるということで、これは入学費や授業料などはもちろん非課税ですが、文具や教科書などを学校を通すか学校指定の業者から購入する場合は非課税になるので注意が必要となります。
さらに、全体で1,500万円の非課税枠が定められていますが、後者の習い事などに対する費用はそのうちの500万円以内と定められています。
塾などに通わせる場合は計画的に行う必要があります。
教育資金の贈与のポイント
ポイントをまとめましょう。祖父母から30歳までの孫に対する一括贈与が対象です。
口座開設などの手続きが多少煩雑になりますが、一度開設してしまえばその後の手続も不要で、1500万円までという高い節税効果を発揮することが可能です。
一方で、残額に対しては贈与税がかかる可能性があるので、計画的に使い切る必要があります。
不動産の贈与で節税を行う
不動産と金銭なら不動産の贈与の方が圧倒的に有利
現金の贈与は当然ですが現金の額面に対して贈与税がかかりますが、贈与する不動産は実際の価格ではなく評価額で決まります。
土地は相続税路線価(公示価格の8割程度)、家屋は固定資産税評価額(公示価格の7割程度)に対して贈与税の課税となるため、そのまま現金で贈与するよりも高い節税効果を発揮することができます。
夫婦間で居住用不動産に関する贈与は2,000万円の配偶者控除を受けられる
夫婦の間で「居住用不動産」もしくは「居住用不動産を取得するための金銭」の贈与があった場合に、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除できるという特例があります。この配偶者控除を受けるにはいくつか条件が必要です。
- 婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 自分が住むための国内の居住用不動産か、その居住用不動産を取得するための金銭であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住用不動産に実際に住んでおり、今後も住む見込みであること
- 同一の配偶者からの贈与で配偶者控除を使用していないこと(同じ配偶者からの配偶者控除は一生に一度)
もちろん、これも通常の不動産の贈与と同じく、金銭よりも不動産の贈与の方が節税効果は高くなります。
不動産贈与の注意点
このように現金を不動産にして贈与するだけで高い節税効果がありますが、購入した直後に贈与などは節税目的の購入および贈与とみなされ、不動産の購入費用全額に対して贈与税をかけられる可能性があるので注意が必要です。
また、不動産の受贈者は登記代や不動産取得税のほか、贈与税も現金一括払いで納める必要が有るため、贈与する相手とよく相談して贈与する必要があります。
生前贈与のまとめ
贈与税自体は相続税よりも税率が高いですが、全体的な相続財産や様々な税率が優遇されている贈与の仕組みを利用することで、次の世代へ財産をより多く残すことが可能です。
- 年110万円の基礎控除枠をうまく利用する
- 相続時精算課税は注意が必要。計画的に利用する
- 孫への教育支援ならば、1500万円まで非課税で贈与できる
- 現金よりも不動産の方が節税効果が高い