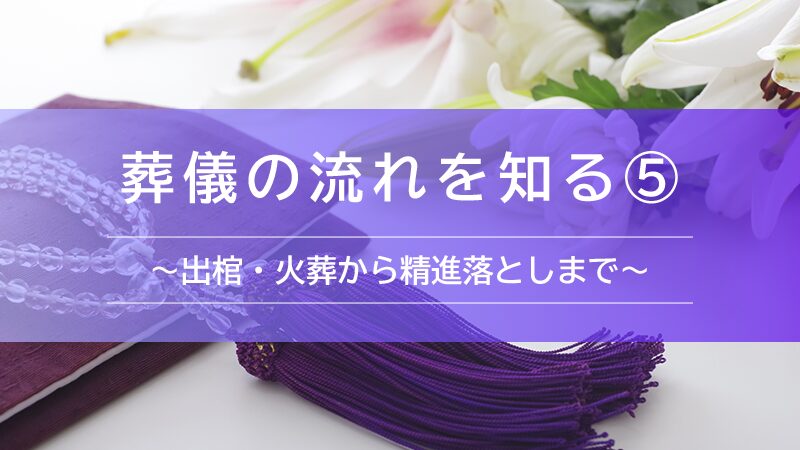【葬儀の手順】
- 危篤から安置まで (危篤、臨終、連絡、安置、役所への手続き)
- 安置から納棺まで (葬儀日程の決定、斎場の決定、戒名と御布施の用意、納棺)
- 通夜 (通夜の準備、通夜の流れ、通夜振る舞い)
- 葬儀・告別式 (葬儀告別式の準備、流れ、お布施の包み方・渡し方)
- 出棺・火葬から精進落としまで ( 出棺、火葬場への移動、繰り上げ初七日法要、精進落とし、葬儀後の手続きの整理)
- 葬儀後の手続き (役所への手続き、香典返しと葬儀費用の精算)
大切な方を見送る葬儀もいよいよ最後の段階です。出棺(しゅっかん)から火葬、そして初七日法要と精進落としまでの一連の流れについて、一般的な仏教の習慣に沿ってわかりやすく解説します。全国共通のマナーや実務的なポイントを押さえておけば、いざという時にも慌てず故人を送り出すことができるでしょう。最後には、葬儀後に行う各種手続きについても整理しています。それでは、一つひとつ見ていきましょう。
目次
出棺(棺を運び出す際の流れとマナー)
 儀・告別式のあとに故人の棺を式場から霊柩車へ運び出すことです。ここでは、出棺時の主な儀式とマナーについて説明します。
儀・告別式のあとに故人の棺を式場から霊柩車へ運び出すことです。ここでは、出棺時の主な儀式とマナーについて説明します。
見送りのマナー
棺が霊柩車に納められ、発車した後は、参列者は車が見えなくなるまで合掌や黙礼をして見送ります。完全に見えなくなる前に談笑するのは避けましょう。寒い時期でも見送りの際はコートを脱ぐのが作法とされています。特に故人と親しかった方は、深く一礼し、冥福を祈りながら送り出すとよいでしょう。
以上が出棺の主な流れです。深い悲しみの中でも、故人を最後まで慎み深く送り出すことが大切です。
火葬場への移動と手続き

霊柩車で火葬場へ向かい、到着後に火葬を執り行うまでの流れについて説明します。
移動の仕方
葬儀式場と火葬場が離れている場合は車で移動します。火葬場へ同行するのは遺族や親族が中心で、一般会葬者は葬儀式でお別れとなり、火葬には立ち会わないことが多いです。ただし、故人と特に親しかった友人などには事前に声をかけ、立ち会ってもらう場合もあります。移動時の車列は僧侶を先頭に霊柩車が続き、遺族・親族の乗った車がその後に続く形になります。また、火葬許可証は火葬を行うために必須の書類ですので、霊柩車に積み忘れがないよう注意しましょう。
火葬場到着後の手続き
火葬場に到着したら、まず受付で火葬許可証を提出します。係員が許可証を確認し、手続きが完了すると埋葬許可証として返却されます。これは遺骨をお墓に納める際に必要な重要書類であり、再発行できないため紛失に注意しましょう。多くの場合、係員が埋葬許可証を骨箱に入れてくれますが、自宅に戻った後も大切に保管してください。
火葬炉前での納めの式
手続きを終えたら、棺を火葬炉の前に安置し、納めの式を行います。炉前には遺影写真と位牌が飾られ、僧侶による読経が捧げられます。喪主から順に親族が焼香を行い、全員の焼香が終わると、いよいよ棺が炉へ納められます。この瞬間が故人の肉体との本当の最後の別れとなるため、心を込めて送り出しましょう。
火葬と待ち時間の過ごし方
火葬が始まると、遺族や同行者は控室で火葬が終わるのを待ちます。火葬にはおよそ1~2時間かかるため、その間は火葬場の待合室やロビーで過ごします。多くの火葬場ではお茶や水が用意されていますが、長時間になる場合に備えて、軽いお茶菓子や飲み物を持参するとよいでしょう。昼食時にかかる場合は、簡単な軽食をとることもできます。
控室では、同行した親族や知人にお茶菓子やお酒を振る舞いながら談話することが一般的ですが、故人を偲ぶ場であるため、節度をもって過ごすことが大切です。また、公営の斎場では時間短縮のため、火葬中の待ち時間に精進落としの食事を始める場合もあります。
拾骨(収骨)

火葬が終わると、係員の案内で控室から収骨室(骨揚げ室)へ移動します。ここで遺族が骨壺へ遺骨を納める「骨上げ(拾骨)」の儀式を行います。
収骨は二人一組で行い、長い箸を使い、同じお骨を同時につかんで壺へ納めます。この風習から、日本では箸と箸で食べ物を受け渡すことが縁起が悪いとされ、日常では避けられています。遺骨の中でも、喉仏(のどぼとけ)と呼ばれる首の骨の一部は、故人の仏様に見立てられ、最も近しい親族が最後に拾い上げるのが一般的です。
地域によって収骨の方法には違いがあり、関東では遺骨をすべて骨壷に納めるのに対し、関西では足元側の骨など、一部のみを納める場合もあります。地域による違いはありますが、いずれの場合も故人を敬い、丁重に扱う気持ちに変わりはありません。
骨壷と埋葬許可証の受け取り
収骨が終わると、係員から骨壷が渡されます。重量があるため、喪主かご遺族が受け取り大切に抱えて持ち帰ります。また、この時に埋葬許可証も渡され、通常は骨箱に入れて返却されます。これで火葬場での一連の儀式が終了します。
以上が火葬場で行う一連の流れです。火葬場から戻る際は、霊柩車ではなく遺骨を持った遺族の車が先導し、他の親族の車がそれに続いて斎場や自宅へ戻ります。
なお、地域によっては火葬場の職員へ心付けを渡す習慣が残っている場合があります。地域のしきたりや葬儀社のアドバイスに従い、必要に応じて不祝儀袋に少額を包んで用意するとよいでしょう。ただし、公営の火葬場では職員が受け取りを辞退することも多いため、事前に確認することをおすすめします。
繰り上げ初七日法要(式中初七日法要)

火葬を終えて斎場や自宅へ戻ったら、繰り上げ初七日法要を行うのが一般的です。初七日法要とは、本来、故人が亡くなった日から数えて7日目(命日を1日目として6日後)に営まれる仏教の追善供養です。仏教では、亡くなった魂が冥土へ向かい、7日ごとに閻魔様の審判を受けるとされています。特に初七日は故人が三途の川のほとりに到着し最初の審判を受ける日とされるため、遺族が読経や焼香を行って功徳を積み、故人の冥福を祈る大切な法要です。
しかし現代では、親族が再び集まる負担を軽減するため、多くの場合、初七日法要を葬儀当日に繰り上げて執り行います。火葬後に斎場の一角や寺院の本堂、自宅の祭壇前など、場所を改めて法要を営むのが一般的です。また、地域によっては告別式の流れの中で初七日の読経を続けて行う「式中初七日」の形式を採ることもあります。
繰り上げ初七日法要では、葬儀を担当した僧侶が引き続き読経を行い、その間に遺族・親族が順番に焼香をします。読経時間はおよそ20分程度が一般的です。喪主から順に焼香を行い、故人の冥福と加護を祈ります。読経の後は、僧侶による説法やお経の締めくくりがあり、最後に喪主が参列者へお礼の挨拶を述べます。この挨拶では、本来の初七日法要を繰り上げて行った旨や、参列への感謝を簡潔に伝えるとよいでしょう。さらに、精進落としの席への案内もここで触れておきます。「これより、ささやかではございますが精進落としの席をご用意しておりますので、どうぞお召し上がりください」と一言添えると、より丁寧な印象になります。
法要後、僧侶が精進落としに参加せず先に帰られる場合は、このタイミングでお布施(読経への謝礼)を渡します。袱紗からお布施の封筒を出し、僧侶へ手渡して丁重にお礼を述べ、お見送りをします。また、お車代(交通費)や御膳料(食事辞退の場合の慰労料)を別途包んでいる場合は、これらも同時に渡します。
以上で、初七日法要は終了です。
精進落とし(料理内容、席順、マナー)

精進落としとは、火葬までお付き合いいただいた親族や関係者への感謝を込めて振る舞う食事の席です。もともとは、四十九日の忌明け後に精進料理(肉や魚を避けた食事)から日常の食事へ戻る区切りの食事を指す言葉でした。かつて遺族は四十九日間、精進料理で過ごし、忌明けに精進落としとして久しぶりに動物性の食事をとったのです。
現代ではこの慣習が変化し、初七日法要後の会食を「精進落とし」と呼ぶようになりました。儀式的な意味合いよりも、火葬に付き添った方々への慰労とお礼の場としての側面が強くなっています。
精進落としの席と料理
精進落としの食事は、葬儀会場の控室や別室、または料亭・レストランの個室などで行います。規模は葬儀の形態によりますが、家族葬では近親者のみ、一般葬では親族や特に故人と親しかった方が中心となります。
料理は仕出しの和食膳や会席料理が用意されることが多く、寿司、天ぷら、煮物など、品数豊富なお膳が振る舞われます。最近では、葬儀社がケータリングや仕出し弁当を手配するケースも増えています。肉や魚を含む料理が一般的で、これは「忌中は控えていたものを解禁する」という意味合いに由来するものです。ただし、宗派や地域によっては精進料理のみを提供する場合もあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。
席には、故人の遺影写真、位牌、そして収骨した遺骨の入った骨壷を飾ります。さらに「影膳」として故人の席を設け、ご飯や汁物、故人が好んだ飲み物などを供えるのが一般的です。例えば、小さなお膳に一口分の料理と箸を並べ、グラスに故人が愛飲していたお酒を注ぐことで、故人も食事に加わっているという気持ちを表します。
席順と振る舞いのマナー
精進落としは、火葬まで付き添ってくださった親族や関係者へ感謝を伝えるための場です。かつては四十九日後に日常の食事へ戻る節目として行われていましたが、現代では初七日法要後の会食を指すようになりました。食事の時間を通じて故人を偲び、参列者の労をねぎらうことが目的となるため、席順や振る舞いには配慮が求められます。
- 席順について
精進落としでは、遺族が参列者をもてなします。僧侶が出席する場合は、僧侶が最上座(上席)です、僧侶が不参加の場合は故人の兄弟姉妹や年長者など、親族内の来賓格の方が上座に座ります。続いて、故人と縁の深い親族や友人がその近くに座り、喪主や遺族は末席(下座)に位置するのが基本です。ただし、参列者が席を辞退して譲ることもあり、その際は形式にこだわらず、状況に応じて柔軟に対応するとよいでしょう。 - 開席の挨拶と献杯
席に着いたら、喪主が開席の挨拶を行います。「本日はお忙しい中、最後までお付き合いいただきありがとうございます。ささやかではございますが、故人を偲びながら、お食事を召し上がってください」等、ねぎらいと感謝の言葉を述べます。その後、献杯の音頭を取ります。弔事の席ではグラスを合わせず、「乾杯」ではなく「献杯」と発声して、故人への敬意を表します。「それでは、故人〇〇の冥福を祈りまして、献杯。」と述べ、参列者全員でグラスを静かに上げて飲みます。声高に発声したり、グラスを打ち鳴らすのは避けましょう。

- 会食時の振る舞い
精進落としの場では、遺族は接待役として振る舞います。喪主や遺族代表者は各テーブルを回り、参列者一人ひとりにお酌をしながら、お礼の言葉を伝えます。「本日は本当にありがとうございました。どうぞごゆっくりお召し上がりください」と声をかけるとよいでしょう。遺族自身は忙しく動き回るため、食事をとる時間が限られるかもしれませんが、適度に箸をつけても構いません。むしろ遺族が食事を始めることで、参列者も食べやすい雰囲気になります。
精進落としの席では、悲しみの場であることを踏まえつつも、必要以上に沈痛な雰囲気になりすぎないようにすることも重要です。久々に顔を合わせた親族同士が故人の思い出を語り、和やかに談笑する場面もよく見られます。適度にお酒も入り緊張がほぐれる時間ですが、泥酔するほどの飲酒は控えましょう。また、タバコは所定の場所で吸う、騒がしくしないなど、一般的なマナーを守ることも大切です。 - 閉会の挨拶とお見送り
精進落としの時間は、1時間前後がひとつの目安です。長くなりすぎると、遺族や参列者の負担となるため、頃合いを見て切り上げます。
閉会の際には、喪主または親族代表が挨拶を行います。「本日は最後までお付き合いいただき、誠にありがとうございました。おかげさまで、無事に一連の行事を終えることができました。皆様のご厚情に深く感謝申し上げます」など、お礼の言葉と今後の支援のお願いを述べるとよいでしょう。その後、遺族一同で参列者に深く一礼し、僧侶にも改めてお礼を伝え、お見送りします。 - 会葬御礼の品の手渡し
お開きとなったら、会葬御礼の品(香典返し)をまだお渡ししていない方に忘れずに手渡します。最近では、葬儀当日に即日返しとして品物を渡すことが一般的ですが、精進落としまで残っていただいた親族や知人には、別途記念品を用意する場合もあります。地域や家庭の慣習によりますが、「本日は遠方からありがとうございました。些少ですが、お納めください」と声をかけながら手渡すと、より丁寧な印象になります。
精進落としは、故人を偲びながら参列者との時間を過ごす、大切な場です。儀式的な意味合いは時代とともに変化してきましたが、感謝の気持ちを伝え、労をねぎらう場であることに変わりはありません。格式にこだわりすぎることなく、故人への敬意と参列者への心遣いを大切にしながら、穏やかに過ごせるよう配慮するとよいでしょう。
長い一日が終わり、葬儀当日のすべての行事が終了となります。遺族代表の挨拶とともに参列者を見送り、最後に遺族のみが残り、ようやく静かな時間が訪れることでしょう。遺骨は、当日すぐにお墓へ納める(納骨)ことも可能ですが、四十九日までは自宅に安置するのが一般的です。後日、四十九日の法要に合わせて納骨の準備を進めるとよいでしょう。
まとめ

葬儀から初七日法要、精進落とし、そして諸手続きまで、一連の流れをご説明しました。仏教の一般的な作法に沿った形をご紹介しましたが、地域や宗派によって細かな違いもあります。不安な点があれば、事前に葬儀社やお寺、経験のある親族に相談しながら進めると安心です。
葬儀は、大切な人との最後の時間を過ごし、故人への思いやりと周囲への感謝の気持ちを形にする場です。しっかり準備と心構えをしておけば、悲しみの中でも落ち着いて故人を送り出し、その後の手続きを進めていけることでしょう。
- 危篤から安置まで (危篤、臨終、連絡、安置、役所への手続き)
- 安置から納棺まで (葬儀日程の決定、斎場の決定、戒名と御布施の用意、納棺)
- 通夜 (通夜の準備、通夜の流れ、通夜振る舞い)
- 葬儀・告別式 (葬儀告別式の準備、流れ、お布施の包み方・渡し方)
- 出棺・火葬から精進落としまで ( 出棺、火葬場への移動、繰り上げ初七日法要、精進落とし、葬儀後の手続きの整理)
- 葬儀後の手続き (役所への手続き、香典返しと葬儀費用の精算)