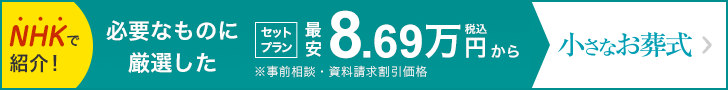【葬儀の手順】
身近な人が危篤状態に陥ったり亡くなったりすると、深い悲しみの中でも様々な手続きを迅速に行う必要があります。本記事では、宗教や宗派を問わず全国共通で押さえておきたい「危篤から遺体安置まで」の葬儀準備の流れについて、初めての方にも分かりやすく解説します。大切な方をきちんと見送るために、危篤時の対応、臨終直後の初動、訃報の連絡方法、ご遺体の安置方法と注意点、そして役所での手続きといったポイントを順を追って説明します。
目次
危篤の際に家族がすべきこと

ご家族が危篤(きとく)と医師から告げられたら、まず何よりも最後のお別れの準備を始めましょう。医師から「危篤」と判断された場合には、できるだけ早く親戚や親しい友人などに連絡を取り、看取りに立ち会ってもらえるよう病床に集まってもらいます。これは、残された人々にとって悔いのないお別れをするためにも大切な対応です。また、意識がない状態でも周囲の声は聞こえているとも言われます。旅立ちの瞬間を迎えるその人が一人きりで寂しい思いをしないように、できる限り大切な方々とともに寄り添って見送ってあげましょう。
危篤の連絡を受けて駆けつける親族には、病院や自宅へ来る際の注意(面会時間外でも病院に申し出れば対応してもらえること、来られない遠方の親族には電話越しに声を聞かせてあげる等)も必要に応じて伝えます。なお、危篤段階で余裕があれば、葬儀社の検討や事前相談も視野に入れてください。特に容体が不安定な場合、早めに信頼できる葬儀社を決めておくことで、いざ臨終を迎えた際の負担が軽減されます。
臨終直後の初動対応

実際にご臨終を迎えたら、深い悲しみの中でもすぐにやらなければならないことがあります。医師による死亡の確認と証明書の受け取りがその最初のステップです。通常、病院で亡くなった場合は医師が死亡を確認し、「死亡診断書」(または「死体検案書」)という公的な証明書を発行してくれます。病院では引き続き、看護師などスタッフによってご遺体の体を清拭(せいしき)して清め、着替えや死化粧といった処置を施してもらえるのが一般的です。病院によって程度は異なりますが、いわゆるエンゼルケア(ご遺体の清拭や処置)はこの段階で行われます。
一方、自宅で亡くなった場合は対応が少し異なります。まず慌てずに、かかりつけの主治医に連絡して死亡確認と死亡診断書の発行をしてもらいましょう。主治医がいない場合は警察に連絡し、警察が死亡確認と死体検案書の発行の対応をします。明らかに死亡が確認できる状態であれば、救急車を呼ぶ必要はありません。救急車は基本的にご遺体を搬送できないため、死亡確認後のご遺体は警察によって搬送されることになります。救急車を呼んだ場合もその場で死亡が確認されると警察が来ることになりますので、最初から警察に連絡したほうがスムーズです。また、医師や警察による死亡確認が終わるまでは、ご遺体には手を触れずそのままの状態で安置してください。勝手に体を動かしたり衣服を着せ替えたりすると、状況によっては警察による検証の支障になる恐れがありますので注意が必要です。
なお、臨終直後には、古くからの習わしで「末期の水(まつごのみず)」と呼ばれる儀式を行うことがあります。末期の水とは、お葬式における最初の儀式として行われるもので、臨終に立ち会った家族が順番に故人の口元に水を一滴ずつ含ませて潤すことです。「死に水を取る」とも言われ、旅立つ直前の喉の渇きを癒してあげる意味があります。病院で臨終を告げられた直後や、自宅にご遺体を安置した後に行われることが多い慣習ですが、宗教によっては行われないこともあるなど、考え方はさまざまです。強制ではなく、ご家族が心を込めて送り出したいというお気持ちがあれば行えばよいでしょう。
臨終後は深い悲しみで冷静さを欠いてしまいがちですが、上記のような死亡確認と必要な処置をまず済ませることが大切です。そして、並行して次に説明する親族や関係者への訃報連絡やご遺体の搬送と安置場所の手配を進めていきます。
親族・関係者への訃報連絡

身内の訃報を伝える際は、まず優先すべき相手に迅速に連絡することが重要です。 一番に連絡すべき相手は親や子ども、兄弟姉妹といった近親者(おおよそ三親等以内の親族)です。これら近い親族には、深夜や早朝であってもできるだけ早く電話で直接知らせるようにしましょう。訃報を伝える手段としては電話連絡が基本的なマナーとされています。突然の連絡で驚かせてしまうかもしれませんが、まずは故人が亡くなった事実を正確に伝え、お通夜や葬儀の日程が決まり次第改めて知らせる旨を簡潔に伝達します。
電話がどうしてもつながらない場合や、連絡する相手によってはメールやSNSを活用しても構いません。たとえば遠方の親戚で夜間に電話するのをためらう場合には、翌朝に見ることを想定してメールで訃報を送る選択肢もあります。しかし、メールやメッセージで知らせる場合でも、最低限「誰の訃報なのか(故人の氏名とあなたとの関係)」「亡くなった日時」「今後の通夜・葬儀の日程(未定なら後日連絡する旨)」など必要な情報は漏れなく伝えるようにしましょう。件名や冒頭に訃報であることを明記し、丁寧な文面で簡潔に伝えます。
訃報連絡の際には誰にどこまで知らせるかも考えておきます。基本的には、近親者への連絡が済んだら、故人と関わりの深かった友人知人、勤務先やご近所などにも順次お知らせします。一般的な優先順位としては、「家族・親族」→「会社など仕事関係」→「故人の友人・知人」→「近所や町内会」の順で連絡していくとよいでしょう。誰に連絡すべきかリストアップし、漏れがないよう確認しながら進めると安心です。
故人が現役でお勤めだった場合は、勤務先への連絡も忘れずに行います。たとえ家族葬などごく近親者のみで葬儀を執り行う場合でも、故人の会社および遺族(あなた自身)の職場へは訃報の連絡が必要です。ただし、家族葬で行う場合には「家族葬のため参列はご遠慮いただいている」旨を明確に伝える配慮も必要になります。会社への訃報連絡では、故人の氏名やあなたとの続柄、亡くなった日時、通夜・葬儀の日時と場所、喪主(施主)の氏名と連絡先などを伝えるとよいでしょう。会社関係者に対してはマナーとしてできるだけ早めに電話で伝え、その後詳細をメールで共有するなどのフォローをすると丁寧です。
遺体の安置方法と注意点

ご臨終後、正式なお葬式や火葬を行うまでの間、ご遺体をどこに安置するかを決めて搬送する必要があります。日本の法律では「死亡後24時間は火葬を行えない」と定められているため、葬儀の日程にかかわらず少なくとも一日はご遺体を安置しておかねばなりません。また、多くの病院では遺体の長時間の留置きができないため、ご臨終後は速やかに病室または病院内の霊安室からご遺体を搬送する段取りをとる必要があります。すでに葬儀社が決まっている場合は直接依頼して病院から安置場所へ搬送してもらえますが、未定の場合には速やかに葬儀社を手配し、安置場所まで搬送してもらいましょう。
安置場所の代表的な選択肢としては自宅、葬儀場内の安置専用室、もしくは葬儀社の安置施設(霊安室など)があります。それぞれにメリット・デメリットがありますので、ご家族の事情に合わせて選びます。以下に主な特徴を説明します。
自宅に安置する場合
ご遺体をご自宅へ搬送し、布団やベッドの上に安置します。枕元には枕飾りと呼ばれる簡易的な祭壇を設置し、線香やローソク、水や花などをお供えします。自宅での安置の最大の利点は、故人とのお別れの時間を気兼ねなくゆっくり過ごせることです。住み慣れた我が家から見送ってあげたいという場合には最適でしょう。ただし、家族以外で自宅に弔問に訪れる人がいる場合、その対応が遺族の負担になることがあります。また、一般的な住宅では遺体保全のための設備がないため、室温を低めに保つ工夫が必要です。特に夏場はエアコンを効かせ、葬儀社から提供されるドライアイスでご遺体を冷却保存します。葬儀社のスタッフが安置時にドライアイス処置を施し、その後も適宜交換してくれますので指示に従いましょう。故人の頭を北向きにする北枕にして安置する慣習がありますが、絶対ではありません。住宅事情により難しければ無理にこだわる必要はありませんが、習わしとして行うご家庭も多いです。
葬儀場・斎場の安置室に預ける場合
葬儀場や火葬場等には、ご遺体を安置できる専用の部屋(霊安室や安置室)が用意されていることがあります。ご遺体を式場の安置室に搬送して預けておけば、通夜・葬儀の際に改めて移動させる必要がなく、そのまま式を執り行えるという利点があります。自宅から式場が遠かったり、自宅に安置できるスペースや環境が整わなかったりする場合には、有力な選択肢となるでしょう。ただし、安置室の使用には別途費用が発生するのが通常です。葬儀プランによって安置室料が含まれる場合もありますが、事前によく確認しましょう。また、安置室によっては面会できる時間帯や付き添いの可否が決まっている場合もあります。多くの場合「○時〜○時まで面会可」などの制約があるため注意が必要です。
葬儀社の保管施設(安置施設)に預ける場合
自宅に安置できない事情がある、あるいは仕事などで付き添いが難しい場合には、葬儀社の設備内でお預かりしてもらう方法もあります。安置専用の冷蔵保管施設で葬儀の日まで遺体を管理してもらえるため、遺族の負担は軽くなるでしょう。時間帯の制約や要事前連絡などの条件つきで面会が可能な施設もありますが、保管中はご遺体と対面できない(面会不可)施設もあり、そのようなケースでは通夜または告別式当日まで故人に会えない点がデメリットです。また、当然ながら保管料などの費用も発生します。やむを得ない事情で自宅安置ができない場合、葬儀社と相談しながら決めるとよいでしょう。
いずれの方法を選ぶにせよ、ご遺体の搬送は速やかに行う必要があります。特に病院から自宅や安置先への搬送には葬儀社の手配が不可欠です。先述のように危篤時点で葬儀社を決めていなかった場合でも、病院には全国の葬儀社の一覧や紹介が用意されていることがありますので、看護師や医療ソーシャルワーカーに相談してみましょう。搬送から安置まで滞りなく済ませたら、次はいよいよ葬儀の日程調整や各種手続きの段階です。
死亡届・火葬許可証など役所での手続き
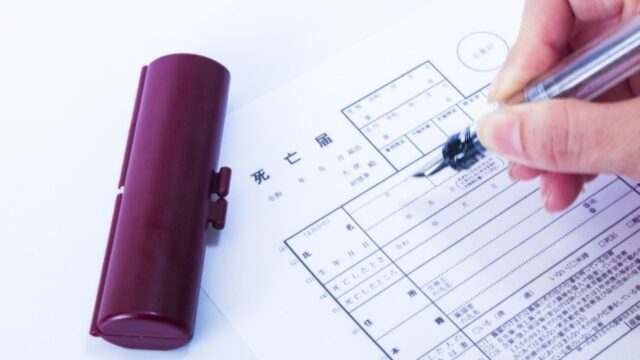
最後に、役所への死亡手続きについて説明します。身内が亡くなられたら、まず忘れずに受け取らなければならないのが死亡診断書(死体検案書)です。病院で医師から受け取った死亡診断書(自宅で警察が介入した場合などは「死体検案書」)は、死亡届の提出や火葬の許可を得るための大切な書類です。死亡診断書には故人の氏名や死亡時刻、死因等が医師によって記載されていますので、内容を確認しましょう。
続いて行うべきは市区町村役場への死亡届の提出と火葬許可証の申請です。通常これらは同時に行います。死亡届とは戸籍上の死亡を届け出る書類で、用紙は死亡診断書と一体になっています。用紙の右側が医師記入欄(死亡診断書)で、左側が届出人(ご遺族)が記入する死亡届になっています。必要事項を漏れなく記入し、原本を役場に提出します。
死亡届の提出期限は、法律上は「死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡の場合は3カ月以内)」と定められています。しかし、多くの場合はご逝去から2~3日後には通夜・葬儀を執り行い、その直後に火葬まで行う流れになります。火葬を行うには「火葬許可証」が必要不可欠であり、これが交付されていなければ火葬場で受け入れてもらえません。火葬許可証は、死亡届と同時に提出する「埋火葬許可申請書」によって自治体から交付されるものです。そのため、「一週間以内に提出すれば良い」と悠長に構えず、なるべく速やかに死亡届の提出と火葬許可証の交付を受ける必要があります。葬儀の日程が決まり次第、早めに手続きを完了させておきましょう。
死亡届の提出先は、故人の死亡地(亡くなった場所)か本籍地、または届出人(通常は喪主)の住所地の市区町村役場です。届け出を行うのは故人の親族が多いですが、実は届出人の資格は親族以外でも構いません。代理人による提出も可能であり、実務上は葬儀社の担当者がご遺族に代わって役所に提出してくれるケースもよくあります。初めての葬儀では戸惑う手続きも多いですが、葬儀社はこうした役所対応にも精通していますので、分からないことは遠慮なく相談しながら進めましょう。
以上、危篤時からご遺体の安置、そして死亡後の行政手続きまでの一連の流れについてご説明しました。初めてのことで不安も大きいかと思いますが、ポイントを押さえて対応すれば大切な方を安心して送り出すことができます。悲しみの中でも慌てず、一つひとつ手順を踏んでいきましょう。不明な点があれば病院スタッフや葬儀社に確認し、周囲のサポートも得ながら、悔いのないお見送りとなるよう願っています。
【葬儀の手順】