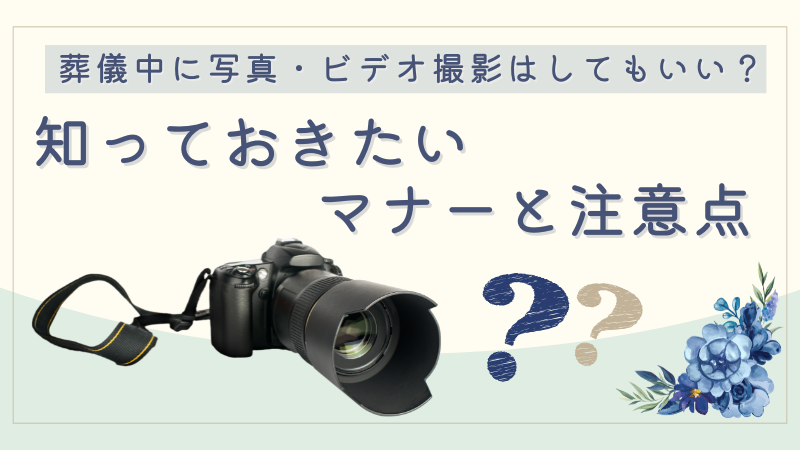スマートフォンの普及により、どんな場面でも手軽に写真や動画を撮影できるようになりました。大切な人との最後の別れの場である葬儀でも、その様子を写真やビデオに収めて残したいと考える遺族や、思い出をSNSで共有したい若い世代もいるでしょう。
しかし、葬儀は厳粛な儀式の場です。葬儀中の写真・ビデオ撮影には慎重な配慮とマナーが求められます。
本記事では、葬儀中の撮影が許されるケースや地域差、撮影する場合のマナー、そしてプロのカメラマンに依頼する際やSNS共有の注意点について解説します。正しい知識を持って行動すれば、故人との思い出を残しつつも周囲に失礼のない形で記録を残すことができるでしょう。
葬儀中の写真・ビデオ撮影は許される?
 葬儀の最中に写真やビデオを撮っても良いのだろうか?」と戸惑う方は少なくありません。葬儀は通常、故人を送り出す厳かな場であり、参列者も慎み深く振る舞うのが一般的です。そのため、多くの人にとって式中の撮影はマナー違反ではないかと感じられます。
葬儀の最中に写真やビデオを撮っても良いのだろうか?」と戸惑う方は少なくありません。葬儀は通常、故人を送り出す厳かな場であり、参列者も慎み深く振る舞うのが一般的です。そのため、多くの人にとって式中の撮影はマナー違反ではないかと感じられます。
ただ近年では、故人との最後の時間を写真や映像に残したいという遺族の希望で撮影が行われるケースも増えています。まずは、葬儀中の撮影が許容される場合や基本的な考え方について確認しましょう。
基本は慎むべきだが禁止ではない場合もある
葬儀の場での撮影は法律などで禁じられているわけではなく、「絶対にNG」という明確な決まりはありません。実際、葬儀での写真撮影は遺族や会場が了承している場合に限り問題ないとされています。
例えば喪主や遺族が後で葬儀の様子を見返すために写真を残したいと希望する場合や、供花や祭壇の様子を記録したいと考える場合は、マナーを守れば撮影が行われることもあります。ただし、「許可が得られていること」が大前提です。
遺族の中には撮影に抵抗を感じる方もいますし、葬儀社や斎場によっては独自に撮影禁止のルールを設けていることもあります。したがって、勝手な撮影は厳禁であり、必ず事前に遺族や式場の許可を得るようにしましょう。許可が得られなかった場合は、たとえ親しい間柄でも撮影は潔くあきらめるのがマナーです。
遺族の意向で撮影が行われるケースもある
近年、故人との最後の思い出を写真に残したいと考える遺族が増えてきました。悲しみの中でも写真を残しておけば、後から故人を偲ぶよすがになると考える人もいるためです。
また、葬儀には普段なかなか集まれない親族が一堂に会する機会でもあります。そのため、参列者や式の様子を記録に残す目的で、遺族が葬儀社やプロのカメラマンに撮影を依頼するケースも増えています。このように、遺族の希望が明確にあって撮影を行う場合には、周囲も「公式な記録係がいるのだな」と認識できます。
ただし、その場合でも配慮やマナーは欠かせません。「遺族が頼んだから大丈夫」と油断せず、慎重に振る舞うことが大切です。
地域の風習による違いにも注意しよう
日本の葬儀における写真撮影の扱いは地域によって風習が異なる場合があります。例えば、北海道など一部の地域では、告別式前後に祭壇の前で遺族・親族の集合写真を撮る習わしがあることで知られています。普段会えない親戚が揃う機会であるため記念に残す目的もあり、プロのカメラマンが正式に撮影を担当します。
一方で、地域や世代によっては葬儀中の撮影自体を好まないところもあります。特に厳粛さを重んじる土地柄では、「葬儀の場でカメラを向けるなんて非常識だ」という感覚を持つ人もいるでしょう。ですから、土地の習慣やしきたりも確認しておく必要があります。自分の地元では平気でも、別の地域の葬儀ではタブーとなる行為もあり得ます。
また、葬儀によっては最初から「本日は参列者による写真撮影はご遠慮ください」と案内がある場合もあります。その際は案内や張り紙の指示に従い、決して独断でカメラやスマホを取り出さないようにしましょう。
葬儀中の写真・ビデオ撮影は、基本的には慎むべき行為ですが、遺族の明確な希望や公式な依頼がある場合には適切なマナーのもとで許容されることもあります。まずは遺族や式場への事前確認が絶対条件であり、許可がなければ撮影しないのが礼儀です。
また、地域の習慣や個々の感じ方にも違いがあるため、自分の常識だけで判断せず周囲の雰囲気を読むことが大切です。「撮っていい場面かどうか」に少しでも迷いがあるなら、カメラはしまっておきましょう。
葬儀中に写真・ビデオ撮影する際のマナーと注意点

葬儀の最中にやむを得ず写真や動画を撮影する場合でも、周囲への配慮は最優先です。厳かな式の進行を妨げず、他の参列者に不快な思いをさせないためのマナーを守る必要があります。
ここでは、葬儀中に撮影するときに心得ておきたい具体的な注意点を解説します。スマホであれカメラであれ、撮影者は一挙手一投足に気を配り、「自分の行動がマナー違反になっていないか?」と常に意識しましょう。
式の進行を邪魔しないタイミングと立ち位置
葬儀は故人を送り出す厳粛な儀式です。読経中や焼香中など、参列者が故人に祈りを捧げている最中の撮影は控えるのが原則です。お坊さんが経を上げている間や、参列者がお焼香をしている最中にカメラを向ければ、カシャッという動きだけでも視界に入り式の邪魔になりかねません。撮影するなら、式の合間や区切りの時間を選び、絶対に儀式の核心部分を妨げないようにしましょう。
また、撮影時の立ち位置にも注意が必要です。祭壇や棺に極端に近づきすぎたり、参列者の前を横切って移動したりするのはマナー違反です。特に祭壇に背を向ける姿勢で撮影するのは避けてください。故人や祭壇に対して背中を向けてカメラを構える行為は、たとえ記録目的でも失礼にあたると考えられます。どうしてもそのアングルが必要な場合でも、一礼する、一言断るなど細心の配慮をしましょう。
基本的には会場の後方や端から静かに撮影し、式の流れを乱すような動きをしないことが大切です。事前に葬儀当日の流れをしっかり把握しておきましょう。
 葬儀の流れを知る④〜葬儀・告別式〜
葬儀の流れを知る④〜葬儀・告別式〜
カメラの音やフラッシュは厳禁
葬儀場では静寂な雰囲気が保たれています。その空気を壊さないためにも、シャッター音や電子音は絶対に出さないよう心がけます。デジタルカメラであれば事前にサイレント撮影モードに設定するか、静音機種を使用しましょう。スマートフォンの場合、通常はシャッター音を消せない機種が多いですが、静音カメラアプリを利用するなどして撮影音が鳴らない工夫をしてください。
また、フラッシュ撮影は厳粛な雰囲気を台無しにするため絶対に避けます。暗い室内でも無理にフラッシュを焚かず、多少暗めの写真になっても構わないくらいの気持ちでいましょう。急に眩しい閃光が光れば遺族や参列者が驚くだけでなく、式場の雰囲気も一気に損なわれてしまいます。加えて、電子機器の操作音や通知音も忘れずにオフにしておきます。
操作ミスで動画録画開始音が鳴ってしまった、着信音が鳴ってしまった、では取り返しがつきません。スマホはマナーモードではなく電源OFFに近い機内モード等にし、必要なときだけ起動するくらい慎重でもやりすぎではありません。とにかく音と光で式の邪魔をしないよう徹底しましょう。
故人や他の参列者を尊重する
葬儀で撮影するときは、誰をどのように撮るかにも心配りが求められます。まず、故人の遺体や遺影の撮影は特に慎重に扱うべき問題です。基本的に、遺族から正式に頼まれた場合以外は故人の姿を撮影しない方が良いでしょう。
たとえ生前親しかった故人でも、棺の中のご遺体を無断で写真に収めるのはマナー違反とされています。どうしても最後の別れの姿を残したい場合でも、必ず事前に遺族に理由を伝えて了承を得ることがマナーです。了承を得られた場合でも一瞬だけに留め、角度や枚数を工夫して他の遺族や参列者の心情を害さないよう最大限配慮しましょう。
次に、他の参列者が写り込むことへの配慮も忘れないでください。会場の様子を撮る際に、他の参列者の顔や姿がはっきり写ってしまうと、プライバシーの問題や肖像権の問題が生じる可能性があります。親族内で後で閲覧する記録用であっても、他人が映る写真は取り扱いに注意が必要です。できる限り参列者個人が特定できる形で写さないか、写り込みそうな場合は事前に声をかけて許可をもらうなどの配慮をしましょう。特に一般の弔問客同士で記念写真のように撮影するのは避けるべきです。遺族の許可なく参列者同士で写真を撮り合う行為も慎みましょう。
葬儀はあくまで故人を送る場であり、参加者全員が哀悼の意を表している時間です。他の方の気持ちを第一に考え、被写体選びやカメラの向け方にも礼節をわきまえることが重要です。
絶対にやってはいけないこと
撮影した写真や動画の扱い方にもマナーがあります。最近はスマホで撮った写真をすぐSNSに投稿して共有する人も多いですが、葬儀の写真や動画をSNSにアップする行為は厳に慎むべきです。たとえあなた自身は善意で「故人を偲んでみんなで共有したい」と思っても、インターネット上に公開された写真は不特定多数の目に触れることになります。遺族が知らないところで故人の最後の姿が広まってしまったり、参列者の顔が勝手に晒されてしまう可能性もあります。
それだけでなく、SNSに葬儀の情報や写真を載せると葬儀の場所や日時が第三者に知られ、香典泥棒など留守宅を狙った犯罪につながる危険さえ指摘されています。実際に葬儀中やその直後は家を空けている家庭も多く、防犯面からもSNSで広く発信するのは望ましくありません。
したがって、どんなに親しい間柄でも葬儀の様子をネット上に公開するのはNGと心得ましょう。写真はあくまで自分や近親者内で思い出を振り返るためのものとして手元に保管し、不用意な共有は避けてください。
どうしてもSNS等で共有したい場合は投稿範囲を限定したプライベートグループにする、事前に遺族全員の了承を得るなど、細心の注意を払う必要があります。そして、それでもリスクはゼロでないことを覚えておきましょう。
葬儀中に写真やビデオを撮影する際は、「記録すること」より「儀式を優先すること」を常に意識する必要があります。式の流れを妨げないタイミングと場所を選ぶ、機材の音や光で雰囲気を乱さない、そして被写体となる故人や参列者の気持ちに最大限の配慮を払うことが大切です。撮影者はあくまで黒子に徹し、周囲から浮いてしまう行動を慎みましょう。「こんな場面で撮っていいのかな?」と少しでも感じたら、その場は撮影を諦める勇気も必要です。また、撮った後の写真・動画の取り扱いにもマナーがあります。ネットへの安易な公開は厳禁であり、記録は個人的な思い出として静かに保管するのが原則です。
プロに葬儀撮影を依頼する場合のマナー

最近では、葬儀社のサービスの一環としてプロのカメラマンに葬儀の撮影を依頼するケースも増えています。プロに任せれば遺族は撮影に気を取られず故人との別れに集中できるほか、写真の品質面でも安心感があります。
ただし、プロに任せる場合でも守るべきマナーがあります。この章では、葬儀を取り仕切る葬儀社や僧侶などへの事前連絡、参列者への配慮、さらに撮影時の注意点について詳しく解説します。
葬儀社・式場スタッフ・僧侶への事前連絡
プロのカメラマンを手配する場合、葬儀を取り仕切る葬儀社や式場スタッフ、司式を務める僧侶などへの事前連絡は不可欠です。事前の説明なく撮影が始まると、式の進行に支障が出たり、トラブルになったりする可能性があります。
あらかじめ撮影を行う旨を伝えておき、司式者や会場スタッフがスムーズに対応できるよう準備を整えておきましょう。
参列者への撮影の周知と配慮
参列者に撮影の存在を周知することも重要なマナーです。受付付近に「本日は記録のため、撮影を行います」と案内を掲示するか、受付スタッフから口頭で案内してもらうとよいでしょう。
特に葬儀にカメラが入ることに抵抗を感じる参列者も少なくありません。公式な撮影担当者であることを示す腕章などをカメラマンに着用させ、周囲に誤解や不快感を与えないよう配慮しましょう。
気になる人は、家族だけで静かに故人を見送れる「家族葬」を選ぶのもひとつの方法です。写真やビデオの撮影についても柔軟に相談しやすく、落ち着いて撮影することができます。
 初めてでも迷わない!家族葬の流れと費用 丸わかりガイド
初めてでも迷わない!家族葬の流れと費用 丸わかりガイド
例えば「小さなお葬式」では家族葬プランが充実しており、撮影サービスや式の進行についても丁寧に対応してもらえます。希望に応じて撮影可否の相談や式場スタッフとの連携もサポートしてくれるので、初めての方でも安心です。
撮影範囲やタイミングの指示
プロのカメラマンは葬儀の撮影に慣れているとはいえ、遺族によって撮影を希望するタイミングや範囲は異なります。
例えば、「祭壇や棺の前は撮影しても構わないが、故人の顔や火葬場での収骨シーンは撮影しないでほしい」など、事前に明確な指示を出すことで、当日の混乱を避けられます。撮影すべきシーンや控えるべきシーンがあれば、具体的に打ち合わせしておきましょう。
火葬場での撮影は基本的に禁止
特に注意したいのが、火葬場での撮影です。多くの斎場では火葬炉前や収骨場面での撮影を明確に禁止しています。他の喪家への配慮や遺族の心情を考えても、火葬場での撮影は控えるべきです。
プロのカメラマンに依頼する際にはこの点をはっきり伝えておき、当日のトラブルを未然に防ぎましょう。
プロのカメラマンを依頼する際には、葬儀社や司式者への事前許可、参列者への配慮、撮影範囲の明確な指示が大切です。カメラマンを雇う目的は遺族が葬儀に集中できるようにすることですから、撮影によって逆に混乱が生じることがないよう、周到な準備と細やかな配慮を心がけましょう。
SNS時代の新しい弔い方とデジタルマナー

スマートフォンやインターネットが普及した現代では、葬儀においてもオンライン配信やSNSを活用するケースが出てきました。遠方で参列できない親族や知人に向けて葬儀をライブ配信したり、SNS上で故人への哀悼の意を共有したりといった、新しい弔いの方法が広がりつつあります。
しかし、こうしたデジタル環境を活用した弔い方にも守るべきマナーがあります。SNS時代ならではの注意点を詳しく見ていきましょう。
オンライン葬儀・ライブ配信のマナー
最近では、遠方にいる親族や知人がオンラインで葬儀に参列できるようライブ配信するサービスも登場しています。ただし、配信を行う場合は事前に参列者や司式者の同意を必ず得ましょう。
また、配信の視聴範囲を限定し、不特定多数に公開されないよう設定することが重要です。葬儀というデリケートな場面だからこそ、細心の注意が必要です。
SNSに投稿する際の基本マナー
葬儀の写真や動画をSNSにアップすることは、原則として控えるべきです。自分では「故人への追悼の気持ち」として発信したつもりでも、不特定多数に晒されることで遺族や他の参列者が不快な思いをする可能性があります。
投稿したい場合は、必ず遺族の許可を得て、公開範囲を厳しく制限するなどの慎重な配慮をしましょう。
故人の写真を共有する際の注意点
SNSで故人との思い出を共有したい場合は、遺族への事前確認と公開範囲の設定が必須です。故人の顔がはっきり映っている写真や棺の中の遺体写真をアップするのは絶対に避けましょう。
故人を偲ぶ気持ちを共有すること自体は自然な行為ですが、公開する写真選びには最大限の慎重さが求められます。
デジタルでも変わらない弔いの心
どれほど技術が進歩しても、葬儀の根本的なマナーは変わりません。デジタル環境だからこそ、普段以上に気を配ることが必要です。
デジタルツールはあくまで参列できない方が故人との別れを惜しむ手助けとなるものであり、故人や遺族への敬意を失わないことが大切です。技術の利便性に流されず、心情を第一に考えて活用しましょう。
SNS時代の新しい弔い方は確かに便利な面がありますが、それだけに使い方には慎重さが求められます。オンライン配信やSNS投稿を行う際は、必ず遺族や参列者の気持ちを尊重し、許可を得てから公開範囲を設定するなど配慮を徹底しましょう。故人や遺族への敬意を忘れず、適切なマナーを守って弔うことが何より大切です。
まとめ

葬儀中の写真・ビデオ撮影について、マナーと注意点を詳しく見てきました。大切なのは、遺族の気持ちを第一に考えることです。記録を残したい気持ちは自然なものですが、葬儀は故人との最後の別れの時間でもあります。撮影するにしても儀式の妨げとならないように細心の注意を払い、許可なく無遠慮にカメラを向けることのないようにしましょう。
撮影OKの場合でもフラッシュや音を消して静かに行う、SNSなど不特定多数への公開は厳禁といったポイントを守れば、葬儀の厳粛な雰囲気を壊すことなく思い出を写真や映像に残せます。現代では写真や動画の共有方法も多様化していますが、だからこそ従来からの礼儀やエチケットを改めて意識することが大切です。
最後にもう一度、「迷ったらまず遺族に確認し、遠慮する」という基本に立ち返りましょう。それが故人への尊敬と遺族への思いやりを示す、何よりのマナーと言えるのです。