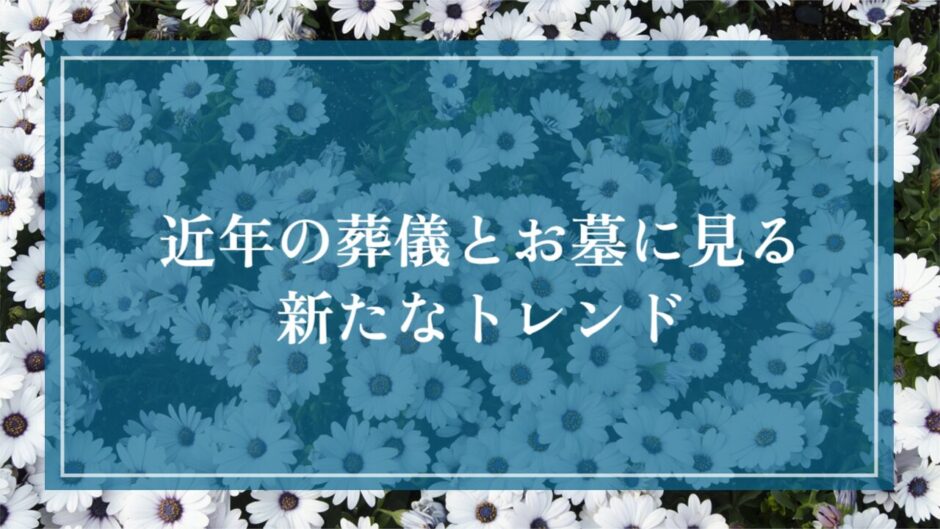近年、日本の葬儀やお墓のあり方が大きく変わりつつあります。かつては盛大な葬儀を行い、先祖代々のお墓を守っていくのが当たり前でしたが、現代では葬儀の規模が小型化し、供養の方法も多様化しています。
本記事では、葬儀が小規模化する背景と種類、そして散骨や樹木葬などお墓の新しい形について解説します。少子高齢化・核家族化やコロナ禍といった社会要因も踏まえ、今後の展望や注意点まで、わかりやすくお伝えします。
目次
小型化する葬儀の背景と種類

かつて日本の葬儀と言えば、通夜から告別式まで通しで行い、親族のみならず職場や近所の方々まで大勢が参列する一般葬が主流でした。しかし近年は葬儀の小型化が顕著です。参列者を家族やごく近しい人だけに限定した家族葬や、通夜を省略して告別式のみ1日で終える一日葬、さらには宗教的儀式を行わず火葬だけを行う直葬(火葬式)といった簡略化された形式が広まりました。
-
家族葬:通夜・葬儀・告別式を行いますが、参列者は親族やごく親しい知人に限った小規模な葬儀。近年最も選ばれている形式です。
-
一般葬:従来からある通夜・葬儀・告別式を行う葬儀で、地域の方や職場関係者など幅広い参列者が集まる大規模な形式。
-
一日葬:通夜を行わず告別式だけを1日で行う葬儀。忙しい現代人のニーズに合い増えてきました。
-
直葬(火葬式):通夜や告別式を行わず、火葬だけで故人を送り出す最も簡略な形式。費用負担は軽いものの、お別れの機会が限られます。
鎌倉新書が行った調査[1]によれば2024年時点で家族葬が全体の50.0%を占め、一般葬は30.1%、一日葬10.2%、直葬9.6%という割合でした。家族葬が半数を占めるのは前回調査に続き最多で、「都市化や核家族化による地域のつながりの希薄化」といった社会背景が葬儀小型化の要因と分析されています。
コロナ禍以前は親族以外も多数参列する一般葬が一般的でしたが、感染対策の観点から葬儀を家族中心で執り行うケースが増え、この流れが定着しつつあるのです。
 親の葬儀準備は何から始める?家族葬・直葬から費用・葬儀社選びまで徹底解説
親の葬儀準備は何から始める?家族葬・直葬から費用・葬儀社選びまで徹底解説
少子高齢化や核家族化も葬儀小型化の大きな要因です。子供の数が減り親族の範囲が狭まったことで、葬儀に呼ぶ親戚自体が少なくなっています。また地方から都市部への人口移動で地元の地域コミュニティとの結びつきが弱まり、近所総出で葬儀に参列するといった昔ながらの風習も薄れました。親しい関係者のみで静かに故人を見送りたいという価値観の多様化もあり、形式にとらわれない小さなお葬式が受け入れられやすくなっています。

さらに新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の流行は葬儀規模に直撃しました。2022年に行われた調査[2]では家族葬が55.7%と過去最高、逆に一般葬は25.9%と過去最少まで落ち込んでおり、多くの人が集まる従来型葬儀が敬遠されたことが分かります。参列者数の減少により香典収入も減ったため、平均的な葬儀費用の総額も約110.7万円に縮小し、2020年比で73.6万円も減少しました。
コロナ禍で一時的に葬儀規模は大幅に縮小しましたが、その後2023年前後からは行動制限の緩和に伴い一般葬がやや持ち直し、2024年には一般葬の割合が30%程度まで回復しています。とはいえ依然として家族葬が主流であり、葬儀小型化という流れは今後も続くとみられます。
葬儀を小規模にすることで費用負担が軽減される点も見逃せません。従来、参列者が多ければ香典も多く集まりましたが、その分通夜振る舞いや返礼品などの費用も増大しました。しかし、小さな葬儀では参列者が少ないため飲食接待や返礼品の数が抑えられ、トータル費用を低くできます。
前出の調査[1]では一般葬の平均費用が161.3万円だったのに対し、家族葬は105.7万円、一日葬87.5万円、直葬は42.8万円と、規模の小さい葬儀ほど費用も安く済んでいます。経済的な理由から「できるだけ費用をかけたくない」という人にとっても、家族葬などの小型葬儀は現実的な選択肢となっているのです。
「小さなお葬式」が選ばれる理由とサービス紹介

葬儀の小型化が進む中で、特に注目を集めているサービスの一つが「小さなお葬式」です。その名の通り小規模でシンプルなお葬式に特化したもので、2009年にインターネット葬儀のパイオニアとして誕生しました。不透明になりがちな葬儀費用を徹底的に見直し、無駄を省いた低価格のパッケージプランを提供したことで利用者を伸ばし、2025年3月時点で59万件以上もの依頼実績があります(※1)。葬儀受注件数で2017~2024年の8年連続全国No.1との調査結果もあり(※2)、現在日本で最も利用されている葬儀サービスと言えるでしょう。
 「小さなお葬式」とは? 費用やプラン、口コミなど徹底的に調べてみました
「小さなお葬式」とは? 費用やプラン、口コミなど徹底的に調べてみました
「小さなお葬式」が支持される最大の理由は、その費用の安さ・明瞭さにあります。一般的な葬儀の全国平均費用(約108万円)に比べ、大幅にコストを削減したセットプランを用意しており、最安プランでは税抜99,000円~と、非常に経済的な料金設定です。
これほど料金を安く抑えられる理由は、サービスを必要最低限の物品や儀式に絞り、適正価格に見直していること、全国の提携式場の空き時間を活用してコストを削減していること、そして現代のニーズに合わせて小規模な家族葬に特化した運営を行っているためです。「過剰な装飾や過度なおもてなしを省き、本当に必要なものだけをセットにした」からこそ実現できた価格なのです。
また、葬儀に必要な項目はあらかじめパッケージ化されており、追加費用が発生しにくい料金設定になっています。火葬料や、既定の料金を超えた場合の式場利用料など一部に別途費用がかかる場合もありますが、事前に丁寧な説明があるため、低価格でも安心して利用できます。

宗教者(お坊さん)の手配やお布施が定額で利用できるプランも用意されており、初めて喪主を務める方でも戸惑わないよう、手厚くサポートされています。
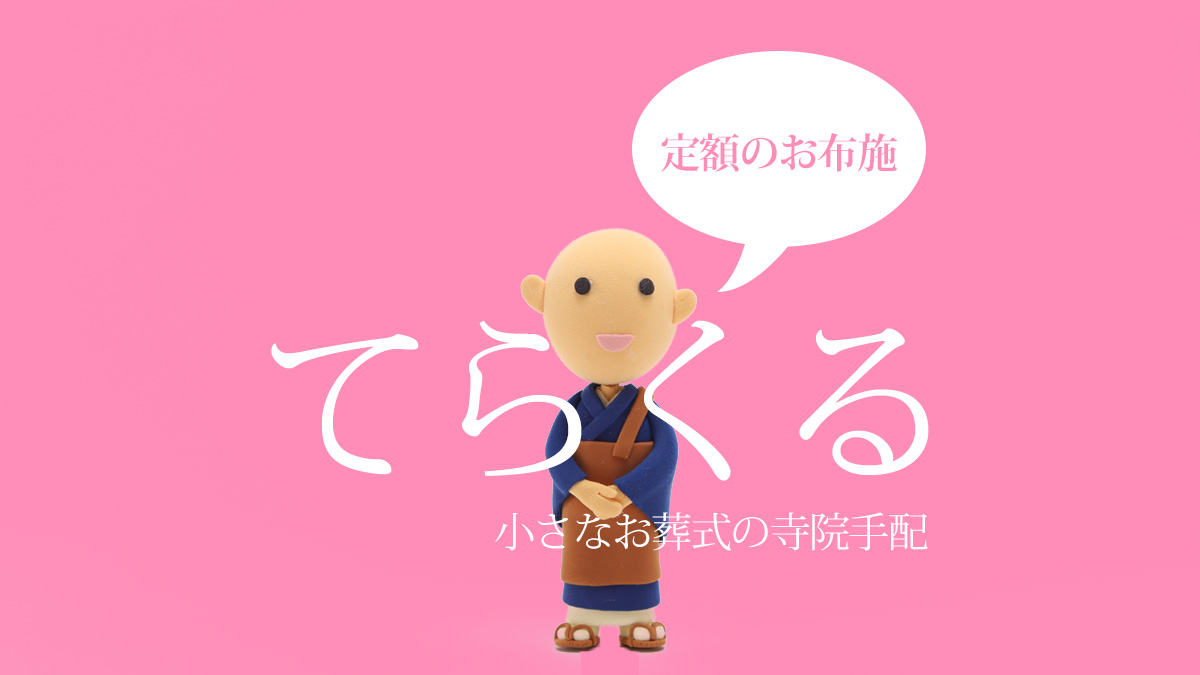 小さなお葬式の寺院手配「てらくる」とは?サービス内容と口コミ・評判を解説
小さなお葬式の寺院手配「てらくる」とは?サービス内容と口コミ・評判を解説
全国に4,000か所以上の提携式場を持ち、自宅近くで葬儀を行える体制が整っているのも大きな特長です。24時間365日対応のコールセンターがあり、急な相談にもすぐ対応できます。これらのきめ細やかなサービスにより、利用者満足度は96%と高い水準を誇っています(※3)。
「小さなお葬式」が選ばれる理由としては、やはり「費用を抑えたいが粗末にはしたくない」というニーズに応えている点でしょう。実際に「家族葬専門の格安プランがあると安心」という声や、「明確な料金体系で追加費用の心配が少ないのが良い」といった口コミも多く見られます。身内だけでアットホームに送りたい方、遠方の親族が少なく大がかりな式は望まない方、経済的に負担を抑えたい方などに幅広く支持されているようです。
なお、「小さなお葬式」の公式サイトでは無料で資料請求をすることができ、請求者限定の特典も用意されています。ウェブから資料を取り寄せると葬儀費用が5万円割引になるクーポンが付き、さらに万一の時に役立つ小冊子『喪主が必ず読む本』がプレゼントされるキャンペーンが実施されています。
資料請求や見積もりは1分程度で簡単に申し込めるので、「いざという時のために情報だけでも…」という場合でも気軽に利用できます。低価格で利用しやすい「小さなお葬式」は、葬儀の小型化時代における代表的なサービスとして今後も注目が集まりそうです。
※1 対象期間:2009年10月~2025年3月 2025年4月 ユニクエスト調べ
※2 2017~2024年 葬儀受注件数に関する調査(TPCマーケティングリサーチ調べ。仲介や再委託による施行を含む件数)
※3 2024年度 ご利用アンケート(回答数40,268件)の平均値を四捨五入 2025年4月ユニクエスト調べ
変化するお墓のありかた

近年、葬儀の形だけでなく、お墓のあり方にも大きな変化が訪れています。かつては「○○家之墓」と刻まれた先祖代々のお墓を自宅近くの墓地や寺院に設け、子や孫が受け継ぎ守っていくのが当たり前でした。しかし、少子高齢化や都市部への人口集中、ライフスタイルの変化に伴い、「お墓を持たない」選択や新しい供養スタイルが広がっています。
墓じまいの増加とその背景
まず注目すべきは、先祖代々のお墓を整理してしまう「墓じまい」が増えていることです。墓じまいとは、現在の墓から遺骨を取り出し墓石を撤去してお墓を閉じること(法律上は「改葬」)を指します。2022年度の厚生労働省調査[3]では改葬件数が15万件を超え、過去最多となるなど増加傾向が明確です。また、鎌倉新書の調査[4]でも改葬や墓じまいの相談が増加していると報告されています。
墓じまいを検討した理由で最も多いのは「お墓が遠方にあり過ぎてお参りに行けない」(54.2%)で、続いて「お墓の継承者がいない」ことが多い一方、「お墓を継ぎたくない」と感情的に拒否する人は1割未満にとどまります。つまり、墓じまいは物理的・現実的な事情によるものが主であり、感情的な理由とは限らないのです。
墓じまい後の多様な供養スタイル
墓じまい後の遺骨の扱いも多様化しています。従来は近場の墓地に移すか、寺院の合祀墓に永代供養を依頼するケースが一般的でした。しかし現在は、散骨や樹木葬、手元供養、合葬墓(他の遺骨と合同で祀る共同墓)、屋内型納骨堂など、多彩な選択肢が増えています。
こうした流れは、葬儀の家族葬化とも連動しており、「身内だけで静かに見送り、その延長で供養もシンプルに」という考え方が広まっています。実際、「墓じまい後は新たにお墓を持たずに別の形で供養したい」という声も多く聞かれます。
散骨の広がり

まず注目されるのは「散骨」です。遺骨を粉状にして海や山に撒き自然に還す散骨は、法律で明確に禁止されていないこともあり、近年選ぶ人が増えています。特に海洋散骨は人気で、例えば東京湾で散骨を行う海洋記念葬®シーセレモニーでは、2022年の施行件数が2020年の2倍、2023年には4倍近くに増加する見通しです[5]。
屋外でマスクを外して見送れる開放感に加え、少子高齢化や都市部への人口集中、新型コロナによる遠方墓参の困難さが背景にあります。かつては「遺骨を海に撒く」ことに抵抗感もありましたが、「故人が海を愛していた」「お墓の管理負担を残したくない」という前向きな理由で散骨を選ぶ人が増加しています。
散骨は自然志向の新しい供養スタイルとして市場も拡大しています。全国優良石材店の会の調査[6]によれば、国内で年間約2.5万人が海洋散骨を選び、将来的には現在の10倍以上に増加する可能性があります。実際に散骨を経験した人はまだ2~3%程度ですが、認知度は約9割に達しており「選択肢の一つ」として定着しつつあります。
 お墓の代わりに選ぶ「散骨」とは?種類・費用・メリット・デメリット・注意点
お墓の代わりに選ぶ「散骨」とは?種類・費用・メリット・デメリット・注意点
樹木葬の急成長
もう一つ急速に普及しているのが「樹木葬」です。墓石の代わりに樹木や草花を墓標とし、遺骨を土中に埋葬して自然に還す供養方法で、跡継ぎ不要の永代供養付きプランが多いのが特徴です。都市部・地方を問わず人気が高く、「子孫に管理負担をかけたくない」「自然に帰りたい」というニーズに応えています。
鎌倉新書が2022年に行った調査によると[7]、新規でお墓を購入した人のうち51.8%が樹木葬を選び、従来型の石のお墓を上回る勢いです。これは長寿化で長男すら遠方や海外に住むことが増え、お墓の継承が難しくなった事情も背景にあります。
費用面でも従来型墓石に比べ手頃で、数十万円から利用できるプランが多いことも支持されています。また、明るく緑豊かな霊園の雰囲気や、夫婦・家族用、ペット同伴区画など多様なニーズに応えるバリエーションも豊富で、次世代の供養スタイルとして定着しています。
 樹木葬とは?お墓の代わりに選ばれる理由と種類・費用まで解説
樹木葬とは?お墓の代わりに選ばれる理由と種類・費用まで解説
永代供養墓と納骨堂の普及
さらに、永代供養墓や屋内納骨堂も増えています。永代供養墓とは個人や夫婦の遺骨を寺院や霊園が永続的に供養・管理するもので、多くは他の遺骨と合同で祀る合祀型です。地方の墓じまい後に永代供養墓へ移すケースや、生前契約する身寄りのない人も増加しています。
都市部ではビル型の納骨堂が続々と登場し、自動搬送装置で遺骨収蔵箱を運ぶハイテク施設や、仏壇ロッカーのようなマンション型霊園も見られます。これらはお墓の継承者がいなくても利用でき、「子どもに負担をかけたくない」「遠方からでも手を合わせたい」というニーズに応えています。
このように、現代日本では「お墓を持たない」「新しい形のお墓にする」人が確実に増えています。供養の多様化は、超高齢社会の中で避けられない流れと言えるでしょう。
 跡継ぎ不要・管理不要のお墓とは?永代供養と納骨堂のすべて
跡継ぎ不要・管理不要のお墓とは?永代供養と納骨堂のすべて
今後の展望と注意点―多死社会と供養のこれから

葬儀・お墓の新トレンドを見てきましたが、今後さらにどのような変化が予想されるでしょうか。また、こうした新しい選択肢を検討する際に注意すべき点は何でしょうか。本章では「今後の展望と利用者側の注意点」についてまとめます。
増え続ける死亡者数と、葬儀・供養のこれから
日本は今後、しばらく「多死社会」に向かって進んでいくと予測されています。実際、死亡者数は今後20年ほど増え続け、2030年代から2040年代にかけてピークを迎える見通しです[8]。そうなると当然、葬儀や供養の需要は増えていきます。
とはいえ、だからといって業界全体が成長するわけではありません。葬儀の小型化や、1件あたりの費用の低下が進んでいるからです。矢野経済研究所の調査[9]によると、葬祭ビジネスの市場は今後縮小していくとの見方も。これは、多死化による利用件数の増加以上に「一件ごとの単価減」の影響が大きいことを意味しています。
こうした流れの中、葬儀会社は価格競争やネット対応といった新たな課題に直面しており、業界構造自体も変わろうとしています。
広がる多様な選択肢――IT、宇宙葬、VRまで
葬儀のスタイルもさらに多様化しています。最近では、オンラインでの葬儀やリモートでの参列といったITを活用したサービスが登場しており、今後は一般的になっていくかもしれません。さらに、故人の人生を映像で振り返る「お別れ会」や、遺骨を宇宙空間に送る「宇宙葬」など、個性的なプランも注目されています。
供養の世界でも新しい形が出てきています。たとえば、インターネット上で故人を偲ぶ「デジタル墓参り」や、故人との思い出をVRで体験できるサービスなども登場。これまでのような「型にはまった供養」ではなく、それぞれの価値観に合わせたパーソナルな見送りが、これからの主流になるかもしれません。
 【2025年最新版】えっ⁉︎ ここまで進化した葬儀サービス6選──液体火葬からAI追悼までまるっと解説!
【2025年最新版】えっ⁉︎ ここまで進化した葬儀サービス6選──液体火葬からAI追悼までまるっと解説!
簡素な葬儀がもたらす「心残り」に注意
ただし、新しいスタイルを選ぶ際には注意も必要です。最近増えている直葬(火葬式)は、時間や費用を抑えられる反面、形式を簡略にしすぎることで後悔が残るケースあります。鎌倉新書が行った調査[2]によると、直葬を行った人のうち「何も後悔はない」と答えたのは38.7%に留まり、多くの人が「やはりお別れの場を設ければよかった」と感じているのです。
そうした後悔を防ぐためにも、たとえ家族葬や直葬を選んだ場合でも、後日「お別れ会」や「偲ぶ会」を開く、あるいは遠方の親戚には書面やオンラインで報告するといった、心のフォローになる工夫が大切です。
また、生前から「葬儀は簡素に」と希望していても、それを家族と共有しておかないとトラブルの元になります。大切なのは、故人の希望と家族の気持ち、どちらも大事にすること。生きているうちにしっかり話し合っておくことが、後悔を防ぐ最善の方法です。
散骨・樹木葬・永代供養墓――新しい供養法の落とし穴

供養のかたちもさまざまになってきましたが、ここにも注意点があります。
たとえば、最近人気の散骨。実は法律上の明確なルールはありませんが、実施には公衆衛生や周辺環境への配慮が欠かせません。海に撒くなら沖合で、山で撒くなら私有地の許可を取るなど、きちんとしたルールにのっとって行う必要があります。また、悪質な散骨業者のトラブルも報告されています。信頼できる業者を選ぶことが大前提です。
もうひとつ注意したいのは、「散骨すると遺骨が残らない」こと。これが意外と後から後悔につながることもあります。「やっぱりお墓に入れてあげればよかった」と感じる人もいるのです。最近では、散骨場所の緯度・経度を記録するサービスもありますが、やはり形が残らないことに抵抗感を持つ家族も少なくありません。家族でよく話し合い、全員が納得したうえで進めることが大切です。
 遺骨を手元供養したい方へ:基礎知識と進め方ガイド
遺骨を手元供養したい方へ:基礎知識と進め方ガイド
樹木葬や永代供養墓を検討する場合にも、契約内容を細かく確認することが必要です。たとえば、「○年間は個別に安置、その後合祀」というように期間が決まっているケースもあれば、粉骨して土に撒く場合も。名前プレートの有無、合同法要の有無など、霊園によって条件はさまざまです。現地見学や資料取り寄せで事前に確認しておくことで、「こんなはずじゃなかった」という後悔を防ぐことができます。
お金と手続きの準備も忘れずに
お墓を移す、いわゆる「墓じまい」には費用も手間もかかります。墓石の解体費用は1平米あたり10~15万円が相場で、墓地が広ければ数十万円の支出になることも。改葬先への納骨費用や永代供養料なども必要です。
また、自治体から改葬許可証を取得するなどの手続きも発生します。お金のこと、書類のこと、しっかりとした準備が必要です。
こうしたさまざまな選択を後悔なく進めるためには、やはり「終活」の意識が重要です。
終活とは、人生の終わりに向けてあらかじめ準備をしておくこと。たとえば、自分の葬儀はどんな規模でやってほしいか、誰に連絡してほしいか、お墓や散骨についてどう考えているか。そうした希望を、エンディングノートに書き残しておくと、残された家族が迷うことなく対応できます。
供養のスタイルが多様化した今だからこそ、本人と家族の意思のすり合わせが、これまで以上に大切になっているのです。
まとめ

以上、近年の日本における葬儀とお墓のトレンドについて見てきました。葬儀の小型化は経済状況や家族構成の変化、コロナ禍を経て加速し、家族葬や一日葬が主流となりつつあります。一方で、それに合わせて供養の形も見直され、お墓を持たないという選択や自然に還る葬送(散骨・樹木葬)が広がってきました。
こうした新たな潮流は、時代のニーズに即した合理的なものですが、同時に伝統的な儀式や慣習が持つ心のケアの面も忘れないようにしたいものです。大切なのは形式の大小よりも、故人を想う気持ちのあり方でしょう。それぞれの家庭に合った最良の送り方・供養の仕方を選択できるよう、本記事の情報がお役に立てば幸いです。
脚注
- 鎌倉新書「第6回お葬式に関する全国調査」(2024年)↩︎
- 鎌倉新書「第5回お葬式に関する全国調査」(2022年)↩︎
- 厚生労働省「衛生行政報告例」(2022年度)↩︎
- 鎌倉新書「第3回 改葬・墓じまいに関する実態調査」(2024年)↩︎
- 海洋記念葬®シーセレモニー 2023年3月17日プレスリリースによる↩︎
- 一般社団法人 全国優良石材店の会「散骨に関する調査」(2023年)↩︎
- 鎌倉新書「第14回 お墓の消費者全国実態調査」(2023年)↩︎
- 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(令和5年推計)結果の概要」(2023年)↩︎
- 矢野経済研究所「葬祭ビジネス市場に関する調査」(2023年)↩︎