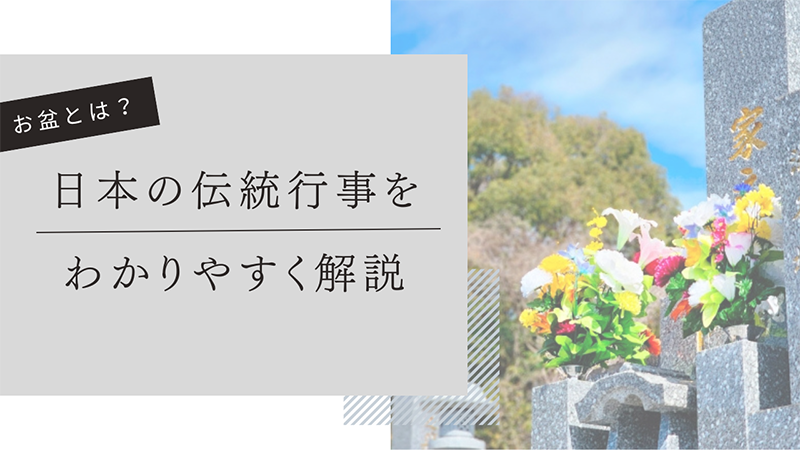夏の盛り、毎年お盆の時期になると、ふるさとへ帰省したりお墓参りをしたりと、忙しくも懐かしい思いをされる方も多いのではないでしょうか。
お盆とは、古くから日本で行われてきた伝統行事で、ご先祖様の霊を家にお迎えし、供養する期間のことです。地域によって時期は異なりますが、一般的には毎年8月13日から16日(地域によっては7月や旧暦に行う場合もあります)に行われます。
お盆は仏教行事である盂蘭盆会(うらぼんえ)が起源ですが、日本古来の先祖信仰とも結びつき、長い歴史の中で人々に親しまれてきました。
お盆の期間中は、家族や親族が集まり、ご先祖様に感謝を伝える様々な風習が各地で行われます。例えば、家の玄関先で火を焚いて霊を「迎え」、また火を焚いて霊を「送る」迎え火・送り火や、キュウリやナスで作った精霊馬(しょうりょううま)、お墓参りや盆踊り、盆提灯を飾ること、川や海に灯籠を流すことなど、実に多彩です。
この記事では、お盆の由来や意味、代表的な風習、地域ごとの違い、現代のお盆の過ごし方、準備するものや心構えまで、分かりやすく丁寧に解説します。年配の方には馴染み深いお盆ですが、改めてその背景や作法を知ることで、より一層ご先祖様を偲ぶ気持ちが深まるかもしれません。それでは、お盆について一緒に見ていきましょう。
目次
お盆の由来と意味 – 仏教の教えと先祖供養

お盆は正式には「盂蘭盆(うらぼん)」といい、古代インドの言葉で「ウラバンナ(逆さ吊り)」を語源とします。一見物騒な意味に思えますが、これはお釈迦様の弟子である目連(もくれん)尊者が亡き母親を救おうと奮闘した仏教説話に由来しています。
目連尊者の母は死後に餓鬼道という世界に堕ちて苦しんでいましたが、目連尊者はその母を何とか救おうとします。最後に頼ったのがお釈迦様の教えであり、大勢の僧侶たちと共に修行し功徳を積んだことで、ついに母を救うことができた――これが『仏説盂蘭盆経』(ぶっせつうらぼんきょう)に説かれる物語です。この教えは「親孝行の大切さ」を説いたものでもあり、日本のお盆行事のルーツになっています。
なお、『盂蘭盆経』そのものは後世に中国で作られた経典で、正式な仏教経典(真経)ではないため偽経と呼ばれますが、内容の尊さに違いはなく、お盆行事に大きな影響を与えました。
日本には古来より祖先の霊を祀る先祖崇拝の風習がありました。奈良時代頃までには中国から伝わった仏教行事の盂蘭盆会が宮中行事として取り入れられた記録が『日本書紀』に残っています。日本の盂蘭盆会は、先述の『盂蘭盆経』の教え(亡き人を供養し救済する教え)と、日本古来の祖霊信仰(先祖の霊を敬い慰める信仰)が融合し、平安時代以降、貴族や武士階級にも広まっていきました。
やがて庶民の間にも定着し、江戸時代になると精霊棚(しょうりょうだな)と呼ばれるお盆飾りの棚を用意したり、お坊さんに棚経(たなぎょう)といってお経を上げてもらったり、迎え火・送り火を焚いたり、盆踊りを踊ったりといった現在につながる風習が盛んになったとされています。
ところで、「お盆(盆)」という言葉自体の意味についても触れておきましょう。「盆」とは本来、お供え物を載せる容器(盆)を指す言葉であり、転じて霊に供物を供える行事(盂蘭盆会)の略称になったとも言われます。地域によっては先祖の霊を「盆様(ぼんさま)」と呼ぶこともあり、言葉の上でもお盆行事と霊魂信仰が混じり合っていることがわかります。つまりお盆とは、「亡くなったご先祖様の霊を家にお迎えし、供養するための大切な期間」だと言えるでしょう。
お盆の代表的な風習あれこれ

お盆には先祖の霊を迎えて供養するための様々な風習があります。その多くは地域や宗派を問わず全国的に見られるものです。ここでは、一般的なお盆の習慣をいくつかご紹介します。
迎え火と送り火 – ご先祖様の送り迎え
お盆の入り(一般的には 8月13日)には、ご先祖様の霊が迷わず帰って来られるように迎え火を焚きます。また、お盆が明ける16日には、霊をあの世へお送りする送り火を焚いて見送ります。この迎え火・送り火は、お盆の期間中でも最も象徴的な風習でしょう。
普通は家の門口や庭先で、麻がら(おがら)と呼ばれる麻の茎を燃やしたり、焙烙(ほうろく)という素焼きのお皿の上で松葉を燃やしたりして火を焚きます。燃え上がる火は小さいながらも、暗い中で霊に「こちらが我が家ですよ」と知らせる目印になると言われます。
迎え火で「ようこそお帰りなさい」とお迎えし、送り火で「またお帰りください」と送り出す——ご先祖様に対する思いを込めた大切な儀式です。
ただし現代では、住宅事情で屋外で火を焚けない場合もあります。マンション住まいの方などはベランダで線香を焚くだけにしたり、迎え火用のローソク(屋内でも安全に焚ける工夫を凝らした商品)を利用するケースもあるようです。昔ながらのやり方にこだわらずとも、ご先祖様をお迎えする気持ちがあれば形は問いません。火を使う場合は安全に十分注意し、無理な場合は省略しても大丈夫です。
ちなみに昭和の頃には、あるお年寄りがお盆にマンションのエレベーター前で迎え火を焚き、煙探知機を誤作動させて大騒ぎになったという出来事がありました。現代ならではのエピソードですが、「ご先祖様に迷われては困る」という切実な思いが、思わぬトラブルを招いてしまった例とも言えるでしょう。
精霊馬と盆飾り – 馬と牛に込められた意味

お盆期間中、仏壇や精霊棚(しょうりょうだな)と呼ばれる祭壇に飾られるものの中に、とてもユニークな飾りがあります。それが精霊馬(しょうりょううま)と呼ばれるキュウリやナスで作った馬と牛の飾りです。
割り箸や麻がらの棒を四本、キュウリやナスに刺して動物の足に見立て、青々としたキュウリは馬、丸々としたナスは牛に仕立てます。この馬と牛には、ご先祖様の霊を「乗り物」に乗せて送り迎えするという意味があります。「行き(こちらへ来る時)は足の速い馬で一刻も早く、帰りは名残惜しいので牛に乗ってゆっくりと」というわけです。キュウリの馬はスピードを、ナスの牛はゆったりとした歩みを象徴しており、先祖に早く来てほしい・できるだけゆっくり帰ってほしいという家族の願いが込められているのです。
また、精霊馬以外のお盆飾りや供え物にも様々な意味があります。例えば、お盆棚に下げたり供えたりするそうめん(素麺)は細く長い形から長寿や良縁を願う縁起物とされていますし、ご先祖様の霊があの世に帰る際の馬の手綱や荷を結ぶ紐に見立てる地方もあります。ほおずき(鬼灯)は赤く膨らんだ提灯のような形の実で、「提灯代わり」つまり霊が灯りを頼りに帰ってくる目印になるとされ、お盆飾りによく使われます。
他にも、季節の野菜や果物、故人の好物だったお菓子や飲み物などもお供えされます。昆布は「よろこぶ」に通じる語呂合わせで縁起が良いとされ、ナスやキュウリを細かく刻んだものと米を混ぜ水を張った供え物(水の子といいます)は、迷っている霊や無縁仏の霊が喉を潤せるようにとの意味があります。このように一つひとつの飾りや供物に、先祖や故人への思いや願いが込められているのです。
盆棚の周りには盆提灯(ぼんちょうちん)も飾ります。盆提灯は仏壇や盆棚の左右に立てたり吊るしたりする華やかな灯籠で、これも文字通り明かりでご先祖様をお迎えする役割があります。初めてお盆を迎える家(新盆・初盆といいます)では、親族から白木の提灯(白紋天)など絵柄入りの盆提灯を贈る習慣もあります。
最近では「提灯はお好みのものを選んでください」という気持ちで提灯代(現金)を包むケースも増えています。盆提灯の柔らかな灯りが揺れる様子は、お盆ならではの情緒を感じさせます。電気式の提灯もありますが、多くの家庭では伝統的な絵柄入りの提灯が飾られ、ご先祖様に明るい道しるべと心温まるおもてなしの気持ちを示しています。
お墓参り – 家族揃って先祖に感謝

お墓参りもお盆に欠かせない大切な習慣です。普段なかなかお墓に行けない方も、お盆だけは家族揃って故郷のお墓に足を運ぶという話をよく聞きます。お盆の時期には帰省した親族と一緒にお墓の掃除をし、新しいお花や線香を供えて手を合わせる光景が全国各地で見られます。
特にお盆の入りである13日にお墓参りをするのが良いとされますが、これは墓前で迎え火を焚いてご先祖様をお迎えする昔の風習に由来すると言われます。地域によっては、お墓で迎え火を焚き、その火を提灯に移して家まで持ち帰る「お迎え提灯」の習慣が残っている所もあります。墓地から自宅まで先祖の霊をご案内するという、風情のある風習です。
なぜお盆にお墓参りをするのかについては諸説あります。一つには前述のように「迎え火・送り火を墓で行っていた名残」だとする説、もう一つには中国の伝承に基づく「魂魄(こんぱく)思想」による説です。魂魄思想では、人には「魂」(精神)と「魄」(肉体)があり、亡くなった後、魂は家に帰ってくるけれど魄は墓に留まると考えます。そのため、お盆に家へ帰ってきた魂だけでなく、お墓に残る魄にも手を合わせる必要がある、というのです。
いずれにせよ、ご先祖様に日頃の感謝を伝えるためにお墓参りをする習慣は、現代でも広く守られています。忙しくてお盆の時期にお墓参りに行けない場合は、無理をせず日を改めても構いません。お盆に限らず、お墓参りは「いつ行っても良い」のが本来の考え方です。大切なのは気持ちですから、時間が取れる時にお墓を訪れ、墓石をきれいにしてお線香を手向け、ご先祖様に思いを馳せれば十分供養になります。遠方でどうしても行けない方は、自宅の仏壇や位牌に手を合わせるだけでも、ご先祖様はきっと喜んでくださるでしょう。
盆踊り – みんなで踊って供養と交流

夏祭りの風物詩としてお馴染みの盆踊りも、お盆の行事の一つです。現在のような賑やかな盆踊り大会のイメージからは想像しにくいかもしれませんが、起源は平安時代に浄土宗の僧・空也が始めたとされる念仏踊りに遡るともいわれます。空也上人が念仏を称えながら踊り歩いたという記録も残されており、これが盆踊りの原型とされています。
その後、室町時代頃までに精霊を慰める踊りとして各地に広がり、江戸時代には庶民の夏の娯楽として定着しました。太鼓や笛の囃子に合わせて老若男女が輪になり踊る盆踊りは、亡き人の霊を慰めると同時に、地域コミュニティの交流の場ともなってきました。
有名なものでは、徳島県の阿波踊りが日本三大盆踊りの一つに数えられます。残る二つは、秋田県西馬音内(にしもない)の盆踊りと、岐阜県郡上(ぐじょう)おどりです。
阿波踊りでは、三味線や鉦(かね)、太鼓の音に乗せて、「連(れん)」と呼ばれる踊りのグループが街中を舞い踊ります。掛け声も勇ましく、見る人も一緒になって踊り出したくなる熱気があります。また、西馬音内の盆踊りでは踊り手が深い編み笠や黒頭巾で顔を隠して踊る独特の風習があり、「亡き人に扮している」という説や、仮面を付ける地域も含め「輪の中に先祖の霊が紛れて踊っていてもわからないようにするため」とも言われます。
こうした伝統的な盆踊りは、近年ユネスコの無形文化遺産への登録も検討されるなど再評価されており、各地で大切に保存・継承されています。
一方、都市部や最近の住宅地などでは、自治会や町内会主催の盆踊り大会が夏祭りとして開催され、子供からお年寄りまで浴衣姿で集まって踊ります。昔ながらの「炭坑節」「東京音頭」から、アニメソングに合わせた創作踊りまで様々ですが、みんなで輪になって踊る楽しさは今も昔も変わりません。
盆踊りの輪には、もしかしたらあなたの知らないご先祖様もこっそり混じって一緒に踊っている…そんな風に想像すると、お盆の夜が少し不思議で温かいものに感じられませんか?
精霊流し・灯籠流し – 光に乗せて送り出す

お盆のフィナーレとして各地で行われる送り火の行事には、地域独特のものがあります。その代表が、長崎県を中心に見られる精霊流し(しょうろうながし)です。
精霊流しは、初盆(その年に亡くなった方の最初のお盆)を迎えた家で行われることが多く、家族や親族が手作りした精霊船(しょうりょうぶね)という船型の御輿に故人の霊位を乗せ、提灯や花で美しく飾り付けて町中を練り歩きます。道中では「ドーイ、ドーイ」という掛け声とともに爆竹が盛大に鳴らされ、にぎやかに故人を天国へ送り出します。
かつてはその精霊船を海や川へ流していたそうですが、現在では環境面の配慮から実際に流すことはせず、決められた流し場まで運んだら解体されるのが一般的です。
長崎の精霊流しで運ばれる精霊船。提灯や花で華やかに飾り立てられ、爆竹の音とともに街を練り歩く様子は迫力があります。
精霊流しとよく混同されますが、全国各地で行われる灯籠流し(とうろうながし)もお盆の送り火行事の一つです。こちらは紙や木で作った灯籠(四角い小さな灯り)に火を灯し、川や海に流してご先祖様の霊を送る伝統行事です。京都の鴨川や東京の隅田川など、各地で灯籠流しのイベントが行われ、夕闇に無数の灯籠がゆらめき流れる光景はとても幻想的です。灯籠に「○○家先祖之霊」など故人や先祖の名前を書いて流し、感謝と鎮魂の気持ちを捧げます。
また、京都の有名な五山の送り火(大文字焼き)は、お盆の送り火行事を代表するものです。毎年8月16日夜、京都市内の五つの山で「大文字」「妙・法」などの巨大な炎の文字や絵が点火され、京都盆地全体を照らします。これはお盆に帰ってきた精霊をあの世へ送り届けるための火であり、市民や観光客が夜空に浮かぶ炎を見上げながら亡き人に思いを馳せます。
他にも、地域によって様々な送り火がありますが、いずれも炎や灯りに霊を託して見送るという点では共通しています。明かりの揺らめきには不思議と心を慰める力があり、「また来年も帰ってきてね」という願いを込めて手を合わせる人々の姿が各地で見られます。
地域によるお盆の違い – 時期と風習の地域色

日本全国で行われるお盆行事ですが、その時期や習慣には地域ごとの違いもあります。大きく分けると、お盆の時期は 7月盆(新暦盆) と 8月盆(旧暦盆、月遅れ盆)、そして沖縄など一部で行われる旧暦盆の三つに分かれます。
現在、全国的に最も多いのは 8月13日〜16日 に行うお盆(いわゆる「8月盆」)です。しかし、東京や神奈川の多くの地域、金沢市の旧市街地、静岡県の都市部などでは 7月13日〜16日 にお盆を行う「7月盆」が主流となっています。
これは明治維新の際に暦が旧暦(太陰太陽暦)から新暦(太陽暦)に変わったことに由来します。本来旧暦7月15日がお盆でしたが、新暦では季節感がずれるため約1ヶ月遅れの8月になりました。しかし各地で従来の習慣をすぐには改められず、結局「月遅れ」の8月にお盆を行う地域が大半となったのです。
一方、いち早く新暦を採用した都市部では新暦7月にお盆を行う風習が残ったというわけです。東京でも下町は7月盆、郊外の一部は8月盆など混在している場合もあります。また、東京都多摩地域の一部では7月末から8月2日にかけて行う地域もあるとのこと。さらに沖縄県では旧暦の7月15日を中心にお盆を行うため、新暦では毎年日付が変動し、8月中旬から9月上旬頃になります。
このように、お盆の時期は地域によって「ひと月」前後することがあるので、引っ越し等で土地が変わった場合には地元の方に確認すると良いでしょう。
風習にも地域色豊かな違いがあります。前述の精霊流しや灯籠流しは長崎県や各地で独自に発展したものですし、京都ではお盆前の8月8日〜10日に「六道まいり」といってお寺の鐘をつき、ご先祖迎えの準備をする行事があります。京都市東山区の六道珍皇寺(ろくどうちんのうじ)では、かつて平安の歌人・小野篁(おののたかむら)が境内の井戸から冥界(あの世)に通ったという伝説があり、そこにある「迎え鐘」を一般参拝者が次々と撞く風景が風物詩となっています。
沖縄のお盆といえばエイサーです。エイサーは沖縄各地の若者たちが旧盆の夜に太鼓を打ち鳴らし、三線や歌に合わせて踊り歩く伝統芸能で、先祖の霊を歓待し、送り出すためのものとされています。旧盆の時期になると、沖縄の集落では色鮮やかな衣装を身に付けた青年団が勇壮な踊りを披露し、地域総出でご先祖を迎え送る光景が見られます。近年ではエイサーは観光資源としても注目され、沖縄全島エイサー祭りなど大規模なイベントも開催されています。
そのほか、関西の一部ではお盆明けの8月23日頃に子ども向けの地蔵盆という行事を行う地域もあります。地蔵盆は町内の地蔵尊を祀り、子ども達の健やかな成長を祈るお祭りで、お盆と近接した時期に行われるため混同されることもありますが、趣旨としては子供の守護仏であるお地蔵さんのお祭りです。ただ、迎え火・送り火や盆踊りなどが子ども向けにアレンジされ、地域コミュニティの親睦行事にもなっており、「お盆+夏祭り」的な色彩が強いとも言えます。
このように、お盆行事は全国共通の部分と地域独自の部分が混ざり合って受け継がれてきました。どの地域でも共通するのは「この時期にご先祖様が帰ってくる」という信仰であり、それを迎える方法が土地の文化や歴史によって様々に彩られているということです。ご自分の郷里や現住所のお盆行事に目を向けてみると、新たな発見や郷土愛が深まるかもしれません。
現代のお盆の過ごし方 – 帰省・家庭での供養・簡略化の傾向

現代の日本社会においても、お盆は家族の絆を再確認する大切な時間として位置付けられています。ただ、その過ごし方は昔と比べて少しずつ変化してきている部分もあります。
帰省と家族団欒: 伝統的にお盆は帰省シーズンです。都市部で働く人々が一斉に故郷へ帰るため、新幹線や高速道路、空港は毎年お盆前後に「帰省ラッシュ」と呼ばれる混雑に見舞われます。多くの企業が8月中旬に数日間の夏季休暇(いわゆるお盆休み)を設けるのも、江戸時代の藪入り(奉公人が正月と盆に休暇をもらい実家に帰った風習)が現代にも引き継がれたものとされています。
このように、このように、家族が集まり、お墓参りや仏壇に手を合わせるためのまとまった休みが社会的に定着していることから、お盆は今なお日本人の生活行事として根づいています。特にご高齢の親御さんにとって、お盆に子や孫が帰ってくることは何よりの楽しみでしょう。親族一同で集まり、ご先祖様を迎えるとともに、久しぶりの団欒に花が咲く――お盆は現世の家族にとっても大切な再会の時間なのです。
家庭での供養と行事
現代では、昔のように形式にこだわらず、それぞれの家庭に合った形でお盆を過ごすのが一般的になっています。
たとえば、お仏壇がある家では、あらかじめ掃除をして、新しいお花やお線香を備えることが多いようです。お盆用の飾りも、最近はスーパーやホームセンターにお盆コーナーが設けられており、ミニサイズの精霊馬セットや提灯、蚊取り線香、造花のホオズキ、そうめんや果物の詰め合わせなど一式が手軽に購入可能です。仏具メーカーや専門店も初心者向けに盆飾りセットを販売しているので、詳しい知識がなくても説明書通りに飾れば形が整うよう工夫されています。インターネットやパンフレットで情報収集しながら準備する若い世代も増えています。
「何をどうしていいか分からない」と悩むより、こうした既製品の力を借りて粛々と行うのも現代流のお盆の過ごし方と言えるでしょう。大切なのは気持ちですから、形にとらわれすぎず、しかしご先祖様第一の心で準備することが肝心です。
簡略化・合理化の傾向
都市化や核家族化が進む現代では、伝統的なお盆行事をすべて行うのが難しい家庭も少なくありません。
たとえば、一戸建てが少ない都市部では、迎え火や送り火を実際に焚く家はほとんど見られなくなっています。その代わり、安全に配慮したカメヤマローソク社の迎え火用ローソクのようなアイテムを使ったり、迎え火自体を省略して仏壇に手を合わせるだけにする家庭もあります。また、精霊棚についても、広い座敷がないマンションなどでは大きな祭壇を設けるのが難しいため、テーブルの上に小さな盆飾りを並べる程度にとどめることが多いようです。
こうした需要に応えて、厚紙で簡易組み立てできる段ボール製の盆棚や、必要最低限の飾りを詰め合わせた「らくらくお盆セット」という商品も登場しています。セットには敷物のゴザやミニ提灯、精霊馬用のナス・キュウリ、まこも(莚)、お供えの乾物や器まで一通り入っており、届いたらすぐ飾れる便利な商品です。まさに現代のライフスタイルに合わせた合理的なお盆準備と言えるでしょう。
また、お墓が遠方にあって簡単に行けない場合、近年はお墓参り代行サービスやオンライン墓参りなども話題になりました。コロナ禍では、帰省や集まりを控えた家庭も多く、自宅でリモートでお坊さんに読経してもらったり、各自が離れた場所で同時刻に手を合わせたりと、新しい形の供養も模索されました。
世情に応じてお盆のあり方も変わりつつありますが、「ご先祖様を思う心」だけは変わりません。たとえ形式や手順を簡略化しても、心を込めて感謝し故人を偲ぶというお盆の本質はしっかりと受け継いでいきたいものです。
お盆の準備と関連するもの – 何を用意すればいい?

ここで改めて、お盆を迎えるにあたって一般的に準備するものやお供えについてまとめてみましょう。初めてお盆を経験する方や、毎年なんとなくやっているけれど改めて確認したいという方の参考になればと思います。
-
お仏壇の掃除
お盆前に仏壇や位牌周りをきれいに掃除します。普段なかなか掃除しにくい仏具も、この機会に磨き上げましょう。また、仏壇がない場合でも写真や遺影の周りを整え、故人を迎えるスペースを清潔にしておきます。お墓参りに行く予定の方は、墓所の掃除道具(ほうきや雑巾、柄杓など)も準備しておくと良いでしょう。 -
精霊棚・盆飾り
仏壇のある家では、お盆の時期に盆棚(精霊棚)を仏壇の前に設けるか、仏壇の内部をお盆仕様に飾り付けます。具体的には、盆棚用の台がなければ座卓などで代用し、その上にゴザや白布を敷いて、お位牌を仏壇から移して安置します。周囲に盆提灯を配置し、精霊馬(ナスとキュウリの牛馬)を作って供えます。さらに、お膳立てとして精進料理のミニ御膳、季節の野菜・果物、お菓子、故人の好物、団子や重ね餅などを供えます。地域によっては、そうめんや昆布、ほおずき、ミソハギ(盆花)などを用意する場合もあります。
飾り付けの正式な手順は地域や宗派で異なりますが、大切なのは「ご先祖様をもてなす」気持ちで華やかにお迎えすることです。生花をお供えするときは、トゲのあるバラなどは避け、日持ちのする菊やユリ、季節の花を選ぶのがよいでしょう。飾り付けはお盆初日の朝までに済ませるのが理想とされていますが、忙しい場合は当日に準備しても当日に準備しても構いません。 -
迎え火・送り火の道具
迎え火には上述の麻がら(乾燥させた麻の茎)や焙烙皿、マッチやライターなどを用意します。最近はホームセンターで「おがら」「焙烙」のセットが手に入ります。送り火には迎え火と同じものを使うほか、13日に使った提灯や精霊馬を送り火で一緒に燃やす地域もあります。ただし無理に燃やさず、後述するようにお盆明けに処分しても問題ありません。 -
お供え物(供物)
具体的なお供え物は各家庭で様々ですが、一般的によく供えられるものようなものが挙げられます。果物(季節の梨・葡萄・桃など)、野菜(キュウリ・ナス・トウモロコシなど夏野菜)、米や餅(新米や精白米、重ね団子)、お菓子(落雁や故人の好きだった和洋菓子)、飲み物(故人が好んだお酒やジュース、お茶)など。地域によっては、そうめんや昆布、ホオズキ。
お供えには「これでなくてはいけない」という決まりはありませんので、故人やご先祖様が好きだったものを選ぶと良いでしょう。最近では、ミニジョッキに入ったビール型のローソクや、お寿司やラーメンの食品サンプルのようなおもしろキャンドルも市販されています。お坊さんによっては「あまりふざけるものではない」と苦言を呈されるかもしれませんが、遺族にとっては「○○さんはビールが大好きだったね」と思い出しながら用意する時間そのものが供養になります。ご先祖様ファーストの心で選びましょう。
-
御仏前や御供(おそなえ)のやりとり
お盆に親戚や近所の家へ挨拶に伺う際には、手土産を持参するのが一般的です。定番の品としては、線香やロウソクのセット、乾麺の素麺、お菓子の詰め合わせなどがあります。のし紙には「御供」「御仏前」などと書きます(初盆の家には「新盆御見舞」とする地域も)。
訪問先でこうしたお供えをいただいた場合、後日半返し〜1/3返し程度の品物を送るのがマナーです。品物でなく現金(御仏前)を包まれることもありますが、その場合も金額の半額程度を目安にお返しします。地域によってはお盆の時期にお中元を兼ねてやりとりする場合もありますが、いずれにせよ感謝の気持ちを込めてやりとりすることが大切ですね。 -
後片付け
お盆が終わったら、供えた食べ物のうち生ものや傷みやすいものは下げて家族でいただき、残ったものや飾り類は処分します。処分の際は半紙や白紙に包んで塩で清め、可燃ごみ等に出します。精霊馬なども同様です。盆提灯や盆棚、器類など再利用できるものは綺麗に掃除してから箱に納め、湿気に注意して保管します。提灯の火袋(紙の部分)は意外と傷みやすいので、破れなどないか確認しましょう。
こうした後片付けを速やかに行うのも、実は年中行事の約束事です。お迎えの準備には時間をかけても、送り出した後の片付けは手早く済ませ、新しい日常に切り替えていく——寂しいようですが、これも古くからの知恵なのです。
以上がお盆準備の大まかな内容です。もちろん地域や家によって細かな違いはありますが、「ご先祖様をお迎えするための掃除と飾り付け」「心のこもったお供え」「送り出しと後始末」という流れは共通しています。難しく感じるかもしれませんが、いざ準備を始めると「去年もこんな風に飾ったな」「これは祖父が好きだったお菓子だっけ」などと記憶や会話がよみがえり、自然と心が温まるものですよ。
お盆に込める思い – 故人を偲び、今を生きる私たちへ

お盆は形の上ではご先祖様や故人をお迎えし供養する行事ですが、その根底にあるのは「家族の絆」と「感謝の心」です。私たちが今ここにいるのは、代々のご先祖が命を繋いできてくれたおかげです。お盆は一年に一度、そのご先祖様に改めて想いを寄せ、「ありがとうございます」と手を合わせる大切な機会なのです。
仏教的に言えば、お盆は「亡き人に報恩感謝し、供養する場」であると同時に、「亡き人から自分自身が生かされていることに気付く場」でもあります。先に旅立った人を偲ぶことで、生きている私たちは自分の命の尊さや有限であることに想いを巡らせます。浄土真宗では、亡き人は迷える私たちを仏の教えへ導いてくれる諸仏であると捉え、「亡き人を偲びつつ、自らも真実の生き方を問い直す時間」にすることがお盆の意義だと説いています。宗派によって考え方は様々ですが、いずれもお盆を通じて命のつながりや人として大切にすべきことに思い至るという点では共通しているでしょう。
年配の方の中には、幼い頃に両親や祖父母に連れられて提灯行列をした思い出や、家族総出で迎え火を焚いた情景を覚えている方も多いことでしょう。当時は意味もよく分からずにやっていた行事も、今振り返れば「そうか、自分もこうして先祖を迎える一員だったのだ」と感慨深く思えるかもしれません。ぜひこのお盆に、若い世代へ当時の思い出話を聞かせてあげてください。それが何よりの心の伝承となり、お盆の文化が次の世代へ受け継がれていくことでしょう。
お盆の期間中は、仏壇に手を合わせて家族で故人の思い出を語り合ったり、お墓参りで子や孫にご先祖様の話をしたりする良い機会です。「昔おじいちゃんはね…」「おばあちゃんはこういう人でね…」といったエピソードを語ることで、亡き人の存在が家族の記憶に生き生きと蘇ります。そうした時間を共有すること自体が、何よりの供養であり家族の絆を深めることになるでしょう。
最後に――お盆は決して悲しい行事ではありません。懐かしい人々が年に一度帰ってきて、共に過ごす温かいひとときでもあります。提灯の灯りや線香の香り、団扇で仰ぐ夜風、そして家族の笑い声。すべてが揃って、ご先祖様もきっと微笑みながら皆さんと過ごしていることでしょう。お盆を迎える心構えはただ一つ、「ようこそお帰りなさい。そしていつも見守ってくれてありがとう」という素直な気持ちです。形式にとらわれすぎず、ご先祖様と自分たちの心が通うひとときを大切に過ごしましょう。それがお盆の本当の意義であり、先祖を敬い、自らの命を見つめ直す尊い時間となるはずです。