目次
喪中とは何か?喪中ハガキを出す理由
「喪中」とは、親族など身近な方が亡くなってから一周忌までの約1年間、お祝い事を控える期間のことです。特にお正月に送る年賀状は新年を祝うためのものなので、喪中の間は出さないのがマナーとされています。そのため、自分が喪中で年賀状を遠慮する場合、代わりに「年賀欠礼状(喪中ハガキ)」を送って相手にお知らせします。
喪中ハガキを出す理由は、「こちらは喪中のため新年の挨拶ができない」ことを事前に知らせるためです。相手が年賀状の準備を始める前に伝えておけば、相手は喪中の人へ年賀状を出すことを避けられます。これは相手の手間を減らすだけでなく、喪中であるあなた自身も、新年のお祝い事を控えている旨をきちんと伝える思いやりにもなります。
なお、喪中の人に対してはこちらからも年賀状を出してはいけません。もし知人から喪中ハガキが届いた場合は、年賀状の代わりに「寒中見舞い」(後述)を出すのが一般的です。
※喪中については、こちらの記事をご参考ください。
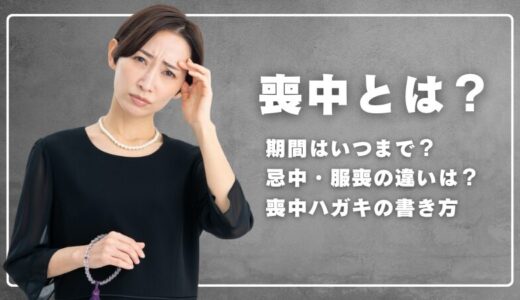 2025年版・喪中とは何か?期間はいつまで?忌中・服喪の違いとマナーを徹底解説
2025年版・喪中とは何か?期間はいつまで?忌中・服喪の違いとマナーを徹底解説
喪中ハガキに書くべき内容
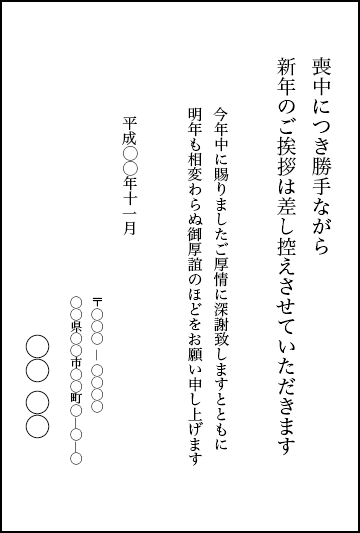
喪中ハガキ(年賀欠礼状)には、以下のような内容を盛り込むのが基本です。
年賀欠礼の挨拶
自分が喪に服しているため、新年の挨拶を控えさせていただく旨を伝えます。例えば「喪中につき新年のご挨拶を失礼させていただきます」などの文言です。これにより、年賀状を出さない理由が喪中であることが明確になります。
故人に関する情報(必要に応じて)
差出人と故人との続柄(例:「父 ○○ が…」)や、亡くなった日付、葬儀を行った日付など。特に家族葬や密葬などでまだ周囲に訃報を知らせていない場合は、喪中ハガキで故人の詳細を伝えても差し支えありません。すでに訃報連絡が行き届いている場合は、これらの詳細は簡略にしても構いません。
お礼とお願いの挨拶
喪中ハガキでは新年の挨拶自体は控えますが、「昨年中にお世話になったお礼」や「来年以降も変わらぬお付き合いをお願いします」といった感謝とお願いの言葉を添えるのが一般的です。例として「本年中に賜りましたご厚情に深謝申し上げます」「明年も変わらぬご交誼のほどよろしくお願い申し上げます」等の定型表現があります。堅苦しく感じるかもしれませんが、日頃の感謝と今後の変わらぬ関係を願う気持ちを伝える大切な一文です。
以上が喪中ハガキの主な内容です。文章全体としては丁寧で慎ましい表現を心がけ、年賀状を出せないお詫びと感謝の気持ちが伝わる文面にしましょう。
喪中ハガキに書いてはいけない内容
喪中ハガキはあくまで「新年のお祝いを辞退するお知らせ」です。そのため、お祝いごとに関する言葉や、新年を寿ぐような表現は一切書かないように注意しましょう。具体的には「おめでとうございます」「賀正」「年賀」「お慶び」といった新年を祝う文言はNGワードです。これらを入れてしまうと喪中ハガキの趣旨に反してしまいます。
また、近況報告や個人的な連絡事項など、年賀欠礼の挨拶以外の内容も書いてはいけません。喪中ハガキはあくまでフォーマルな挨拶状です。ついでに最近の出来事を書きたくなるかもしれませんが、私的なメッセージは控えましょう。相手への気遣いと礼儀を第一に、内容は必要最低限に留めるのがマナーです。
喪中ハガキを出すタイミング。いつ出す?
喪中ハガキは相手の手元に11月中から遅くとも12月初旬までに届くよう投函するのが理想です。相手が年賀状の準備を始める前に喪中であることを知らせる必要があるためで、一般的には11月中には投函を済ませる方が多いです。12月も中旬以降になると相手が年賀状を書いてしまったり、郵便も年末で混み合ったりしますので、できるだけ早めに出しましょう。
万が一、12月中旬以降になってから不幸があった場合や喪中ハガキを出しそびれた場合は、無理に年内に出そうとせず、お正月明けに「寒中見舞い」を出す方法があります(寒中見舞いについては後の章で解説します)。本来は喪中はがきで年内にお知らせするのが望ましいですが、タイミングを逃した場合は焦らず寒中見舞いで丁寧に事情を伝えましょう。
喪中ハガキが買える場所

郵便局には喪中ハガキ専用のハガキは販売されていません。一般には、通常の官製はがき(郵便局が販売する郵便はがき)を利用して喪中の挨拶状を作成します。とはいえ、派手でない落ち着いたデザインの官製はがきが別途販売されており、それが喪中ハガキによく使われています。代表的なのが胡蝶蘭の切手印刷が入った郵便はがきです。胡蝶蘭の絵柄は上品で控えめな印象のため、喪中ハガキや寒中見舞いに利用されることが多いデザインです。
※この胡蝶蘭はがきはあくまで通常の郵便はがきの一種であり、喪中専用というわけではありません。
はがきを入手したら、自宅のプリンターで印刷したり、手書きで宛名・文面を書き込んで作成することができます。パソコン用の喪中ハガキ作成ソフトや無料テンプレートなども利用すれば、自作でもそれなりに綺麗な喪中ハガキを準備できるでしょう。ただし、喪中はがきは出す枚数が多くなりがちで、しかも早めの準備・投函が必要です。枚数が多い場合や自分で印刷・宛名書きをする時間がない場合は、次に紹介する便利な印刷サービスを活用すると負担が軽減できます。
※Amazonなどには私製の喪中はがきが販売されています。→Amazonで確認する
便利な喪中ハガキ印刷サービス【2025年最新】
最近では郵便局や民間各社から、喪中ハガキを手軽に作成できる印刷サービスが提供されています。こうしたサービスを利用すると、豊富なデザインテンプレートから選び、差出人情報や挨拶文を入力するだけで、完成した喪中ハガキを自宅まで届けてくれるので非常に便利です。サービスによっては宛名印刷や、そのまま投函(発送代行)まで行ってくれるところもあります。ここでは2025年時点で利用できる主な喪中ハガキ印刷サービス(日本郵便、挨拶状ドットコム、大手コンビニ各社)について、サービス内容や価格、宛名印刷・発送代行の有無、割引情報などをまとめます。
日本郵便(郵便局)の喪中ハガキ印刷サービス

ハガキ印刷といえばまず思い浮かぶのが郵便局でしょう。日本郵便では年賀状や名刺なども含めた「郵便局の総合印刷サービス」として喪中ハガキの印刷も行っています。
特徴
主な特徴は次のとおりです。
-
文例が豊富:用途に合わせた定型文例があらかじめ用意されており、自分で一から文面を考えなくても安心です。
-
レイアウト自由編集:レイアウトや文章の内容も自由に編集可能なので、必要に応じて細かな調整もできます。
-
仕上がりイメージ確認:注文前に仕上がりのプレビューを画面で確認できるため、誤字やレイアウト崩れもチェックできます。
-
故人2名まで対応:喪中ハガキには通常、同一年内に亡くなった方を連名で2名まで記載することが可能です。
-
宛名印刷・投函代行(※会員限定):日本郵便のサイトで会員登録(無料)をすると、宛名印刷やポスト投函代行サービスを利用できます。会員向けの「マイ住所録」に宛先を登録し、基本料1,100円+1枚あたり31円で宛名面も印刷可能です。さらに、宛名印刷したハガキは日本郵便が直接投函(発送)してくれるため、自宅に取り寄せず相手に送ることもできます。この投函代行サービスは追加料金無料で利用できます。
価格
価格は選ぶデザインや枚数によって異なります。おおまかな目安として、最も安いデザインの場合は10枚で約3,460円程度、多くのデザインでは10枚で3,860円程度となっています。高級感のある箔押し仕上げのデザインなどプレミアム仕様の喪中ハガキも用意されており、その場合は10枚で5,040円とかなり高価になります。一般的なデザインであれば上記の通常料金で十分でしょう。
なお、この料金は印刷料金のみで別途はがき代(1枚85円)がかかります。
割引制度
- 会員割引: 会員登録後、ログインして注文すると印刷料金が5%割引になります(一部対象外商品あり)。
- アンケート割引: 注文時に表示されるアンケートに回答すると、102円引きとなります。
- 複数割引: 同時に2件以上の商品を同一のカートで注文すると、印刷代金が5%割引になります(別々のカートでの注文は割引対象外)。
- 追加注文割引(会員限定): マイページの注文履歴から追加注文すると印刷代金が5%割引になります。
- 早期割引(年賀状・喪中はがき・寒中見舞い限定): 特定の期日までの注文で10%割引となります(一部対象外商品あり)。
- リピーター割引(年賀状・喪中はがき・寒中見舞い限定): 過去に同サービスを会員ログインで利用した方が、再びログインして注文すると印刷代金が5%割引となります(ダイレクトメール割引との併用不可)。
- ダイレクトメール割引(年賀状・喪中はがき・寒中見舞い限定): 昨年郵便局窓口で年賀状印刷を注文し、今年度ダイレクトメールを受け取った方が、注文時に番号入力すると214円引きになります(リピーター割引との併用不可)。
- ネットショップ会員割引(年賀状・喪中はがき・寒中見舞い限定): 郵便局のネットショップ会員IDを認証すると、200円引き(税込)となります(会員登録が必要)。
- 年賀先行予約キャンペーン割引: キャンペーンエントリー期間中に申し込んだ方が注文すると、200円引きとなります(エントリー期間は終了)。
- 年賀キャンペーン割引: 特定の期日までに郵便局のプリントサービスで商品を注文すると、年賀状・喪中はがき・寒中見舞いの注文時に自動的に200円引きとなります(キャンペーン期間は終了)。
おたより本舗の喪中ハガキ印刷サービス

![]()
おたより本舗は、喪中はがきや年賀状印刷に特化したネット印刷サービスです。年賀状印刷のネット通販受注件数で5年連続全国1位の人気サイトで、喪中はがきでも28年以上の印刷実績があります。大切な挨拶状を安心して任せられる専門店です。
注文はPC・スマホから簡単に行え、初めての方にも分かりやすい画面設計で操作もスムーズ。平均20分ほどで注文完了し、困ったときはFAQや動画ガイドがあり、メール問い合わせも迅速対応なので初心者でも安心です。
デザインの種類も非常に豊富。喪中はがきは定番から写真入り・趣味を偲ぶデザインまで約400種類、年賀状は業界最大級の850種類以上のテンプレートが揃います。テイストもカジュアル・ユニーク系からフォーマル・ビジネス向けまで幅広く、挨拶文も自由に編集できるので自分らしい一枚に仕上げられます。
価格も非常に良心的でコスパ抜群です。基本料金0円で印刷代+はがき代のみの明朗会計に加え、全国送料無料、宛名印刷も完全無料と他社では有料のオプションが標準サービスで付いてきます。1枚から少量でも注文OK。さらに早期注文なら早割で最大30~40%OFFになるほか、同時注文割引や追加注文割引など割引も充実(併用可)で、使えば使うほどお得です。会員登録すれば翌年以降は会員限定割引(最大20%OFF)も受けられます。
納期の早さもトップクラスで、通常は13時までの注文なら当日中に出荷してもらえます。繁忙期でも素早く届けてもらえるため、「届くのが早い」「仕上がりも綺麗」と口コミ評価も上々です。利用者からの評価が高いことも安心感につながっています。スピード・品質・価格・サポート全てに優れたおたより本舗は、初めてでも安心して利用できるおすすめのサービスです。
ローソンの喪中ハガキ印刷
ローソンでは、ネット注文による喪中はがき印刷サービスを提供しています。マイプリント株式会社のサービスを利用しており、スマートフォンやパソコンから専用サイトにアクセスし、デザインを選択して注文することができます。
宛名印刷にも対応しており、パソコンからCSV形式で住所録を取り込んで一括で宛名面を印刷することができます。
料金の目安はシンプル喪中はがきが50枚4,227円、スタンダード通常はがきタイプで50枚6,116円、ハイグレード私製はがきタイプで50枚8,602円となっています。(印刷代のみ)
投函代行サービスはありません。
ファミリーマートの喪中ハガキ印刷
ファミリーマートでも、ローソンと同様にマイプリント株式会社のサービスを利用しており、スマートフォンやパソコンから専用サイトにアクセスし、デザインを選択して注文することができます。
同じサービスですので、ローソンと画面など注文方法は同じです。
ファミリーマート、ローソンともにオリジナルのデザインも用意しているようです。
料金の目安はファミリーマートオリジナル喪中タイプで50枚5,682円、ハイグレード私製はがきタイプで50枚7,820円となっています。(印刷代のみ)
少しでも価格を抑えたい場合は、ローソンのシンプル喪中はがき(50枚4,227円)を選択するとよいでしょう。
セブンイレブン
セブン‐イレブンでは、店内のマルチコピー機を利用して、USBメモリーやスマートフォンからデータを送信し、はがきに直接印刷する「はがきプリント」サービスを提供しています。
しかしながら、デザインや宛名印刷は自分で準備する必要があり、セブン-イレブンで喪中はがきを印刷して利用するのは現実的ではありません。
投函代行サービスはありません。
あなたに合った喪中ハガキサービスの選び方
いくつかサービスをご紹介しましたが、「結局どれを使うのが自分にベストなの?」と悩む方も多いでしょう。
上記サービスを比較すると、コンビニ各社のサービスはどうしてもサービスの中途半端さが否めません。(デザインの少なさ、投函代行サービスがないなど)
よって、郵便局のサービスを利用するか、挨拶状ドットコムのような充実したサービスがあるところを選択することをお勧めします。
寒中見舞いも忘れずに:喪中ハガキが間に合わなかった場合は?
最後に、「寒中見舞い(かんちゅうみまい)」について簡単に触れておきます。寒中見舞いとは、本来は松の内(正月飾りを出している期間)明けから立春までの間に出す、寒中の時期の挨拶状のことです。具体的には1月8日頃から立春(2月4日頃)までに出す季節の便りで、相手の健康を気遣う内容などをしたためます。
喪中ハガキを受け取った側は新年の挨拶状として寒中見舞いを返すのが一般的です。例えば友人から「今年は喪中につき…」というハガキが来たら、こちらからは「寒中お見舞い申し上げます。今年もどうぞよろしくお願いいたします」といった寒中見舞いハガキを1月8日以降に出します。こうすることで、喪中の方へ年賀状を出さないマナーを守りつつ、時期をずらして改めて挨拶を交わせます。
また、自分自身が年末ギリギリに不幸があった場合など喪中ハガキが出せなかったケースでは、年が明けてからお世話になった方々に寒中見舞いを出し、喪中であったことを伝える方法があります。文面は喪中ハガキと似た形で、「遅ればせながら○月に◯◯(続柄)○○が他界いたしました。本年の年始のご挨拶をご遠慮させていただきましたことをご容赦ください」などと報告とお詫びを書き添えるとよいでしょう。寒中見舞いは本来は相手を気遣う内容が中心ですが、近年では喪中はがきを出せなかった場合の事後報告兼ご挨拶として用いられることも増えています。
寒中見舞いハガキも喪中ハガキと同様に、自分で作成することもできますし、印刷サービス各社では寒中見舞いデザインを選んで印刷することもできます。出すタイミングは繰り返しになりますが1月8日~2月4日頃までです。この時期を逃すと「余寒見舞い」(立春以降に出す寒中見舞いと同様の便り)となってしまいますので注意しましょう。
※寒中見舞いについてはこちらの記事をご参考ください。
 喪中ハガキをもらったら年賀状ではなく「寒中見舞い」を返そう
喪中ハガキをもらったら年賀状ではなく「寒中見舞い」を返そう
まとめ
喪中ハガキの基礎知識から最新のサービス情報、寒中見舞いのマナーまでをまとめました。2025年現在、喪中ハガキの準備は郵便局からコンビニ、ネットサービスまで多彩な方法があります。大切なのは、大切な人への思いやりを形にすることです。ぜひ本記事を参考に、負担の少ない方法で早めに喪中ハガキの準備を進めてみてください。この記事がお役に立てましたら幸いです。





