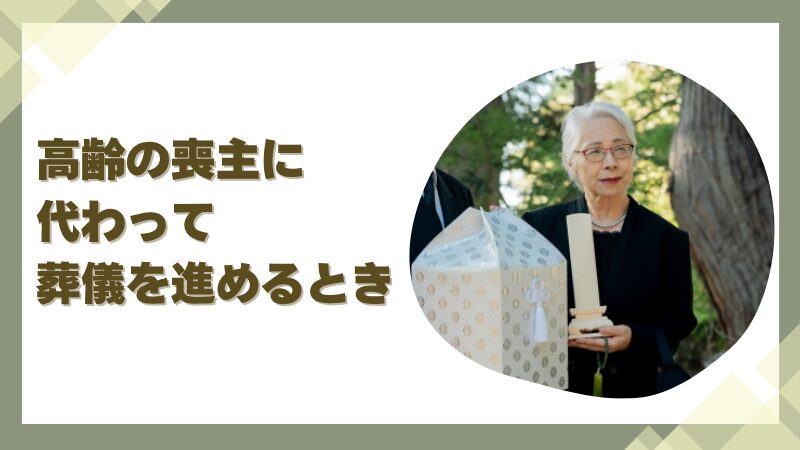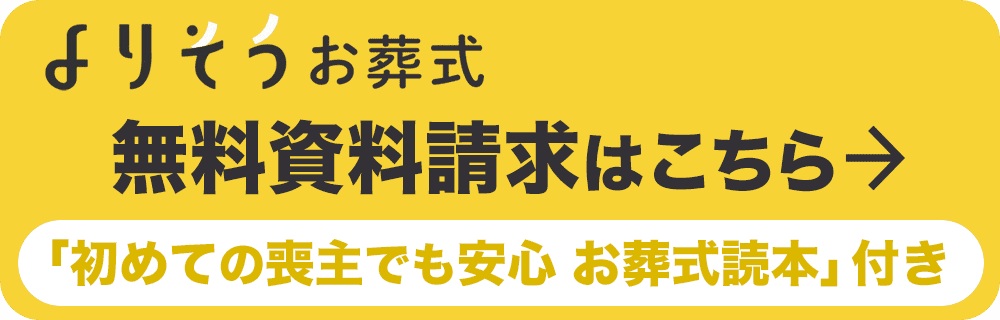葬儀では、故人に最も近い遺族が「喪主」を務めるのが一般的です。多くの場合、配偶者や長男・長女が選ばれます。しかし、配偶者が高齢である場合、喪主の役割を果たすのが難しいこともあります。体力的な問題に加え、認知症や病気の影響で会葬者への挨拶が困難なケースも見られます。
こうした状況で有効なのが「代理喪主」という考え方です。喪主の名義は変えず、実際の進行や挨拶を別の家族が担当することで、葬儀を円滑に進めることができます。
本記事では、代理喪主の立て方や挨拶の工夫を中心に、高齢の喪主を支える方法を具体的に解説します。
目次
高齢の喪主にのしかかる負担の実情

喪主という役割には、思っている以上に多くの責任が伴います。挨拶や進行だけでなく、葬儀社とのやり取り・参列者への対応・式後の手配まで、さまざまな対応が求められます。高齢の方がそのすべてを担うのは、体力的にも精神的にも大きな負担です。
ここでは喪主に求められる主な役割と、高齢者にとっての負担の実情について解説します。
長時間の参列や挨拶が負担に
喪主は葬儀の進行を担う重要な存在ですが、高齢の方にとっては負担が大きくなりがちです。
葬儀当日は、早朝からの準備や通夜・告別式への出席、参列者の対応などで長時間立ちっぱなしになることも珍しくありません。とくに80代以上になると、長時間の着席や立ち話そのものが体力的に難しくなることが多くなります。
日本老年医学会の調査[1]によると、要支援・要介護認定を受けている高齢者の割合は85歳以上で58.7%にのぼります。喪主がそういった状態である場合、葬儀全体を支えるのは非常に大きな負担となります。
喪主は準備から進行までを担う存在
喪主は当日の挨拶や式中の立ち振る舞いだけでなく、葬儀全体の準備と進行に関わる重要な存在です。判断を求められる場面は多く、体力や集中力が必要になります。
以下は、喪主が担う代表的な役割です。
- 葬儀社や寺院との打ち合わせ
- 親族や参列者への連絡
- 通夜・葬儀当日の参列と対応
- 式中の挨拶(通夜・告別式)
- 香典返しや会葬御礼の手配
- 火葬場・埋葬などの実務確認
これらを短期間でこなすには、相当な体力と気力が必要です。高齢の喪主がすべてを担うのではなく、家族で手分けしてサポートすることが理想です。
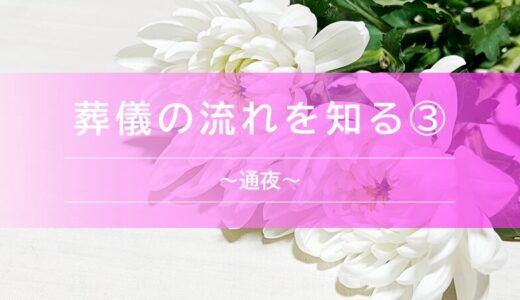 葬儀の流れを知る③〜通夜〜
葬儀の流れを知る③〜通夜〜
一人で抱え込まず手を借りる判断も
葬儀の準備や進行は、家族で協力することで喪主の負担を大きく減らすことができます。最近では、形式上は喪主のままでも、実際の対応を子どもや親族が担うケースが多く見られます。
たとえば、次のような対応は家族が代行しやすい部分です。
- 式中の進行確認や合図出し
- 会葬礼状や香典返しの手配
- 式後の弔問客への連絡
これらを家族で分担することで、喪主本人の体力的・精神的な負担が大幅に軽くなります。「すべて自分でしなければ」と思い込まず、周囲に頼る判断が、結果として良い葬儀のかたちにつながります。
喪主を支える体制づくりが大切
喪主は形式的な役割以上に、精神的な重圧を伴います。とくに配偶者を亡くした直後であれば、深い悲しみと向き合いながら葬儀の中心に立たなければなりません。
もし体調や年齢を理由に役割を果たせない場合でも、形式上の喪主を保ちつつ、周囲が支える体制をつくることが大切です。周囲が協力をすることで、本人の気持ちを尊重しながら、葬儀を滞りなく進めることができます。
高齢の喪主を支えることは、後悔のない見送りを実現する上でも重要なポイントです。
代理喪主を立てるときに気をつけたいこと

高齢や体調の問題で喪主が実務を担うのが難しいとき、家族の中から「代理喪主」を立てるという方法があります。
ただし誰に頼むか、どの範囲を代理するかなど、配慮すべき点も多くあります。とくに親族間で認識のズレがあると、思わぬトラブルにつながることもあるため注意が必要です。
ここでは、代理を頼む際の考え方や注意点をわかりやすく整理します。
代理を任せるのにふさわしい人とは?
代理喪主を立てる場合、形式上は喪主を変更せず、進行や挨拶などを別の家族が担うことになります。誰が適任かはご家庭の事情によりますが、一般的には次のような条件を満たす人が選ばれやすいです。
- 喪主本人と関係が近く、意思疎通がしやすい
- 親族や参列者にとって自然な立場である
- 葬儀の段取りや流れを把握している
- 落ち着いて対応できる精神的な余裕がある
たとえば、長男や長女が代わりに対応するケースが多く見られます。喪主が高齢の配偶者である場合、子ども世代が引き受けることはとくに自然な流れになります。
事前の話し合いでトラブルを防ぐ
代理喪主を立てる場合は、なるべく早い段階で家族や親族と相談しておくことが重要です。「本人の意向を尊重しつつ、無理をさせないようにしたい」という立場を丁寧に説明することで、理解されやすくなります。
また、以下のような点を事前に確認しておくと、当日の混乱を防げます。
- 喪主本人が担う範囲と、代理が行う範囲の明確化
- 式中の挨拶や会葬対応を誰が行うかの確認
- 親族や参列者にどのように伝えるか
「喪主が高齢のため、当日は家族が対応させていただきます」と一言伝えておくだけでも、参列者からの誤解や不満を防げます。
地域や親戚の考え方にも配慮を
地域によっては、喪主は式の中心に立つべきという考え方が強く残っている場合があります。
とくに親戚付き合いが密な地域では、「喪主が表に立たないのは失礼」と受け取られる場合もあります。こうした懸念があるときは、葬儀社の担当者に地域の慣習を相談しておくと、柔らかい伝え方のアドバイスをもらえるでしょう。
また、宗派によっては、読経や儀式の流れにおいて喪主が特定の動作を担う場面もあります。たとえば、位牌を持つ・焼香を最初に行う・僧侶への挨拶をするなどです。こうした場面も代行しても問題がないか、寺院と確認しておくと安心です。
無理なく進めるための準備をしておく
代理喪主を立てる際は、何をどこまで任せるのかあらかじめ明確にしておくことが重要です。本人の気持ちを尊重しつつ、周囲でサポートできる体制を整えておくことで、式当日も落ち着いて対応できます。
また、葬儀社に事情を伝えておけば、進行の流れや挨拶のタイミングなどを柔軟に調整してもらえることが多いです。代理を立てるということは喪主の責任を軽んじるのではなく、よりよい送り方を考える柔軟な判断の一つです
高齢の喪主の挨拶をサポートする工夫

葬儀では、喪主が会葬者に向けて挨拶を行う場面が何度かあります。通夜の冒頭や告別式の終了時など、儀式の中で要所を締める役割を担う重要な場面です。しかし、高齢や病気のために声が出にくい、長く話すのが難しいというケースも少なくありません。
ここでは、挨拶が困難な場合にどのような方法で喪主の気持ちを伝えるか、実例を交えて紹介します。
声が出しづらいときは代読が有効
年齢や体調の影響で、長時間話すことや人前で話すことが難しい方もいます。特に声が通りにくい場合や、途中で息が続かなくなるような状況では、無理に挨拶をさせること自体が喪主にとって大きな負担になります。
このようなときは、あらかじめ用意した文章を別の家族が代読するのが一般的です。「喪主の意向により、ご家族が挨拶を代読いたします」といった説明を一言そえれば、参列者にも自然に受け入れられます。
誰に代読を任せるかは早めに相談を
代読を行う際は、誰が担当するかを事前に決めておくことが大切です。急な指名だと戸惑う人も多いため、以下のような条件をもとに無理のない人選を考えましょう。
- 喪主と近い立場(長男・長女など)である
- 落ち着いて話せるタイプである
- 本人が代読を了承している
挨拶文の内容も、喪主の想いをきちんと共有しておくことで、読み上げる人も気持ちを込めやすくなります。
伝えたい言葉は事前にまとめておく
挨拶の内容は、その場で考えるよりも事前に紙にまとめておくのが安心です。通夜や告別式で求められる挨拶の趣旨は異なるため、場面ごとに簡潔なメッセージを準備しておきましょう。
事前に用意しておくと良いメッセージは、たとえば次のような内容です。
- ご多用の中お越しいただいたことへのお礼
- 故人の生前の感謝の気持ち
- 今後の見守りへのお願いや締めの言葉
短くても十分に気持ちは伝わります。口調や文体は、本人らしい自然な言葉で構いません。
 はじめて喪主を務める方へ|挨拶のポイントと文例
はじめて喪主を務める方へ|挨拶のポイントと文例
形式よりも気持ちが伝わることを大切に
葬儀の挨拶で最も大切なのは、完璧に話すことではなく、感謝の気持ちや心からの言葉が伝わることです。喪主が挨拶できない状況でも、家族が気持ちを代わりに届けることで、式全体が温かい雰囲気になります。
また、葬儀社のスタッフに相談すると、代読のタイミングや流れについてサポートしてもらえる場合があります。負担を減らしながら想いのこもった葬儀を行う工夫のひとつとして、代読はぜひ選択肢に入れておきたい方法です。
高齢の喪主の負担を考えた葬儀形式の選び方

葬儀には一般葬・家族葬・一日葬など、さまざまな形式があります。喪主が高齢の場合、選ぶ形式によって身体的・精神的な負担が大きく変わります。無理のなく葬儀を進めるには、故人や遺族の希望を尊重しつつ、喪主の負担軽減を考慮する必要があります。
この章では、代表的な3つの葬儀形式の特徴と、喪主への影響をわかりやすくご紹介します。
一般葬は参列者対応が多くなる
一般葬は、親族だけでなく故人の友人や知人、地域の関係者などを幅広く招いて行います。通夜と告別式の2日間にわたって行うのが一般的です。
この形式では、喪主は以下のような場面で表に立つことが求められます。
- 通夜・告別式での参列者対応
- 式中の挨拶や僧侶への謝礼
- 香典の受け取りやお礼の手配
- 会葬礼状の準備と手配
参列者が多くなるほど喪主の役割も増えるため、高齢の方には負担が大きくなりやすい形式といえます。
家族葬は柔軟に対応しやすい
家族葬は、親族やごく近しい知人だけで行う小規模な葬儀です。招く人数を抑えることで、喪主への身体的・精神的な負担が軽減されます。挨拶も略式にできることが多く、全体の進行も比較的ゆったりとしています。
以下のような点で、高齢の喪主にも無理なく対応できる形式といえるでしょう。
- 式場の移動や準備が最小限で済む
- 挨拶は略式や代読も可能
- 香典返しや対応も省略・簡略化できる
また、式後は家族だけでゆっくりと過ごすことができ、気持ちの整理がしやすいというメリットもあります。
 初めてでも迷わない!家族葬の流れと費用 丸わかりガイド
初めてでも迷わない!家族葬の流れと費用 丸わかりガイド
一日葬という新しい選択肢も
近年は、通夜を行わずに告別式と火葬を1日で済ませる「一日葬」が増えています。高齢の喪主でも身体的・精神的な負担が少ないため、選択肢のひとつとして注目されています。
鎌倉新書のお葬式に関する全国調査(2024年)[2]によれば、一日葬の実施割合は10.2%と、全体の1割を超えています
 一日葬とは?一般葬・家族葬・直葬との違いから流れ・費用まで徹底解説
一日葬とは?一般葬・家族葬・直葬との違いから流れ・費用まで徹底解説
一日葬の特徴は次の通りです。
- 通夜がないため準備がシンプル
- 式が1日で完結し、高齢者にも負担が少ない
- 式場使用料や人件費を抑えられる
なかでも小さなお葬式が提供する「小さな一日葬」プランは、必要なサービスがあらかじめセットになっており、追加費用の心配が少ないのが魅力です。事前相談にも対応しているため、高齢の喪主や遠方の親族がいても安心して準備を進められます。
ただし、地域や親族によっては略式と受け止められることもあります。選択する場合は事前に関係者に説明し、納得を得ることが望ましいです。
形式に縛られすぎない考え方も大切
葬儀の形式に正解はありません。一般葬だから丁寧、家族葬だから簡略というわけではなく、大切なのは「その家族にとって無理のない送り方」を選ぶことです。
喪主が高齢であれば、式の内容をできるだけシンプルにすることで、進行や挨拶の負担を大きく減らすことができます。葬儀社と相談しながら、喪主の状況や故人の意向にあわせた最適な形式を選びましょう。
高齢の喪主の不安を軽くする工夫

喪主が高齢の場合でも、葬儀を無理なく進めることは十分に可能です。近年はさまざまな葬儀の形式やサポート体制が整っており、喪主の負担を減らしながら、心のこもった送り方ができる選択肢も増えています。
この章では「喪主として何を優先するか」という視点から、葬儀をスムーズに進める考え方やサポートの活用方法についてご紹介します。
無理にすべてを背負わない判断も必要
喪主は形式上、葬儀の中心的な役割を担いますが、すべてを一人でこなす必要はありません。年齢や体力に不安がある場合は、周囲に頼ることが自然です。それは決して責任を放棄することとは異なります。
たとえば、葬儀の対応や挨拶を別の家族が担うことで、喪主自身は儀式の流れに集中できます。精神的にも落ち着いて式に臨むことができるでしょう。
サポート体制を整えることで安心感が生まれる
喪主の負担を減らすには、以下のようなサポート体制を早めに整えておくことが効果的です。
- 葬儀社との事前相談を早めに行う
- 代理喪主の役割分担を家族で明確にする
- 式場への移動や段取りを付き添いと一緒に進める
とくに葬儀社との事前相談は、喪主の体調や希望に合わせた柔軟な段取りをしてもらえる機会になります。
たとえば「小さなお葬式」や「よりそうお葬式![]() 」などでは、事前に喪主の状況を伝えることで、参列者への挨拶や住職への対応なども含めて細やかなサポートを受けられます。
」などでは、事前に喪主の状況を伝えることで、参列者への挨拶や住職への対応なども含めて細やかなサポートを受けられます。
形式よりも気持ちを大切にする
喪主を務めるうえで大切なのは、形式的な役割を完璧に果たすことではなく、故人を悼む気持ちをどう伝えるかという点です。挨拶が代読になっても、葬儀形式が簡略になっても、参列者には気持ちがきちんと伝わるものです。
高齢であるがゆえに、自分に喪主が務まるか不安に感じる方も少なくありません。だからこそ、家族やまわりの人が「できる範囲でいい」と無理なく参加できるよう工夫することが、喪主にとって大きな安心につながります。
支え合いで築く葬儀のかたち

喪主は葬儀の中心に立つだけでなく、参列者の想いを受け止める大切な役割もあります。高齢ですべてを担うことが難しい場合でも、家族の支えや適切な工夫があれば、その場に寄りそうことができます。
形式にとらわれすぎず、「何を大切にしたいのか」という想いを基準に、無理のない方法を選びましょう。それこそが、喪主としての責任を果たせる、もうひとつの自然なかたちです。