地球温暖化への関心が高まる現代、人生の最期を迎えるときも「地球に優しい葬儀をしたい」という声が増えています。従来の葬儀による環境負荷が故人や遺族の環境意識と矛盾する場合もあり、エコ葬儀という選択肢が知られるようになりました。
段ボール製棺・自然葬・植林付きプランなど、環境に配慮しながらも心のこもった弔いを実現する方法が注目を集めています。
目次
エコ葬儀とは?従来の葬儀との違いと取り組み

日頃からエコバッグの利用や節電など、環境に配慮した行動を心がけている人は多いものです。しかし、葬儀における環境負荷についてはあまり意識されていないのが実情ではないでしょうか。
ここでは、環境への負荷をできるだけ抑えながら、大切な人を心を込めて見送る“エコ葬儀”という新しい弔いのかたちについて解説します。
従来の葬儀が環境に与える影響
従来の葬儀で最も環境負荷が大きいのは火葬です。火葬では高温での燃焼により多くのエネルギーを消費し、CO2を排出します。また、木製棺の燃焼時には接着剤や金具から有害物質も発生します。
また、葬儀で使用される花や装飾品のほか、会葬御礼・香典帳などの大量の紙製品()も環境負荷の一因です。参列者の移動によるCO2排出、会食での食材廃棄など、葬儀全体で見ると相当な環境インパクトがあることが分かります。
環境に配慮したエコ葬儀の取り組み
エコ葬儀とは、環境への負荷をできるだけ減らすことを目的とした葬儀スタイルです。実際の取り組みとしては、次のような工夫があります。
-
CO2の排出を抑えた移動手段の利用
-
紙製や竹製など、再生可能素材の棺の使用
-
葬儀で出る廃棄物の削減
-
デジタル香典や電子会葬でのペーパーレス化
-
カーボンオフセットによる排出量の相殺
こうした配慮によって、故人を偲ぶ時間が地球を思いやる行動にもつながっていきます。エコ葬儀は、持続可能な未来を意識した新しい供養の方法のひとつです。
世界と日本で進むエコ葬儀の取り組み
世界各国ではすでにエコ葬儀が実践され始めています。市場調査を行うカナダの企業「Emergen Research」の調査[1]によると、世界のグリーン葬儀市場は2021年に約5億7,000万ドル規模に達しています。さらに、2030年までには年平均8.7%のペースで成長し、約12億ドルを超えると予測されています。
また、60.5%の人が「環境にやさしい葬儀を検討したい」と回答しており、水火葬や堆肥葬といった新しい技術の開発も進んでいます。
日本国内でも今後、環境問題への関心の高まりとともにエコ葬儀への注目が集まっていくでしょう。
環境への配慮は、いまや日常生活だけでなく、人生の最期の場面にも求められる時代になっています。エコ葬儀は故人の生前の環境意識の有無に関わらず、現代を生きる私たちが貢献できる環境配慮の形のひとつです。
時代に合った弔い方を選ぶことで、より心穏やかにお別れの時間を過ごすことができます。
エコ葬儀で選べる具体的な方法とは

ひと口にエコ葬儀といっても、その方法はさまざまです。段ボール製のエコ棺・植林付きプラン・電気自動車の霊柩車・デジタル香典など、従来の葬儀を環境に配慮した形に見直すことが可能です。
ここでは実際に選べる具体的なオプションと、その環境への効果について詳しく解説します。
段ボール製のエコ棺で有害物質を抑制
エコ葬儀を代表するアイテムのひとつが、段ボールで作られた「エコ棺」です。主に間伐材や段ボールを原料としており、火葬時に排出される二酸化炭素が少ないのが特徴です。価格は一般的な合板製の棺とほぼ同じくらいで、費用を抑えながら環境に配慮できます。
従来の合板製棺と比較して使用する木材の量が少なく、接着剤や釘などの金具が不要なことから、火葬時の有害物質の排出を削減できるとされています。強化段ボールで作られているため強度がしっかりしており、見た目も従来の棺と遜色ありません。
現在では全国各地の葬儀社で取り扱いが広がっており、とくに生協系や環境意識の高い葬儀社を中心に導入が進んでいます。
植林付きのエコ棺で環境保護
環境への負荷を減らすだけでなく、前向きに自然へ貢献できるのが「植林付きエコ棺」です。植えられた木が二酸化炭素を吸収し、生態系の保護にもつながることから、地球にやさしい弔いの方法として注目されています。
たとえばウィルライフ株式会社が販売する「エコフィン」シリーズの棺では、棺1つにつき1本の植林を行う取り組みが導入されています。この植林プロジェクトは「エコフィン生命の森」と呼ばれ、モンゴルでの植林活動を通じて温暖化防止と砂漠化防止に貢献しています。
故人の想いが未来へとつながっていく、あたたかな供養のかたちといえるでしょう。
ペーパーレス葬儀で紙を減らす
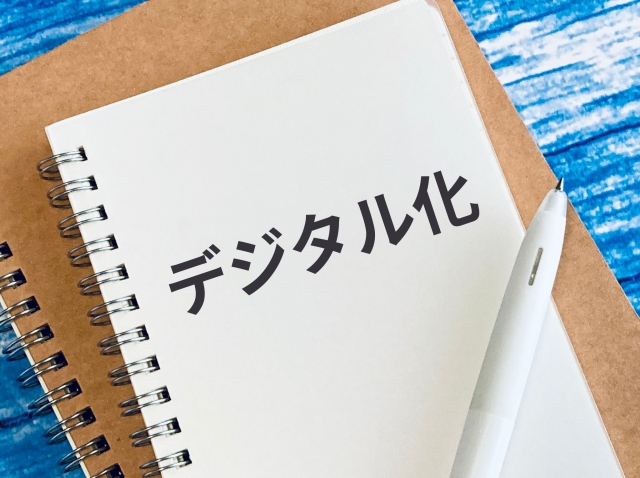
最近では、デジタル技術を活用したペーパーレス葬儀も広がっています。たとえば以下のような方法で、紙の使用を減らすことができます。
- デジタル香典
QRコードやアプリを使った電子決済で香典を受け取る。 - 電子会葬録
参列者の名前やメッセージをデジタルで記録・管理。 - オンライン配信
遠方の家族がリモートで葬儀に参加できる。 - 電子お礼状
メールやSNSで感謝の気持ちを伝える。
これらの工夫により香典袋や案内状、会葬御礼など、大量に使われていた紙資源を大幅に削減できます。
会場・移動もエコを意識
葬儀の会場や移動手段でも、環境に配慮した選択ができます。たとえば、次のような取り組み方があります。
電気自動車の霊柩車を使うことで、移動時のCO2排出を大幅に削減できます。
地域で栽培された花や装飾材を使用することで、輸送による環境負荷を削減できます。季節の花を使うことで、故人と自然とのつながりも表現できます。
ドライアイスを使わずに専用のフリージングパッドを使用することで、CO2の排出を抑えられます。
エコ葬儀の取り組みは、個別に見ると小さな工夫に思えるかもしれません。しかし、それらを組み合わせることで、従来の葬儀と比べて大幅な環境負荷削減へとつながります。
何より大切なのは、こうした取り組みによって社会全体に環境保護への意識が広がっていくことでしょう。
樹木葬・散骨による環境保護

樹木葬や海洋散骨は、「自然に還る」という想いを叶える環境に優しい葬儀のかたちとして関心が高まっています。この章では、それぞれの特徴や環境への効果、法的な注意点、費用や手続きについて解説します。
樹木葬とは?木々に見守られて眠る新しいかたち
樹木葬とは墓石の代わりに樹木を墓標とし、遺骨を自然に還す埋葬方法です。遺骨は土に還され、木の根の栄養として取り込まれ、自然の循環の中に生き続けます。
墓石を建てる必要がないため、一般的なお墓よりも費用を抑えられるのも大きな利点です。近年は都市部にも専用の霊園が増えており、後継者の問題を抱える家庭にも選ばれやすくなっています。
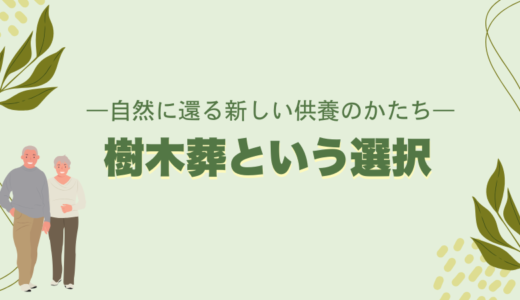 樹木葬という選択 ―自然に還る新しい供養のかたち―
樹木葬という選択 ―自然に還る新しい供養のかたち―
海洋散骨とは?海と共に生きる自然葬
海洋散骨は、遺灰を海に撒くことで自然に還す埋葬方法です。正しく行えば環境への負荷が非常に少なく、近年人気が高まっています。
主な環境への配慮として、以下のような工夫がされています。
遺灰が必要以上に広がらないよう配慮
茎や葉は除き、自然に還りやすくする
環境汚染防止のため禁止
現在、日本では海洋散骨を直接禁止する法律はありませんが、厚生労働省が定めた「散骨に関するガイドライン(PDF)により、海岸から十分に離れた沖合で行うことが推奨されています。また、法的な事前許可は不要ですが、漁業権や観光業への配慮、周辺住民への配慮が必要です。
そのため、実施の際は専門の業者に依頼するのが安心です。
 お墓の代わりに選ぶ「散骨」とは?種類・費用・メリット・デメリット・注意点
お墓の代わりに選ぶ「散骨」とは?種類・費用・メリット・デメリット・注意点
樹木葬・海洋散骨にかかる費用と手続き
樹木葬や海洋散骨といった自然回帰型の埋葬を選ぶ際は、以下のような費用や手続きが必要です。
- 費用相場
30万円〜100万円程度 - 手続き
まず霊園を選び、希望の区画で契約を結びます。埋葬許可証などの必要書類を準備し、指定日に遺骨を埋葬します。 - 注意点
霊園によって管理費が年間1〜3万円ほどかかる。
- 費用相場
20万円〜50万円程度 - 手続き
専門業者に依頼して遺骨を粉骨した後、沖合の海域で散骨を行います。許可申請は不要です。 - 注意点
指定海域での実施や地域住民への配慮が必要。
手続きについてさらに詳しく知りたい方は、樹木葬や散骨を扱う専門業者に相談することをお勧めします。
自然回帰型の埋葬は、ただ環境に優しいというだけでなく、生と死のつながりを感じる新しい死生観を与えてくれます。樹木葬では故人の栄養が木々の成長を支え、海洋散骨では海の生態系の一部となります。残された家族にとっても「故人が自然の中で生き続ける」ということは、大きな慰めとなるでしょう。
エコ葬儀の準備と葬儀社選びのポイント

エコ葬儀に興味を持っても、実際にどう準備を進めればいいのか、誰に相談すればよいのか迷ってしまう方も多いでしょう。この章では、エコ葬儀をスムーズに実現するための事前準備や家族への説明、葬儀社の選び方のポイントをわかりやすくまとめます。
家族や親族の理解を得る方法
エコ葬儀を選ぶときに大切なのが、家族や親族の理解です。特に年配のご家族の中には、昔ながらの葬儀の形式にこだわる方もいるかもしれません。
まずは、エコ葬儀を選ぶ理由や思いを丁寧に伝えましょう。一方的に決めつけるのではなく、相手の価値観にも耳を傾ける姿勢が大切です。時間をかけてじっくりと話し合うことで、皆が納得できるかたちに近づけます。
生前に備えておきたい3つの準備
エコ葬儀をスムーズに進めるためには、生前の準備がとても重要です。元気なうちに次のような準備をしておくと、万が一のときも慌てずに対応できます。
- エンディングノートの活用
環境への配慮や希望する葬儀スタイルなどをエンディングノートに記しておくことで、家族も迷わずに判断できます。 - 事前相談の活用
最近では多くの葬儀社が「事前相談」を受け付けています。希望に合うプランの提案や費用の見積もり、説明用の資料準備までサポートしてくれます。 - 関連サービスとの連携
将来的にお墓の管理が困難になる可能性がある方は、墓じまいについてもあわせて検討することをお勧めします。永代供養付きの樹木葬なら、環境への配慮をしながらお墓の後継者問題も解決可能です。
樹木葬を検討している方で、遺族のお墓の管理負担をなるべく減らしたい場合は、永代供養付きの霊園を選ぶのがおすすめです。
たとえば「アンカレッジの樹木葬![]() 」ならアクセスしやすい立地の霊園が多く、各お寺の住職が永代にわたり供養してくれます。自然に囲まれた静かな環境も魅力です。
」ならアクセスしやすい立地の霊園が多く、各お寺の住職が永代にわたり供養してくれます。自然に囲まれた静かな環境も魅力です。
また、所有しているお墓の後継者がおらず「墓じまい」を考えている方は、「わたしたちの墓じまい![]() 」などの離檀代行サービスを利用するのもひとつの方法です。肉体的にも精神的にも負担の大きいお寺との交渉や行政手続きなどを、一括で代行してもらえます。
」などの離檀代行サービスを利用するのもひとつの方法です。肉体的にも精神的にも負担の大きいお寺との交渉や行政手続きなどを、一括で代行してもらえます。

![]()
こうした準備をしておくことで、本人の意思を尊重したエコ葬儀を実現しやすくなります。家族にとっても、迷いや負担を軽減できる大切なステップとなるでしょう。
エコ葬儀の準備は、自分自身や家族の価値観を考え直す機会でもあります。環境への配慮という軸を持つことで、人生の最終段階においても一貫した選択ができ、家族にとっても故人らしい送り方として納得できるものになるでしょう。事前の準備と情報収集をしっかりしておくことで、慌ただしい時期にも落ち着いて適切な判断ができます
エコ葬儀で広がる新しいお別れのかたち

エコ葬儀はただ環境にやさしいだけでなく「どのように生き、どう見送られたいか」を考えるきっかけにもなります。故人の生き方や価値観を反映した葬儀は、残された家族にとっても深い意味を持つ時間になります。
持続可能な社会を目指す中で、葬儀にも環境への配慮を求める声は今後もさらに広がっていくでしょう。エコ葬儀は、次の世代へ「地球を大切にする想い」をつなぐ、あたたかなメッセージでもあります。





