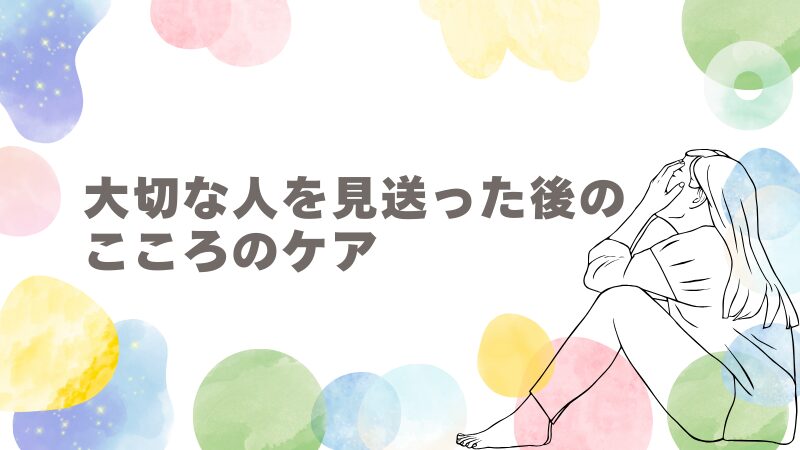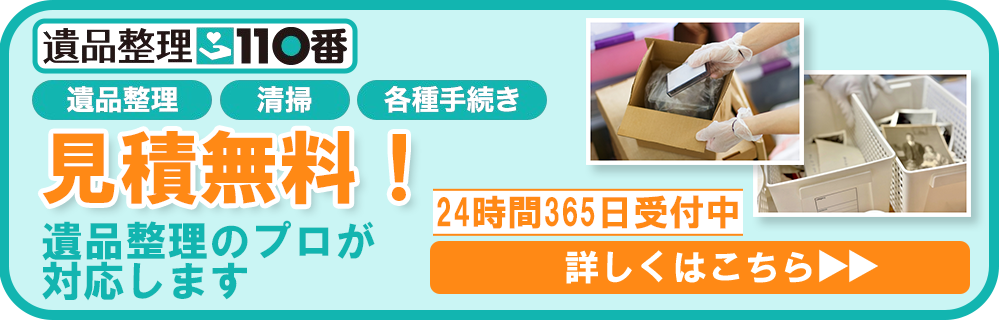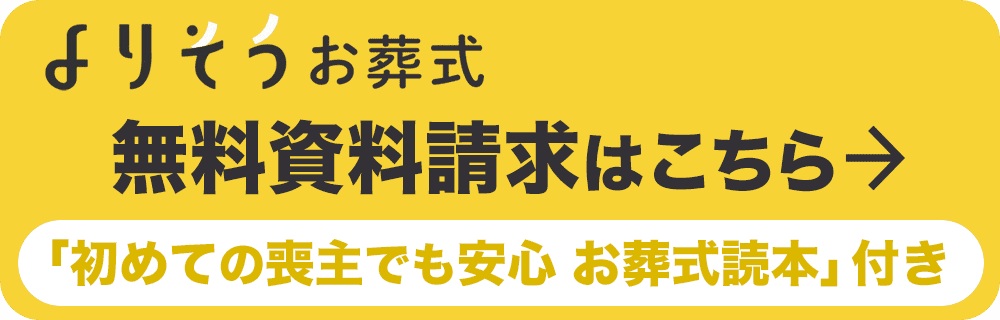家族や親しい人を亡くした後、深い悲しみとともに心身にさまざまな不調が現れることがあります。例えば、夜に眠れなくなったり、食事が喉を通らなかったり、何をする気力も湧かなくなったりするかもしれません。
こうした反応は決して珍しいものではなく、多くの遺族が経験する「悲嘆反応」の一部です。しかし、そのまま放置して日常生活に支障をきたすようになると、深刻なうつ状態へと進行する可能性があります。
本記事では、葬儀後に現れやすい心のサインと対処法について、公的機関のデータや専門家の知見をもとに解説します。心の健康を守るために、早めに自分の状態に気づき適切なケアを行うヒントをお届けします。
目次
悲しみによる心の変化に気づく

大切な人を失った悲しみは、気持ちだけでなく睡眠や食欲、思考力など様々な面に影響を及ぼします。これらは誰にでも起こり得る自然な反応ですが、あまりに長引いたり深刻化したりすると注意が必要です。
まずは「悲嘆反応」と呼ばれる状態について理解し、心のサインに気づくことから始めましょう。
一般的に現れる心身の症状
愛する人との死別は非常に強いストレスであり、多くの遺族に心身の不調が表れます。代表的な症状には次のようなものがあります。
- 睡眠障害
なかなか眠れない、何度も夜中に目が覚める - 食欲不振
食べ物が喉を通らない、体重減少が続く - 意欲の低下
趣味や仕事に手がつかず無気力になる - 感情の不安定
突然涙が出る、イライラや不安感が強まる - 集中力の低下
物事に集中できない、些細なことで注意力が散漫になる
これらは死別後しばらくの間、誰にでも起こり得る反応です。実際、日本の看護研究[1]によれば死別直後の遺族の7~9割が何らかの身体的・精神的健康の不調を抱えるとの報告があります。
たとえば「夜眠れない」「食事を取る気力がない」といった状態は、ごく自然な悲嘆のプロセスの一部です。
深刻なサインを見逃さない
多くの場合、心身の症状は時間とともに和らいでいきますが、中には長期間にわたり続くケースもあります。
強い悲しみが一年以上続く「複雑性悲嘆(プロロンゲッドグリーフ)」になると、生活への影響は深刻です。死別後1年未満では遺族の25~30%、1年以上で10~20%程度が該当するとされています。
つまり、大半の人は徐々に回復に向かうものの、一定数の方は長期にわたり深い悲嘆や抑うつを抱える可能性があります。
とくに次のような症状は、専門家に相談すべきサインです。
- 何も感じられない
- 将来に希望が持てない
- 故人の後を追いたい気持ちがある
心のサインは、頭痛・胃痛・めまい・息苦しさなど、身体症状として現れることもあります。
まずは自分の心と体に起きている変化を客観的に捉え、「今の自分は少し休むべき状態かもしれない」と気づくことが、回復への第一歩です。
悲しみを知ることから始まる癒し
心身に現れる悲嘆のサインは、あなたがそれだけ大切な人を想っている証でもあります。無理に「元気にしなければ」と焦る必要はありません。
ただ、症状が長引いたり強まったりする場合は、自分の心の声に耳を傾けてみてください。「悲しむ自分」を責めずに受け入れることが、回復への出発点です。
次章では、こうしたつらい状態の中で日々を乗り越えるための具体的な対処法について考えていきます。
日常生活を取り戻すための対処法

深い悲しみはすぐには消えませんが、少しずつでも心と体をいたわり、日々の生活リズムを整えることが大切です。十分な睡眠や栄養、周囲からの支えなど、できることから始めてみましょう。
ここでは専門家が推奨するいくつかの対処法を挙げ、それぞれ実践する際のポイントを説明します。
つらいときに試したいセルフケア
悲嘆に暮れる中でも、自分自身でできるケアがあります。以下は心の専門機関が提案するセルフケアの例です。
- 規則正しい睡眠を心がける
寝付きが悪いときでも、毎晩同じ時間に布団に入る習慣を続けます。眠れなくても横になるだけで体は休まります。
軽い音楽やアロマなどリラックスできる環境作りも効果的です。 - 少しでも食事をとる
食欲がなくても水分や栄養補給は大切です。スープや果物など喉を通りやすいものから摂りましょう。
「何も食べられない」日が続く場合は栄養ドリンク等も活用し、徐々に通常の食事に戻していきます。 - できる範囲で体を動かす
家の中の短い散歩や簡単なストレッチでも構いません。軽い運動は気分転換になり、睡眠の質向上にもつながります。
天気の良い日に日光を浴びるだけでも効果があります。 - 気持ちを言葉にする
信頼できる家族や友人に今の気持ちを話してみましょう。
「泣いて迷惑をかけたら…」と遠慮する必要はありません。話すことで心の重荷がいくらか軽くなることがあります。
日記や手紙に書き出すのも有効です。 - 故人を偲ぶ時間を持つ
アルバムを見る、好きだった音楽を一緒に聴くなど、故人との思い出に浸る時間を意識的に作ります。悲しい気持ちを抑え込まず、涙が出るときは我慢せず涙を流しましょう。
これらのセルフケアは、簡単なようでいて悲しみの中では忘れがちです。特に睡眠と食事は心の健康と直結します。たとえ十分に取れなくても、「全く眠れない・食べられない」という事態を避けるだけでも体調は違ってきます。
また、自分の感情を誰かに話すことは大きなストレス軽減になります。
身近に話せる人がいなければ、電話相談やSNS相談など匿名で気持ちを聞いてもらえる公的な窓口もあります。大切なのは、「一人で抱え込まない」ことです。
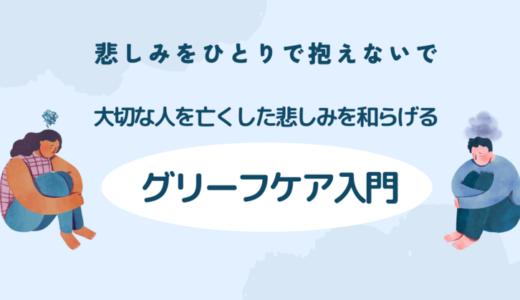 【悲しみをひとりで抱えないで】大切な人を亡くした悲しみを和らげるグリーフケア入門
【悲しみをひとりで抱えないで】大切な人を亡くした悲しみを和らげるグリーフケア入門
周囲の支えを積極的に受け入れる
悲しみに沈んでいるとき、人はつい他人との関わりを避けがちです。「迷惑をかけたくない」「一人にしてほしい」と感じるかもしれません。しかし、周囲の支援を受け入れることは回復への重要な一歩です。ご家族や親しい友人が手伝いを申し出てくれたら、遠慮せず甘えてみましょう。
例えば、「食事を作って持ってきてくれる」「用事に付き添ってくれる」といったサポートは非常に助けになります。また、近年では自治体やNPOが主催するグリーフケアの集いや自助グループも各地で開催されています。同じ経験を持つ遺族同士で話をすることで、孤独感が和らぎ前向きな気持ちが芽生えることもあります。
どうしても人と直接会うのがつらい場合は、オンライン上のコミュニティや掲示板で気持ちを吐露する方法もあります。「自分だけがこんな思いをしているのではない」と知るだけでも、心は少し軽くなるでしょう。
気分転換とリラックスを取り入れる
悲しみの渦中にあっても、短時間でも別のことに意識を向ける時間を持つことは有効です。好きな映画を見る、本を読む、庭いじりをする、お風呂にゆっくり浸かるなど、自分にとって心地よい活動を意識的に取り入れてみてください。
罪悪感を覚える必要はありません。「こんなときに楽しんでは故人に悪いのでは」と感じる方もいますが、故人もきっとあなたの笑顔を望んでいるはずです。
実際、気分転換をすることは精神的エネルギーを充電し、再び向き合う力を養う効果があります。少し元気が出たら、部屋の掃除や短い散歩など達成感を得られる小さな目標をこなしてみるのも良いでしょう。それが自己肯定感の回復につながり、日常生活への復帰を後押しします。
支え合いながら取り戻す日常
つらい状況で自分をケアするのは簡単ではありません。しかし、「休む・頼る・泣く」といった基本的なことを恥じる必要はまったくありません。少しでも安らげる方法は何でも試してみてください。
どんな小さな前進でも自分を褒めつつ、できる範囲で心と体を労わっていきましょう。
次章では、こうしたセルフケアでも改善しない場合に検討すべき専門家の力を借りる方法について説明します。
専門家の力を借りるタイミング

悲しみが長引いたり深刻化したりしていても、「心療内科や精神科に行くほどではない」と思い込んでいませんか?しかし、気持ちの落ち込みが数週間以上続き日常生活に支障を来すようであれば、早めに専門家に相談することが大切です。
ここでは、心のケアのプロである医師やカウンセラーに相談すべきタイミングと、その具体的な手順、公的医療制度について説明します。
相談の目安となるサイン
一般的に、次のようなサインが見られたら受診を検討する目安となります。
- 著しい睡眠障害が続く
布団に入ってもほとんど眠れない日が2週間以上続く、悪夢で何度も目覚めるなどの状態。 - 体重の急激な減少
食事が取れず短期間で極端に痩せてしまった場合。 - 日常生活の維持が困難
出社・外出がままならない、身の回りのこと(入浴や片付け等)もできない状態。 - 強い自己否定や罪悪感
「自分が悪い」「自分には価値がない」といった思考が消えない。 - 死にたい気持ちが出てきた
「消えてしまいたい」「故人のところに行きたい」という気持ちが繰り返し湧く。
これらの症状は、通常の悲嘆の範囲を超えてうつ病の可能性が考えられるサインです。決して「気の持ちよう」の問題ではなく、脳の働きが変調をきたしている可能性があります。特に自殺念慮(死にたいと思う気持ち)が現れた場合は、一刻も早く専門機関に連絡を取りましょう。
厚生労働省の「自殺未遂者および自殺者遺族等へのケアに関する研究」[2]によれば、自死遺族(家族を自殺で亡くした人)はうつ病・不安障害・PTSD・アルコール依存症を発症しやすいと報告されています。
重篤化する前にプロの助けを借りることは、あなた自身と周囲の人生を守るためにも重要です。
心療内科・精神科でできること
心療内科や精神科では医師による診察のもと、状態に応じた治療やサポートが受けられます。具体的には、カウンセリングや抗うつ薬などの薬物療法があります。カウンセリングでは、臨床心理士や精神科医と話をしながら感情を整理し、対処法を学ぶことができます。
薬物療法に対して抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、適切な薬は脳内の化学バランスを整え、つらい症状を和らげる助けになります。風邪をひいたら内科に行くのと同じように、心が風邪をひいたら心療内科に行く、それくらい身近に考えてください。
日本では医療保険の適用により、精神科での診療や薬の費用も3割負担で受けられます。必要に応じ、自立支援医療制度(精神通院医療)などで経済的負担を軽減できる場合もあります。困ったときは経済面も含めて相談してみましょう。
カウンセリングや支援機関の活用
医療機関以外にも、心の専門家に相談できる場があります。
各都道府県には「精神保健福祉センター」が設置されており、こころの健康に関する幅広い相談に応じています。また、市区町村の保健センターでも保健師や心理士による相談窓口があります。
これらは公的なサービスで、多くの場合無料で利用可能です。予約制の面接相談だけでなく、電話相談を実施しているところもあります。
たとえば東京都世田谷区では、区が選定した団体と連携してグリーフ(悲嘆)に関する個別相談を無料で行う事業を実施しています。初回2時間は無料で専門の相談員がお話を聞いてくれるという内容で、必要に応じて適切な医療や他の支援機関につないでもらえる仕組みです。
厚生労働省でも、全国の精神保健福祉センターに関する情報を提供をしています。ぜひお住まいの地域で利用できるサービスがないか、役所や保健所のホームページを調べてみましょう。
専門家はあなたが言葉にできない思いも汲み取り、整理するお手伝いをしてくれます。特にカウンセリングでは、安心できる空間で自由に感情を表現することで、心の傷を癒やす効果が期待できます。
あなたの心の痛みに寄り添うプロがいることを忘れないでください。
専門家を頼る勇気
「これくらい自分で何とかしなければ…」と頑張りすぎていませんか。心の不調は決して意志の弱さではなく、専門的なケアが必要な“こころの病”です。
適切なタイミングで適切な支援を受けることは、決して甘えではなく勇気ある選択です。医師やカウンセラーに相談することで、今の苦しみから抜け出す糸口が見つかるかもしれません。あなたは一人ではありません。遠慮せず、利用できるサポートに手を伸ばしてみてください。
次章では、公的な相談窓口や生活面で役立つサービスの活用法について紹介します。
公的支援や便利なサービスの活用法

自治体や国が提供するメンタルヘルスの相談窓口が全国に整備されています。また、日常生活の負担を減らすためのサービス(遺品整理やお墓の相談など)も存在します。
こうした支援策を上手に利用することで、自分だけでは解決が難しい問題に対処し、心の負担を軽減することができます。必要なときに適切な支援につながるための情報を確認しましょう。
自治体のメンタルヘルス相談窓口
各自治体では、心の悩みに対応する相談窓口を設けています。
代表的なものが「こころの健康相談統一ダイヤル」(0570-064-556)です。これは厚生労働省が紹介する全国共通の電話番号で、発信地域の公的相談機関につながります。
平日の日中を中心に、各都道府県の精神保健福祉センター等で相談員が対応します。相談は無料(通話料のみ自己負担)で、匿名でも可能です。
例えば「夜眠れない」「このままでよいのか不安」など、些細に思える悩みでも遠慮なく電話してみましょう。専門知識を持った職員が話を丁寧に聞き、必要に応じて適切な機関や受診先の案内をしてくれます。
この統一ダイヤル以外にも、多くの市区町村の保健センターで電話・面接相談が可能です。
遺族を支える民間サービス
公的支援と併せて、民間企業や団体が提供するサービスも遺族の負担軽減に役立ちます。
葬儀後には、故人の遺品整理やお墓の管理など、心身が疲れている中で対処しなければならない課題が次々と出てくるものです。こうした実務面で無理をしないためにも、プロの手を借りることを検討してみてください。
例えば、遺品整理の大手専門業者「遺品整理110番![]() 」では、自宅まで来て遺品の仕分けや処分、清掃まで一括して行ってくれます。相談・出張・見積費用はすべて無料で、24時間365日体制で相談を受け付けています。
」では、自宅まで来て遺品の仕分けや処分、清掃まで一括して行ってくれます。相談・出張・見積費用はすべて無料で、24時間365日体制で相談を受け付けています。
実際に利用した人からは次のような声も寄せられています。
![]() 40代女性
40代女性
![]() 50代男性
50代男性
自分では手を付けられない遺品の山も、プロに任せれば数時間で片付くケースもあります。
また、お墓の問題で悩んでいる方には、墓じまい(お墓の撤去や改葬)の代行サービスもあります。
例えば「わたしたちの墓じまい![]() 」は創業2002年の墓じまい専門業者で、離檀交渉から墓石撤去、改葬手続き、永代供養先の紹介まで一括して対応しています。全国15か所に支店を持ち、沖縄を含む全47都道府県に対応可能です。
」は創業2002年の墓じまい専門業者で、離檀交渉から墓石撤去、改葬手続き、永代供養先の紹介まで一括して対応しています。全国15か所に支店を持ち、沖縄を含む全47都道府県に対応可能です。
丁寧かつリーズナブルなサービスで実績を積んでおり、遠方にお墓があって管理が難しい、後継ぎがいないので墓を畳みたいといった相談にものってもらえます。
さらに、葬儀そのものに関して負担を感じている場合は、葬儀サポートサービスを利用する手もあります。
最近は小規模で費用を抑えた葬儀プランを提供する会社も増えており、例えば「小さなお葬式」は2009年のサービス開始以来、累計約59万件以上の利用実績がある大手葬儀社です。
低価格ながら明確な料金体系で安心できると評判で、利用者の口コミでも平均評価4.5/5.0と高く評価されています。
「よりそうお葬式![]() 」も年間約5万件の相談実績を持ち、遺族の希望に応じた葬儀を全国一律料金で提案してくれるサービスです。
」も年間約5万件の相談実績を持ち、遺族の希望に応じた葬儀を全国一律料金で提案してくれるサービスです。
葬儀会社との意思疎通がうまくいかず不満が残ると、後々の心の健康にも影響する可能性が指摘されています。そうした意味でも、信頼できるサービスを活用して納得のいくかたちで送り出せるよう支援を受けることは、心のケアの一環と言えるでしょう。
経済的負担への公的支援

大切な人を亡くした後は、葬儀や諸手続きに伴う出費が増えます。経済的な不安を軽くするために、以下の制度を活用しましょう。
- 葬祭費・埋葬料
国民健康保険や協会けんぽ加入者の場合、申請により約5万円(自治体により異なる)が支給 - 遺族年金
故人が厚生年金加入者だった場合に受給可能 - 高額療養費制度
医療費が高額になった際に自己負担を軽減できる - 傷病手当金
心の治療で働けない場合に支給されることがあります
経済面のサポートも含め、総合的に活用できるものは活用する姿勢が大切です。各制度の詳細は、役所の窓口で確認してください。
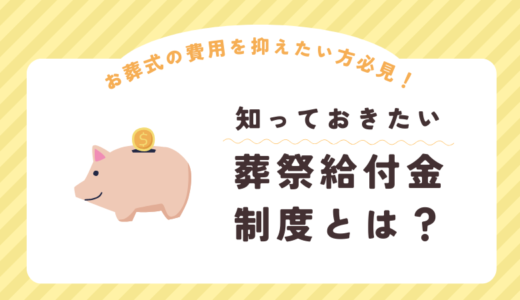 親の葬儀後に申請できる「給付制度」って?【2025年版】補助金制度まとめ
親の葬儀後に申請できる「給付制度」って?【2025年版】補助金制度まとめ
広がる支援の輪の中で
公的支援や各種サービスは、困っている人のために用意された「手すり」のようなものです。遠慮せずにつかまって、少しでも心と生活の安定につなげてください。
行政や企業のサポートを受けることで、「自分はこんなに支えてもらっている」という安心感が生まれ、孤独や不安も和らぐでしょう。周囲にはあなたを支えるしくみがたくさん存在します。どうか一人で抱え込まず、社会のリソースを活用して心の健康を守ってください。
未来へ踏み出すために

大切な人を失った悲しみは、その人を愛していたからこそ湧き上がる当然の感情です。心が深く傷ついてしまうのも無理はありません。しかし、あなた自身の人生もまた大切なものです。故人が生前に願っていたのは、きっとあなたが健やかに暮らすことではないでしょうか。
眠れない夜や涙する日々が続いても、少しずつで構いません、ご自身の心の声に耳を傾けてあげてください。つらいときは周囲の支えや専門家の力を借りながら、一歩一歩ゆっくりと日常を取り戻していきましょう。
心のケアに目を向けることは決して弱さではなく、明日を生きるための賢明な選択です。あなたがまた笑顔で前を向ける日が来ることを、社会のさまざまな支援策が後押ししてくれるはずです。自分の心をいたわりながら、故人との思い出を胸に、これからの人生を歩んでいってください。