「終活」とは、「人生の終わりを考えることを通して、残りの人生をいきいきとしたものにする活動」のことです。自分の人生の最終章に向けて、お葬式やお墓の準備、財産や身の回りの整理、延命治療の希望の確認などを事前に進めておくことを指します。かつては「死について考えるなんて縁起でもない」と敬遠されがちでしたが、現代では多くの高齢者が前向きに終活に取り組んでいます。
実際、内閣府の調査(2024年)では約60%の高齢者が何らかの終活の準備を進めている[1]ことがわかりました。終活を行うことで、人生の最終段階への不安を減らし、今をより充実して生きることにもつながります。大切なのは難しく考えすぎず、できることから少しずつ取り組むことです。自分らしいペースで準備を進めれば、心にゆとりが生まれ、残りの人生をより穏やかに過ごせるでしょう。
目次
エンディングノートの概要
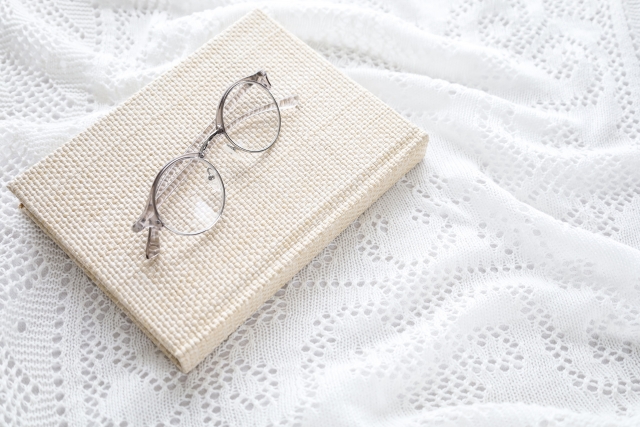
エンディングノートは、終活を進めるうえでとても役立つツールです。自分の意思や希望、大切な情報を整理し、家族や親しい人に伝えるためのノートのことを指します。例えば、葬儀の希望、相続についての考え、重い病気になったときに延命治療を望むかどうか、伝えておきたい自分史(経歴や想い出)などを自由に書き留めておくことができます。エンディングノート自体に法的な効力はありませんが、あらかじめ希望を書いておくことで家族の負担を軽減し、トラブルを防ぐ助けになります。
書き方に決まりはなく、自分が伝えたいことを自分の言葉で綴れるのが特徴です。市販の専用ノート(数百~数千円程度)を使っても良いですし、自治体が無料配布しているひな形を活用することもできます。自治体発行のエンディングノートは無料で入手できるだけでなく、行政の制度や相談窓口の情報も掲載されており安心です。思いついたタイミングで少しずつ書き足し、内容は定期的に見直すと良いでしょう。エンディングノートを書くこと自体が、自分の人生を振り返り整理する機会にもなります。書き終えたら、家族にも存在と保管場所を伝えておくと安心です。
※関連記事はこちら
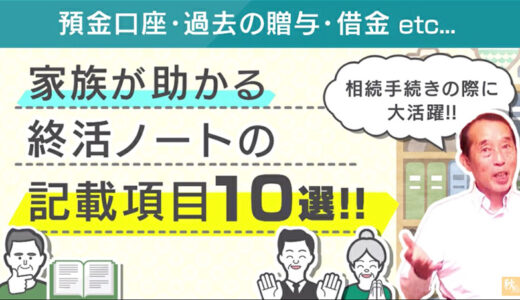 相続手続きの際に家族が助かるエンディングノートの記載項目10選! | 国税OB 税理士 秋山清成
相続手続きの際に家族が助かるエンディングノートの記載項目10選! | 国税OB 税理士 秋山清成
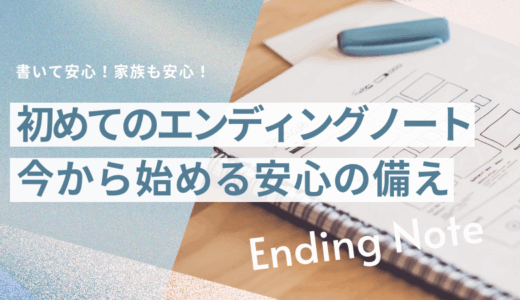 はじめてのエンディングノート〜今から始める安心の備え〜
はじめてのエンディングノート〜今から始める安心の備え〜
相続や遺言書の基礎知識
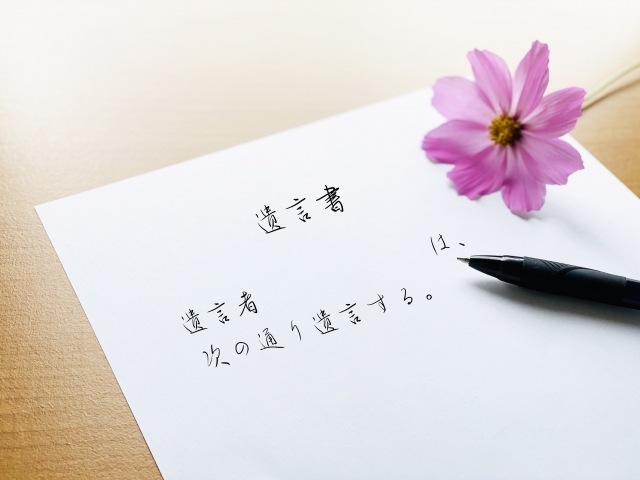
人生の最終章には、財産の相続についても考えておく必要があります。自分が亡くなった後、残された財産(預貯金、不動産など)は法律に沿って家族が相続することになります。しかし、遺言書を用意しておけば、自分の希望する形で財産分けを指定することが可能です。遺言書は、相続をめぐる家族間の紛争を防止する有用な手段とされています。法務省によれば、法律上「遺言で指定された相続方法は法定相続に優先する」と定められており、遺言があれば法律で決まった割合よりも自由な分配が可能です。例えば「長男に多めに残したい」「血縁でない大切な人に一部遺したい」といった希望も、遺言書があれば実現できます。
遺言書には主に2種類あります。自筆証書遺言は自分で全文を書いて作成する遺言で、手軽ですが形式に決まりがあります。一方、公正証書遺言は公証役場で公証人に作成してもらう遺言で、形式不備の心配がなく安全に保管されます。それぞれ利点がありますが、いずれの場合も内容を明確に書き、最新の家族状況に合わせて見直すことが大切です。また、自筆の遺言書は法務局の遺言書保管制度に預けることもできます。この制度を利用すれば、遺言書の紛失や改ざんを防ぎ、相続人が必要なときに閲覧できるようになります。いざという時に遺言書が見つからなかったり無効になったりしないよう、早めに準備して正しく保管しておきましょう。
※関連記事はこちら
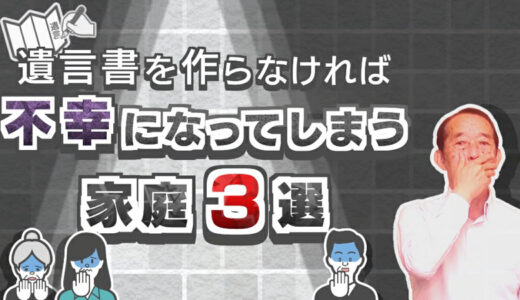 【重要】遺言書を作らなければ不幸になってしまう家庭〝3選〟 | 国税OB 税理士 秋山清成
【重要】遺言書を作らなければ不幸になってしまう家庭〝3選〟 | 国税OB 税理士 秋山清成
お墓や供養に関する選択肢

高齢になると「自分のお墓をどうするか」も大切なテーマです。昔は先祖代々のお墓を守るのが一般的でしたが、今はお墓のあり方も多様になっています。後継ぎがいない場合や、子に負担をかけたくない場合は、従来のお墓にこだわらない選択も検討しましょう。考えられる供養の選択肢には次のようなものがあります。
墓じまい
現在ある先祖代々のお墓を撤去し、埋葬されている遺骨を合同のお墓(合葬墓)など新しい場所へ移すことです。故郷のお墓を維持する人手がない場合などに行われます。墓じまい後の遺骨は、永代供養墓(寺院や霊園が永続的に供養してくれるお墓)に納めるケースが一般的です。親族やお寺と十分相談し、正式な手続きを経て行います。
納骨堂(のうこつどう)
屋内に遺骨を収蔵する施設で、言わば室内型のお墓です。ロッカー状の収蔵スペースや仏壇があり、遺骨の入った骨壺を安置します。屋内施設なので天候に左右されずお参りでき、管理も容易です。費用も一般的なお墓より抑えられる場合が多く、都市部でも人気が高まっています。
樹木葬(じゅもくそう)
墓石の代わりに樹木を墓標とする埋葬方法です。自然志向の供養として注目されており、公園のような緑地に木や花とともに遺骨を埋葬します。樹木葬は承継者(お墓を継ぐ人)が不要な点が大きな特徴で、後を継ぐ人がいなくても利用しやすいため選ぶ人が増えています。費用も比較的安く、管理は霊園や寺院が行ってくれるため、子や親族に負担をかけずに済みます。
これら以外にも、遺骨を海や山にまく散骨や、自宅で手元供養する方法などもあります。それぞれメリット・デメリットや費用、宗教的な考え方が異なりますので、自分と家族にとって何が一番心安らかかを考えて選ぶと良いでしょう。お墓の決定や改葬(お墓を引っ越すこと)は大きな決断ですが、事前によく調べて家族とも話し合い、納得のいく供養方法を見つけてください。
※関連記事はこちら
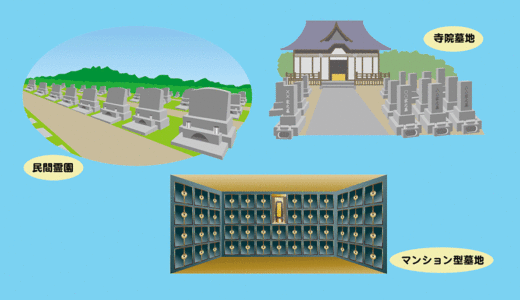 最近のお墓事情と新しい供養の形について紹介します
最近のお墓事情と新しい供養の形について紹介します
 お墓の代わりに選ぶ「散骨」とは?種類・費用・メリット・デメリット・注意点
お墓の代わりに選ぶ「散骨」とは?種類・費用・メリット・デメリット・注意点
事前に資料請求でお得になることも
お墓や供養に関する選択肢を検討する際、事前に資料請求を行うことは非常に有益です。特に「小さなお葬式」のようなサービスでは、資料請求を通じて具体的な情報を得られるだけでなく、費用面でもメリットがあります。
「小さなお葬式」では、無料で資料請求を行うと、葬儀費用が5万円割引になる特典が用意されています。この資料には、各種葬儀プランの詳細や地域の提携式場情報、葬儀の流れを解説した冊子などが含まれており、事前に葬儀の内容や費用を把握するのに役立ちます。また、資料請求後のしつこい勧誘はなく、安心して情報収集が可能です。
事前に資料を取り寄せておくことで、万が一の際にも慌てずに対応でき、希望に沿った供養方法を選択するための準備が整います。終活の一環として、信頼できるサービスの資料請求を検討してみてはいかがでしょうか。
介護や医療への備え

高齢期には、将来の介護や医療についての備えも重要です。元気なうちから「もし介護が必要になったらどうするか」「どんな医療を望むか」を考えておくことで、いざという時に慌てずに済みます。まず、日本には公的な介護保険制度があります。65歳以上(特定疾患がある場合は40歳以上)になると介護保険のサービスを利用でき、要介護認定を受ければホームヘルパーの派遣、デイサービス、福祉用具のレンタル、施設入所など様々な支援を1割〜3割の自己負担で利用できます。日常生活で不自由を感じ始めたら、地域包括支援センターなどに相談し、介護保険の申請やサービス利用の準備をしましょう。早めに情報収集しておくことで、自分に合った介護サービスや施設を選びやすくなります。
また、どのような介護施設に入るかも検討事項です。自宅での生活が難しくなった場合の受け皿として、以下のような施設があります。
特別養護老人ホーム(特養)や介護老人保健施設
要介護度が高い方向けの公的な入所施設です。費用負担が比較的低い反面、入居待ちが発生することもあります。医療ケアやリハビリ体制が整っており、長期的な療養や介護が必要な方に適しています。
有料老人ホーム
民間運営の高齢者施設で、介護付き・住宅型など種類があります。手厚いサービスが受けられる反面、入居一時金や月額費用が高めになる傾向があります。それぞれの施設で特徴やサービス内容が異なるため、見学や説明を受けて比較検討すると良いでしょう。
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)
高齢者が入居できるバリアフリー構造の賃貸住宅で、安否確認や生活相談などのサービスが付いた住まいです。比較的自立した生活が可能な方向けで、自宅に近い自由さと見守りサービスの安心感を両立した住まいと言えます。介護が必要になれば外部の介護サービスを利用しながら暮らせます。
いずれの選択肢も一長一短がありますので、自分の健康状態や経済状況、家族の希望などを総合的に考えて決めましょう。できれば元気なうちに実際に施設見学をしたり、ケアマネジャーに相談したりして情報を集めておくと安心です。「最後まで住み慣れた自宅で過ごしたい」という方も多いと思います。その場合は、バリアフリー化(手すりの設置や段差解消など)や見守りサービスの導入など、自宅で安全に暮らし続ける工夫を検討しましょう。
医療の意思表示
さらに、忘れてはならないのが医療の意思表示です。例えば「心肺停止になったとき延命措置をするか」「胃ろうなど人工的な栄養補給を望むか」といった延命治療の希望は、人それぞれ考えが異なります。事前によく考え、家族や主治医に伝えておくことが大切です。
厚生労働省は「人生会議」(アドバンス・ケア・プランニング)という取り組みを推進しています。[2]「もしものときのために、自分が望む医療やケアについて前もって考え、家族や医療・ケアチームと繰り返し話し合い共有する」ことが人生会議の趣旨です。難しい専門用語で言うとリビングウィル(生前意思表示書)とも呼ばれますが、要は「どこまでの医療を望むか」「誰に判断を任せるか」を事前に示しておくことです。書面に残しておけば安心ですし、エンディングノートに希望を記入しておくのも良いでしょう。家族にとっても、あなたの意思がわかっていればいざという時に悩まずに済みます。元気な今のうちに、一度ご家族と「自分はこんな治療を望んでいるんだ」と穏やかに話し合ってみてください。
保険やお金の整理

終活では、お金の整理も避けて通れないテーマです。人生の締めくくりを迎える前に、保険や年金、預貯金などの財産を一度棚卸ししておきましょう。
生命保険の整理
生命保険については、加入中の保険の内容を再確認してください。高齢になると医療保険や介護保険(民間のもの)は更新できなくなったり、保障内容が自分のニーズに合わなくなったりすることがあります。葬儀代程度の少額の生命保険に加入していれば、万一の際に家族の金銭的負担を軽減できます。また、既に保険に入っている場合は受取人が最新の状況に合っているか確認し、必要に応じて変更手続きをしておきましょう。せっかくの保険金が想定外の受取人に渡ったり、手続きが分からず受け取れなかったりすると残念ですので、どの保険に入っているか家族に共有しておくことも大切です。
年金・公的給付の整理
次に年金や公的給付についてです。年金は毎月決まった額が振り込まれるため、特に手続きをしなくても日常生活では意識しづらいかもしれません。しかし、自分が亡くなった後に残された配偶者が遺族年金を受け取れるかどうか、条件や手続きを確認しておくと安心です。例えば厚生年金に一定期間加入していれば、妻または夫に遺族厚生年金が支給されます。また逆に、自分が配偶者を先に亡くした場合、未支給年金(死亡月までの年金額)を請求できる制度もあります。役所への届出や年金事務所での手続きが必要になりますので、家族と一緒に年金証書や基礎年金番号がわかる書類の保管場所を確認しておくと良いでしょう。
預貯金・証券などの整理
預貯金や証券などの資産も、生前に整理をしておきましょう。複数の銀行に口座がある場合はリストアップし、通帳やキャッシュカード、印鑑をどこにしまっているか明確にしておきます。オンライン銀行や証券口座を利用している場合は、ログインIDやパスワードも含めてエンディングノート等に記録しておくと、いざという時に家族が探し出せず困る事態を防げます。最近はインターネットサービス(SNSやサブスクリプション契約など)も増えていますので、そうしたデジタル遺産の整理も忘れずに。使わなくなったサービスは解約し、必要なものは一覧にまとめておくと安心です。
お金の整理
お金の整理では、誰に何を託すかも考えておきましょう。判断能力が衰えてきたと感じたら、早めに信頼できる家族に財産管理の代理をお願いすることも検討できます。具体的には、銀行の手続きを代理してもらうための委任状を書いたり、場合によっては任意後見契約(将来判断能力が低下した際に後見人となってもらう契約)を結んだりする方法もあります。ただしこれは専門的な内容になりますので、必要に応じて司法書士や弁護士、行政書士といった専門家に相談すると良いでしょう。
いずれにせよ、財産の全体像を把握して整理しておくことが、残された家族への最後の思いやりになります。「自分は大した財産なんてないから…」と思われるかもしれません。しかし、少額でも口座が点在すると手続きが煩雑になりますし、思いがけない請求書や負債が後から見つかって家族が驚くこともあります。そうならないように、生前にしっかり情報をまとめ、「何がどれだけあるか」「どの口座にいくらあるか」を把握しておきましょう。これは決してお金持ちの方だけの話ではなく、誰にでも当てはまる大切な準備です。
生前整理(物の整理)
生前整理とは、元気なうちに自分の持ち物や財産を整理し、死後に遺族が遺品整理で苦労しないようにするための準備です。これは、遺族への思いやりであると同時に、自分自身の人生を振り返り、これからの生活をより豊かにするための行動でもあります。
物の生前整理:心を込めて身の回りを整える
物の生前整理は、自分の人生を振り返りながら、持ち物を見直し、必要なものと不要なものを分ける作業です。この整理を通じて、心の整理も進み、これからの生活をより快適に過ごすことができます。
生前整理を始める前に
まずは、整理する場所や物の種類、期間を決めましょう。一度に全てを片付けようとせず、少しずつ進めることが大切です。例えば、「今日は食器棚を1時間で整理する」といった具体的な目標を設定すると、無理なく進められます。
整理のステップ
-
持ち物の分類
持ち物を「必要なもの」「不要なもの」「保留」に分けます。判断に迷うものは一時的に保留とし、一定期間使用しなければ処分するなど、自分なりのルールを設けましょう。 -
必要なものの保管
必要と判断したものは、使いやすい場所に整理して保管します。定期的に見直しを行い、常に整理された状態を保つことが大切です。 -
不要なものの処分
不要と判断したものは、自治体のルールに従って処分します。リサイクルショップやフリマアプリを活用するのも一つの方法です。 -
思い出の品の整理
写真や手紙など、思い出の品は特に慎重に扱いましょう。デジタル化して保存することで、スペースを取らずに保管できます。
 終活に備えて写真をデータ化するメリットとおすすめサービス「まんてん録」の紹介
終活に備えて写真をデータ化するメリットとおすすめサービス「まんてん録」の紹介
家族との共有
整理の過程で、家族と話し合いながら進めることも重要です。特に、遺したいものや譲りたいものについては、事前に家族の意向を確認しておくと、後のトラブルを防ぐことができます。
専門業者の活用
大きな家具や家電の処分、整理が難しい場合は、専門の業者に依頼することも検討しましょう。複数の業者から見積もりを取り、サービス内容や料金を比較することが大切です。
住まいに関する考え

老後の住まいについても、早めに選択肢を検討しておくと安心です。歳を重ねてもできる限り自宅で暮らしたいという方もいれば、体が弱ってきたときに備えて施設入居も視野に入れておきたいという方もいるでしょう。それぞれの事情に応じて、住まい方を考えてみましょう。
自宅に住み続ける
長年住み慣れた自宅で最後まで暮らすのは、多くの高齢者にとって一番の希望かもしれません。その場合は、安全で快適に暮らせる環境作りがポイントです。手すりの取り付けや段差の解消、トイレや浴室の改修などバリアフリー化を検討しましょう。介護が必要になった場合も、訪問介護や訪問看護、宅配サービスなどを利用すれば自宅生活を継続できます。ただし独居の場合は、緊急時の連絡手段(緊急呼び出しボタンや見守りセンサーなど)を用意しておくと安心です。近隣の支援ネットワーク(民生委員や地域包括支援センター)ともつながりを持っておくと良いでしょう。
高齢者向け施設に入居
自宅での生活に不安が出てきたら、老人ホーム等の施設入居も選択肢の一つです。上で紹介した特養や有料老人ホームなどがこれにあたります。施設に入れば、食事・入浴・排泄など日常生活上の介助や、健康管理、レクリエーションなどのサービスを受けられます。24時間スタッフが常駐している施設も多く、夜間も含めて見守りがある安心感があります。一方で、住み慣れた自宅を離れる寂しさや費用負担の問題もありますので、家族ともよく話し合って決めることが大事です。施設によって雰囲気や方針も様々ですから、可能なら複数の施設を見学して、自分に合いそうな場所かどうか確認してみましょう。
サービス付き高齢者向け住宅
上述のサ高住は、自立度が比較的高い方向けのバリアフリー賃貸住宅です。自宅と同じようにプライバシーの保たれた空間で暮らしながら、緊急時の対応や生活相談など最低限のサポートを受けることができます。介護が必要になった場合も、外部の介護サービスを利用しながらそのまま住み続けられる柔軟性があります。「元気なうちは自由に生活し、困ったときだけ支援を受けたい」という方には適した選択肢でしょう。民間業者や自治体が運営しており、間取りや家賃も物件によって様々です。入居一時金が不要で月々の家賃制になっているところが多く、経済的な計画も立てやすいと言えます。
住まいに関して大切なのは、早め早めの情報収集と心構えです。歳を取ってから急に住み替えを検討するのは精神的・体力的にも負担が大きくなります。まだ比較的元気なうちに、パンフレットを取り寄せたり見学会に参加したりして、「自分だったらここで暮らせそうかな?」とイメージを持っておくと良いでしょう。もちろん最終的に自宅で看取られることになっても構わないのです。ただ、「もしもの選択肢」を知っておくことで心に余裕が生まれますし、万一介護度が重くなっても適切な場所に移れる準備ができていれば、自分も家族も安心です。どこで暮らすにせよ、自分らしく穏やかに生活できる環境を整えることが一番の目標です。
大切な人とのコミュニケーション

終活を進める中で、家族や親しい人とのコミュニケーションも欠かせません。自分の希望や考えを周囲に理解してもらうためには、話し合いの時間を持つことが大切です。例えば、お葬式の希望や財産の分け方について、家族と事前に話しておけば、いざという時に皆が迷わずに済みます。最初は話題に出しづらいかもしれませんが、「ちょっと聞いてほしいことがあるの」と穏やかに切り出してみましょう。ポイントは、自分の希望を押し付けるのではなく、気持ちを共有することです。「私はこう考えているけれど、どう思う?」と家族の意見も聞きながら進めると、お互い納得感が得られます。
特に延命治療や介護の方針など、生と死に関わる重いテーマについては、一度では結論が出ないこともあります。何度か機会を設け、ゆっくり話し合うと良いでしょう。厚労省が提唱する人生会議のように、繰り返し対話し意思を共有するプロセスが大事です。また、遠方の親族には電話や手紙で気持ちを伝えるのも一つの方法です。「もしものときお願いね」と頼みたいこと(例えばペットの世話や、葬儀のときの連絡先など)を伝達しておくだけでも相手は安心します。
さらに、終活を機に感謝の気持ちや思い出を家族に伝えることもぜひしてみてください。普段は照れくさくて言えない「ありがとう」や「ごめんね」を伝える良い機会でもあります。口頭で言うのが難しければ、エンディングノートに家族宛のメッセージを書くのも素敵です。残された人にとって、あなたからの手紙や言葉は何にも代えがたい宝物となるでしょう。終活とは単に事務的な準備ではなく、大切な人との絆を再確認し、深める時間でもあります。家族だけでなく、昔お世話になった友人や恩師に連絡を取ってみるのも良いですね。「元気にしているよ」と知らせたり、「あの時はありがとう」と感謝を伝えたりすることで、相手もきっと喜んでくれるはずです。
老後の生きがいと日々の暮らしの整え方

終活に取り組む中で忘れてならないのは、これからの毎日をどう充実させて生きるかという視点です。決して終活は「人生の終わりの準備」だけが目的ではありません。それを通して残りの人生をより良く生きることこそが本当の意義なのです。では、老後の生きがいを見つけ、日々をいきいきと過ごすためにどんなことができるでしょうか。
まず大切なのは、社会とのつながりを保つことです。退職すると人付き合いが減りがちですが、意識して外の世界と関わりを持ち続けましょう。地域のサークルや趣味の会に参加したり、ボランティア活動に挑戦してみたり、近所のイベントに顔を出したりと、できる範囲で構いません。終活の過程で重要な要素の一つが社会とのつながりを維持することだと指摘されています。仕事や地域活動、ボランティアなどに関わり続けることで、精神的に充実した老後を送ることができるからです。人と話す機会があるだけで生活にハリが出ますし、自分の経験や知識が誰かの役に立てば生きがいも感じられます。
また、趣味や楽しみを持つことも生きがいづくりには有効です。長年の趣味を続けるのはもちろん、新しいことにチャレンジするのも脳の刺激になって良いでしょう。例えば、家庭菜園や料理に凝ってみる、本や映画をゆっくり楽しむ、絵や書道など創作活動を始める、シニア向けの学び直し講座で勉強する…など、今だからこそできることがきっとあります。「自分はもう年だから」とあきらめる必要はありません。何歳からでも挑戦できることはたくさんありますし、「これをやってみたい」と思った時が始めどきです。新しい趣味が見つかれば毎日の楽しみが増えますし、同じ趣味を持つ仲間との出会いもあるかもしれません。
そして、心と体の健康を保つことが何より基本です。適度に体を動かし、バランスの良い食事と十分な睡眠を心がけましょう。体調が良ければ気持ちも前向きになります。医療や介護の備えをしつつも、「なるべくお世話にならずに済むよう自分も努力しよう」という意識で日々過ごすことが、結果として生きがいにつながることも多いです。無理のない範囲で散歩や体操を習慣にしたり、健康チェックを定期的に受けたりして、自分の体を大切にしてください。
最後に、終活を通じてぜひ人生の棚卸しもしてみましょう。これまでの人生を振り返り、「あんなことがあったな」「この人との出会いが自分を変えてくれたな」と一つひとつ思い出してみるのです。辛かった経験も、振り返ってみれば「よく頑張って乗り越えた」と自分を褒めてあげられるでしょう。人生の棚卸しをすることで、自分が大切にしてきた価値観やこれから大事にしたいことが見えてくるかもしれません。それは同時に、残りの時間をどう過ごすかのヒントにもなります。例えば、「やっぱり自分は家族が一番大事だ」と思えば、家族との時間を優先して過ごす計画を立てることもできます。「やり残した趣味がある」と気づけば、今からでも再開してみれば良いのです。終活とは終わりの準備であると同時に、これからの生き方を見つめ直す機会でもあります。
おわりに:前向きに人生の最終章へ
ここまで、終活に関わる主要なテーマについて網羅的にお話ししてきました。初めは戸惑うことも多いかもしれませんが、終活は決して悲観的なものではなく、自分の人生をよりよく締めくくるための前向きな活動です。準備を進める中で、自分がどれほど多くの人や出来事に恵まれてきたかに気付き、感謝の気持ちが湧いてくることもあるでしょう。ときには懐かしい写真を眺めながら、笑ったり涙したりするかもしれません。それも含めて、終活は自分の人生をまるごと振り返る大切な時間です。
読者の皆さんも、この記事をきっかけにぜひ一歩を踏み出してみてください。すべてを一度に完璧にしようとしなくて大丈夫です。エンディングノートにペンを走らせる一行目から、終活は始まります。今日できなければ明日でも構いません。自分のペースで、できることから少しずつ取り組んでみましょう。わからないことや迷うことがあれば、市区町村の相談窓口や信頼できる専門家に相談するのも良い方法です。周りには同じように終活に取り組んでいる仲間も大勢います。不安を抱え込まず、時には情報交換や励まし合いもしながら進めていきましょう。
人生の最終章は、寂しさや不安だけでなく、穏やかな充実感や達成感で満たすこともできます。終活によって大切な人への感謝を形にし、自分自身も納得のいく幕引きを迎えられるようになります。準備が整えば、あとは毎日を安心して、自分らしく楽しむだけです。どうか前向きな気持ちで終活に取り組んでみてください。あなたの人生が最後まで輝き続けることを、心から応援しています。








