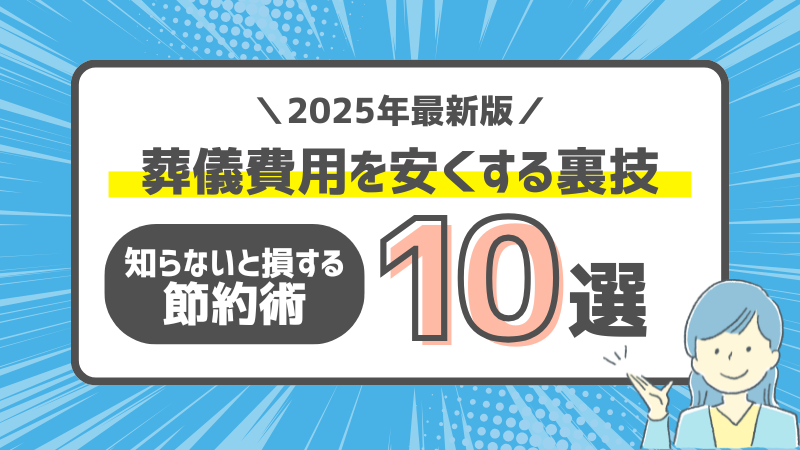葬儀費用は全国平均で約118万円(鎌倉新書2024年調査[1])と言われています。まとまった金額が必要なだけに、きちんとした形で故人を送りたいと思いながらも費用はなるべく抑えたいという方は多いでしょう。
実は、知らないと損をする節約術は数多く存在します。補助金活用・相見積もり・不要なオプションの見極め方など、今回ご紹介する10の裏技を実践すれば、30万円以上の節約ができる可能性もあります。
大切な方を心を込めて送りつつ、賢く費用を抑える方法をお伝えします。
基本の節約術で大幅削減を実現する

葬儀費用を安く抑える第一歩は、基本的な節約術をマスターすることです。多くの人が見落としがちなポイントを押さえることで、一般葬でも大幅な費用削減が期待できます。
ここでは、すぐに実践できる基本的な節約方法をご紹介します。
裏技①:複数社から相見積もりを取る
相見積もりの効果は想像以上に大きく、見積もりを1社しか取らない場合と2社以上取る場合では、火葬式で約2万円、家族葬では10万円以上の差が生じることが判明しています[2]。
具体的には、直葬・火葬式において見積もりを取った葬儀社数と費用の関係を見ると、1社では19万4,917円、2社では17万6,910円、3社以上では16万7,123円と、明らかに見積もり社数が多いほど費用が下がる傾向にあります。
効果的な相見積もりの取り方は、まず同一条件で少なくとも3社から見積もりを取得することです。「安心葬儀」などの一括見積サービスを活用すれば、24時間365日いつでも複数社の見積もりが効率的にできます。
裏技②:不要なオプションを見分ける方法
葬儀社から提案されるプランには、必ずしも必要でないオプションが含まれていることがあります。豪華な棺や花輪、生演奏、メモリアルビデオなどが、故人や家族にとって本当に必要かどうかを見極めることが重要です。
不要なオプションを見分けるには、以下の手順で進めます。
上記の流れで進めることで、個人や家族にとって過剰な演出や装飾を省くことができます。一つひとつの項目を丁寧に確認し、冷静に判断することで5万円~15万円程度の節約効果が期待できます。
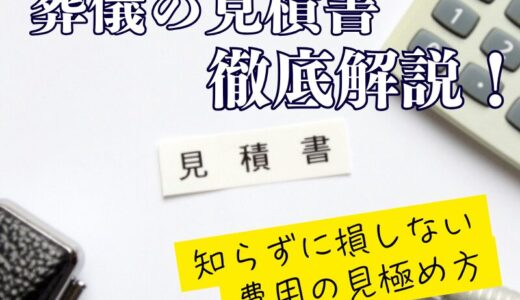 葬儀の見積書を徹底解説|知らずに損しない費用の見極め方
葬儀の見積書を徹底解説|知らずに損しない費用の見極め方
裏技③:祭壇・棺のグレードを賢く下げる方法

棺や祭壇のグレードを最小限に抑えることで、場合によっては数万円~数十万円節約できることもあります。節約したいなら、「棺も祭壇も葬儀の数時間のためだけのもの」と割り切って、予算に沿ったものを選ぶという選択肢もあります。
まず、葬儀社が提案したプランを確認し、棺・祭壇のランクが高すぎないかチェックしてみましょう。見栄えより予算を優先し、最低限の装飾・生花ボリュームに抑えたランクを選びます。
プランに価格明記がない場合は葬儀社に直接問い合わせ、棺・祭壇それぞれの単価を確認しましょう。そして、複数社から同等内容の見積もりを取り、最もコストパフォーマンスの高い選択をします。
裏技④:会食・返礼品の工夫で接待費を半減
接待費は葬儀費用の大きな部分を占めており、鎌倉新書の調査によると平均で約20万円とされています。そのため、通夜振る舞いや精進落としの規模を縮小し、仕出し弁当で簡素化することで大幅な削減が可能です。参列者数を正確に把握して、無駄な注文を減らすことも大切です。
香典返しは、香典額の半額~3分の1程度に抑えます。カタログギフトなどにすると、受け取り側からの評判も高くおすすめです。
会葬御礼はお茶など、500~1,000円程度の実用的な品を選択しましょう。葬儀会館が許せば、外部手配や持ち込みでコストダウンを図ることも可能です。
予算設定が成功の鍵を握る
基本的な節約術を実践するうえで最も重要なのは、事前の予算設定です。葬儀費用は感情的になりやすく、気づけば想定以上の金額になってしまうケースも少なくありません。
あらかじめ上限を決めておくことで、冷静に判断しやすくなります。とくに初めて葬儀を経験する方ほど、予算の枠を明確にしておくことが大切です。葬儀社との交渉時に「この金額以内で」と明確に伝えておきましょう。
公的制度を活用して負担を軽減する

意外と知られていない公的制度を活用することで、葬儀費用を大幅に軽減できます。国民健康保険や社会保険の給付金、自治体の支援制度など、申請すれば確実に受け取れる制度を見逃す手はありません。
裏技⑤:葬祭費・埋葬料の申請で最大7万円を取得
国民健康保険の葬祭費は自治体によって異なりますが、1万円~7万円の支給が受けられます。たとえば、東京都23区では5万円~7万円、東京・神奈川・千葉・埼玉の市町村では概ね5万円が支給されます。
社会保険の埋葬料は、全国健康保険協会から一律5万円が支給されます。被保険者が亡くなった場合は「埋葬料」、被扶養者が亡くなった場合は「家族埋葬料」として支給されます。
申請に必要な書類は以下のとおりです。
| 制度 | 必要書類 |
|---|---|
| 葬祭費 (国民健康保険に加入) |
・葬祭費支給申請書 ・故人の国民健康保険被保険者証 ・申請者の認印 ・喪主名義の銀行口座情報 ・喪主であることを証明する書類(会葬あいさつ状、葬儀費用領収書のコピーなど) |
| 埋葬料 (健康保険に加入) |
・健康保険埋葬料支給申請書 ・死亡診断書 ・埋葬許可証 ・火葬許可証のコピー |
※上記は一例です。必要書類は自治体や健康保険組合によって異なる場合があるため、申請時に必ず各窓口で確認してください。
裏技⑥:市民葬・区民葬で大幅コストダウン
市民葬・区民葬は、自治体と葬儀社が協定を結んで提供する低価格な葬儀サービスです。東京都の例では、棺を含む祭壇の料金は100,100円~325,380円の4段階設定となっており、通常の葬儀より大幅にコストを抑えられます。
利用条件は、亡くなった方が当該自治体に住んでいたか、喪主が当該自治体に住んでいることです。申し込み方法は、市役所・区役所への直接申し込みと、自治体提携葬儀社への直接申し込みの2通りがあります。死亡届提出時に市民葬利用を申し込み、受理後に自治体提携葬儀社から業者を選んで葬儀を依頼します。
裏技⑦:生活保護世帯向け葬祭扶助制度
生活保護受給者は、葬祭扶助制度により自己負担0円で必要最小限の葬儀(直葬)を執り行うことができます。この制度は、経済的に困難な状況にある家庭を支援するもので、遺族が葬儀を行う際に必要な費用の一部または全額を自治体が負担します。
申請には生活保護受給証明書・葬祭扶助申請書・死亡診断書などが必要で、事前に福祉事務所への相談が必要です。給付額は地域によって異なりますが、東京都では約20万円程度が支給されます。
なお、「小さなお葬式」では、生活保護受給者の方が葬祭扶助制度の適用を受けた場合に限り、自己負担0円で直葬プランを利用することが可能です。専用ページでは制度の概要や申請の流れについても詳しく説明されています。該当する方は、ぜひ確認してみてください。
申請期限を逃さない準備が大切
公的制度の多くは申請期限が設けられています。死亡翌日から2年を経過すると申請は一切受け付けられず、5万円~7万円程度の給付金を受け取る権利を失います。
必要書類を葬儀中に確実に保管し、早めの申請を心がけることが重要です。書類は葬儀期間中にすべて入手・保管しましょう。また、記入漏れや添付書類不足で審査に通らないケースを避けるため、申請書は複数回チェックすることが推奨されます。
一般葬でも費用を抑える実践テクニック

家族葬や一日葬は葬儀費用を抑えられますが、一般的な葬儀でも費用を抑える方法があります。参列者が多い場合でも工夫次第で無駄な出費を削減し、心のこもった葬儀を実現できます。
裏技⑧:式場選びで大幅コストダウン
多くの場合、葬儀プランに最初から含まれている搬送費用には距離の上限があり、その距離を超えると追加料金が必要になります。したがって、火葬場近くの斎場を選択することで、斎場から火葬場への搬送費用を削減できます。また、参列者のバス手配費なども省けるため、交通費の観点でも有効です。
公営斎場と民営斎場の使い分けも重要です。公営斎場は料金が安く設定されていることが多いものの、予約が取りにくい場合があります。民営斎場は料金が高めですが、設備やサービスが充実しています。予算と必要性のバランスを考慮して選択しましょう。
オフシーズンや平日の利用では割引が適用される場合があります。また、使用時間の短縮により料金を抑えることも可能です。
裏技⑨:お布施・宗教費用の適正化
お布施の相場は地域や宗派によって異なりますが、鎌倉新書の調査によると平均で約23万円とされています。菩提寺や宗教者との事前相談により、予算を正直に伝えて適切な額を決めることが重要です。
御車代は5,000円~1万円程度、御膳料は5,000円~2万円程度が相場です。これらも事前に確認・交渉することで、予算内に収めることができます。
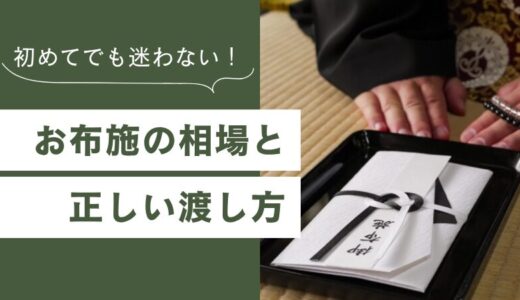 初めてでも迷わない!お布施の相場と正しい渡し方
初めてでも迷わない!お布施の相場と正しい渡し方
戒名料についてはランクによって大きく費用が変わるため、故人の意向や家族の方針を考慮して適切なレベルを選択しましょう。
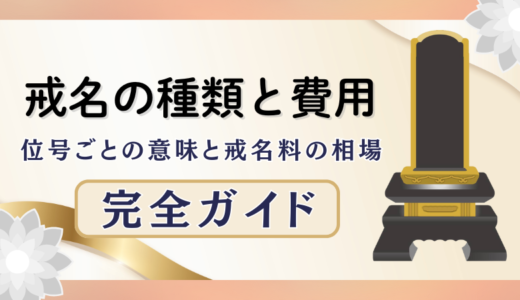 戒名の種類と費用|位号ごとの意味と戒名料の相場完全ガイド
戒名の種類と費用|位号ごとの意味と戒名料の相場完全ガイド
地域性を活かした賢い選択
一般葬で費用を抑える秘訣は、地域の特性を活かした選択です。地元の葬儀社や公営施設を活用し、無理のない範囲でサービスを調整することで、参列者にも満足してもらえる葬儀を実現できます。
地域の慣習や風習を理解し、それに合わせた適切な規模や内容を選択することで、過不足のない葬儀を執り行うことができます。また、地域のネットワークを活用することで、質の高いサービスを適正価格で受けることが可能になります。
事前準備で更なる節約を実現する

最も効果的な節約術は、生前からの準備です。急な事態に備えて事前に情報収集し、準備を整えておくことで、慌てずに適切な判断ができ、結果的に大幅な費用削減に繋がります。
裏技⑩:生前見積もりで最適プランを把握
生前に複数の葬儀社から見積もりを取得することで、冷静な判断ができ、比較検討が可能になります。事前相談のメリットは、時間的余裕があるため納得のいく選択ができることです。
希望条件の整理方法として、予算・参列者数・葬儀形式・宗教や宗派・会場の希望などを明確にしておきます。見積もりの保管と更新のタイミングも重要で、年1回程度の見直しを行い、料金改定や内容変更に対応することが推奨されます。
また、見積もりをもとに葬儀・納骨代金を事前に支払い、備えておけるサービスもあります。たとえば「小さなお葬式」では、あらかじめ希望に合った葬儀プランを選び、「生前契約」として準備することが可能です。将来の親族の負担をなるべく減らしておきたい人におすすめです。
 小さなお葬式の「生前契約サービス」とは?特徴・流れと終活におけるメリットを解説
小さなお葬式の「生前契約サービス」とは?特徴・流れと終活におけるメリットを解説
葬儀保険の活用で負担軽減
少額保険の活用により、月々数百円程度の負担で葬儀費用を準備できます。保険金は被保険者が亡くなった際に速やかに受け取ることができ、葬儀費用の即座の支払いに充てることができます。
保険金受け取りの流れは、死亡診断書の提出・保険金請求書の記入・必要書類の添付・保険会社での審査を経て、通常1週間程度で支払われます。費用対効果の計算では、月々の保険料と保険金額を比較し、長期的な視点で判断することが重要です。
 葬儀保険は本当に必要?加入前に知っておくべき仕組みとポイント
葬儀保険は本当に必要?加入前に知っておくべき仕組みとポイント
事前の準備で生まれる心の余裕と節約効果
事前準備の真価は、費用削減だけでなく、いざという時の心の余裕にあります。しっかりと準備を整えることで、故人を偲ぶ時間を大切にしながら、経済的な負担も軽減できる理想的な葬儀が実現できます。
また、家族間での連携も取れるため、一人に負担が集中することを避けることも可能です。
賢い葬儀で故人への思いを形に

本記事でご紹介した10の裏技を実践することで、費用面での不安を軽減しながら、故人への感謝と愛情を込めた葬儀を執り行うことができます。大切なのは、単なる節約ではなく、本当に必要なものを見極め、心のこもった送別の時間を作ることです。
費用を抑えながらも、故人への最後のお別れを心を込めて行うことで、遺族にとっても参列者にとっても満足のいく葬儀となることでしょう。