近年、葬儀費用の負担を軽くしたいという声が増える中、直葬(火葬式)を選択する家庭が多くなってきています。2024年の調査[1]によれば、9.6%の家庭が直葬を選んでおり、その背景には経済的な理由やシンプルな儀式を希望する価値観の変化があります。
費用を大幅に抑えられるという魅力がある反面、後になって後悔するケースも報告されています。この記事では、直葬の実際の流れや法的に必要な手続き、失敗しないための準備方法まで、検討中の方が知っておくべき情報を詳しくお伝えします。
直葬とは何か-選ばれる理由と現状

直葬(火葬式)は、お通夜や告別式を行わず、火葬だけで故人をお見送りする葬儀の形です。一般的な葬儀では121万円程度の費用がかかりますが、直葬なら約20万円と5分の1程度に費用を抑えることができます。
ただし、経済的なメリット以外にも、現代の家族関係や社会情勢の変化が選択理由として大きく影響しています。
直葬とは
直葬は、宗教的な儀式を一切行わず、火葬のみで故人をお送りする葬儀スタイルです。参列するのは家族や近しい親族だけで、通常は10人以下の小規模で行われます。
宗教儀式を省くことで、お坊さんへのお布施、式場の使用料、参列者への食事代などが一切不要になり、葬儀費用を大きく削減できます。準備にかかる時間も短く、亡くなってから火葬まで最短で2日程度で済ませることも可能です。
直葬を選ぶ人の心理
直葬を選択する理由として最も多いのは、やはり費用面での負担軽減です。一般的な葬儀の121万円に対し、直葬であれば20万~30万円程度で済むため、約90万円以上の節約が可能になります。
現代社会特有の事情も大きく関わっています。高齢社会が進む中、故人の友人や知人も高齢化し、葬儀への参列が困難なケースが増えています。核家族化の影響で親戚同士の付き合いも薄くなり、大々的な葬儀の必要性を感じない家庭が増加傾向にあります。
都市部では特に近所との関係が希薄で、昔のような地域ぐるみでの葬儀は現実的でなくなっています。このような「つながりの薄い社会」では、参列者が限られる直葬が現実的な選択となっているのです。
本当はしたいのに諦める現実
直葬を選ぶご家庭の中には、「本当はもう少しきちんとしたお葬式をしてあげたいけれど、経済的に余裕がなくて…」という複雑な思いを抱えている方も多くいらっしゃいます。
年金暮らしの高齢者世帯、おひとり様世帯、収入が不安定な方などにとって、100万円を超える葬儀費用の準備は現実的ではありません。医療費や介護費用で家計が圧迫され、葬儀にまでお金をかけられないという状況も珍しくありません。
その一方で、「故人が飾らない人だったから」「お金をかけることよりも気持ちが大切」という考えから、積極的に直葬を選択するご家庭も存在します。直葬を選ぶ背景は、経済的な制約と価値観の変化が複雑に関係しているというのが実情です。
直葬の具体的な流れ

直葬は手続きが簡単とはいえ、法律で決められた要件や必要な準備は通常の葬儀と基本的に同じです。特に、24時間の安置義務や火葬許可証の手続きなど、法的に守らなければならないルールを正しく理解しておくことで、スムーズに進行できます。ここでは、ご家族が事前に把握しておくべき手順を順番に説明していきます。
臨終後は24時間の安置が必要
日本の法律では「死亡から24時間以内の火葬を禁止」と決められているため、直葬でも必ず24時間以上は故人を安置しなければなりません。
安置場所にはいくつかの選択肢があります。ご自宅での安置は費用がかかりませんが、十分な広さや搬入経路を確保できるかどうかが重要なポイントです。葬儀社の安置施設を借りる場合、1日につき1~2万円程度の料金が発生します。公営斎場の安置室は比較的リーズナブルですが、民間の専用施設は設備が整っている分、利用料金も高くなります。
安置している間は、ご遺体の保存のためにドライアイスが必要で、1日5,000~8,000円程度かかります。安置日数が長くなるほど費用が積み重なるため、できるだけ早く火葬の日程を決めることが費用を抑えるコツです。
死亡届の提出と火葬許可証の取得
故人が亡くなってから7日以内に、市区町村の役場へ死亡届を提出する必要があります。多くの場合、葬儀社がこの手続きを代行してくれますが、届け出る人は法律で決められた親族でなければなりません。
死亡届と一緒に火葬許可申請書も提出し、「火葬許可証」を発行してもらいます。この許可証がないと火葬を行うことができません。
手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 死亡届(死亡診断書と一体になった用紙)
- 火葬許可申請書
- 届出人の身分証明書
- 印鑑
葬儀社が書類の準備をサポートしてくれることが多いですが、身分証明書と印鑑はご家族で用意する必要があります。火葬許可証は火葬が終わった後「埋葬許可証」として戻ってくるので、納骨まで大切に保管しておきましょう。
火葬当日の流れ
火葬場の予約手続きは、通常葬儀社が代わりに行ってくれます。
火葬当日は参列者が火葬場に集まり、お棺の蓋を開けて故人との最後のお別れをします。この時、故人が大切にしていた物や生花などを一緒に納めることができますが、燃えにくい材質や体に有害な物は入れられないため、事前に確認が必要です。
お棺を火葬炉に入れた後は、火葬が終わるまで控室で待機します。直葬では食事の席を設けないことが一般的ですが、少人数での軽食を希望される場合は前もって手配しておく必要があります。
火葬が完了すると、収骨室でお骨拾いを行います。地域によって拾い方に違いがあるため、火葬場のスタッフの案内に従って進めることが大切です。
直葬の費用相場と内訳
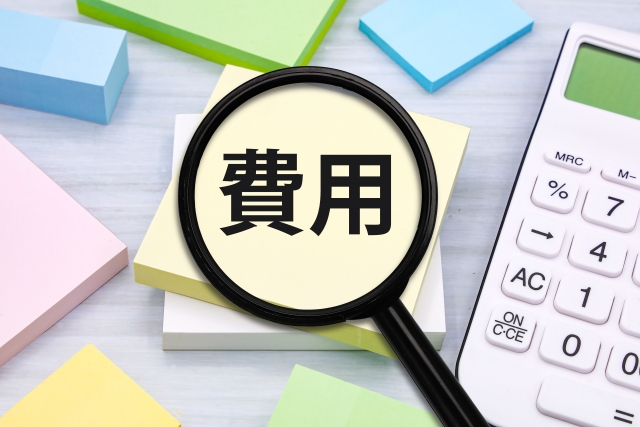
直葬は最も費用を抑えられる葬儀の形として注目されていますが、実際にどれくらいの費用がかかるのか、内訳まで把握している方は意外と少ないでしょう。
この章では直葬の全国平均費用や地域差、具体的な内訳、追加費用を避けるための注意点までを詳しく解説します。
直葬の費用相場と全国平均
直葬にかかる費用の全国平均は約20万円となっています。これを一般葬や家族葬の平均費用と比べてみると、かなり安価であることがわかります。
ただし、住んでいる地域によって費用に違いがあり、10万円~30万円程度の幅があります。この差が生まれるのは、主に火葬場の料金設定や葬儀社の基本セットの内容が異なるためです。
できる限り安く抑えたい場合は、公営の火葬場を利用し、葬送用品も必要最小限のものを選べば10万円程度に収めることも不可能ではありません。反対に、民営の火葬場を使ってお棺や骨壺のグレードを上げ、簡単な会食まで行うとなると30万円を超える場合もあります。
 直葬のすべてがわかる!費用から地域別の相場まで詳しく解説
直葬のすべてがわかる!費用から地域別の相場まで詳しく解説
費用の内訳
直葬でかかる費用は、主に葬儀社に支払う分と火葬場に支払う分の2つに分かれます。それぞれの費用の主な内訳と相場は、次の通りです。
葬儀社への費用
| 項目 | 費用相場 | 詳細 |
|---|---|---|
| お棺代 | 30,000~50,000円 | 木製のシンプルなお棺が一般的。布張りや装飾があると価格が上がる。 |
| 骨壺代 | 5,000~30,000円 | 陶器・磁器・桐箱など材質やデザインで変動する。 |
| 安置費用 | 10,000円/日 | 火葬までの間、遺体を保管する施設の利用料。 |
| 寝台車代 | 10,000~20,000円 | 病院や自宅から安置施設へ搬送するための車両費用。 |
| 霊柩車代 | 10,000~20,000円 | 安置場所から火葬場まで故人を搬送する車両費用。 |
| ドライアイス代 | 5,000~8,000円/日 | ご遺体の保冷保存に使うドライアイスの費用。 |
火葬場への費用
| 火葬場の種類 | 費用相場 | 備考 |
|---|---|---|
| 公営火葬場(住民の利用) | 無料~40,000円 | 予約が取りにくい |
| 公営火葬場(住民以外の利用) | 50,000~100,000円 | 予約が取りにくい |
| 民営火葬場 | 50,000~150,000円 | 料金は一律で居住地を問わない |
上記以外にも、火葬場の待合室使用料や、追加の車両費用などが別にかかる場合があります。これらすべてを合計すると、直葬の総費用はおおよそ20万円程度になります。
ただし葬儀社や火葬場、追加するオプションによって金額は大きく変わります。複数の会社から見積もりを取って内容を比較することをお勧めします。
時間がなく効率的に見積もりを取りたい場合は、一括見積サービスを活用するのがおすすめです。たとえば全国の葬儀社対応の一括見積サービス「安心葬儀」では、たった1分の入力で簡単に複数社の見積もりができます。24時間365日いつでも相談できるので、急いでいるときでも安心です。
追加費用を避けるための注意点
直葬であってもオプションサービスや予想外の追加費用で、当初の予算を大幅に超えてしまうことがあります。予算内に費用を収めるには、見積もりの段階で次のポイントを確認しておきましょう。
- 基本パックに含まれているサービス内容
- 別料金が発生するサービス項目
- 火葬場が公営か民営かの違いとそれぞれの料金
- 安置日数が延びた場合の追加費用
複数の葬儀社から詳しい見積もりを取り寄せ、サービス内容をしっかり比較することが大切です。また、最初に予算の上限を決め、葬儀社にしっかりと伝えましょう。わからないことは質問し、十分に納得できる説明を受けてから契約を結ぶことが、満足のいく結果につながります。
トラブルを避けるために

直葬を選択したご家庭の中には、あとになって「違う方法にすれば良かった」と感じる方が一定数いらっしゃいます。菩提寺から納骨を断られる、親族から反対される、お別れの時間が短すぎるなど、実際に起こりがちな問題を事前に知っておくことで、適切な対策を講じることができます。実体験に基づく対処法も含めてご紹介します。
菩提寺との関係-納骨拒否のリスクと対策
直葬で起こる最も深刻な問題が、菩提寺からの納骨拒否です。
納骨を断られる理由はいくつか考えられます。お経や焼香などの宗教的な儀式なしに火葬を行ったこと、菩提寺に事前の相談なく勝手に直葬を決めてしまったこと、檀家としての務めを果たしていないと見なされたことなどが主な原因として挙げられます。
最も重要な対策は、菩提寺への事前相談です。直葬を決める前に必ずお寺に相談し、承諾を得ておくことが欠かせません。火葬炉の前でお経を読んでもらうなど、最低限の宗教儀式を行うことや、菩提寺のお坊さんに火葬場まで来てもらうことも効果的な対策になります。
もし納骨を断られてしまった場合の解決策として、宗旨宗派を問わない民営霊園への変更が考えられます。こうした霊園なら宗教的な制約を受けることなく納骨が可能です。自治体が運営する公営霊園も宗教的な縛りが少ないため、検討する価値があります。
さらに、永代供養墓という選択肢もあります。合祀墓や樹木葬など、お寺に頼らない供養方法を選ぶことで問題を解決できます。
 跡継ぎ不要・管理不要のお墓とは?永代供養と納骨堂のすべて
跡継ぎ不要・管理不要のお墓とは?永代供養と納骨堂のすべて
親族間でのトラブル-事前の話し合いの重要性
直葬では、親族から「故人をちゃんと送ってあげられていない」という批判を受けることがよくあります。特に年配の親族や故人と親しかった方々にとって、お通夜や告別式を省略することは受け入れがたいものです。
よく聞かれる親族間のもめごとには以下のようなものがあります。
- 「もっとちゃんとした葬儀にすべきだった」という批判
- 「故人がかわいそう」という感情的な反発
- 「近所の目が気になる」という世間体への心配
- 参列できなかった親族からの不満
このようなトラブルを防ぐには、事前の話し合いが何よりも大切です。葬儀の方法について親族でよく相談し、全員が理解できる選択をすることが重要です。直葬を選ぶ理由を丁寧に説明し、経済的な事情や故人の意向などを理解してもらう努力も必要です。
経済的な理由で直葬を選ぶ場合は、親族全員で費用を負担し合うという提案も検討できます。また、後日改めてお別れの会や法要を行うことを約束することで、親族の理解を得やすくなります。
お別れ時間の短さによる心残り

直葬では火葬炉の前でのお別れ時間が5~10分程度と短く、「心の整理がつかないうちに火葬が始まってしまった」という後悔を抱く遺族の方が多いことがわかっています。
お別れ時間の短さから生じる問題と、それぞれの対策方法を以下の表にまとめました。
| よくある後悔・悩み | 対策方法 | タイミング | 効果 |
|---|---|---|---|
| 最後にゆっくり対面できなかった | 安置期間を延ばす | 火葬前 | 落ち着いてお別れの時間が確保できる |
| 気持ちの整理がつかない | 当日の朝に面会時間を設ける | 火葬当日の朝 | 心の準備が整い、後悔が残りにくくなる |
| 参列者みんなが満足にお別れできない | 手紙やお別れの言葉を準備してもらう | 火葬前日まで | 限られた時間でも気持ちを伝えられる |
| 故人との思い出が形に残らなかった | 記念品や写真などを用意する | 火葬後 | 故人の記憶を形として手元に残せる |
対策方法はそれぞれ行うタイミングが異なるため、計画的な準備が大切です。特に安置期間を延ばす場合は費用もかかるため、予算との兼ね合いを考えながら検討する必要があります。
参列希望者への対応とフォロー
直葬は家族や親族だけで行うため、後から「参列したかった」と言われることがよくあります。
参列希望者への対応で最も重要なのは、事前連絡の徹底です。直葬を行う前に関係者への連絡を済ませ、直葬を選んだ理由を理解してもらうことが大切です。
後日お別れの機会を設けることも有効で、お別れ会や法要への参加機会を提供できます。特に故人と親しかった方には個別に対応し、思い出を語り合う時間を作ることも考慮すべきです。
亡くなってから1~2週間以内にお知らせの手紙を送り、直葬を選んだ経緯と故人への思いを伝えることで、関係者の理解も得やすくなります。
直葬を選ぶことは単に費用を抑えるだけでなく、現代社会での「弔い」の意味を根本から考え直すことでもあります。従来の葬儀スタイルにとらわれず、故人と遺族にとって最も良い方法を選択する決断力が求められます。
ただし直葬を選ぶ場合、事前準備と事後のフォローが欠かせないことは忘れてはいけません。
直葬で後悔しないための準備と葬儀社選びのポイント

直葬を成功させるには、事前の準備と正確な情報収集が不可欠です。葬儀社選びから家族との意思確認、必要な手続きの準備まで、後悔のない選択をするための実践的なアドバイスをお伝えします。
経済的な制約がある中でも、故人を心を込めてお送りするための方法を一緒に考えていきましょう。
家族の意思をひとつにする
直葬を成功させる上で最も大切なのは、家族全員の気持ちをひとつにすることです。一人で勝手に決めてしまうのではなく、関係者みんなが納得した上で選択することが、後悔を防ぐ最大のポイントになります。
最初に確認すべきは、故人が生前に話していた意向です。「派手な葬儀は嫌だ」「身内だけで静かに送ってもらいたい」といった希望があったかどうかを家族で話し合ってみましょう。同時に、家計の実情を隠さずに共有し、無理のない予算設定を行うことが重要です。
年配の親族の中には、「きちんとした葬儀をするべきだ」と考える方もいるでしょう。そんな時は、直葬を選ぶ理由を丁寧に説明し、必要があれば後日お別れ会や法要を開くことを提案して、理解してもらえるよう努力することが大切です。
葬儀社選びのポイント
直葬を任せる葬儀社選びは、費用と品質のバランスを見極めながら慎重に行う必要があります。複数の会社から見積もりを取り寄せ、最適な選択をするためのポイントをご紹介します。
葬儀社選びのチェックポイント
| 確認項目 | 重要度 | 詳細 |
|---|---|---|
| 基本料金 | ★★★ | 追加費用込みの総額を確認する。 |
| 安置施設 | ★★★ | 自社に安置施設があるか、利用料金は1日あたりいくらかを確認。 |
| 搬送範囲 | ★★☆ | 病院や自宅からの搬送対応エリアはどこまでか。 |
| 火葬場連携 | ★★★ | 地元の公営火葬場と連携できているか、予約代行の有無を確認。 |
| 24時間対応 | ★★☆ | 深夜や早朝の連絡・搬送に対応しているか。 |
| 納骨サポート | ★☆☆ | 希望する納骨先の紹介や手配をしてくれるか。 |
見積もりを比較する際には、以下の点を重点的に確認しましょう。
- 基本セットの内容の詳細
- 追加費用が発生する可能性と、その上限額
- 支払いのタイミング(前払いか後払いか)
- キャンセルした場合の規定と、急な変更への対応
これらのポイントを総合的に判断し、ご家族にとって最適な葬儀社を選ぶことが、満足できる直葬を実現する鍵となります。特に費用面では、単純に安いだけでなく、料金が明確で信頼できる葬儀社を選ぶことが重要です。
たとえば「小さなお葬式」の「小さな火葬式」プランでは、必要最低限の内容をパッケージ化し、追加費用の発生を最小限に抑えた明瞭な料金設定が特徴です。直葬に必要な手続きを一括で任せられるため、初めての方でも安心して依頼できます。
納骨先の確保と将来の供養方法

直葬を選ぶ際は、火葬の後にお骨をどこに納めるか事前に決めておくことが重要です。菩提寺への納骨が難しい場合の代わりの方法を準備しておくことで、あとあとの問題を避けることができます。
| 納骨先 | 特徴 | 費用相場 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 菩提寺 | 先祖代々の墓に納骨可能 | 檀家料・お布施が必要 | 事前相談と承諾が必須、簡単な宗教儀式が条件 |
| 公営霊園 | 宗教的制約が少ない | 比較的安価 | 申し込み時期が限定される場合がある |
| 民営霊園 | 宗旨宗派不問が多い | 比較的高額 | 設備が充実しているが費用負担が大きい |
| 永代供養墓 | 合祀墓・樹木葬・納骨堂など多様な選択肢 | 5万円~200万円程度 | 供養方法により費用と制約が大きく異なる |
| 散骨 | 海洋散骨・山林散骨による自然葬 | 5万円~50万円程度 | 法的制約や環境配慮、許可された場所での実施が必要 |
最も大切なのは、直葬を決める前に納骨先のめどを立てておくことです。とくに菩提寺がある場合は事前に相談し、受け入れてもらえるかどうか確認する必要があります。
直葬の心構えと準備
直葬を選ぶ場合、通常の葬儀とは違った心構えや準備が必要です。シンプルな形だからこそ、故人を大切に思う心が重要となります。儀式の規模ではなく、故人への感謝の気持ちを大切にし、心のこもったお見送りをすることが重要です。
また、経済的な制約を受け入れ、できる範囲でより良い弔いをしようという姿勢も必要です。少人数だからこそ、家族の絆を深める機会と捉えましょう。直葬では大勢の参列者に気を使うことなく、家族だけで故人を偲ぶことができます。
後悔しない選択をするためには、事前の情報収集と準備が欠かせません。
直葬は経済的な制約がある中でも、故人を心を込めてお送りできる選択肢です。ただし、「安いから」という理由だけで選ぶのではなく、故人の意思とご家族の気持ちを最優先に考えることが大切です。限られた予算の中でも準備を怠らず、関係者との調整を丁寧に行いましょう。
故人への想いを大切にする葬儀の在り方

直葬は決して「妥協して選ぶもの」ではありません。限られた予算の中でも、故人への感謝と愛情を込めてお送りできる立派な葬儀のスタイルです。大切なのは残されたご家族が心から故人を偲び、前向きに歩んでいけるかどうかです。
現代社会では葬儀の形も多様化しており、直葬を選ぶご家庭は今後も一定数いると予想されます。経済的な制約があっても、故人との最後の時間を大切にする気持ちこそが、本当の弔いの心なのではないでしょうか。
直葬を選ぶ際は、事前の準備と家族との話し合いを十分に行いましょう。そして葬儀が終わった後も故人を偲ぶ気持ちを大切にし、適切な供養を続けていくことが最良の弔いなのです。







