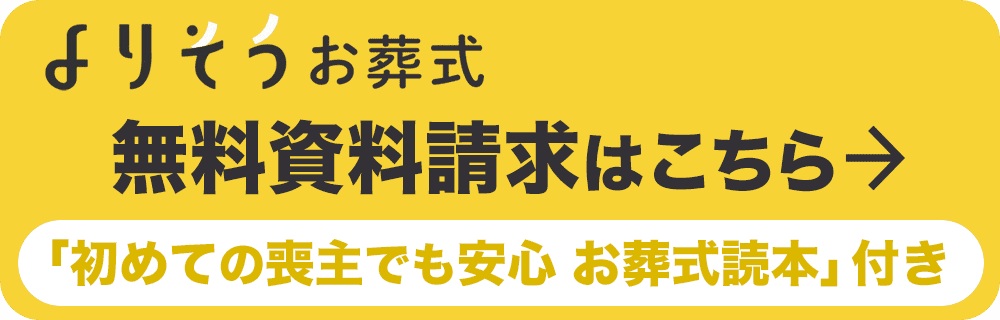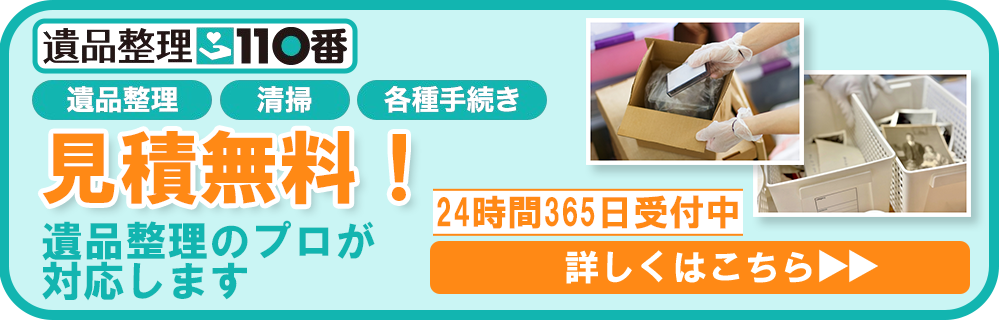![]()

![]()

目次
終活の基本 – 始めるタイミングと目的Q&A

![]()

終活はなぜ必要?どんな目的があるの?
終活は自分の人生のゴールを自分らしく迎えるために行います。
「家族に迷惑をかけたくない」という理由で終活を始める人が最も多く、50代以上では約8割が終活の必要性を感じているとの調査結果[1]があります。
しかし、実際に行動に移せている人は4人に1人程度で、多くの人は必要と感じつつ「まだ早い」と考えて先延ばしにしがちです。
終活は早すぎることはありません。体力や判断力がしっかりしているうちに始めることで、余裕をもって準備ができます。
終活はいつから始めるべき?まだ50代でも早くない?
終活を始めるタイミングに決まりはありませんが、50~60代で関心を持つ人が増えています。
「まだ自分には早い」と思うかもしれませんが、健康なうちに少しずつ準備を進めることをおすすめします。特に定年退職前後は生活の節目として終活を始める良い機会です。
また親世代が高齢の場合、自分自身の終活と並行して親御さんの終活を考える必要が出ることもあります。急な病気や判断能力の低下は誰にでも起こり得ますので、思い立ったときが始め時といえるでしょう。
終活では何をすればいいの?どこから手を付けるべき?
終活でやることは多岐にわたりますが、まず取り組みやすいのは身の回りの整理です。
終活に取り組んでいる人の73.5%が「物の整理・片付け」を実践しており、それが一番の関心事にもなっています。
終活で行うべき主な項目は、次のとおりです。
家財道具や思い出の品など、不要なものを少しずつ片付けます。元気なうちに整理することで、亡くなった後に家族が遺品整理で苦労する負担を減らせます。
通帳・証書類や不動産関連書類、保険証券など重要書類をまとめ、家族にも所在を伝えておきます。財産リストを作成しておくと、相続手続きで家族がスムーズに対応できます。
後述するエンディングノートに、自分の希望や伝えておきたい事柄を書き残します。医療や介護の希望、葬儀やお墓の希望、連絡してほしい人のリストなど、項目ごとに整理して記録します。自治体が無料で配布するノートやテンプレートも活用できます。(参考例:杉並区)
どんな葬儀を望むか、戒名や宗教の希望、お墓をどうするか(先祖代々のお墓に入るか、新たに永代供養墓にするか等)を考えておきます。近年は「家族葬がよい」と希望する人や、「葬儀はしない」という選択を考える人も増えてきています。自分の希望を明確にしておきましょう。
終活の内容について家族や信頼できる人に共有しておくことも大切です。残された家族が戸惑わないよう、元気なうちに希望を伝えておくと安心です。
一度に全て完璧にやろうとせずに、できることから少しずつ取り組むのがコツです。
終活は人生の整理でもあります。早めに始めておけば時間にゆとりをもって進められ、心の整理にもつながるでしょう。
 【終活のすすめ】心も暮らしもすっきり整える方法
【終活のすすめ】心も暮らしもすっきり整える方法
エンディングノートと遺言書 – 書き方と効力Q&A
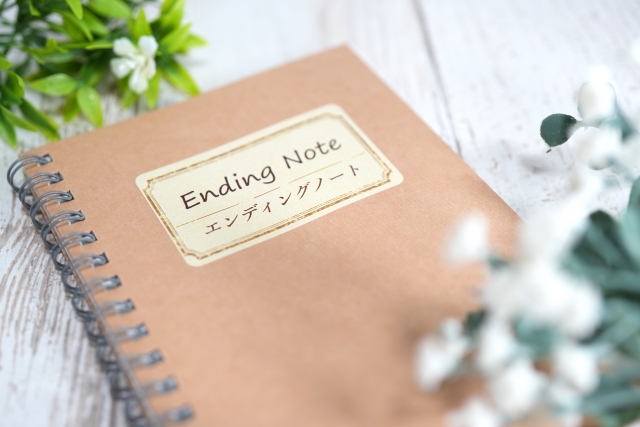
![]()

エンディングノートとは?作る目的はあるの?
エンディングノートとは、自分の希望や大切な情報をまとめて書き記すノートです。
法的効力はありませんが、家族や周囲へのメッセージとして非常に有用です。
たとえば、万一自分に何かあったときに「どんな治療を望むか」「葬儀はどうしたいか」「財産や保険の情報」などを伝えることができます。
自治体や企業も高齢者支援の一環としてエンディングノート作成を推奨しており、杉並区のように無料配布する自治体もあります。
エンディングノートを用意しておけば、もしもの時に家族が迷わず対応でき、自分の意思も尊重してもらいやすくなります。また、生前にノートを書き進める過程で「自分はこれからどう生きたいか」を見つめ直す機会にもなります。
エンディングノートは「自分らしく最後まで生きるための道しるべ」とも言えるでしょう。
エンディングノートには具体的に何を書けばいいの?
エンディングノートには、自分に関する様々な項目を網羅的に書いておきます。
一例として、静岡市が公開しているエンディングノートの主な構成は次の通りです。
- 自分のこと
氏名や生年月日、家族・親族など基本的な情報や自分史。必要に応じて家系図や経歴なども記します。 - これからの人生の希望
今後やりたいこと、会いたい人、伝えたいことなど。人生の目標や楽しみについて書く欄です。 - 医療・介護の希望
延命治療の希望の有無や、認知症になった場合のケアについて、自分の意思を書いておきます。尊厳死や臓器提供についての希望も含まれます。 - 大切な人へのメッセージ
家族や友人、伝えたい相手へのメッセージ欄です。感謝の言葉やお願い事など、自由に記します。 - 葬儀やお墓の希望
葬儀の規模や形式、宗教者の有無や戒名の希望、連絡してほしい人のリスト、埋葬方法(どのお墓に入るか、散骨希望か等)を具体的に書きます。 - 財産・相続の情報
預貯金口座や不動産、保険、負債などの財産リスト、誰に相続させたいかの希望(※法的効力はないため参考情報として)。遺言書を作成した場合はその保管場所も記載します。 - 終活の進め方メモ
自分が行った終活の内容や、今後やる予定のことを書いておく欄です。「〇〇の手続きを済ませた」「△△の準備を検討中」などのメモを残せます。 - 緊急連絡先
もしもの時に連絡してほしい親族・知人や関係機関(かかりつけ医、保険会社など)の連絡先をまとめます。
ノートは最初からすべて埋める必要はありません。思いついたことから書き進め、定期的に見直して更新日を記入しましょう。書いたノートの保管場所は家族に伝えておくと安心です。
エンディングノートは一度書いたら終わりではなく、人生の変化に応じて随時アップデートしながら活用しましょう。
エンディングノートと遺言書の違いは?
エンディングノートは遺言書と違い法的な効力がありません。
そのため、特定の財産を誰に相続させたいかなど明確な遺志がある場合は遺言書の作成が必要です。遺言書があれば法定相続の配分と異なる財産分与が可能で、相続手続きもスムーズになります。
一方、エンディングノートには法的拘束力はないものの、葬儀や介護の希望、遺産以外に伝えたいこと(ペットの世話やデジタル遺産の扱いなど)を自由に書けるメリットがあります。
つまり遺言書は法的手続き用、エンディングノートは気持ちや希望を伝えるコミュニケーション用と考えるとよいでしょう。
両者を上手に使い分け、必要に応じて司法書士・弁護士・行政書士などの専門家に相談すると安心です。
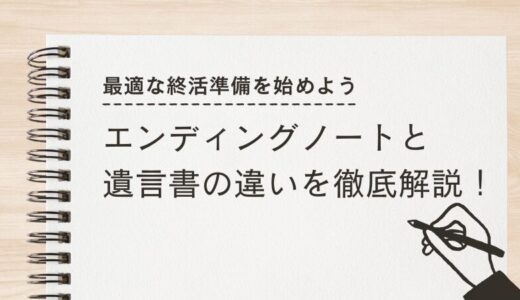 エンディングノートと遺言書の違いを徹底解説!最適な終活準備を始めよう
エンディングノートと遺言書の違いを徹底解説!最適な終活準備を始めよう
葬儀とお金に関する基本 – 形式・費用・準備Q&A

![]()

葬儀の形式には何がある?みんなはどんな葬儀を希望しているの?
現在の葬儀の主流は家族葬などの小規模な形式です。
自分の葬儀は「家族葬」がよいと考える人が46.7%[1]と最多でした。次いで希望者が多いのは通夜を省略した一日葬や火葬のみ行う直葬(火葬式)です。「お葬式はしない(直葬にする)」と考える人も約25%[2]います。
一方で従来型の一般葬を希望する人は減少傾向で、ごく少数派になりつつあります。この背景には高齢化や核家族化で参列者がそもそも少ないことや、費用を抑えたい意向があります。
宗教や地域の慣習によって様々な形式がありますが、「できるだけ簡素に、費用をかけずに送りたい」と望む人が増えているのが現代の傾向です。家族とも相談し、どんな形でお別れしたいか意思を共有しておくとよいでしょう。
 初めてでも迷わない!家族葬の流れと費用 丸わかりガイド
初めてでも迷わない!家族葬の流れと費用 丸わかりガイド
葬儀にはどのくらい費用がかかるの?
式の規模や内容によって幅がありますが、全国平均は約150~160万円と言われます。
ただし、近年は家族葬や直葬の増加で「葬儀費用100万円以下」というケースも増えています。
たとえば、全国展開している「小さなお葬式」では火葬式が税込99,000円(火葬料金別)から利用できます。定額プランが用意されているため、費用が明確で安心です。
また「よりそうお葬式」も人気で、火葬式のシンプルなプランを税込100,100円(火葬料金別)で提供しています。事前の資料請求等で割引があるのも魅力です。
どちらも全国対応のサービスなので、地域に合った葬儀プランを選べます。
葬儀社はどう選べばいい?生前に準備や相談はできるの?
葬儀社選びのポイントは、料金の明確さや対応エリア・実績、そして自分や家族との相性です。
最近はインターネットで情報収集したり、葬儀社紹介サイトの「安心葬儀」などの一括見積比較サービスを利用することも一般的になっています。事前相談を利用し信頼関係を築いておけば、いざという時に心強いでしょう。
生前契約(プレニード契約)という形で葬儀プランを予約しておくこともできますが、急なプラン変更やキャンセルポリシーなど注意点もあります。まずは資料を取り寄せたり無料相談を活用したりして、自分たちに合った葬儀社を見極めておくと安心です。
 小さなお葬式の「生前契約サービス」とは?特徴・流れと終活におけるメリットを解説
小さなお葬式の「生前契約サービス」とは?特徴・流れと終活におけるメリットを解説
公的な給付はある?申請の窓口と期限は?
健康保険の加入者が亡くなった場合、埋葬を行う人に給付金が支給されます。
会社員等で社会保険に加入している場合は「埋葬料(または埋葬費)」の支給があり、定額5万円が基本です
国民健康保険の加入者は、市区町村から「葬祭費」が支給されます。支給額は自治体ごとに異なり、例として大阪市は5万円、世田谷区は7万円となっています。
申請期限や窓口は加入制度・自治体によって異なりますので、必ず勤務先やお住まいの自治体に確認しましょう。
その他の終活 – お墓と身辺整理Q&A

![]()

お墓はどうすればいい?「墓じまい」が増えているって本当?
後継ぎがいない場合や遠方で管理が難しい場合、「墓じまい」を検討してもよいでしょう。
墓じまいを行う場合、現在のお墓から遺骨を取り出して改葬先(新しい供養先)に移すことになります。改葬先としては、次のような例があります。
- 永代供養墓
寺院や霊園が永続的に供養してくれる合同墓 - 納骨堂
故人の遺骨を安置・供養するための屋内施設
- 樹木葬
樹木を墓標とする埋葬方法 - 散骨
海や山への遺灰散布
最近は墓じまいの専門業者も登場しており、行政手続きや墓石の撤去、永代供養先の紹介までワンストップで対応してくれます。
例えば「わたしたちの墓じまい![]() 」は、2002年の創業から800件以上の実績をもつ墓じまい専門サービスです。全国対応で寺院との交渉代行から墓石撤去、改葬手続き、永代供養先の手配まで一括して行います。
」は、2002年の創業から800件以上の実績をもつ墓じまい専門サービスです。全国対応で寺院との交渉代行から墓石撤去、改葬手続き、永代供養先の手配まで一括して行います。
対応が丁寧で料金も良心的、トラブルなく円満に墓じまいできると利用者から高く評価されています。
お墓の問題はデリケートだからこそ、早めに家族と話し合って希望を共有しておくことが大切です。
自宅や持ち物の整理はどう進めればいい?プロに頼む手もある?
「思い出の品だけど自分しか価値が分からないもの」や「使っていない衣類・家具」などは処分や譲渡を検討しましょう。
身の回りの整理整頓(生前整理)は終活の基本です。少しずつ無理のない範囲でよいので、継続することがポイントです。。
重要書類や貴重品はわかりやすく整理し、何がどこにあるかリストを作っておくと安心です。
大量の片付けや大型家具の処分などは、専門の業者に依頼する方法もあります。近年は「遺品整理」「生前整理」を専門とするサービスが各地にあり、プロの手で迅速かつ適切に整理してもらえます。
例えば「遺品整理110番![]() 」というサービスは全国にネットワークを持ち、24時間365日対応で遺品整理・生前整理から特殊清掃まで請け負っています。
」というサービスは全国にネットワークを持ち、24時間365日対応で遺品整理・生前整理から特殊清掃まで請け負っています。
料金は物量や作業内容によりますので、見積もりをとって検討してみましょう。
なお、デジタル時代の終活では「デジタル遺品の整理」も重要です。
- パソコンやスマホ内の写真・連絡先・SNSやメールアカウント情報の整理
- 契約サービスの整理
- 家族にID・パスワード・アクセス方法を伝える
- SNSの「追悼アカウント機能」の活用を検討
紙にIDやパスワードを書き残す場合は、盗難・紛失に注意しましょう。デジタル資産も含めて整理しておくことが、現代の終活には欠かせません。
 デジタル終活完全ガイド|SNSやネット口座、そのままで大丈夫?
デジタル終活完全ガイド|SNSやネット口座、そのままで大丈夫?
終活にお金はどれくらい必要?保険や供養費用の準備は?
終活そのものに多額の費用はかかりませんが、葬儀費用やお墓の費用など将来かかるお金の準備は計画しておきましょう。
葬儀費用は預貯金や生命保険で備えるのが一般的です。たとえば終身保険に入っておき、死亡保険金を葬儀代にあてる方も多いです。
また、葬儀社の中には生前相談で葬儀費用を前払いできる契約(互助会・プレニード契約)ができるところもあります。ただし途中解約時の手数料や対応エリアの制限などもあるため、利用する際は規約をよく確認しましょう。
お墓については、墓地の永代使用料や墓石代、管理費など維持費も必要です。もしお墓を新たに求める予定なら、墓地の種類によって費用が大きく異なります。
昨今人気の樹木葬や納骨堂は比較的費用を抑えられる傾向がありますが、それでも数十万円~が一般的です。
 自然葬の種類と手続き|海洋散骨・樹木葬・宇宙葬の完全ガイド
自然葬の種類と手続き|海洋散骨・樹木葬・宇宙葬の完全ガイド
また、墓じまいをする場合は墓石の解体撤去費用や離檀料、改葬先への費用が発生しますが、これも規模によってまちまちです。
 墓じまいの進め方 ~費用や改葬手続き、親族への説明ポイント~
墓じまいの進め方 ~費用や改葬手続き、親族への説明ポイント~
そのほか、遺品整理や不動産の処分費用も見込んでおくと安心です。
必要に応じてファイナンシャルプランナー等に相談し、無理のない範囲で備えを整えてください。
自分らしい最期に向けて準備を進めよう

人生の終わりの準備というと寂しい印象があるかもしれませんが、終活は「残りの人生をより充実させる」きっかけにもなります。
大切なのは一人で抱え込まず、家族や専門家と相談しながら少しずつ進めることです。準備が整えば心にゆとりが生まれ、これからの毎日を安心して過ごせるでしょう。
今日できる小さな一歩から始めて、あなたらしい最期の迎え方をじっくり描いてみてください。
出典
参考リンク
- 杉並区「杉並区エンディングノートについて」
- 大阪市「葬祭費の支給」
- 世田谷区「葬祭費の支給」
- 静岡市「エンディングノート~これからの人生を豊かにしていくために~」
- 全国健康保険協会 協会けんぽ「ご本人・ご家族が亡くなったとき」