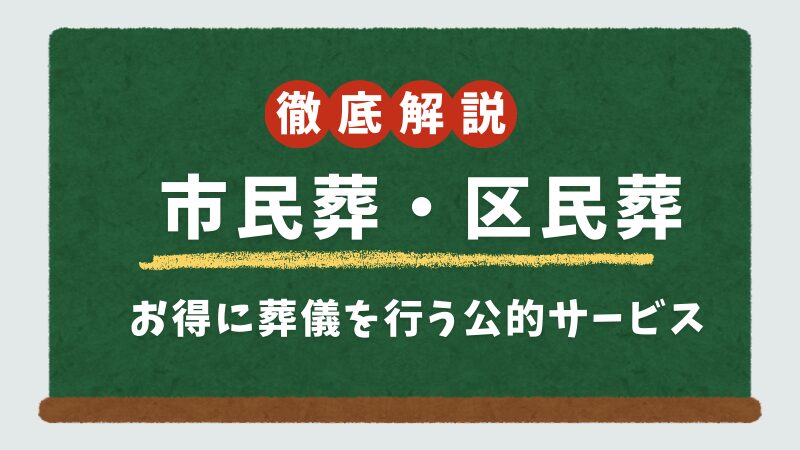葬儀費用の負担を少しでも減らしたい…そんなときに検討したいのが「市民葬」「区民葬」「規格葬儀」といった自治体の葬儀制度です。これは各自治体(市区町村)が地域の葬儀社と提携し、地域住民が比較的安い費用で葬儀を行えるようにしたサービスです。普段あまり積極的に宣伝されていないため、ご存知ない方も多いかもしれませんが、条件が合えば葬儀費用の一部を大きく節約できる可能性があります。この記事では、この制度の概要や対象者、東京都23区の区民葬と大阪市の規格葬儀の仕組み・申込方法・費用などを中心に、メリット・デメリットや手続きの流れをわかりやすく解説します。
市民葬・区民葬・規格葬儀の制度概要
市民葬・区民葬・規格葬儀は、自治体と葬儀社が協力して提供している定額・低負担の葬儀プランです。自治体が直接葬儀を執り行うわけではなく、自治体と契約した地元の葬儀社が決められた規格・料金で葬儀サービスを提供します。例えば川崎市の市民葬儀制度では、規格A(基本料金49万5,000円)と規格B(基本料金20万9,000円)という2種類のプランがあり、それぞれ決められた祭壇や棺、人件費など必要最低限の内容が含まれています。ただし火葬料や霊柩車での搬送費用、お布施などの宗教者への謝礼は基本料金に含まれず別途必要です。
名称は自治体によって様々で、一般的に市が行う場合は「市民葬」、東京23区のように特別区が行う場合は「区民葬」、大阪市のように「規格葬儀」と呼ぶケースもあります。いずれも趣旨は同じですが、提供されるプラン内容や料金体系は自治体ごとに異なります。また、全国すべての自治体で実施されているわけではなく、制度を設けている自治体もあれば廃止された地域もあり、対応はまちまちです。制度があるかどうかはお住まいの市区町村の公式サイトや窓口で確認できます。
歴史と背景
この公的葬儀制度は、戦後間もない生活が苦しい時代に生まれました。東京では戦後すぐ、葬祭業協同組合が東京都に働きかけ、通常より安価な「都民葬」という仕組みを作ったのが始まりです。のちに運営主体が東京都から23区に移され、現在の「区民葬儀」に至っています。なお、この制度は自治体が費用を補助するものではなく、あくまで参加葬儀社の奉仕精神によって割安料金が設定されているのが特徴です。
利用できる人(対象条件)
市民葬・区民葬・規格葬儀はその自治体に住民登録がある方が利用できます。自治体によって細かな条件は異なりますが、一般的には以下のいずれかを満たす場合に利用可能です。
-
故人(亡くなった方)が生前にその自治体に住民登録していた場合
-
喪主(葬儀を主催する人)がその自治体に住民登録している場合
自治体によっては、上記に加え外国人登録をしている住民も対象に含めていたり、実際に地域内の公営斎場・火葬場を利用することを条件としている場合もあります。たとえば東京都23区の区民葬では、故人または葬儀を執り行う親族が23区内の住民であれば利用でき、かつ区から「区民葬儀利用券(葬儀券)」を発行してもらう必要があります。大阪市の規格葬儀では大阪市民であることが条件で、申込み時に「大阪市規格葬儀を利用したい」旨を伝えることで適用されます。
また注意点として、葬儀後の事後申請は認められない自治体が多いです。利用したい場合は必ず葬儀を行う前に申請や手続きを行う必要があります。利用方法は自治体によって多少異なりますが、次章から東京都23区と大阪市の具体的な制度と手続きを見ていきましょう。
東京都23区の「区民葬」

東京都23区では、各区が区民葬儀の制度を設けており、23区内に住む方であればどなたでも利用できます。区民葬儀は自治体と東京の葬儀社団体(東京都葬祭業協同組合など)が協力して運営されており、区から直接の補助金が出るわけではありませんが、提携葬儀社が定められた内容で葬儀を執り行います。
利用条件と申し込み方法
利用条件: 故人または喪主となるご遺族が東京都23区内の住民であることが前提です。例えば故人が他県在住でも、喪主が23区在住であれば利用可能です(逆の場合も各区に確認しましょう)。
申し込み手続き: 区民葬を利用する場合、以下のような流れで手続きを行います。
-
指定の葬儀社に区民葬儀で依頼することを連絡します。各区には「区民葬儀取扱指定店」となっている葬儀社がありますので、その中から希望の葬儀社を選び、「区民葬でお願いしたい」と伝えます。葬儀社がまだ決まっていない場合は、東京都葬祭業協同組合に問い合わせれば紹介してもらえます。
-
死亡届を区役所に提出する際、区民葬儀利用券(葬儀券)を受け取ります。死亡届提出時に職員に「区民葬を利用したい」と申し出ると、区役所の担当課で葬儀券が発行されます。発行には医師の死亡診断書の提示が必要です。
-
葬儀社に葬儀券を渡します。依頼した葬儀社へ葬儀券を提出することで、区民葬の規定料金が適用されます。葬儀社側で区への手続きを代行してくれる場合もあります。
各区とも基本的な流れは同じですが、詳細は区役所によって異なる場合があります。葬儀券の申請書類提出方法などは事前に各区役所に確認すると安心です。
区民葬の費用プラン
東京都23区の区民葬では、4種類の祭壇プラン(A1・A2・B・C券)が用意されています。いずれも祭壇と棺がセットになったプランで、祭壇の規模や棺の種類によって料金が異なります。以下が区民葬儀の祭壇プラン料金(税込)です。
| プラン券種 | 内容(祭壇規模) | 料金(税込) |
|---|---|---|
| A1券 | 金襴(きんらん)5段飾り祭壇+桐張棺(高級棺) | 312,180円 |
| A2券 | 金襴4段飾り祭壇+桐張棺 | 259,600円 |
| B券 | 白布3段飾り祭壇+プリント棺 | 136,400円 |
| C券 | 白布2段飾り祭壇+プリント棺 | 100,100円 |
※祭壇の名称「金襴○段飾り」は装飾の華やかさを示し、A1が最も大きく豪華な祭壇、C券が最も簡素な白布祭壇です。桐張棺は桐の薄板を貼った棺、プリント棺はプリント模様の比較的廉価な棺です。サイズは通常6尺棺(内寸170cm程度)を想定しています。
なお、故人の身長が高かったり体格が大きい場合には「長尺棺」(約185cm程度の大型棺)を使用する必要があります。その場合は上記料金に棺の差額分が追加され、例えばA1券は325,380円(税込)、C券は135,300円(税込)になるなど少し割高になります。
その他の定額費用: 区民葬では祭壇・棺プラン以外にも、葬儀に必要ないくつかの費用が定められています。代表的なものは霊柩車(遺体搬送車)料金、火葬料金、骨壺(遺骨収納容器)代です。それぞれ区民葬利用者向けに次のような規定料金があります。
-
霊柩車運送料金(23区内): 普通霊柩車(洋型)の場合10kmまで19,220円、20kmまで23,840円。宮型霊柩車(和風の屋根付き車)の場合10kmまで37,400円。(距離超過時は加算あり)
-
火葬料金(民営火葬場): 大人1体 59,600円、小人(6歳以下)34,500円。東京23区は民営火葬場が多く火葬料が有料ですが、この料金は標準的な等級での定額料金です(非課税)。
-
遺骨収納容器代(骨壺一式): 大人用2号骨壺一式 11,900円、3号(少し小さめ)10,780円、子供用6号 2,530円。
区民葬の総費用は、「祭壇・棺プラン」+「霊柩車料」+「火葬料」+「骨壺代」の合計になります。例えば最も簡素なC券プランを利用し、普通霊柩車で火葬場まで搬送・大人火葬・骨壺2号とした場合、約100,100+14,160+53,100+10,900 ≒ 178,000円となります(別途かかる費用は除く)。一方、A1券プランで宮型霊柩車・火葬・骨壺を利用すれば30万円台後半になる計算です。通常、一般的な葬儀費用の平均は120万円程度とも言われますので、規模を抑えればかなり費用負担を軽減できることがわかります。
区民葬で含まれない費用
注意したいのは、区民葬=すべてコミコミの格安プランというわけではない点です。区民葬で定額になるのは先述の祭壇・棺、霊柩車、火葬場、骨壺に関わる費用のみで、それ以外の費用は含まれていません。別途必要になる代表的な費用の例を挙げます
-
ドライアイス代(ご遺体の安置・保全に必要)
-
遺影写真代(葬儀用の額入り写真)
-
会葬礼状の印刷費(参列者へお礼状)
-
返礼品の費用(会葬御礼の品物)
-
通夜や告別式での飲食接待費(通夜振る舞い等)
-
供花・供物の費用(飾り花や果物籠など)
-
式場使用料(自宅以外の式場を借りる場合)
-
テントや受付設営費(自宅葬で玄関先にテントを張る等)
-
ハイヤー・マイクロバス代(火葬場へ参列者を送迎する車両)
これらは葬儀の規模や形式によって必要なものですが、区民葬プランには含まれないため各葬儀社ごとに実費となります。そのため、たとえ区民葬を利用しても、オプションを色々追加していけば費用は増えていきます。場合によっては、民間の一般葬儀社が提供する直葬(火葬式)や家族葬の低価格プランと同程度か、内容次第ではそれ以上の費用になる可能性もあります。区民葬を利用する際は「含まれるのは最低限のものだけ」と認識し、不足する部分の費用をあらかじめ見積もっておきましょう。
大阪市の「規格葬儀」

次に、大阪市が提供している「規格葬儀」制度について見てみましょう。大阪市規格葬儀は、大阪市民を対象に市内の指定葬儀社が提供する公定価格の葬儀プランです。東京の区民葬と同様に、市民の葬儀費用の負担軽減を目的としており、大阪市内の多数の葬儀社(現在71社)が取扱指定店として登録されています。
利用条件と申し込み方法
利用できる方: 大阪市内に住所がある大阪市民の方が対象です(大人=10歳以上、小人=10歳未満と定義)。故人または喪主が大阪市民であれば利用可能と考えてよいでしょう。
申し込み方法: 東京都の区民葬と違い、葬儀券の交付など役所での手続きは特に必要ありません。大阪市の規格葬儀指定店名簿の中から希望の葬儀社を選び、直接葬儀社に「規格葬儀を利用したい」と申し込むだけで手続き完了です。指定店一覧は大阪市の公式HPやパンフレットで公開されており、電話一本で申し込めます。申し込みの際は必ず「規格葬儀希望」であることを伝え、見積書を受け取って内容を十分確認してから正式依頼するよう大阪市も案内しています。葬儀社側で市への届け出等を行い、規格葬儀の契約に沿った価格・サービスで進めてくれます。
規格葬儀の費用プラン
大阪市規格葬儀には、プランの名前として「百合(ゆり)」と「桔梗(ききょう)」という2種類のコースが用意されています。それぞれ祭壇規模や付帯サービスの充実度が異なるプランで、費用も異なります。料金は大人(10歳以上)と小人(10歳未満)で区分されています。
-
百合プラン: 大人 356,180円(税込) / 小人 335,170円(税込)
-
桔梗プラン: 大人 204,270円(税込) / 小人 183,260円(税込)
百合は桔梗よりも費用が高い分、祭壇や付帯設備がより充実したプランになっています。一方、桔梗は必要最低限の飾り付けに抑えた簡素なプランです。どちらも通夜・告別式を前提とした一般的な仏式葬儀に対応する内容となっています。
規格葬儀のサービス内容と含まれないもの
大阪市規格葬儀で提供されるサービス内容は、主に遺体の搬送・納棺などの処置、葬祭用品の提供、祭壇の飾り付け、式場や火葬場の手続き代行といった一連の葬儀施行に必要な項目です。両プランに共通する基本内容として、寝棺一式(棺、仏衣、棺台など)、位牌、焼香設備一式、枕飾り一式、式進行係などスタッフ手配などが含まれます。
その上で、百合プランには以下のような備品・サービスが含まれています。
-
門前飾り付け: 故人名の看板(尊名札)、日付看板、玄関飾り、提灯台、祭壇幕など
-
祭壇飾り付け: 白布付き祭壇、白絹幕・鯨幕など複数種の幕、経机(経台)、位牌台、掛軸、香炉・香鉢、両袖飾り花 など
-
その他設備: 音響設備(マイクやスピーカー)、受付用テント・机・椅子、記帳帳簿、必要貼紙類(受付案内や忌中札)、納棺・飾り付けスタッフ、式進行スタッフ など
桔梗プランに含まれる内容は百合より簡素で、例えば門前飾りは日付札と幕のみ、祭壇飾りも鯨幕や掛軸など最低限にとどまります。受付設備や音響も含まれません。ただし、棺や位牌など葬儀の根幹部分は百合と同等のものが含まれています。
含まれない費用: 大阪市規格葬儀でも、遺影写真代はプランに含まれていないため別途用意が必要です。また、宗教者へのお布施や通夜・告別式での飲食接待費、火葬料金、斎場(式場)使用料、搬送用の寝台車料金、火葬場への霊柩車費用などはプラン外です。大阪市内の公営斎場(瓜破斎場など)の火葬料は、実は大阪市民の場合無料(札幌市など一部自治体同様に市民は火葬料が免除)となっており費用負担はありませんが、式場を使用する場合は別途式場使用料が発生します(公営斎場併設式場の場合、例:大式場半日18.7万円など規模・時間帯で料金設定あり)。必要に応じて寝台車やタクシーでの病院からの搬送費、火葬場へのマイクロバス手配等も別料金となります。
宗教形式: 規格葬儀は原則として仏式のみを想定した内容になっています。キリスト教式や神道式で葬儀を行いたい場合、規格葬儀指定店の葬儀社と相談のうえ、可能な範囲で対応してもらう形になります。仏式以外だからといって割引がなくなるわけではありませんが、用意された祭壇等が仏教前提である点に留意しましょう。
以上のように、東京23区の区民葬と大阪市の規格葬儀は細部は異なりますが、「祭壇や棺など基本セットを定額で提供し、その他必要に応じて実費負担」という点では共通しています。それでは、このような公的葬儀制度を利用するメリットとデメリットを整理してみます。
市民葬・区民葬・規格葬儀のメリットとデメリット
公的な葬儀制度には良い点もあれば注意点もあります。利用を検討する際にメリットとデメリットの両面を押さえておきましょう。
メリット
葬儀費用の一部負担を大きく抑えられる
最低限の祭壇や棺がセットになっているため、一般的な葬儀と比べると大幅に安い価格で葬儀を行える可能性があります。自治体と提携葬儀社との協定により霊柩車や火葬料金が割引になっている場合もあり、トータルで見ると経済的負担の軽減につながります。
自治体お墨付きの葬儀社なので安心感がある
自治体が提携する葬儀社は一定の基準をクリアした地元の業者です。公的な制度に参与していることで信頼性が担保されており、「葬儀社選びに失敗して高額請求されるのでは…」といった不安も和らぐでしょう。
簡素な葬儀ニーズにマッチする
「盛大な葬儀ではなく簡素で構わない」「費用をできるだけ抑えて火葬だけ行いたい」といった希望の場合、公的プランのシンプルな内容がちょうど合うケースもあります。例えば最小限の直葬プラン(東京C券など)であれば、本当に最低限の儀式で送りたいというニーズに沿った内容です。
デメリット
想像以上に質素な内容になることがある
市民葬・区民葬は費用を抑えるため祭壇や棺も非常にシンプルなものです。昨今主流の生花祭壇などに慣れた感覚で利用すると、「かなり質素で物足りない」と感じる可能性があります。制度上、白木祭壇など昔ながらの様式が基本のため、遺族の希望で柔軟に変更するといったことが難しい面もあります。現代的で自由な演出を求める場合、公的プランでは対応できないことが多い点に注意が必要です。
結局追加費用が多く発生しがちである
前述のとおり、プラン外の費用(ドライアイスや料理代など)は別途かかります。必要最低限のセット以外はオプション扱いのため、要望に合わせて追加していくとメリットを上回る出費になる恐れもあります。細かな部分にこだわってオプションを足していくと、一般的な葬儀社の低価格プランより高くなる場合もあることを心得ておきましょう。
葬儀社やプランの選択肢が限定される
利用できる葬儀社は自治体指定の業者に限られます。馴染みの葬儀社があっても指定店でなければ依頼できません。またプラン内容も規格で決まっているため、「祭壇は豪華にしたいが費用は抑えたい」といった都合の良いカスタマイズは難しく、葬儀の自由度は低くなります。
利用できる自治体が限られる
住んでいる地域によってはそもそも制度自体がなかったり、あっても内容が十分でない場合もあります。特に東京23区や政令市以外では実施していない市町村も多く、その場合はこの制度は利用できません。
以上を踏まえると、公的葬儀制度は「費用を抑えるために内容を簡素化する」ことを受け入れられる場合に有用と言えます。一方で、ある程度しっかりお葬式をしたい気持ちがある場合は、結果的にオプション追加で高くつく可能性も念頭に置きましょう。
まとめ:上手に公的葬儀制度を活用するポイント
市民葬・区民葬・規格葬儀は、公的な仕組みを利用して葬儀費用を軽減できる有難い制度です。対象地域にお住まいで質素なお葬式でも構わないという方にとっては、大いに検討する価値があります。実際、東京23区の区民葬C券+必要最低限で済ませれば20万円前後、大阪市の規格葬儀(桔梗)でも火葬料無料を活かせば同程度で葬儀を行うことも可能でしょう。
その一方で、「できるだけ安くしたいが、ここだけは外せない」というポイントもそれぞれあると思います。公的プランにこだわりすぎず、民間の葬儀社が提供する低価格プランとの比較検討もおすすめします。昨今は家族葬や直葬専門の格安プランを用意している葬儀社も多く、内容次第ではそちらの方が総額が安くなるケースもあります。公的制度だから必ずしも最安とは限らない点も覚えておきましょう。
公的制度を利用する際のポイント
事前に制度の有無を確認する
まずお住まいの自治体にこの制度があるか公式サイト等で確認します。あれば概要や指定葬儀社リスト、申請方法を調べましょう。自治体の窓口や24時間受付の葬儀社紹介ダイヤルがある場合もあります。
早めに申し出る
利用するには死亡届提出時までに手続きが必要な場合があります。葬儀社へ依頼する段階で早めに「市民葬(区民葬)希望」と伝え、役所手続きも忘れずに行いましょう。
他の公的補助も活用する
健康保険や自治体から支給される葬祭費・埋葬料制度も忘れず申請しましょう。例えば故人が国民健康保険または後期高齢者医療に加入していた場合、葬儀を行った人(喪主)が申請すると葬祭費(葬儀費用の給付金)を受け取れます。自治体によりますが5万円程度が支給されることが多いです。ただし直葬など簡易な葬儀形態では支給対象外となる場合もあるので確認してください。また、喪主が生活保護受給者の場合は葬祭扶助という形で葬儀費用そのものの援助を受けられる制度もあります。
条件が重複する場合は比較検討
もし故人の住所地と喪主の住所地が異なり双方に制度がある場合、どちらの制度を使うか選べるケースもあります。例えば「故人はA市民だが喪主(子)はB市民」という場合、A市・B市両方の市民葬制度を調べて有利な方を使う、といったことも可能です(ただし実際に葬儀を行う地域でしか使えないため、現実的には火葬をどこで行うかなども関係します)。このように条件が重なる場合は両方の自治体の制度内容を確認してみましょう。
最後に、大切なのは「経済的な安心」と「ご遺族が納得できるお見送り」のバランスです。公的な葬儀制度は費用面で心強い味方となりますが、無理にそちらに合わせて後悔が残っては本末転倒です。自治体の担当窓口や提携葬儀社に相談しながら、ぜひご希望に合ったかたちで故人を送り出してあげてください。必要とあれば民間の葬儀プランも含めて比較検討し、「安くできてよかった」と思えるお葬式にできるよう情報を活用してみてください。