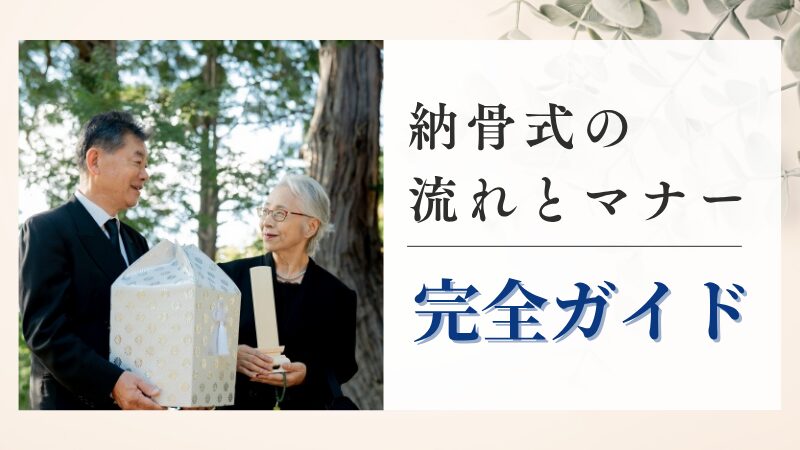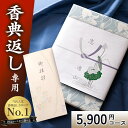納骨式は、故人のご遺骨をお墓などに納める大切な儀式です。初めて納骨式を迎える遺族にとっては、「どんな手順で進むのか」「服装や持ち物は何を準備すべきか」「マナー違反にならないか」など不安が多いことでしょう。
特に最近では、お墓が遠方にあったり遺骨を手元に置いて供養したいなどの理由で、ご遺骨を親族間で分ける分骨をするケースも見られます。
本記事では、納骨式の進行手順と作法について、僧侶の読経から遺骨の納め方、喪主や遺族の振る舞い、必要な持ち物に至るまで順を追って解説します。併せて参列者の服装・香典マナーや法要後の会食のポイントにも触れますので、納骨式の流れとマナーを押さえて不安を解消しましょう。
納骨式とは何をする儀式?

納骨式とは、故人のご遺骨をお墓や納骨堂など所定の場所に埋葬するための儀式です。葬儀・火葬が終わった後、四十九日法要に合わせて執り行われるのが一般的ですが、厳密な時期の決まりはありません。
ここでは納骨式の基本知識として、その意味や時期、そして昨今増えている「分骨」について解説します。納骨式の意義を理解し、適切なタイミングで執り行えるようにしましょう。
納骨式の意味と役割
納骨式(納骨法要)は、火葬後に骨壷に収めた故人の遺骨を正式にお墓などへ納める儀式です。僧侶にお経をあげてもらい、遺族や親しい人々が集まって故人の供養と埋葬を行います。
葬儀が「お別れの儀式」だとすれば、納骨式は故人を先祖代々の眠る場所や供養の場に安置し供養を続けていくための儀式と言えます。仏教では四十九日の忌明けに行われることが多く、これを一区切りとして遺族が日常生活に戻る意味合いもあります。
 遺骨の納め方で迷わない!納骨式と供養方法徹底比較【決定版】
遺骨の納め方で迷わない!納骨式と供養方法徹底比較【決定版】
納骨式を行う時期
納骨式をいつ行うかについて明確な法律上の期限はありませんが、一般的には故人の49日目の忌明け法要(四十九日法要)に合わせて行うケースが多いです。
四十九日法要は故人が極楽浄土へ無事旅立てるよう祈る大切な仏事で、納骨式はその後に執り行われるのが習わしです。ただし、49日までにお墓の準備が整わない場合や、遺族の心の整理がつかない場合は、無理に四十九日にこだわる必要はありません。
初盆(初めてのお盆)や百箇日、一周忌や三回忌など、故人の命日に合わせて納骨式を後日に行うこともあります。大切なのは遺族が納得できるタイミングで行うことであり、葬儀直後や火葬当日に納骨を済ませるご家庭もあれば、遅くとも三回忌までに納骨するのが望ましいとも言われます。
納骨式の意義
納骨式は、故人の遺骨を正式にお墓などに納めて供養を継続していく重要なセレモニーです。
時期は四十九日後が一般的ですが、遺族の状況に応じて柔軟に選べます。お墓の準備が整っていない場合や遠方である場合は、無理をせず一周忌や三回忌までに行えば問題ありません。最近増えている分骨も適切な手続きを踏めば認められた供養方法です。
まずは納骨式の意味とタイミングを正しく理解し、ご家族で納得できる計画を立てましょう。
納骨式当日までに準備すること

滞りなく納骨式を執り行うためには、事前準備を念入りに行っておくことが肝心です。施主(喪主)として日程調整や関係者への連絡、お墓・遺骨の準備、必要な持ち物の手配など抜け漏れがないようにしましょう。
ここでは納骨式当日までに準備すべきことを具体的に解説します。早め早めの準備で心の負担を減らし、当日を安心して迎えられるようにしましょう。
日程の決定と寺院への依頼
まずは納骨式を行う日程を決めます。付き合いのあるお寺として菩提寺がある場合は、僧侶の都合を確認して日程を調整しましょう。お盆や彼岸の時期は僧侶の予定が埋まりやすいため、早めの連絡が大切です。
寺院に依頼する際には、卒塔婆(塔婆)が必要かどうかも確認します。宗派によってはお墓の後ろに立てる供養の塔婆を用意する習慣があり、その場合は戒名や命日を記した卒塔婆の手配をお寺にお願いしておきます。なお、浄土真宗では卒塔婆は用いません。
菩提寺がない場合でも、納骨式のみ僧侶に読経をお願いすることは可能です。その際は地域の寺院に相談するか、僧侶手配サービスを利用するとよいでしょう。
たとえば「よりそうお葬式![]() 」では、「よりそうお坊さん便」という僧侶の手配サービスを提供しています。全国どこでも僧侶を派遣してもらえて、料金も明瞭なので安心して依頼できます。
」では、「よりそうお坊さん便」という僧侶の手配サービスを提供しています。全国どこでも僧侶を派遣してもらえて、料金も明瞭なので安心して依頼できます。
 初めての喪主でも安心!『よりそうお坊さん便』徹底ガイド【僧侶手配】
初めての喪主でも安心!『よりそうお坊さん便』徹底ガイド【僧侶手配】
参列者への案内と招集
日程が決まったら、納骨式に来ていただきたい親族や関係者へ案内を出します。規模にもよりますが、身内だけで行うなら電話連絡でも問題ありませんが、親族以外も招く場合はハガキやメールで案内状を送ると丁寧です。
連絡事項としては、納骨式を行う霊園名や区画番号などの日時・場所、集合時間・集合場所、施主の連絡先、服装の案内(略礼服で良いか等)を伝えておきます。
当日会食を行う場合はその旨も知らせ、香典を辞退する場合は予め案内状に記載しておくと親切です。
高齢の参列者には送迎の手配や足元の悪い霊園の場合の注意喚起など配慮しましょう。遠方から来る親族がいる場合は、日程だけでなく開始時間帯にも配慮し、無理のないスケジュールを心がけます。
お墓と遺骨の準備・必要書類の確認
納骨式を迎えるまでに、お墓の準備を整えておきます。すでに先祖代々のお墓がある場合でも、墓誌(墓碑)に故人の名前や没年月日・享年を刻む手配が必要です。石材店に戒名の彫刻を依頼する際は時間がかかるため、日程決定後できるだけ早く依頼しましょう。
新しくお墓を建てる場合は開眼供養の日程も考慮しつつ準備します。また、墓石下の納骨室(カロート)の石蓋を開ける作業は素人では難しいため、石材店に納骨室の開閉作業を依頼しておくのが一般的です。霊園や墓地の管理事務所にも、何日に納骨を行うか事前連絡し、必要なら当日の立会いを依頼します。
加えて、忘れてはならないのが「埋葬許可証」(火葬場で交付される火葬済み証明書)です。遺骨をお墓に埋葬するには埋葬許可証の提出が法律上必須であり、これが無いと納骨できません。火葬後に役所や火葬場から受け取った埋葬許可証は大切に保管し、納骨式当日に必ず持参します。霊園によっては墓地使用許可証や墓所の鍵、認印などが必要な場合もあるため、事前に確認しましょう。
納骨する遺骨は、火葬後から納骨まで自宅で大切に安置します。納骨式当日は骨壷の汚れを拭き清め、風呂敷で丁寧に包んで持参するとよいでしょう。
お供え物・返礼品・会食の手配
納骨式当日に墓前に供えるお供え物も準備しておきます。基本的に制限はありませんが、生花や故人の好物だったお菓子・果物、酒、水、丸餅などを用意するのが一般的です。ただし公営霊園などではアルコール類のお供えを禁止している場合もあるため、事前に霊園のルールを確認しましょう。
線香・ローソク・マッチやライターも忘れずに準備します。風で火が消えやすい野外では、風防付きのローソク立てがあると便利です。
施主は参列者からいただく香典への返礼品(香典返し)も用意しておきます。香典返しはいただいた金額の3分の1〜半額程度が目安で、日持ちするお菓子やお茶、コーヒー、タオルなどの消えものを選ぶのが一般的です。
最近ではカタログギフトを用いるケースも増えています。法要当日に渡せるよう、熨斗(のし)に「志」または「忌明」など表書きをして準備しましょう。
さらに、会食を行う場合は会食会場や仕出し料理の手配も必要です。四十九日法要と同日に納骨式を行う場合は、その後の精進落としの席を用意するケースが多いです。会食の場所は霊園近くの和食処や自宅、菩提寺の客殿など落ち着いた雰囲気の場所が適しています。
出席者の人数を把握し、料理の内容は法要後であることを伝えて相談するとよいでしょう。高齢者や子供の出席がある場合は椅子席がある会場を選ぶ、遠方から来る方のために開始時間をゆったりめに設定する、といった配慮も大切です。
事前準備を万全にして安心を
納骨式当日までに余裕を持って準備を整えておけば、当日の進行に集中でき安心です。日程の調整は早めに行い、寺院や霊園、親族への連絡をきちんと済ませましょう。
お墓の開封作業や戒名彫刻などは専門業者への依頼が必要です。また、埋葬許可証などの書類や骨壷、線香・供物といった持ち物も前日までにチェックしておきます。
香典返しや会食の準備も含め、リストを作って一つひとつ段取りすれば抜け漏れ防止になります。万全の事前準備によって、納骨式当日は心静かに故人を偲ぶことに専念できるでしょう。
納骨式当日の流れ

いよいよ納骨式当日です。ここでは、納骨式当日の一般的な進行手順を説明します。会食の時間を除くと、当日の式自体は通常1時間程度で終了します。
寺院で読経を行う場合や参列者数によって多少前後しますが、おおむね次のような順序で進行します。当日の流れを把握し、所作に迷わないようにしておきましょう。
1. 墓前の準備とお供えの設営
まず、お墓の前で祭壇や供物の準備を行います。
霊園に到着したら施主や遺族は墓石の前を清掃し、持参した生花を花立てに供え、線香皿やローソク立てをセットします。墓前には故人のための水やお酒を入れた器、故人の好きだったお菓子や果物などのお供え物を並べます。
同時に、墓石の納骨室(カロート)を開けられる状態にしておくことも重要です。事前に石材店へ依頼してある場合は、石材店担当者がこの時点でカロート石の蓋を開けて待機してくれているでしょう。もし遺族自身で開閉する場合は、墓石の構造を事前に確認し、六角レンチや専用フックなど必要な道具を用意しておきます。
以上の準備が整ったら、参列者には墓前に集まり式開始を待ちます。遺骨の入った骨壷は施主または喪主が持ち、所定の位置に立ちます。多くの場合、墓前か焼香台の側に遺骨安置台が用意されます。
準備段階で不明な点があれば、この時までに僧侶や霊園スタッフに確認しておきましょう。
2. 施主による開式の挨拶
墓前での準備が整ったら、施主(喪主)による挨拶で納骨式を開始します。
施主は参列者に一礼してから一歩前に出て、お集まりいただいたお礼を述べます。「本日はお忙しい中お集まりくださりありがとうございます」といった感謝の言葉に続けて、故人への思いや現在の遺族の心境を簡潔に伝えます。たとえば、「皆様に見守られ、無事に〇〇(故人名)の納骨の日を迎えることができました。故人もさぞ安心していることと思います」といった内容です。
あわせて「この後、僧侶の読経と納骨を行い、式後にはささやかですが会食をご用意しております」など、当日の流れを案内するひと言を添えておくと親切です。
挨拶が終わったら再度一礼し、施主は所定の位置に戻ります。
なお、挨拶の内容は格式張ったものでなくても問題ありませんが、事前に話す内容を考えておくとスムーズです。参列者も施主の挨拶中は静かに聞き、終了後に一礼して応じます。
3. 僧侶の読経と納骨の儀
施主の挨拶に続いて、僧侶による読経が始まります。菩提寺の住職など僧侶が墓前に立ち、読経を厳かに唱えます。屋外の墓前で読経するケースが多いですが、霊園内の法要施設や本堂に移動して読経を行う場合もあります。
参列者は合掌して静かに耳を傾け、読経が一通り終了したら、いよいよ納骨の儀式に移ります。僧侶の合図やお経の切れ目で、施主または遺族代表が骨壷を持って墓石の納骨口へ進みます。そしてあらかじめ開けておいた納骨室に、故人の遺骨を納めます。
納骨の方法には地域や墓所の習慣によって違いがありますが、一般的には次のいずれかです。
-
骨壷ごと納める
骨壷の蓋をしっかり閉じた状態でそのまま納骨室に収める方法です。骨壷が入る大きさのカロートであればこの方法をとります。 -
遺骨を直接納める
骨壷から遺骨(焼骨)を取り出し、直接カロート内に安置する方法です。土に還す意味合いで遺骨のみを埋葬する地域もあります。 -
納骨袋に移して納める
いったん骨壷から遺骨をさらし製の納骨袋(布袋)に移し替えてから、その袋ごと納骨室に収める方法です。遺骨が湿気で傷まないよう通気性を持たせる意図があります。
このように土地柄によって異なるため、事前にどの方法で行うか菩提寺や霊園に確認しておきましょう。
遺骨を納める際には、基本的に新しい遺骨が手前側になるように配置します。すでに他のご遺骨が納められている先祖墓の場合は、奥から順に古い遺骨を並べ、入り口側に新しい遺骨を置く形です。
施主が遺骨を納め終えたら石材店または遺族が墓石の蓋を静かに閉じ、納骨の儀式は完了します。
4. 焼香

納骨が終わった後、僧侶にもう一度お経をあげていただきます。この二度目の読経は「納骨経」とも呼ばれ、納骨が無事済んだことを供養するお経です。僧侶の読経が始まったら、参列者は順に焼香を行います。
焼香の順番は決まっている場合が多く、一般的には施主(喪主)から始め、次に親族、続いて友人知人など一般参列者の順で行います。僧侶が焼香のタイミングを指示してくれる場合もありますので、その指示に従いましょう。
一人ずつ祭壇または焼香台の前に進み、遺影や位牌に一礼してから抹香をつまんで静かに香炉にくべ、合掌して一礼して下がります。全員の焼香が終わりお経も一区切りついたところで、僧侶がお経本を閉じます。
これで納骨式の法要部分は終了です。僧侶に対し施主がお礼の合掌をし、参列者もそれにならって合掌します。
5.会食への案内
式そのものは終了となりますが、焼香後に会食(お斎)を設けることが多いです。その場合、僧侶と参列者はあらかじめ手配された会食会場や控室に移動します。
会食が始まる前に、施主が改めて皆にお礼を述べ、故人に対して献杯を行います。故人の位牌や遺影の前にも注がれたお酒の杯を置き、全員で故人に敬意を表してから頂きます。会食中は和やかに故人の思い出を語り合いながら、精進落としの料理をいただきます。忌明け後の席とはいえ砕けすぎず、故人を偲ぶ穏やかな雰囲気で過ごすのがマナーです。
会食のお開きの際は、施主がもう一度皆様へお礼の挨拶をします。「本日はお忙しい中ありがとうございました。おかげさまで無事に納骨を終えることができました」といった感謝の言葉を伝えましょう。僧侶へお布施を渡すタイミングなどを、ここで調整しても構いません。
最後に香典返し(返礼品)を参列者一人ひとりに手渡し、散会となります。会食を行わない場合は、納骨式終了後その場で仕出し弁当と香典返しをお渡しして解散することもあります。
納骨式の流れのまとめ
納骨式当日は、お墓の準備から始まり、挨拶・読経・納骨・焼香と一連の流れが進みます。式自体の所要時間はおおよそ1時間程度で、特に難しい作法はありません。要所では僧侶や葬儀社スタッフが声をかけて誘導してくれるので落ち着いて対応しましょう。
施主は開式と閉式の挨拶を務めるため、感謝の気持ちを中心に簡潔に言葉を準備しておくと安心です。納骨の場面では地域ごとの慣習に従い、骨壷の扱い方を間違えないよう事前確認が必要です。
焼香は順番こそありますが、作法は通常の法要と同じです。会食まで含めた流れを把握しておけば、初めての納骨式でもスムーズに対応できるでしょう。
納骨式の服装・持ち物と参列マナー

納骨式に参列する際の服装や持ち物のマナーについて解説します。葬儀ほど厳格ではありませんが、宗教的な儀式であり故人を弔う場ですので、節度ある服装・所作を心がける必要があります。
ここでは遺族側・参列者側それぞれの適切な服装、数珠や香典の扱い方、そして法要後の会食でのマナーについて説明します。基本的なマナーを押さえておけば、初めての納骨式でも恥をかくことなく故人を偲ぶことに集中できるでしょう。
遺族・参列者の服装マナー
納骨式の服装は、執り行う時期によって若干異なります。四十九日以前または四十九日法要当日に納骨式を行う場合、遺族も参列者も喪服(正喪服または準喪服)を着用するのが一般的です。
具体的には、男性ならブラックスーツかモーニング、女性なら黒無地のワンピースやアンサンブル(和装の場合は喪章を付けた黒紋付)が該当します。遺族側であれば格式の高い正喪服でも構いません。
百箇日や一周忌法要と合わせて納骨する場合など、一周忌より前の時期も基本は準喪服で、男性はブラックスーツ・女性はブラックフォーマルスーツを選びましょう。
一周忌を過ぎた後に納骨式を行う場合や、ごく内輪で簡易に行う場合は、平服に近い略喪服でも差し支えありません。とはいえ黒・グレー・紺など落ち着いた色合いのスーツやワンピースを着用し、過度にカジュアルにならないよう注意します。
派手なネクタイ・シャツは避け、女性は黒ストッキングを履きましょう。アクセサリーは結婚指輪程度に留め、光沢の強いバッグや靴は避けます。小さな子どもが参列する場合も、可能な範囲で地味な服装を心がけます。学校の制服があれば、制服が礼装になります。
このように、時期に応じて適切な喪服を選べば問題ありませんが、迷う場合は葬儀と同じ服装が確実です。
数珠や必要な持ち物のマナー
納骨式に参列する際は、数珠(念珠)を忘れずに持参しましょう。数珠は仏式の法要では必須の持ち物であり、焼香や読経中に手にかけて合掌します。各自が一連または二連の数珠を用意し、男性は左手、女性は両手にかけて合掌すると所作が美しく見えます。白いハンカチも用意し、汗や涙を拭う際に使用します。
遺族(施主)は埋葬許可証などの書類を持参するのはもちろん、お布施を入れた封筒(不祝儀袋)を袱紗(ふくさ)に包んで用意します。お布施の相場は地域や寺院によりますが、四十九日と納骨を同時に行う場合で3万〜5万円程度が目安です。
表書きは「御布施」、下段中央に施主の名字を書きます。併せて、遠方から来ていただいた僧侶には御車代(交通費)や、会食を辞退された場合の御膳料を包むケースもありますので、必要に応じて準備します。
参列者側で必要な持ち物は主に数珠と香典ですが、夏場で屋外なら日傘や帽子、冬場ならカイロなど体調管理の物も持参すると良いでしょう。
また、納骨式は墓前での立ち仕事が多くなります。女性はヒールの低い靴を選び、長時間立っていても疲れにくい服装を工夫します。高齢の方は杖や折りたたみ椅子があると安心です。
「厳粛な式である」という意識を持ち、必要以上の荷物は持ち込まないこともマナーの一つです。
香典の金額相場と包み方
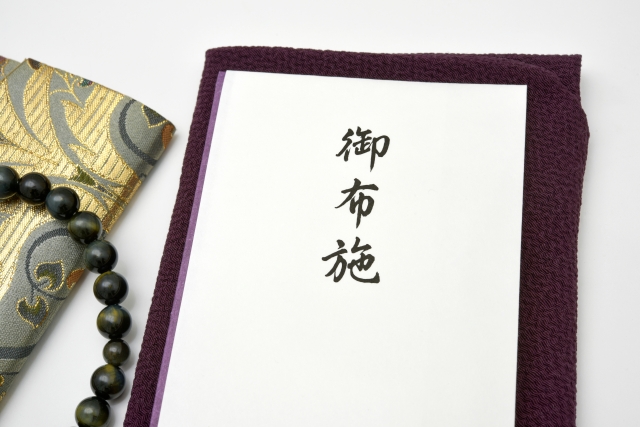
香典(こうでん)とは、故人への弔意として参列者が施主に渡す金包みのことです。納骨式のみ参列する場合でも香典を持参するのが一般的で、金額の相場は故人との関係性にもよりますが5千〜1万円程度が目安です。
四十九日法要と納骨式が同時の場合は、香典を2つ用意する必要はなく一つにまとめて渡します。金額はやや多めに包み、表書きは四十九日に合わせます。香典袋の表書きはタイミングにより異なる点に注意しましょう。
仏式の場合、四十九日以前の法要では「御霊前」、四十九日以降は「御仏前」と書き分けます。納骨式がちょうど四十九日法要後に行われるなら「御仏前」となります。
一方で神式であれば「御玉串料」、キリスト教式なら「御花料」等と宗教に応じた表書きを用います。
香典袋の中袋には住所・氏名と金額を毛筆または筆ペンで書いておきます。新札は避け、使用済みの綺麗なお札を入れるのがマナーです。香典は袱紗に包んで持参し、受付または式終了後に施主にお渡しします。
受け取った施主側は、当日中に香典返しを手渡すか、後日改めてお礼状と共に香典返しの品を郵送するのが一般的です。なお、「香典辞退」と案内があった場合は無理に持参する必要はありませんが、その際も手ぶらではなく菓子折りや供花などで気持ちを表す方もいます。
いずれにせよ故人や遺族への哀悼の気持ちを形に表すものですので、心を込めて用意しましょう。
会食(お斎)での振る舞い
納骨式後の会食(お斎・精進落とし)に参列する場合のマナーについても触れておきます。会食の席は、葬儀後の精進落としと同様に故人を偲ぶ場です。席に着いたら私語は慎み、まず施主の挨拶と献杯が終わるのを待ちます。
献杯では全員が起立または姿勢を正し、「献杯」の発声で盃を静かに持ち上げてから一口飲み、故人に敬意を表します。その後は着席し、料理が振る舞われます。
アルコールが出ても、羽目を外すような飲み方は厳禁です。故人の思い出話や遺族へのいたわりの言葉など、和やかで穏やかな会話を心がけます。大声で笑ったり騒いだり、故人と無関係な世間話ばかりするのはマナー違反です。食事のマナー自体は通常の会食と同様ですが、箸の上げ下ろしも落ち着いて行い、料理に手を付けるタイミングは施主や目上の方に合わせます。
服装は引き続き略喪服のままで構いません。途中で席を立つ際も、周囲に一礼して静かに移動します。会食がお開きになったら、施主から香典返しを受け取りましょう。「本日はありがとうございました」と一言添えて受け取り、その場で開封はせず持ち帰ります。最後に施主へ改めてお悔やみとお礼の言葉を伝え、静かに退出しましょう。
以上のように、一連の所作は葬儀後の会食マナーと大きく変わりません。故人への敬意と遺族への配慮を忘れず、節度ある振る舞いで終始することが大切です。
服装・所作に配慮し厳かな態度を
納骨式は葬儀ほど大規模ではないものの、正式な弔いの儀式である点に変わりありません。時期に応じた喪服を着用し、地味で清潔感のある身なりで臨みましょう。数珠や香典など必要な持ち物を準備し、特に香典は表書きや金額に注意が必要です。
会食においても故人を偲ぶ場であることを忘れず、控えめで落ち着いた態度で過ごしてください。これらのマナーを押さえておけば、初めての納骨式でも戸惑うことなく、心を込めて故人に手向けることができるでしょう。
納骨式をサポートしてくれるサービスの活用

遠方にお墓がある場合や菩提寺との付き合いがない場合など、納骨式の執行に不安を感じるときは、専門のサービスに頼るという選択肢もあります。
近年、一部の葬儀社では納骨の代行や僧侶手配など、納骨式に関するサポートプランを提供しています。ここでは代表的なサービスとして「小さなお葬式」と「よりそうお葬式![]() 」の納骨サポートについて紹介します。
」の納骨サポートについて紹介します。
必要に応じてこうしたサービスを活用すれば、遺族の負担を軽減しつつ故人をきちんと供養することができるでしょう。
小さなお葬式の「おまかせ納骨プラン」
大手葬儀社の一つ「小さなお葬式」では、納骨先がない方や費用を抑えたい方のために「おまかせ納骨プラン」いうサービスを提供しています。
例えば、「お墓が無いけれど自宅に遺骨を置いておくのも心配」「身寄りがなく後を任せる人がいない」といったケースに対応したプランで、葬儀プランに追加料金一律3万円で利用できます。ほかに追加の費用は一切発生せず、申し込みから納骨完了までをすべて代行してもらえるのが特徴です。
具体的な流れとしては、電話等で申し込み後、遺骨を「小さなお葬式」提携の寺院に送付します。寺院では遺骨を細かい粉状に粉骨し、他の遺骨と合祀して永代供養墓に納骨します。納骨が完了すると納骨証明書が発行され、寺院が責任を持って供養を続けてくれます。
納骨式に関わる大変な作業をすべて代行してもらえるため、遺族の負担を大きく軽減できます。「おまかせ納骨プラン」を利用すれば僧侶へのお布施や会食の手配も不要となり、納骨にかかる負担と費用を大幅に軽減できます。
その反面、一度他の遺骨と合祀してしまうため「後から遺骨を取り出せない」「親族の理解が得られにくい」などのデメリットもあります。実家のお墓に納めないことに対する抵抗感が家族にないか、菩提寺がある場合は了承を得られるか、といった点に注意が必要です。
条件が合えば、「おまかせ納骨プラン」は費用3万円で永代供養まで任せられる有力な選択肢と言えるでしょう。
よりそうお葬式の「よりそうお坊さん便」
葬儀・法要ポータルの「よりそうお葬式![]() 」では、納骨式に関連して「よりそうお坊さん便」という僧侶の手配サービスを提供しています。
」では、納骨式に関連して「よりそうお坊さん便」という僧侶の手配サービスを提供しています。
「遠方にお墓があって自分たちだけでは納骨式ができない」「菩提寺が無いのでお坊さんをお願いしたい」といった場合、「よりそうお葬式![]() 」の窓口で相談することで、僧侶を紹介・派遣してもらうことができます。「よりそうお坊さん便」の大きな特徴は、全国どこでも定額料金で対応してもらえる点と、お寺との付き合いが全く無くても利用できる点です。
」の窓口で相談することで、僧侶を紹介・派遣してもらうことができます。「よりそうお坊さん便」の大きな特徴は、全国どこでも定額料金で対応してもらえる点と、お寺との付き合いが全く無くても利用できる点です。
「お寺と付き合いがない方でも依頼可能」「全国どこからでも依頼可能」「法要と納骨をまとめても別々でも柔軟に対応」「全国一律の明朗会計」など、多数のメリットがあります。
電話やWEBで希望日程や宗派などを伝えるだけで、地元近くのお寺や僧侶をマッチングして派遣してくれます。費用も公式サイトに明記されており、例えば読経と納骨法要一式で〇万円(※地域や内容によります)など定額の分かりやすい料金体系です。遠方に住んでいても、葬儀とは別の土地で納骨法要だけしっかり行いたいという遺族の思いを形にしてくれる強い味方になってくれるでしょう。
注意点としては、墓地管理者への埋葬許可証提出などの手続きは自分で行う必要があることです。サービスはあくまで法要のお坊さんを手配するものであり、お墓の準備や役所手続きまでは代行しませんので、利用者側で忘れずに対応しましょう。
また、「よりそうお葬式![]() 」では、永代供養墓や納骨堂の紹介サービス「よりそう永代供養墓」も展開しています。お墓自体がない方には、葬儀から納骨先紹介までワンストップでサポートできる体制が整っています。
」では、永代供養墓や納骨堂の紹介サービス「よりそう永代供養墓」も展開しています。お墓自体がない方には、葬儀から納骨先紹介までワンストップでサポートできる体制が整っています。
これらを上手に活用すれば、「お墓がない」「菩提寺がない」「遠方ですぐ行けない」といった事情があっても、故人を適切に供養する方法が見つかるでしょう。
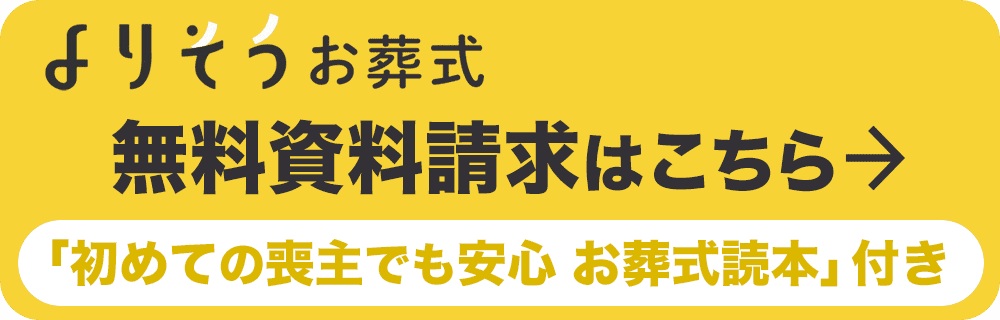
サービス利用のメリットと注意点
納骨式関連のサービスを利用することには、遺族の身体的・精神的負担を減らせるメリットがあります。小さなお葬式の「おまかせ納骨プラン」のように費用が明瞭かつ低額であれば経済的負担も軽減できます。また、「よりそうお葬式![]() 」の「よりそうお坊さん便」のように全国一律料金でどこでも対応してもらえる仕組みは、核家族化や地方への墓参が難しい現代のニーズに合致しています。
」の「よりそうお坊さん便」のように全国一律料金でどこでも対応してもらえる仕組みは、核家族化や地方への墓参が難しい現代のニーズに合致しています。
親族内に寺院との付き合いがない場合でも利用できるため、「どうやってお坊さんを探せばいいか分からない」という不安も解消してくれます。一方で注意すべきは、サービス利用にあたって親族の理解を得ることです。従来のやり方と違う形で納骨を進める場合、年配の家族の中には抵抗感を示す方もいるかもしれません。
例えば「おまかせ納骨プラン」では他人と合同のお墓に納めることになりますが、それを「可哀想だ」「成仏できないのでは」と心配する声もあり得ます。しかし実際には合祀墓であっても寺院が永続的に供養してくれるため問題はありません。大切なのは事前によく話し合い、サービスの内容と意義を家族で共有しておくことです。
また、菩提寺との関係にも配慮が必要です。菩提寺があるにも関わらず他所で納骨や法要を済ませてしまうと、後々お寺との関係が悪化する恐れもあります。この場合は事前に住職に相談し、一部の遺骨をお墓に納める・お経だけお願いするなど折衷案を検討すると良いでしょう。
総じて、納骨式サポートサービスは現代の多様な供養ニーズに応える有用な手段です。埋葬許可証の提出など、公的な手続きだけは忘れずに自分で行うことを念頭に、上手に活用してください。
必要に応じて専門サービスの力を借りよう
納骨式を自分たちだけで執り行うことが難しい場合、葬儀社の提供する納骨代行・僧侶手配サービスを利用するのも一つの方法です。小さなお葬式の「おまかせ納骨プラン」では、費用一律3万円で納骨と永代供養を任せることができ、遠方にお墓がない方の強い味方となっています。
また、よりそうお葬式![]() の「よりそうお坊さん便」では、全国どこでも定額で僧侶を紹介してもらえ、菩提寺が無くても安心して法要を依頼できます。
の「よりそうお坊さん便」では、全国どこでも定額で僧侶を紹介してもらえ、菩提寺が無くても安心して法要を依頼できます。
これらを活用すれば、遺族の負担軽減と確実な供養の両立が可能です。ただし親族間の合意形成や菩提寺への配慮などは怠らず、サービスのメリット・デメリットを理解した上で選択しましょう。
必要に応じて専門家の力を借りながらも、故人を思う気持ちを第一に最適な納骨方法を検討してください。
納骨式に臨むあなたへ

納骨式は、今後の供養につなげていく大切な儀式です。初めてのことで緊張もあるかもしれませんが、事前に流れとマナーを把握しておけば当日はきっと落ち着いて臨めるでしょう。
服装や振る舞いのポイントを押さえ、心を込めて故人を送り出すことが何よりの供養になります。お墓が遠方にある方や遺骨を分けて供養する方も、それぞれの事情に合わせて無理のない方法で納骨式を行ってください。
最近では納骨をサポートするサービスも充実していますので、困ったときは専門家に相談することも一つの方法です。
故人への想いは形は違えど皆同じです。どうか納骨式という節目を通じて、故人とのお別れに一区切りをつけ、残されたご家族が心穏やかに故人を偲び続けられますように。