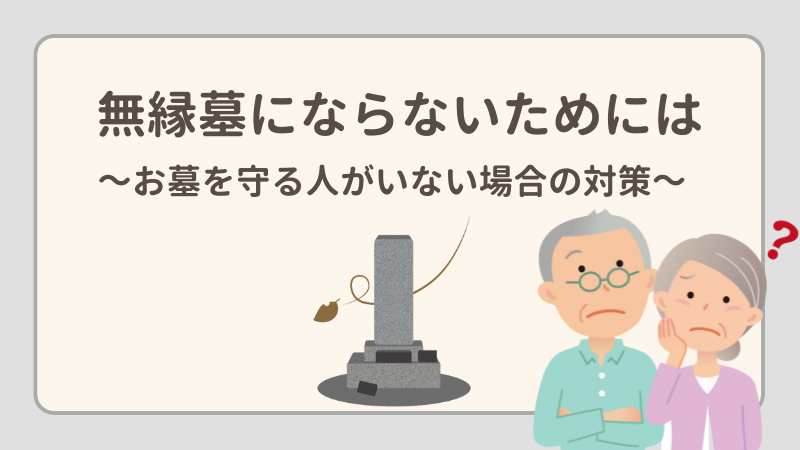「自分が亡くなったあと、このお墓はどうなるのだろう」——お墓を引き継ぐ人がいないと、そんな不安が大きくなります。承継者がいないまま放置されると、お墓は「無縁墓」とみなされ、合葬や撤去の対象となる可能性があります。
この記事では、身寄りがない方や一人暮らしの高齢者でもできる備えとして、永代供養墓や公営の合葬墓、死後事務委任契約などを紹介します。
目次
無縁墓を避けるためにできること

お墓を放置したからといって、すぐに「無縁墓」とされるわけではありません。墓地の規約や契約状況を確認したうえで判断されます。
承継者がいない場合でも、生前にできる準備はいくつもあります。ここでは、身寄りがなくても無縁墓にならないようにするための、具体的な備えを紹介します。
無縁墓とは?
無縁墓とは、使用者が亡くなったあとに承継者がいない、または連絡が取れず管理ができなくなった墓を指します。すぐに撤去されるわけではなく、一定期間の公告や通知を経て、合葬墓への改葬や撤去が行われます。
生前に管理者に希望を伝えたり、永代供養墓へ移したりすることで、死後も供養が続くように備えられます。
生前の意思を残しておく
家族がいなくても、自分の希望を残す方法はいくつもあります。
たとえばエンディングノートに「どこに納骨してほしいか」「永代供養墓に移したい」などを書いておけば、後に関わる人や役所に伝わりやすくなります。さらに確実にしたい場合は、公正証書遺言として残すことで、法的にも意思を反映しやすくなります。
身寄りがなくても記録を残しておくだけで、お墓が無縁墓になるのを防ぐ手立てになります。
承継者がいない人が選べる方法
墓を継ぐ人がいない場合には、次の方法が有効です。
- 墓じまいをして永代供養墓に移す
- 自治体が運営する合葬墓を利用する
- 死後事務委任契約を結び、信頼できる人に手続きを託す
いずれも「承継者がいない」という不安を解消する有効な手段です。費用の見通しや契約条件を確認し、早めに準備を始めることが大切です。
不安を減らす3つの基本
無縁墓を避けたい一人暮らしの方にとって、重要なのは次の3点です。
- 生前に意思を文書で残す
- 永代供養墓や合葬墓を検討する
- 死後事務を委任できる人や機関を決めておく
これらを早めに整えておけば、墓が無縁墓になる不安を和らげられます。自分の死後に頼れる人がいなくても、制度を使えばお墓をきちんと守る準備ができます。
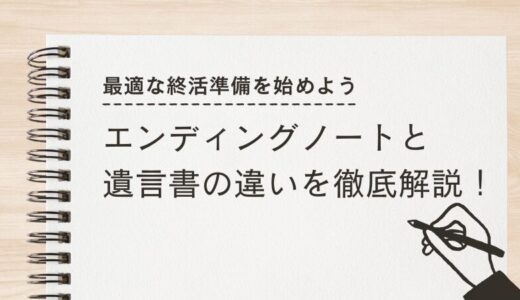 エンディングノートと遺言書の違いを徹底解説!最適な終活準備を始めよう
エンディングノートと遺言書の違いを徹底解説!最適な終活準備を始めよう
墓じまいと改葬の進め方

お墓を守る人がいないとわかっている場合、現実的な方法は「墓じまい」をして、遺骨を永代供養墓や合葬墓に移すことです。生前のうちに手続きを進めておけば、無縁墓となる心配を減らせます。
ここでは、墓じまいと改葬の手順や費用の目安を、わかりやすく解説します。
墓じまいの基本の流れ
墓じまいは複雑に感じるかもしれませんが、大きく分けて次の6つのステップで進みます。
- 墓地管理者に墓じまいの意向を伝える
- 石材店に撤去工事の見積を依頼する
- 新しい納骨先(永代供養墓など)を決めて受入証明をもらう
- 市区町村に改葬許可を申請する
- 閉眼供養を行い、墓石を撤去する
- 遺骨を新しい納骨先に移す
手順を知っておくだけで、どの段階で誰に依頼すればよいかが明確になります。
あらかじめ全体像を把握しておけば、急に準備が必要になったときにも落ち着いて動けます。また、必要な相談先を早めに見つけておくきっかけにもなるでしょう。
 墓じまいの進め方 ~費用や改葬手続き、親族への説明ポイント~
墓じまいの進め方 ~費用や改葬手続き、親族への説明ポイント~
費用の目安
墓じまいには石材撤去費や閉眼供養のお布施、新しい納骨先の契約料などがかかります。主な費用の目安は、次のとおりです。
| 項目 | 費用目安 |
|---|---|
| 墓石撤去(1㎡あたり) | 約10〜15万円 |
| 閉眼供養(お布施) | 約3〜10万円 |
| 離檀料(寺院を離れる場合) | 約3〜20万円 |
| 改葬手続き(書類発行) | 数百円〜1,000円程度 |
| 永代供養墓(納骨先) | 約5〜150万円 |
これらを合計すると、一般的には50〜100万円前後で収まるケースが多いですが、規模や納骨先によって30万円ほどで済む場合もあれば、200万円を超えることもあります。
複数の業者や霊園から見積もりを取り、内訳を確認すること大切です。
とくに初めて墓じまいを検討する方にとっては、どこに相談すればよいか迷うこともあるでしょう。そんなときは、信頼できる墓じまい専門サービスを利用するのも安心です。
たとえば 「わたしたちの墓じまい![]() 」では、離檀交渉から行政手続き、墓石撤去までトータルでサポートしてくれるため、初めてでもスムーズに進められます。
」では、離檀交渉から行政手続き、墓石撤去までトータルでサポートしてくれるため、初めてでもスムーズに進められます。
料金体系もわかりやすく、全国に対応しているので、多くの人にとって利用しやすい選択肢といえます。
準備で大切なこと
墓じまいと改葬を考えるときに大切なのは、次の3点です。
- 管理者に早めに意向を伝える
- 改葬先を決めて受入証明書を確保する
- 費用を見積もり、死後事務委任契約などに組み込んでおく
これらを整えておけば、実際に手続きが必要になったときも迷わず進められます。承継者がいなくても、無縁墓になる不安をしっかりと防ぐことが可能です。
永代供養墓という選択

お墓を継ぐ人がいなくても、永代供養墓を利用すれば安心して遺骨を納めることができます。
永代供養墓は、寺院や霊園が供養と管理を続けてくれる仕組みで、承継者の有無に左右されません。近年では、自治体が運営する公営の合葬墓も広がっており、ひとり暮らしの方や身寄りのない方にとっても利用しやすい選択肢になっています。
ここでは、永代供養墓の特徴と利用前に確認すべきポイントを見ていきましょう。
永代供養墓の仕組み
永代供養墓は霊園や寺院が責任をもって管理を続けるため、承継者がいなくても供養が途切れません。納骨方法にはいくつか種類があり、費用の目安も異なります。
- 合祀墓 ⇒ 最初から他の遺骨と一緒に納骨
5万円〜30万円ほど - 集合墓 ⇒ 一定期間は個別安置し、その後に合祀
20万円〜60万円ほど - 個別墓 ⇒ 個別スペースを利用し、永代にわたり安置
50万円〜150万円ほど
いずれも一人あたりの費用として設定されていることが多く、複数人で利用する場合は人数分の費用がかかります。
契約内容には供養の頻度や法要の有無、合祀される時期が明記されているかを必ず確認しましょう。不明点は口頭説明だけでなく、必ず書面で残してもらうことが大切です。
 永代供養とは?仕組みから費用、メリット・注意点まで徹底解説
永代供養とは?仕組みから費用、メリット・注意点まで徹底解説
公営の合葬墓を利用する
自治体が運営する合葬墓は、承継者がいなくても安心して利用できる制度です。
申し込みには居住地や遺骨の有無などの条件があり、募集の時期も自治体ごとに異なります。基本は合葬ですが、中には数十年のあいだ個別安置できるところもあります。
費用は条例で決まっており、数万円から十数万円程度で利用できる場合が多いです。参拝方法や献花の可否、名前を刻むかどうかは施設によって違うため、事前に見学して確認しておくと安心です。
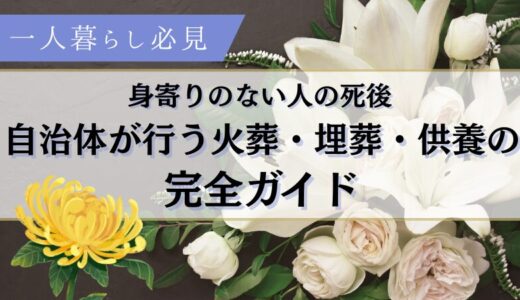 一人暮らし必見|身寄りのない人の死後、自治体が行う火葬・埋葬・供養の完全ガイド
一人暮らし必見|身寄りのない人の死後、自治体が行う火葬・埋葬・供養の完全ガイド
永代供養墓に関するQ&A
永代供養墓に入ったあと、誰もお参りしなくても大丈夫ですか?
大丈夫です。契約を結んだ寺院や霊園が供養を続けるため、参拝者がいなくても供養が途切れることはありません。ただし、年忌法要や合同供養の開催方法は施設ごとに異なるので、事前に確認しておきましょう。
費用は最初に払えば追加はかかりませんか?
多くは一括払いで完結しますが、年会費や合同法要の参加費が別途かかる場合もあります。契約前に「含まれる費用」と「別料金になるもの」を明細で確認しておくことが大切です。
生前に自分で申し込んでも、死後にきちんと納骨されますか?
生前申込みの場合は、契約内容に「死後の連絡先」「遺骨を届ける人」を指定する仕組みがあります。身寄りがない方は、死後事務委任契約と組み合わせて、確実に納骨が実行される体制を整えておくと安心です。
選ぶときの確認ポイント
永代供養墓を選ぶときには、次の点を確認しておきましょう。
- 契約書や規約に、供養方法や合葬の時期が明記されているか
- 費用の内訳がわかりやすいか、追加費用が発生しないか
- 参拝方法や供養行事の内容が自分の希望に合っているか
- 立地や交通の便がよく、自分や親しい人が通いやすい場所か
事前に条件を比べておけば、契約後に「思っていた内容と違った」といった後悔を防げます。必ず書面で内容を確認し、できれば現地を訪れて雰囲気を確かめることも大切です。
死後事務の委任

お墓のことと同じくらい大切なのが「死後の手続きを誰に任せるか」という点です。死亡届や公共料金の清算、葬儀や納骨の手配などを放置すると、遺骨の行き場が決まらず、結果として無縁墓になる恐れもあります。
家族がいなくても、信頼できる人や専門職に頼める仕組みとして注目されているのが「死後事務委任契約」です。ここでは、その内容と準備のポイントを解説します。
死後事務委任契約とは
死後事務委任契約とは、本人が亡くなったあとに必要な手続きを、生前のうちに信頼できる人へ託す仕組みです。
対象は死亡届や火葬許可の申請、病院や施設からの退去手続き、葬儀・納骨の実施、遺品の整理、公共料金や家賃の清算など多岐にわたります。契約を公正証書で作成しておくと確実性が高まり、受任者が役所や霊園に説明するときにスムーズです。
身寄りがない人にとっては、自分の意思を実際の行動に移してもらうための大切な準備になります。
委任できる内容の例
死後事務委任契約で任せられる内容は幅広く、自分に必要なものだけを選んで契約できます。
- 死亡届や火葬許可の申請
- 病院や介護施設からの退去・荷物の整理
- 葬儀・火葬・納骨の実施
- 遺品や生活用品の処分
- 公共料金や家賃などの精算
- 永代供養墓や合葬墓への納骨手続き
一見バラバラに見える手続きですが、すべて「亡くなったあとに生活をきちんと締めくくるための手続き」です。契約に明記しておくことで、家族がいなくても滞りなく進めてもらえます。
生前の準備があるかどうかで、死後の安心感は大きく変わるのです。
死後事務委任に関するQ&A
誰に依頼できますか?
弁護士や司法書士などの専門職に依頼するのが一般的ですが、信頼できる知人に依頼することも可能です。大切なのは、確実に実行してもらえるかどうかです。
費用はどのくらいかかりますか?
契約書作成や公正証書化の費用に加え、葬儀・納骨・遺品整理などの実費が必要です。内容によって差があるため、生前に見積を取り、必要額を預けておくと安心です。
遺言と何が違いますか?
遺言は財産分与や相続に関する意思表示ですが、死後事務委任契約は「実務の代行」を任せる仕組みです。両方を併用すれば、より確実に自分の希望を実現できます。
準備のポイント
死後事務委任を考えるときは、次の点を押さえておきましょう。
- 契約内容を具体的に決め、曖昧な部分を残さない
- 費用の預け方と精算方法を取り決める
- 契約書の控えを信頼できる人や専門職に渡しておく
これらを整えておけば、亡くなったあとに手続きが滞ることを防げます。承継者がいなくても、契約を通じて「確実に実行される仕組み」を作ることができ、安心して日々を過ごせるようになります。
無縁墓にしないため準備した人の体験談

制度や手続きの情報だけでは、なかなかイメージしにくいものです。ここでは、無縁墓を避けるために実際に行動した方々の体験を紹介します。
境遇や選んだ方法は異なりますが、どの方も「生前に準備したことで安心できた」と語っています。
永代供養墓を選んだケース
![]() 70代・女性
70代・女性
夫も子どももおらず、私が亡くなったら誰もお墓を守れません。そこで菩提寺に相談し、永代供養墓へ移す契約をしました。
費用は30万円ほどで、年に一度の合同法要もあると説明を受けました。これで自分がいなくなっても供養が続くとわかり、心から安心しました。
公営の合葬墓を利用したケース
![]() 60代・男性
60代・男性
地方に先祖代々のお墓がありましたが、私は都会で独り暮らしです。戻る予定もなく、墓守もいないため、市が運営する合葬墓に申し込みました。費用は10万円以下で、納骨後も市が管理してくれる仕組みです。
手続きは広報紙で募集を見つけたときに行い、思っていたより簡単でした。
死後事務委任契約を結んだケース
![]() 80代・男性
80代・男性
兄弟もおらず、親戚付き合いもありません。死後の手続きを誰に頼むかが一番の不安でした。司法書士に相談し、死後事務委任契約を公正証書で結びました。
費用の預託や納骨先の指定も契約に含めたので、これで死後に手続きが滞ることはないと思えます。契約書を手にしたとき、ようやく肩の荷が下りた気がしました。
体験から見える共通点
3つの体験に共通しているのは、「自分が亡くなったあとに備えて行動していた」ことです。
永代供養墓、公営合葬墓、死後事務委任契約と方法は違っても、いずれも制度を利用して「無縁墓にならない仕組み」を整えています。大きな決断を一度にする必要はなく、資料を取り寄せたり、専門家に相談したりするだけでも第一歩になります。
身寄りがなくても準備できる選択肢があることが、安心につながるのです。
今日から始められる安心の備え

承継者がいない場合でも、永代供養墓や公営の合葬墓、死後事務委任契約といった制度を利用することで、死後にお墓や手続きが放置される心配を減らせます。
大切なのは「いつかやろう」ではなく、今から準備を始めることです。契約書やパンフレットを取り寄せてみるだけでも、不安は少し和らぎます。さらに、必要な費用を確認して契約や遺言、エンディングノートに残しておけば、自分の希望をより確実に実現できます。
今日からできることを積み重ね、自分らしい最期の形を整えていきましょう。