葬儀を終えたあと、「四十九日法要も小さなお葬式でお願いできるのか」と気になる方もいるでしょう。
四十九日は忌明けにあたる大切な節目であり、本位牌の準備や納骨、参列者への案内など、実務的な準備が重なる時期でもあります。
この記事では、小さなお葬式の僧侶手配サービス「てらくる」で四十九日法要を依頼できるのかを中心に、費用の目安や準備の流れ、注意点までを整理しました。
初めて法要を執り行う方でも、よくある疑問を押さえることで必要な段取りを把握しやすくなるでしょう。
四十九日法要の基本

四十九日法要は、故人の魂を極楽浄土へと導き、遺族が忌明けを迎える大切な区切りの儀式です。
初七日が葬儀当日に簡略化されることが多いのに対し、四十九日は親族を招いて正式に営まれることが一般的です。本位牌の準備や納骨を伴うため、葬儀後にあらためて整えるべき実務も多くあります。
ここでは、初七日との違い、日程の数え方、儀式の意味、準備すべき物品を順に押さえ、四十九日の全体像を確認していきましょう。
初七日とのちがい
初七日法要は、亡くなってから7日目に行う最初の法要で、本来は命日から7日後に営まれます。しかし現代では、参列者が再度集まる手間や費用に配慮して葬儀と同日に「繰り上げ初七日」として行うのが一般的になりました。
一方の四十九日法要は、七七日(7×7=49日目)にあたり、仏教では、故人の霊が極楽に往生できるかどうかが決まる日と考えられています。この日を境に忌明けとなり、遺族にとっても喪中が明ける節目となります。
つまり、初七日が「葬儀に付随する簡易な法要」であるのに対し、四十九日は「忌明けの本格的な法要」という違いがあります。
本位牌と仮位牌の役割
葬儀で用いられる白木の位牌は「仮位牌」と呼ばれます。四十九日法要では、この仮位牌から漆塗りの本位牌へ魂を移す「開眼供養」が行われ、以後は本位牌が正式な礼拝の対象となります。
本位牌の準備の際は、次の点をチェックしておきましょう。
- 戒名や俗名を刻むため、注文から完成まで約2週間を要する
- 仏壇がない場合は、この時期に小型仏壇を新たに整える家庭もある
- 納骨を同日に行う場合、本位牌とあわせてお墓の準備も必要
このように、本位牌は四十九日までに準備しておくべき重要な仏具といえます。
 位牌の基本【種類、文字の入れ方、大きさ、その後の処分方法まで】
位牌の基本【種類、文字の入れ方、大きさ、その後の処分方法まで】
日程の決め方
四十九日法要は、命日を1日目として数えた49日目に営むのが本来です。
ただし実際には平日と重なることも多く、その場合は直前の土日に前倒しで行うのが一般的です。仏事においては「後ろ倒しを避ける」のが慣習であり、50日目以降にずらすのは望ましくありません。
親族の予定や会場の都合もあるため、できれば1か月前には候補日を固め、僧侶や会場を早めに押さえておくのが安心です。特に春秋のお彼岸や年末年始など、法要が集中しやすい時期は予約が難しくなるため注意が必要です。
四十九日の儀礼と意味
四十九日法要では、僧侶による読経・焼香・法話を通じて故人の冥福を祈ります。
一般的な流れは次のとおりです。
- 僧侶が読経を開始し、参列者は静かに合掌
- 喪主から順に焼香を行い、全員が席に戻るまで読経を継続
- 読経の後に法話があり、遺族を慰める言葉や仏教の教えが伝えられる
- 本位牌への魂入れ(開眼供養)を行い、仮位牌は後日お焚き上げされる
- 納骨を同日に行う場合は墓前で読経と焼香を行い、遺骨を納める
四十九日は、故人が仏のもとへ導かれる節目とされています。
儀式を丁寧に営むことで、故人の行く末を祈るだけでなく、遺族自身も喪に服す期間を終え、新たな日常へ踏み出す区切りを迎えることができます。そのため、現代においても欠かせない法要とされています。
 四十九日法要とは?意味・流れ・準備やマナーをわかりやすく解説
四十九日法要とは?意味・流れ・準備やマナーをわかりやすく解説
節目としての四十九日
初七日と比べ、四十九日は儀式内容や準備の負担が大きく、本位牌や納骨なども関わる節目です。日程は前倒しを基本とし、準備には数週間を要する項目もあるため、葬儀直後から計画的に進めることが大切です。
この法要は、故人が仏のもとへ導かれるかどうかを見届ける重要な区切りであり、遺族にとっても喪に服す日々を締めくくる節目となります。だからこそ、意味を理解したうえで準備を整えることが、落ち着いた気持ちで忌明けを迎えるための大切な歩みとなるのです。
小さなお葬式で四十九日法要を依頼する

葬儀を終えたあと、「四十九日法要も同じように依頼できるのか」と不安に思う方もいるかもしれません。こうした不安に応える形で、小さなお葬式では葬儀後の法要にも対応しています。その仕組みが「てらくる」という僧侶手配サービスです。
「てらくる」では、四十九日法要に加えて一周忌や三回忌などの年忌法要にも対応しており、葬儀を小さなお葬式で行った方はもちろん、他社で葬儀を済ませた場合でも法要だけの依頼が可能です。菩提寺がなくても宗派指定ができ、基本料金が定額で設定されている点が大きな特徴です。
「てらくる」の仕組み
「てらくる」は小さなお葬式を運営する株式会社ユニクエストが提供する、全国対応の僧侶手配サービスです。従来は「檀家でなければ依頼しにくい」とされていた法要を、檀家登録不要で利用できる仕組みにしています。
依頼内容に応じて僧籍簿で資格を確認された僧侶を手配してもらえるため、初めてでも安心感があります。葬儀と独立して使える仕組みなのも心強いところです。
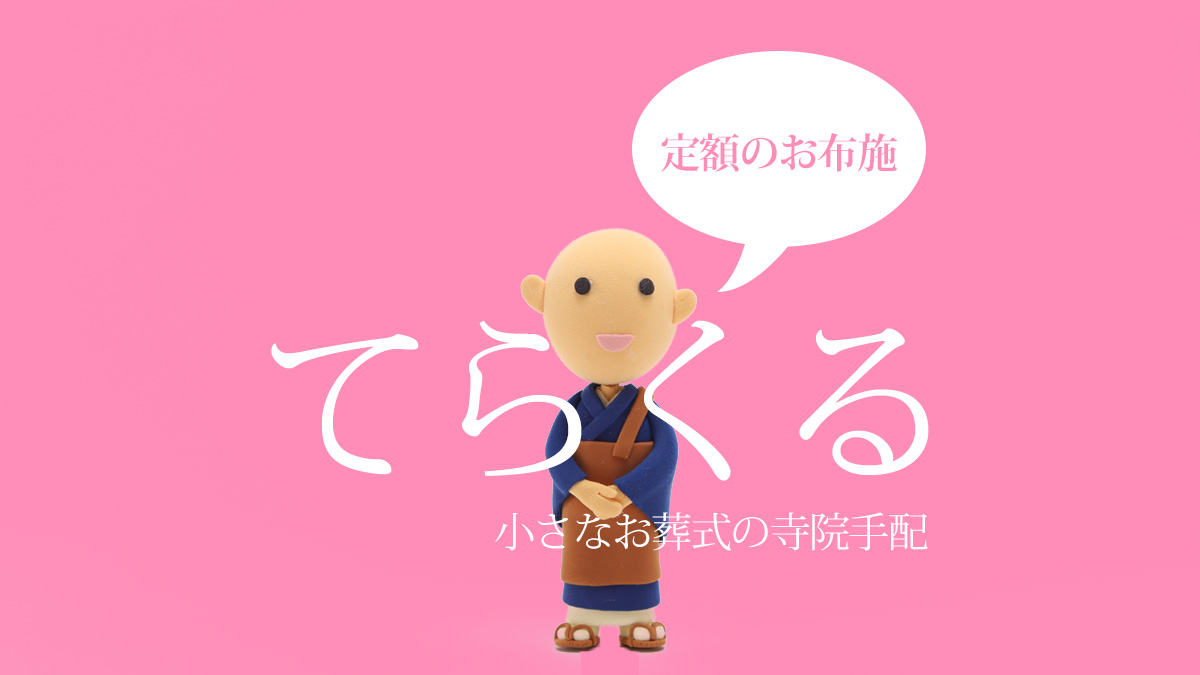 小さなお葬式の寺院手配「てらくる」とは?サービス内容と口コミ・評判を解説
小さなお葬式の寺院手配「てらくる」とは?サービス内容と口コミ・評判を解説
依頼できる内容と範囲
「てらくる」は四十九日だけでなく、初盆や一周忌、三回忌といった年忌法要にも幅広く対応しています。
会場は自宅や菩提寺、セレモニーホールなどから希望に応じて選ぶことができ、僧侶が指定の場所へ出向いてくれます。さらに仏壇の開眼供養や納骨式を同日に行うことも可能で、複数の準備をまとめて依頼できる点も特徴です。
小さなお葬式では、葬儀から四十九日法要、そして納骨までを一貫して任せられる仕組みを整えており、複数の窓口に連絡する必要がないのは大きな強みといえます。
派遣される僧侶は僧籍簿で資格を確認したうえで手配されるため、初めての方でも安心して依頼できるのも魅力です。
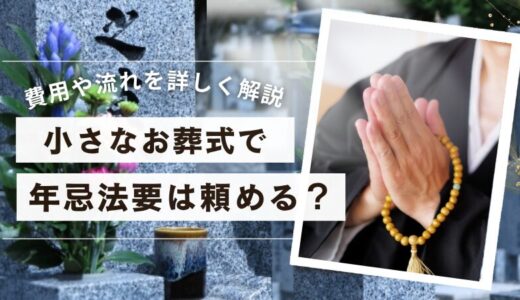 小さなお葬式で年忌法要は頼める?費用や流れを詳しく解説
小さなお葬式で年忌法要は頼める?費用や流れを詳しく解説
菩提寺への依頼との比較
従来は菩提寺に依頼し、「お布施はお気持ちで」とされることが多く、金額が不明瞭でした。
お布施の目安は3万〜10万円程度といわれますが、御車代や御膳料を別に包む必要があるため、総額は不透明になりがちです。
| 項目 | 小さなお葬式「てらくる」 | 従来の菩提寺への依頼 |
|---|---|---|
| 僧侶手配料 (お布施) |
50,000円 ※全国一律・追加費用は必要な場合のみ |
30,000〜100,000円程度 ※地域・寺院により差が大きい |
| 含まれる内容 | 含まれる内容:読経・法話・宗派指定料・お車代・御膳料・心づけ・開眼供養・納骨法要 | 通常は読経のみ ※御膳料や御車代は別途必要 |
| 檀家登録の要否 | 不要(一回限りの利用可) | 檀家である必要がある場合あり |
| 特徴 | 僧籍簿で資格を確認した僧侶を手配 全国どこでも利用可能 |
故人ゆかりの寺院で柔軟な対応が可能 |
「てらくる」は費用をあらかじめ把握でき、会場や宗派を柔軟に選べる点が現代の暮らしに合った強みといえます。
一方、菩提寺への依頼は費用の幅が大きく、地域の慣習や縁に左右されやすいため、初めて依頼する方にとっては予算や準備の見通しを立てにくいことがあります。
「てらくる」の強み
「てらくる」では、檀家登録をしなくても僧侶を依頼でき、宗派指定も可能です。従来のように「お布施はお気持ちで」とされる不明瞭さがなく、明確な金額で準備できます。
ここうした特徴は、菩提寺との縁がない家庭や、法要にかかる費用を事前に把握したい方にとって判断材料の一つになります。サービスの仕組みを理解しておくことで、葬儀後も落ち着いて法要を迎えられるでしょう。
依頼方法と料金のしくみ

小さなお葬式の四十九日法要は、料金体系が分かりやすく、手続きもシンプルです。
お寺にお願いする場合、お布施は「お気持ちで」と言われることが多く、いくら包めばよいか悩んでしまいます。しかし小さなお葬式なら最初から料金がはっきりしているので、初めて法要を行う方でも迷うことなく、スムーズに進められます。
ここからは、申し込みから当日までの流れと、料金の詳細や追加でかかる可能性のある費用について説明します。
依頼から当日までの流れ
「てらくる」に四十九日法要を依頼する流れは次のとおりです。
- 申し込み
電話またはWebフォームから希望の日時・宗派・会場を伝える - 打ち合わせ
担当者や僧侶から連絡が入り、法要の進行や準備物を確認 - 当日
僧侶が会場に到着し、読経・焼香・法話・位牌の開眼・納骨などを執り行う - 終了後
現金払いを選んだ場合は、この時点で僧侶に直接支払います
※クレジットカードや銀行振込を選んだ場合は、先払いとなります。
申し込みのあとは打ち合わせで準備を確認すればよく、当日は僧侶の案内に従って進められます。初めて四十九日を迎える方でも戸惑うことなく、安心して臨むことができます。
定額料金に含まれるサービス
小さなお葬式「てらくる」の四十九日法要は、50,000円を基本とした定額制で依頼できます。料金には、次のような内容が含まれています。
- 僧侶による読経・法話
- 宗派指定料
- 交通費(お車代)
- 御膳料(僧侶の食事代)
- 心付け
これらの法要に必要な項目がすべて含まれているため、事前に予算が立てやすくなっています。そのため、準備に追われがちな時期でも落ち着いて式に向き合うことができます。
追加費用がかかる場合
「てらくる」のサービスは原則として定額制ですが、条件によっては別途料金が発生します。代表的なのは以下のケースです。
- 場所を移動する場合(例:自宅で読経後、墓所で納骨を行う場合)にかかる交通費
- 同日に複数の法要を行う場合(2件目以降+15,000円)
- 寺の本堂や式場等、会場を借りる場合
- 塔婆供養や過去帳記入など、プランに含まれていないオプションを依頼する場合
- 主要八宗派以外の宗派・神道などで法要を行う場合
これらは予約時の打合せで明示されるため、不安があれば早めに確認しておくことが大切です。
料金を考えるときのポイント
「てらくる」の定額制は、「お気持ちで」と包む従来のお布施と比べて、費用の目安を立てやすい点が特徴です。
ただし移動距離や追加の法要をお願いする場合など、条件によっては費用が変わることがあるため、事前に確認しておくことが欠かせません。
申し込みの流れ自体はシンプルですが、当日の行き違いを防ぐためにも、打ち合わせの段階で希望や疑問をしっかり伝えておくことが大切です。計画的に備えておけば、落ち着いた気持ちで四十九日法要を迎えられるでしょう。
四十九日に向けた準備と段取り

四十九日法要は、故人を偲び、忌明けを迎える大切な節目です。そのためには本位牌や仏壇、納骨の準備に加えて、参列者への案内や会食、返礼品といった幅広い段取りが必要になります。
準備の範囲が多岐にわたるからこそ、限られた期間の中で順序立てて進めることが重要です。ここでは、時系列で進めやすいように、具体的な準備の流れと注意点を整理していきます。
日程と会場を決める
四十九日法要の日程は、命日から数えて49日目を基準に決めます。もし平日と重なる場合は、直前の土日に前倒しで行うのが慣習であり、後日にずらすのは避けた方がよいとされています。親族の予定を調整する必要もあるため、できれば3〜4週間前には日程を確定させるのが望ましいでしょう。
会場は自宅で営むケースが多いものの、参列者が多いときには菩提寺や霊園の法要施設、セレモニーホール、ホテルの一室などを選ぶこともあります。
それぞれ使用料や食事の持ち込み可否といった条件が異なるため、早めの確認と予約が必要です。
本位牌と納骨の準備
四十九日法要では、仮位牌から本位牌へ魂を移す「開眼供養」が営まれるため、本位牌の準備が必要です。
戒名や俗名を刻む工程があり、完成までには、目安として2週間ほどかかることが一般的です。仏壇がない家庭では、新たに小型タイプの仏壇を用意するケースも増えています。その場合も、早めに手配しておきましょう。
さらに、同日に納骨を行う予定なら、墓石への刻字や石材店への墓開け依頼といった準備も欠かせません。
どれも直前では間に合わないことが多いため、葬儀直後から取りかかる意識が大切です。
案内と返礼の準備
参列者は親族が中心となりますが、故人と特に親しかった友人を招く場合もあります。
人数が多いときには案内状を送り、日時・会場・服装・香典の扱いを明記して出欠を確認するのが丁寧です。少人数であれば、電話やメールでの連絡でもよいでしょう。
法要後には「お斎(おとき)」と呼ばれる会食を設けるのが一般的です。仕出し弁当を取り寄せる方法と、料亭やレストランを利用する方法があります。どちらにするかは、参加人数や会場の状況に応じて決めましょう。
「てらくる」を利用する場合は僧侶の食事を別途用意する必要はありません。料理の手配は遅くとも2週間前には進めておくと安心です。
さらに返礼品の準備も必要です。内容は食品や日用品といった「消えもの」が一般的で、金額の目安は一人あたり2,000〜5,000円程度です。のし紙には「志」や「忌明」と記し、下段に施主の名前を入れます。
遠方から来る方にはかさばらない品を選ぶなど、受け取る側の負担に配慮するとよいでしょう。
こうした案内・会食・返礼を事前に準備しておくことで、参列者への心配りが行き届いた法要になります。
注意しておきたいこと
菩提寺がある場合は、まずそのお寺に依頼するのが基本です。
檀家でありながら他の僧侶に依頼すると、後々の関係に影響する恐れがあるためです。また、墓地を管理する寺院を利用する際には、他寺の僧侶に読経をお願いする前に必ず承諾を得ておく必要があります。
日程についても注意が必要です。法要は命日から49日目を基準に、やむを得ない場合は直前の土日に前倒しで行うのが通例です。直前の変更やキャンセルは調整が難しいため、できるだけ早めに日程を確定し、関係者に伝えておきましょう。
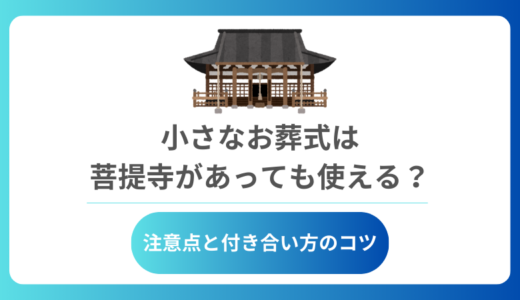 小さなお葬式は菩提寺があっても使える?注意点と付き合い方のコツ
小さなお葬式は菩提寺があっても使える?注意点と付き合い方のコツ
準備を計画的に進めるために
四十九日法要は多くの準備が必要ですが、流れを時系列で整理しておけば着実に進められます。とりわけ本位牌や納骨に関する手配は時間を要するため、葬儀直後から意識して動くことが欠かせません。
計画的に備えを整えておけば、当日は実務に追われることなく、故人を偲ぶ気持ちに集中できるでしょう。
よくある質問(Q&A)

四十九日法要を準備する中で、「誰を呼べばいいのか」「服装や会場はどうすればよいのか」と迷う方は少なくありません。
ここでは、初めて法要を迎える方が特に気になりやすい疑問をまとめました。事前に確認しておくことで、安心して当日を迎えることができます。
四十九日法要は必ず49日目に行わなければいけませんか?
本来は命日から数えて49日目が理想ですが、平日に当たる場合は直前の土日に前倒しで行うのが一般的です。49日を過ぎて後ろ倒しにするのは避け、できるだけ近い日に調整しましょう。多少早めても問題はなく、供養の気持ちを大切にすることが何よりも重要です。
四十九日法要には誰を呼ぶべきですか?
基本は親族中心で、目安としては故人から見て四親等以内とするのが一般的です。配偶者・子・孫・兄弟姉妹・おいめい・いとこなどが該当します。友人や近隣は通常招きませんが、特に親しかった方を呼ぶことは問題ありません。 参列者が少ない場合は、法要後に「忌明けの挨拶状」を送って感謝と報告を伝える方法もあります。
四十九日法要ではどんな服装で行けばいいですか?
施主や近親者は正式喪服が基本です。男性は黒のスーツに黒ネクタイ、女性は黒のアンサンブルやワンピースに黒の靴とバッグを合わせます。アクセサリーは一連の真珠程度にとどめます。遠縁の参列者は略喪服や地味な平服でも失礼にはなりませんが、色味は黒系で統一しましょう。子どもも制服や落ち着いた服装を心がけると安心です。
自宅が狭いのですが、別の場所でも法要は可能ですか?
可能です。会場は自宅以外に菩提寺、霊園併設の法要所、葬儀社のホール、ホテルや料亭の一室などが利用できます。小さなお葬式の僧侶手配サービスは、希望の会場へ僧侶が出向く形式のため、会場を選びやすい仕組みです。ただし、会場の使用料や持ち込み条件は利用者側で確認・手配する必要があります。
四十九日までに準備が間に合わなかった場合は?
本位牌や墓石の刻字が間に合わなくても、法要自体は予定日に行うのが望ましいです。仮位牌のまま読経を受け、後日本位牌に開眼供養を依頼することも可能です。墓石刻字も法要後に追加する形で問題ありません。大切なのは四十九日に合わせて供養の場を設けることなので、細部の準備は多少遅れても大丈夫です。
初七日法要を省略した場合、四十九日で補う必要はありますか?
初七日を行っていなくても心配は不要です。現代では葬儀当日に繰り上げて行うのが一般的なため、省略された形でも四十九日には影響しません。僧侶にその旨を伝えれば、初七日から七七日までの供養の意を踏まえて読経が行われることもあります。四十九日を丁寧に営むことで、十分に供養の気持ちは伝わります。
一周忌など今後の法要も小さなお葬式で頼めますか?
依頼できます。「てらくる」は四十九日に限らず、一周忌や三回忌、百箇日などの年忌法要にも対応しています。檀家登録の必要もありません。
四十九日を大切な節目として

四十九日法要は葬儀を締めくくると同時に、遺族にとって気持ちを切り替える大切な節目となります。本位牌の準備や会場の手配、参列者への案内など段取りは多岐にわたりますが、早めに取りかかれば無理なく進めることができます。
小さなお葬式の「てらくる」を利用すれば、僧侶の依頼から当日の進行までを一括して任せられ、費用も定額制でわかりやすく安心です。菩提寺がない家庭や、金額面の不透明さに不安を覚える方にとって、頼れる選択肢になるでしょう。
何より大切なのは、形式にとらわれすぎず、家族が納得できる形で故人を供養することです。計画的に準備を整えることで、四十九日法要は慌ただしさに追われるものではなく、心静かに故人を偲ぶ時間となります。
忌明けを穏やかに迎えられるよう、準備のひとつひとつを丁寧に進めていきましょう。











