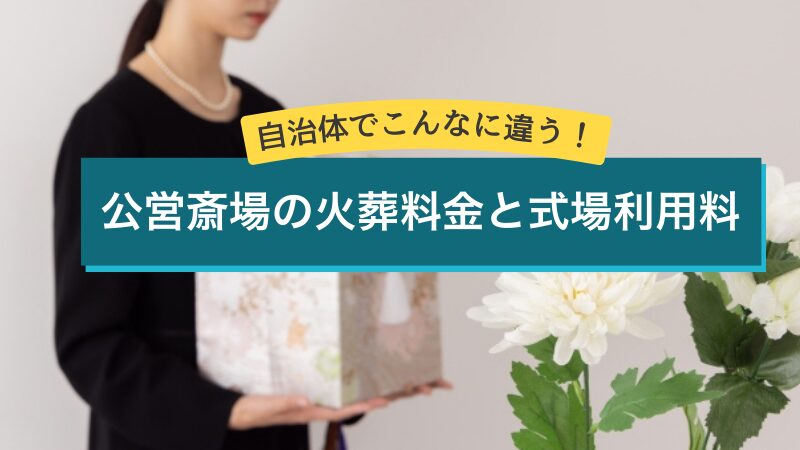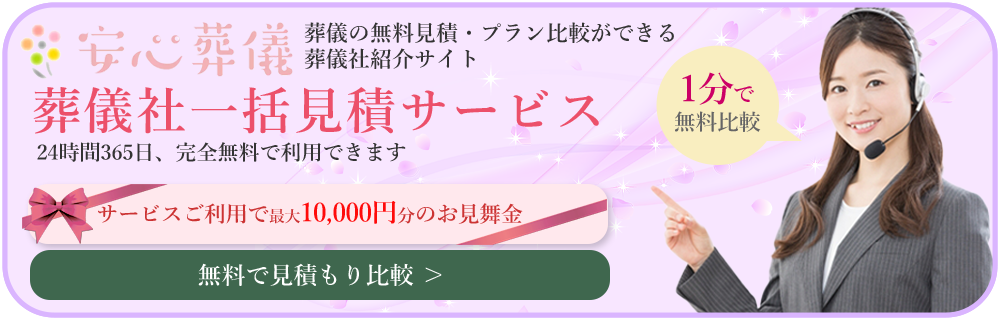葬儀費用の中でも、火葬料金と式場利用料は地域によって大きな差があります。
札幌市や新潟市のように市民は火葬が無料の地域もあれば、東京23区の民営施設では十数万円にのぼることもあります。式場についても、公営に併設されていれば数万円程度で利用できる一方、都市部では民間施設に頼らざるを得ず数十万円に達する場合があります。
本記事では、主要都市と地方都市を例に、公営斎場の火葬料や式場利用料が地域ごとになぜこれほど違うのかを整理します。制度の違いを知っておけば、葬儀費用の見通しを立てやすくなります。
火葬料金が地域で異なる仕組み

同じ火葬でも、地域によってかかる費用は大きく変わります。市民は無料の地域もあれば、数万円の料金がかかる地域もあり、都市部ではさらに高額になることもあります。
こうした差は火葬場を誰が運営し、どのように料金を決めているかによって生まれます。
自治体が決める火葬料金
日本の火葬場の多くは市町村や一部事務組合が運営しており、火葬料金は条例で定められています。全国で共通の基準はなく、各自治体の方針や財政状況によって金額が異なります。
基本的には市民料金が適用されれば無料から数万円程度で済みますが、市外利用者は倍以上の料金を請求されるのが一般的です。
公営施設が少ない都市部では民営火葬場の利用が中心となり、一回あたり数万円から十数万円に及ぶ場合もあります。こうした仕組みを知っておくことが、費用を見通す第一歩となります。
市民は無料になる公営火葬場も
一部の自治体では、市民の火葬料金を無料に設定しています。札幌市では市民0円・市外49,000円、新潟市では市民0円・市外28,000円と定められており、住民に限って負担をなくしているのです。
さらに、複数の自治体が合同で運営する「広域公営斎場」も多く見られます。埼玉県の越谷市斎場では、構成市町の住民に優遇料金が適用されます。
こうした仕組みは、火葬が公共性の高い営みと考えられていることの表れであり、地域ごとに負担の在り方が異なることを示しています。
費用差から見えること
火葬料金の違いは、単なる金額の差ではなく、地域ごとに「住民にどこまで公費を充てるか」という考え方の違いを映し出しています。ある地域では住民の負担を軽くすることを重視し、別の地域では外部利用の制限を優先するなど、方針はさまざまです。
葬儀を準備する際には自分の暮らす自治体の制度を事前に確認しておくことで、安心して備えることができます。
地域別に見る公営火葬場の料金相場

地域によって、公営火葬場の料金は大きく異なります。
札幌市や新潟市のように市民は無料で利用できる地域もあれば、東京23区では利用する施設によっては10万円を超える場合もあります。名古屋市や大阪市では1万円前後と比較的低額ですが、市外利用では数倍に跳ね上がる設定です。
こうした差は、自治体の財政方針や施設の整備状況の違いによるものです。ここでは、まず主要都市の市民向け火葬料金を一覧表で紹介し、地域ごとの特徴を詳しく見ていきます。
主要都市の公営火葬場の市民料金比較(2025年時点)
| 地域名 | 火葬料 (市民・成人) |
備考 |
|---|---|---|
| 札幌市 | 無料 | 市民以外は49,000円。控室利用は別料金。2026年度から市民も有料化予定。 |
| 東京23区 | 臨海斎場:44,000円 瑞江葬儀所:59,600円 |
臨海斎場は対象区民44,000円、対象外は88,000円。瑞江葬儀所は都民59,600円、都民以外71,520円。民営火葬場は約9万〜16万円と割高。 |
| 名古屋市 | 5,000円 | 市民以外は70,000円。市民料金は全国的に見ても低額。 |
| 大阪市 | 10,000円 | 市民以外は60,000円。 |
| 福岡市 | 20,000円 | 市民以外は70,000円。待合室利用は2時間5,000円。 |
関東(東京23区)の火葬料金
東京都23区は公営火葬場の数が限られており、料金水準は全国的に見ても高めです。
臨海斎場では対象区民が利用すれば約40,000円、瑞江葬儀所では59,600円と、市民料金でも他都市に比べて割高です。さらに、23区内の多くの火葬場は民営で、9万〜16万円と高額に設定されています。
近郊の多摩斎場は構成市町村の住民であれば無料で利用できますが、対象外の利用者は数万円を負担する仕組みです。そのため、23区に暮らす人々は結果的に民営施設を利用する割合が高く、費用面で大きな負担を感じやすい状況にあります。
なお、関東では埼玉県の越谷市斎場のように複数自治体が共同で火葬場を運営する例もあり、構成市町村の住民にとっては利用しやすい制度となっています。
 【2025年最新版】なぜ東京23区には公営の火葬場が少ないのか
【2025年最新版】なぜ東京23区には公営の火葬場が少ないのか
関西・中部地方の火葬料金
関西・中部では、自治体によって料金の差が大きいのが特徴です。
名古屋市は市民5,000円と全国的にも安価ですが、市外は7万円と一気に跳ね上がります。京都市も市民2万円に対し、市外は10万円の設定です。大阪市や神戸市は比較的穏やかですが、それでも市外との差は数倍に及びます。
市民料金は抑えられている一方で、区域外には大きな差を設ける自治体が多いのがこの地域の特徴です。
北海道・東北地方の火葬料金
北海道・東北地方では、長らく市民料金を無料または低料金に設定してきた自治体が目立ちます。
札幌市は市民無料を続けてきましたが、施設維持費の増大を背景に、2026年度から市民にも有料化を予定しています。仙台市は市民9,000円と比較的安く、新潟市も市民無料の制度を維持しています。
いずれも市外利用は数万円の設定ですが、全国的に見れば市民料金の低さが特徴的です。無料や低額を維持してきた歴史がある一方で、札幌市のように今後は見直しが進む可能性がある点も注目されます。
九州地方の火葬料金
九州地方では、市民料金を1〜2万円台、市外料金を5〜7万円台に設定する自治体が多く見られます。
福岡市葬祭場「刻の森」では市民2万円・市外7万円、北九州市では市民1.5万円、市外5.5万円とされています。首都圏や関西圏の大都市と比べると、市民料金はやや低めに抑えられているのが特徴です。
九州の大都市では人口流入が続いているものの、本州の大都市圏ほど施設がひっ迫していないため、住民料金を比較的低く設定できていると考えられます。
火葬費用はなぜ地域で違うのか
公営火葬場の料金は「無料〜2万円前後」が市民の目安、「市外利用では3〜10万円前後」が想定される相場です。東京23区では民営施設が多く料金が高くなりがちで、地方では住民への優遇が目立ちます。
葬儀を計画する際は、まず故人や喪主が住民登録している自治体の火葬料金を確認することが重要です。加えて、健康保険や自治体の葬祭費補助などを活用すれば、実際の負担を軽減できます。
こうした制度を理解したうえで、具体的にどの葬儀社に依頼するかも事前に検討しておくと安心です。
たとえば 「小さなお葬式」では、全国の式場に対応しており、費用や内容を比較しながら選べる仕組みが整っています。事前に資料を取り寄せておけば、いざというときにも落ち着いて準備ができます。
地域差を理解し、落ち着いて準備することが備えのポイントです。
火葬料金の目安と知っておきたい制度
火葬料金は自治体によって数千円から数万円まで差があり、都市部では高額に、地方では無料や低額に設定される例も見られます。こうした幅があることを知っておけば、いざというときに費用を見通しやすくなります。
- 市民料金の目安
無料〜2万円台 - 市外利用の目安
3万〜7万円前後(自治体によっては10万円程度) - 東京23区など都市部
民営施設中心で9万〜16万円
実際の負担は、このほかに健康保険の葬祭費や自治体独自の補助制度で軽減できる場合があります。
火葬料金は生活に直結する日常的な費用ではないため、制度の存在を知らずに過ごす人も少なくありません。補助の仕組みまで含めて把握しておけば、急な出費に直面しても慌てずに対応できます。
式場利用料の地域差

葬儀式場の利用料も、地域によって大きく差があります。どのようなときに費用が高くなり、逆に抑えられるのか、具体的な要因を整理しましょう。
都市部の式場費用が高くなる要因
都市部では利用者が集中する一方で土地に余裕がなく、公営式場の数が限られています。そのため、民間施設に依存せざるを得ず、使用料が大きな負担になりやすいのが現状です。
- 公営式場の数が少なく希望者が集中しやすい
- 民営式場では数十万円に及ぶケースがある
- 自社式場を持たない葬儀社では、貸し式場の利用が前提になる
このような環境では、公営と民営の料金差が大きく開きやすく、都市部の遺族ほど費用負担が重く感じられる傾向があります。
公営式場は基本的に予約制で、地域によっては希望者が多いと抽選になる場合もあります。利用を検討する際は、予約の仕組みや空き状況を事前に葬儀社に確認しておくことが重要です。
地方都市の式場費用が抑えやすい要因
地方都市や公営施設の整った地域では、式場利用料を低めに設定しているケースが多く見られます。住民向けに整備された施設や、地域に根ざした葬儀社の存在が背景にあります。
- 公営火葬場に式場が併設され、2〜5万円程度で借りられることがある
- 地方の葬儀社は自社式場を備えており、都市部の民営施設より低料金に抑えられている
- 土地や維持費の負担が都市部に比べ小さく、追加費用が発生しにくい
このような環境では、都市部と比べて式場代が半分以下に収まることも珍しくありません。公営式場や地元葬儀社の自社式場を候補に含めることで、全体の葬儀費用を抑えやすくなります。
さらに、実際にどの葬儀社を選ぶか検討するときには、一括見積サービスを活用すると効率的です。たとえば 「安心葬儀」では、複数の葬儀社のサービスや費用を比較できるので、自分の希望に合ったプランを見つけやすくなります。
地域ごとの事情と見えてくる特徴
都市部では公営式場が限られるため民営施設に頼る割合が高く、式場代が数十万円になることもあります。東京23区の代々幡斎場のような大規模施設では火葬料と合わせて負担が大きくなりやすいのが実情です。
一方で、新潟市青山斎場や臨海斎場などの公営式場は数万円台で利用でき、地方の葬儀社が持つ自社式場も10万円前後に収まるケースが多くみられます。
こうした違いは金額の大小にとどまらず、利用できる施設の数や種類そのものが異なることを示しています。葬儀を考えるときは料金だけでなく「どの施設を選べるのか」に注目することで、納得感のある準備につながります。
火葬料金に関するよくある質問Q&A
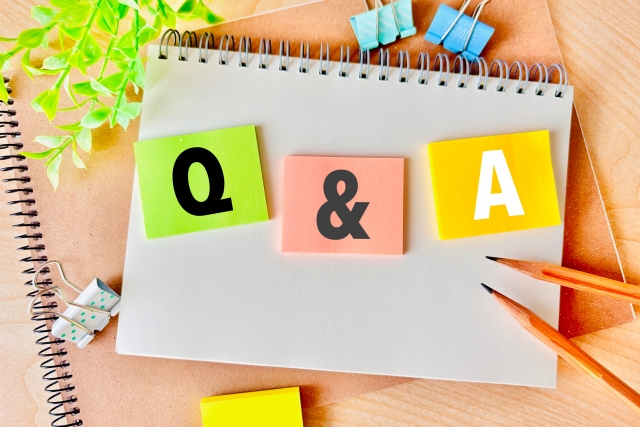
火葬料金については、「なぜ地域で差があるの?」「支払い方法はどうなるの?」など、疑問を持つ方も少なくありません。ここでは、特によく寄せられる質問をまとめて解説します。
火葬料金が無料の自治体があるのはなぜですか?
火葬は公共性の高い手続きとされているため、住民の負担を減らす目的で無料にしている自治体があります。札幌市や新潟市が代表例ですが、施設維持費の増加から将来的に有料化されるケースも見られます。
なぜ市外利用の料金は高く設定されているのですか?
火葬場は地元住民の税金で維持されているため、非住民は割高な料金を課されます。市民料金の5〜10倍に設定されることもあり、外部利用を抑制する狙いも含まれています。
火葬料金は将来変わることもありますか?
各自治体の条例で決められているため、状況に応じて改定されることがあります。札幌市も2026年度から市民料金を新設する予定で、利用状況や維持費の増加が影響しています。
火葬料金の支払い方法はどうなっていますか?
多くの自治体では、葬儀社を通じてまとめて支払う流れになっています。現現金精算のほか、近年はカード払いや振込対応が可能な斎場も増えています。事前に確認しておくと安心です。
葬儀費用の準備で知っておくべきこと

火葬や式場にかかる費用は、自治体や施設の事情によって大きく変わります。全国的に差があるのは事実ですが、実際に備えるうえで重要なのは、自分の住む地域でどのくらいの費用がかかるのかを把握しておくことです。
また、健康保険から支給される葬祭費や自治体独自の補助制度を利用できる場合があります。制度をあらかじめ調べておけば、予算の見通しが立ち、急な葬儀にも落ち着いて対応できます。
大切なのは金額の大小に振り回されるのではなく、利用できる制度や仕組みを理解し、自分たちに合った準備を整えておくことです。それが、いざというときに家族を支える力となります。