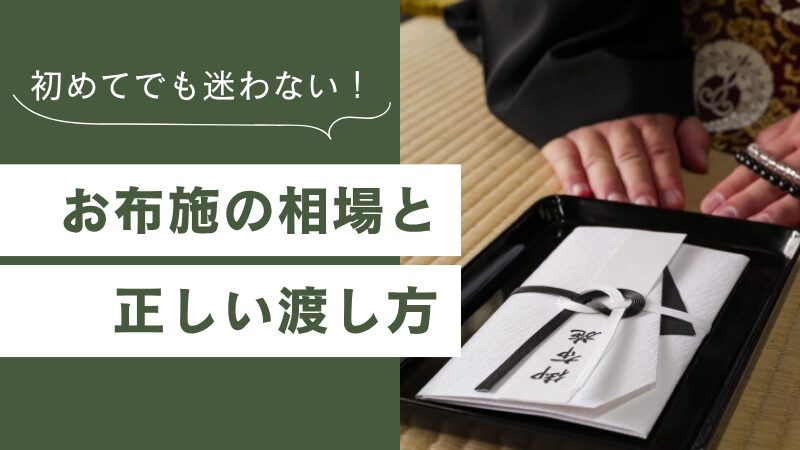お葬式や法事で僧侶に渡す「お布施」。お布施は本来「お気持ち」であり決まった額はありませんが、一般的な相場は存在します。
本記事では、通夜・葬儀のお布施の平均額や初七日・四十九日法要での目安金額、地域や宗派による違い、さらにお布施の包み方や渡すタイミングなどマナーについて詳しく解説します。
菩提寺がなく僧侶との付き合いがない方でも安心して準備できるよう、新常識を分かりやすく紹介します。
目次
葬儀におけるお布施の相場とポイント
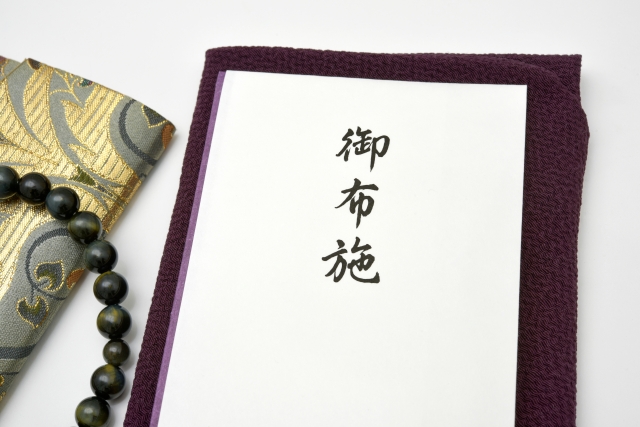
まずは通夜・葬儀で僧侶に渡すお布施の相場から見ていきましょう。お布施は本来「お礼・感謝の気持ち」なので金額に決まりはありませんが、一般的な葬儀では数十万円単位のまとまった金額を包むことが多いです。
多くの遺族が「相場が分からないと不安」と感じるため、近年では寺院側が目安額を提示するケースも増えています。
寺院との関係性や地域によって差はありますが、平均相場や内訳を知っておくと安心です。また、戒名料や御車代など葬儀特有の費用も絡むため、お布施の金額が高額になりがちな理由についても押さえておきましょう。
葬儀・告別式のお布施相場
一般的に、通夜から葬儀までの一連で僧侶に渡すお布施は20~50万円程度が相場とされています。全国平均額は約26万円とされていますが、金額には地域差があります。
例えば北海道・東北では30万円前後、関東は29万円程度、近畿では24万円程度といった傾向が報告されています。地域の慣習や物価、寺院との関係性によっても差はありますが、おおよその目安として把握しておきましょう。
お布施の内訳と宗派による違い
葬儀のお布施が高額になりやすい理由の一つが、戒名料の存在です。
戒名の位によって金額が大きく変わり、一般的な「信士・信女」なら数万円~十数万円ですが、最高位の「院居士・院大姉」では数十万~100万円以上になるケースもあります。宗派によって戒名の考え方や料金体系も異なり、例えば浄土真宗では戒名(法名)はあらかじめ決まったものをいただくため追加費用が発生しない場合もあります。
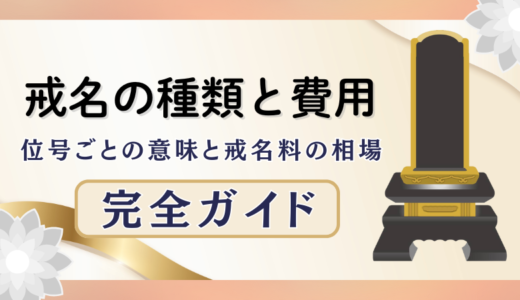 戒名の種類と費用|位号ごとの意味と戒名料の相場完全ガイド
戒名の種類と費用|位号ごとの意味と戒名料の相場完全ガイド
そのほかにも葬儀では、僧侶の移動費としての「お車代」(5,000~1万円程度)や、会食を辞退された場合の「御膳料」(5,000~1万円程度)を別途包むことがあります。これらを含めてトータルでお布施と考え、適切な金額を用意しましょう。
菩提寺がない場合の僧侶依頼方法
菩提寺がない方は、葬儀社に僧侶を紹介してもらったり、インターネットから僧侶手配サービスを利用したりする方法があります。たとえば、「よりそうお葬式」では「よりそうお坊さん便」というサービスが用意されており、定額料金で葬儀・法要のお坊さんを手配してくれます。
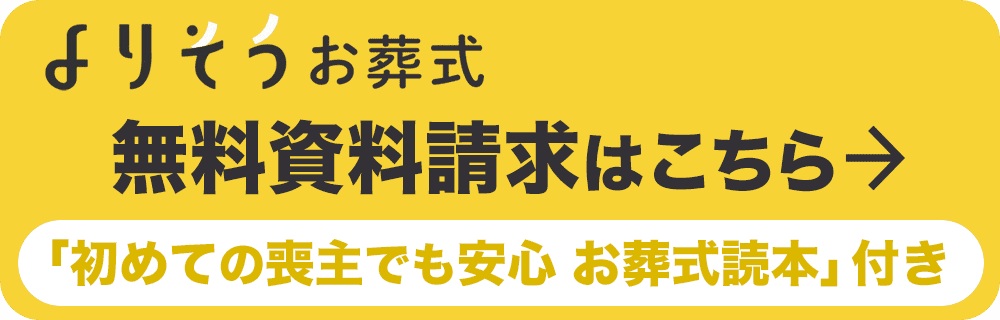
全宗派に対応し、戒名のランクごとの費用が明示されていることも多いので安心して依頼できます。菩提寺がなく相場感がつかめない場合でも、こうしたサービスを利用すれば必要なお布施額が事前にわかるため、経済的な不安を和らげられるでしょう。
お布施は「お気持ち」とはいえ相場があります。葬儀社や専門サービスの力も借りつつ、無理のない範囲で感謝の気持ちを包むことが大切です。
法要ごとのお布施相場と注意点

葬儀のあとも、初七日や四十九日など故人の冥福を祈る忌日法要が続きます。法要で僧侶にお経をあげていただく際にもお布施をお渡ししますが、葬儀に比べると金額は数万円程度と小さくなります。
ここでは初七日・四十九日法要を中心に、お布施の相場と包み方のポイントを解説します。また、地域によっては初七日を葬儀当日にまとめて行うケースや、浄土真宗では忌日法要自体を行わないケースがあるなど、宗派・地域の違いについても触れておきます。
初七日法要のお布施相場
初七日(しょなのか)とは、命日から7日目に行う最初の忌日法要です。僧侶へのお布施相場は3万~5万円程度とされています。
近年では葬儀当日に初七日法要を繰り上げて行う地域も多く、その場合は葬儀のお布施に含めて渡すか、あるいは別途数万円を包むこともあります。初七日法要では戒名のお披露目を兼ねる場合もあり、戒名代が含まれることからやや高めの金額設定になる傾向があります。
菩提寺がない場合でも、葬儀を依頼した葬儀社などが初七日の進行をサポートしてくれますので、適宜相談するとよいでしょう。
四十九日法要(忌明け法要)のお布施相場
四十九日(しじゅうくにち)法要は、故人が仏教の世界観で忌明けを迎える大切な法要です。お布施の相場は初七日と同じく3万~5万円程度が一般的です。一つの目安としては、「葬儀で渡したお布施額の1~2割程度」という考え方もあります。
たとえば葬儀のお布施が30万円なら四十九日は3~6万円、50万円なら5~10万円といった具合です。
なお、四十九日ではお墓への納骨式も同時に行うことが多く、その場合お布施は納骨分も合わせて包むのが一般的です。別々に行う場合、納骨のお布施は1万~5万円程度が目安になります。
その他の法要(初盆・年忌法要)の相場
忌明け後も、一周忌や三回忌などの年忌法要や、初盆・お彼岸などで僧侶を招いて供養する機会があります。これらのお布施相場も四十九日と同様に3万~5万円程度が基本です。
ただし年数が経つにつれ参列者や規模が小さくなることから、三回忌以降は1万~3万円程度に下がるケースもあります。初盆は特に盛大に供養するため3~5万円が目安ですが、地方によっては寺院での合同供養(盆会や彼岸会)に参加し、3千~1万円程度の志を納める形もあります。自宅で僧侶に来てもらう場合は個別法要となり相場は3~5万円です。
いずれにせよ、法要の種類に応じて数万円規模のお布施を用意するのが一般的と覚えておきましょう。
宗派・地域による法要習慣の違い
法要のお布施は宗派や地域によっても違いがあります。例えば浄土真宗では「故人はすぐ成仏する」との教えから初七日の忌日法要を行わないことも多いです。また関西などでは五十日祭(神式の忌明け)に合わせて四十九日を省略する地域もあります。
お布施額も寺院の方針で定額化されている場合や、「お気持ちで」と言われる場合など様々です。菩提寺がない場合は、地域の葬儀社や僧侶からアドバイスをもらい、その土地や宗派のしきたりに合った金額を包むのがおすすめです。感謝の気持ちを大切に、適切な額を包むようにしましょう。
お布施の正しい包み方・渡し方マナー

金額だけでなく、お布施の包み方や渡し方のマナーも覚えておきたいポイントです。市販の不祝儀袋を使う場合や、白無地の封筒に包む場合など形式はいくつかありますが、「御布施」という表書きを書き、袱紗(ふくさ)に包んで丁重に渡すのが基本です。
ここではお布施袋の書き方、入れるお札のマナー、そして実際に僧侶へ手渡しするタイミングと作法について解説します。これらを押さえておけば、いざという時にも恥ずかしい思いをせずに安心して対応できるでしょう。
お布施袋の種類と表書きの書き方
お布施を包む際は、郵便番号枠のない白無地の封筒か、蓮の花などが無いシンプルな不祝儀袋を使用します。水引は基本的に不要ですが、地域によって黒白や黄白の水引をかける風習がある場合はそれに従います。
封筒の表面中央上部に濃墨で「御布施」または「お布施」と表書きをし、その下に施主の氏名を書きます。家族名義で出すなら「◯◯家」としても構いません。裏面には左下に住所と金額を記入します。
なお、神式の場合は表書きは「御祭祀料」や「御礼」、キリスト教では「献金」「御礼」など宗教ごとに異なります。いずれの場合も、毛筆または筆ペンで丁寧に書くようにしましょう。
お布施に入れるお札の向き・お金の準備

お布施に入れる現金は、可能であれば新札を用意するのが望ましいとされています。香典の場合は事前準備を連想させる新札を避けますが、お布施はお寺へのお礼のため、新しいお札で問題ありません。新札がなければ折り目のない綺麗なお札を選びましょう。
お札の入れ方は慶事と同様で、お札の向きを揃えて肖像画が封筒の表を向くように入れます。お札は直接封筒に入れるより、奉書紙や白い半紙で包んでから封筒に入れるとより丁寧です。また、折れてしまわないように封筒は袱紗に包んで持参しましょう。
お布施を渡すタイミングと作法
僧侶にお布施を手渡すタイミングは、葬儀の場合は開式前にお渡しするのが一般的です。僧侶が式場に到着したら、葬儀社スタッフの案内に従いご挨拶とともにお渡しすると良いでしょう。
法要の場合は儀式終了後、僧侶がお帰りになる前にお渡しします。僧侶が法要後の会食に参加されない場合は法要直後に、参加される場合は会食後に退出されるタイミングで差し出します。
いずれの場合も、袱紗からお布施袋を取り出し、切手盆に載せて「本日はありがとうございました。どうぞお納めください」など一言お礼を添えて差し出します。
人前で現金を渡す場面になりますので、できれば他の参列者から見えにくい場所で行うのがマナーです。万一渡しそびれそうになった場合でも、僧侶が帰られる前には必ずお渡しするようにし、遅れた失礼をお詫びする気持ちも伝えましょう。
複数の謝礼(お車代・御膳料)がある場合
お布施とともにお車代や御膳料(食事辞退の謝礼)を渡す場合は、それぞれ別の封筒に包みます。表書きは「御車代」「御膳料」とし、金額は一般的に5千~1万円程度です。
お布施の封筒と合わせて切手盆に載せますが、重ねる順番にもマナーがあります。下から順に「御膳料」「お車代」「御布施」の順で重ね、僧侶から見て文字が正面になる向きに揃えます。いずれの場合も、感謝の気持ちを伝えることが大切です。
形式ばかりに気を取られずとも、「ありがとうございます」という感謝の心をもって丁寧にお渡しすれば、その気持ちはきちんと伝わるでしょう。
神式・キリスト教の「お布施」はどうする?

日本の葬儀の多くは仏式ですが、神式やキリスト教式で葬儀・法要を行う場合にも、宗教者への謝礼をお渡しする慣習があります。「お布施」という呼び方はしないものの、神主や神父・牧師へのお礼として金封を包む点は共通です。
ここでは神式とキリスト教式の場合、それぞれどのような名目・金額でお渡しするのかを解説します。仏式との違いを知り、いざという時に正しい対応ができるようにしておきましょう。
神式の場合|御祭祀料の相場とマナー
神道の形式で葬儀や霊祭を行う際は、神社の神職(神主)に祭祀を執行していただいたお礼として「祭祀料(さいしりょう)」をお渡しします。
表書きは「御祭祀料」や「御祈祷料」、またはシンプルに「御礼」と書くのが一般的です。封筒は白無地か白黒の水引付き不祝儀袋(蓮の絵は不可)を使用します。金額に明確な決まりはありませんが、仏式のお布施に相当するものとして15万~30万円程度を包むケースが多いようです。
神式でも僧侶のお車代・御膳料に相当する謝礼を別途渡す習慣があり、それぞれ5,000円前後が目安です。渡すタイミングは仏式同様、儀式前後の神主への挨拶時に手渡します。
キリスト教式の場合|献金・謝礼の相場とマナー
キリスト教の葬儀でも、司祭や牧師へのお礼を包んで渡すのが一般的です。ただし仏教と異なり、教会への献金としての意味合いが大きいのが特徴です。
具体的には、プロテスタントでは牧師に対して教会に使ってもらう「献金」を渡し、カトリックでは神父に対してミサをしていただいた「謝礼」として渡します。表書きは「献金」または「御礼」などと書きます。
金額は5万~15万円程度が一つの目安と言われます。戒名料がない分、仏式より総額はやや抑えめになるようです。このほか、式でオルガンを弾いてくれた奏者や聖歌隊へのお礼も忘れずに別封筒で用意します。オルガニストへの謝礼相場は5千~2万円程度です。
また、教会ではなく葬儀式場に牧師・神父に来てもらった場合は、5,000円程度の御車代を渡す点も仏式と同様です。渡すタイミングは、式の前後に牧師・神父へ直接手渡すか、教会の場合は式前に受付などでまとめて献金箱へ納める場合もあります。
キリスト教式はカトリックやプロテスタントなど、宗派や教会の方針によっても習慣が異なるため、事前に教会に確認するのが確実でしょう。いずれも感謝の気持ちを込め、適切な名目でお礼を包む点で共通しています。
おわりに

葬儀や法要でのお布施の相場とマナーについて解説してきました。菩提寺がない方でも、一般的な目安を知っておけば過不足ない金額を用意できますし、正しい渡し方のマナーを押さえておけば自信を持って当日に臨めます。
故人を送り出す場では、形式も大事ですが何より大切なのは感謝の心です。無理のない範囲で心を込めてお布施を包み、丁寧にお渡しすれば、その想いはきっと僧侶にも伝わることでしょう。
もし「お布施の準備や僧侶への依頼が不安…」という場合は、小さなお葬式やよりそうお葬式![]() などの僧侶手配付きの葬儀プランを利用するのもおすすめです。こうしたサービスではお布施の額が初めから提示されているため、初めての方でも安心して依頼できます。
などの僧侶手配付きの葬儀プランを利用するのもおすすめです。こうしたサービスではお布施の額が初めから提示されているため、初めての方でも安心して依頼できます。
新しい葬儀の形を取り入れ、故人とご家族が納得のいくご供養を検討しましょう。