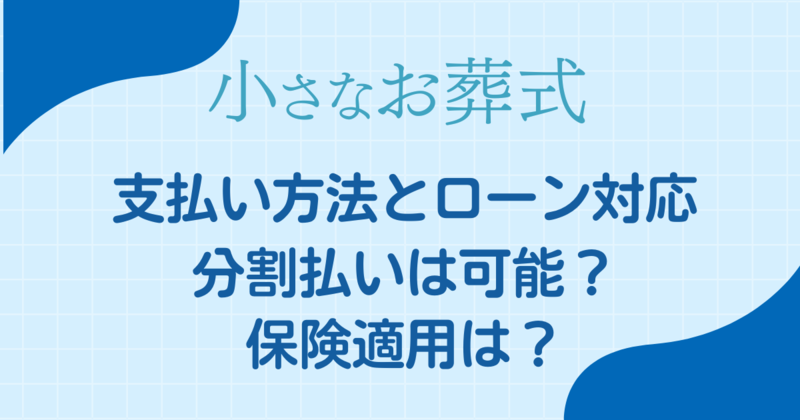大切なご家族の葬儀費用をどう支払うかは、多くの高齢者やご家族にとって大きな不安材料です。特に、低価格で葬儀を提供する「小さなお葬式」を利用する場合でも、クレジットカードは使えるのか、分割払い・ローンは可能か、生命保険や公的給付金は当てられるのかといった点が気になることでしょう。
本記事では、小さなお葬式が提供する各プランの料金と、利用できる支払い方法(現金・カード・電子決済・ローン・保険等)について詳しく解説します。信頼できる情報をもとに丁寧に説明しますので、ご自身に合った支払い手段を検討する際の参考にしてください。
目次
小さなお葬式の葬儀プランと料金

「小さなお葬式」では規模や内容に応じて5つの基本プランが用意されています。それぞれのプランの概要とともに料金を確認しておきましょう。
小さなお別れ葬
火葬のみを行う最も簡素なプランです。通夜や告別式などの儀式は一切行わず、宗教的な儀礼も省いた無宗教者向けの最安プランになっています。式典にかかる祭壇や仏具を用いないため費用を最小限に抑えられます。料金:154,000円→資料請求割適用後:99,000円(火葬料別)。
小さな火葬式
通夜・告別式を行わず火葬のみ執り行うシンプルな直葬プランです。最低限の葬儀サービスが含まれており、参列者を招かず祭壇も飾らないため経済的負担を抑えられます。料金:231,000円→資料請求割適用後:176,000円(火葬料別)。
小さな一日葬
お通夜を省略し、告別式から火葬まですべて1日で行う葬儀プランです。ご高齢の参列者や遠方から来られる方の負担も軽減でき、儀式自体は執り行うため故人とのお別れもしっかりできます。料金:440,000円→資料請求割適用後:385,000円(火葬料別)。
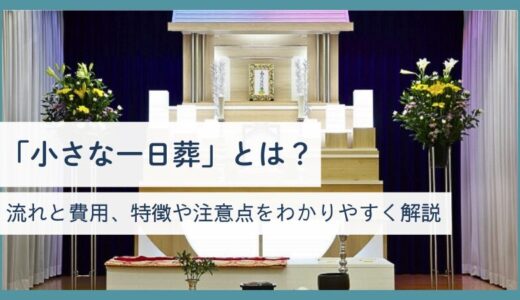 「小さな一日葬」とは?流れと費用、特徴や注意点をわかりやすく解説
「小さな一日葬」とは?流れと費用、特徴や注意点をわかりやすく解説
小さな家族葬
家族や親族中心で通夜・告別式の二日間を行う家族葬プランです。一般会葬者(職場関係者や近所の方など)を招かず身内だけでゆっくりお別れの時間を過ごせる内容になっています。料金:550,000円→資料請求割適用後:495,000円(火葬料別)。
小さな一般葬
ご近所や仕事関係の方々など多数の参列者を招いて通夜・告別式を行う一般葬プランです。大人数の葬儀に必要な物品・サービスが含まれており、従来型の一般的なお葬式を低価格で執り行えます。料金:715,000円→資料請求割適用後:660,000円(火葬料別)。
※上記料金はいずれも税込価格です(火葬料金は別途負担となります)。火葬料金は地域や火葬場によって異なり、首都圏の一部民営火葬場では6万円程度かかる場合があります。契約前に火葬料の目安も含め、総額を確認しておきましょう。
 「小さなお葬式」とは? 費用やプラン、口コミなど徹底的に調べてみました
「小さなお葬式」とは? 費用やプラン、口コミなど徹底的に調べてみました


現金払い(葬儀後の現地支払い)

現金一括払いは最もシンプルで追加手数料のかからない支払い方法です。小さなお葬式では基本的に火葬終了後に葬儀社スタッフへ現金で費用を支払います。現金払いのメリットは、金利や決済手数料が一切かからず、借金の心配をせずに済む点です。その場で口座残高以上の支払いを強いられることもなく、後日の返済負担が残らないため、費用を用意できる場合は最も安心な方法と言えます。
注意点として、大金を用意する必要があるため銀行やATMからの引き出しに手間がかかることや、急な出費に即座に対応できない場合があることが挙げられます。しかし費用を用意できるのであれば余計な利息負担がない現金払いが最も経済的です。また、葬儀費用の支払い期限は、担当する提携葬儀社によって異なります。現金払いの場合は期限までに用意できるよう計画しておきましょう。
クレジットカード払い(一括・分割)

クレジットカード決済は、小さなお葬式で利用できる便利な支払い方法です。JCB・VISA・Mastercardなど主要なカードブランドであれば、オンライン決済フォームからカード決済が可能です。カード払いの利点は、現金をすぐ用意しなくても支払いができる点と、カードのポイントやマイルが貯まる点です。例えば高額な葬儀費用をカード払いにすれば、まとまったポイントが付与され後日お得に活用できるでしょう。
小さなお葬式ではクレジットカード利用時に一括払いだけでなくカード会社の分割・リボ払いを利用した分割決済も可能です。ただし、カードの分割払いやリボ払いを利用する場合はカード会社所定の手数料(年利)が発生します。また、高額決済になるためカード利用限度額にも注意が必要です。事前に利用枠を確認し、不足する場合はカード会社に臨時枠の増額を相談するか、一部を現金で支払うなどの計画を立てましょう。
電子決済・後払いサービス(コンビニ・スマホ決済)

「小さなお葬式」では、現金やカード以外に後払い決済サービスも利用できます。これは、葬儀後にコンビニエンスストアや銀行・郵便局で支払える請求書後払い方式で、「@払い(アット払い)」という決済サービスが導入されています。後払いサービスを利用すれば今すぐにまとまった現金を用意できなくても大丈夫で、請求書が発行されてから一定期間内(通常14日以内)に支払えばよいため無理なく利用できます。
後払いの仕組み
葬儀依頼時にスタッフから案内があった場合、後払いを選択できます(すべての利用者に必ず案内されるわけではなく、状況に応じ案内されるようです)。葬儀終了後、決済代行会社の株式会社SCOREより郵送で払込票(請求書)が送付されてきます。払込票が届いてから14日以内に、全国のコンビニ・銀行・郵便局で支払いを行います。コンビニで支払う場合は深夜でも対応可能ですし、銀行・郵便局での振込にも対応しています。また、払込票のバーコードを利用してスマホ決済アプリから支払うことも可能です。普段スマホ決済に慣れている方は、自宅から支払いが完結するため便利です。
手数料と利用条件
後払いを利用する場合、手数料として一律11,000円(税込)が葬儀費用とは別にかかります。この手数料はサービス利用料として必要になりますので、例えば葬儀費用15万円の場合は+1.1万円で計約16.1万円を支払う形になります。後払いには利用上限額が340,000円(税込)と定められており、基本的には「小さなお別れ葬」「小さな火葬式」「小さな一日葬」のような比較的費用の小さいプランで利用可能なサービスです(費用が340,000円を超える場合は利用できません)。また後払いは一括払いのみで、分割払いには対応していません。
審査について
後払いサービスを利用する際には、決済代行会社による簡易な審査(与信確認)があり、必要に応じて確認連絡が入る場合があります、信用情報に基づき後払い利用可否が判断されます。過去に金融トラブル(長期延滞や債務整理など)がある場合などは後払い利用が断られる可能性もあります。万一審査に通らなかった場合には、他の支払い方法(例えばクレジットカードや葬儀ローン等)に切り替える必要があります。後払いを希望する方は、あらかじめこうした点も念頭に置きつつ、必要であればスタッフに相談すると良いでしょう。
葬儀ローン(分割払い)
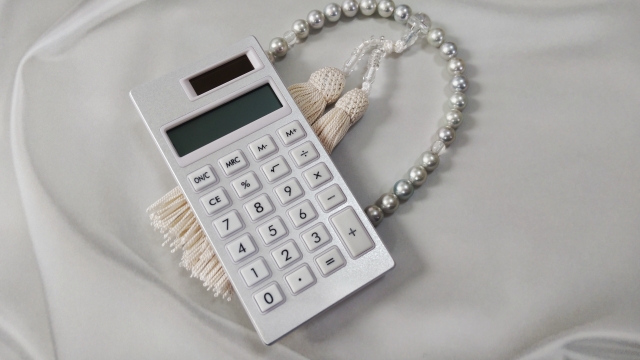
葬儀費用を一度に用意できない場合、葬儀ローン(分割払いローン)を利用する方法もあります。小さなお葬式ではオリコ(オリエントコーポレーション)と提携したローン払いが用意されており、オリコのローン規定に基づく支払い回数を選択して分割返済することが可能です。ローンを利用すれば、手元にまとまったお金がなくても毎月少しずつの支払いで葬儀費用を賄うことができ、予算オーバーしがちな場合でも費用を分割できるため、支払い方法の選択肢が広がるというメリットがあります。
申し込み方法
葬儀ローン利用を希望する場合は、依頼時にスタッフへ相談します。葬儀社経由でオリコのWebクレジット申込み手続きを行うと、審査がスムーズに進みます。ただし、葬儀後にローンを申し込むことはできないため、葬儀社との打ち合わせ段階で必ずローン利用の意思を伝え、契約時に組んでおく必要があります。
金利と費用
葬儀ローンを利用する際には、当然ながら所定の金利(分割手数料)が発生します。金利(分割手数料)はオリコの規定に基づきます。カードローンや消費者金融よりは低金利とはいえ、無利息の現金払い等と比べれば割高になるため、ローン利用時は毎月の返済額と総支払額をよく計算して計画を立てることが大切です。
審査基準
葬儀ローンも通常のローンと同様に信用情報に基づく審査があります。提携ローンは通りやすい傾向とはいえ必ず審査に通るわけではなく、債務整理や自己破産の経験がある方、現在多額の借入がある方、過去に支払い滞納歴がある方などは審査通過が難しくなる可能性があります。実際に審査により利用できない場合もあるため、信用情報に不安がある場合は他の支払い方法も検討しておくことが安心です。
葬儀ローン利用時の注意
一つ注意したいのは、葬儀ローンの融資金は葬儀社に支払う費用にのみ充当可能という点です。例えばお寺へのお布施や宗教者へのお礼(読経料など)は葬儀社への支払いではなく直接寺院へ渡す費用のためローンには含められません。小さなお葬式では僧侶手配サービス(お布施込み)もオプション提供していますが、その費用をローンに組み込めるか事前に確認しておきましょう。なお、ローンを申し込んだものの万一審査に落ちた場合でも諦める必要はありません。葬儀社の担当者に相談すれば、規模を縮小して費用を抑える提案や、自治体の市民葬・区民葬制度の案内など、可能な対策を一緒に考えてくれるはずです。まずは遠慮なく相談することが大切です。
生命保険金や自治体の給付金を葬儀費用に充当する

葬儀費用の支払いには、故人が残した生命保険金や公的な給付金制度を当てることも可能です。ただし、これらは一時的な立替えにはなり得ても直接その場での支払い手段にはなりにくい点に注意が必要です。以下、生命保険金や自治体から支給される葬祭費補助について解説します。
生命保険金の活用
故人が生命保険に加入していた場合、受取人(多くはご遺族)は所定の手続きを経て死亡保険金を受け取ることができます。葬儀費用を保険金でまかなおうと考える方も多いですが、実際には保険金の請求から振込までに時間がかかる点に留意しましょう。保険会社に請求書類を提出してから保険金の支払いまでには一定の日数がかかり、場合によっては数週間に及ぶこともあります。一方で前述の通り葬儀社への支払い期限は葬儀後1~2週間程度が目安です。そのため、保険金が振り込まれるタイミングでは葬儀社への支払い期日に間に合わない可能性が高いのです。
では、保険金を充てたい場合どうすれば良いかというと、一時的に他の手段(カード払いや後払い等)で立替えておき、後から保険金で補填する方法が現実的です。例えばクレジットカードで葬儀費用を支払い、翌月以降に保険金が下りたらカード支払い分を充当する、といった形です。または、どうしても保険金の受取りを待って支払いたい事情がある場合には、葬儀社に相談して支払い期日を延ばしてもらえるか掛け合ってみる手もあります。小さなお葬式のように実績豊富な葬儀社であれば、状況に応じて柔軟に対応策を提案してくれることもありますので、まずは正直に状況を伝えてみると良いでしょう。
 葬儀保険は本当に必要?加入前に知っておくべき仕組みとポイント
葬儀保険は本当に必要?加入前に知っておくべき仕組みとポイント
公的な葬儀費用の給付金制度
故人が公的医療保険に加入していた場合、葬儀後に申請することで給付が受けられる制度があります。代表的なものは「葬祭費」(故人が国民健康保険加入者だった場合など)および「埋葬料」(故人が会社勤めで社会保険〔健康保険〕加入者だった場合)です。これらはいずれも喪主に対して支給される給付金で、故人の遺産ではなく喪主自身の財産となります。受給には葬儀後に申請書類を提出する必要がありますが(申請期限は死亡翌日から2年以内のことが多い)、申請さえすれば誰でも受け取れる公的支援ですので、忘れず活用しましょう。
国民健康保険加入者の場合の「葬祭費」
故人が国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入していた場合、葬儀を行った喪主に葬祭費が支給されます。支給額は自治体によって異なりますが、おおむね1万円~7万円程度が一般的です。例えば東京23区では一律7万円、その他の地域でも5万円程度の自治体が多くなっています。後期高齢者医療保険の場合も3万~7万円(東京23区は7万円)と定められています。なお国家公務員共済組合など職域の共済に加入していた場合は、組合によりますが10万円~27万円と高額の給付になるケースもあります。申請先は国民健康保険なら市区町村の役所(保険年金課)、共済なら所属していた共済組合です。支給までには申請から数週間程度を要することがありますが、申請しないともらえないお金ですので必ず手続きを行いましょう。
会社員等・社会保険加入者の場合の「埋葬料」等
故人が健康保険(社会保険)に加入していた場合、勤務先の健康保険組合から埋葬料が支給されます。金額は原則一律5万円(被扶養者が亡くなった場合も同額の「家族埋葬料」5万円)です。健康保険組合によっては付加給付として給与1か月分相当額が上乗せ支給されるところもあり、一概には言えませんが、少なくとも5万円は受け取れると考えておきましょう。一方、故人に扶養者がおらず喪主が本人でない場合(例:お一人暮らしの方の葬儀を親族が行った場合)には、実費を支給する埋葬費として上限5万円まで受け取れる制度もあります。いずれにせよ健康保険証を返却する際に案内がありますので、会社もしくは加入していた保険組合に確認してみてください。申請期限は葬祭費と同じく2年以内です。
生活保護受給者の場合の「葬祭扶助」
故人が生活保護を受給していた世帯の場合、自治体の葬祭扶助制度によって葬儀費用の全額または一部が公費負担されます。葬祭扶助は生活保護世帯や自治体が定める一定の低所得世帯が対象で、事前に福祉事務所へ申請する必要があります。支給額は自治体ごとに異なりますが、概ね20万円前後が上限です。例えば東京都では葬祭扶助として約20万円が支給されます。この制度を利用すれば、小さなお葬式の「小さな火葬式」や「小さなお別れ葬」の費用は自治体負担でまかなわれ、自己負担0円で葬儀を行うことも可能です。葬儀費用に不安がある方は、お住まいの自治体に葬祭扶助の条件や手続きを確認してみてください。
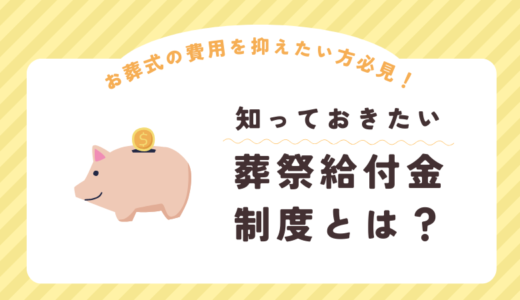 親の葬儀後に申請できる「給付制度」って?【2025年版】補助金制度まとめ
親の葬儀後に申請できる「給付制度」って?【2025年版】補助金制度まとめ
支払い方法を検討する際の注意点
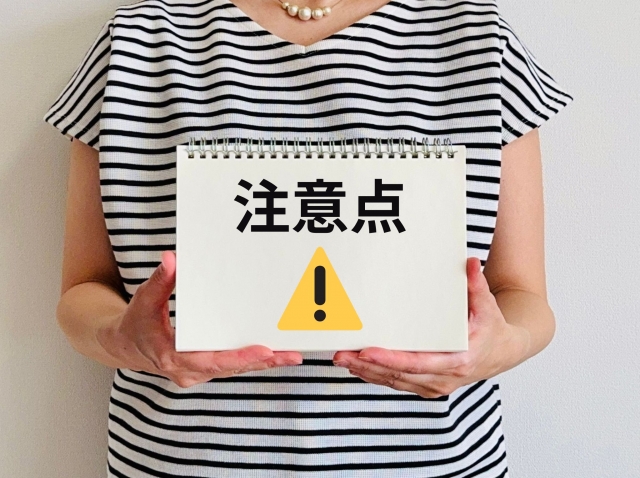
葬儀費用の支払い方は複数ありますが、どの方法を選ぶにせよいくつか注意しておきたいポイントがあります。
事前相談と手続きが肝心
カード払いやローンは、依頼時にスタッフへ希望を伝える必要があります。後から「やっぱりカードで払いたい」と思っても対応できないので、最初に決めておきましょう。また、生活保護の葬祭扶助を利用する場合も事前の手続きが必要です。いずれの場合も早め早めの相談・申請がスムーズな支払いにつながります。
ローン審査や後払い審査に落ちる場合もある
葬儀費用のローンや後払いには審査が伴います。誰でも必ず利用できるとは限らないことを念頭に置いてください。万一、ローンの審査に通らなかった場合でも代案はあります。葬儀社に相談すれば、状況に応じて個別提案が行われる場合があります。支払いが難しいときほど一人で悩まず、遠慮なく専門家に相談しましょう。
各種支払いのコストに注意
現金払い以外の方法には、それぞれコストがかかります。クレジットカードの分割払いやリボ払いは年利手数料が、葬儀ローンにはオリコの規定に基づく利息が発生し、後払いには手数料11,000円が上乗せされます。これらは便利さと引き換えの費用と言えます。予算に限りがある場合は、手数料負担まで含めて計画を立てましょう。逆に言えば、費用面で余裕があるなら現金払いが最も経済的です。
生命保険・給付金はタイミングに注意
生命保険金や葬祭費給付金は、請求から受け取りまで一定の時間がかかるため、葬儀直後の支払いには使いにくい点を押さえておく必要があります。まとまった金額を後から受け取れる見込みがある場合は、いったんカード払いや後払いなどで立て替え、受取後に返済へ充てる方法が現実的です。ローンの繰上返済が可能かどうかは契約によって異なるため、利用前に確認しておくと安心です。また、公的給付金には申請期限があるため、葬儀後に忘れず手続きを行い、受け取った給付金を家計の補填に活用すると良いでしょう。
寺院へのお布施等の扱い
葬儀プランに僧侶へのお布施は含まれないケースが多いです(小さなお葬式でもオプション扱い)。お布施は葬儀社ではなく寺院へ直接渡すものなので、クレジットカード払いやローンには基本的に含められません。お布施分は現金を別途用意するか、契約内容によっては葬祭費用の一部を早期に受け取れる特約が付いている場合があるため、その制度を利用するなど工面が必要です。この点も計画に入れておきましょう。
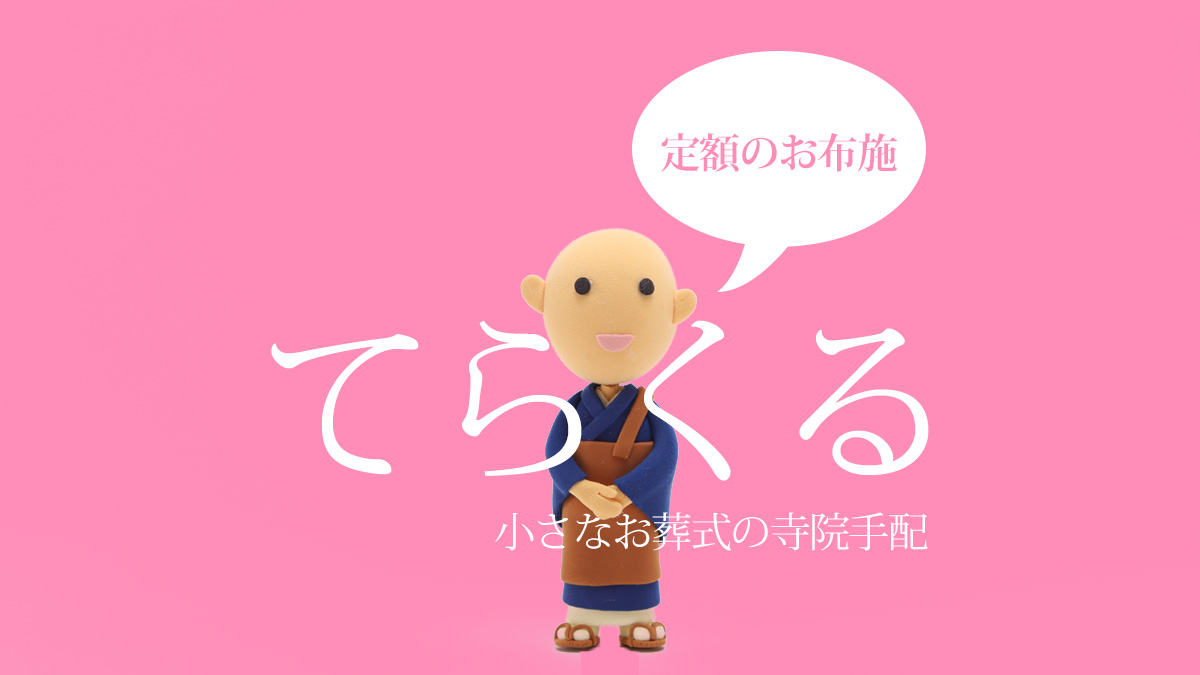 小さなお葬式の寺院手配「てらくる」とは?サービス内容と口コミ・評判を解説
小さなお葬式の寺院手配「てらくる」とは?サービス内容と口コミ・評判を解説
まとめ

「小さなお葬式」では、現金・クレジットカード・後払い・ローンと複数の支払い方法が用意されており、それぞれにメリットと留意点があります。現金払いは追加手数料がかからない、カード払いはポイントが貯まり即時決済可能、後払いは手元資金ゼロでも利用可、ローン払いは費用を月々に分散できる…といった具合です。それに加えて、生命保険金や自治体の給付金制度もうまく活用すれば葬儀費用の実質的な負担を減らすことができます。大切なのは、安心して支払い方法を選べるよう十分な情報を持つことです。本記事で解説した内容を参考に、ご自身の経済状況やご希望に合った支払い手段を検討してみてください。不明な点や不安があれば、遠慮なく葬儀社のスタッフに相談しましょう。専門スタッフは24時間体制で対応しており、相談に応じてもらえることが多いでしょう。各種支払い方法の特徴を把握しておくことで、葬儀に必要な準備や費用計画を進めやすくなります。