日本の葬儀マナーや作法には、地域ごとに意外な違いがあります。とくに仏式の葬儀では、関東と関西で習慣や進め方に大きな差が見られることがあります。
例えば、関東では葬儀会場の入口に「花輪」を飾るのが一般的ですが、関西では常緑樹の「樒(しきみ)」を供える伝統があります。こうした相違点を知らずに引っ越してきた人が「同じ日本なのに葬儀の習慣がこんなに違うのか」と驚くことも少なくありません。
本記事では、香典の金額や表書き、焼香の作法、服装や挨拶、通夜・告別式の流れ、精進落としや香典返しまで、関東と関西のお葬式マナーを比較し、その背景や注意点をわかりやすくご紹介します。
目次
香典の金額・包み方・表書きの違い

葬儀で遺族に渡す香典は、関東と関西で金額の相場や包み方などに違いが見られます。さらに、香典を受け取るかどうかの習慣も地域によって異なります。こうした差を理解しておけば、参列時に慌てず対応できるでしょう。
水引と表書きの違い
香典袋の水引は、関東・関西ともに黒白や銀色が一般的です。ただし関西では、地域や慣習によって黄白が使われることもあります。
表書きについては、関東では宗教を問わず「御霊前」が広く使われ、仏式では「御香典」や「志」とすることもあります。関西でも香典袋には同様の表書きが用いられますが、香典返しの表書きに「満中陰志」と記す習慣が根付いており、この点で地域差が表れます。
さらに浄土真宗では故人をすぐ仏とみなすため、香典袋に「御仏前」と書くのが本来の作法です。地域差と宗派差を分けて理解することが大切です。
香典金額の相場
香典に包む金額は、関東ではやや高め、関西では低めの傾向があります。
これは関東に「通夜ぶるまい」の習慣があり、その費用を含める意味合いがあるためです。一方、関西では通夜後の会食を設けないのが一般的で、香典は比較的抑えられています。
代表的な相場を比べると次のとおりです。
| 続柄・関係 | 関東の相場 | 関西の相場 |
|---|---|---|
| 両親 | 10万円 | 5万円 |
| 兄弟姉妹 | 5万円 | 3〜5万円 |
| 祖父母 | 3万円 | 1〜3万円 |
| その他親族 | 1万円 | 5千〜1万円 |
| 友人・知人 | 5千〜1万円 | 3〜5千円 |
| 上司 | 5千〜1万円 | 5千円 |
| 同僚・部下 | 5千〜1万円 | 3〜5千円 |
表のとおり、金額は関東が高めに設定される傾向があります。相場を大きく超えると遺族に気を遣わせる場合があるため、地域の慣習に沿った額を包むことが大切です。
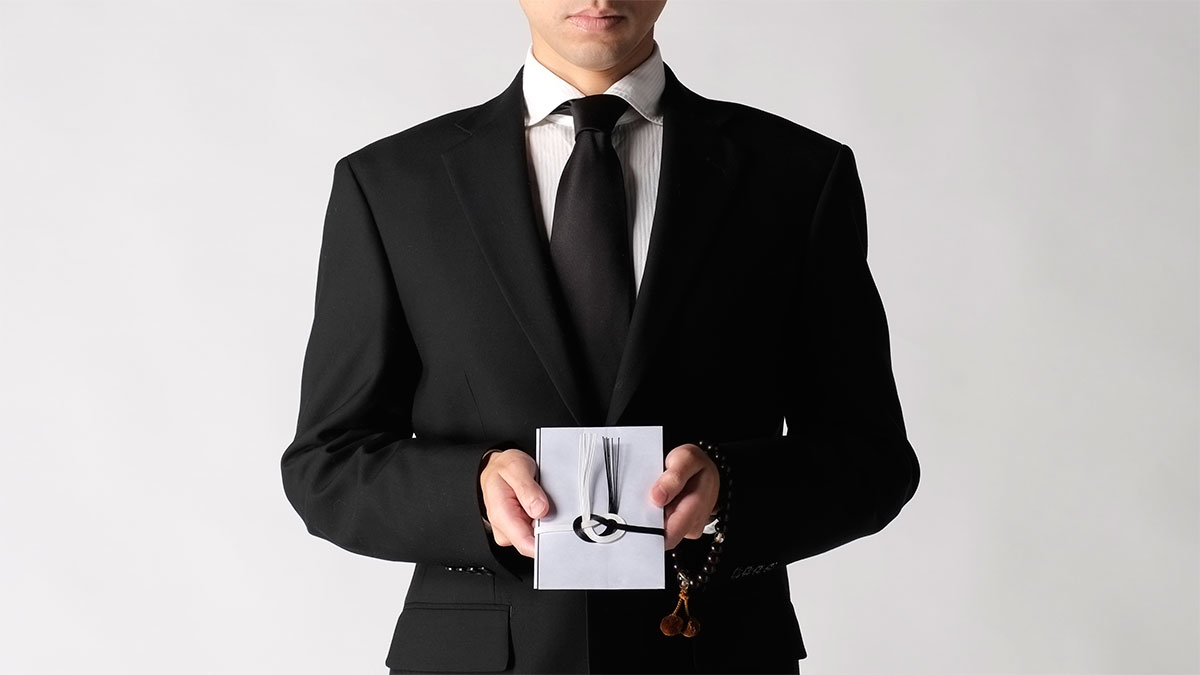 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
香典辞退の習慣
香典を受け取るかどうかについても、関東と関西では傾向が異なります。
関東では香典を受け取るのが一般的で、参列者は相場に沿った額を包み、遺族は後日返礼する形が主流です。一方、関西では近年「香典はご遠慮ください」と辞退する例が増えています。
これは「援助を受けなくても葬儀を営める」という意思表示や、返礼の負担を減らす目的があるとされます。大阪などでは受付に掲示を出すこともあり、その場合は無理に渡さず、弔電や供花で気持ちを伝えるのが適切です。
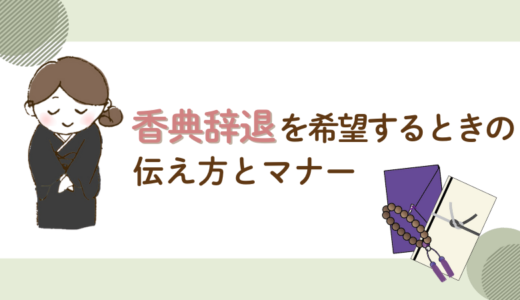 香典辞退を希望するときの伝え方とマナー
香典辞退を希望するときの伝え方とマナー
香典対応のポイント
香典は、金額の相場、水引や表書き、辞退の有無など、地域ごとの違いがはっきり表れる部分です。参列前に地元の葬儀社や親族に確認しておけば安心できます。
迷ったときは無理に自己流で判断せず、周囲のやり方に合わせるのが最も失礼のない対応です。地域性を理解して臨めば、相手に不快感を与えることなく弔意を伝えられます。
喪服・服装マナーの違い

喪服の基本的な形は全国共通ですが、細かな部分には地域ごとの特色が残っています。
かつては関東と関西で好まれる和装の生地に違いがあり、家紋の付け方にも差がありました。また、関東では洋装への移行が早かったのに対し、関西では今も和装を選ぶご家庭があります。
小物や身だしなみの細かな決まりも知っておけば、地域の葬儀に参列する際に迷わず対応できるでしょう。
和装喪服の生地と家紋
昔の和装喪服では、関東では光沢のある羽二重、関西ではシボのある縮緬がよく選ばれていました。江戸の武家文化は張りのある質感を好み、京文化は落ち着いた風合いを重んじたため、この違いが生まれたと考えられます。
家紋についても違いがあり、関東では結婚後の女性は夫方の紋(男紋)を付けるのが一般的でしたが、関西では実家の紋(女紋)を付けることもありました。これは妻の出自を示し、家の系統を両方大事にする考え方が背景にあります。
現在は黒縮緬が主流となり、地域ごとの差はあまり意識されなくなっていますが、伝統の名残として知っておくと理解が深まります。
洋装喪服の広がり
現代の葬儀では、男女ともに洋装の喪服が主流になっています。男性は黒の礼服に白シャツと黒ネクタイ、女性は黒のワンピースやアンサンブルに黒のストッキングを合わせるのが一般的で、全国的に共通しています。
ただ、関西では格式を重んじる家庭では、今でも遺族の女性が五つ紋付きの黒喪服を着ることがあります。関東は明治の欧化の流れもあって洋装への移行が早かったため、比較的洋装が定着しやすかった地域といえます。
現在では地域差よりも遺族の考え方や世代による違いの方が大きく、洋装と和装のどちらを選んでも失礼に当たることはありません。
小物や身だしなみ
アクセサリーは結婚指輪と真珠の一連ネックレス程度にとどめ、派手な装飾や香水は控えるのが基本です。髪型は落ち着いた色でまとめ、靴やバッグも黒で統一します。これらは全国共通のマナーであり、地域差はほとんどありません。
ただし関西では、喪主や近親者に和装を望む声が残る地域もあります。参列の際は、親族の意向や葬儀社の案内に従えば安心です。
全体を通して「質素で清潔」を意識しておけば失礼になることはありません。
服装で迷ったときの選び方
喪服に関する地域差は歴史的背景によるものが多く、現在では大きな違いはほとんど見られません。
参列の際に迷ったときは、まず全国共通の洋装を選ぶのが無難です。和装を望む声がある場合や親族から指定があった場合のみ、臨機応変に対応すると良いでしょう。
大切なのは故人や遺族への敬意を示す姿勢であり、過度に形式にとらわれず、清潔感のある身だしなみを整えて臨めば十分です。
 お葬式の身だしなみマナー完全ガイド|髪型・靴・アクセサリーの選び方と注意点
お葬式の身だしなみマナー完全ガイド|髪型・靴・アクセサリーの選び方と注意点
焼香の作法に見られる地域差

仏式葬儀で行う焼香は、香炉に抹香を捧げて故人を弔う大切な所作です。基本は全国共通ですが、回数や動作は宗派ごとに定めがあり、地域に根付いた宗派の違いによって関東と関西で慣習が分かれる傾向があります。
特に「回数」と「額にいただく動作」は東西で差が大きく、参列者が戸惑いやすい部分です。
焼香の回数
焼香は1〜3回行うのが一般的ですが、関東では2〜3回繰り返す作法が多く、関西では1回だけの作法が主流です。これは地域そのものの違いではなく、広まっている宗派の影響によるものです。
関東では曹洞宗や浄土宗が多く、複数回焼香する作法が目立ちます。一方、関西では浄土真宗の信徒が多いため、1回だけで済ませる作法が一般的に浸透しています。
つまり「関東は2〜3回」「関西は1回」というのはあくまで宗派の分布が反映された結果であり、作法そのものは宗派ごとに全国共通です。
額にいただく所作
焼香の際に抹香をつまみ、額に近づけてから香炉にくべる所作は、宗派によって有無が分かれます。
浄土真宗では額にいただかず、そのまま香炉に入れるのが作法です。一方、曹洞宗や浄土宗などでは額にいただく動作を行うことが一般的です。そのため、浄土真宗の寺院が多い関西では「額にいただかない焼香」が広まり、禅宗や浄土宗の寺院が多い関東では「額にいただく焼香」が主流に感じられるのです。
つまり所作そのものは宗派ごとに全国共通であり、地域差のように見えるのは宗派分布の違いが背景にあります。参列の際は周囲に倣えば失礼になることはありません。
線香の扱いとそのほかの作法
焼香と同様に、線香の扱いも宗派によって違いがあります。
浄土真宗では線香を立てずに横に寝かせ、日蓮宗では3本立てるなど、作法は宗派ごとに定められています。これらは地域差というより宗派の違いですが、その地域に多い宗派の影響で「土地の習慣」として広まることがあります。
さらに火葬後の収骨にも関東と関西で違いがあり、参列者が戸惑いやすい部分です。
| 項目 | 関東の特徴 | 関西の特徴 |
|---|---|---|
| 焼香の回数 | 2〜3回が多い(曹洞宗・浄土宗の影響) | 1回が多い(浄土真宗の影響) |
| 額にいただく所作 | 行う宗派が多く、一般化している | 浄土真宗が多く、額にいただかない |
| 線香の扱い | 宗派により異なるが立てる作法が主流 | 浄土真宗の影響で寝かせることが多い |
| 収骨の方法 | 遺骨をすべて拾い、大きな骨壺に納める | 喉仏など主要な骨だけを小さな骨壺に納める |
| 箸渡しの方法 | 二人一組で箸から箸へ骨を渡す | 一人ずつ順番に骨を拾う |
このように、焼香や収骨の作法は宗派ごとの違いが地域ごとに色濃く表れているため、「東西の違い」として印象づけられています。参列する際は、事前に宗派や地域の慣習を確認するか、その場で周囲の動作に合わせれば安心です。
焼香マナーが違う理由
焼香の作法は、関東と関西で異なるように見えますが、その背景は宗派の分布にあります。関東では曹洞宗や浄土宗の影響で複数回焼香する作法が広まり、関西では浄土真宗の影響で一回のみが主流になっています。いずれも宗派ごとの正しい作法であり、地域差そのものではありません。
一方、火葬後の収骨方法については地域文化の違いによるものです。関東では遺骨をすべて拾い上げて大きな骨壺に納めるのに対し、関西では喉仏などの主要な骨を中心に小さな骨壺に納めます。どちらも伝統として受け継がれた方法であり、優劣はありません。
参列の際に迷ったときは、無理に自分のやり方にこだわらず、周囲の動きに合わせれば安心です。大切なのは形式そのものよりも、故人と遺族に敬意を込めて丁寧に臨む姿勢です。
葬儀で交わされる言葉の地域差

葬儀の場では、遺族や参列者への声かけに細やかな配慮が求められます。
形式は全国共通ですが、関東と関西では好まれる表現に少し違いがあります。関東では丁寧で簡潔なお悔やみの言葉が多く、関西では親しい間柄であれば率直な声かけが許容される傾向があります。
場の空気を読む力が必要とされるため、地域の特色を理解しておくと安心です。
遺族へかけるお悔やみの言葉
遺族への声かけは、葬儀の場で最も気を遣う場面の一つです。
全国的に「ご愁傷様でございます」「心よりお悔やみ申し上げます」といった定型の表現が用いられますが、関東では改まった言葉を簡潔に伝える傾向が強いです。一方、関西では親しい関係であれば「今日はご苦労さま」「大変やったね」など、ややくだけた表現が交わされることもあります。
もちろん公式の場や目上の方に対しては、関西でも丁寧な言葉が無難です。大切なのは地域差を気にしすぎるよりも、遺族の気持ちに寄り添った言葉を選ぶことです。
なお、やむを得ず葬儀に参列できない場合は、弔電を送って気持ちを伝えるのがおすすめです。直接会って言葉をかけられなくても、丁寧な弔意を届けることができます。
たとえば「VERY CARD(ベリーカード)」なら、スピーディに心のこもった弔電や供花を遺族に届けられます。14時までの申込で全国即日配達(一部商品・地域を除く)できるため、突然の訃報のときにも安心です。
 格安弔電で評判!VERY CARDの特徴と使い方、文例、サービス比較(ベリーカード)
格安弔電で評判!VERY CARDの特徴と使い方、文例、サービス比較(ベリーカード)
葬儀で使う「お疲れ様でした」
葬儀後に遺族へ「お疲れ様でした」と声をかける表現は、評価が分かれるところです。
関東では仕事や日常の挨拶に近いため、弔事にはそぐわないと考える人が多く、あまり好まれません。対して関西では、遺族の労をねぎらう率直な言葉として比較的受け入れられる傾向があります。たとえば「今日は本当に大変やったね。お疲れさま」といった声かけも、親しい間柄なら温かい気持ちとして伝わる場合があります。
ただし、場が改まっている場合や関係が浅い場合は、関東・関西を問わず定型的な弔意の言葉を選んだ方が安心です。
弔辞や挨拶の語り方の違い
弔辞や喪主の挨拶は全国的に定型表現が多く、地域差は大きくありません。ただし話し方や内容には、東西で傾向の違いが感じられます。
- 関東の特徴
簡潔で形式的な挨拶を好む傾向があり、故人との思い出を語るよりも儀礼を重んじる姿勢が強い。 - 関西の特徴
故人との思い出や少し和やかなエピソードを交えて語ることがあり、会場をあたたかい雰囲気にする場合もある。
こうした違いは地域性というより、関東には武家文化の影響が、関西には京文化の気風が色濃く残っているためとも言われます。ただし、最終的には故人や遺族の方針に左右されるため、地域の違いにとらわれすぎず、場の雰囲気に合わせることが大切です。
言葉遣いで大切なポイント
葬儀での挨拶や声かけは、地域によって表現の幅に差があるように見えます。関東では丁寧で簡潔な言葉が多く、関西では親しい間柄なら率直な声かけが受け入れられることがあります。
ただしどちらの地域でも、改まった場では定型的な弔意表現を選ぶのが安心です。迷ったときは「ご愁傷様でございます」「心よりお悔やみ申し上げます」といった普遍的な言葉を使えば失礼にはなりません。
大切なのは形式にとらわれることよりも、遺族の気持ちを思いやる姿勢です。
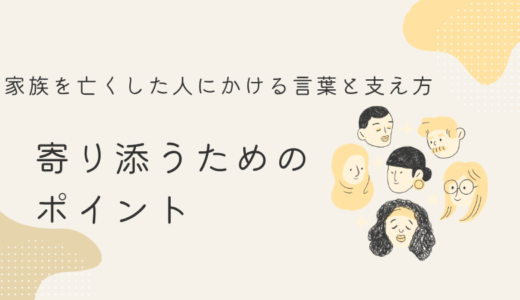 家族を亡くした人にかける言葉と支え方|寄り添うためのポイント
家族を亡くした人にかける言葉と支え方|寄り添うためのポイント
通夜・告別式の流れや参列習慣の違い

葬儀は全国で通夜・告別式・火葬という基本の流れは同じですが、関東と関西では進め方や参列習慣に特徴があります。
特に通夜後の「通夜ぶるまい」の有無や、葬儀の日程を組む際の考え方にはっきりとした違いが見られます。また、火葬後の収骨の仕方にも地域性があり、初めて異なる土地で葬儀に参列すると驚くことも少なくありません。
通夜ぶるまいの有無
通夜後に参列者へ料理や飲み物をふるまう「通夜ぶるまい」は、地域によって大きく異なります。
関東では参列者全員に食事を勧めるのが一般的で、寿司やオードブルが並び、参列者は一口でも箸をつけてから帰るのが礼儀とされます。これに対し関西では、一般参列者に食事をふるまう習慣はなく、通夜が終わればそのまま帰るのが普通です。会食が行われるとしても、遺族やごく近い親族だけに限られます。
この違いは香典相場にも影響しており、関東は通夜ぶるまいの費用を含めて金額がやや高め、関西は費用負担が少ないため香典も控えめになる傾向があります。
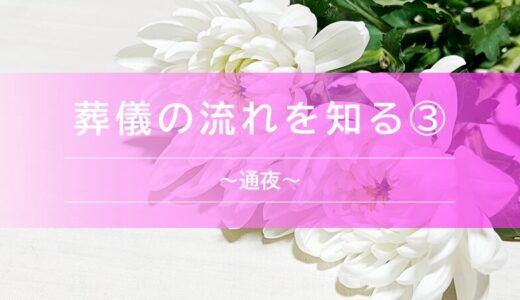 葬儀の流れを知る③〜通夜〜
葬儀の流れを知る③〜通夜〜
葬儀日程と友引の考え方
葬儀の日取りにも東西で傾向の差が見られます。
関東では火葬場の混雑事情から、亡くなってから通夜まで2〜3日あけることが珍しくありません。告別式も数日後になるため、比較的ゆとりを持った日程になりやすいです。一方、関西では火葬場の予約が取りやすく、亡くなった翌日に通夜、翌々日に告別式と早い進行が一般的です。
さらに六曜の「友引」の扱いにも違いがあり、関東では火葬場自体が休業することも多く日程を避けるのが通例です。関西では友引でも葬儀を行うことがあり、その場合は「友をあの世に連れて行かない」意味で棺に人形を納める風習が残っています。
収骨の方法の違い
火葬後の遺骨を骨壺に納める「収骨」にも、関東と関西で違いがあります。
関東では遺骨をすべて拾い上げて大きめの骨壺に納めるのが一般的です。お墓にも骨壺ごと納めるため、遺骨を残さないことが丁寧なお見送りとされてきました。
これに対し関西では、喉仏などの主要な骨を中心に小さな骨壺に収め、残りは火葬場に合葬される場合が多く見られます。納骨の際に骨壺から布袋に移し替える習慣もあり、土に還す考え方が色濃く残っています。
関東と関西でどちらが正しいというものではなく、地域に根付いた伝統の違いとして理解しておくと安心です。
地域ごとに異なる葬儀の習慣
通夜ぶるまいの有無、日程の進め方、収骨の方法など、葬儀の流れには地域ごとの特色が表れます。
関東では参列者全員に料理をふるまい、火葬場の混雑から日程が延びることも多く、遺骨はすべて骨壺に納めます。関西では通夜ぶるまいを行わず、葬儀日程は早めに進み、主要な骨を中心に収骨する形が一般的です。
いずれも長く受け継がれた習慣であり、優劣ではなく文化の違いです。こうした違いに戸惑ったときは、地域の慣習に詳しい葬儀社に相談するのがおすすめです。
たとえば「小さなお葬式」なら全国対応のネットワークを持っており、地域の慣習に精通したスタッフが丁寧にサポートしてくれます。参列や準備で迷う場面でも、安心して相談できる心強い存在です。


精進落とし・香典返しの違い

葬儀が終わった後の食事や香典返しの方法にも、関東と関西で違いが見られます。
精進落としは親族が集まって故人を偲ぶ食事ですが、招く範囲や料理の内容には地域ごとの特色があります。香典返しも表書きや返礼の金額感に東西差があり、関西では「満中陰志」という独特の表書きが広く用いられてきました。
いずれも感謝の気持ちを表す大切な習慣ですが、地域によって形が異なるため、事前に理解しておくと安心です。
精進落としの席
精進落としは、葬儀や火葬を終えた後に親族が集まって食事をする習慣です。関東と関西のいずれでも行われますが、呼び方や料理の内容に違いが見られます。
関東では「精進落とし」や「お斎(おとき)」と呼ばれ、葬儀後に落ち着いた雰囲気で行われます。関西では「仕上げの食事」と表現されることもあり、初七日法要に合わせて用意される場合もあります。地域によっては高野豆腐を三角に切って供えるなど、独自の風習が残っていることもあります。
誰を招くかについても、関東は遺族や親族が中心で、関西では通夜に参加できなかった知人を呼ぶこともあり、範囲に幅がある点が特徴です。
返礼のタイミングと金額の目安
香典返しの時期や品物の金額には地域差があります。
関東では四十九日の忌明け後に「志」と表書きした品を贈り、いただいた額の半分程度を返す「半返し」が基本です。
関西でも忌明けに返礼する点は同じですが、「満中陰志」と記すのが特徴で、黄白の水引をかける地域もあります。返す金額も三分の一程度とやや控えめにする習慣がありました。さらに関西では葬儀当日に「粗供養」として一律の品を手渡し、後日の返礼を簡略化する方法も広く行われています。
いずれの地域でも、香典に込められた心に感謝を形で示すことが最も大切とされています。
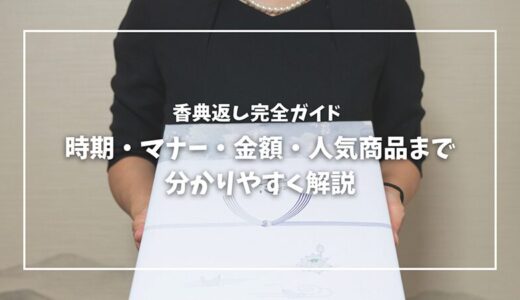 香典返し完全ガイド|時期・マナー・金額・人気商品まで分かりやすく解説
香典返し完全ガイド|時期・マナー・金額・人気商品まで分かりやすく解説
葬儀後に見える東西の特色
精進落としや香典返しの習慣には、関東と関西の文化の違いが色濃く表れています。
関東では「志」と記した半返しを忌明けに贈るのが基本で、通夜ぶるまいとあわせて参列者への丁寧なもてなしが重視されます。関西では「満中陰志」と表記し、三分の一程度を返すことも多く、さらに当日に粗供養を渡して後日の返礼を簡略化する習慣も広く根付いています。
精進落としに招く範囲や料理の内容にも地域ごとの差があり、どちらも長い歴史の中で形成された大切な作法です。形式の違いにこだわるよりも、感謝の気持ちを正しく伝えることこそが本質といえるでしょう。
文化や歴史が生んだ葬儀マナーの東西差

関東と関西の葬儀マナーの違いには、宗派の分布や地域文化、都市事情などが影響しています。背景を知ると、形式だけでなく「なぜそうなったのか」も理解しやすくなります。
- 宗派の広がりの違い
関西は浄土真宗の信徒が多く、簡素で合理的な作法が中心に。関東は禅宗や浄土宗が広まり、厳粛さを重んじる傾向があります。 - 歴史的な文化圏の違い
京文化は華やかさと和やかさを重視し、江戸文化は質実で粛々とした姿勢を尊びました。喪服の生地や弔辞の雰囲気にまで影響が見られます。 - 都市事情の違い
首都圏は火葬場が混雑し、日程が延びやすいのに対し、関西では余裕があるため早めに進行する傾向があります。 - 地域コミュニティの違い
関東は葬儀社主導で進むことが多い一方、関西では自治会や近所の協力が残り、香典辞退や供花の取りまとめなどに地域色が表れます。
こうした要素が積み重なり、今も東西の違いとして受け継がれています。
引っ越して気づく東西の葬儀の違い

異なる地域に住むと、いざ葬儀に参列したときに思わぬ違いに戸惑うことがあります。関東と関西では、香典の扱いや通夜ぶるまいの有無、焼香の回数や収骨の方法など、慣習の細部が異なります。
どちらも長く続いてきた正しい作法であり、優劣はありません。大切なのは「郷に入っては郷に従え」の姿勢で、その土地に合わせて行動することです。
ここでは、引っ越し先でよく直面する違いと対応のポイントを紹介します。
関東から関西へ——よくある違い
関東から関西に移ると、最初に戸惑いやすいのが香典や通夜後の過ごし方です。
関東では通夜ぶるまいが当たり前ですが、関西では一般参列者には料理を出さず、そのまま帰るのが一般的です。また関西では「香典辞退」が比較的多く見られ、受付に掲示があれば素直に従うのがマナーです。
焼香も一回だけの場合が多く、短いと感じてもそれが作法です。さらに関西の言葉遣いは親しい相手にはくだけた表現を使うこともあり、慣れないうちは驚くかもしれません。
迷ったときは周囲の人や葬儀社の案内に合わせれば安心です。
関西から関東へ——よくある違い
関西から関東に移ると、食事や香典の扱いに違いを強く感じることがあります。
関西では焼香後すぐに帰宅するのが一般的ですが、関東では通夜ぶるまいが用意され、参列者は一口でも箸をつけるのが礼儀です。香典の金額も関西より高めで、友人や知人でも一万円を包むケースが多く見られます。
焼香は複数回行う宗派が多いため、慣れていないと戸惑いますが、葬儀社スタッフに確認したり周囲の所作に合わせれば問題ありません。言葉遣いも関東では形式的で丁寧な表現が好まれ、くだけた言葉は避けた方が安心です。
地域差を知って心を込めた見送りを

関東と関西の葬儀マナーには、香典の扱い、服装の細部、焼香の回数、通夜ぶるまいの有無など、多くの違いが見られます。背景には宗派の分布や歴史的な文化の差、都市事情や地域コミュニティの在り方が関わっています。
どちらの習慣も長い年月をかけて根付いたもので、優劣をつけるものではありません。大切なのは形式の差にとらわれすぎず、遺族や故人への思いやりを持ってふるまうことです。
地域が変われば戸惑うこともありますが、周囲の人の所作を参考にしながら柔軟に対応すれば、失礼にあたることはありません。互いの違いを理解し合うことが、心のこもった見送りにつながります。





