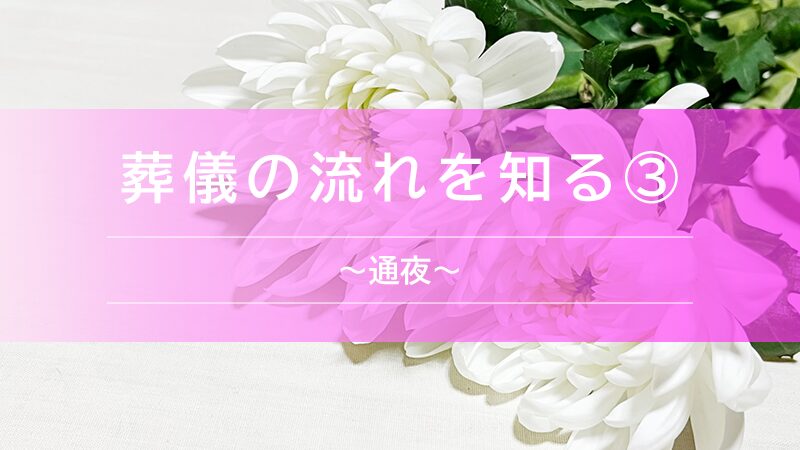【葬儀の手順】
お通夜(通夜)とは、本来、亡くなった方のそばで夜を通して過ごし、故人に寄り添うための儀式です。現在では、葬儀・告別式の前夜に、夕方6~7時頃から1~2時間程度で営まれる「半通夜」と呼ばれる形式が一般的になっています。
突然の不幸で喪主(葬儀を主催する遺族の代表)を務めることになった方や、初めてお通夜に参列される方にとっては、何をどうすればよいのか戸惑うこともあるでしょう。
本記事では、お通夜の準備や当日の流れ、そして通夜ぶるまいについて、専門的な内容を分かりやすくご紹介します。初めての方にも読みやすい表現を心がけていますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
お通夜の準備

お通夜を執り行うことが決まったら、まず葬儀社と打ち合わせを行います。葬儀社の担当者が遺族の意向をくみ取り、適切な葬儀プランを提案し、見積もりを作成してくれます。多くの場合、限られた時間の中で決定を迫られることになりますが、疑問点があれば遠慮せずに相談しましょう。
打ち合わせでは、お通夜および葬儀の日程・場所、規模、宗教形式の有無など、基本的な事項を決定します。菩提寺(寺院)がある場合は、僧侶への依頼や日程の調整も必要です。多くの場合、葬儀社がその仲介も担ってくれるため、任せられる部分は安心して任せましょう。
関係者への連絡
日程と会場が決まったら、故人と親交のあった方々へお通夜と葬儀の日程をお知らせします。電話やメールなどで、まずは親族、次に故人の友人・知人、職場や学校関係者と、順を追って伝えるのが一般的です。各グループの代表者に伝えておけば、その方を通じて周囲にも情報が行き渡るでしょう。
突然のことで時間に余裕がない場合でも、できる限り早めに訃報と式の日程を伝えることが大切です。
手伝いの依頼
当日、喪主や近親者は弔問客の対応に追われるため、全体の進行や細かな受付業務を遺族だけでこなすのは難しいものです。親族やご近所の方、親しい友人などに手伝いをお願いしましょう。受付や会計、案内など、それぞれの役割を担う人がいると、当日の運営がスムーズになります。
規模に応じて必要な人数は異なりますが、一般的なお通夜でも数名のスタッフがいると安心です。手伝いを依頼した方には、式の後に「お礼(志)」として謝礼や品物をお渡しする場合もあります。急なお願いになるかもしれませんが、「遺族を代表して支えていただく」という意識で協力してもらえると、準備がより円滑に進みます。
必要品の手配

お通夜に向けて、以下の物品を事前に準備・手配しておきます。
-
通夜料理の手配
参列者に振る舞う料理や飲み物は、参列予定人数のおおよその目安がついた段階で忘れずに注文しておきましょう。料理の量は判断に迷うこともありますが、詳しくは後述の「通夜ぶるまい」の項でご紹介します。料理の種類や注文の締切時間は、葬儀社に確認したうえで、期限に間に合うように依頼します。追加注文が可能な場合もありますが、基本的には前日までに必要数を伝えておくと安心です。 -
供花(きょうか、弔花)の手配
故人に供える供花も、事前の準備が必要です。遺族・親族からの供花は、葬儀社を通してまとめて注文します。外部の方から申し出があった場合は、葬儀社の連絡先を案内し、直接ご注文いただくとスムーズです。供花は式場に並べられるため、どなたから届いたものかをリストにまとめておくと、当日の確認がしやすくなります。 -
返礼品・会葬礼状の準備
弔問客へのお礼としてお渡しする会葬御礼品や礼状も、あらかじめ用意しておきます。品物の内容や必要な数量については葬儀社と相談し、余裕を持った数を発注しましょう。通常は、余った分を葬儀社で返品対応してもらえることが多いため、不足しないよう多めに準備しておくと安心です。参列者へ手渡す手順もあらかじめ確認し、受付係とも情報を共有しておきます。
喪服や数珠(念珠)など、遺族の服装を整えるのはもちろんのこと、当日使用する写真(遺影)や祭壇に飾る思い出の品があれば、あらかじめ葬儀社に預けておきましょう。
また、受付で使用する芳名帳(参列者の記帳帳簿)、筆記用具、香典を収めるためのカバンなど、細かな備品も事前に確認が必要です。これらは葬儀社が用意してくれることもありますが、心配な場合はあらかじめ担当者に確認し、必要であれば自分たちで準備しましょう。
こうした準備を整えておくことで、当日を落ち着いて迎えることができます。
お通夜当日の流れ

いよいよお通夜当日を迎えます。僧侶(お坊さん)は開式の30分ほど前に到着すると想定し、それに合わせて喪主や遺族も1時間ほど前には式場に入って準備を整えます。早めに会場に入り、控室で待機しながら僧侶や参列者を迎える準備を進めましょう。
ここからは、一般的なお通夜の進行について、順を追ってご紹介します。
受付開始と弔問客の対応
会場の準備が整ったら、受付を開設します。受付係は弔問客(参列者)へ挨拶し、芳名帳への記帳を案内するとともに、香典を受け取るのが主な役割です。
お通夜が始まる30分ほど前から弔問客が訪れ始めるため、受付は開式の30分前には始めておくとよいでしょう。受付では「本日はお忙しい中お越しいただき、ありがとうございます」と、お悔やみへのお礼を述べて香典を受領します。香典は袱紗(ふくさ)から出した不祝儀袋ごと受け取りますが、お盆がある場合はお盆の上に載せ、ない場合は両手で丁重に受け取るのが礼儀とされています。
受付係には、式の予定時刻や会場内の設備(トイレの場所など)について尋ねられることもあります。落ち着いて対応できるよう、事前に案内事項を把握しておきましょう。
僧侶の入場・開式
開式時刻になると、式壇の前で僧侶による通夜法要(つやほうよう)が始まります。
参列者は席について僧侶の到着を待ち、葬儀社スタッフの案内に従い起立して僧侶の入場を迎える場合があります。地域や宗派によって「全員が起立する」「遺族のみが起立する」など習わしが異なりますが、当日は司会進行役(葬儀社スタッフなど)が「それでは皆様、ご起立ください」などの案内をしますので、指示に従えば問題ありません。
僧侶が式壇へ進み、一礼を交わした後、全員が着席すると通夜の法要が始まります。
読経(どきょう)と焼香

僧侶が入場すると、お経を読み上げる読経が始まります。お経の長さは宗派や式の規模によりますが、一般的には30~40分ほど続きます。読経の途中で、参列者による焼香(しょうこう)が行われます。焼香とは、香炉の抹香(まっこう/粉末状のお香)を指でつまみ、額のあたりまで持ち上げてから香炉に落とし、手を合わせて拝む一連の所作です。案内係の合図に従い、まず遺族、次に親族、その後一般の弔問客が順番に焼香を行います。
席の前方に座っている方から順に立ち上がり、祭壇中央の焼香台へ進みます。一般的な式場では、内側の列の参列者は中央通路から前へ進み、焼香後は外側の通路を通って席に戻る動線になっています。作法が分からない場合は、周囲の方のやり方をそっと参考にするか、事前に葬儀社が説明をしてくれることもあります。宗派によって焼香の回数など細かな違いはありますが、形式にこだわる必要はなく、心を込めて一礼すれば問題ありません。
僧侶の法話
読経と焼香が終わると、僧侶による法話(ほうわ)が行われます。仏教の教えをもとにしたお話ですが、説教というよりは故人や遺族に寄り添い、分かりやすく語られることが多いです。
故人の生前のお人柄に触れた話や、生きること・死ぬことの意味を考えさせられるエピソードなど、内容は僧侶によってさまざまですが、参列者は静かに耳を傾けましょう。
喪主挨拶と閉式
法要が終わり僧侶が退場した後、喪主が遺族を代表して参列者への挨拶を行います。
挨拶では、「本日はご多用の中、お運びいただき誠にありがとうございます」といったお礼の言葉に加え、故人に代わって感謝の気持ちを伝えます。長々としたスピーチは不要で、「故人もさぞ喜んでいることと思います。皆様、本日は誠にありがとうございました」といった、簡潔な感謝の言葉が一般的です。
喪主の挨拶が終わると、お通夜の式典部分は閉式となります。
近年、お通夜のみ参列する方も少なくありません。本来、お通夜は近親者が故人を偲び、静かに寄り添う時間とされており、一般の方がお別れをする場は翌日の葬儀・告別式でした。しかし、仕事の都合などで昼間の葬儀への参列が難しいケースが増えたため、現在ではお通夜が告別の場としての役割を担うことも多くなっています。
そのため、「通夜だけ参列し、告別式は欠席する」あるいはその逆の形でも問題なく、都合の良い方に参列すればよいとされています。どちらか一方の参列でも失礼にはあたりませんので、遠方の方や平日に休みを取ることが難しい方は、お通夜のみ参列する形でも問題ありません。
通夜ぶるまいとは?

通夜ぶるまいは、通夜の法要が終わった後に参列者へ食事や飲み物を振る舞う場です。僧侶が退場した後、会場の案内に従い、別室または式場内に設けられた席へ移動します。
お通夜に参列してくださった方々を感謝を込めてもてなし、食事を共にしながら故人を偲ぶ時間でもあります。遺族や参列者が酒や料理を囲み、和やかな雰囲気の中で故人の思い出を語り合います。
通夜ぶるまいは、一般的に1~2時間程度で切り上げられることが多いです。
通夜ぶるまいの内容と準備
通夜ぶるまいでは、寿司やオードブルなどの大皿料理が振る舞われます。かつては精進料理(肉や魚を使わない料理)が中心でしたが、近年は形式にこだわらず、さまざまな料理が用意されるようになっています。
各テーブルにオードブルの盛り合わせや寿司桶が並べられ、参列者が自由に取り分けられるスタイルが主流です。飲み物はビールや日本酒、ソフトドリンクなどが用意されるほか、宗教的な理由でお酒を控える場合は、ウーロン茶などのノンアルコール飲料が選ばれることもあります。
料理の注文数の目安
通夜ぶるまいの料理は、参列者全員分を用意する必要はありません。というのも、焼香を済ませて帰る方も多く、すべての参列者が食事の席に残るとは限らないためです。
料理の注文数は、予想参列人数の6~7割程度を目安にすることが一般的です。一方で、親族や受付係など手伝いをしている方々は食事に参加することが多いため、その人数分は十分に準備しておきます。例えば、参列予定者が100人の場合、一般参列者向けには60~70人分程度を用意し、そこに親族やスタッフの分を加算する形になります。もし料理が不足しそうな場合でも、寿司や煮物など当日追加が可能なメニューもあります。
なお、会場や仕出し業者によって当日追加の締切時間が異なるため、事前に葬儀社へ確認しておくと安心です。葬儀社を通じて手配すれば、こうした数量の調整についてもアドバイスを受けることができます。
通夜ぶるまいの会場
通夜を葬儀会館などで行った場合は、同じ施設内または隣接した会食スペースで通夜ぶるまいが行われることがほとんどです。式が終わると係員が案内をするため、参列者は指示に従って移動しましょう。
自宅でお通夜を行う場合は、近隣の料亭や仕出し料理店から料理を取り寄せ、自宅の座敷や集会所で通夜ぶるまいを行うこともあります。
最近では、通夜の式を省略して通夜ぶるまいのみ簡易に行うケースや、逆に通夜ぶるまいを設けず家族葬として執り行うケースもありますが、一般的なお通夜では、参列者と共に食事を囲む場を設けることが多いです。
通夜ぶるまいのマナー

通夜ぶるまいは、故人を偲びながら参列者へ感謝の気持ちを伝える場です。厳格な作法を気にする必要はありませんが、以下のような点に気を付けるとよいでしょう。
遺族側の振る舞い
喪主やご家族は、参列者と共に食事をいただきながらも、一度は各テーブルを回り、お酌をしながら挨拶をするのが丁寧な対応とされています。参加者一人ひとりに「本日はお越しいただき、ありがとうございます。どうぞごゆっくりお召し上がりください」と声をかけ、直接感謝を伝えましょう。グラスが空いている方には、お酒や飲み物を注ぎ足しながら挨拶をすると、より心配りが感じられます。ただし、遺族が無理にお酒を飲む必要はありません。あくまで、お礼と労いの気持ちを伝える場と考え、負担のない範囲で対応しましょう。
参列者側の心得
遺族にすすめられた場合は、可能な限り通夜ぶるまいに参加するのが礼儀とされています。地域によっては一般の弔問客が辞退する習慣があることもありますが、誘われた際は短時間でも席に着き、飲み物や料理をいただくのが望ましいでしょう。故人への供養になるとも考えられているため、食欲がない場合でも、お茶や汁物だけでも口にするとよいとされています。「明日仕事があるので、短時間で失礼します」など一言添え、30分ほどで中座しても問題ありません。
ただし、お酒の席だからといって羽目を外すのは厳禁です。通夜ぶるまいは弔事の一環であるため、大声で騒いだり泥酔したりしないよう注意が必要です。
切り上げのタイミング
通夜ぶるまいは長くなりすぎないよう、1~2時間を目安にお開きとなります。翌日に葬儀・告別式を控える遺族は準備や休息を取る必要があるため、参列者も遅くとも21~22時頃には退席するのが望ましいでしょう。退席の際は、「そろそろ失礼します。本日はありがとうございました」と声をかけ、遺族へ一礼して席を立ちます。会場によっては終了時間が決められている場合もあるため、参列者も様子を見ながら適切なタイミングで切り上げるよう心がけましょう。
持ち帰りについて
通夜ぶるまいの料理がたくさん残ってしまった場合は、料理を折詰め(折り箱)に詰めて参列者に持ち帰ってもらうこともあります。また、地域によっては「お清め」として、寿司折りをお土産として渡す習慣があることもあります。遺族側から「よかったらお持ち帰りください」と勧められた際は、遠慮せずに受け取るとよいでしょう。ただし、自ら積極的に持ち帰るのは避け、あくまで勧められた場合に限ります。
まとめ

お通夜の準備から当日の流れ、通夜ぶるまいまでを一通りご説明しました。
初めてのことで戸惑いや不安もあるかもしれませんが、葬儀社の力を借りながら流れを押さえれば安心して進めることができます。お通夜の段階では、遺族は気が動転し、十分な余裕が持てないこともあります。しかし、何より大切なのは故人を偲ぶ気持ちと、参列者への感謝の心です。形式にとらわれるよりも、心を込めて対応すれば、それが故人への何よりの供養となるでしょう。
【葬儀の手順】