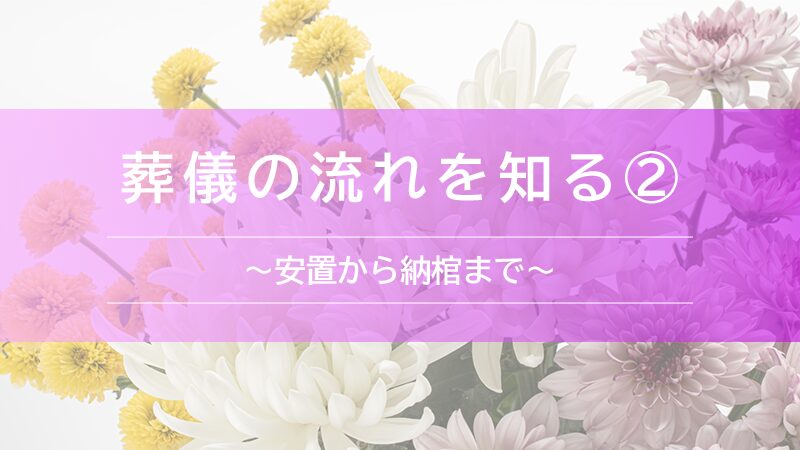【葬儀の手順】
大切な人が亡くなった後は、遺体を自宅などに安置し、その後すぐにお通夜や葬儀の準備を進める必要があります。初めて喪主を務める方や、葬儀の経験が少ない方にとっては、不安や戸惑いもあるかもしれません。この記事では、宗派を問わず全国的によく行われている習慣をもとに、遺体の安置から納棺までの一般的な流れをわかりやすく解説します。各ステップの具体的な内容や、押さえておきたいポイントも丁寧にご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
葬儀日程の決定

遺体を安置したあとは、葬儀の日程を決めることが最初の大切な準備になります。関係者との調整や、会場・火葬場の予約など、決めるべきことは多くありますが、一つずつ確認しながら進めていきましょう。
喪主と葬儀方針の決定
まず初めに、葬儀を取り仕切る遺族の代表として「喪主」を決めます。一般的には、配偶者(妻または夫)、長男、次男、長女、次女…といった順で喪主を選ぶことが多く、たとえばご両親のどちらかが亡くなった場合は、残された配偶者が喪主に、それが難しい場合は長男が喪主になるといったケースが一般的です。近年では、子どもが親より先に亡くなるなどの事情から、親が喪主を務めることもあります。
喪主が決まったら、必要に応じて葬儀の運営を手伝ってくれる「世話役」を依頼するかを検討します。かつては葬儀の規模に応じて受付や進行などを担う世話役を複数立てることが一般的でしたが、近年は家族葬など小規模な葬儀も増え、世話役を置かないケースも多くなっています。依頼する場合は喪主と相談のうえ、受付係・会計係・会葬者の案内係など、役割分担を決めておくと安心です。
喪主(および世話役)が決まったら、次に葬儀の基本方針について話し合いましょう。具体的には、葬儀の形式(宗教形式や、無宗教葬、家族葬、一般葬など)、葬儀の規模(参列者の範囲や人数)、予算、式場の場所などを検討します。これらの要素は互いに関係しており、たとえば「親族と親しい友人だけで家族葬にしたい」「できるだけ費用を抑えたい」などの希望によって、式場の選び方や準備内容も変わってきます。喪主を中心に、ご家族で意見を出し合いながら、故人の遺志やご遺族の意向を尊重して、方針をしっかりと固めましょう。
日程調整と火葬場の予約
葬儀の方針が決まったら、次は日程の調整に進みます。その際は、関係者との調整が必要になります。まずは親族や親しい方々の予定を確認し、できるだけ多くの方が参列できる日を検討しましょう。
菩提寺がある場合は、住職の予定も確認が必要です。葬儀で読経を依頼する場合、他の法要などと日程が重ならないかを伺い、都合のよい日時を相談します。菩提寺がない場合や、無宗教で行う場合にはご遺族の希望を中心に日程を決めて構いませんが、菩提寺がある場合はお寺の予定を優先するのが一般的です。
日程の目安が立ったら、火葬場の予約を行います。いわゆる「24時間ルール」と言われるように、日本の法律では「死亡から24時間以内に火葬してはならない」と定められており、亡くなってすぐに火葬することはできません。そのため、ご遺体は最低でも一晩は安置し、火葬は死亡翌日以降の日程となります。また、火葬場は「友引」(暦注の一つで「友を引く」として葬儀を忌む日)に休業していることが多いため、日程を組む際はカレンダーも確認しましょう。
火葬場の予約は、通常は葬儀社が代行してくれます。希望日を伝えれば空き状況を確認し、予約まで行ってくれます。自分で手配する場合は、役所や火葬場の窓口に問い合わせましょう。
火葬の日程が決まると、それに合わせてお通夜と葬儀・告別式の日程も決まります。火葬の前日にお通夜を行い、当日の午前中から昼ごろにかけて葬儀・告別式を、その後出棺して火葬という流れが一般的です。一日葬(通夜を省略して葬儀・告別式のみ行う形式)や直葬(通夜・葬儀を行わず火葬のみ)の場合はこの限りではありませんが、いずれの場合も火葬場の予約時間をもとに、式の開始時間を逆算して決めていく必要があります。
近年では、特に都市部を中心に火葬場が混み合っており、希望する日時に予約が取れないこともあります。「○日までに葬儀を終えたい」といった希望がある場合は、できるだけ早めに手配を進めることが重要です。
葬儀式場(斎場)の仮押さえと確認

日程の候補がある程度決まったら、葬儀を行う式場(斎場)の予約も進めます。斎場の選び方については次の章で詳しく説明しますが、日程と斎場の予約は密接に関わっており、どちらか一方だけで決めるのは難しいことが多いです。
希望日が決まっていても、利用可能な斎場が見つからなければ日程の見直しが必要になることもあります。反対に、「この斎場で送りたい」という強い希望がある場合は、空き状況を優先して日程を調整するケースもあります。
一般的に、公営斎場(自治体が運営する式場)は費用が抑えられるため人気が高く、予約が取りづらい傾向があります。数日先まで埋まっていることも珍しくありません。一方、民営斎場(葬儀社や民間企業が運営する式場)は比較的予約が取りやすいですが、使用料は公営に比べて割高になることが多いです。
火葬場や菩提寺、親族の都合などと併せて、斎場の空き状況を確認しながら、無理のないスケジュールで全体の日程を調整していきましょう。
たとえば「亡くなった日に親族で打ち合わせを行い、翌日にお寺と火葬場へ連絡、翌々日に通夜、3日後に葬儀・火葬」といった流れで進めるケースもあります。法律により、亡くなってから24時間以内の火葬はできませんが、条件が整えば、翌日に通夜、その翌日に葬儀・火葬という日程で執り行うことも可能です。ただし、火葬場や式場の予約状況によっては希望通りに進まない場合もあるため、実際には2〜5日程度の余裕をもって予定を立てるご家庭が多いのが現状です。
斎場の決定

葬儀を行う斎場には、公営斎場と民営斎場があります。それぞれに特徴があり、費用や利便性、利用条件に違いがあります。
公営斎場と民営斎場の違い
公営斎場の特徴
公営斎場は、市区町村などの地方自治体が運営する葬儀式場です。税金で運営されているため、利用料が比較的安価に設定されているのが大きなメリットです。特に故人や喪主が自治体の住民である場合、住民割引が適用され、さらに安く利用できることがあります。
また、多くの公営斎場は敷地内に火葬場を併設しており、通夜・葬儀・告別式・火葬を同じ施設内で完結できる利便性があります。高齢の参列者や小さな子どもがいる場合、移動の負担が少ないのは助かりますし、霊柩車やマイクロバスの移動費用も抑えられます。
公営斎場を利用する際の注意点
公営斎場は費用の安さから利用希望者が多く、予約が取りづらい点に注意が必要です。特に人気のある斎場では、数日待ちになることもあります。
また、多くの場合、利用できるのはその地域の住民に限られるため、故人または喪主の住民票が該当自治体にあることが利用条件となります。管轄外の人が利用する場合、料金が割高になる、または市民の予約が優先されることがあります。
ただし、公営斎場は宗旨・宗派を問わず誰でも利用でき、特定の葬儀社の指定がないため、自由に業者を選べるというメリットもあります。
民営斎場の特徴
民営斎場は、葬儀社や宗教法人(寺院など)が運営する式場です。主に以下の3種類があります。
- 葬儀社直営ホール:特定の葬儀社が自社で運営
- 寺院の葬儀会館:寺院が所有し、宗教的な葬儀が可能
- 貸し式場:葬儀社以外の企業が式場スペースのみを提供
民営斎場は公営に比べて施設数が多く、予約が取りやすいのが特徴です。希望の日程に合わせやすく、急な葬儀や公営斎場が空いていない場合でも、利用できる可能性が高くなります。
また、駅に近い、駐車場が広いなど、アクセスの良い場所に立地していることが多く、館内設備やサービスも充実しています。例えば、控室の快適さ、音響設備、美しい祭壇、貸衣装や宿泊設備など、公営斎場では提供されないサービスが整っていることもあります。
民営斎場を利用する際の注意点
民営斎場のデメリットは、費用が高めに設定されている点です。同程度の広さでも公営より使用料が高額になる場合が多く、葬儀プランとセットでの支払い形式が一般的です。特に、葬儀社直営ホールでは、その葬儀社のプランを利用することが前提になります。
ただし、民営斎場の費用はさまざまで、家族葬向けの小規模な式場であれば、公営斎場と大差ない料金で利用できるところもあります。サービス内容を考慮しながら、予算に合った民営斎場を選ぶと良いでしょう。
寺院斎場や自宅葬という選択肢

葬儀の会場選びには、公営斎場や民営斎場のほかにも、寺院斎場や自宅葬という選択肢があります。故人の信仰や遺族の希望によって、伝統的な葬儀の形を選ぶことも可能です。それぞれに特徴があるため、利便性や費用を考慮しながら選択するとよいでしょう。
寺院斎場で葬儀を行う
寺院斎場とは、菩提寺の本堂や寺院会館を葬儀の場として利用する形態です。故人が熱心な檀家だった場合や、格式ある寺院で葬儀を行いたい場合に選ばれます。寺院での葬儀は厳かな雰囲気の中で執り行うことができ、伝統的な儀式を重んじる方に適しています。また、檀家の場合、会場使用料が無料または安価で済むことが多い点もメリットです。
ただし、寺院斎場の設備は専用斎場に比べて控室や駐車場が不足していることがあります。さらに、檀家以外の方が利用する場合は、その寺院の宗派の作法に則った式になることが一般的です。加えて、非檀家の場合は戒名料とは別に会館使用料として数万円〜十数万円の費用がかかることがあるため、事前に確認しておくことが重要です。
自宅で葬儀を行う
かつては自宅で通夜・葬儀を行うことが一般的でしたが、現在では斎場葬が主流となりました。それでも、「故人を住み慣れた家から送り出したい」と考える遺族が、自宅葬を選ぶこともあります。自宅葬は式場費用がかからない点が大きなメリットです。また、慣れ親しんだ空間で家族と故人を静かに見送ることができるため、アットホームな葬儀を希望する方に適しています。
しかし、自宅葬を行うにはいくつかの条件を考慮する必要があります。まず、自宅が多数の弔問客を迎えられる広さがあるか、また近隣への配慮(駐車スペースや騒音)が必要です。また、自宅で故人を安置できない場合は、葬儀社の安置施設(霊安室)を利用することになり、その費用が発生します。
斎場選びは柔軟に
斎場選びでは、希望する会場が予約で埋まっている場合に備え、柔軟に対応することが重要です。
例えば、都市部に住むAさんは、費用を抑えるため公営斎場を第一候補に考えていました。しかし、役所に問い合わせたところ、週末まで予約が埋まっており、火葬も4日後まで空きがない状況でした。日程を延ばすのが難しかったため、近隣の民営斎場を選択しました。結果として公営より費用は高くなりましたが、希望していた日程で葬儀を行え、設備も充実していたため満足できました。
このように、斎場の空き状況によっては、別の選択肢を検討する柔軟さも大切です。
戒名とお布施の用意

仏式の葬儀を行う際は、故人の安置中に戒名(かいみょう)とお布施(ふせ)の準備を進めておくことが重要です。
戒名とは、故人が仏門に入ったことを示す名前であり、あの世での新たな呼び名となります。また、お布施は、僧侶に葬儀や戒名の依頼をする際に渡す謝礼であり、戒名料(戒名を授かる際の謝礼)も含めてお渡しするのが一般的です。お布施の額や渡し方には一定のしきたりがあり、適切な準備が求められます。
ここでは、戒名の意味や依頼方法、お布施の相場やマナーについて詳しく解説します。
戒名とは?本来の意味と必要性
戒名はもともと、生前に仏門に入った者(出家した仏弟子)に授けられる名前です。仏教では、生前使っている名前を「俗名(ぞくみょう)」と呼び、仏弟子として戒律を受け修行に励むことで、新たに戒名を頂く習わしがあります。しかし現在の日本では、出家せずとも葬儀の際に僧侶から戒名を授かり、故人を仏弟子として送り出すのが一般的です。「仏式の葬儀には戒名が必須」と言われることがありますが、これは仏教の形式に則り、極楽往生を願うための伝統的な考え方によるものです。
また、お墓に故人を埋葬する際に戒名が必要になるケースが多いことも理由のひとつです。特に寺院墓地では、先祖代々の墓に入る際に戒名を求められることが一般的であり、菩提寺を持つ家庭では戒名を授かることがほぼ必須となります。
ただし、戒名は必ずしも必要というわけではありません。たとえば菩提寺がなく、公営の霊園などにお墓を持っている場合や、無宗教葬・キリスト教式の葬儀を行う場合には、戒名は用いません。また最近では、生前に「戒名はいらない」「俗名のまま送り出してほしい」と希望する人も増えています。その場合、葬儀を依頼する際にその旨を伝えれば、僧侶を招かず戒名なしで葬儀を行うことも可能です。
とはいえ、菩提寺があるにもかかわらず戒名を拒否すると、お寺との関係が悪化し、将来的に同じ墓に入れなくなる可能性もあります。戒名を付けない選択をする場合は、事前に菩提寺と相談し、墓の管理についても確認しておくことをおすすめします。
戒名の依頼方法と「戒名料」の相場
仏式の葬儀を行う際には、戒名を授かるための準備も必要になります。戒名は故人が仏門に入った証として与えられる名前であり、多くの場合、僧侶に依頼して授かります。また、戒名を授かる際には、お布施として「戒名料」をお渡しするのが慣習です。戒名の依頼方法や戒名料の相場は、お寺の方針や家の状況によって異なるため、事前の確認が重要です。
戒名の依頼方法
戒名を授かるには、通常、僧侶に依頼します。故人や家族が檀家としてお世話になっている菩提寺がある場合、そのお寺に葬儀と戒名の依頼をするのが一般的です。まずは菩提寺に電話で臨終を報告し、葬儀の日程を相談しましょう。住職が通夜・葬儀の日程を決める際に、戒名も授けてもらうのが通常の流れです。戒名だけを別の寺院に依頼することはほとんどなく、葬儀を執り行うお寺が戒名を授けるのが一般的です。
一方、菩提寺がない場合(無宗教の家庭や、菩提寺が遠方で呼べないケースなど)は、葬儀社に相談すれば僧侶の手配サービスを紹介してもらえます。近年はインターネットを通じて僧侶を依頼できるサービスも増えており、「定額のお布施で戒名と読経を依頼できる」といったプランも登場しています。この場合も、葬儀を執り行う中で僧侶に戒名を授けてもらう流れとなります。信頼できる葬儀社や紹介サービスを活用し、希望に合った僧侶に依頼することが大切です。
戒名料(お布施)の相場

戒名を授かる際の謝礼として、お布施を僧侶にお渡しします。お布施の額には明確な決まりはなく、菩提寺や家庭の事情によって異なります。菩提寺と長く付き合いがある場合、「お気持ちで」と言われることもあります。一方で、相場が分からず不安な場合は、親戚に相談したり葬儀社に確認するのも一つの方法です。一般的には葬儀一式のお礼も含め、数十万円を包むケースが多いとされています。
目安としてよく言われるのは、「30万~50万円」ほどですが、これは戒名の位号(格式)によって変動します。戒名には俗に「ランク」があると言われ、格式が高いほど慣例的にお布施も高額になる傾向があります。
例えば、戒名の末尾は以下のような種類があります。
- 男性:「◯◯居士(こじ)」「◯◯信士(しんじ)」
- 女性:「◯◯大姉(だいし)」「◯◯信女(しんにょ)」
一般的に、居士・大姉のほうが信士・信女より格式が高い戒名とされます。また、戒名の頭に「院号」や「院殿号」がつくと、さらに高位になります。
慣例的な相場としては、
- 信士・信女:10万~50万円程度
- 居士・大姉:50万~80万円程度
- 院号付きの戒名:100万円以上
ただし、これはあくまで目安であり、必ずしも決まった金額ではありません。家の経済状況に合わせて無理のない範囲で決めることが大切です。お寺によっては定額を提示している場合もあり、葬儀社を通じて僧侶を紹介してもらった場合は、適正なお布施の金額を事前に案内されることが多いため、安心して相談できます。
お布施を渡す際のマナー
葬儀の際に僧侶へお渡しするお布施は、適切な準備とマナーを守ることが大切です。特に、お布施の包み方や渡すタイミングには決まりがあり、失礼のない形でお渡しすることが望まれます。ここでは、お布施の準備方法や渡し方のポイントについて解説します。
お布施の準備方法
お布施の金額が決まったら、葬儀当日までに準備を整えます。お布施は、不祝儀袋ではなく白い封筒に包むのが一般的です。黒白の水引(飾り紐)が付いた不祝儀袋は香典用であり、お布施には適しません。郵便局などで購入できる無地のものか、「御布施」と印字された白い封筒を使用するとよいでしょう。また、二重構造の封筒(内袋と外袋があるタイプ)は「不幸が重なることを連想させる」とされ、避けるのがマナーとされています。
封筒の表面には、毛筆または筆ペンで「御布施」と記入し、裏面に小さく喪主(または施主)の住所と氏名を記載すると丁寧です。金額は封筒には書かず、気になる場合は中に金額を記したメモを添えるとよいでしょう。
お布施に入れるお札は新札が望ましいとされています。香典の場合は「事前に用意していたように見えるのはよくない」として新札を避けますが、お布施は僧侶への謝礼にあたるため、綺麗なお札を用意することが心遣いとして好まれます。ただし、急な訃報の場合は無理に新札を準備しなくても問題ありません。その場合でも、できるだけ折り目のない綺麗なお札を選ぶとよいでしょう。
お布施の渡し方
準備したお布施は、袱紗(ふくさ)に包んで持参します。袱紗から封筒を取り出し、相手に向けて差し出すのが正式な所作ですが、難しい場合は袱紗ごと渡してもかまいません。
渡すタイミングは、通夜や葬儀の前後で僧侶と落ち着いて言葉を交わせる場面を選ぶのが理想です。その際、「本日はどうぞよろしくお願いいたします(葬儀前)」「本日はありがとうございました(葬儀後)」など、一言添えて手渡しするのがマナーとされています。人前で大げさに渡す必要はなく、控えめな態度で渡すのが礼儀です。
御車代・御膳料について
お布施とは別に、「御車代」や「御膳料」を渡すケースもあります。
- 御車代:僧侶が遠方から来る場合の交通費として渡す謝礼。5千円~1万円程度が目安。
- 御膳料:通夜振る舞いや精進落としに僧侶を招待する代わりに渡す謝礼。5千円~1万円程度が目安。
これらは必須ではありませんが、僧侶がすぐに帰られる場合など、「お気持ち」として用意するとよいでしょう。御車代・御膳料はそれぞれ別の封筒に入れ、表書きも「御車代」「御膳料」と記入し、お布施の封筒とまとめて袱紗に包んで渡すのが正式な形です。
納棺

納棺とは、故人のご遺体を棺に納める儀式のことです。葬儀の準備を締めくくる大切なものであり、「納棺の儀」とも呼ばれます。安置されていた故人と、思い出の品を棺に収め、蓋を閉じるまでが納棺の流れです。かつては遺族が主体となって行う作業でしたが、現在では葬儀社のスタッフである納棺師が進行を担うことが一般的になっています。
この章では、納棺の手順や、湯灌、副葬品についての重要なポイントを解説します。
遺体の清拭と死装束の準備
仏教の習わしでは、故人の体をお湯で洗い清める湯灌(ゆかん)という儀式が行われます。湯灌では、ご遺体を湯船に入れて洗い清め、髪を整えた後、死装束を着せて棺に納めます。近年では、簡易的に温かいタオルで体を拭く清拭(せいしき)が一般的となっています。清拭であっても、故人を美しく整え、旅立ちの準備をする大切な儀式です。納棺師や葬儀社のスタッフが中心となり、遺族にも協力をお願いしながら、丁寧に体を拭き清めます。必要に応じて女性にはお化粧を施し、男性には髭を剃るなど、生前の穏やかな顔立ちに近づけるエンゼルメイクを行うこともあります。
体を清めた後は、故人に死装束(しにしょうぞく)を着せます。かつては白い着物(経帷子〈きょうかたびら〉)を着せるのが一般的でしたが、最近では故人が愛用していた洋服や旅支度の装束を着せるケースも増えています。納棺のプランによっては、伝統的な白装束一式(経帷子、頭陀袋、手甲脚絆など)が用意され、それを着せることもあります。また、三途の川の渡し賃として六文銭(現在は紙に印刷された模擬貨幣やお守り)を持たせたり、頭に三角の布である天冠をつけることもあります。洋装を希望する場合、スーツやドレス、あるいは寝間着のまま安らかな姿で旅立つこともあります。宗派や地域によって異なる習慣がありますが、故人らしい旅立ちの装いを整えてあげることが何より大切です。
遺体の清めと服装の準備が整ったら、棺へ移します。葬儀社の納棺師が作法を説明しながら、遺族にも手伝いを促すことがあります。
例えば、個人の体に白布をかける役割や、棺に納める際に頭を支える役を家族が担うこともあります。納棺は単なる儀式ではなく、故人との最後のふれあいの機会でもあります。納棺師の指示に従いながら、感謝の気持ちを込めて、そっと棺へと納めましょう。
副葬品を棺に納める

故人を棺に納めた後、副葬品として思い出の品や愛用品を一緒に収めることができます。副葬品は、故人への感謝の気持ちを込めた大切な品物であり、ご家族や親しい方が「故人らしいもの」として選ぶとよいでしょう。
ただし、火葬の際に適さないものもあるため、入れる品物を慎重に選ぶ必要があります。ここでは、副葬品の選び方や納棺の流れについて説明します。
副葬品として入れられるもの
副葬品は、故人が生前に愛用していた品や、旅立ちに持たせたいものを選びます。たとえば、次のような品物が選ばれることが多いです。
- 写真や手紙:家族や友人からのメッセージ
- 愛読書や趣味の品:故人が大切にしていたもの
- 小物類:お気に入りのアクセサリーや日用品
- 嗜好品:愛飲していたお酒、好んでいたタバコ
「これを見ると故人を思い出す」と感じられる品があれば、ぜひ副葬品として納めるとよいでしょう。
副葬品として入れられないもの
火葬の際に適さない品物には注意が必要です。代表的なものは以下の通りです。
- 燃えないもの(金属製品、ガラス類、陶器類など)
- 例:眼鏡のフレーム、貴金属類、湯飲み茶碗
- 火葬炉の中で燃え残るため、入れることができません。
- 燃やすと有害物質が出るもの(プラスチック製品、化学繊維のぬいぐるみなど)
- 例:ビニール製のお人形、化学繊維の衣類
- 有毒なガスやダイオキシンが発生するため避けるべきです。
- 高温で溶けるもの(ゴム製品、ろうそく、電池類など)
- 例:スプレー缶、ライター、リップクリーム
- 炉内で溶け出したり、高温で破裂する危険があるため、絶対に入れてはいけません。
副葬品を選ぶ際に迷った場合は、葬儀社のスタッフに確認すると確実です。例えば、眼鏡を入れたい場合は、レンズを外し、プラスチックフレームのものを用意するなどの工夫もできます。
納棺後のお別れの儀
副葬品を納めた後、故人の顔や体の周りに花を手向けます。葬儀では参列者全員が「お別れの儀」で花を棺に入れる場面がありますが、納棺時にも遺族や近親者が花を手向けることができます。故人が好きだった花や季節の花を入れると、棺の中が華やかになります。
こうして副葬品と花に囲まれた故人の姿が整ったら、棺の蓋を閉じ、釘打ちを行い、出棺の時を待つことになります。
納棺のタイミングと準備
納棺のタイミングは、各家庭や葬儀社の進行によって異なります。
- 通夜式の直前に安置先(自宅や安置室)で納棺を行い、そのまま式場へ移動する場合
- 通夜当日の朝~午後に葬儀社の施設で納棺を済ませ、夕方に式場に棺を安置する場合
いずれの場合も、通夜が始まるまでに納棺を完了させることが必要です。納棺後、故人はドライアイスなどで冷やされ、通夜・葬儀を経て、出棺・火葬へと進みます。
納棺までに決めておくこと
安置から納棺までの流れをスムーズに進めるために、次の3点を決めておくことが重要です。
- 喪主の選定
- 葬儀社と葬儀プランの確定
- 菩提寺や僧侶との調整
喪主を中心に、信頼できる葬儀社を選び、宗教者との段取りを確認しておきましょう。斎場は、多くの場合、葬儀社が所有・提携する式場や公営斎場を利用します。連絡や調整は負担が大きいものですが、葬儀社に相談すればサポートを受けられるため、一人で抱え込まず進めることが大切です。
まとめ

葬儀の準備は、慣れないことばかりで戸惑うことも多いものです。しかし、一つひとつの工程を丁寧に進めていけば、故人を滞りなく送り出すことができます。安置から納棺までの時間は限られていますが、その中でお別れの準備を整え、悔いのない形で故人を見送ることが大切です。
ご家族にとっては、悲しみの中で慌ただしい時間を過ごすことになりますが、周囲の支えを受けながら故人との最後のひとときを大切にしてください。
【葬儀の手順】