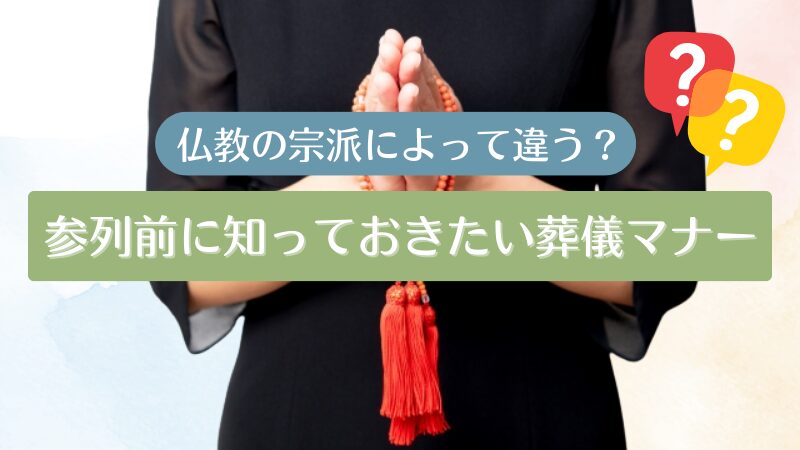仏式の葬儀に参列するとき、焼香の回数や合掌の作法など「これで正しいのかな」と迷ったことはありませんか?実は仏教の宗派ごとに葬儀のマナーや所作には細かな違いがあります。
本記事では、特に参列時に気をつけたいポイントを中心に、浄土宗、浄土真宗(本願寺派・大谷派)、禅宗(臨済宗・曹洞宗)、日蓮宗の主要な宗派別に解説します。
初めての方でも安心して参列できるよう、実際の流れに沿って比較していきましょう。
目次
会場到着から着席までのふるまい

葬儀会場に到着したときの所作は、宗派に関係なく第一印象を左右する大切な場面です。受付でのふるまいや数珠の持ち方ひとつで、落ち着いた印象を与えることができます。
ここでは、受付から着席までに気をつけたい基本的なマナーをご紹介します。
受付でのあいさつと手順
葬儀会場に着いたら、まずは受付で香典を渡します。言葉は「ご愁傷さまです」など短く丁寧に伝えれば十分です。芳名帳への記入を済ませたら、深く礼をして会場内へ。控えめな態度が好印象につながります。
服装は黒のスーツや喪服が基本です。ネクタイピン、時計、香水など、目立つものは避けましょう。女性のアクセサリーも、真珠など控えめなもの以外は外しておくのが無難です。
 葬儀のマナー完全ガイド:服装、靴、言葉遣い、ご香典について
葬儀のマナー完全ガイド:服装、靴、言葉遣い、ご香典について
席へ向かうときの注意
受付が済んだら、会場内に入り静かに着席します。遺族と顔を合わせても、あえて声をかける必要はありません。目礼や軽い会釈で十分気持ちは伝わります。大声や私語、スマホの操作などは厳禁です。
案内の人がいない場合は、後方の空席に静かに座るのがマナーです。混雑しているときは、周囲に配慮しながら空いている場所を選びましょう。
着席後のふるまい
席についたら、かばんは足元や椅子の下に置きます。隣席の方に軽く会釈するなど、場に馴染む動作があると落ち着きやすくなります。
読経が始まりそうなタイミングでは背筋を正して黙礼し、式に集中できる姿勢を整えましょう。
焼香の作法

葬儀の中で参列者がとくに緊張しやすいのが焼香です。回数や動作には宗派によって違いがあり、戸惑う方も少なくありません。
ここでは、主要宗派ごとの焼香回数や所作の特徴をわかりやすく比較しながら、気をつけたいポイントを紹介します。
焼香回数の違いと対応のコツ
焼香の回数は宗派によって異なりますが、「絶対に正しくないといけない」というものではありません。前の人の動きに合わせれば問題ありませんし、迷ったら1回だけで十分です。
浄土真宗は特に回数と所作が特徴的で、本願寺派では1回、大谷派では2回とされています。他宗派は1回または3回が一般的です。
宗派によって違いがあることだけ意識しておけば、過度に緊張する必要はありません。
 知っておきたい焼香マナー | 作法・仕方・やり方、回数など
知っておきたい焼香マナー | 作法・仕方・やり方、回数など
焼香時の所作と立ちふるまい
焼香台では、まず遺影に向かって一礼し、静かに焼香を行います。その後、合掌または黙礼をして退きます。動作はゆっくり丁寧に行いましょう。焦ってしまうと所作が乱れやすく、場の空気にそぐわない印象になってしまいます。
香をくべる手順よりも、「どんな心持ちで行っているか」が大切です。
抹香を額に当てる作法の注意点
浄土宗や曹洞宗では、香を額に当てる作法が残っている場合もあります。
一方、浄土真宗ではこの所作は誤りとされます。とくに真宗では“阿弥陀仏の功徳にゆだねる”という考えが強いため、「個人の祈願を表す所作」とされる額にいただく仕草は行いません。
事前に宗派がわかっている場合は、抹香の扱いにも注意しましょう。
読経中のふるまいと参加の仕方

読経中の時間は、参列者にとって故人を偲び、心を静める大切なひとときです。しかし合掌の仕方や唱和の有無など、宗派によって違いがあるため、不安に思う方もいるかもしれません。
ここでは宗派ごとの特徴と、迷わず過ごすための心構えを紹介します。
念仏やお題目を唱える場面とは?
宗派によって、読経中に念仏やお題目を唱える作法が異なります。
- 「南無阿弥陀仏」
浄土宗・浄土真宗・天台宗 - 「南無妙法蓮華経」
日蓮宗 - 「南無大師遍照金剛」
真言宗
ただし参列者全員が声を出しているわけではなく、必ずしも唱和が求められるわけではありません。無理に合わせる必要はなく、静かに手を合わせるだけでも敬意は十分に伝わります。
宗派による違いがあっても、心を向ける姿勢こそが大切です。
禅宗では「静かに聞く」が作法
禅宗に属する臨済宗や曹洞宗では、読経中に声を出すことは基本的に行いません。むしろ沈黙の中で心を整える時間として捉えられており、導師の読経を静かに聞くことが重要とされます。
合掌も必要最低限にとどめ、私語や身じろぎを控えて座っていることが作法の一つです。
何もせずに静かにしているだけで良いのかと不安に思うかもしれませんが、それがもっとも自然で礼を尽くしたふるまいとされています。
周囲の動きに合わせることが基本
読経中の動きに迷ったときは、まわりの参列者の様子を参考にするのがもっとも自然です。声を出している人がいなければ無言を貫き、合掌のタイミングだけを合わせれば、礼を欠くことはありません。
葬儀では“目立たないこと”が最大の配慮になる場面もあります。知らない作法を無理に真似してぎこちなくなるよりも、静かに礼を尽くすことで十分に故人を偲ぶことができます。
数珠の扱い方と基本マナー

仏式の葬儀において、数珠はただの装飾品ではなく、仏とのつながりを象徴する大切な法具です。数珠の扱い方や合掌の仕方は、日常生活ではあまり意識することがないため、いざ参列する場面で迷ってしまう人も少なくありません。
宗派によって細かな違いはあるものの、基本的な所作を理解しておけば、周囲に不快感を与えることなく礼を尽くせます。
ここでは数珠の持ち方の基本、宗派ごとの特徴、そして数珠がない場合の対応までを紹介します。
数珠の持ち方の基本を知っておく
仏式の葬儀では、数珠を持参するのが一般的です。
基本的には左手にかけ、合掌の際に両手に軽く通して使います。かばんやポケットに無造作に入れたり、ジャラジャラと音を立てるのは避けましょう。
焼香や合掌の動作と同様に、数珠の扱いもその人の所作として見られることがあります。持ち方に自信がない場合は、手に持って静かに扱うだけでも問題ありません。
 お葬式で使う『数珠』の基礎知識:意味・マナーから選び方まで
お葬式で使う『数珠』の基礎知識:意味・マナーから選び方まで
各宗派の数珠の扱い方
宗派によって、数珠の持ち方や扱い方は大きく異なります。
- 浄土宗
念仏の回数を数えるために用いる。合掌する際、数珠の輪を親指と四指の間にかけ、房が下に垂れるようにして両手を合わせる。 - 浄土真宗
手首にかけないのが特徴。 合掌する際は数珠を両手の親指以外の4本の指にかけ、房を下に垂らして手を合わせる。
阿弥陀如来の力にすべてをゆだねる「他力本願」の教えを反映した作法。 - 天台宗
平たい玉が特徴。 合掌するときは、数珠を人差し指と中指の間に挟んで両手を合わせ、房を下に垂らす。 - 真言宗
数珠を特に重要視する。 合掌する際は、数珠を二重にして両手の中指にかけ、そのまま手を合わせる。 - 臨済宗・曹洞宗
数珠を二重にして左手の親指と人差し指の間にかけ、右手を合わせて合掌する。 房はそのまま下に垂らす。 - 日蓮宗
房が3本と2本に分かれているのが特徴。 お題目を唱える際は、房が3本ある方を左手の中指に、2本ある方を右手の中指にかけて、8の字にねじってから合掌。 房は外側に垂らす。
数珠の所作には、各宗派の教えや考え方が色濃く反映されています。参列前に、故人の宗派を確認しておくと安心です。
数珠がなくても参列は可能
数珠を持参していなかったとしても、それだけでマナー違反になることはありません。
ただし正式な場では数珠を持っている人が多いため、特に親族や会社関係者として参列する場合は、準備しておくと安心です。
どうしても用意が間に合わないときは、合掌だけで礼を尽くせば十分です。持っていないことを咎められるような場面は、まずありません。
故人の宗派がわからないときの対応

葬儀に参列するとき、故人や遺族の宗派がわからないことは珍しくありません。焼香の回数や香典袋の表書きなど、判断に迷う場面もあるでしょう。
そのような場合は「静かに・丁寧に・目立たない」を意識すれば、失礼になることはありません。
- 焼香は1回で十分
- 抹香は額に当てない
- 数珠がなければ合掌だけでも可
- 念仏やお題目は無理に唱えなくてよい
- 前の人の動きを参考にする
作法の違いを知らないことよりも、「無理に独自の動きをしない」ことの方が大切です。宗派がわからなくても慌てず落ち着いて行動すれば、故人にも遺族にもきちんと礼が伝わります。
ただ、今後もし喪主の立場になった場合には、宗派に応じた葬儀の流れなど、多くのことを把握しておく必要があります。
わからないことがあっても丁寧にアドバイスをもらえる、小さなお葬式のような全国対応のサービスを知っておくと心強いでしょう。
【比較表】宗派ごとの主な作法・マナーの違い

代表的な六つの宗派について、参列者が特に気を付けたい作法をまとめました。
| 宗派 | 焼香回数 | 合掌 | 念仏・お題目 | 数珠 |
|---|---|---|---|---|
| 浄土宗 | 1~3回 | 焼香前後に必ず | 「南無阿弥陀仏」 | 合掌時に両手で持つ |
| 浄土真宗 (本願寺派) |
1回 (額に押しいただかない) |
必ず行う | 「南無阿弥陀仏」 | 合掌時に両手で持つ |
| 浄土真宗 (大谷派) |
2回 (額に押しいただかない) |
必ず行う | 「南無阿弥陀仏」 | 合掌時に両手で持つ |
| 臨済宗 | 1回または2回 | 焼香後に必ず | 黙祷 | 合掌時に左手で持つ |
| 曹洞宗 | 2回または3回 | 焼香後に必ず | 黙祷 | 合掌時に左手で持つ |
| 日蓮宗 | 1回または3回 | 焼香後に必ず | 「南無妙法蓮華経」 | 合掌時に左手で持つ |
※この表はあくまで一般的な目安です。寺院の方針や地域の習慣によって違いがある場合もあります。
参列時は、まず会場の案内や周囲の流れに従うことが一番大切です。形式を完璧に守ることよりも、静かに心を込めて故人を偲ぶ姿勢が何よりの礼儀になります。
まとめ

仏教の葬儀では、宗派ごとに焼香や合掌の仕方、読経への参加など細かな作法の違いがあります。しかし、参列者に一番求められるのは「敬意をもって丁寧にふるまうこと」です。
完璧な作法よりも、落ち着いた動きと静かな姿勢が何よりの礼儀になります。
宗派がわからない場合でも焼香は1回、抹香は額に当てず、静かに合掌すれば失礼にはなりません。今回ご紹介したポイントを押さえておけば、安心して葬儀に臨むことができるでしょう。