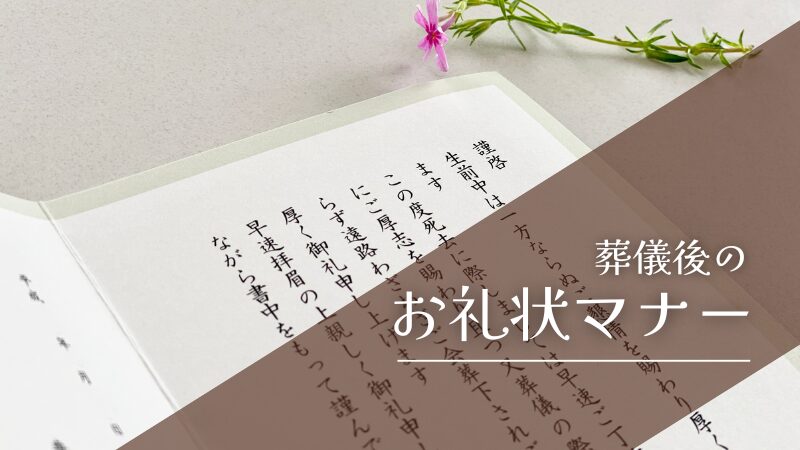身内のご不幸で葬儀を終えた後には、お世話になった方々へ感謝の気持ちを伝える機会があります。
ご会葬くださった方への会葬礼状や、葬儀に参列できず弔電(お悔やみ電報)や供花・供物をくださった方へのお礼状など、何をどう書けばよいか戸惑う方も多いでしょう。
この記事では、会葬礼状の文例や弔電お礼状のマナーをはじめ、供花・供物へのお礼状について、基本的なマナーや注意点を丁寧に解説し、実際に使える文例を複数ご紹介します。一般的な内容に留めていますので、宗教や地域を問わず参考にしていただけます。本記事がお悔やみの気持ちを伝えるお手伝いになれば幸いです。
会葬礼状とは?基本マナーと文例

会葬礼状の役割と渡すタイミング
会葬礼状(会葬御礼状)とは、通夜や葬儀・告別式に参列(会葬)してくださった方へ感謝を伝える手紙のことです。
一般的には葬儀当日の受付時にお渡しし、香典返しの品(会葬返礼品)とともに手渡します。参列者全員に渡すのが基本で、香典をいただいたかどうかに関わらずお礼状を用意します。
当日参列されなかった方でも弔電や供花・供物、お悔やみ状などをくださった場合には、葬儀後できるだけ早めにお礼状を送ります。葬儀後の落ち着かない時期かもしれませんが、感謝の気持ちはなるべく早く形にしてお伝えすることが大切です。
会葬礼状の書き方・基本構成
会葬礼状に明確な決まりはありませんが、一般的に次の7つのポイントを押さえて書きます。(※正式には縦書き・毛筆を想定した伝統的な形式です)。
主な構成要素は以下のとおりです。
故人の名前と続柄を冒頭に記載
「故 〇〇〇〇 儀」または「亡父(亡母)〇〇儀」のように記載します。亡くなった方の名前の後には「儀」と書くのが一般的です。
儀には「~に関すること」「~のこと」といった意味合いがあり、故人への敬意を表すために用いられます。省略せずに記載するのがマナーです。
参列いただいたことへの御礼
「ご多忙の中ご会葬いただき誠にありがとうございました」「ご厚情を賜り厚く御礼申し上げます」といった表現で、足を運んでくださったことへの感謝の言葉を伝えます。
香典など金品を頂戴している場合のお礼
香典は「ご香典」「ご厚志」「ご芳志」などと表現し、「ご厚志を賜り厚くお礼申し上げます」「ご鄭重なご香典を賜り深謝申し上げます」のように書きます。
無事に葬儀が執り行えた旨の報告
「おかげさまで滞りなく葬儀を終えることができました」などと記し、支えてくれたことへの感謝と安堵の気持ちを伝えます。
故人が生前に受けたご厚情への感謝
「生前に賜りましたご厚情に深く感謝申し上げます」のように、生前お世話になったことへの御礼を付け加えると丁寧です。
手紙での御礼をお詫びする結びの言葉
「本来であれば拝顔の上お礼を申し上げるべきところですが、略儀ながら書中にてご挨拶申し上げます」といった一文で、直接お会いできない非礼を詫びます。この「略儀ながら~」という表現を添えるのがマナーです。
日付と、差出人(喪主)の住所・氏名を末尾に記載
差出人名の後には「喪主〇〇〇〇 外 親族一同」などと書き添えるのが一般的です。これにより、喪主だけでなく家族・親戚一同からの感謝であることを表します。
上記のような構成を押さえれば、形式ばった内容でも心のこもった会葬礼状を書くことができます。「何を書けば良いのか分からない…」という場合は、これら項目を順番に満たす文章を作ればひな形になります。
なお、故人と特に親しかった方へ送る場合などは、定型文だけでなく個人的なメッセージやエピソードを織り交ぜても構いません。
例えば「〇〇様には故人も生前大変お世話になりました。家族一同心より感謝しております」など故人と受取人の関係性に触れたり、家族ぐるみで親交のあった方には「今後とも変わらぬお付き合いをお願い申し上げます」といった文を加えるのも良いでしょう。
ただし長くなりすぎないよう、あくまで感謝の気持ちをシンプルに伝えることが大切です。
会葬礼状の文例(例文)
上記ポイントを踏まえた会葬礼状の文例を2つ紹介します。
実際の文章では一般に句読点を付けませんが、ここでは読みやすさを考慮して句点「。」などを用いています(正式な礼状を作成する際は、後述のマナーに沿って句読点を省略してください)。
文例1(一般的な会葬礼状)
亡父 ◯◯◯◯ の通夜並びに葬儀に際し、ご多忙中にもかかわらずご会葬賜り誠にありがとうございました。
生前に賜りましたご厚情とあわせ、厚く御礼申し上げます。おかげさまで滞りなく葬儀を執り行うことができました。
本来なら拝眉にてお礼申し上げるべきところではございますが、略儀ながら書中にてご挨拶申し上げます。
令和◯年◯月◯日
住所〇〇県〇〇市〇〇
喪主 ◯◯◯◯ 外 親族一同
文例2(よりカジュアルな文例・家族葬など向け)
亡母 ◯◯◯◯ の葬儀に際しましては、ご多用中にもかかわらずご参列いただき誠にありがとうございました。
お寄せいただいたお心遣いに家族一同心より感謝しております。○○様には生前◯◯(故人名前)も大変お世話になりました。
この場をお借りして厚く御礼申し上げます。略儀ではございますが、まずは書中にて御礼申し上げます。
(※家族のみの葬儀など、内輪の場合は故人の人柄や思い出に触れる一文を入れることもできます。例えば「◯◯は生前○○様との△△(趣味や活動)を大変喜んでおりました」などと書くことで、参列者と故人の思い出を共有することもできます。)
上記のような文例を参考に、自分の言葉も交えつつ感謝の気持ちを丁寧に綴りましょう。印刷サービスや葬儀社が用意する定型文を使う場合でも、故人の名前や日付、差出人名などを正確に記載するのを忘れないでください。
会葬礼状を書くときの7つの注意点とマナー
会葬礼状を作成する際には、一般的な手紙とは異なる弔事独特のマナーがあります。以下の7つにまとめました。
①時候の挨拶は書かない
慶事の手紙とは異なり、忌明け前(四十九日以前)の弔事の挨拶状では季節の挨拶は不要です。いきなり本題(故人名や御礼の言葉)から書き始めましょう。
②頭語や結語
「拝啓・敬具」「謹啓・謹白」といった頭語・結語は入れても入れなくても構いません。
入れる場合は両方セットで用い、どちらか一方だけになるのはマナー違反です。略式の場合は省略しても失礼にはあたりません。
③薄墨を使う
手書きで礼状を書く場合、薄墨の筆ペンや万年筆を使うのがマナーです。
薄墨には「急な訃報で濃墨を用意できなかった」「涙で墨が薄くなった」などの意味合いがあり、哀悼の意を表します。パソコンで作成する際も、可能であれば文字色をグレーがかった薄墨色に設定すると良いでしょう。
④句読点を使用しない
弔事の正式な文書では句読点(、。)を打たないのが一般的です。
もともと毛筆の縦書き文化では句読点を用いなかったことや、「終わり(区切り)がないように」という忌み意識から、葬儀関係の挨拶状では句読点を避ける習慣があります。
最近ではそれほど厳格でない場合もありますが、形式を重んじる方へ送る場合は基本に倣っておくと安心です。
⑤忌み言葉・重ね言葉を避ける
不幸が繰り返すことを連想させる言葉は避けます。「重ね重ね」「再び」「続いて」「度々」「ますます」などは忌み言葉となるため使用しません。
また「死ぬ」「生きる」など直接的な表現も避け、「逝去」「生前」「ご健在の折」など婉曲な表現に言い換えます。うっかり使いがちな言葉ですが注意しましょう。
⑥数字の表記: 日付や歳など数字を書く際、漢数字を使うのが通例
(例:「令和三年八月一日」「享年六十」など)。不幸を連想させる「四」「九」などの数字も忌避する習慣がありますが、お礼状の日付等ではあまり気にしすぎる必要はありません。
ただし「仏滅」など不吉な暦日は避けて日付を書く、など細かい配慮をする地域もあります。
⑦用紙や形式
宛名を印刷したハガキ形式や封書など、形式に明確な決まりはありません。
一般的には白無地の便箋やハガキを用い、黒枠入りの専用用紙を使うこともあります。地域の風習や葬儀社と相談し、形式を選ぶとよいでしょう。
いずれの場合も丁寧な言葉遣いとマナーに沿って書けば気持ちは伝わります。
以上を踏まえ、まずは会葬礼状を準備しましょう。
次に、弔電や供花など個別のケースでのお礼状マナーについて解説します。
弔電(お悔やみ電報)を頂いた場合のお礼状

遠方や都合により葬儀に参列できない方からは、「弔電」やお悔やみの手紙をいただくことがあります。丁寧な方はわざわざ電報で哀悼の意を寄せてくださいますが、弔電を頂いた場合にも後日必ずお礼状で感謝を伝えるのがマナーです。
葬儀当日に会葬礼状を直接手渡しすることができなかった分、改めて書状で気持ちを伝えましょう。以下に弔電へのお礼状マナーと文例を紹介します。
弔電へのお礼状を書くポイント6つ
早めに送る
弔電のお礼状は、葬儀後なるべく早く送りましょう。できれば葬儀の翌週以内には投函し、遅くとも四十九日までには届くようにします。時間が経ちすぎると感謝の気持ちが伝わりにくくなるため、忘れずに対処しましょう。
弔電への感謝を述べる
弔電を頂いたことへのお礼をしっかり伝えます。「ご多忙中にもかかわらずご弔電を賜り厚く御礼申し上げます」「温かいお悔やみのお言葉を頂戴し誠にありがとうございました」など、電報を送ってくださったことへの感謝を表現します。
葬儀が無事済んだ報告
可能であれば「おかげさまで滞りなく葬儀を執り行いました」「◯月◯日に告別式も相済みました」など、葬儀が無事終了したことのご報告を簡潔に含めます。弔電をくださった方も気に掛けているはずなので、結びの前に一言触れておくと良いでしょう。
故人や遺族の気持ちに触れる
弔電の文面でいただいた故人へのお言葉に対し、お礼状で返答する形で触れるのも丁寧です。
例えば「○○様の温かいお悔やみのお言葉に、家族一同慰められました」「△△様より頂戴した励ましの電報の文面に故人もきっと喜んでいることと存じます」など、電報の好意が励みになった旨を伝えると、先方にも気持ちが伝わります。
略儀のお詫び
会葬礼状と同様、本来は直接会って御礼すべきところを手紙で失礼するお詫びを入れます。
「略儀ながら書面にて御礼申し上げます」「まずは書中にて御礼申し上げます」などの定型表現で締めくくりましょう。
差出人・日付
差出人(喪主)の氏名と日付も忘れずに記載します。弔電のお礼状も、会葬礼状と同じく喪主名+「親族一同」とすると丁寧です。封書の場合は別途封筒に宛名を書きますが、ハガキ形式なら文面中に宛名を書くスペースは不要です。
弔電のお礼状の文例
弔電を頂いた方へのお礼状文例を2つ紹介します。電報をくださった相手との関係性や文面に応じて、表現を調整してください。
このたびは亡夫 ◯◯◯◯ の葬儀に際しまして、ご丁重なる弔電を賜り誠にありがとうございました。おかげさまで◯月◯日に滞りなく葬儀・告別式を執り行うことができました。
生前、故人が公私にわたり◯◯様にお世話になりましたことを改めて感謝申し上げます。
いただいた温かいお言葉に家族一同大変慰められました。本来ならば拝顔の上直接御礼申し上げるべきところではございますが、略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます。
令和◯年◯月◯日
喪主 ◯◯◯◯ 外 親族一同
このたびは◯◯(故人名前)のためにご鄭重な弔電を頂き、本当にありがとうございました。
◯◯様からの心のこもったお悔やみの言葉は遺族一同大きな支えとなりました。お陰をもちまして◯月◯日に家族葬を滞りなく終えることができ、故人も安らかに旅立っていったことと存じます。
お忙しい中お気遣いいただきましたこと、心より厚く御礼申し上げます。まずは略儀ながら書中にてご挨拶申し上げます。
弔電へのお礼状では、電報本文に触れて感謝することで「ちゃんと読んだ上で心に届いた」ことが伝わり、より真心が伝わります。
また、会社関係の方からの弔電であれば、故人(亡くなった方)が生前に職場でお世話になったことへの御礼を述べるのも良いでしょう。
「生前在職中は格別のご厚情を賜り心より御礼申し上げます」など一文加えると丁寧です。
供花へのお礼状のマナーと文例
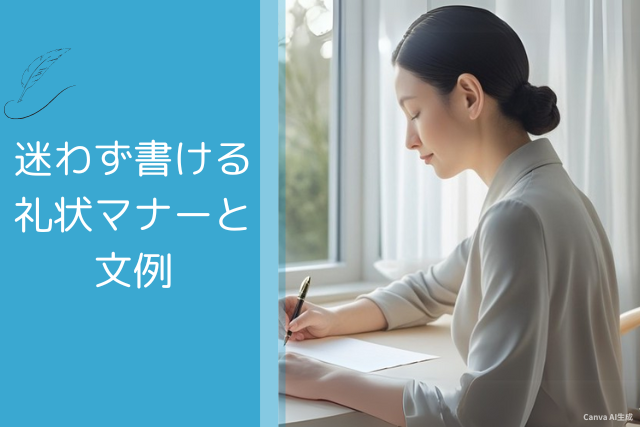
葬儀や通夜の際に故人ゆかりの方から供花(くげ、供え花、生花)を頂くことがあります。祭壇や式場を飾る立派なお花をお送りいただいた場合、そのお気持ちに対しお礼状を送るのがマナーです。供花のみを頂いたケースでは「香典を頂いていないからお返しは不要では?」と迷うかもしれません。
しかし、供花にも相応の費用がかかっていますし、何よりお気遣いをいただいた事実に変わりありません。
品物でのお返しをしない場合でも、必ず感謝の気持ちをお礼状で伝えましょう。
供花へのお礼状のポイント5つ
できるだけ早く出す
基本は葬儀後なるべく早めに手紙を投函します。
遠方の方には郵送、近しい間柄であれば忌明け前に直接会ってお礼を伝えるのも良いでしょう。
地域によっては四十九日明け(忌明け)に改めてお礼状とお礼の品を贈る習慣もありますが、まずは葬儀終了後一週間以内を目安にお礼状だけでも送ると丁寧です。
供花を受け取ったお礼
供花へのお礼状では、まず綺麗なお花をいただいたことへの感謝を述べます。
「このたびは亡父◯◯の葬儀に際し、結構なお花をお供え賜り厚く御礼申し上げます」など、頂戴した供花へのお礼をはっきり書きましょう。
供花を飾った報告
お花は故人への供養として捧げられていますので、「頂いたお花は霊前に飾らせていただきました」など、ちゃんと祭壇に供えた旨を伝えると先方も安心します。
故人や遺族の喜び
可能であれば「祭壇が華やぎ故人もきっと喜んでいることと存じます」「温かなお気持ちに遺族一同慰められました」など、お花をいただいたことによる心情にも触れます。
お花が式場を彩り心強かったことを一言伝えると、贈った側も報われるでしょう。
略儀のお詫び
他のお礼状と同様に、「本来なら拝眉にてお礼申し上げるべきところですが、略儀ながら書中にて失礼いたします」などの結びで締めくくります。品物を頂戴した場合でもまず手紙でお礼を伝えるのがマナーです。
供花へのお礼状の文例
供花を頂いた方へ送る礼状の文例を紹介します。故人との関係性や地域の習慣によって文言は多少調整してください。
文例1(一般的な供花のお礼状)
亡父 ◯◯◯◯ の葬儀に際しましては、立派なご供花をお供え賜り誠にありがとうございました。
お贈りいただいたお花は謹んで拝受し、早速祭壇に飾らせていただきました。おかげさまで式場が華やぎ、故人もさぞ喜んでいることと存じます。
ご厚情に家族一同心より感謝申し上げます。本来であればお伺いの上直接御礼申し上げるべきところではございますが、略儀ながら書中にて御礼申し上げます。
令和◯年◯月◯日
喪主 ◯◯◯◯ 外 親族一同
謹啓 先般 亡母 ◯◯◯◯ 儀 葬儀に際しましては、結構な生花をご恵贈賜り厚く御礼申し上げます。
頂戴いたしましたお花は謹んで霊前にお供えさせていただきました。ご教示くださった故人へのお心遣いに一同深謝申し上げます。
本来なら早速拝眉の上御礼申し上げるべきところ、略儀ながら書中をもちまして御礼申し上げます。敬具
(※頭語「謹啓」および結語「敬具」を用いた正式な文例です。省略する場合はこれらの頭語・結語を除いた文章にします。)
上記のように供花へのお礼状では「受け取ったお花を霊前に供えた」ことを伝える表現がポイントです。
また、生花を贈ってくださった厚意への感謝を丁寧な言葉で綴りましょう。地域によっては、供花をくださった方へ後日お礼の品(返礼品)を贈るケースもあります。
そお場合は、四十九日法要後に「志」(志料)として品物をお送りし、お礼状を添えるとよいとされています。
ただし品物の有無にかかわらず、まずは文章で真心を伝えることを大切にしてください。
供物(お供え物)へのお礼状のマナーと文例
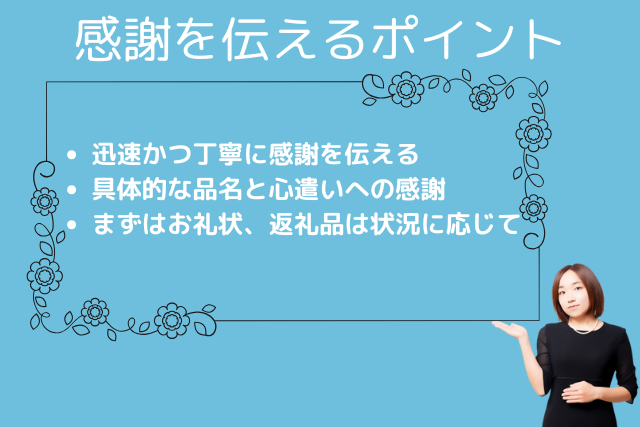
「供物(くもつ)」とは、故人に供える果物籠や菓子折り、飲み物、その他供養の品のことです。
葬儀に際し生花以外の品物をお供えくださる方もおり、これもありがたいお気持ちの表れです。供物を頂いた場合も、基本的には供花と同様にお礼状を出して感謝を伝えます。
供物へのお礼状を書く4つのポイント
供花の場合と同様に対応
供物へのお礼状マナーは供花の場合とほぼ同じです。葬儀後できるだけ早めに礼状を出し、頂いた品物への御礼と供えた報告をします。
例えば「このたびは結構なお供物を賜り誠にありがとうございました。頂戴しました品はただちに霊前にお供えいたしました」といった具合です。
具体的な品名にも触れる
差し支えなければ、頂いた供物の内容(果物や菓子など)に触れてお礼を述べると丁寧です。
「ご恵贈いただきました果物籠は早速祭壇に供えさせていただきました」「◯◯をお供え賜り…」など具体的に記すことで、相手にも気持ちが伝わります。ただし宗教的にタブーな品でない限り、深く言及しなくても構いません。
供花同様、略儀を詫びる
供物の場合もお礼は本来直接伝えるのが礼儀ですが、現実には難しいため手紙で失礼する旨を書き添えます。「略儀ながら書中にて御礼申し上げます」という一文で結びましょう。
香典返しとの兼ね合い
供物のみ頂いた場合、供花と同じく後日お礼の品をお送りする習慣がある地域もあります。判断に迷う場合は、まずお礼状だけでも送り、その後の返礼品の要否は葬儀社や年長者と相談するとよいでしょう。
供物へのお礼状の文例
供物(お供え物)を頂戴した場合のお礼状文例をご紹介します。
文例1(供物へのお礼状)
亡祖母 ◯◯◯◯ の葬儀に際しましては、ご丁重なお供物を頂戴し誠にありがとうございました。
いただきました果物籠は謹んで霊前にお供えさせていただきました。◯◯様の温かいお心遣いに、一同心より感謝申し上げます。
本来なら早速拝眉の上お礼申し上げるべきところ、まずは略儀ながら書中にて御礼申し上げます。
令和◯年◯月◯日
喪主 ◯◯◯◯ 外 親族一同
文例2(供物へのお礼状・シンプルな例)
このたびは◯◯(故人名前)の葬儀にあたり、お心のこもったお供えを賜り厚く御礼申し上げます。
頂戴いたしました品は葬儀式場の祭壇に供えさせていただき、故人もさぞ喜んでおりますことと存じます。
ご教示いただいたご厚情に深く感謝いたします。略儀ではございますが、まずは書中をもちまして御礼申し上げます。
供物への礼状では、品物そのものだけでなくそのお気持ちへの感謝を丁寧に述べることが大切です。弔問や香典とはまた別にお気遣いいただいた厚意ですので、「お心遣い」「ご厚情」などの言葉を使って感謝を表現しましょう。
供花と同じく、後日改めて品物でお返しをする場合でも、まずは言葉で真心を伝えるお礼状を送ることを優先してください。
さいごに:お礼状で感謝の気持ちを丁寧に伝えよう

葬儀後のお礼状(会葬礼状や弔電・供花・供物への礼状)は、遺族からお世話になった方々への大切な心遣いです。
基本マナーを押さえつつ、丁寧で温かな言葉で感謝を綴れば、きっと相手にも真心が伝わることでしょう。紹介した文例はあくまで一例ですので、故人やご家族の状況に合わせて適宜アレンジして構いません。
文章の形式ばかりに捉われず、「ありがとう」の気持ちを大切に書くことが一番のポイントです。悲しみで忙しい時期にお礼状の準備は大変かもしれませんが、一通一通に感謝を込めて届ければ、きっと故人も安心してくれることでしょう。
困ったときは本記事のマナーと文例を参考に、心のこもったお礼状を作成してみてくださいね。