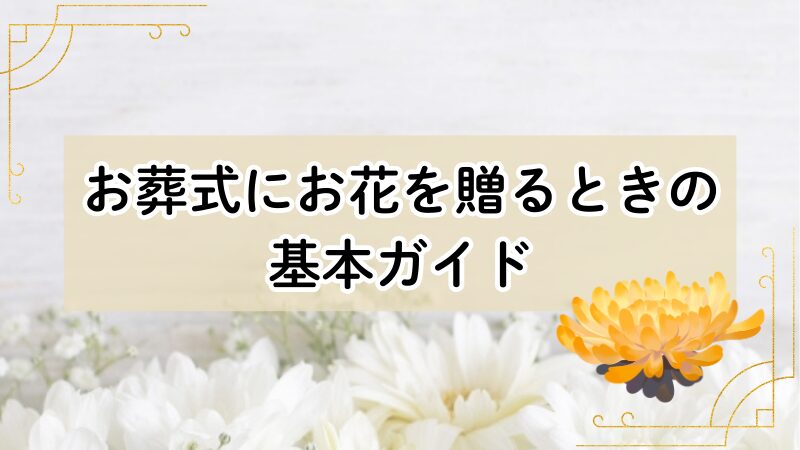訃報を受けて「花を贈りたい」と思っても、どんな花を選べばよいか迷う方は少なくありません。
親族として供花を出す場合と、友人や勤務先の立場から贈る場合では手順や費用の相場に違いがあります。また、宗教や会場の方針によっては花の種類や名札の書き方に制限が設けられることもあります。
慌てて手配すると喪家の意向に合わず、かえって負担を増やす恐れもあります。基本的な考え方をあらかじめ知っておくことで、失礼を避けながら落ち着いて準備を進められます。
本記事では、贈る立場や場面ごとの違い、費用の目安や注文の流れを整理し、迷いやすいポイントを具体的に解説します。
目次
供花を贈るときの基本ポイント

「供花」「枕花」「弔問の花」など、お葬式で使われる花の呼び方は分かりにくく、どんな場面でどれを贈ればよいのか迷う方は少なくありません。
親族として贈る場合と、友人や勤務先の立場から贈る場合でも判断は変わり、会場や宗教によって受け入れ方も異なります。まずはそれぞれの形と特徴を知ることで、どんな状況でも安心して選べる基礎が身につきます。
ここでは、代表的な花の種類と贈られる場面を整理して紹介します。
贈る場面ごとの花の違い
お葬式に贈る花は、届ける時期や目的によって「枕花」「供花」「弔問の花」と呼び方が分かれます。主な違いは以下のとおりです。
| 種類 | 贈る時期・場面 | 特徴・注意点 |
|---|---|---|
| 枕花 | 逝去直後(病院・自宅) | 近親者や親しい友人が届ける。小ぶりで控えめ。受け取り可能な時間帯を確認する必要あり |
| 供花 | 通夜・葬儀会場 | 祭壇に飾る。会場の統一仕様に従い、サイズや配置は指定に合わせる |
| 弔問の花 | 葬儀後(自宅) | 供花辞退や混雑回避のときに用いる。落ち着いた時期に贈りやすい |
枕花は静かに気持ちを伝えるための花、供花は式場全体を整える花、弔問の花は葬儀後に心情へ寄り添う花と位置づけられます。
いずれの場合も、香りが強い品種や花粉が落ちやすい品種は避け、搬入や廃棄のルールを確認しておくと遺族の負担を減らせます。
宗教ごとの花の考え方
花の選び方は、宗教や会場の方針によって異なります。白を基調とすることが多いとはいえ、宗派ごとに違いがあるため事前の確認が安心です。特にキリスト教式では、教会によって外部からの供花を受け付けないこともあるので注意が必要です。
以下の表に、代表的な宗教形式ごとの花の傾向と注意点を整理しました。
| 形式 | 主な花の傾向 | 注意点 |
|---|---|---|
| 仏式 | 白菊・胡蝶蘭・カーネーションなど | 原色は避ける傾向。地域によって違いあり |
| キリスト教式 | 百合・カーネーションなどの洋花 | 教会によって外部持ち込み不可の場合あり |
| 神式 | 白百合・菊・榊など | 玉串の儀礼が中心のため、配置は要確認 |
| 無宗教式 | 白基調の洋花や季節の花 | 喪家の希望や会場方針を優先する |
宗派や地域で禁忌が明確に決まっていない場合もあるため、迷ったときは白を中心に落ち着いた色合いを選ぶと安心です。色数を抑えた花は、写真の印象を損ねず、他の供花とも調和しやすいという利点もあります。
確認するときに意識したいこと
花を手配する際は、まず受け入れの可否と会場の指定条件を確かめましょう。宗教や地域ごとの慣習があっても、細かい点は会場の方針によって異なります。
白を基調とした落ち着いた花を基本にすると失敗がありません。枕花は控えめなサイズで早めに届け、供花は会場の仕様に合わせて依頼すると遺族の負担を減らせます。また、札の名義やカード文面は簡潔にまとめ、追悼の気持ちを穏やかに伝えることを意識すると安心です。
判断に迷ったときは、葬儀社や会場の担当者へ確認・相談することがスムーズに手配する近道です。
たとえば大手葬儀社の「小さなお葬式」なら、葬儀の準備・マナーに関する相談にもスタッフが丁寧に対応します。不安な点があるときは、担当スタッフに遠慮なく確認してみましょう。
立場ごとの花の贈り方と注意点

花を贈る方法は、送り主の立場によって変わります。
親族として贈る場合は、喪主の意向を尊重するのが基本です。勤務先の関係者なら、会社の規定や慣例などを優先する必要があります。友人や近隣の方は、供花辞退の方針が出ているときには弔電や後日の弔問に切り替える柔軟さが求められます。
ここでは立場ごとの考え方や注意点を整理し、迷いやすい場面で役立つ判断のポイントを紹介します。
親族として花を贈る場合
親族が花を贈る場合は、喪主の方針や会場の仕様に合わせることが最優先です。個別に派手な装花を持ち込むのは避け、会場全体の調和を大切にします。供花の配置や札名の並びは、葬儀社へ調整を依頼すれば当日の混乱を防げます。
親族として花を贈るときの主な注意点は次のとおりです。
- 枕花は基本的に親族ではなく、友人ややや離れた親族が手配する
- 連名にする場合は名字や世帯の順序を事前に決める
- 費用負担は相場の範囲で分担し、記録を残す
- 供花と香典を両方出すときは、全体の負担額を考えて調整する
あらかじめ整理しておけば、親族として無理のない形で花を贈ることができます。
勤務先の関係者として花を贈る場合
勤務先から花を贈る場合は、個人で判断せず規程や慣例を必ず確認することが大切です。
特に取引先の葬儀では、供花の受け入れ可否や持ち込みの制限を直接問い合わせてから手配するのが安心です。会計処理なども含めて、事前の準備が欠かせません。
勤務先から供花を贈るときの注意点は次のとおりです。
- 名義は個人名義・部署名義・代表者名入りなど社内規程に沿って決める
- 連名にする場合は、会計と名簿管理の担当を事前に決める
- 名札は会場の規格に従い、会社名を強調し過ぎない
- 領収書・請求書の宛名を先に確認し、会計処理を円滑にする
- 香典と供花の重複可否は、必ず社内規程を確認する
こうした点を押さえることで、勤務先の関係者としての礼儀を守りながら滞りなく手配できます。
友人や近隣の人から花を贈る場合

友人や近隣の方が花を贈る場合は、遺族の負担を増やさないことを第一に考えましょう。
会場が混雑しそうなときは弔電や後日の弔問花に切り替えるなど、柔軟な対応が望まれます。親しい関係で枕花を届ける場合も、時間帯や大きさに配慮して控えめにすることが大切です。
友人や近隣から花を贈るときの注意点は次のとおりです。
- 混雑が想定される場合は、弔電や後日の自宅宛てに切り替える
- 枕花を届けるときは、家族の休息を妨げない時間帯を選ぶ
- 色味は白を中心に落ち着いたトーンにし、大きすぎる装花は避ける
- 複数人で連名にする場合は、名字や表記を事前に統一する
- 供花と香典を両方検討する場合は、関係性の深さに応じてどちらかを選ぶ
このように配慮すれば、友人や近隣の立場からでも無理なく弔意を伝えられます。
贈り主の立場から意識したいこと
どの立場から花を贈るにしても、まず確認したいのは「供花を受け付けているか」「仕様や搬入のルールはどうなっているか」という点です。
親族なら喪主の方針を尊重し、会社関係では規程や決裁の流れを整理し、友人や近隣の場合は無理のない方法に切り替える柔軟さが求められます。名札の表記や連名の順序は、会場で混乱しやすい部分なので早めに決めておくと安心です。
迷ったときは葬儀社や会場へ相談すると、大きなトラブルを避けられます。費用やサイズで見栄を張る必要はなく、心を込めた花を過不足なく贈ることが、自然で印象に残る供花の形といえるでしょう。
供花を手配するときのポイント

供花を準備するときに気になるのは、費用の目安です。価格帯は地域や会場の仕様で幅がありますが、一般的な相場を把握しておくと検討がしやすくなります。また、名札の書き方は受け手の印象に直結するため、表記の仕方や敬称の有無を誤らないことも大切です。
ここでは費用の目安と名札の表記ルールを中心に、迷いやすい点を整理して解説します。
立場別に見た供花の費用の目安
供花の費用は立場によって変わります。
親族は喪主や近親者との関係性に応じて調整し、勤務先や取引先では社内規程や慣例に従うのが一般的です。部署単位で出す場合は、一基を大きめにして連名にすることが多いです。友人や近隣の人は負担の少ない範囲でまとめて贈るケースが目立ちます。
いずれの場合も、会場の規格と喪家の方針を確認してから手配すると安心です。
| 立場 | 費用の目安(1基) |
|---|---|
| 親族 | 15,000〜30,000円 |
| 勤務先・取引先 | 20,000〜30,000円 |
| 友人・近隣 | 10,000〜20,000円 |
| 部署連名 | 30,000〜50,000円程度 |
金額はあくまで目安であり、多ければよいというものではありません。無理のない範囲で心を込めて贈れば十分に気持ちは伝わり、他の供花との調和も保ちやすくなります。
名札の書き方
名札は遺族や参列者が最初に目にする部分であり、簡潔さと正確さが求められます。表記は会場の規格に合わせ、誤記を防ぐため注文時に必ず原稿を共有しましょう。
個人はフルネーム、夫婦は連名、会社関係は社名を先に記すのが一般的です。敬称の「様」は通常付けず、肩書きは必要な場合のみ最小限にとどめます。
部署連名では「〇〇部一同」とまとめ、読み上げで混乱が起きにくい表記を選びます。会社名と個人名を併記する場合は、会社名を上段、個人名を下段に置くと識別しやすくなります。
| 立場 | 名札例 |
|---|---|
| 個人 | 山田太郎 |
| 夫婦 | 山田太郎・花子 |
| 会社 | 株式会社〇〇 |
| 会社+個人 | 株式会社〇〇 代表取締役 山田太郎 |
| 部署連名 | 株式会社〇〇 営業部一同 |
文字数が多いと読みにくくなるため、簡潔さを重視します。特に会社関係では「どの範囲を代表する花なのか」が一目でわかる形にすることが大切です。
葬儀社が校正する場合もありますが、注文時に表記原稿を渡し、差し替え可能な期限を確認しておくと安心です。
連名にする場合の考え方
供花を連名で贈る方法は、一基にまとめることで会場のスペースを取り過ぎず、遺族の負担を増やさない利点があります。人数が多いときは「〇〇部一同」などにまとめ、名簿は別に保存しておくと弔電や香典との混同を防げます。
費用面では、参加者ごとに負担額を事前に決めておき、端数の処理方法まで合意しておくと不公平感が生じにくくなります。名札は文字数が多いと読み上げや掲示で見づらくなるため、会場の規格に合わせて簡潔に表記することが重要です。
また、後から追加の参加者が出る場合を見込み、差し替え可能な期限や入金の締切をあらかじめ定め、代表者の連絡先を明記しておくと全体の管理がスムーズになります。
供花を手配するときに意識したいこと
供花の準備で大切なのは、会場と喪家の方針に合わせることです。相場はあくまで目安と考え、無理のない範囲で準備することが大切です。
名札は読みやすさを優先し、敬称や肩書は最小限にとどめましょう。会社関係では社名の書き方を統一すると印象が整います。連名の場合は代表者を決めて名簿や領収書を管理すると安心です。
判断に迷ったときは独断せず、会場や葬儀社に確認して進めることが重要です。
供花を手配するときの流れ

お葬式に供花を贈りたいと思っても、「まず何から始めればいいのか」と迷う方は少なくありません。会場の規格や搬入口の条件で選べる花のサイズが変わり、名札の表記確認や支払いのタイミングにも関わってきます。
ここでは供花を手配するときの流れを時系列で整理し、迷いやすい場面を具体的に見ていきます。手順を理解しておけば、複数人での依頼や会社関係の連携もスムーズになり、当日の負担を減らすことができます。
まず確認から始める
最初に行うのは「供花を受け付けているか」の確認です。会場によってはスタンド花や籠花の持ち込みに制限があり、搬入口の大きさや配置の規格で選べる仕様が限られる場合もあります。
確認する主な内容は次のとおりです。
- 供花を受け付けているかどうか
- 搬入可能なサイズや花の種類
- 名札の規格(文字数や表記方法)
- 搬入時間と設置の手順
これらを早めに確認することで、注文後の差し戻しや変更を防げます。
注文を進める
仕様が確認できたら、実際の注文に進みます。
多くの場合、葬儀社や会場指定の花店に依頼することになり、外部持ち込みは制限されることがあります。花の種類や色味の希望を伝えられる場合もありますが、会場の統一感を優先しましょう。
注文時に押さえておきたい点は次のとおりです。
- 希望を伝える際は会場の方針に従う
- 複数人での依頼は代表者を決め、連絡窓口を一本化する
- 支払い方法と期日を早めに確認する
- 搬入や配置は会場が管理するため、時間や規格だけを確認しておく
この流れを踏むことで、当日の行き違いを大きく減らせます。
なお、会場に指定店がない、または遠方から手配したいときは、オンラインの弔電・供花サービスも便利です。たとえば「VERY CARD」なら、式場向けの供花と弔電をあわせて手配できるため、突然の訃報にも迅速に対応できます。
名札を確認する

注文が済んだら、名札の表記を確認します。
供花の名札は遺族や参列者が目にする部分であり、誤記があると訂正が難しいため注意が必要です。表記は事前に原稿を用意し、敬称や肩書を最小限にしたうえで、社名や連名の並び順を統一します。
確認するときの主なポイントは次のとおりです。
- 個人名はフルネームで表記する
- 夫婦の場合は連名で並べる
- 会社関係は社名を先に記す
- 連名は「〇〇部一同」など簡潔にまとめる
- 誤記を防ぐため、必ず原稿を共有する
名札の内容は葬儀社が校正を行う場合もあるため、差し替え可能な期限を事前に確認しておくと安心です。
供花が辞退されたときの対応
葬儀案内に「供花辞退」と記されている場合は、別の形で弔意を示すことが大切です。無理に供花を届けると遺族に負担をかけるため、案内の方針に従いましょう。
供花の代わりに選ばれる方法には、次のようなものがあります。
- 弔電
式場で読み上げられるため、遺族の目に届きやすい - 香典
供花の代わりとして金銭で気持ちを伝える場合がある - 後日の弔問花
落ち着いた時期に自宅へ届け、静かに気持ちを伝える - 手紙やメッセージ
形式にとらわれず、個人的な思いを伝えられる
電報サービスの「VERY CARD」では、インターネットから簡単に弔電の手配が可能です。14時までの申込で全国即日配達(一部地域・商品を 除く)のため、急な訃報にもすばやく対応できます。
どの方法を選ぶかは、遺族との関係性や地域の慣習によって変わります。大切なのは、遺族が受け取りやすい方法を選ぶことです。
流れを把握するときに意識したいこと
供花を手配するときは、手順を一つずつ確認していくことで当日の混乱を防げます。
複数人で依頼する場合は、連絡先を一本化し、変更の締め切りを明確にしておくとスムーズです。名札の並びや表記を直す作業も短時間で済み、会場への負担を減らせます。また、写真で配置を残しておけば後日の精算や報告にも役立ちます。
供花辞退の案内があれば、柔軟に代替の方法へ切り替えましょう。独断は避けて会場や葬儀社に確認を入れることで、関係者全員が安心して準備を進められます。
供花を準備するときの心構え

お葬式に供花を贈るとき、多くの人が迷うのは「どんな花を選べばよいか」よりも「どう準備を進めればよいか」という点です。大切なのは会場の規格や喪家の方針に沿って進めることであり、費用や規模を競う必要はありません。
手配の際は、まず供花を受け付けているかを確認し、仕様や名札の内容を早めに決めておきましょう。複数人で依頼する場合は代表者を決めて情報を一本化し、供花辞退の案内があるときは弔電や後日の弔問に切り替えると、遺族への負担を減らせます。
供花は「贈る側の配慮」が伝わるものです。手順を理解し、落ち着いて一つひとつ確認していけば、安心して準備を進められます。迷った場合は独断せず葬儀社や会場に相談することで、心のこもった花を届けられるでしょう。