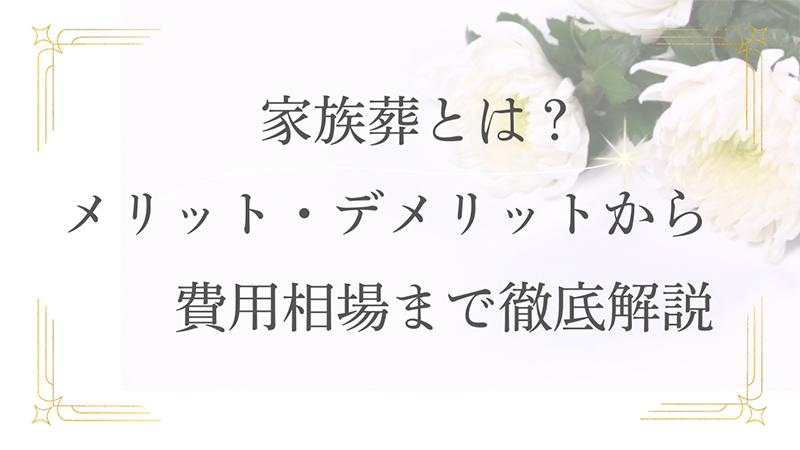近年、従来の大規模な葬儀ではなく家族葬を選ぶご家庭が増えています。家族葬は基本的に家族やごく親しい方だけで執り行う小規模な葬儀のことで、形式ばらずにゆったりとお別れできる点が注目されています。
本記事では、家族葬の定義や流れ、メリット・デメリット、費用相場、参列者の範囲や連絡の仕方、さらに具体的なプラン例として小さなお葬式社の「小さな家族葬」プランについてわかりやすく解説します。
目次
家族葬とは何か(定義と一般的な流れ)

家族葬(かぞくそう)とは、故人の家族やごく親しい人だけを中心に故人をお見送りするお葬式の総称です。明確な定義や参列範囲に決まりはありませんが、一般的に会社関係者やご近所の方などへの大々的な弔問案内は行わず、限られた身内だけで執り行う葬儀を指します。
必要な手順や式の進行自体は通常の葬儀(一般葬)とほぼ同じで、仏式であれば通夜→翌日の葬儀・告別式→火葬という流れになります。ただし、家族葬では弔電の披露や弔辞など形式的な部分を簡略化することも多く、よりアットホームな雰囲気で進む傾向があります。
一般的な家族葬の流れを簡単にまとめると次のようになります。
このように、基本的な葬儀の流れは一般葬と同じですが、参列者を限定して故人とのお別れに専念できる点が特徴です。形式にとらわれず、リビングのような落ち着いた雰囲気で故人を送りたいというニーズに応える葬儀スタイルといえます。
家族葬のメリット

家族葬には、遺族や故人にとって嬉しい利点がいくつかあります。主なメリットを見てみましょう。
ゆっくりとお別れの時間が取れる
参列者が少人数のため、遺族は大勢の弔問客への対応に追われずに済みます。その分、故人とのお別れに集中でき、ゆったりと最後の時間を過ごせます。親しい人たちと故人の思い出話をしたり、心静かに見送りの時間を共有できるでしょう。
アットホームな雰囲気
気心の知れた身内や親しい友人だけで送るため、緊張せずリラックスした雰囲気の中で葬儀を進められます。形式張った儀礼にとらわれず、故人や遺族の想いを反映した温かな式にしやすいこともメリットです。
例えば、故人が好きだった音楽を流したり、ゆっくり時間をかけてお花を手向けたりといった演出も取り入れやすくなります。
遺族の心身の負担軽減
一般葬では多くの参列者への気配りや準備で遺族の負担が大きくなりがちですが、家族葬ならその負担が軽減されます。身近な方中心なので気疲れしにくく、葬儀後の精神的な疲労も少なくて済むでしょう。
費用を抑えやすい
規模が小さい分、葬儀費用が比較的安くなる傾向があります。
全国調査によると家族葬の平均費用は約105.7万円で、一般葬(約161.3万円)より50万円以上抑えられています。式場を小規模な施設で済ませたり、料理や返礼品の数を減らせることが主な理由です。経済的な負担が軽くなる点は、大きなメリットでしょう。こうした背景から、家族葬は近年主流の選択肢の一つになりつつあります。
高齢者の葬儀では、交友関係の縮小や参列者自身の高齢化といった背景から、結果的に家族葬というかたちをとるケースも多く見られます。遺族に寄り添い、故人との別れの時間をゆっくりと過ごせる方法としても評価されています。
家族葬のデメリット

一方で、家族葬には注意すべきデメリットも存在します。あらかじめ理解しておきたいポイントを挙げます。
香典が少なくなりがちな分、費用負担に注意が必要
家族葬は参列者が限られるため、香典(弔慰金)をいただく人数も少なくなります。
葬儀費用は香典によって一部が補われることも多いため、結果的にご遺族の自己負担が増える傾向があります。そのため、「料理や会場費は抑えられても、香典が少なく、結果的に一般葬とあまり変わらない負担になった」というケースもありえます。
費用面では、必ずしも負担が軽くなるとは限らない点に注意が必要です。
後から弔問対応が発生する
葬儀に呼ばなかった方々が、故人の訃報を後で知って自宅に弔問に訪れる場合があります。突然の訪問に対応するため自宅の片付けやお茶の用意に追われたり、香典をいただいた場合には香典返し(お礼の品)を個別に準備しなければならず、手間がかかることも少なくありません。
家族葬後も想定外の対応に追われ、結果的に負担が増える可能性がある点はデメリットと言えるでしょう。
周囲から理解を得にくい場合がある
地域の慣習や故人・遺族の立場によっては、家族葬という形を親族や知人が受け入れてくれない場合もあります。
「どうして参列させてくれなかったのか」「みんなでお別れしたかったのに」等、不満や寂しさの声が出てしまい、遺族との関係に影響することも考えられます。
「家族だけで葬儀を済ませるなんて故人が粗末に扱われている」といった捉え方をされるケースもあり、不義理と受け取られないよう配慮が必要です。
参列できなかった人への対応
家族葬を選択すると、会社関係やご近所、故人の友人など多くの方が葬儀に参列できません。その場合、後日お詫びとお知らせをする必要があります。訃報を知らなかった方々から問い合わせや弔意をいただいた際にも丁寧に対応しなければならず、精神的負担を感じる場合もあります。
このように、家族葬には経済面や対人関係で生じうるデメリットもあります。ただし事前に十分な説明や連絡を行うことで、これらのリスクはかなり軽減できます。次の章では「誰を呼ぶか」「誰にどう知らせるか」について詳しく見ていきましょう。
家族葬では誰を呼ぶべきか

家族葬に参列してもらう範囲はご遺族の判断に委ねられており、明確な決まりはありません。
「本当に家族だけ」で行うこともあれば、ご親戚や故人と親しかった友人が加わる場合もあります。一般的には、配偶者・子供・孫・兄弟姉妹などの近親者を中心に、故人と特に縁の深かった人たちに声をかけるケースが多いです。
逆に、会社の同僚や町内の知り合いなど広範囲の人々には基本的に声をかけません。あくまで「故人を送りたい」と家族が感じる身近な方だけに参列をお願いするイメージです。
ただし注意したいのは、「誰も彼もお断りで家族だけ」にこだわりすぎるあまり、本来声をかけるべき相手まで外してしまうことです。大切なのは故人にとってふさわしいお別れの形かどうかであり、無理な線引きをすると後々トラブルになる可能性があります。たとえば、生前特に親しかった従兄弟や親友なのに「家族じゃないから」と伝えずにいると、後で「なぜ教えてくれなかったのか」と悲しまれるかもしれません。
参列者の範囲を決めるポイントは、以下のとおりです。
-
近親者
家族葬では、血縁の近い親族を中心に参列していただくのが一般的です。特に故人と生前深く関わりのあったご親族には、家族葬であっても声をかける方が自然でしょう。 -
親しい友人・知人
血の繋がりはなくても、家族同然にお付き合いのあった友人や恩人がいれば、家族葬にお招きしても問題ありません。「家族葬=家族のみ」でなければいけないわけではないので、柔軟に判断してください。 -
呼ばない範囲
会社関係者や近所の方、趣味のサークル仲間など、基本的には公的な繋がりの方々には参列をご遠慮いただくことが多いです。「近親者のみで執り行います」という一文でお知らせし、弔問は辞退する旨を伝えます。相手側もその場合は遠慮してくださるのが一般的です。
家族葬の参列範囲に正解はありませんが、「誰に来てもらえたら故人が喜ぶか」「後々失礼にならないか」を軸に検討しましょう。不義理とならない範囲で、故人と関係が深かった方には事前に事情を説明しておくと安心です。
家族葬で知らせるべき相手と知らせ方

家族葬では参列者を限定するため、訃報(死亡の知らせ)を誰にどう伝えるかにも工夫が必要です。全員に一律で「亡くなりました」と連絡する必要はありませんが、関係性によって適切な伝え方を考えておきましょう。
以下に、主要な相手別の連絡ポイントをまとめます。
親族への連絡
近親者にはできるだけ早く訃報を伝えます。参列をお願いする親族には日程や場所も連絡し、それ以外の親族には「○月○日に○○(故人)が亡くなりました。葬儀は家族のみで執り行います」という形で、まずは死亡の事実だけ知らせるケースもあります。
特に高齢の親戚などは後日知るとショックを受けることもあるため、家族葬にする旨を含め事前に電話で伝えると親切です。「家族葬で行いますのでご弔問等はご遠慮ください」といった断りを入れておくと良いでしょう。
連絡手段は電話が基本ですが、遠方で深夜の場合はメールやSNSで一報を入れ、後で改めて電話する配慮も大切です。
勤務先(会社)への連絡
故人が現役で勤務していた場合も、ご家族が勤め先を休む場合も、会社への連絡は必須です。家族葬であっても「〇〇(故人)が亡くなった」事実と葬儀は近親者のみで行う旨を会社に報告します。「香典や弔電、供花はご辞退申し上げます」など会社側の対応についても伝えておくとスムーズです。
連絡先は直属の上司または人事部が一般的で、まずは電話で簡潔に伝え、その後必要であればメールなどで詳細を送ります。会社から弔慰金が出たり休暇手続きがあるため、家族葬だからといって会社連絡を省略しないようにしましょう。
友人・知人への連絡
故人の親しい友人やご近所の親しい方で、今回参列をご遠慮いただく方々には、後日改めて訃報を通知する方法が一般的です。「○○が○月○日に永眠いたしました。○○の意向により葬儀は近親者にて相済ませました」等の文面で、葬儀を執り行った旨と感謝を伝える通知状(挨拶状)を郵送するケースが多いです。
親しい友人であれば電話で直接伝えても良いですが、その際も「家族葬で見送りました。お気持ちだけありがたく頂戴します」とお伝えすると先方も安心します。生前に関係の深かった方には知らせが全くないと心配をかけるため、タイミングを見てきちんとお知らせすることが大切です。
このように、家族葬では「参列をお願いする人」と「参列しないが知らせる人」を分けて整理して連絡すると良いでしょう。訃報連絡のマナーに不安があるときは、担当の葬儀社に相談すれば文例や注意点を教えてもらえます。事前の連絡と気配り次第で、「なぜ教えてくれなかったの!」と責められるリスクも減らせます。家族葬を円滑に進めるためにも、関係者への周知は丁寧に行いましょう。
家族葬に向いている人・ケース

家族葬はすべてのケースに万能ではありませんが、以下のような希望や状況がある方には特に適した葬儀スタイルと言えます。
身内やごく近しい人だけで故人を見送りたい
「たくさんの人ではなく、本当に親しかった人たちだけで穏やかにお別れしたい」というご希望がある場合、家族葬は最適です。アットホームな空気の中、気兼ねなく故人との最期の時間を共有できます。
参列者が少ない見込み
故人が高齢で友人知人が少なかった場合や、親族が少ないご家庭では、大きな葬儀より家族葬の方が適切でしょう。無理に一般葬の形を取ろうとして参列者が集まらず寂しい式になるより、初めから家族葬にしておけば規模に合った温かい式にできます。
小規模で費用を抑えた葬儀を考えている方
経済的な事情や「葬儀は質素で良い」という故人の遺志がある場合、家族葬なら比較的費用を抑えて葬儀を行うことができます。一般葬のような会葬礼品や大規模会場費が不要なので、必要最低限かつ心のこもった式が実現できます。
ただし前述のとおり香典収入も少なくなるため、費用面のプランニングは事前によく検討しましょう。
故人の遺志で小さく送りたい
故人が生前「身内だけで送ってほしい」「葬式は簡単でいい」と希望していたケースにも家族葬が向いています。遺族もその遺志を尊重することで、心残りの少ないお見送りができるでしょう。
形式にとらわれず心を込めた葬儀をしたい
できるだけ自由な発想で、故人らしさを表現した葬儀にしたい方にも家族葬はマッチします。少人数だからこそ柔軟に演出を工夫でき、「小さいけれど温かな葬儀」にしたいという想いを形にしやすい傾向があります。
以上のケースに当てはまる方は、家族葬を選択肢の一つとして検討してみるとよいでしょう。反対に、「交友関係が広く多くの方に見送ってほしい」「地域の習わし上、家族葬は難しい」という場合は一般葬の方が適しているかもしれません。
大切なのは故人と遺族の気持ちを第一に考えることです。家族葬は「こうしなければいけない」が少ない柔軟な葬儀なので、状況に応じてベストな形を葬儀社と相談しながら決めていきましょう。
小さなお葬式の「小さな家族葬」プランの詳細

家族葬を具体的にイメージするために、全国対応の葬儀社である「小さなお葬式」が提供しているセットプラン「小さな家族葬」をご紹介します。これは通夜と告別式を少人数で執り行う家族葬向けのパッケージプランで、必要なサービスが一式含まれているのが特徴です。
◆ 基本プランの概要
「小さな家族葬」は通夜式+告別式の2日間の葬儀プランで、全国各地の提携式場で利用できます。料金は通常550,000円ですが、資料請求経由の申し込みで5万円割引が適用され、495,000円になります。
この料金には、葬儀に必要な基本的なサービスがほぼすべて含まれており、追加費用が発生しにくい明瞭会計のセットプランです。
※火葬料金はプランに含まれず別途必要です。料金は地域によって異なります。
◆ プランに含まれる主な内容
-
遺体搬送・安置
病院や自宅から安置場所までの搬送(寝台車・50kmまで)、安置施設でのご遺体お預かり最大4日間、ドライアイス(4日分)によるご遺体保全などが含まれます。自宅で安置できない場合でも、葬儀まで最大4日間は提携施設でご遺体をお預かり可能なので安心です。 -
納棺・祭壇等の準備
お棺一式(棺本体・棺用布団)、仏衣(故人に着せる白装束)、枕飾りセット(ご安置中に飾る簡易祭壇)、線香・ろうそく等の祭壇用消耗品がプラン内に含まれています。専門スタッフによる納棺の施行も料金内で行い、オプションで湯灌(ゆかん)やメイクを追加することも可能です。式場には生花祭壇が用意され、美しいお花で故人を飾って送り出せます(祭壇のグレードアップも希望に応じて選択可)。 -
式場・運営費用
通夜・告別式を行う式場使用料(最大10万円)がプラン料金に含まれています。また式当日の司会進行スタッフや運営スタッフの人件費も含まれており、受付セット(受付台や芳名帳、香典帳など備品一式)、焼香に必要な用具一式なども完備されています。遺族控室(親族控室)も利用でき、通夜~告別式の間ゆったり過ごせる環境が整っています。 -
付帯サービス
遺影写真の準備(四つ切サイズ額入り写真+手元用写真のセット)、会葬御礼状(お礼の挨拶状)最大60枚、火葬場への搬送(寝台車・50kmまで)、火葬手続き代行(火葬許可証の申請代行)、収骨容器(骨壺・骨箱)、そして後飾り祭壇(白木位牌とご遺骨を自宅安置するための飾り一式)まで含まれています。葬儀後の49日法要まで、遺骨を安置しておくための台や位牌もセットになっているのは嬉しいポイントです。
このように「小さな家族葬」プランは、搬送から火葬後のフォローまで必要なものが一通りパッケージ化されています。
追加費用が発生するのは、式場利用料がプランの上限(10万円)を超える場合や、通夜の食事・返礼品の手配、お布施(お寺への謝礼)、オプションサービスを希望する場合などです。一部の式場ではプラン外の費用がかかることもありますが、契約前に見積もりで丁寧な説明があるため、安心して検討できます。
小さなお葬式社では、明確な見積もりと良心的な価格設定を掲げているため、予想以上に費用がかかってしまうといった心配を減らすことができます。
資料請求でじっくり比較検討を
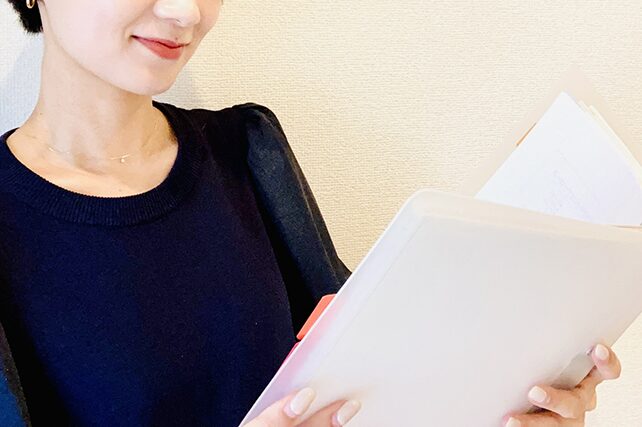
家族葬を検討する際は、複数の葬儀社のプランや費用を比較したり、詳しい資料を取り寄せて検討することが大切です。
小さなお葬式社では無料の資料請求を受け付けており、ウェブから1分程度で簡単に申し込めます。資料請求をするとすべての葬儀プランが5万円割引になる特典があり、「喪主が必ず読む本」というハンドブックも無料プレゼントされます。家族葬プランについて具体的な内容を知りたい方や、費用の詳細が気になる方は、まずはパンフレットを取り寄せてみることをおすすめします。
資料には各プランの価格・サービス内容はもちろん、葬儀の準備やマナーに関する情報も載っているため、手元にあると安心です。「無料」かつ「自宅にいながら取り寄せ可能」なので、気軽に活用してみてください。
特に「小さなお葬式」のように全国対応の大手葬儀社なら、地域ごとの費用相場や式場情報も網羅されています。資料請求後に営業電話がしつこく来る心配もなく、じっくり比較検討できるので安心です。


まとめ

家族葬は故人とのお別れを大切にできる反面、初めてだと不安に感じることもあるかもしれません。本記事で紹介したようにメリット・デメリットを踏まえながら、信頼できる葬儀社の情報を集めて準備しておくことで、落ち着いて対応しやすくなるでしょう。
資料請求などを活用して、納得のいく葬儀の形を選びましょう。葬儀社への事前相談は無料ですので、わからないことがあれば遠慮なく問い合わせてみてください。