突然の悲報に動揺している状況でも、関係者へできるだけ早く正確に連絡しなければなりません。電話・メール・SNSといった連絡手段ごとの適切な使い分けや、案内状に記載する宗教形式や服装の案内など、知っておくべきマナーがあります。
本記事では、訃報連絡を中心に、こうした連絡手段ごとの注意点や文例を具体的に紹介します。
重要な知らせを伝える基本マナー

まずは、訃報連絡を含む重要なお知らせを伝える際の基本的なマナーについて押さえましょう。誰にいつ連絡するか、どのような手段を選ぶかといった判断が必要です。悲しみの中でも相手への配慮を忘れず、迅速かつ確実に情報を届けることが大切です。
本章では、連絡先の範囲や順序、連絡手段の概要など基本的なポイントを解説します。
迅速で丁寧な連絡の心構え
訃報の連絡はできる限り早く、そして確実に伝える必要があります。特に親しい家族や親族には、遺体の安置が済み次第すぐに電話で知らせるのが望ましいでしょう。
深夜や早朝の場合は無理に電話せず、朝になってから連絡するなど相手の状況にも配慮します。知らせる際には動揺していても冷静で丁寧な言葉遣いを心がけ、不幸を連想させる「忌み言葉」は避けます。
亡くなった日時や通夜・葬儀の日程など、伝える内容を事前にメモして手元に置いておくと言い間違いを防げるでしょう。大事なお知らせだからこそ、正確さと礼儀を忘れない心構えが必要です。
連絡すべき相手の範囲と順序
誰にどこまで連絡するかは状況によって異なりますが、基本的には「葬儀に参列してほしい相手」を目安に考えます。
家族・親族は最優先で、次に故人と親しかった友人知人、勤務先関係者やご近所の方などに順次知らせます。親族で三親等程度までが一般的な連絡範囲とされますが、故人との関係性が深かった方には親族以外でも早めに伝えるようにしましょう。また、遠方に住む方には移動時間を考慮して早めの連絡が望ましいです。
ただし、家族葬など近親者のみで葬儀を執り行う場合には、他の方への訃報連絡は葬儀後でも差し支えありません。その場合は後日改めて手紙やメールで報告し、連絡が遅れた非礼を詫びるのがマナーです。
 初めてでも迷わない!家族葬の流れと費用 丸わかりガイド
初めてでも迷わない!家族葬の流れと費用 丸わかりガイド
また、故人が住んでいた地域や勤めていた会社など、広い範囲や大勢に訃報を知らせる手段として「死亡通知」を出す方法もあります。
 訃報を知らせる時や家族葬の事後報告に 死亡通知状の書き方
訃報を知らせる時や家族葬の事後報告に 死亡通知状の書き方
いずれの場合も、相手の立場に合わせて失礼のないタイミングで伝えることが大切です。
連絡手段の選択と基本的な考え方
訃報を伝える手段としては、電話が最も直接的で確実な方法とされています。特に年配の方には「大事な連絡は電話で」という考えの方も多く、電話連絡が無難でしょう。
一方で、現代ではメールやLINEなどのSNSで通知するケースも増えています。
メールやSNSはあくまで略式の手段であり、親しい友人同士などでは利用できますが、目上の方には失礼と感じられる可能性があります。相手の年齢や普段の連絡手段を踏まえて、電話と書面、メールやSNSの使い分けを検討しましょう。
また、一度に多人数へ知らせる必要がある場合、電話だけでなくメール等も併用しなければならない場合がありますが、その際も配慮が必要です。相手に確実に伝わることと礼を失しないことを両立させ、適切な手段を選択することが重要です。
重要なお知らせを伝える際の基本として、迅速かつ丁寧な連絡と相手への配慮が何より大切です。まずは最も関係の深い方から順に電話で連絡し、状況に応じてメールやSNSも活用しますが、どの手段でも礼儀正しい言葉遣いで確実に用件を伝えます。
また、誰にいつ連絡するかをあらかじめ家族で話し合い、連絡先リストを用意しておくと万一の際にも落ち着いて対応できるでしょう。相手の立場や気持ちに思いを致し、「伝えるべきことを漏れなく正しく伝える」という基本を踏まえて連絡することが、マナーある対応につながります。
電話で訃報を伝える方法と文例

訃報を伝える手段として最も一般的なのは電話です。直接肉声で伝えることで、相手に確実に知らせることができます。しかし突然の電話になるため、電話口での切り出し方や伝える内容には細心の注意が必要です。
本章では、電話連絡をするときのポイントと、故人との関係性ごとの伝え方の例をご紹介します。
電話連絡のポイント
電話で訃報を伝える際は、冒頭で名乗りと非礼のお詫びを述べ、すぐに本題を簡潔に伝えます。突然の連絡で相手を驚かせてしまうため、「突然のお電話で申し訳ありません」など一言添えると良いでしょう。また、故人との関係や自分の立場(「〇〇の長男の△△です」等)を伝えてから、亡くなった事実と日付を知らせます。
通夜や葬儀の日程・場所が決まっている場合は併せて案内し、未定の場合は「日程が決まり次第改めて連絡する」旨を伝えます。電話を切る前に、相手に自分の携帯番号などを伝えておく配慮も忘れないようにしましょう。
電話口でのお知らせは辛いものですが、あらかじめ伝える内容を整理しておけば落ち着いて対応できるでしょう。
もし葬儀全体の準備に不安がある場合は、「小さなお葬式」のように、プランが明確でサポート体制が整った葬儀サービスを活用するのも一つの方法です。家族葬や火葬式など、多様なニーズに応じたプランが用意されており、費用も事前に確認できるので安心です。
電話連絡の文例
次に、故人と相手との関係性ごとの電話連絡の文例を紹介します。必要事項を漏れなく伝えられるように、事前にメモなどに書いて準備しておくとよいでしょう。
親族に電話で知らせる場合
「〇〇の長男の△△です。かねてから入院中だった母が、今朝方亡くなりました。取り急ぎ、お知らせのためお電話いたしました。
通夜・葬儀の日時と場所は、決まり次第追ってご連絡いたします。遺体は〇〇斎場に安置しております。ご対面いただける場合は、私の携帯電話にご連絡ください。番号は〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇です。」
故人の友人・知人に電話で知らせる場合
「突然のお電話、申し訳ありません。私、〇〇の長男の△△と申します。以前より入院していた父〇〇が、〇月〇日の深夜に亡くなりました。生前は大変お世話になりました。
通夜は、明日〇月〇日〇時より、告別式は明後日の〇月〇日○時より、〇〇斎場にて〇〇式で行います。喪主は私△△が務めます。ご連絡いただく際には、私の携帯にお願いいたします。電話番号は〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇です。」
故人の勤務先へ電話で知らせる場合
「お世話になっております。〇〇部の〇〇の妻、△△と申します。かねてから入院していた夫が、〇月〇日早朝に亡くなりました。生前は大変お世話になりました。
通夜は〇〇斎場で明日〇月〇日〇時より、告別式は明後日〇月〇日〇時より同斎場にて〇〇式で執り行います。喪主は私△△が務めます。
恐縮ですが、貴社内の関係者の皆さまにこちらの訃報をお伝えいただけますでしょうか。お問い合わせは私の携帯までお願いいたします。電話番号は〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇です。」
電話で訃報を伝える際は、短時間で要点を漏れなく伝えることを心掛けます。名乗りとお詫びから始め、誰がいつ亡くなったのかを正確に伝え、通夜や葬儀の日程・場所・宗教形式、喪主の情報など必要事項を簡潔に案内します。相手が動揺して聞き漏らす可能性もあるため、可能なら最後に今後の連絡先を伝えてフォローしましょう。
親しい間柄か仕事上の関係かによって語り口は多少変わりますが、いずれの場合も礼儀正しく丁寧な話し方を心掛けることが大切です。
メールやSNSで連絡する場合のマナー

訃報をメールやSNSで伝えるケースも近年増えてきました。遠方に住んでいる方や、日頃からオンラインでやり取りしている相手には、これらの手段が迅速で便利な場合もあります。ただし、メール・SNSは略式の連絡手段であるため、使う際には慎重な判断とマナーへの配慮が必要です。
本章では、メールとSNSのどちらを使うか判断する基準と、SNSで一斉に連絡する際の注意点について解説します。
メールやSNSを選ぶ判断基準
メールやSNSでの連絡がふさわしいかどうかは、相手との関係性や状況に応じて判断します。たとえば上司や恩師などには略式の連絡は控え、可能な限り電話や直接会って伝えるのが望ましいでしょう。一方で、遠方の友人に迅速に知らせたい場合はメールやSNSも選択肢になります。
大切なのは相手に確実に情報が伝わることと、相手の気持ちを害さないことの両立です。「失礼にならないか」「きちんと受け取ってもらえるか」を基準に手段を選び、必要に応じて後日正式に手紙や電話でお知らせを補足することも心掛けましょう。
以下は、メール・SNSでの連絡で良いかの判断基準です。
相手との関係性
目上の方や年配の方にはメール・SNSでの訃報連絡は失礼にあたる場合があります。できるだけ電話や対面で丁寧に伝えた方が良いでしょう。一方、普段から親しくしている友人や同僚であればメールやSNSでも差し支えありません。
関係の深さや立場に応じて手段を選びましょう。
相手の年齢や通信手段の習慣
相手が日常的にメールをチェックしているか、LINEなどのSNSでいつも連絡を取り合っている関係かどうかも判断材料です。高齢の方やビジネス関係者はメールを好む傾向がありますが、若い世代や親しい仲間内ではSNSのほうが早く確実に伝わることもあります。
連絡の緊急度・タイミング
深夜や早朝に急ぎ知らせたい場合、電話よりもメールやSNSで送信し相手の負担にならない時間に確認してもらう方法もあります。すぐに知らせる必要はあるが電話が憚られる時間帯には、いったんメール等で簡易に連絡し、後で改めて電話する選択肢も検討します。
連絡先情報の有無
相手のメールアドレスを知らない場合やSNSでしか繋がっていない場合は、その手段を使うしかありません。逆に、メールアドレスしか分からなければメールで連絡するなど、入手している連絡先によって手段を決める実務的判断も必要です。
SNS一斉送信時の注意点

SNSは情報拡散力が強いため、必要以上の範囲に広がらないよう設定を確認します。受け取った側の心情にも配慮し、できるだけ丁寧な文面で送ることが大切です。
やむを得ず一斉連絡する場合は形式的になりがちなため、後ほど個別にお礼や説明を伝えるなどのフォローも心掛けましょう。略式の連絡であっても真心が伝わるよう、慎重な対応を心がけてください。
SNSで一度に多くの人へ訃報を伝える際は、以下の点に十分注意する必要があります。
公開範囲に注意する
SNS上に訃報や葬儀の詳細を公に投稿することは避けましょう。 設定によっては意図しない相手にまで情報が拡散する恐れがあります。葬儀の日程など個人情報が含まれる内容は、不特定多数が閲覧できる場に載せるべきではありません。
送信先の選定と誤送信防止
一度に多くの人に連絡する際も、必要な相手のみに限定し、送信先の選択は慎重に行います。SNSのグループ機能を使う場合はメンバーをよく確認し、招待される側のプライバシーにも配慮します。
メールであればBCC機能を利用して受信者同士のアドレスが見えないようにするなど、誤送信や情報漏洩を防ぐ工夫が必要です。
文面は丁寧かつ簡潔に
SNSであっても訃報連絡のメッセージでは絵文字やスタンプ、不要な飾り表現は控え、改まった文章表現を用います。
長文になりすぎないよう簡潔にまとめつつ、敬意の伝わる丁寧な言葉遣いを心掛けましょう。「お知らせまで」といった結びの言葉も添えると丁寧です。
可能なら個別フォローも
グループ送信や一斉連絡で済ませた場合でも、親しい間柄の方やお世話になった方には後日個別に連絡や挨拶をすると丁寧です。
一斉通知のみでは事務的になりがちですので、「まとめてのご連絡となり失礼いたします」など断りを入れるか、補足のフォローアップを検討しましょう。
メールやSNSによる訃報連絡は迅速さと手軽さが利点ですが、その分マナー面での注意が必要です。手段を選ぶ際は相手との関係性や状況をよく考慮し、略式になりすぎないよう配慮します。特にSNSで多人数に連絡する際は公開範囲や文面の丁寧さに気を配り、受け手が不快に感じない工夫が求められます。
どのような手段であれ、「相手に敬意を払い、確実に情報を届ける」姿勢を忘れないことが重要です。メールやSNSを上手に活用しつつ、必要に応じて電話や直接の連絡も織り交ぜることで、円滑かつ失礼のない訃報連絡を行いましょう。
案内状での宗教形式・服装案内の書き分け

訃報を受けた方々には、後日あらためて案内状や通知メールで通夜・葬儀の詳細をお知らせすることがあります。その際、葬儀の宗教形式(仏式・神式・キリスト教式・無宗教など)や服装に関する案内文を適切に書き分ける必要があります。
式の形式によって参列者の心構えも異なりますし、服装指定の有無は大切な情報です。本章では、宗教形式と服装案内の書き方についてポイントをまとめます。
仏式の場合
「通夜・告別式は〇月〇日〇時より〇〇斎場にて仏式にて執り行います。」といった形で、仏式で行う旨を明記します。服装については特別な但し書きがない限り喪服(正喪服)で参列するのが一般的なので、案内状に服装指定は記載しないのが通常です。
神式の場合
神社式場や斎場にて神式で行う旨を記載します。神式も仏式同様に正式な喪服着用が基本です。仏式との違いは儀式内容(玉串奉奠など)ですが、案内状では「神式で執り行います」と触れる程度で、服装案内は特に記載しないことが多いです。なお、参列者は黒の喪服を着用します。
キリスト教式の場合
教会や式場にてキリスト教式の葬儀を執り行う旨を記します。カトリックかプロテスタントかによって呼称は異なりますが、案内状ではシンプルに「キリスト教式」で差し支えありません。服装はブラックスーツなどの黒を基調とした平服で参列するのが一般的です。必要に応じて「平服でお越しください」と記す場合もありますが、教会葬では特に指定しないケースもあります。
無宗教形式の場合
無宗教形式のお別れの会や社葬などでは、その旨を明記します。例えば「〇月〇日〇時より〇〇会館にて無宗教形式のお別れの会を執り行います。」と記載します。
また多くの場合、案内状に「平服にてお越しください」と添えられます。この「平服」とは日常の普段着という意味ではなく、“喪服ほど格式ばらない服装”を指します。男性なら濃紺やグレーのダークスーツ、女性なら地味目のスーツやワンピースなど、過度に喪服然としない服装で構いませんという趣旨です。
 お別れ会・偲ぶ会の運営はどうやるの?当日までの準備、費用、流れ
お別れ会・偲ぶ会の運営はどうやるの?当日までの準備、費用、流れ
案内状や通知文では式の宗教形式を明示し、必要に応じて服装についての案内を加えましょう。仏式や神式のように、慣習的に喪服着用が当然とされる場合にはあえて服装には触れないのが一般的です。一方、無宗教の場やカジュアルなお別れの会では「平服でお越しください」と明記し、参列者の負担を軽くします。
この“平服”という表現は「格式張った正装ではなくて構いません」という配慮であり、決して普段着で良いという意味ではない点には注意が必要です。宗教形式・服装の案内を丁寧に書くことで、受け取った方にも適切な心構えを持って参列してもらえるでしょう。
おわりに
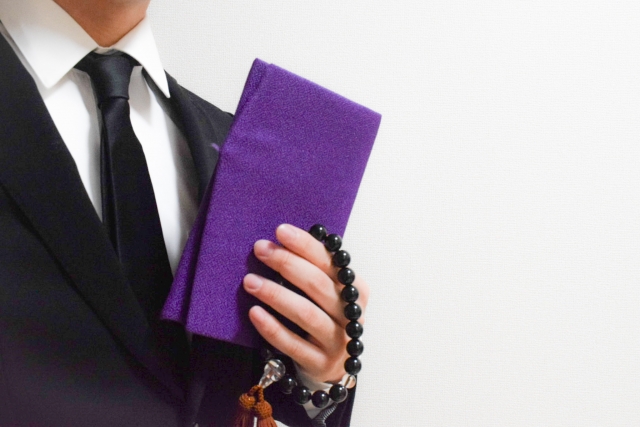
訃報の連絡は誰しも戸惑うものですが、本記事で述べたポイントを押さえておけば、いざという時にも落ち着いて対応できるでしょう。電話・メール・SNSといった手段を状況に応じて使い分け、相手への思いやりを持って伝えることが何より大切です。
形式的なマナーに気を配ることは、ひいては故人やご遺族の気持ちを尊重することにもつながります。また、案内状や通知の文面では宗教形式や服装など必要な情報を正確に伝え、受け取る方に親切な案内を心掛けましょう。
悲しみの中でも丁寧で確実な連絡を行うことで、周囲の方々に対する感謝の気持ちと礼節を示すことができます。本記事の内容が、皆様のコミュニケーションのお役に立てば幸いです。







