葬儀に関するよくある質問をまとめてみました。疑問から逆引きしてより詳しい記事へ行けます。
葬儀マナーに関するFAQ
また、殺生を連想させる毛皮のマフラーやコートなどはNGです。
女性の場合、化粧は派手すぎない自然なもので、素足はNGなので黒のストッキングを履くようにします。
喪服などに限らず光沢のあるものは弔事では避けるようにします。
アクセサリーも同様ですが、涙の象徴とされるパールだけは例外です。
パールを身に付ける場合は一連のものを使用します。
二連のものは不幸が重なることを連想させるためです。
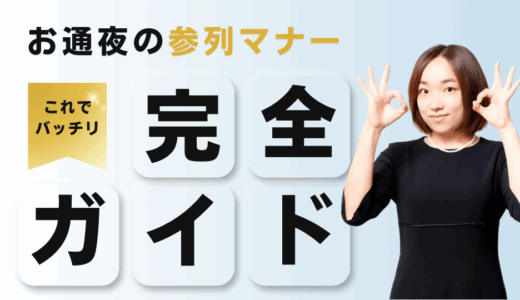 お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
 告別式の全てを教えます。告別式の流れや香典、服装や持ち物まで
告別式の全てを教えます。告別式の流れや香典、服装や持ち物まで
元々通夜は訃報を受けてから、時間がなく取り急ぎで駆けつけるものなので平服が一般的で、逆に喪服だと「死の準備をしていたようだ」ということで不適切とされていました。
しかし、現在では伝達手段や保存技術も発達して時間にも余裕があり、通夜は故人と一般会葬者の最後の別れの場の性格が強くなったため、喪服を着て行くことが一般的となったのです。
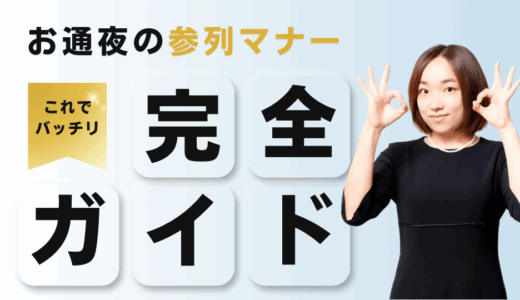 お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
- 自分の順番が来たら焼香台の前まで行き、僧侶・遺族に一礼
- 焼香台に一歩近づき、遺影に向かって一礼します。
- 抹香を親指・人差し指・中指の三本でつまみ、頭を軽く下げながら目の高さまで上げます。
- 香炉に抹香を落とします
- 3と4を1~3回行い、遺影に向かって合掌します。
- 一歩下がり、僧侶と遺族に一礼して自分の席に戻ります。
焼香の順番は故人に近い関係の順です。
また、焼香の回数などは宗派により違いがあるので、気になる方は調べてみましょう。
 知っておきたい焼香マナー | 作法・仕方・やり方、回数など
知っておきたい焼香マナー | 作法・仕方・やり方、回数など
ただ、慣習として数珠を持参する場合は自分の家の宗派のものを持つようにしましょう。
 お葬式で使う『数珠』の基礎知識:意味・マナーから選び方まで
お葬式で使う『数珠』の基礎知識:意味・マナーから選び方まで
葬儀費用に関するFAQ
葬儀社のパンフレット等で見る葬式の平均費用は大体が日本消費者協会のアンケート調査を引用しています。
しかし、「みんながどれくらい葬儀にお金をかけているのか?」という疑問に対して、費用の平均値というデータは必ずしも役に立つデータではありません。
平均所得額と同じく中央値のほうが葬儀費用の実態を知るには適していると言えます。
人口100人の集落で、90人が年収200万円だとしても、10人が年収5000万円であれば平均年収は680万円となってしまい、実態と大きくかけ離れることになる。
つまり、葬儀費用に関しても平均値は大規模な葬儀に引っ張られる形で平均値がつり上がっているです。
実際に葬儀社の人の多くは日本消費者協会のアンケート調査の平均額について実態よりもかなり高いという印象を持っているようです。
実際のところ、一般的な葬儀にかかる平均費用は120万~150万円程度と言われています。
近年は家族葬などの需要の高まりで葬儀の小規模化が進んでおり、費用も更に安くなってきています。
 葬儀費用が高いのはなぜ?内訳の具体例と全国平均、費用を抑える方法
葬儀費用が高いのはなぜ?内訳の具体例と全国平均、費用を抑える方法
お布施はあくまでも謝礼であって、サービスの対価ではありませんが、渡す側からすると以下のことを考えなければなりません。
- 読経一式(通夜・葬儀・炉前読経・初七日法要など)
- 戒名授与(戒名のランクごとに金額が変わる)
- お車代(僧侶が自身の足で来たときの交通費)
- 御膳料(僧侶が会食を辞退したときの食事代)
日本消費者協会によると寺院費用の平均値は約45万円です。もちろんこれは地域や宗派により様々で、平均なので実際より高いということもあるでしょう。
一番確実な方法は檀家の代表である檀家総代に聞いたり、住職本人に思い切って聞いてみることです。
また、葬儀社の紹介の僧侶であれば葬儀社が金額を明示してくれることが多いです。
最近では僧侶を派遣するサービスがあります。
僧侶派遣では金額が明示されていることが多く、お布施の金額に迷うこともありませんが、菩提寺がある場合は菩提寺の許可を取らなければ納骨などを断れる場合もあるので注意が必要です。
 葬儀費用が高いのはなぜ?内訳の具体例と全国平均、費用を抑える方法
葬儀費用が高いのはなぜ?内訳の具体例と全国平均、費用を抑える方法
お布施はあくまでも謝礼であって、サービスの対価ではありませんが、渡す側からすると以下のことを考えなければなりません。
- 読経一式(通夜・葬儀・炉前読経・初七日法要など)
- 戒名授与(戒名のランクごとに金額が変わる)
- お車代(僧侶が自身の足で来たときの交通費)
- 御膳料(僧侶が会食を辞退したときの食事代)
日本消費者協会によると寺院費用の平均値は約45万円です。もちろんこれは地域や宗派により様々で、平均なので実際より高いということもあるでしょう。
一番確実な方法は檀家の代表である檀家総代に聞いたり、住職本人に思い切って聞いてみることです。
また、葬儀社の紹介の僧侶であれば葬儀社が金額を明示してくれることが多いです。
最近では僧侶を派遣するサービスがあります。
僧侶派遣では金額が明示されていることが多く、お布施の金額に迷うこともありませんが、菩提寺がある場合は菩提寺の許可を取らなければ納骨などを断れる場合もあるので注意が必要です。
 葬儀費用が高いのはなぜ?内訳の具体例と全国平均、費用を抑える方法
葬儀費用が高いのはなぜ?内訳の具体例と全国平均、費用を抑える方法
これらを合計すると全国平均で約154万円程度かかっているようです。(鎌倉新書のアンケート調査)
ここにさらに墓所の管理費用や開眼法要などの寺院費用などが加わる形になります。
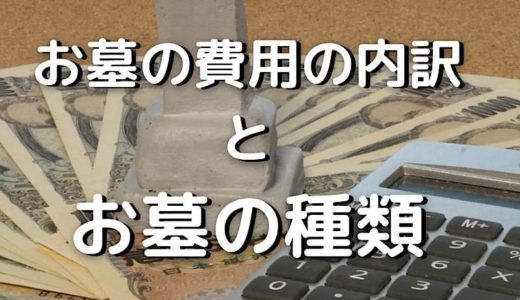 気になるお墓の費用の内訳とお墓の種類、値段と選ぶポイント!
気になるお墓の費用の内訳とお墓の種類、値段と選ぶポイント!
お通夜に関するFAQ
これは亡くなったお釈迦様を弟子達が囲み、一晩中語り合ったことから由来しています。
また、昔はドライアイスなどの保存ができなかったため、保存のための手入れや臭い消しのためのお香などを焚くために一晩中寄り添う必要もありました。
現在では、告別式に出席できない人達が最後のお別れとして通夜に参列することが普通です。
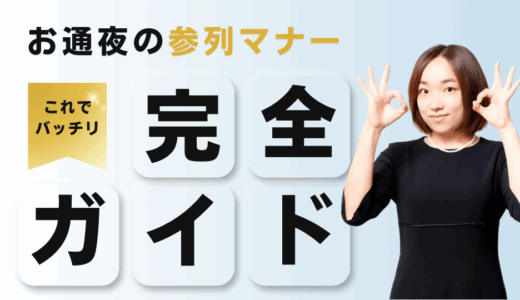 お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
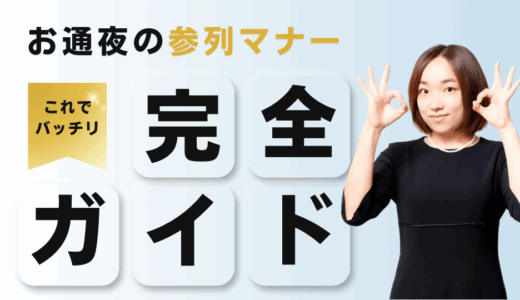 お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
しかし現在では、一般会葬者にとっての最後の別れの場という意味合いが強くなってきており、喪服を着用することが一般的となっています。
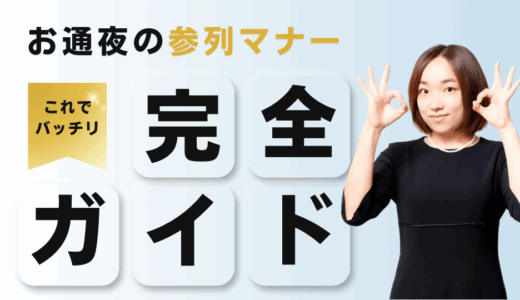 お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
また、殺生を連想させる毛皮のマフラーやコートなどはNGです。
女性の場合、化粧は派手すぎない自然なもので、素足はNGなので黒のストッキングを履くようにします。
喪服などに限らず光沢のあるものは弔事では避けるようにします。
アクセサリーも同様ですが、涙の象徴とされるパールだけは例外です。
パールを身に付ける場合は一連のものを使用します。
二連のものは不幸が重なることを連想させるためです。
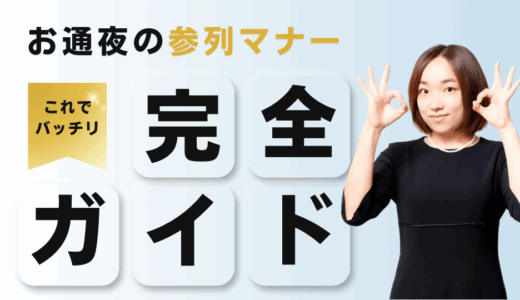 お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
 告別式の全てを教えます。告別式の流れや香典、服装や持ち物まで
告別式の全てを教えます。告別式の流れや香典、服装や持ち物まで
通夜振る舞いは故人の供養の意味合いもあるので、基本的には断らずにいただくのがマナーです。
食べられない場合でも、箸で少量を取り分けたり、飲み物を一口いただくようにしましょう。
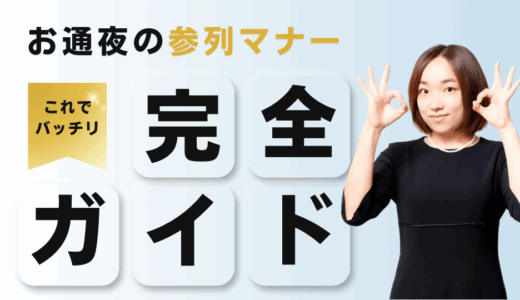 お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
葬儀・告別式に関するFAQ
また、殺生を連想させる毛皮のマフラーやコートなどはNGです。
女性の場合、化粧は派手すぎない自然なもので、素足はNGなので黒のストッキングを履くようにします。
喪服などに限らず光沢のあるものは弔事では避けるようにします。
アクセサリーも同様ですが、涙の象徴とされるパールだけは例外です。
パールを身に付ける場合は一連のものを使用します。
二連のものは不幸が重なることを連想させるためです。
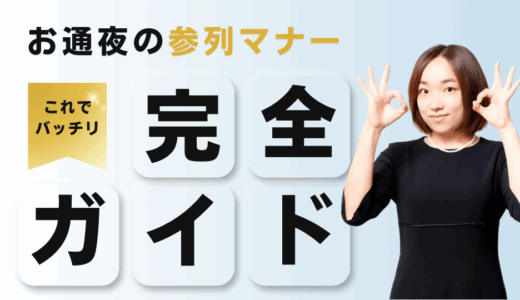 お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
 告別式の全てを教えます。告別式の流れや香典、服装や持ち物まで
告別式の全てを教えます。告別式の流れや香典、服装や持ち物まで
また、殺生を連想させる毛皮のマフラーやコートなどはNGです。
女性の場合、化粧は派手すぎない自然なもので、素足はNGなので黒のストッキングを履くようにします。
喪服などに限らず光沢のあるものは弔事では避けるようにします。
アクセサリーも同様ですが、涙の象徴とされるパールだけは例外です。
パールを身に付ける場合は一連のものを使用します。
二連のものは不幸が重なることを連想させるためです。
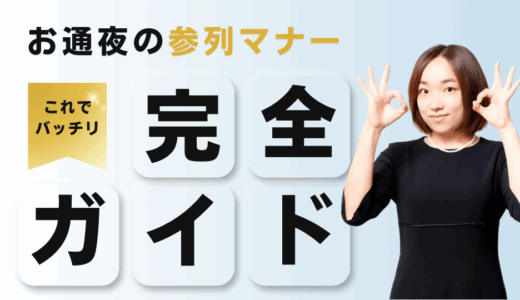 お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
 告別式の全てを教えます。告別式の流れや香典、服装や持ち物まで
告別式の全てを教えます。告別式の流れや香典、服装や持ち物まで
香典に関するFAQ
また、殺生を連想させる毛皮のマフラーやコートなどはNGです。
女性の場合、化粧は派手すぎない自然なもので、素足はNGなので黒のストッキングを履くようにします。
喪服などに限らず光沢のあるものは弔事では避けるようにします。
アクセサリーも同様ですが、涙の象徴とされるパールだけは例外です。
パールを身に付ける場合は一連のものを使用します。
二連のものは不幸が重なることを連想させるためです。
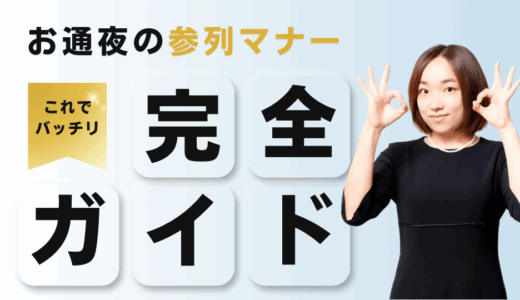 お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
お通夜マナー完全ガイド|服装・香典・挨拶・流れまで徹底解説
 告別式の全てを教えます。告別式の流れや香典、服装や持ち物まで
告別式の全てを教えます。告別式の流れや香典、服装や持ち物まで
香典はどのような場面でも香典袋に入れて渡すようにしましょう。
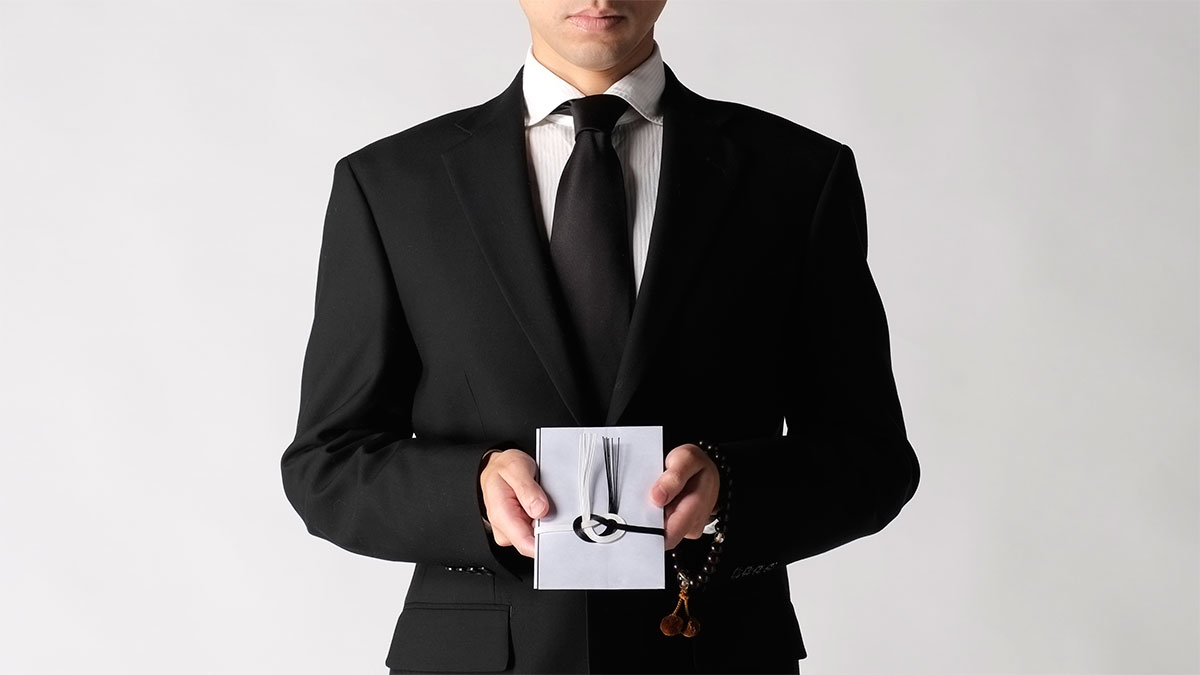 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
 弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
香典の郵送は喪主の自宅に送りますが、これは現金書留で送る場合、弔電と違って葬儀前に斎場に到達できるかどうかが不明なため、確実に届けるために喪主の自宅に送ります。
逆に弔電は、確実に葬儀に間に合わせることが重要です。
同じに見えるお悔やみでも、全く意味合いが違うので、両方送るべきなのです。
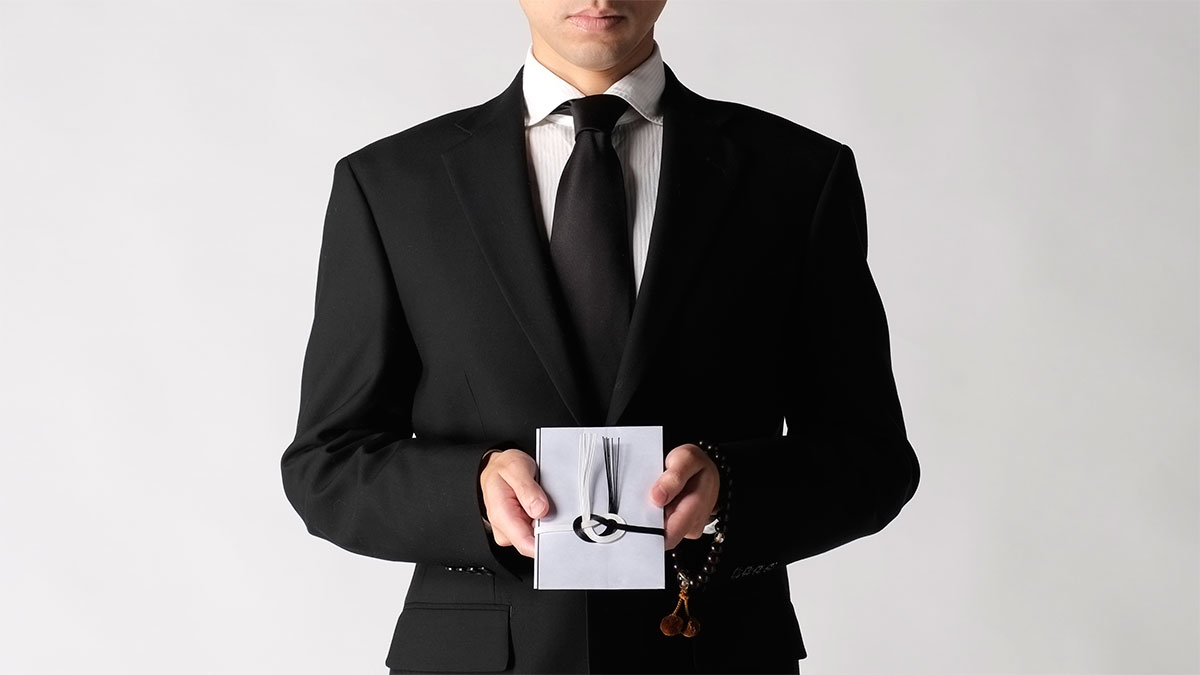 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
 弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
お葬式そのものにかかる費用は、通夜や葬儀の費用や斎場使用料、ドライアイスなどの料金など葬儀本体に必要な諸経費です。
飲食接待費は通夜振る舞いや精進落としなど、通夜や葬儀の後の会食の費用や、会葬返礼品・香典返しなどの参列者に関する費用です。
寺院費用は読経をあげる僧侶へのお布施やお車代、御膳料、戒名料など寺に支払う費用です。
 葬儀費用が高いのはなぜ?内訳の具体例と全国平均、費用を抑える方法
葬儀費用が高いのはなぜ?内訳の具体例と全国平均、費用を抑える方法
金額が明示されておらず、地域や家の考えによっても異なるため、包む金額には非常に悩むポイントです。
香典の相場のポイントは自分と故人の関係です。以下にアンケート調査の最多回答額を参考に出しておきます。
| 故人 | 最多回答額 |
|---|---|
| 祖父母 | 10,000円 |
| 親 | 100,000円 |
| 兄弟姉妹 | 50,000円 |
| おじ・おば | 10,000円 |
| 上記以外の親戚 | 10,000円 |
| 職場関係 | 5,000円 |
| 勤務先社員の家族 | 5,000円 |
| 取引先関係 | 5,000円 |
| 友人・その家族 | 5,000円 |
| 隣人・近所 | 5,000円 |
| その他 | 5,000円 |
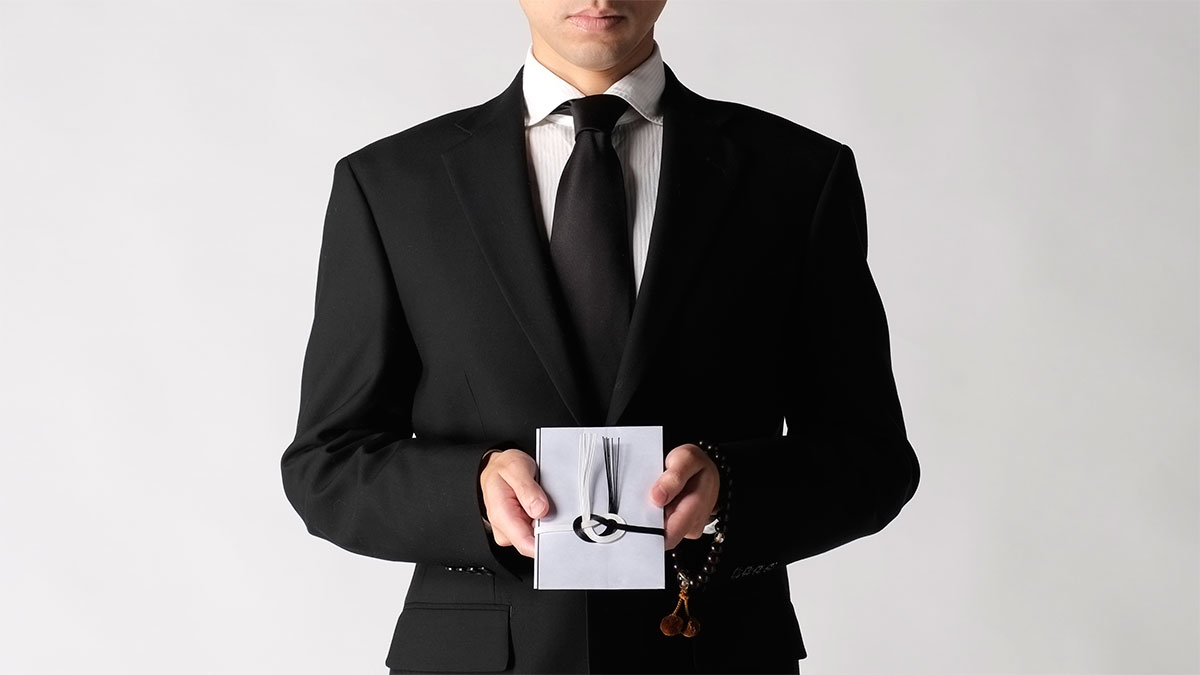 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
準備するのに手間のかかる新札は死を予想して準備していたようで不適切とされているからです。
旧札でそれほど汚くないお札がなかなか見つからないときもあるので、新札に折り目をつけてから包むということもできます。
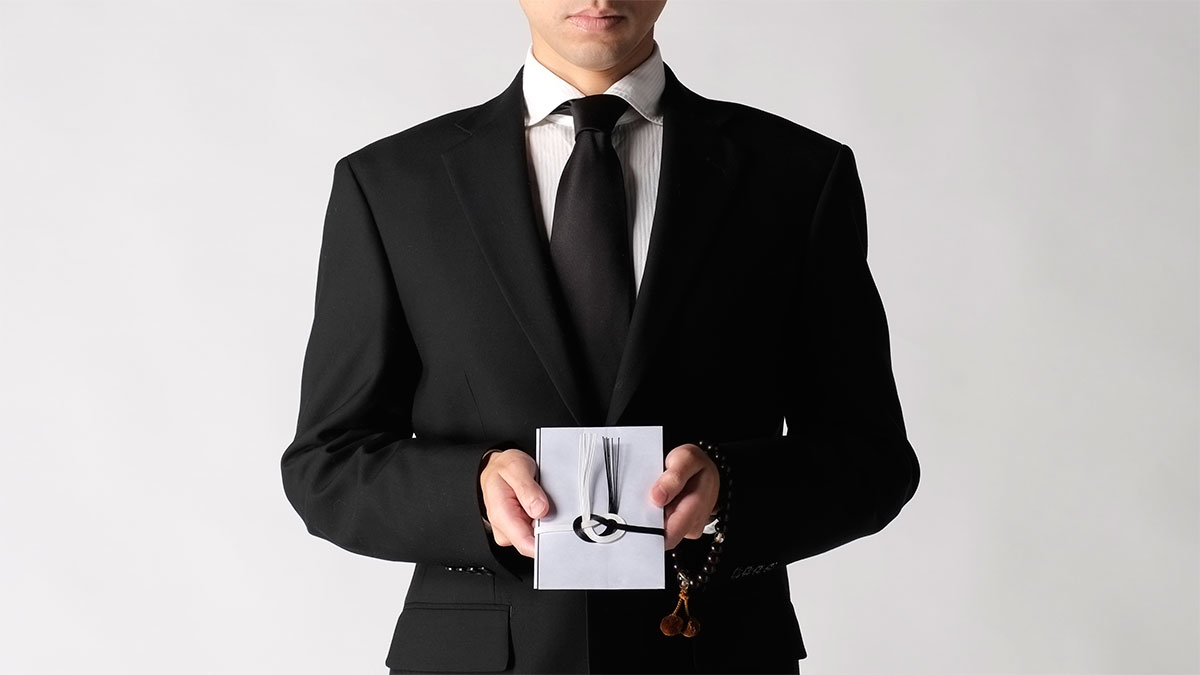 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
コンビニエンスストア等でも売られています。
蓮の花が印刷されたものは仏教ではOKですが、他宗教ではNGです。(逆にキリスト式の百合や十字架も仏式や神式ではNG)
香典袋は包む金額に応じたものを選ぶのが作法とされています。例としては
- 香典の金額が5,000円前後の場合は、水引きが印刷された略式のもの
- 1万円~2万円の場合は、白黒の水引きをかけたものなど
- 3万円~5万円の場合は、高級和紙に銀の水引きをかけたものなど
- 10万円以上の場合は、さらに手の込んだ装飾がされているものなど
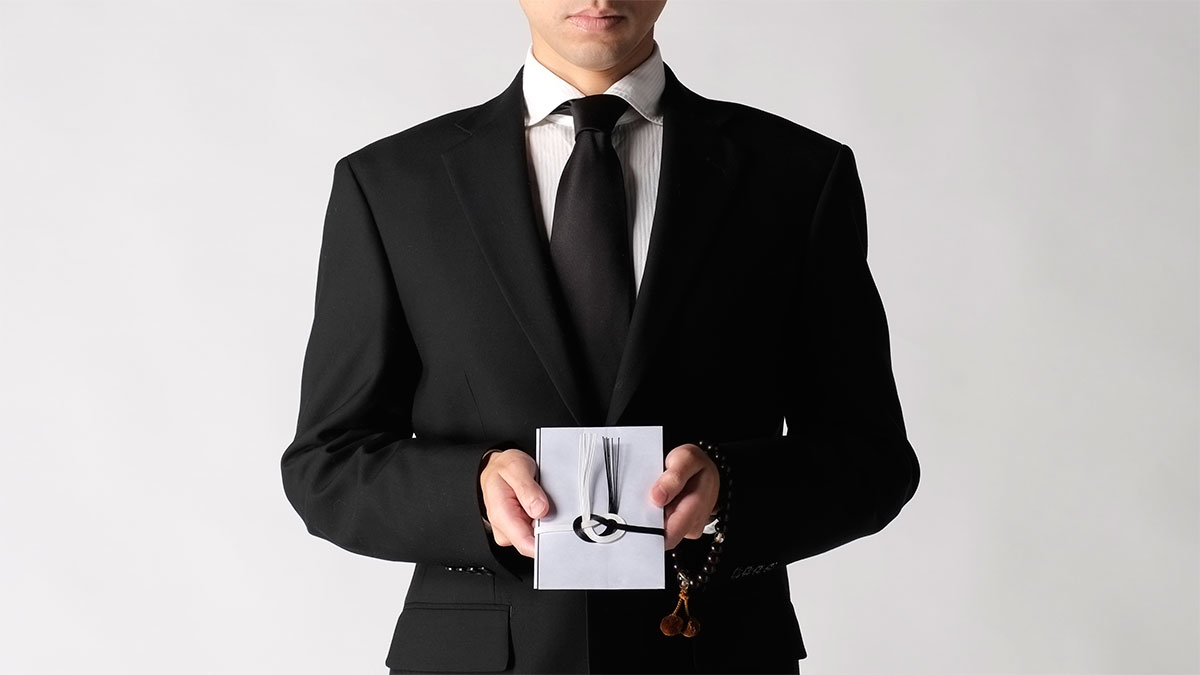 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
ただ注意が必要なものが浄土真宗のお葬式で、浄土真宗では亡くなった後すぐに仏になるという考えから御霊前は使いません。
同様に、その他の宗派でも四十九日以後は仏になるという考えですので、もし四十九日後に香典を持参するケースが有る場合は御仏前と表書きします。
葬儀に参列する際は、可能であれば故人の宗派を確認しておきましょう。
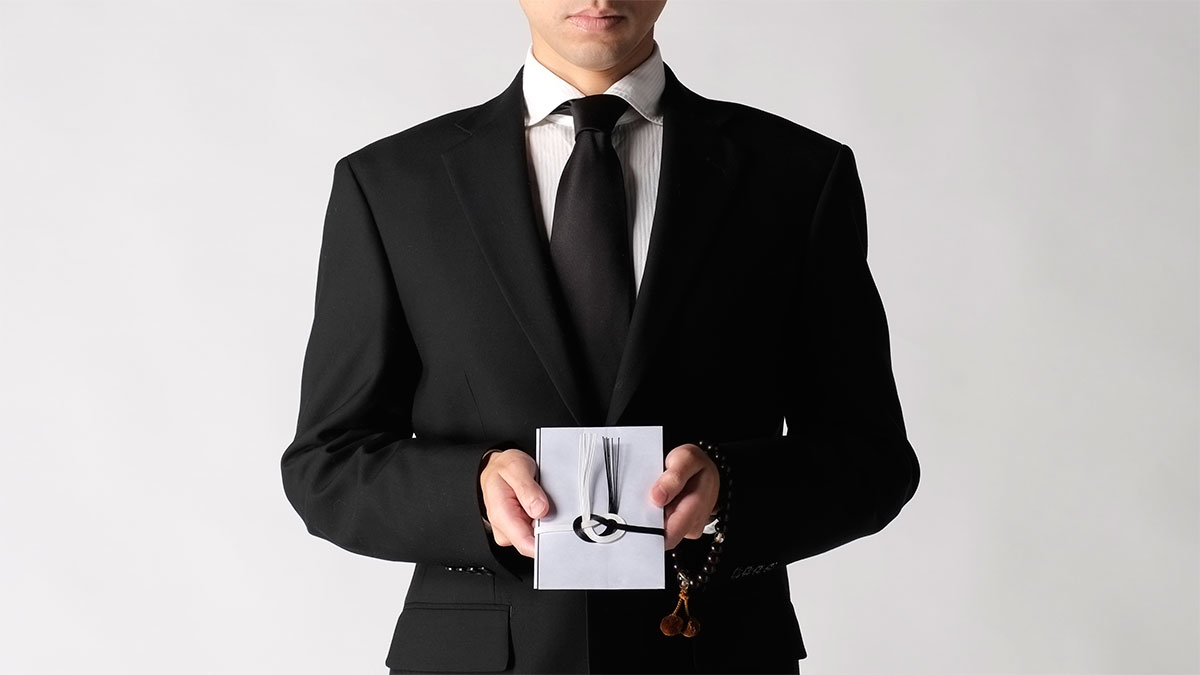 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
袱紗は慶弔両方に使える紫色のものを持っておくと便利です。
袱紗を包む順番は慶事とは逆です。
- 袱紗を広げてひし形のように置き、中心よりやや右寄りに香典袋を置きます。
- 最初に右をたたみます
- 下をたたみます
- 上をたたみます
- 最後に左をたたみます
香典を渡す際には右手の上に袱紗を乗せて、左手で香典袋を取り出します。
袱紗はたたんで置いておくか、台の代わりにして両手で差し出します。
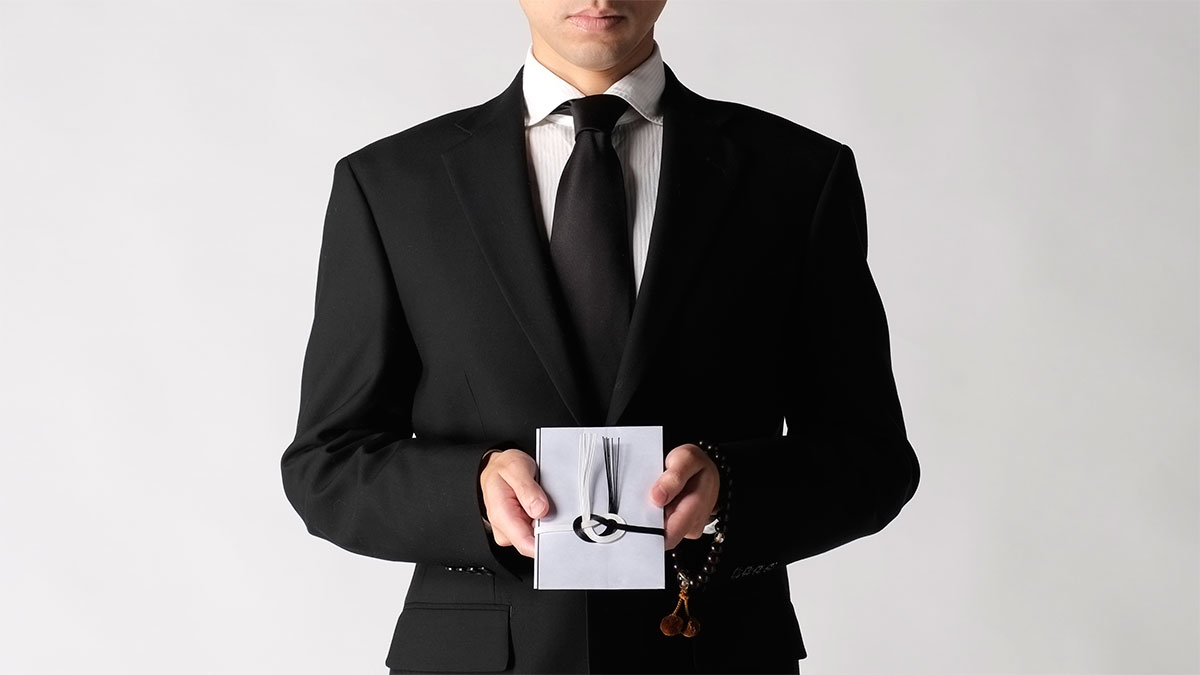 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
まず、香典を渡す回数は一回だけです。二回以上は「不幸が重なる」ことを連想されるため不適切です。
通夜と告別式両方に参列する場合は通夜で渡すことが多いようです。
通夜・告別式会場に受付がある場合には記帳を済ませた後、受付に手渡しします。
受付が無い場合は、拝礼の時に御霊前に供えるか遺族に手渡しします。
香典は袱紗に包んで持ってくるようにしましょう。
香典を袱紗から取り出し、両手で渡す相手から名前が見れるように渡します。
この際、「御霊前にお供えください」などと一言を添えるようにしましょう。
御霊前に供えるときは表書きを自分が読める方向にして供えます。
通夜と告別式に参列できない時は、代理人を立てるか現金書留で香典を郵送するようにしましょう。
なお、遺族が香典を辞退された時は遺族の意向を尊重して持参しないようにしましょう。
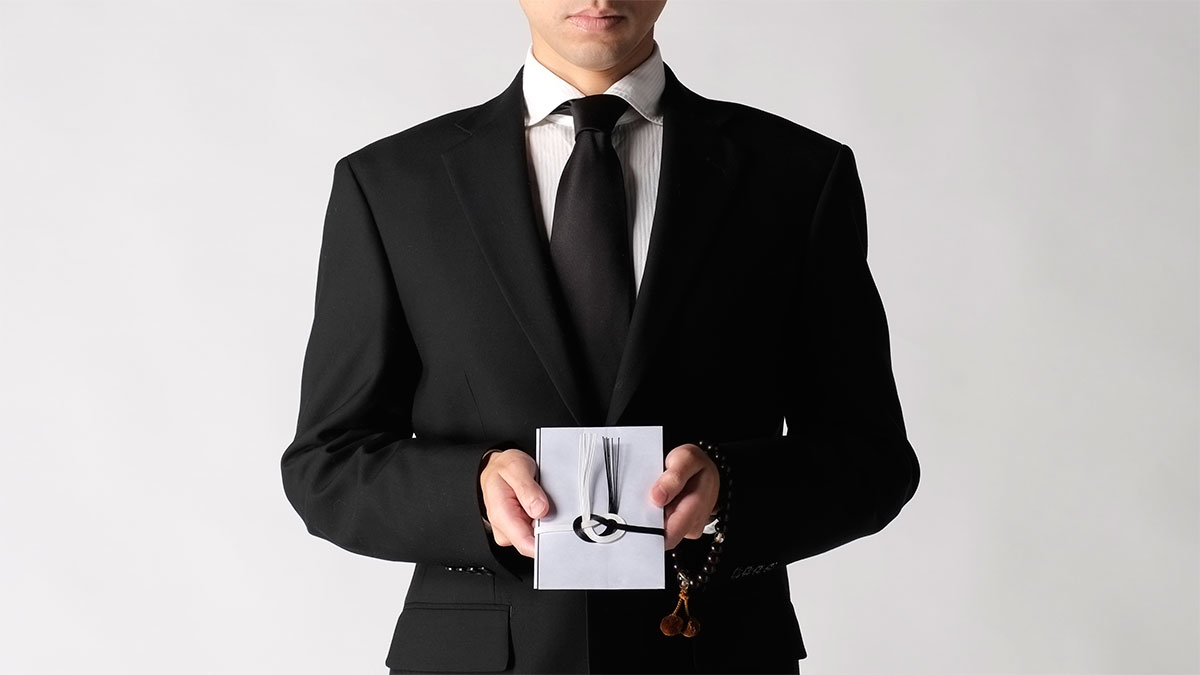 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
ですので、忌明けの四十九日法要後に香典返しをまとめて発送する場合は、香典帳の金額を参考に香典返しの金額を決めることになります。
最近では葬儀当日に香典返しの品を贈る即日返し(即返し・当日返し)を行う事が多いです。
即日返しはあらかじめ、一定の金額の香典返しを参列者全員に葬儀当日に渡し、通常の香典よりも高額な香典をもらった人には、忌明けに改めて差額分の香典返しを贈るという方法です。
通常、一般の会葬者であれば香典は5,000円程度が相場ですので、香典返しも2,000円〜2,500円の間で用意しておきます。
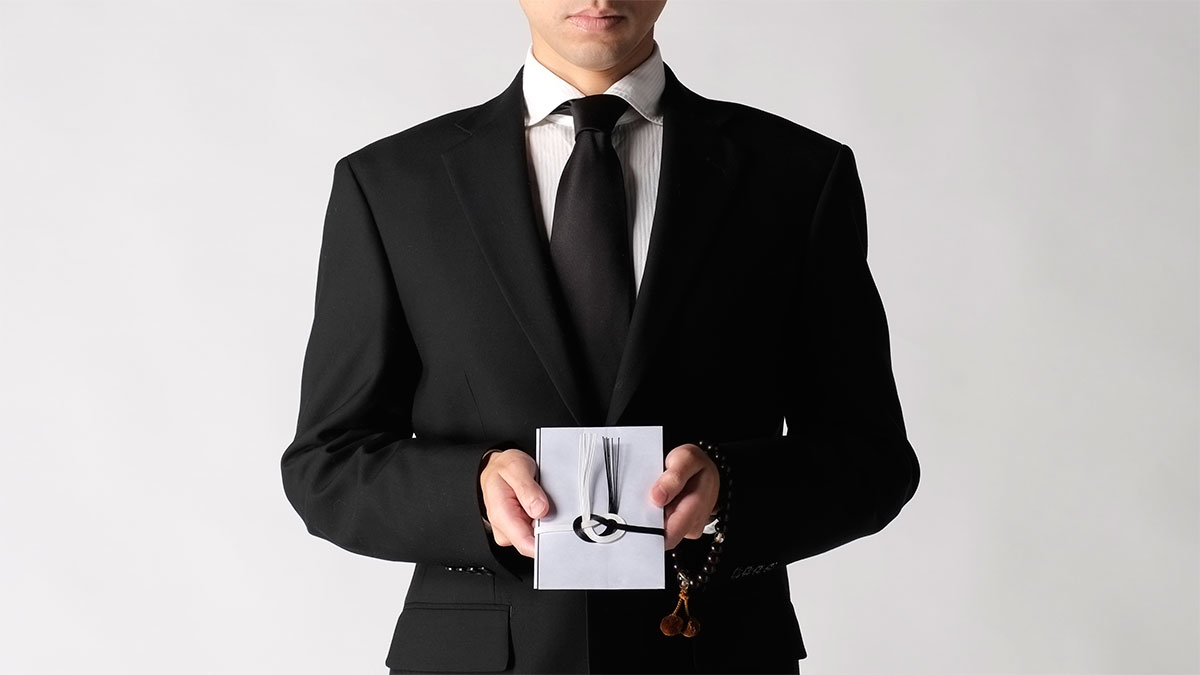 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
弔電に関するFAQ
- 香典を香典袋に入れる
- お悔やみの言葉、葬儀に参列できない理由などを書いたお悔やみ状を用意する
- 香典袋・お悔やみ状を現金書留の封筒に入れる
- 喪主・遺族の自宅に郵送する
 弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
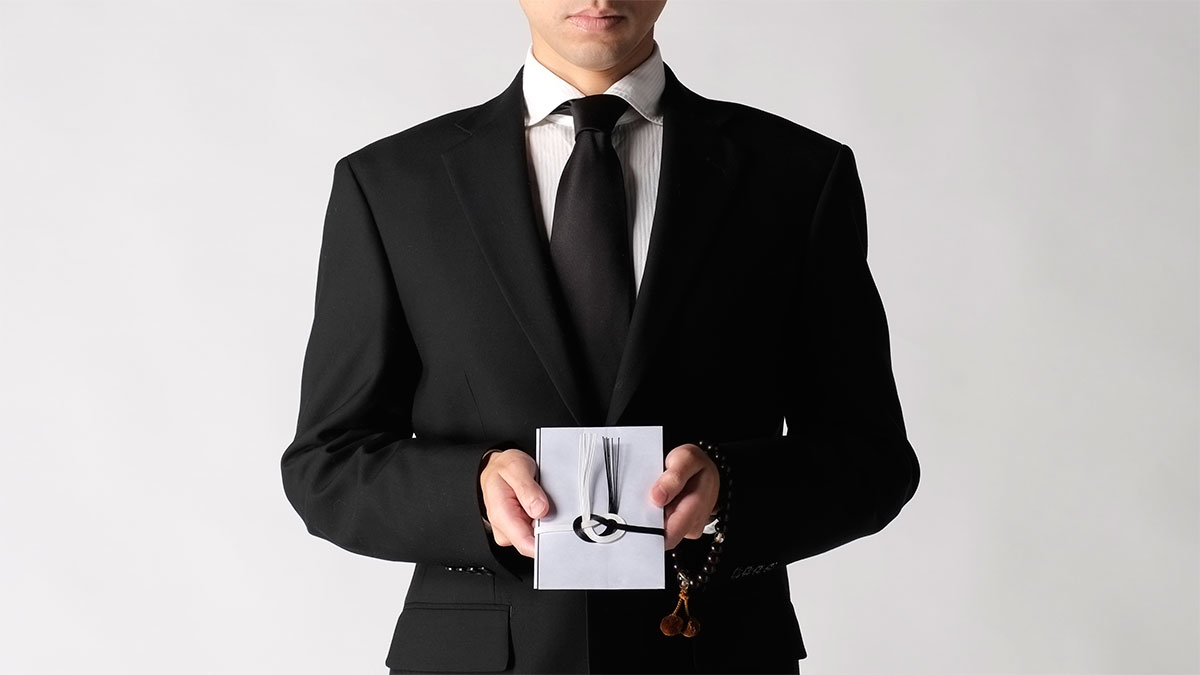 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
香典はどのような場面でも香典袋に入れて渡すようにしましょう。
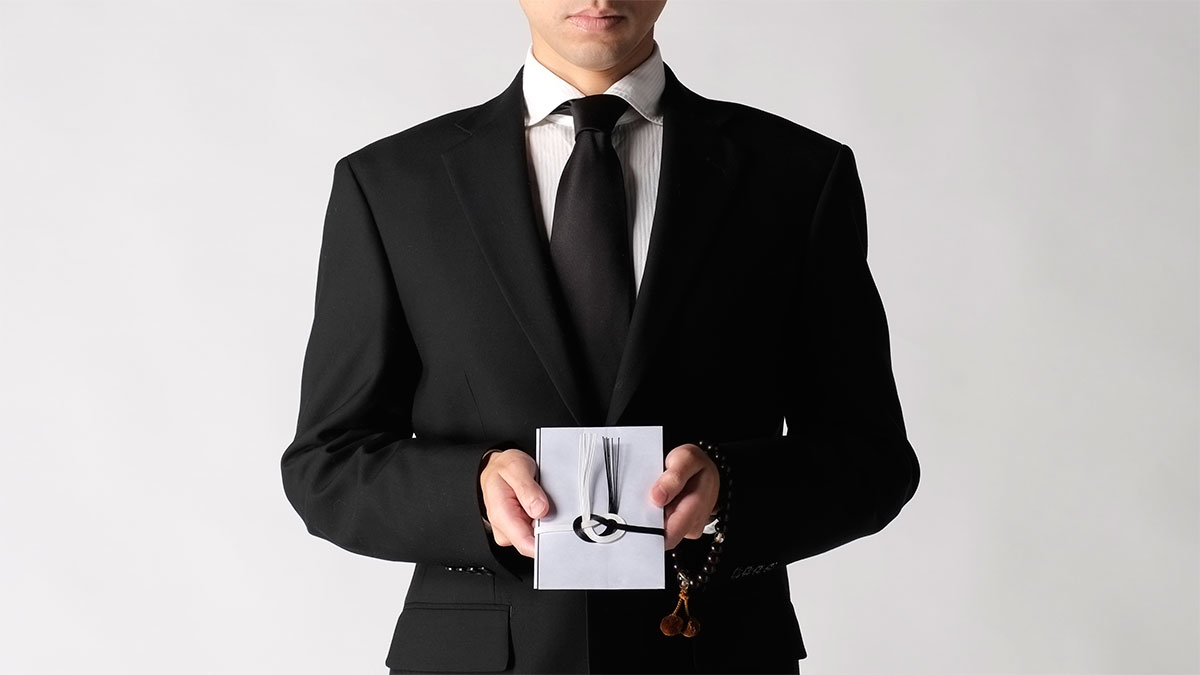 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
 弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
香典の郵送は喪主の自宅に送りますが、これは現金書留で送る場合、弔電と違って葬儀前に斎場に到達できるかどうかが不明なため、確実に届けるために喪主の自宅に送ります。
逆に弔電は、確実に葬儀に間に合わせることが重要です。
同じに見えるお悔やみでも、全く意味合いが違うので、両方送るべきなのです。
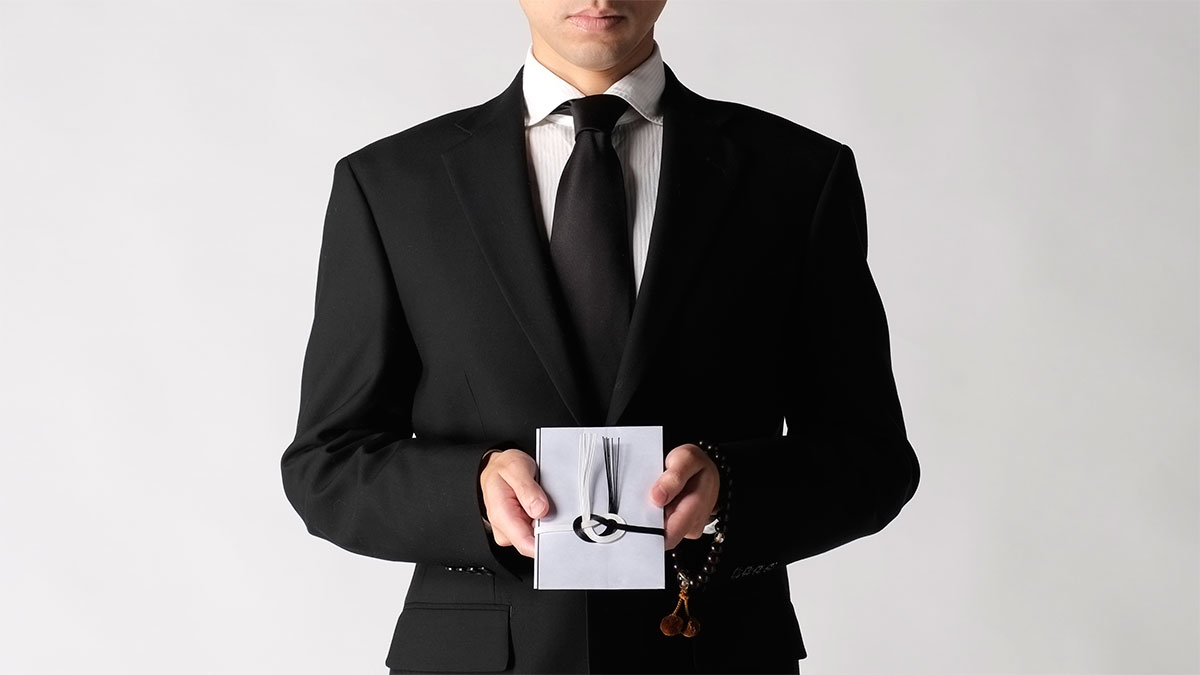 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
 弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
また、香典ももらっている場合は四十九日の忌明けに香典返しを送ります。香典返しを送る人へも礼状は別に送るようにします。
 弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
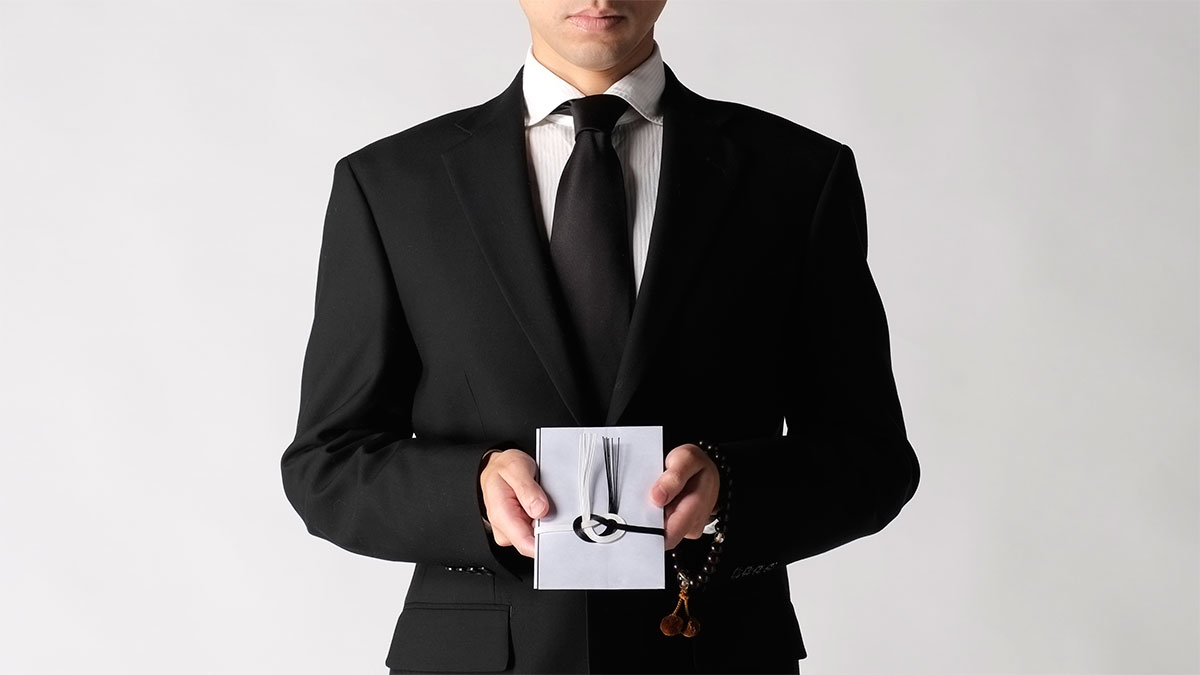 【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
【2025年版】知っておきたい!香典の金額(相場)・入れ方・渡し方・香典袋の書き方・包み方
弔電は基本的には訃報を受けたものの、通夜や告別式に参列できないときに弔意を伝えるために使います。
弔電の内容はお悔やみの言葉と葬儀に参列できない理由とお詫びです。ほとんどの場合は定型文を用いますが、自分の言葉で送ることも可能です。
また、弔電を送るのに合わせて香典を郵送することがほとんどです。
 弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
最もポピュラーなのはNTTの電報サービスで、固定電話とSoftbank以外の携帯電話からは「115」で繋がるコールセンターでオペレーターの指示に従い作成するか、インターネットから申し込む方法もあります。
また、郵便局も電報サービスを行っており、この場合はコールセンターへの電話、ネットからの申し込みに加えて、郵便局でも申し込むことが可能です。
現在では様々な企業が電報サービスを行っていますが、弔電に必要なのは決められた日時に確実に届けてくれることです。
信頼性のある会社に申し込むようにしましょう。
 弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
 NTT東日本・NTT西日本の弔電の送り方・申し込みの方法:「115」「D-MAIL」
NTT東日本・NTT西日本の弔電の送り方・申し込みの方法:「115」「D-MAIL」
 郵便局の弔電サービス「レタックス」とは?【最新ガイド 2025】
郵便局の弔電サービス「レタックス」とは?【最新ガイド 2025】
 弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)
弔電の送り方・文例・マナー完全ガイド(2025年最新版)




