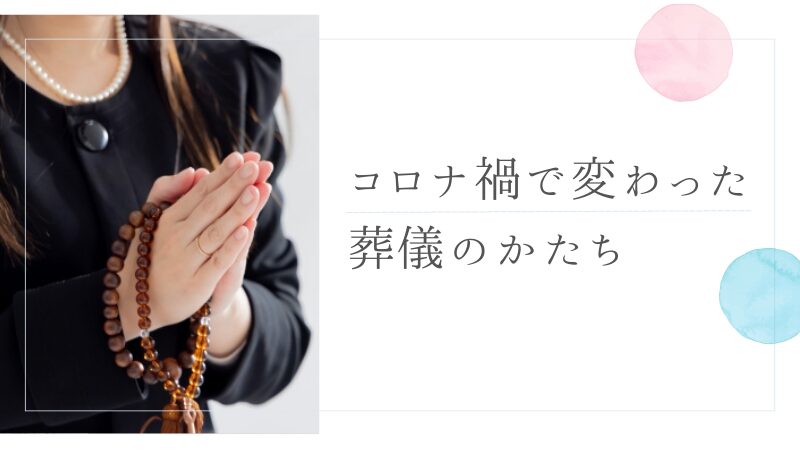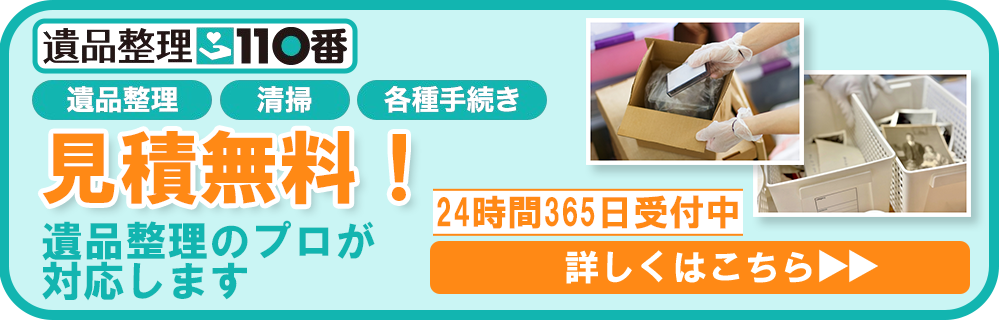コロナ禍は、葬儀のかたちを大きく変えるきっかけとなりました。葬儀の小規模化や簡素化は感染対策から始まりましたが、費用や心身の負担を抑えられることから、現在も多くの方に選ばれています。
一方で、大切な人を多くの人で見送りたいという気持ちから、一般葬が少しずつ回復している傾向もあります。
本記事では、コロナ前後の変化や最新データをもとに、これからの葬儀のあり方を整理します。
目次
コロナ禍以降の葬儀形式の変化

新型コロナ以前から「家族葬」や「直葬」が増えつつありましたが、コロナ禍を経てその傾向は一層強まりました。参列者数が制限されたことをきっかけに、規模の小さい葬儀が一般的な選択肢として定着したのです。
ここではその変化を、データと背景をあわせて見ていきます。
葬儀形式の割合(全国調査)
コロナ禍の前後を比較すると、葬儀のかたちがどのように変わったのか明確にわかります。
| 葬儀形式 | コロナ禍以前 | コロナ禍以降 |
|---|---|---|
| 一般葬 | 約52% | 約30% |
| 家族葬 | 約40% | 約50% |
| 一日葬 | 約5% | 約10% |
| 直葬・火葬式 | 約3% | 約10% |
出典:鎌倉新書「葬儀後の後悔に関する実態調査(2019年)」 / いい葬儀「第6回お葬式に関する全国調査(2024年)」
一般葬は大幅に減少し、家族葬が過半数を占めるまでに増加しました。また、一日葬や直葬などの簡素化された形式も増えています。
背景には、高齢化に伴う「呼べる親族や友人が少ない」事情や、「費用を抑えたい」という経済的理由もあります。単なる数字の変化ではなく、家族の事情や社会構造の変化を反映しているのが特徴です。 家族葬が主流になったことは、多くの遺族にとって「身近な人だけで落ち着いて見送りたい」というニーズに合致しました。 一方で、一般葬が完全に消えたわけではありません。地域の結びつきが強い地方では、いまも一定数行われています。また、近年は「コロナで呼べなかった人に改めて参列してもらいたい」との思いから、四十九日や一周忌でやや大きめの法要を行うケースも見られます。 つまり、一般葬は減少しつつも形を変えて続いていると言えるでしょう。 一日葬や直葬は、都市部を中心に選ばれることが増えています。背景には、核家族化と高齢世帯の増加があります。喪主自身が高齢で、2日にわたる通夜・告別式を取り仕切る体力的負担が重いため、短縮した形式を選ぶのです。 また、経済的な理由から「最低限の火葬のみ」を選ぶ人もいます。ただし、後から「お別れの時間が足りなかった」と後悔する声も少なくありません。 簡素さと納得感のバランスをどう取るかが、今後さらに課題になっていくでしょう。 コロナ禍を経て、葬儀におけるマナーの基準も少しずつ変わってきました。かつては「三密を避ける」「マスク着用を徹底する」ことが参列者の最低限の心得とされましたが、感染症法の分類変更以降は緩和され、現在はより自然な形へ戻りつつあります。 それでも、完全に元通りというわけではなく、参列者が安心できるような配慮は求められています。 参列者の服装は従来どおり喪服が基本ですが、コロナ禍を機に「必要以上に長時間着席しない」「季節に応じた快適さを優先する」など、やや柔軟な傾向が見られます。 ハンカチや数珠と並んで、アルコールスプレーやマスクを携帯する人はまだ少なくありません。 完全に必須ではないものの「持っていると安心できる物」として定着しつつあり、葬儀社側も受付に消毒液を常備して参列者を迎えるのが一般的になりました。 コロナ禍直後は「焼香をしない」「黙礼で済ませる」など従来の所作が省略される場面も目立ちました。 現在では再び焼香が一般的に行われていますが、焼香台に並ぶ際の距離感や時間配分には以前より気を使う人が増えています。また、挨拶も長い会話を避け、短い言葉で気持ちを伝える傾向が続いています。 形式を重視するよりも、相手に負担をかけない心配りが新しいマナーといえるでしょう。 感染拡大期には「家族のみ」や「十数名規模」の葬儀が多く見られましたが、現在は再び参列者の人数も増えつつあります。ただし、従来のように数百人規模を集めることはまれで、50名程度の中規模が主流になっています。 葬儀社側も受付や会場配置を工夫し、混雑を避けながら落ち着いた雰囲気を保つよう配慮しています。 通夜振る舞いや精進落としの場も、コロナ禍では簡略化や中止が相次ぎました。現在は少人数での会食や折詰弁当の提供など、形を変えて復活しています。 大人数での飲食は依然として控えられる傾向があり、「食事よりも気持ちを伝える場」としての意味合いが強くなっているのが特徴です。 このように、葬儀のマナーは「従来に戻る部分」と「新しい習慣として残る部分」が入り混じっています。マスクや消毒といった備えは必須ではなくなったものの、互いに安心して参列できる環境づくりは今も大切にされています。 コロナ禍を通じて生まれた新しい習慣は、一時的な対応にとどまらず、今後の葬儀のあり方そのものに影響を与えています。 小規模化や簡素化の流れは一定の支持を得ており、これからは「どの形式が正しいか」ではなく「遺族や参列者にとって最も納得できる形は何か」が重視されていくでしょう。 また、オンライン参列や自宅での見送りといった新しい選択肢も生まれ、葬儀はより多様で柔軟なものへと移行しつつあります。ここでは、今後の方向性について具体的に考えてみます。 家族葬や直葬はすでに多くの家庭で選ばれるようになり、費用や準備の負担を抑えたいというニーズに応えています。一方で、仕事や地域でのつながりが広い方には、やはり一般葬がふさわしいと考える遺族も少なくありません。 こうしたニーズに応えるため、利用者の希望に合わせて多様なプランを提供する葬儀社が増えています。 たとえば「小さなお葬式」では、家族葬から一般葬まで幅広いプランが用意されています。費用の明確さやサポート体制も整っているため、初めての方でも安心して相談できます。 これからは「どの形式が正解か」というよりも、「誰を招き、どのように送りたいか」を軸に柔軟に選ぶ時代になっています。 遠方に住む親族や高齢で参列が難しい方にとって、オンライン配信や録画は便利な手段です。ただし、世代によって抵抗感があるのも事実です。そのため「必要な場合に限定して利用する」ことが現実的でしょう。 利用にあたっては、視聴範囲や録画データの扱いをあらかじめ決めておくことで、安心して取り入れることができます。 葬儀の形式が増えたことで、サービス選びはこれまで以上に大切になりました。なるべく複数社の見積を取り、予算や希望に合った葬儀サービスを選びましょう。 ゆっくり検討する時間がない場合は、一括見積サービスを活用すると葬儀プランを効率よく比較検討できます。たとえば葬儀社紹介サービスの「安心葬儀」なら、全国対応で24時間365日いつでも一括見積や相談が可能です。 単に価格だけで判断するのではなく、サポート体制やアフターケアが充実しているかどうかも含めて選ぶことが、満足度の高い葬儀につながります。 葬儀が終わった後も、遺品整理や各種の名義変更、相続手続きなど、多くの課題が残ります。こうした作業を専門に扱う「遺品整理業者」や行政書士・司法書士のサービスを利用することで、家族の負担を大きく減らすことができます。 中でも全国対応の遺品整理サービス「遺品整理110番 また、あらかじめエンディングノートを作成しておけば、財産や手続きに関する希望を家族と共有できるため、葬儀後の混乱を防ぎやすくなります。 事前の準備として取り入れておくと、残された家族の安心にもつながるでしょう。 葬儀に関する疑問は人それぞれです。コロナ禍を経て葬儀の形式やマナーが変化したことで、従来とは違う悩みを抱える方も増えています。 ここでは最近よく寄せられる質問とその答えをまとめました。 現在はマスク着用やアルコール消毒を義務付ける葬儀会場は少なくなりました。ただし、高齢者や体調に不安のある参列者が多い場合には、マスクを着ける・消毒液を準備するなど最低限の配慮をしておくと安心です。 家族葬にすると親族から不満が出ませんか? 家族葬は増えていますが、参列の案内を受けなかった親族が不満を抱くケースもあります。事前に「故人や家族の意向で家族葬とする」ことを説明し、後日弔問の機会を設けるとトラブルを避けやすくなります。 会社関係者や遠方の親族を呼ばず、近しい家族や親戚だけで行う傾向が強まっています。ただし、社会的なつながりが深い場合や地域性によっては、従来型の一般葬を選ぶこともあります。 一日葬や火葬式といったシンプルな葬儀も、現在では一般的になっています。重要なのは形式よりも気持ちをどう表すかであり、心を込めて故人を送る場があれば失礼には当たりません。 近年は大規模な一般葬も少しずつ回復傾向にあります。ただし、費用や準備の負担を考えて、小規模葬を選ぶ家庭が多いのも事実です。 コロナ禍は、私たちの葬儀のあり方を大きく変えました。家族葬や一日葬などの簡素化が広まり、参列者の呼び方やマナーも柔軟に変化しています。こうした流れは一過性のものではなく、今後も続いていくと考えられます。 一方で、地域や親族関係によっては従来の一般葬を望む声も根強く、選択肢はむしろ広がっているともいえるでしょう。 大切なのは「形式に縛られること」ではなく、「どのように故人を偲び、家族が納得できるか」という点です。コロナ禍を経た今だからこそ、慣習にとらわれすぎず、家族にとって無理のない葬儀のかたちを選ぶことが求められています。
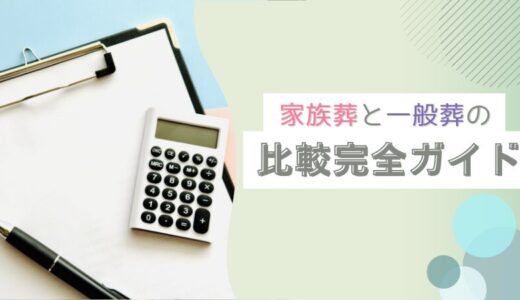 家族葬と一般葬の比較完全ガイド
家族葬と一般葬の比較完全ガイド
家族葬と一般葬の今後の行方
一日葬や直葬が増える理由
 一日葬とは?一般葬・家族葬・直葬との違いから流れ・費用まで徹底解説
一日葬とは?一般葬・家族葬・直葬との違いから流れ・費用まで徹底解説
コロナ禍以降の葬儀におけるマナー

服装と持ち物の変化
焼香や挨拶の変化
参列人数と会場運営の工夫
食事や会食の新しいかたち
今後は形式よりも心配りが優先される傾向が続き、柔軟で思いやりのあるマナーが標準となっていくでしょう。今後の葬儀の方向性は?

多様なスタイルの共存
オンライン葬儀の活用方法
サービス選びと費用の比較
葬儀後に必要なサポート
![]() 」は、明朗な料金体系が強みです。相談・出張・見積費用は無料で、急な依頼でも柔軟に対応してもらえます。
」は、明朗な料金体系が強みです。相談・出張・見積費用は無料で、急な依頼でも柔軟に対応してもらえます。
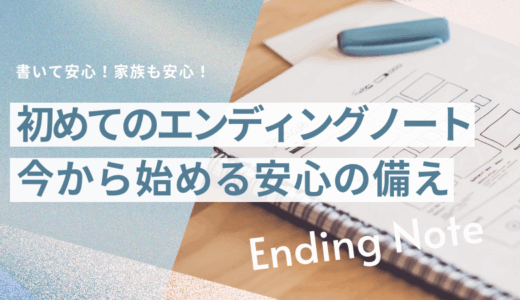 はじめてのエンディングノート〜今から始める安心の備え〜
はじめてのエンディングノート〜今から始める安心の備え〜
コロナ禍以降の葬儀に関するよくある質問

マスクや消毒はまだ必要ですか?
参列者はどこまで呼べばいいのでしょうか?
故人の交友関係と家族の希望を照らし合わせて判断するのがよいでしょう。簡素化された葬儀だと失礼になりませんか?
コロナ前のように大規模な葬儀は戻ってきますか?
今後は「大規模」か「小規模」かではなく、状況や希望に応じて柔軟に選ぶ時代になるでしょう。まとめ