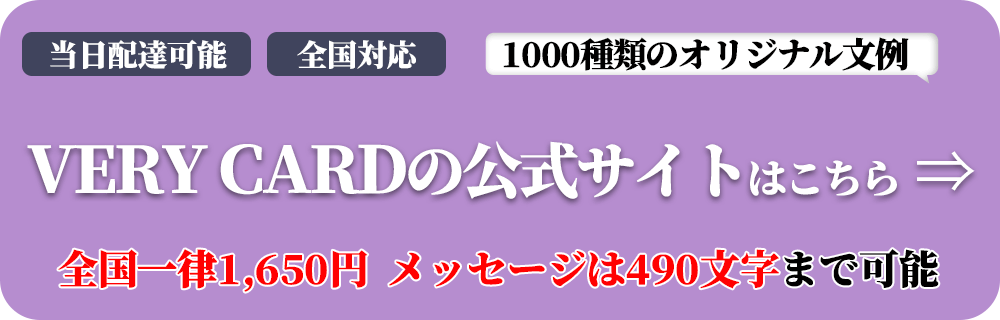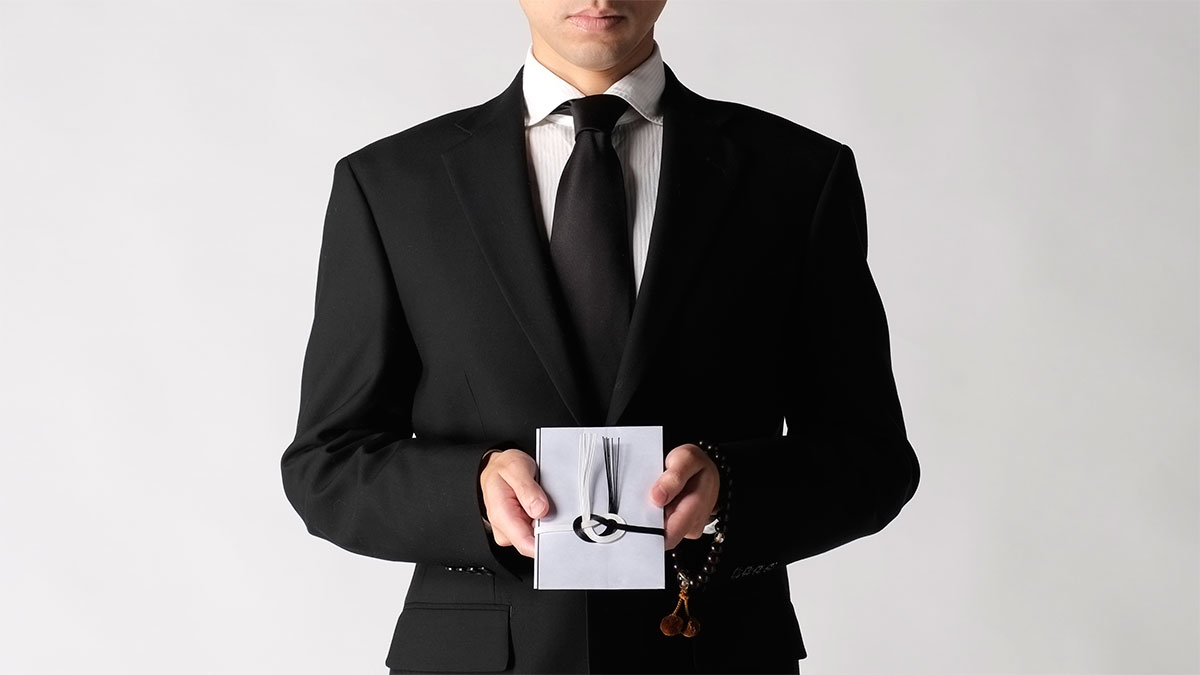葬儀に参列できないときに故人への哀悼の意を伝える「弔電」について、その意味や送る方法、マナーを詳しく解説します。弔電のマナーに不安を感じている方にも分かりやすいよう、親しみやすく丁寧な文体でまとめました。弔電の基本から宗教別の文例、注意すべき言葉、宛名の書き方、台紙の選び方、主要なサービス比較、香典を郵送する際のマナー、そして最新のトレンドまで網羅しています。これを読めば弔電マナーの不安が解消できるはずです。
目次
弔電とは何か?その意味と役割
弔電とは、故人を悼みご遺族に哀悼の意を伝える電報のことです。電報には大きく分けて結婚式などの慶事用と、お葬式などの弔事用(=弔電)の2種類があります。弔電は一般的に、訃報を受け取ったものの何らかの事情で通夜や葬儀・告別式に出席できない場合に送るものです。離れた場所からでも素早く気持ちを届けられる手段として、電話やメールが普及した現在でも正式な弔意の伝達方法として広く利用されています。
なお、「弔電を打ったから葬儀に参列できない」という決まりはありません。弔電を送った後で急遽参列できる状況になった場合は、参列してもマナー違反にはなりません。弔電はあくまで哀悼の意を伝える手段であり、参列の可否とは直接関係ないことも覚えておきましょう。
弔電を送るタイミングと注意点
一番重要なのは、弔電が通夜や告別式の当日に確実に届くよう手配することです。具体的には、葬儀の日程が分かったら式の前日までに手配を済ませるのが望ましいです。多くの電報サービスでは「○時までの申し込みで即日配達可能」といった締め切り時間が定められているため、自分が届けたい日時に間に合うかを必ず確認しましょう。例えばNTTの電報サービスでは、午後2時までの申し込みで全国当日中に配達してもらえます。仕事の合間などで手配が遅れそうなときは、インターネットから24時間申し込み可能なサービスを利用すると安心です。
葬儀の日取りを過ぎて訃報を知った場合など、式に間に合わないタイミングでは無理に弔電を送らない方がよいこともあります。その代わりに、後日ご遺族宛にお悔やみの手紙(弔慰状)を送る方法があります。弔電は本来「式に間に合うこと」が前提のため、式後に届くようではかえってご遺族の負担になる可能性があります。葬儀後になってしまった場合は、改めてお悔やみ状や電話で哀悼の意を伝え、可能なら四十九日までにご自宅を訪問してお線香をあげさせてもらうのが丁寧な対応です。
宗教を確認することも弔電マナーの重要ポイントです。弔電の文面には後述するように宗教ごとに適した表現があります。故人やご遺族の信仰(仏式か神式〈神道〉かキリスト教式かなど)を可能な範囲で確認し、それにふさわしい文例を選ぶようにしましょう。分からない場合は、どの宗教でも使える一般的なお悔やみの表現(「ご逝去を悼み心よりお悔やみ申し上げます」等)を使うと無難です。
また、弔電の送り先(宛先)も事前によく確認してください。弔電は通常、通夜や葬儀の会場(斎場)またはご遺族の自宅に届けます。通夜・葬儀の日程と会場が訃報連絡に記載されている場合はその住所宛てに、個人宅で執り行う場合や会場が不明な場合はご自宅宛てに送るのが一般的です。後述しますが宛名は喪主名で出すのが基本です。
弔電の文例と宗教ごとのNG表現
弔電に書くメッセージ(電文)は、形式ばった挨拶と相手への思いやりを込めた文章でまとめます。電報各社ではあらかじめ豊富な文例が用意されており、NTT西日本では約2000種類ものシーン別文例が提供されています。インターネット申し込み画面で適切なテンプレート文例を選ぶだけでも十分ですが、以下に基本的な例をいくつか紹介します。
-
一般的なお悔やみの文例(仏式):
「突然の悲報に接し、心よりお悔やみ申し上げます。○○様のご冥福をお祈りいたします。」
(故人の冥福を祈る=極楽往生を祈る意味の表現) -
親しい間柄向けの文例:
「○○様のご訃報に接し、いまだ信じられない思いです。ご家族のお悲しみはいかばかりかとお察し申し上げます。心よりご冥福をお祈りいたします。」 -
会社関係(上司や取引先)向け文例:
「○○社長様のご逝去の報に接し、社員一同深い悲しみに包まれております。生前のご厚誼に感謝するとともに、心より哀悼の意を表します。」
文例は宗教や関係性によって使い分ける必要があります。仏式の場合、「ご冥福をお祈りします」「ご焼香(しょうこう)」「成仏」など仏教の概念を使った表現が一般的です。ただし「ご愁傷様です」「安らかにお眠りください」など宗教色の薄い表現も広く用いられるため、仏式か不明な場合はそうした言葉を選ぶとよいでしょう。
神式(神道)やキリスト教式の場合、仏教用語は避けます。例えば「成仏してください」「ご供養ください」等は神式・キリスト教式の葬儀では忌み言葉とされています。キリスト教では「安らかなお眠りをお祈りいたします」や「天国での平安をお祈りします」といった表現がありますし、神道では「〇〇様の御霊(みたま)のご平安をお祈りいたします」などとします。
宗教が分からない場合や迷う場合は、「心よりお悔やみ申し上げます」「哀悼の意を表します」などどの宗教でも受け入れられる表現を使うと無難です。
弔電の文章で注意すべきなのが、忌み言葉(いみことば)と呼ばれる不吉な連想を与える言葉の使用です。不幸が続くことを連想させる言葉や、死亡・別離など直接的すぎる表現は避けるのがマナーとされています。具体的には、葬儀の場では以下のような言葉はNGワードです。
-
不幸や死を連想させる言葉:「死亡」「死ぬ」「九」「四(し)」など数字の四(読みが「死」に通じる)、「苦しむ」を連想させる九など。また「重病」など直接的な不幸の表現も避けます。
-
繰り返しを連想させる重ね言葉:「重ね重ね」「次々」「ますます」「度々」など。同じ言葉を繰り返す表現は「不幸が重なる」ことを連想させるためNGです。代わりに「深く」「改めて」など単発の表現に言い換えます。
-
不吉な忌み言葉の例:葬儀では「浮かばれない(成仏できないことを連想)」「遠からず(後日すぐまた不幸が起きることを連想)」なども避けます。また結婚式の忌み言葉として有名な「終わる」「別れる」なども、本来は弔事では問題ありませんが、念のため避けるケースもあります。
上記のような忌み言葉は弔電の文面でも最低限注意すべきマナーです。送る前に不適切な表現が入っていないか、もう一度読み直すようにしましょう。電報サービス各社の文例はこの点も考慮されているので、あまり自信がなければ文例集からそのまま選ぶのが安心です。
弔電の宛名・宛先の正しい書き方
弔電を送る際、宛名の書き方も迷いがちなポイントです。「故人宛てに出すべきか、それとも喪主宛てか?」と悩む人も多いですが、結論として弔電の宛名(宛先)は受取人である『喪主』にします。電報は故人本人が受け取るものではなく、ご遺族が受け取るものですので、基本的には葬儀を執り仕切る喪主の名前を宛名に書きます。
喪主の氏名と敬称
氏名の後ろに「様」を付けます(例:「山田太郎様」)。肩書き(〇〇家 喪主など)は不要です。会社関係の場合でも、個人宛てに送るのが原則なので「株式会社○○ 社長 山田太郎様」とするより、「山田太郎様(株式会社○○)」とした方が丁寧でしょう。
宛先の住所
通夜・葬儀の会場宛てに送る場合は、その式場の住所と式場名を書き、宛名を「喪主 山田太郎様」とします。自宅宛てに送る場合は、喪主の自宅住所と氏名を書けばOKです。電報申込時にはWebフォームや電話でオペレーターに伝える形になるため、自分で封筒等に書く必要はありませんが、住所や氏名の漢字を間違えないよう正確に伝えましょう。
喪主が分からない場合
訃報通知や案内状に喪主名が書かれていればそれを使いますが、親戚づてに聞いた場合などで喪主が分からないこともあります。その場合は「〇〇〇〇(故人の氏名) ご遺族様」といった宛名で送る方法があります。つまり、故人の姓と名を書き「ご遺族様」と付ければ、「故○○様のご遺族一同」の意味になり、喪主名が特定できなくても失礼にあたりません。
連名で送る場合
職場の同僚一同で送る場合や有志一同で送る場合は、差出人欄に「〇〇部一同」「有志一同」などと記載できます。差出人は本文中に書く形式(電報台紙に印字される)なので、申込時に差出人名を指示しましょう。個人で送る場合でも、夫婦連名や家族連名で出すことも可能です。その場合も宛名は基本的に喪主お一人宛てで問題ありません。
弔電の台紙の選び方と価格帯

電報は本文を印字した紙を「台紙」と呼ばれる台紙・カードに貼り付けた形で届けられます。結婚式の祝電では華やかなカードが選ばれることが多いですが、弔電の場合はお悔やみ用の落ち着いたデザインの台紙を使用します。各サービスで選べる台紙の種類は様々で、シンプルな白黒のものから、蓮の花や百合の花をあしらったもの、高級和紙を使ったもの、さらには線香やロウソクがセットになった台紙、プリザーブドフラワー付きの台紙などもあります。
価格帯も台紙のグレードによって大きく異なります。一般的には一番安価なシンプル台紙で500円前後、中級クラスで1000~3000円程度、装飾が豪華なものや花・品物付きの台紙だと1万円以上するものまで様々です。NTTの電報サービスでも、無料の簡易台紙から有料の豪華台紙までラインナップがあります。たとえばNTT東日本のサイトを見ると、シンプルな弔電専用台紙(白黒の奉書紙様式など)は数百円で選べ、押し花付きや高級和紙台紙は数千円の追加料金となっています。
台紙を選ぶ際は、故人との関係性やご遺族の心情に配慮することが大切です。例えば会社関係で形式的に送る場合は質素なものでも問題ありませんが、親族や親しい方の場合は多少品格のある台紙を選ぶ方が良いでしょう。とはいえ、台紙の豪華さそのものよりも、心のこもったメッセージの方が何倍も大切です。無理のない範囲で選択すれば構いません。ちなみにVERY CARDでは100種類以上の電報台紙を用意しており、低価格帯から選べてデザインも豊富です。費用を抑えつつ失礼のない弔電にしたい場合、VERY CARDのシンプルな台紙は特に人気があります。
弔電サービス主要3社の比較(VERY CARD・NTT・郵便局)
現在、日本で弔電(電報)を送るには主に以下のようなサービスがあります。それぞれ特徴があるので、料金や利便性を比較してみましょう。
VERY CARD(ベリーカード)
佐川急便のグループ会社が提供する電報サービスです。インターネットや電話で簡単に申し込めて、1通あたり1,650円(税込)~とリーズナブルな全国一律料金が特徴です。14時までの申し込みで全国即日配達が可能で、台紙も100種類以上から選べます。文字料金(電文の長さによる追加料金)は基本的になく、約25文字程度の定型文なら追加費用なしで送れるプランもあります(長文の場合は追加料金が発生する場合あり)。支払いはクレジットカードや後払いなどに対応。低価格でデザインも豊富なため個人利用はもちろん、法人の大量利用にも適しています。初めて弔電を送る方にも使いやすいサービスと言えるでしょう。
 格安弔電で評判!VERY CARDの特徴と使い方、文例、サービス比較(ベリーカード)
格安弔電で評判!VERY CARDの特徴と使い方、文例、サービス比較(ベリーカード)
NTT電報(D-MAIL)
NTT東日本・西日本が提供する伝統的な電報サービスです。かつては電話番号「115」での申込が主流でしたが、現在ではWebサイトからの申し込みが主流になっています。NTTの電報料金は本文300文字まで1ページにつき1,320円(税込)が基本で、電話で115を利用すると電話受付料440円が別途かかります。ネットならその電話料分がお得になります。台紙は無料のものもありますが、有料台紙を選ぶとその料金(数百円~数千円)が加算されます。例えばシンプル台紙なら数百円、ぬいぐるみ付き電報(弔電ではなく祝電向けですが)のような特殊台紙だと1万円以上するものもあります。午後2時までの受付完了で当日配達、土日祝も配達可能。老舗だけあって安心感と信頼性は抜群で、困ったときはオペレーターによる電話対応も受けられる利点があります。文例の種類も非常に豊富で、公式サイト上で宗教別・相手別の例文を検索できるなどサポートが充実しています。
 NTT東日本・NTT西日本の弔電の送り方・申し込みの方法:「115」「D-MAIL」
NTT東日本・NTT西日本の弔電の送り方・申し込みの方法:「115」「D-MAIL」
郵便局のレタックス(Webレタックス)
日本郵便が提供する電報類似サービスです。郵便局のWebレタックスは、インターネット上で申し込みができる電子郵便の一種で、料金は全国一律680円(税込)~と非常に割安なのが魅力です。文字数による追加料金はなく文字数無制限で定額という特徴があります。台紙(専用用紙)の種類もお祝い用・お悔やみ用で数種類から選べ、郵便局窓口で申し込むよりWebからの方が安く利用できます。配達もスピーディーで、地域によりますが15時30分まで(※一部地域は13時30分まで)に申し込めば当日配達が可能です。土日祝日も配達してくれる上、配達日を指定したり午前・午後の希望時間帯指定もできます。さらに配達状況を追跡サービスで確認できる点も安心です。注意点としては、NTTやVERY CARDに比べ台紙のデザインバリエーションがやや少なめなこと、支払いに料金後納(一定期間の後払い契約)かクレジットカードが必要なことなどがあります。しかし、「できるだけ費用を抑えて確実にメッセージを届けたい」という場合には最も経済的な選択肢と言えます。
 郵便局の弔電サービス「レタックス」とは?【最新ガイド 2025】
郵便局の弔電サービス「レタックス」とは?【最新ガイド 2025】
どのサービスを選ぶべき?
迷った場合は、費用重視であればVERY CARDやレタックスが低価格でおすすめです。【VERY CARDは安価でシンプルな電報を送りたい方に特に適しています。一方、「やはりNTTの電報というと安心」「電話で色々相談しながら送りたい」という場合はNTT電報を利用するとよいでしょう。いずれのサービスもネットから申し込み可能で即日配達に対応していますので、現在は「115番に電話して電報」というよりインターネットで手配する時代になっています。自分にとって利用しやすい方法で送れば問題ありません。
香典の郵送マナーと弔電との関係
弔電を送る状況では多くの場合、葬儀に参列できないため香典(こうでん)も直接手渡しできません。この場合、香典を現金書留で郵送することになりますが、そのマナーについても触れておきます。
まず香典を郵送すること自体は可能でマナー違反ではありません。諸事情で葬儀に行けない場合、香典は郵送しても問題ありませんが、その際はいくつか注意点があります。
必ず現金書留で送る
現金を普通郵便や宅配便で送ることは法律で禁止されています。必ず郵便局の「現金書留」専用封筒を使用しましょう。現金書留封筒は郵便局で購入でき、不祝儀袋が入る大きめのサイズになっています。現金書留以外の方法(レターパック等)は現金封入不可なので注意してください。
香典を不祝儀袋に入れる
お札はむき出しではなく、不祝儀袋(香典袋)に入れてから封筒に封入します。現金書留封筒にはそのまま不祝儀袋を入れられるポケットが付いています。不祝儀袋の表書き(上段に「御霊前」や「御香典」、下段に自分の氏名)を忘れずに。お札は新札は避け、使い古しすぎるものも避けます。新札しかない場合は一度折り目を付けてから包むと、「あらかじめ用意していた」感が薄れるので無難です。
宛名は喪主宛てにする
現金書留封筒の宛名欄には喪主の名前を書きます。喪主と直接面識がない場合でも、葬儀を執り行う責任者である喪主宛てに送るのが正式です。住所は葬儀会場ではなく喪主のご自宅住所にします。葬儀当日はご家族も慌ただしいため、香典は確実に受け取れるご自宅宛てに送る方が親切です。実際、弔電は式場に届くよう手配し、香典は自宅に送るなど弔電と香典は別々に手配するのが一般的です。
お悔やみの手紙を添える
香典だけを現金書留で送るのは味気ないため、簡単で良いのでお悔やみの手紙(添え状)を同封しましょう。手紙には「本来なら直接お参りすべきところ、欠礼しましたことをお詫び申し上げます」といった不参のお詫びとお悔やみの言葉を書き添えます。「ご迷惑かと存じましたが、心ばかりの御香料をお送りいたしましたのでお納めください」など、香典を同封した旨も一言触れておくと親切です。手紙の用紙は白無地の便箋か略式の弔事用はがきを用います(黒枠の弔事用カードなども市販されています)。
送るタイミング
香典も可能であれば葬儀当日までに届くように発送します。ただし遠方で間に合わない場合は、葬儀後でも失礼にはあたりません。その場合は手紙に「ご連絡が遅くなりましたことをお許しください」などと添えるとよいでしょう。できるだけ訃報を知ってから一週間以内、遅くとも忌明け(四十九日)前までには届くようにします。
弔電と香典の関係ですが、これらはどちらか一方を送れば良いというものではありません。ご自身の立場や故人との関係性によって判断しましょう。一般的には、近しい間柄で本来なら香典を持参するような相手の場合は、弔電+香典の両方を送ることが多いです。弔電で気持ちと言葉を伝え、香典で経済的なお悔やみを表すイメージです。一方、取引先や上司など仕事関係で香典を送る習慣がない間柄であれば、弔電だけ送ることもあります。また、故人やご家族の意向で香典辞退(「ご厚志ご辞退」)の場合は弔電のみ送ります。このようにケースバイケースですが、「行けない代わりに何を送るか」を考える際、香典は本来参列者が持参するもの、弔電は不参の人が送るものという位置づけを踏まえて選択するとよいでしょう。
最新トレンド:デジタル弔電・自動送信サービスなど
時代とともに弔電の形態やサービスも少しずつ変化しています。近年の最新トレンドとしては、以下のような動きがあります。
インターネットでの申込みが主流に
前述のとおり、昔は「115番」に電話して電報を打つのが一般的でしたが、今ではほとんどの人がネットから申し込んでいます。スマホやパソコンから24時間受付可能で、文例選びも画面上で簡単にできるため、若い世代を中心にオンライン申込みが当たり前になりました。NTTもVERY CARDも郵便局もすべてWeb対応しており、電話より手軽で確実です。電報サービス各社は公式サイトやアプリを整備しており、リアルタイムで配達状況を確認できたり、会員登録すれば過去の送信履歴を管理できたりといったデジタル化が進んでいます。
新規参入やサービス多様化
電報はNTTだけでなく、佐川急便グループのVERY CARDやKDDIグループの「でんぽっぽ」など民間企業も参入し、市場が活性化しています。例えばVERY CARDは佐川急便の100%子会社が運営しており、物流ネットワークを活かした即日配達を武器に料金を低く抑えています。また、LINEやメールを使ったオンライン弔電サービスも登場しつつあります。これは正式な電報というより、ご遺族のスマホ等にお悔やみメッセージを届けるサービスで、コロナ禍で遠隔地から葬儀に参加できない人向けに利用が広がりました。写真や思い出のエピソードを添えて送れるといった特徴があります。
弔電自動送信サービス
企業向けには、社員や取引先の訃報を受けた際に社内システムから自動的に弔電を手配できるサービスもあります。例えば、社用システムに訃報情報を登録すると提携する電報サービスが自動で文例を選び電報を発送してくれるといった仕組みです。まだ一般的ではありませんが、業務効率化の一環で導入する企業も出てきています。将来的にはAIが文面をパーソナライズしてくれるようなサービスも考えられており、弔電分野にもDX(デジタルトランスフォーメーション)の波が及んでいます。
電子メールによる弔慰
フォーマルな場面ではありませんが、親しい友人間などではメールやSNSでお悔やみメッセージを送るケースも増えています。特に若い世代では電話よりもまずメールやLINEで知らせることも多く、それに対してお悔やみの返信をする形です。ただし、ビジネスや正式な弔意表明にはメールは軽すぎる印象を与えるため、あくまでカジュアルな範囲に留めるべきでしょう。正式にはやはり弔電や弔問状で気持ちを伝えるのがマナーです。
このように、弔電を取り巻く環境も少しずつ変わっています。しかし「相手を思いやる気持ちを迅速に届ける」という弔電本来の役割は今も昔も変わりません。デジタル化が進んでも、受け取ったご遺族にとっては一通の電報に込められた気持ちが何よりの慰めになります。「弔電なんて古いかな?」と尻込みせず、必要なときにはぜひ活用してみてください。形式にとらわれすぎず、心のこもった言葉を送ることが何より大切です。
まとめ
以上、弔電の送り方やマナーについて最新の情報を盛り込んで解説しました。大切な方を送り出す際のマナーとして少しでもお役に立てれば幸いです。不明点があれば電報サービスの窓口に問い合わせることもできますので、安心してご利用ください。礼儀を尽くしつつもあまり緊張しすぎず、あなたの真心が伝わる弔電を送りましょう。
弔電は安くてシンプルなVERY CARDがオススメ!
 格安弔電で評判!VERY CARDの特徴と使い方、文例、サービス比較(ベリーカード)
格安弔電で評判!VERY CARDの特徴と使い方、文例、サービス比較(ベリーカード)