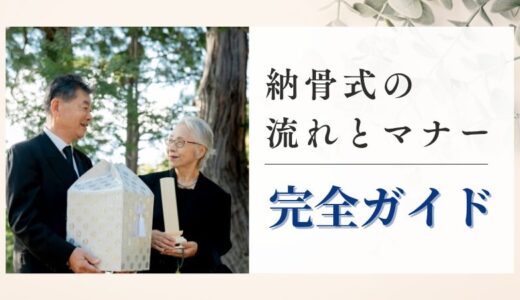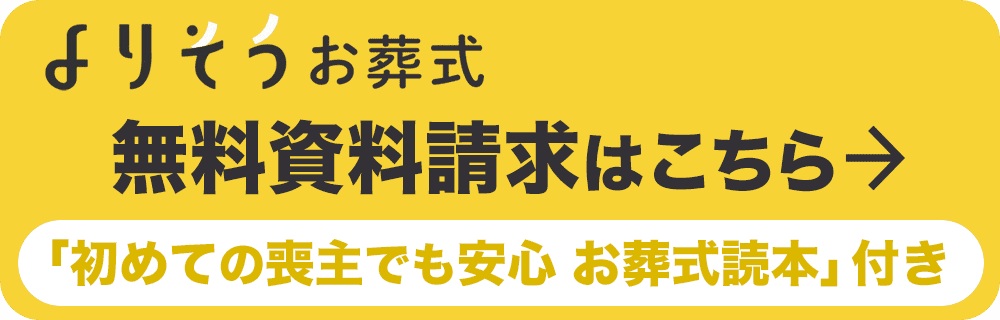少子化や核家族化が進むなか、「お墓を誰が守るのか」という悩みを抱える家庭が増えています。そうした事情に応える形で広がっているのが永代供養です。
寺院や霊園が遺骨の管理と供養を引き受ける仕組みで、後継ぎがいない人や子どもに負担を残したくない人にとって、無理のない供養の形といえます。
本記事では、小さなお葬式が提供する永代供養プラン「OHAKO」を取り上げ、費用の内訳やサービス内容、利用する際の注意点まで詳しく解説します。永代供養を検討する際は、ぜひ参考にしてください。
永代供養の基本

永代供養という言葉には「ずっと自分のお墓を持てる」という印象がありますが、実際の仕組みは少し違います。多くのケースでは、一定期間だけ個別に遺骨を安置し、その後は合同墓に合祀される流れになります。
宗派を問わず利用できることが多く、管理や清掃は寺院や霊園が担ってくれるため、遺族は参拝に集中できるのが特徴です。
ただし、内容を理解しないまま契約すると「思っていたものと違った」と感じることもあるので、まずは基本を押さえておくことが欠かせません。
永代供養の仕組み
寺院や霊園が遺族に代わって遺骨を預かり、契約に沿って供養や管理を続けていくのが、永代供養の基本です。
納骨の方法には大きく二つあり、一定期間は骨壺のまま個別に安置したあと合同墓へ移す場合と、最初から合祀する場合とがあります。合祀に入った遺骨は他の方と混ざるため、後から取り出すことはできません。その一方で、費用を抑えやすいという利点があります。
供養や法要の準備は施設が担うため、遠方に住む家族や高齢の遺族でも安心して任せられます。
 永代供養とは?仕組みから費用、メリット・注意点まで徹底解説
永代供養とは?仕組みから費用、メリット・注意点まで徹底解説
選べる納骨の形態
永代供養には、まず一定期間は骨壺のまま個別に安置し、その後に合同墓へ移す方式があります。気持ちの整理がつくまで時間を取りたいときや、夫婦で同じ時期に合祀したいときに選ばれることが多い方法です。
もう一つは、最初から合祀にする方式で、費用を抑えやすい反面、遺骨を後から取り出すことはできません。
どちらを選ぶかは、家族の考え方や将来的な改葬の可能性によって判断が分かれます。いずれにしても、期間や供養の方法、費用の内訳は契約時にしっかり確認し、書面で残しておくことが重要になります。
体験談:個別安置を選んだ理由
![]()
父の納骨をどうするか話し合ったとき、すぐに合祀する決断はなかなかできませんでした。
小さなお葬式の担当者から「まずは一年だけ個別に安置する方法もあります」と案内を受け、親族で相談した結果、その形を選びました。個別の期間があったことで、合祀に移す時期を家族みんなでじっくり考える余裕が生まれ、結果的に納得して進めることができました。
費用はやや増えましたが、心の整理をつけるための時間を持てたのは大きな意味があったと思います。(40代 女性)
利用前に知っておきたいこと
永代供養を検討するときには、見落としやすい注意点があります。特に次の点は事前に確認しておきたいところです。
- 合祀後は遺骨を取り出せないため、分骨や手元供養を望む場合は事前に準備が必要
- “永代”といっても三十三回忌など、一定期間で区切りを設ける施設が多い
- 供養の内容や法要の頻度、刻名の有無は寺院や霊園によって異なる
- アクセス条件や参拝のしやすさも契約前に確かめておくと安心
これらを理解してから契約すれば、後で「こんなはずではなかった」と感じる心配を減らせます。
特に、合祀後の取り出し不可や供養の頻度は家族の受け止め方に影響するため、あらかじめ話し合っておくことが大切です。
後悔しないための確認ポイント
永代供養は、個別安置と合祀を組み合わせる仕組みが中心で、合祀に入った遺骨を後から取り出すことはできません。そのため、分骨や手元供養を希望するなら納骨前に準備しておく必要があります。
また、供養の内容や法要の頻度、名前を刻む方法は施設ごとに違うため、必ず契約前に確認し書面で残すことが欠かせません。さらに、参拝のしやすさや立地環境も含めて家族と話し合えば、より納得して選べるでしょう。
後悔しないためには、基本的な仕組みを理解したうえで、条件を一つひとつ確認しておくことが大切です。
 遺骨を分ける方法と注意点|手元供養や遠方のお墓の悩みを解消
遺骨を分ける方法と注意点|手元供養や遠方のお墓の悩みを解消
OHAKOの特徴と費用

小さなお葬式では、葬儀のあとに利用できる納骨サービスとして「OHAKO(おはこ)」という永代供養プランを展開しています。全国の提携寺院や霊園を紹介し、定額制の明瞭な料金で納骨と供養を手配できる仕組みです。
従来は不透明になりがちだった費用を分かりやすく示し、生前契約にも対応しているため、自分の希望を前もって形にしたい人にも利用しやすい内容になっています。
選べる納骨先の種類
OHAKOでは、寺院境内の永代供養墓や納骨堂、公園型霊園の合同墓地など、多様な納骨先から選ぶことができます。
なかには樹木葬を取り入れている霊園もあり、自然に還りたいという思いにも応えられます。海洋散骨に対応した施設も紹介されるなど、従来型の墓石建立だけにとらわれない選択肢が広がっているのが特徴です。
都市部から地方まで対応しているため、暮らしの拠点や故郷に合わせて候補を探すことができます。
 自然葬の種類と手続き|海洋散骨・樹木葬・宇宙葬の完全ガイド
自然葬の種類と手続き|海洋散骨・樹木葬・宇宙葬の完全ガイド
費用の目安と内訳
OHAKOの永代供養基本プランは税込6万円で、納骨の際には僧侶による読経も行われます。この費用の中に必要な内容が含まれているため、土地代や墓石代のような大きな出費を別途負担する必要はありません。
料金はあらかじめ定額で決められており、追加で年間管理費を支払う心配もない仕組みです。
負担の見通しが立てやすい点は大きな安心材料となり、とくに年金生活の高齢者や単身世帯にとって計画を立てやすい選択肢といえるでしょう。
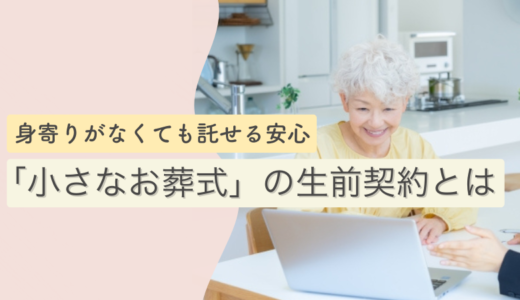 【2025年版】「小さなお葬式」の生前契約とは ― 身寄りがなくても託せる安心
【2025年版】「小さなお葬式」の生前契約とは ― 身寄りがなくても託せる安心
体験談:生前契約で安心できた例
![]()
子どもがいないので、自分が亡くなったあとに誰が納骨してくれるのか心配でした。
小さなお葬式で生前にOHAKOを申し込み、契約書類を家族に伝えておいたことで不安が和らぎました。費用が定額で決まっていたので、貯金の中から準備しやすかったのも助かりました。
契約してからは、死後のことを考えて落ち込むより「今を大切にしよう」と思えるようになりました。(60代 女性)
OHAKOを利用するときの注意点
OHAKOは料金が明瞭で選択肢も豊富なため、多くの利用者に安心感を与えています。ただし、提携先の寺院や霊園ごとに違いがあるため、候補を決める際には次の点を確認しておく必要があります。
- 合祀か個別安置(※)かの方式
- 合同法要の回数や開催時期
- 合同碑への刻名方法(俗名のみ、戒名や没年月日も含める など)
- 参拝できる時間帯や曜日の制限
- 立地や交通の便などアクセス条件
※個別安置は15,000円(税込)/ 1年間のオプションサービス。一部対応していない寺院もあります。
こうした点をあらかじめ確かめておけば、契約後に「思っていた内容と違う」と感じるリスクを減らせます。
納骨と供養の流れ

葬儀を終えた後、納骨や供養について戸惑うご遺族は少なくありません。小さなお葬式のOHAKOを利用すれば、申込みから納骨、そしてその後の供養までを一つの流れとして案内してもらえます。
事前に流れを理解しておくことで、葬儀後の慌ただしい時期にも落ち着きを保ちながら準備を進めることができるのです。
申込みから契約までのステップ
「何から始めればよいのか」と迷うときは、まずは資料請求や電話相談を利用してみましょう。
24時間対応の窓口に希望や予算を伝えると、条件に合った寺院や霊園を候補として示してもらえます。ウェブ検索を利用して探す方法もありますが、高齢の方にとっては電話でのやり取りのほうが安心しやすいでしょう。
候補が定まったら契約を結び、生前から準備を進めておくことも可能です。
納骨式の進め方
火葬を終えた遺骨は、選んだ寺院や霊園に運ばれ、日程を調整して納骨式を迎えます。多くの場合は合同墓に合祀され、僧侶の読経とともに埋葬が行われます。
遺族が立ち会えば最後の時間を一緒に過ごせますし、身寄りがない場合でも寺院が責任を持って手続きを進めてくれるので安心です。この際、市区町村から発行される「埋葬許可証」を提出すれば、法的な手続きも完了します。 参考 墓地、埋葬等に関する法律厚生労働省
合祀と個別安置の違い
納骨の方法には大きく分けて次の2つの方法があります。
- 火葬後すぐに合同墓へ合祀する方法
費用の負担を抑えやすく、手続きも簡潔に進められます。 - 一定期間だけ個別に安置してから合祀する方法
気持ちの整理に時間をかけたい場合に適しています。
個別安置では骨壺のまま納骨壇に安置され、時期が来れば合同墓に移されます。事情や心境に応じて選択できることが、永代供養の柔軟さでもあります。
納骨後の供養とお参り
納骨が終わっても供養は続きます。受け入れ先の寺院では年に一度以上の合同法要が営まれます。
- 年に1回以上の合同法要(お彼岸やお盆に合わせることも多い)
- 参列できる場合は僧侶の読経に合わせて手を合わせられる
- 参列が難しくても供養そのものは途切れない
- 合同墓の供養塔で花や線香を手向けて静かに偲ぶことができる
参拝の時間や条件は施設ごとに異なるため、契約前に確認しておくと安心です。
流れを理解して安心の準備を
申込みから供養までの道筋を知っておくことで、葬儀後の混乱した時期にも迷わず進めます。特に、合祀か個別安置かの選択や、参拝条件の確認は後悔しないために欠かせません。
OHAKOでは相談から納骨、そして供養までを一貫して支えてもらえるため、準備の過程が分かりやすくなります。こうした整った流れがあることで、故人を穏やかに見送る時間に気持ちを向けやすくなるのです。
OHAKOを利用するメリット

永代供養を小さなお葬式のOHAKOで申し込むと、経済面だけでなく心の負担まで軽くなるという声が多く寄せられています。料金の明確さ、豊富な選択肢、運営会社の実績といった要素が組み合わさり、遺族にとって安心できる仕組みになっています。
ここでは、主なメリットをまとめます。
家族の負担を軽くできる
従来のお墓では、掃除や草取り、年忌法要の手配といった役割を家族が担うのが一般的でした。体力的に大変なうえ、遠方に住んでいると通うこと自体が負担になりやすいものです。
永代供養では、清掃や管理を寺院や霊園が行ってくれるため、遺族は節目のときに参拝するだけで十分です。お墓を維持する義務から解放されることは、「子どもや親族に負担を残したくない」という思いを持つ方にとって大きな安心材料になります。
単身世帯や高齢夫婦だけの家庭でも取り入れやすい仕組みといえるでしょう。
明瞭で分かりやすい料金
従来のお墓は、墓地代・墓石代・工事費・管理費と複数の費用が発生し、総額が見えにくいものでした。
OHAKOは基本料金に必要な内容が含まれており、追加費用がかからない明朗な料金設計が特徴です。
| 従来のお墓で発生する主な費用 | OHAKOの永代供養プラン |
|---|---|
| 墓地の使用料 | 定額料金に込み |
| 墓石代・工事費 | 不要 |
| 年間管理費 | 不要 |
| 法要の読経料 | 納骨時に含まれる |
料金が一本化されていることで、特に年金生活の高齢者や単身世帯にとって計画を立てやすくなります。
全国から選べる利便性

OHAKOが紹介する納骨先は全国に広がっており、住んでいる地域だけでなく、実家のそばや思い出の土地を候補にすることもできます。
都市部のアクセスが良い霊園から、自然に囲まれた郊外の寺院まで選択肢はさまざまです。「親戚が集まりやすい場所にしたい」「自分は自然の中で眠りたい」といった希望も、複数の候補を比べながら検討できます。
条件や立地を柔軟に選べることは、将来にわたり無理のない供養を続けるうえで大きな利点になります。
実績と信頼による安心感
OHAKOを提供している小さなお葬式(運営:ユニクエスト社)は、全国で多くの葬儀を手がけてきた実績を持ちます。
葬儀件数は国内有数の規模に達しており、その延長として展開されている永代供養プランも信頼性の高いサービスといえます。大手メディアに取り上げられる機会も多く、社会的な認知度も備わっています。
利用者からは「質問に丁寧に答えてくれて安心できた」「強引な勧誘がなかった」といった声が寄せられており、サポート体制への評価も目立ちます。こうした実績と評判の積み重ねが、初めて永代供養を検討する人にとって心強い後押しとなります。
サービスの質に不安を感じやすい分野だからこそ、信頼できる会社が運営していることは大きな安心材料になるのです。
体験談:丁寧な対応で不安が解消された例
![]()
永代供養を検討していましたが、費用や手続きの流れが分からず不安でした。
資料請求をしてみると、スタッフの方が一つひとつ丁寧に説明してくれて、強引に勧められることもなく安心できました。おかげで家族とも話し合いやすくなり、納得して申し込むことができました。(70代 男性)
利用するメリットの整理
ここまでの内容を振り返ると、OHAKOの永代供養には次のような特徴があります。
- お墓守の負担を背負わせない
- 料金が明確で追加費用が発生しにくい
- 全国から希望に沿う場所を選べる
- 実績ある会社のサポートが受けられる
これらがそろっているからこそ、費用や供養の先行きを見通しやすくなります。永代供養を前向きに選び取るための、安心できる仕組みといえるでしょう。
利用時の注意点

永代供養は管理や費用の面で大きな利点がありますが、すべての人にとって完全に満足できる形とは限りません。契約してから「想像していたものと違った」と感じることがないように、事前に理解しておくべき点があります。
ここでは、利用を検討する際に押さえておきたい代表的な注意点を整理します。
合祀後は遺骨を取り出せない
合同墓に合祀された遺骨は、原則として二度と取り出すことができません。改葬を考える可能性がある場合や、分骨して一部を自宅に置きたいと望む場合は、納骨前に対応を検討する必要があります。
特に親族の中で「ゆくゆくは故郷のお墓に戻したい」と考える方がいると、後から大きなトラブルにつながりかねません。合祀を選ぶと取り返しがつかない点を理解し、事前に家族全員の合意を得ておくことが欠かせません。
 改葬手続きガイド ~新しい供養先の選び方と行政手続きの手引き~
改葬手続きガイド ~新しい供養先の選び方と行政手続きの手引き~
個別のお墓を望む人には不向き
合同墓では、個人ごとに墓石や専用の区画を持つことはできません。
多くの施設では供養塔や合同のプレートに名前を刻む程度で、従来のお墓のように形に残る区画は用意されていないのです。そのため「自分のお墓を建てたい」「家として代々守っていきたい」という希望が強い場合には不向きです。
ただし、永代供養墓の中には個別区画を備えたものや夫婦で利用できる区画型のプランも存在します。費用は高くなりますが、個別性を求める方はそうしたタイプを検討するとよいでしょう。
寺院や霊園ごとに内容が違う
永代供養といっても内容は一様ではなく、受け入れ先によって差があります。
例えば合同法要の回数や参拝条件、供花や線香が許されるかなど、契約後の過ごし方に直結する要素が異なるのです。
- 法要が年1回の施設もあれば、春秋のお彼岸やお盆に複数回行う施設もある
- 参拝できる時間帯が決められている場合がある
- 花や線香を供えられるかどうかが施設ごとに違う
こうした違いは契約前に確認しておくことが欠かせません。可能であれば現地を訪れ、住職や管理者の人柄や雰囲気も確かめると安心につながります。
参拝方法の確認が重要
合同墓の場合、個人の墓標はなく、供養塔の前でお参りする形になります。
参拝スペースが限られていることもあり、花や線香を手向けられる範囲に制限がある場合もあります。また、施設によっては開門時間が決まっているため、いつでも自由にお参りできるとは限りません。
納骨後に「思っていた形でお参りできない」と感じることがないよう、契約時に参拝方法や時間帯をきちんと確認しておくことが大切です。条件を理解しておけば、納骨後の参拝も落ち着いて続けられるでしょう。
注意点を理解したうえで選ぶ
永代供養は便利で利用しやすい反面、合祀後に遺骨を取り出せないことや、参拝条件が施設ごとに異なることなど、後から変更できない点がいくつもあります。
こうした事情を契約前に理解しておけば、「こんなはずではなかった」と感じる不安は小さくなります。
大切なのは、家族の意向を共有しながら納得できる方法を選ぶことです。自分たちに合った供養の形を見つけておけば、納骨後も落ち着いて故人を偲ぶ時間を持ち続けることができます。
他社サービスとの比較

永代供養サービスは近年需要が高まっており、大手を中心に複数の会社が似たような仕組みを提供しています。小さなお葬式のOHAKOの特徴を理解するためには、代表的な他社と比べてみることも大切です。
「よりそうお葬式」との違い
よく比較されるのが「よりそうお葬式![]() 」の永代供養です。両社とも全国対応で料金も数万円台と近い水準にありますが、細かなサービス内容に違いがあります。
」の永代供養です。両社とも全国対応で料金も数万円台と近い水準にありますが、細かなサービス内容に違いがあります。
- 合祀までの流れ
OHAKOは希望すれば有料オプションで一定期間の個別安置が可能(※一部寺院のみ対応)、よりそうは最初から合祀のみ。 - 供養法要の回数
OHAKOは年1回以上を基本とし、よりそうは年4回の合同法要を実施している。 - 料金設定
基本料金は大きな差はなく、いずれも追加費用が発生しにくい定額制。
「一定期間の個別安置を希望できるOHAKO」か「供養の回数が多いよりそうお葬式」か、重視する点によって向き不向きが分かれます。
その他のサービスの例
永代供養の仕組みはOHAKOだけでなく、他の大手葬儀会社でも提供されています。
たとえば「イオンのお葬式」や「ティアの永代供養墓」のように提携霊園の永代供養墓を紹介するサービスを行っています。さらに自治体や宗教法人が合葬墓を整備しているケースも増えており、選択肢は広がっています。
ただし、費用や利用条件は運営主体によって大きく異なるため、個別に探して比較するのは容易ではありません。その点、OHAKOは窓口ひとつで複数の候補を紹介してもらえる仕組みを持ち、検討を始める際に分かりやすい出発点となります。
比較から見えるポイント
複数のサービスを並べてみると、永代供養の基本的な仕組みは似ていても、細部に違いがあることがわかります。
OHAKOは合祀を前提としつつ、有料オプションで一定期間の個別安置を選べる点に柔軟さがあります。一方で、よりそうは合祀のみを基本とし、その代わりに合同法要の回数が多いといった特徴を打ち出しています。
その他の事業者や自治体の合葬墓も含めると、選択肢はさらに広がります。どの方法も「お墓の後継ぎを残さない」という目的は共通していますが、重視するポイントによって適したサービスは変わります。
自分や家族にとって何が優先なのかを整理しておくことが、後悔しない永代供養の選び方につながります。
永代供養を考えるときの道しるべ

ここまで小さなお葬式が提供するOHAKOを中心に、永代供養の仕組みや費用、他社との違いを見てきました。
永代供養は、お墓を継ぐ人がいない場合や家族に負担をかけたくない場合に、無理のない供養の形として選ばれています。管理や清掃は寺院や霊園が担い、遺族はお参りを通して故人を偲ぶことに専念できるからです。
一方で、合祀すると遺骨を取り出せないことや、施設ごとに供養内容や参拝条件が異なる点には注意が必要です。OHAKOは定額制で費用が明確、必要に応じて個別安置のオプションを選べる柔軟さが特徴ですが、それでも契約前の確認は欠かせません。
大切なのは「自分や家族がどのように故人を弔いたいのか」を整理し、納得できる形を選ぶことです。費用・供養の仕方・参拝のしやすさなど、何を重視するかによって最適な答えは変わります。
まずは資料を取り寄せたり現地を見学したりして、自分たちに合った供養の形を探してみることが、安心して未来を迎える第一歩となるでしょう。