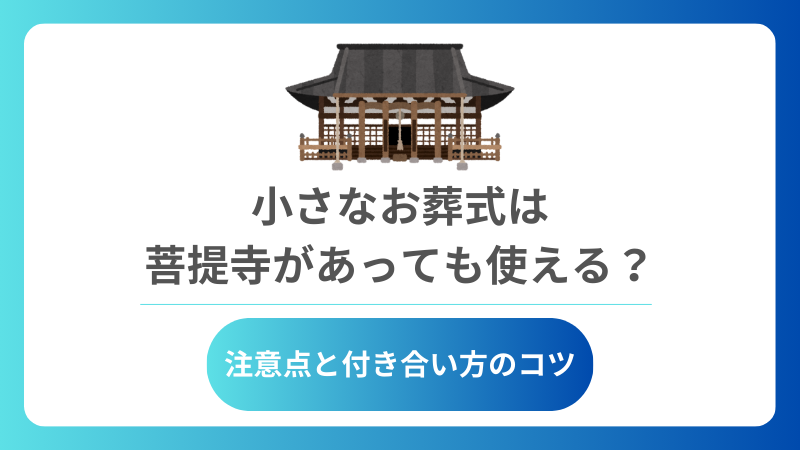菩提寺(ぼだいじ)とは、先祖代々の供養やお墓を任せてきた、家族と深いつながりを持つお寺のことを指します。しかし、近年は核家族化や都市部への移住が進み、「付き合いのあるお寺がない」という家庭も増えています。
こうした中で注目されているのが、費用を抑えてわかりやすいプランを提供する「小さなお葬式」です。ただし、すでに菩提寺がある家庭が利用する場合には、無視できないルールや注意点があります。
この記事では、菩提寺がある場合でも小さなお葬式を利用できるのか、その際に気をつけるべきポイントや円満に付き合うためのコツをわかりやすく解説します。
目次
小さなお葬式とは

費用を抑えつつ、シンプルで分かりやすい葬儀を行いたい方に人気なのが「小さなお葬式」です。
火葬式や家族葬といった小規模プランを、全国一律の定額料金で提供しており、累計の施行件数は59万件以上(2025年時点)※を誇り、葬儀の経験が少ない方や宗教的なつながりが薄い家庭にも利用しやすい仕組みが特徴です。
ここでは、小さなお葬式の仕組みや料金体系、僧侶紹介サービス「てらくる」の内容について詳しく解説します。
※対象期間:2009年10月~2025年3月 2025年4月 ユニクエスト調べ
「小さなお葬式」とは
小さなお葬式の最大の特長は、全国どこでも利用できる「定額制」の料金体系です。あらかじめセット内容と価格が明確に定められており、追加費用が把握しやすい点も特徴です
プランは「小さな火葬式」「小さな一日葬」「小さな家族葬」など、葬儀の規模や希望に応じて選ぶことができます。各プランには、寝台車での搬送・安置施設での管理・納棺・火葬手続きなど、基本的な項目がすべて含まれており、葬儀の経験がない方でも利用しやすい内容です。
資料請求を行うことで5万円の割引が受けられる特典も用意されており、予算に合わせた無理のない形で葬儀を実現できる仕組みになっています。
 「小さなお葬式」とは? 費用やプラン、口コミなど徹底的に調べてみました
「小さなお葬式」とは? 費用やプラン、口コミなど徹底的に調べてみました
僧侶紹介サービス「てらくる」の仕組み
小さなお葬式では、仏式での葬儀を希望する方向けに、僧侶の手配を代行するサービス「てらくる」も提供しています。
この「てらくる」は、付き合いのあるお寺(菩提寺)がない方でも、必要に応じて僧侶を紹介してもらえる仕組みです。2025年4月時点で全国1,500ヶ寺以上と提携しており、葬儀の規模や希望宗派に応じて信頼できるお坊さんを紹介してもらえます。
読経や戒名授与、法話などを含めたお布施は定額制で、税込85,000円から利用可能です。金額にはお車代や御膳料、心づけもすべて含まれており、「あとから追加で渡す費用は?」といった心配がありません。
お布施の金額が不明瞭になりがちな中で、費用がはっきりしている点は、多くの利用者に安心感を与えています。
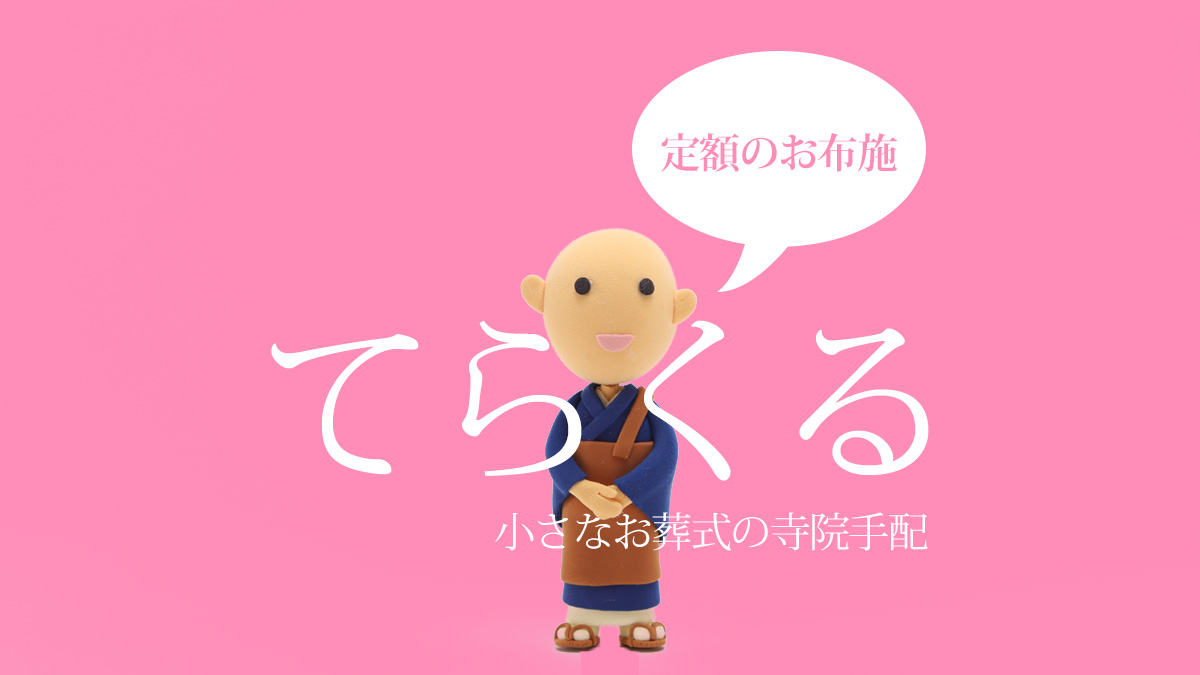 小さなお葬式の寺院手配「てらくる」とは?サービス内容と口コミ・評判を解説
小さなお葬式の寺院手配「てらくる」とは?サービス内容と口コミ・評判を解説
宗派や信仰に合わせた手配が可能
てらくるでは、希望する宗派に合わせて僧侶を紹介してもらえるため、「信仰の違いが心配」という方にも対応可能です。
対応しているのは、浄土宗・浄土真宗・真言宗・日蓮宗・曹洞宗・臨済宗・天台宗・時宗と、仏教八大宗派のほぼすべて。宗派によって焼香の作法や戒名の形式も異なるため、自分や家族の信仰に合った形で葬儀を行いたい方にとっては、大きなメリットです。
「先祖代々〇〇宗だけど、お寺とのつながりが切れてしまっている」といった場合でも、宗派を指定して葬儀ができます。また、信仰が特にない方でも、内容を丁寧に説明してくれるため、無理なく選べる安心設計となっています。
依頼後も檀家になる必要なし
てらくるで紹介される僧侶は、その場限りの依頼が前提となっており、葬儀後に継続的なお付き合いを求められることはありません。檀家制度や寄付の負担が不安という方でも、安心して利用できる点が多くの支持を集めています。
「僧侶が来てくれるのはいいけれど、強引な勧誘があったらどうしよう」と不安に感じる方もいますが、そうしたトラブルを防ぐ体制が整っています。
また、小さなお葬式では事前に僧侶の資格や人柄を確認しており、「満足度の高い寺院のみをご案内」と明記されています。必要な場面でのみ、信頼できる僧侶にお願いできるのは非常に実用的です。
菩提寺がある場合に知っておくべき基本ルール

「小さなお葬式」は、付き合いのあるお寺がなくても利用できる便利なサービスですが、すでに菩提寺(先祖代々の供養を任せてきたお寺)がある場合には、慎重な対応が求められます。
便利に見える仕組みでも、菩提寺との関係を考えずに進めると、思わぬ行き違いにつながることがあります。ここでは、菩提寺がある家庭が「小さなお葬式」を使う際に知っておくべき基本ルールを解説します。
菩提寺があっても利用自体は可能
まず結論から言えば、菩提寺がある場合でも「小さなお葬式」を利用することは可能です。ただし、どのような葬儀社を利用するかは、宗教的な意味だけでなく、お寺との信頼関係にも関わるため、事前の確認と相談が不可欠です。
小さなお葬式の公式サイトでも、「檀家である方は、必ず菩提寺の許可をいただいてからご利用ください」と明記されています。つまり、『利用は可能だが、無断で進めるべきではない』という意味になります」
特に高齢の親族がいる場合などは、お寺との関係性にもより丁寧な配慮が必要です
必ず事前に相談し了承を得ること
菩提寺との関係を保つうえで最も重要なのが、事前の相談です。
住職に無断で他のお寺の僧侶に葬儀を依頼してしまうと、「うちの檀家なのに、なぜ相談もなく他所で済ませたのか」と受け取られ、信頼関係が損なわれる可能性があります
実際、実家のお墓が菩提寺の敷地内にある場合、葬儀を他の僧侶で執り行ったことが原因で、納骨を断られたケースも報告されています。場合によっては、納骨に影響する可能性もあります
後々のトラブルを避けるためにも、まずは住職に相談し、事情を説明したうえで了承を得ることが何より大切です。
菩提寺との調整で困った人の声
実際に「小さなお葬式」を利用しようとして、菩提寺との間で戸惑った経験のある方もいます。
60代女性の体験談
![]()
読経はお願いしたいけど、会場のこともあって…と相談したところ、“それなら構わない”と了承してもらえました
→ 菩提寺側も事情を理解すれば柔軟に対応してくれるケースもあります。伝え方によっては、関係を保てることもあります
50代男性の体験談
![]()
結局、地元の葬儀社でお願いしました
→ 墓地の契約内容によっては、離檀・墓じまいの話に発展することも。早めの確認が不可欠です。
 墓じまいの進め方 ~費用や改葬手続き、親族への説明ポイント~
墓じまいの進め方 ~費用や改葬手続き、親族への説明ポイント~
読経だけ菩提寺に依頼する方法
「小さなお葬式を使いたいけれど、菩提寺との関係も大事にしたい」という場合には、折衷案として「読経だけ菩提寺にお願いする」方法があります。葬儀の手配や会場は小さなお葬式を利用しつつ、読経・戒名授与などは菩提寺のご住職に依頼するという形です。
この方法であれば、外部サービスを利用しながらも、故人の宗派や家のしきたりに沿った形で進められます。また、お寺との関係にも配慮しやすく、納骨や法要の流れも進めやすくなります
なおこの場合、紹介僧侶サービス「てらくる」の定額料金は適用されず、読経のお布施は通常どおり菩提寺にお納めすることになります。あらかじめ金額の目安を確認しておきましょう。
無断で進めると今後の供養にも影響
もし菩提寺に相談せずに葬儀を外部で済ませてしまった場合、四十九日や一周忌、納骨など、後々の供養で支障が出る可能性があります。「今回は仕方なかった」と住職が理解してくれる場合もありますが、そうでなければ、檀家としての扱いに影響が出るかもしれません。
「今後はお墓を移す予定」「納骨は別の場所で考えている」など、菩提寺との関係を解消する覚悟があるなら別ですが、そうでない場合は避けた方が無難です。一度関係が悪化すると、元に戻すのは簡単ではありません
葬儀だけ外部で行い、法要や納骨は改めて菩提寺にお願いするなど、関係の修復を意識した対応も検討しておきましょう
菩提寺がある場合の対応策と注意点

菩提寺があるご家庭が「小さなお葬式」を利用する場合、サービス自体は便利であっても、従来の宗教的慣習とぶつかる部分が出てきます。トラブルを避けながら葬儀の意向を尊重するには、丁寧な説明と事前の相談が重要です
ここでは、代表的な場面ごとの対応策と注意点をまとめました。
住職への相談は早めに行う
「小さなお葬式を使いたい」と考えたら、できるだけ早い段階で菩提寺に相談しましょう。
特に地方の寺院やご高齢の住職の場合、形式の簡略化や外部業者の介入に抵抗感を持つ方もいます。そのため、事情を率直に説明しつつ、「お寺をないがしろにするつもりはない」と丁寧に伝える姿勢が大切です。
相談が遅れるほど、お寺側も対応が難しくなることがあります。住職の理解を得られるよう、「本当はお願いしたいが、やむを得ずこういう形を取らざるを得ない」という立場を丁寧に説明していくことが大切です
早めの対応が、円満な進行の第一歩になります。
菩提寺と小さなお葬式を両立させる方法
サービスと宗教的しきたりの両立には、「できる範囲で住職にも関わってもらう」という工夫が効果的です。たとえば、葬儀そのものは小さなお葬式の会場で行いつつ、読経・戒名授与のみを菩提寺の住職にお願いする方法が挙げられます。
この場合、菩提寺としても「葬儀に関わった」という形が残り、後の納骨や法要もスムーズに進めやすくなります。葬儀を主催する立場としての体裁が保てれば、住職の心情もある程度くみ取ることができます。
もちろん、お布施は通常どおり寺院に直接納めることになりますが、家族の希望と寺院の意向の両方に配慮した進め方として現実的です
菩提寺を使わない場合のリスク
住職に理解を求めたものの承諾を得られず、それでも他のお寺で葬儀をする場合は、いくつかのリスクを覚悟する必要があります。も深刻なケースでは、『納骨を断られる』『檀家としての関係を継続できなくなる』などが挙げられます
お寺によっては「勝手に他で葬儀をしたこと」を非常に重く受け止めるケースもあり、年忌法要の依頼が難しくなる場合もあります。特にご実家のお墓がその寺にある場合は、後の世代にも不都合が及びかねません。
場合によっては「お墓の移動」や「墓じまい」を検討することも必要になります。
もし墓じまいをする場合は、「わたしたちの墓じまい![]() 」などの墓じまい代行サービスに依頼するとスムーズです。お寺との交渉から行政手続き、永代供養までサポートしてくれるため、安心して新しい供養の形を考えることができます。
」などの墓じまい代行サービスに依頼するとスムーズです。お寺との交渉から行政手続き、永代供養までサポートしてくれるため、安心して新しい供養の形を考えることができます。
こうした可能性を踏まえたうえで、「無宗教での供養」など、今後の方向性を見据えたうえでの判断が求められます。
葬儀後の供養も含めて段取りを考える

葬儀が終わっても、そこで区切りとなるわけではありません。四十九日、一周忌、三回忌といった法要の流れも見据えたうえで、段取りを組む必要があります。
小さなお葬式で手配できるのは基本的に「通夜〜葬儀」までであり、その後の供養は別途対応となります。
僧侶紹介サービス「てらくる」を再度利用することも可能ですが、本来は菩提寺がいる場合、こうした法要こそ寺院との関係が重視される場面です。たとえ葬儀を外部で行ったとしても、四十九日以降は菩提寺にお願いすることで、関係を見直すきっかけになる場合もあります
供養の一連の流れを中断しないためにも、葬儀後のことまで見据えて丁寧に準備しておきましょう。
どちらを選ぶかに“正解”はありません
小さなお葬式の「てらくる」は、費用の明確さや一時的な手配のしやすさに優れた仕組みです。
一方で、菩提寺には家族や地域との信頼関係があり、今後の供養や納骨も含めて長く支えてくれる安心感があります。それぞれに良さがあり、事情や価値観によって「自分に合った選び方」が異なります。
以下に主な違いを整理しましたので、迷ったときの参考にしてみてください。
| 項目 | てらくる | 菩提寺 |
|---|---|---|
| 僧侶の依頼方法 | 小さなお葬式が全国の登録寺院から手配(連絡・調整不要) | 自分でご住職に相談し、日程や内容を丁寧に話し合って決定 |
| 宗派の対応 | 仏教八宗派に幅広く対応(宗派指定も可) | 通常は固定の宗派(自宅のお墓や地域のしきたりに合わせやすい) |
| 費用のスタイル | 定額制(85,000円〜・すべて込み)で予算の見通しが立てやすい | お布施の金額は相談によるが、柔軟に対応してくれる寺院も多い |
| 継続的な関係の有無 | 一度限りの依頼でOK(檀家になる必要なし) | 四十九日や年忌法要など、長く寄り添ってもらえる心強い存在 |
| 葬儀後の法要対応 | 通夜・葬儀が中心。法要は希望に応じて別途依頼(寺院との継続関係は不要) | 法要・納骨・墓参まで一貫して依頼できるため、供養の流れを保ちやすい |
| 信頼・安心の面 | 小さなお葬式が事前に人柄・資格を確認した僧侶を紹介 | 地域や家族の歴史をよく知る住職が、相談に親身に乗ってくれる安心感 |
| 向いている人 | 菩提寺がない人、形式より柔軟さや費用の明快さを重視したい人 | 菩提寺がある人、信頼できる住職に長く相談しながら供養を続けたい人 |
菩提寺との関係を円満に保つための工夫

小さなお葬式を利用するにあたり、もっとも繊細で重要になるのが「菩提寺とのコミュニケーション」です。どれだけ合理的で便利なサービスでも、お寺との信頼関係を損ねてしまっては、後の供養や納骨に支障が出かねません。
ここでは、住職と良好な関係を保ちながら葬儀を進めるために意識しておきたいポイントをまとめました
直接会って説明するのが理想的
可能であれば、住職とは電話やメールではなく「直接会って話す」ことが望ましい方法です。長年のお付き合いがあるお寺ほど、形式や礼儀を重んじる傾向があります。丁寧な説明と対面での相談は、その信頼関係を守る第一歩です。
「今の時代はこういったサービスも増えているようで…」と、相手を立てながら背景を伝えることで、理解を得やすくなります。菩提寺側にとっても、急に“結果だけ”を知らされるより、事前に事情を聞いておくほうが心の準備ができます。
多少手間でも、こうした一言のやりとりが、今後の供養全体に大きく影響します。
感謝と事情説明をセットで伝える
経済的事情や家族の意向を正直に話すことは大切ですが、それだけでは「お寺を軽んじている」と受け取られてしまう可能性もあります。「いつもお世話になっていることへの感謝」を忘れずに伝えることが大切です。
たとえば、「本来はご住職にお願いすべきところですが…」「ご無礼を承知のうえで…」といった言葉を添えるだけで、印象は大きく変わります。お寺に対する敬意をしっかり示すことが、最終的に理解を得やすい雰囲気につながります」
伝えたいのは「お寺を外したい」のではなく、「苦渋の選択だった」という立場です。
お寺同士の関係性にも気を配る
紹介僧侶を依頼する場合、「別のお寺に読経を頼む」という行為自体が、菩提寺の住職の立場や感情を刺激することがあります。
これは“僧侶同士のマナー”や“お寺の面目”に関わる部分であり、遺族側にその意図がなくても、住職の側では「礼を欠いた」と受け取られる場合もあります。
そのため、「紹介で読経をお願いする形になりますが、できる限り失礼のないように進めたいと考えています」といった一言が効果的です。こうした配慮は、住職の気持ちをくみ取るだけでなく、自分たちの誠意を形として伝える手段にもなります。
葬儀後の法要で関係修復の姿勢を示す
たとえ葬儀を外部で済ませた場合でも、その後の四十九日や年忌法要を菩提寺にお願いすることが、関係を見直す機会になります、「このたびは事情があり、やむを得ず他で葬儀をお願いしましたが、今後はぜひお寺でお願いしたい」と、あらためて意向を伝えるのも良い方法です。
住職も「これで縁が切れるのか」と心配していたところに、遺族から丁寧な申し出があれば、わだかまりが和らぐ可能性があります。特に納骨や一周忌など、区切りの法要は、関係を結び直す絶好のタイミングです。
失礼があったかもしれないと感じた場合ほど、後の対応で誠意を示すことが大切です
よくある質問|小さなお葬式と菩提寺の付き合い方

「小さなお葬式を使いたいけれど、菩提寺がある場合はどうすればいいの?」「てらくるを使って大丈夫?」
読者の方からよく聞かれる疑問を、Q&A形式でまとめました。不安や迷いを整理しながら、納得のいく選択につなげるための判断材料として役立てていただけるでしょう。
菩提寺があっても「てらくる」を使っていいの?
原則として、ご住職の了承がある場合に限り使うことができます。
てらくるは、付き合いのあるお寺がない方を主な対象としたサービスです。檀家でありながら無断で利用すると、住職の不信感を招き、納骨や法要に支障が出る可能性があります。
事前に住職へ事情を説明し、「今回は外部に依頼してもよい」と了承を得ていれば、てらくるを使っても問題ありません。どうしても相談しにくい場合でも、あとから納骨や法要をお願いする可能性があるなら、先に一言伝えておくとスムーズです
菩提寺の了承が得られなかった場合は?
無理に進めず、菩提寺を含めた形で折衷案を検討するのが望ましいです。
了承が得られなかった場合でも、話し合いの余地が残っていることもあります。たとえば「会場は小さなお葬式の式場を使い、読経だけ住職にお願いする」といった妥協案が可能です。
どうしても外部で葬儀を行いたい場合は、今後のお墓や供養をどうするかも含めて家族で話し合っておく必要があります。最終的に菩提寺との関係が続けられない場合、墓じまいや納骨堂への移転なども視野に入るため、慎重な判断が求められます。
紹介された僧侶と葬儀後も付き合いが必要?
てらくるは一度きりの依頼で継続的な付き合いは不要です。
てらくるで手配される僧侶は、葬儀の読経や戒名授与などを行ったあと、基本的には一度きりの対応となります。檀家になる必要はなく、以後の寄付や年会費などを求められることもありません。
ただし、葬儀後に四十九日法要や納骨を同じ僧侶にお願いしたい場合は、そのお寺に直接相談する形になります。関係を継続するかは利用者が自由に決められる点が、てらくるの利便性の一つといえます
菩提寺とてらくる、どちらに頼めばいいか迷ったら?
まずは「菩提寺があるかどうか」「供養をどこまで任せたいか」で考えてみましょう。
菩提寺があり、今後もお墓や法要をお願いする予定があるなら、まずはそちらに相談するのが基本です。一方、菩提寺がなく継続的な付き合いも考えていないなら、てらくるのような定額サービスが合っているかもしれません。
迷った場合は、小さなお葬式の事前相談窓口(24時間対応)で「こういう事情だがどうすればいいか?」と聞いてみるのもおすすめです。中立的な立場で選択肢を整理してくれるため、落ち着いて判断ができるでしょう。
菩提寺と小さなお葬式を両立させるために

小さなお葬式は、明確な料金体系と安心のサポートで、多くの家庭に選ばれている便利なサービスです。一方で、菩提寺との関係を大切にしてきたご家庭にとっては、その活用に慎重さが求められる場面も少なくありません。
重要なのは、『住職に了承を得ること』『誠意を持って説明すること』です
葬儀だけを小さなお葬式に任せ、法要は菩提寺にお願いするといった折衷案も有効です。提携寺院サービス「てらくる」は便利な制度ですが、菩提寺がある場合には、状況によっては利用を控えた方が適している場合もあります
どうしても外部サービスを使いたい事情があるなら、後の法要や納骨で関係修復を図ることも選択肢に含めましょう。信頼関係を保ちながら新しい葬儀の形を取り入れることが、納得のいくお見送りにつながります