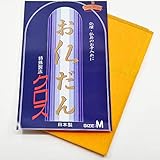この記事では、お仏壇の「よくある疑問」に分かりやすく答えていきます。
- ご購入の仕方
- 選び方
- 置く場所
- 飾り方
- お参りの仕方
さらには、「お手入れの仕方」「引っ越しと移動」「処分方法」までをみてきます。
(この記事の下に移動します。)
仏壇とは
そもそも仏壇とは?

※「須弥壇しゅみだん(内陣)」のイメージ
「仏壇」は、寺院の本尊を安置する壇である「須弥壇(しゅみだん・内陣)」をモデルに小型化されたものです。
たとえて言えば、家庭のなかに設ける小さなお寺のような存在で、ご先祖や家族の位牌を安置する場所になります。
日本で仏壇が普及したのは江戸時代の寺請制度が始まってからで、この頃から各家に仏壇を置き、朝夕の礼拝や命日に供養を行う習慣が一般家庭に広まっていきました。
仏壇の種類はなにがあるの?
仏壇は大きく次の3タイプに分けられます。
- 金仏壇(塗仏壇)
- 唐木仏壇
- 家具調(モダン)仏壇
それぞれの特徴は、次の通りです。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 金仏壇(塗仏壇) | 白木に漆を塗り、金箔や金粉を施した仏壇。特に浄土真宗で多く用いられ、本堂(内陣)の様式を模することが一般的。 |
| 唐木仏壇 | 唐木(シタン、コクタン、タガヤサンなどの輸入銘木)を使用した仏壇。宗派を問わず広く用いられる。 |
| 家具調(モダン)仏壇 | 現代的な住居に合うようにデザインされた仏壇。小型でシンプルなデザインのものが多い。 |
近年はデザイン性を重視したモダンタイプも広く普及しています。
仏壇を置く場所
仏壇を置く部屋はどこ?
昔の家には仏壇を安置するための「仏間」が設けられていることが多くありました。

現在では仏間のない住宅も増えており、仏壇を購入するときに置き場所に迷う人もいます。その場合は、和室に仏壇を置くスペースを作ったり、床の間や居間に安置する方法が一般的です。
また、仏壇を長持ちさせるためには直射日光を避け、風通しの良い場所に置くことも大切です。
仏壇の向き・方角は?

家に仏壇を置く際、どの方角に向けるかを気にする方も多いでしょう。
仏教では仏はどの方角にもおられるとされ、基本的にはどの方角に安置しても問題ありません。何よりも大切なのは、家族が落ち着いてお参りできる場所に置くことです。
その一方で、仏壇の向きに特別な意味を持たせる考え方もあります。代表的なものは、次の3つの説です。
- 南面北座説
- 西方浄土説
- 本山中心説
それぞれをみていきます。
南面北座説について
仏壇を南に向けて、部屋の北側に安置する考え方です。これは古代中国で高貴な人は南を向き、家来は北を向いたという慣習に由来します。
この置き方では仏壇が北側にあるため直射日光が当たりにくく、風通しも良いため仏壇を長持ちさせるのに適しているとされます。逆に、南側は日差しが強いため、仏壇を北向きに置いてはならないと言われるようになった理由の一つとも考えられています。
西方浄土説について
阿弥陀仏の極楽浄土が西にあるとされることから、西を向いて拝めるように仏壇を東側に安置するという考え方です。
さらに、インドでは東が日の出の方角とされ、立身出世の象徴として主人が東に向かって座る慣習があったことも由来のひとつとされています。
本山中心説について
宗派の総本山がある方角を拝むように仏壇を安置する考え方です。この場合は家の所在地によって安置する方角が異なります。
神棚と仏壇の位置関係は?

神棚がある家では、仏壇と同じ部屋に安置しても差し支えありません。ただし、いくつかの注意点があります。
まず、神棚と仏壇を向かい合わせにしないことです。片方にお参りするときにもう一方へ背を向ける形になるため、別々の部屋であっても向かい合わせは避けた方がよいとされています。
また、神棚と仏壇を上下に重ねて安置するのも避けるのが一般的です。これは家相の考え方によるもので、あまり気にしない場合は問題ないともされます。神棚と仏壇を上下に置く場合は、どちらにお参りしているか分かるように位置を少しずらして安置する方法がよく取られています。
仏壇の飾り方

宗派ごとの本尊と脇掛の飾り方
仏壇の最上段には、中央に宗派ごとの本尊を安置します。本尊は仏像の場合もあれば、掛軸の絵像の場合もあります。その両脇には、脇掛として各宗派の祖師像や名号の掛軸を飾るのが一般的です。
下記は代表的な例ですが、宗派内でも寺院や地域によって異なることがありますので、詳しくは菩提寺や仏具店に確認すると安心です。
| 宗派 | 脇掛(左) | 本尊(中央) | 脇掛(右) |
|---|---|---|---|
| 天台宗 | 伝教大師 | 阿弥陀如来 | 天台大師 |
| 真言宗 | 不動明王 | 大日如来 | 弘法大師 |
| 浄土宗 | 法然上人 | 阿弥陀如来 | 善導大師 |
| 浄土真宗本願寺派 | 蓮如上人 | 阿弥陀如来 | 親鸞上人 |
| 浄土真宗大谷派 | 九字名号 | 阿弥陀如来 | 十字名号 |
| 臨済宗 | 各派ごと | 釈迦如来 | 各派ごと |
| 曹洞宗 | 常済大師 | 釈迦如来 | 承陽大師 |
| 日蓮宗 | 大黒天 | 曼荼羅 | 鬼子母神 |
仏壇の位牌の位置
仏壇には先祖や亡くなった家族の位牌を安置します。
安置の場所はご本尊の左右か、一段低い位置が一般的です。向かって右側が上座、左側が下座とされるため、右から年功序列で並べていきます。
位牌が増えて仏壇に収まらなくなったときは、複数の位牌を一つにまとめられる繰出位牌(回出位牌)を用いると便利です。繰出位牌には10枚前後の札板を収めることができ、通常は五十回忌などの弔い上げまでは個別の位牌を祀り、その後は先祖代々の繰出位牌にまとめることが多いです。
なお、位牌を安置するときはご本尊を隠さないようにすることが大切です。宗派によっては位牌を安置しない場合もあるため、菩提寺に確認しておくと安心です。
お供えの飾り方
ご本尊や脇掛、位牌の下にはお供え用の仏具を並べます。
中央のご本尊の前に仏器膳を置き、その上に仏飯器(右側)と茶湯器(左側)を安置します。仏器膳の左右には高月を置き、お菓子や果物を供えます。
実際に供物をのせるときは半紙を敷くのが一般的です。
以下は主な仏具と役割の例です。
| 仏具 | 役割 |
|---|---|
| 仏器膳 | 茶湯器・仏器膳を置く台 |
| 茶湯器 | お供えのお茶や水を入れるための湯呑み |
| 仏飯器 | お供えのご飯を盛るための仏具 |
| 高月 | お供えのお菓子・果物を盛るための仏具 |
三具足・五具足の飾り方

仏壇の最下段には、香炉・火立・花立で一組となる三具足を並べます。基本的な配置は中央に香炉、右に火立、左に花立です。これに加えて火立と花立を左右一対でそろえる五具足の形もあります。
さらに、その手前や下段には線香差・マッチ消、リンとリン棒を置きます。一般的には左に線香差やマッチ消を、右にリン布団を敷いてリンを置きます。
リン棒は浄土真宗ではリンの中に置きますが、他宗派では決まった位置はなく、リンのそばに置くことが多いです。
| 仏具 | 役割 |
|---|---|
| 香炉 | お香を焚くための仏具 |
| 火立て | ろうそくを立てるための台 |
| 花立 | 花を供えるための仏具 |
| リン | リン棒で叩いて鳴らし、仏様を呼ぶための仏具 |
| リン棒 | リンを叩く棒 |
| 線香差 | 線香を刺しておくための台 |
| マッチ消 | 使用したマッチを入れるための容器 |
仏壇に遺影を飾ってもよいか?
仏壇に遺影を飾る人もいますが、これについては意見が分かれます。本来仏壇はご本尊と先祖の位牌を祀る場所であるため、仏具店などでは遺影は仏壇の外に置くことを勧めています。
それでも遺影を手を合わせる対象として飾りたい場合は、本尊が隠れないよう仏壇の手前に置くようにします。迷うときは菩提寺の住職に相談すると安心です。
仏壇の外に飾る場合は、和室であれば長押や鴨居に掛けるのが一般的で、仏壇や神棚の真上は避けるべきとされています。場所がないときは、神棚と同じように少し位置をずらすのがよいでしょう。
最近は和室のない住宅も多いため、仏壇の中に遺影を置く家庭もあります。
仏壇のお参りの仕方

基本的には朝夕の2回
仏壇へのお供えとお参りは、一般的に朝食前と就寝前の1日2回行うのが基本とされています。
朝のお参り
- 仏壇の扉を開け、掃除を行う
- 仏飯、お水(お茶)、お花などをお供えする
- 正座してロウソクを灯す
- 線香をあげ、リンを鳴らす
- 合掌、お経・題目を唱える
- ロウソクの火を消し、仏飯を下げる
就寝前のお参り
- 仏飯をお供えする
- 正座してロウソクを灯す
- 線香をあげ、リンを鳴らす
- 合掌、お経、題目を唱える
- ロウソクの火を消し、仏飯を下げる
仏壇の線香の本数と作法
線香の本数や立て方は宗派によって異なります。以下は一般的な例ですが、詳しくは菩提寺に確認すると安心です。
| 宗派 | 線香の本数と作法 |
|---|---|
| 天台宗 | 3本をまとめて立てる |
| 真言宗 | 3本を正三角形になるように立てる |
| 浄土宗 | 特に定めはない |
| 浄土真宗本願寺派 | 1本を2,3に折って寝かせる |
| 浄土真宗大谷派 | 1本を2,3に折って寝かせる |
| 臨済宗 | 1本を立てる |
| 曹洞宗 | 1本を立てる |
| 日蓮宗 | 1本または 3本を立てる |
仏壇のお参りのマナー
仏壇にお参りするときの基本的なマナーも押さえておきましょう。
- ろうそくの火は息で吹き消さず、仏扇や火消しの道具を使います。
- リンを鳴らすかどうかは宗派や家庭で異なり、浄土真宗では勤行以外では鳴らしません。
- 他家でお参りする際は、その家の宗派に合わせるのが望ましく、分からない場合は自分の作法でも差し支えありません。
- 他家のお仏壇にお参りする際は、他宗派のお経は避けたほうがよいでしょう
- 「不幸があったときに仏壇の扉を閉める」という習慣が言われることもありますが、仏教上の決まりではなく神道の考え方に由来するとされています。
仏壇の購入・選び方

仏壇を安置するときは開眼法要が必要
仏壇は家具のようにただ置くだけではなく、魂を迎えるための法要が必要です。これを「開眼法要」と呼び、入魂式や魂入れと表現されることもあります。
ただし、浄土真宗には魂を込めるという考え方がないため、仏壇を安置する際は「御移徙(ごいし・おわたまし)」と呼ばれる慶事の法要を行います。いずれの場合も、開眼法要や御移徙は菩提寺に依頼して執り行います。
仏壇を購入する時期
仏壇は本来、先祖供養に限らず、家庭で仏様を拝むための小さなお寺とされています。
「生前に仏壇を買うと不幸がある」と言われることもありますが、これは根拠のない迷信です。実際には、亡くなった家族の位牌を安置する必要が出たときに購入を検討する人が多いようです。
購入のタイミングとしては、四十九日法要や一周忌・三回忌といった年忌法要、お盆の法要などがよく選ばれます。開眼法要が必要になるため、こうした法要と合わせて執り行えば、一度で済ませることができます。
仏壇の価格と相場
仏壇の価格はデザインや材質、工法によって幅があり、10万円前後のものから100万円を超える高級品までさまざまです。価格を左右するのは、仏壇の大きさや素材、装飾の度合い、工法へのこだわりなどです。
金仏壇は各宗派の本山を模して金箔など華やかな装飾が施されるため、基本的に高額になります。反対に都市部の住宅でも設置しやすいミニ仏壇は小型で、価格も比較的手頃です。
唐木仏壇は使用する木材の種類や品質によって価格が大きく変わります。
金仏壇に使われる金箔の純度には
- 五毛色
- 1号色
- 2号色
- 3号色
- 4号色
さらに、漆の品質や塗り重ねの回数によっても価格が変わり、丁寧に塗り重ねられたものは価値が高く耐久性も優れています。
また、仏壇の有名名産地の中には経済産業省の伝統工芸品に認定されているものもあります。
「伝統的工芸品」とは、次の要件を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和49年法律第57号、以下「伝産法」という。)に基づく経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。
- 主として日常生活で使用する工芸品であること。
- 製造工程のうち、製品の持ち味に大きな影響を与える部分は、手作業が中心であること。
- 100年以上の歴史を有し、今日まで継続している伝統的な技術・技法により製造されるものであること。
- 主たる原材料が原則として100年以上継続的に使用されていること。
- 一定の地域で当該工芸品を製造する事業者がある程度の規模を保ち、地域産業として成立していること。
仏壇を選ぶ際は、どの程度の品質を重視するかを考えて予算を決めるとよいでしょう。
オススメの仏壇店
仏壇は地域の仏壇店や菩提寺からの紹介などがありますが、最近ではネット上で低価格で購入できる店舗があります。
「recole(リコレ)」
「recole(リコレ)」は定額葬儀ブランド「小さなお葬式」が運営する公式ショップで、仏壇や位牌をはじめとした供養品を取り扱っています。
仏壇は「モダン仏壇」「唐木調仏壇」「デザイン仏壇」「ステージ型仏壇」など種類ごとに分かれており、住宅事情や好みに合わせて選びやすいのが特徴です。ステージ型仏壇の一部には必要な仏具がセットになった商品も用意されています。価格帯はおよそ1万5,000円から15万円台までと幅広く、コンパクトなものから本格的な唐木調まで揃っており、現代の住空間に合った選び方ができます。
位牌についても9,800円(税込10,780円)から56,980円(税込)まで揃っており、文字入れは無料で対応してくれます。仏壇・位牌ともに購入価格にかかわらず全国送料無料で届けてもらえる点も安心です。
「いい仏壇」
「いい仏壇」は、「いい葬儀」「いいお墓」などを運営する鎌倉新書が提供する、日本最大級の仏壇・仏具店クーポンサイトです。
全国5,000店以上の仏壇店を掲載しており、地域や予算、口コミなどから検索して、気になる店舗で実物を確認・購入できます。口コミ件数は3万件以上にのぼり、初めて仏壇を購入する人にとって参考になります。
対象店舗でクーポンを発行すると、店頭での購入金額が5%割引となり、さらに購入後にアンケートへ回答すると購入金額の3%分がAmazonギフトカードで還元されます。店舗によっては追加特典を実施している場合もあり、実店舗で仏壇を選びたい方にとって便利なサービスです。
仏壇のお手入れ
仏壇の掃除
仏壇はロウソクの火や線香の煙で汚れやすいため、こまめな掃除が欠かせません。掃除の際は雑巾よりも柔らかい布を使い、仏壇専用のクロスを利用するのもよいでしょう。木や漆を使った仏壇は湿気に弱いため、水拭きをした場合は必ず乾拭きで仕上げ、水分を残さないことが大切です。
仏壇の修理・修繕
仏壇内部が黒ずんだり、塗りや金箔が剥がれたりした場合は、早めに修理を依頼するのが安心です。
部分的な出張修理で済むこともありますが、全体を修復する「お洗濯」が必要になる場合もあります。特に金仏壇は金箔や漆仕上げが施されているため、専門の職人による修理が欠かせません。
修理は購入した仏壇店に相談するのが基本ですが、近年は修理やクリーニングを専門に行う業者も増えています。
仏壇の引っ越しと移動

仏壇の引っ越しには閉眼供養と開眼供養が必要
開眼法要を行った仏壇は魂が宿るものとされ、むやみに動かさないのが基本です。引っ越しなどで移動が必要なときは、一度閉眼法要(魂抜き)を行い、移動先で改めて開眼法要(魂入れ)を営むのが一般的です。
引っ越しの際には、仏壇は家財の中で最後に出し、新居では最初に入れるという習わしもあります。具体的な流れは次のとおりです。
-
およそ1か月前までに菩提寺へ依頼し、閉眼法要と開眼法要の日程を決める
-
引っ越し日前日までに閉眼法要(魂抜き)を行う
-
仏壇を最後に搬出し、新居では最初に安置する
-
引っ越し後はできるだけ早く開眼法要(魂入れ)を行う
家内での仏壇の移動
本来は仏壇を家の中で別の部屋に移す場合でも、閉眼法要や開眼法要を行うのが正式とされています。ただし、近年では引っ越しの際でさえ法要を省略することもあるため、家庭内での移動については法要を行わないケースも増えています。
特に大型の仏壇は移動の際に怪我や破損の恐れがあるため、自分で無理に動かさず、購入した仏壇店や仏壇の移動に対応できる業者に依頼するのが安心です。
仏壇の処分
仏壇の処分の方法
仏壇を処分する際は、魂が入ったままでは行えません。必ず菩提寺に依頼して閉眼法要(魂抜き)をしてから処分します。
菩提寺にお焚き上げしてもらう
閉眼法要のあと、そのまま仏壇を引き取り、お焚き上げをしてくれる菩提寺もあります。
処分費用はお布施という形で渡すのが一般的で、金額は決まっていないことが多いため、事前に確認しておくと安心です。
仏壇店に引き取ってもらう
購入した仏壇店や買い替え先の仏壇店で処分を依頼できることもあります。引取サービスの有無や費用は店舗によって異なり、中には無料で対応してくれるところもあります。
粗大ごみとして出す、専門業者に回収を依頼する
菩提寺や仏壇店での対応が難しい場合は、自治体の粗大ごみとして処分できます。その際は各自治体で定められた処分費用がかかります。
また、大型の仏壇などは仏壇処分の専門業者に依頼する方法もあります。費用はかかりますが安全かつ確実です。
まとめ
ここまで仏壇に関するさまざまな疑問について解説してきました。
この記事が仏壇について考えるきっかけになれば嬉しく思います。