納骨式とは、火葬後の遺骨をお墓や納骨堂などに納める儀式です。葬儀後、遺骨はしばらく自宅に安置され、その後に納骨式で正式に埋葬します。これは遺族にとって一区切りとなる大切なセレモニーであり、故人を偲び冥福を祈る最後のお別れの場でもあります。
納骨式を行うことで、遺族は故人の死を少しずつ受け入れ、気持ちの整理をつけていくことができるとも言われます。
本記事では、納骨の時期の考え方(四十九日・一周忌・三回忌など現代の傾向)や、納骨式の準備手順(菩提寺や石材店との打ち合わせ、開眼法要など)、お墓以外の新しい供養の選択肢(納骨堂・永代供養墓・樹木葬・散骨など)、卒塔婆の意味と宗派ごとの違い、お布施・御膳料・石材店への寸志など費用相場、家族構成の変化や宗教観の多様化を踏まえた納骨式のあり方、そしてオンライン法要や納骨代行といった最新サービスまで、現在の最新情報を交えて分かりやすく解説します。読み終える頃には、納骨についての疑問がすべて解消できるでしょう。それでは、納骨式の基本から見ていきましょう。
目次
納骨の時期はいつ?〜四十九日、一周忌、三回忌…柔軟になった現代の納骨時期

「納骨はいつ行えばいいのか?」これは多くの方がまず疑問に思うポイントです。結論から言えば、納骨の時期に明確な決まりはありません。法律的にも「○日以内に納骨しなければならない」という期限は定められておらず、遺族の事情や気持ちに合わせて行って差し支えないのです。
一般的には忌明けとなる四十九日法要に合わせて行うことが最も多いですが、お墓の準備が間に合わない場合などは百箇日(ひゃっかにち)や一周忌(満1年)、さらには三回忌(満2年)などの節目に合わせて納骨式を行うケースもあります。実際、四十九日以外にも一周忌やお盆、三回忌に親族が集まった際に納骨するご家族も少なくありません。ただし、三回忌(満2年)を過ぎると次の法要までかなり期間が空いてしまうため、遅くとも三回忌までに納骨するのが一般的とも言われます。とはいえ、あまり神経質になる必要はなく、ご家族が納得できるタイミングで行うことが大切です。
一方、地方の風習や各家庭の事情によってはもっと早く納骨する場合もあります。例えば「亡くなってから3か月をまたがないように」と、四十九日より前(忌明け前)に納骨してしまう地域もありますし、火葬してからすぐにお墓に納める地域もあります。逆に、お墓がすぐに用意できない場合や諸事情で納骨を延期したい場合、遺骨を長く自宅で安置しておくことも可能です。法律上も問題なく、実際に「手元供養」といって遺骨を自宅で保持し続ける選択をする人も増えています。手元供養の場合、一部の遺骨を小さな骨壺やアクセサリーに分けて手元に置き、残りをお墓に納めるという方法もあります。こうした形で故人を身近に感じながら、自分たちのペースで納骨のタイミングを計ることが、現代では受け入れられるようになってきています。
 遺骨を手元供養したい方へ:基礎知識と進め方ガイド
遺骨を手元供養したい方へ:基礎知識と進め方ガイド
ポイントとして、焦って準備が整わないまま納骨を迎える必要は全くありません。たとえば「早く納骨しなければ」と高額な墓石を慌てて購入して後悔するよりも、時間をかけて故人にふさわしい納骨先や供養方法を選ぶ方が大切です。納骨式はあくまで故人と遺族の気持ちを大切に行うものです。家族や親族とよく話し合い、心が落ち着いてからベストな時期に執り行いましょう。
納骨式の準備と流れ:菩提寺・石材店への連絡から必要なものまで

納骨の時期が決まったら、事前の準備と段取りに取りかかります。ここでは、納骨式当日までに何をすべきかを順を追って説明します。
菩提寺への相談と日程調整
まず、菩提寺(先祖代々のお寺)がある方は住職(お坊さん)に納骨式をお願いする連絡をします。日程を相談し、どの法要(四十九日や一周忌など)と合わせて行うかを決めましょう。お寺で執り行う場合はお寺の予定がありますし、遠方の墓地で行う場合はお坊さんに現地まで来てもらう必要があるため、できるだけ早めに打ち合わせしておくことが大切です。特に土日祝など希望日がある場合は、早めに菩提寺に相談しておけば、都合が合わない際に同じ宗派の別のお坊さんを紹介してもらえることもあります。
菩提寺に相談する際に確認しておくポイントは以下のとおりです。
卒塔婆(そとば)が必要かどうか
宗派によっては卒塔婆を立てない場合もあります(浄土真宗は卒塔婆供養の習慣がありません)。必要な場合は本数と料金を確認しておきましょう(卒塔婆の詳細は後述)。卒塔婆料は一般に1本あたり数千円〜1万円程度で、お布施とは別に封筒に包んで渡します。
開眼法要(かいげんほうよう)の依頼
新しくお墓や墓石を建てた場合、そのお墓に魂を入れる儀式である開眼供養(魂入れ・入魂式とも言います)を納骨式と合わせて行う必要があります。開眼法要もお坊さんにお願いするものなので、納骨式と合わせて依頼し日程調整します。
お斎(おとき)への参加可否
納骨式後に僧侶を交えて会食(お斎)を行うかどうかも確認します。お斎とは法要後の食事の席のことです。菩提寺の住職がお斎を辞退される場合は、お礼として御膳料(ごぜんりょう)を別途用意しておきます(御膳料についても後述します)。
菩提寺がない場合や無宗教で行いたい場合は、僧侶への依頼は不要です。この場合は後述するように家族のみで納骨式を行うことも可能ですが、墓地によっては管理者(霊園スタッフなど)に立ち会いをお願いすることがあります。
石材店への連絡とお墓の準備
次に、お墓を管理している石材店にも連絡をします。既にお墓(墓石)がある場合でも、新たに故人の情報を刻むなどの準備が必要だからです。具体的には以下を石材店と打ち合わせましょう。
戒名や俗名の彫刻
故人の戒名(または俗名)や没年月日を墓石の碑面や墓誌(墓石の脇にある名前を刻む石板)に彫ってもらいます。彫刻には時間がかかるため、納骨式の日程が決まったら早めに依頼します。石材店の都合や天候にも左右されるので、納骨式の2〜3週間前までには依頼するのが目安です。
納骨室の石蓋(いしぶた)開けの手配
納骨する際、お墓のカロート(納骨室)を開ける必要があります。多くの場合、重い石の蓋を開閉する作業が伴うため、当日石材店の方に来てもらうよう依頼しておきます。特に古いお墓ですと素人では蓋を動かせないことが多いため、事前に「○月○日の何時頃に納骨するので石蓋開封をお願いします」と予約しておくと安心です。
新しくお墓を建立中の場合は、墓石の完成日と納骨式の日程調整も重要です。施工状況によっては希望の日までに墓石が完成しないこともありますので、石材店から完成予定日を聞き、余裕を持って日程を決めましょう。お墓が完成したら先述の開眼法要を行い、そのまま納骨式という流れになります。
納骨式当日までに用意するものリスト
菩提寺・石材店との打ち合わせが済んだら、当日までに準備しておくべきものを確認しましょう。以下は一般的に納骨式に必要な持ち物・手配品です:
-
遺骨(ご遺灰)・・・火葬後に拾った遺骨一式(骨壺に納めてあるもの)。
-
埋葬許可証・・・火葬場で発行される書類。墓地に遺骨を納める際に提出が必要です。役所に死亡届を出した際に交付されます。紛失しないよう保管して持参しましょう。
-
故人の遺影写真・・・額に入れた写真を祭壇に飾ることがあります。必須ではありませんが、用意するご家庭が多いです。
-
認め印(印鑑)・・・寺院墓地や公営霊園の場合、納骨の届出に施主の印鑑が必要なことがあります。念のため持参を。
-
お供え・・・お花(供花)、故人の好きだった食べ物やお菓子・果物など(供物)、お線香やロウソクなど。供花・供物は必須ではありませんが、故人への供養として用意すると良いでしょう。
-
卒塔婆・・・菩提寺で卒塔婆を建てる習慣がある場合、寺側が用意してくれます。当日までにお布施とは別に卒塔婆料を包み、卒塔婆を書いてもらっておきます(宗派によっては不要)。
-
僧侶へのお布施・・・読経や法要をお願いする謝礼(後述の「費用相場」の項で詳述)。封筒(白無地の封筒や白い奉書紙)に包み、表書きは「御布施」とします。
-
お車代・御膳料・・・上記お布施とは別に、お坊さんへの交通費として「お車代」、お斎を辞退された場合の食事代として「御膳料」を用意します(後述)。お車代・御膳料はそれぞれ別の封筒に入れ表書きします。相場はそれぞれ5,000円程度が目安です。
-
石材店への寸志(謝礼)・・・当日、石蓋の開閉作業などでお世話になる石材店の作業員の方への心づけです。必須ではありませんが、作業してくださる方がいる場合は数千円程度をお渡しするケースが多いようです。
以上が主な準備物になります。当日はこれらを忘れずに持参しましょう。特に「埋葬許可証」は納骨に不可欠です。万一紛失してしまった場合は再発行手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
納骨式当日の流れ(概要)

ここで、当日の大まかな流れも把握しておきましょう。宗派や地域、ご家庭の事情によって多少異なりますが、一般的な納骨式は次のような手順で行われます。
1.読経・法要
お坊さんが同行する場合、まずお墓の前や霊園の会館などで読経を行ってもらいます。四十九日など他の法要と一緒に行う場合は、その法要の一環として読経をしていただきます。無宗教の場合やお坊さんを呼ばない場合は、開始の合図後に遺族で黙祷したり、故人の好きだった音楽を流すなど、形式は自由です。
2.納骨(遺骨を納める)
読経後、墓石のカロート(納骨室)の蓋を開け、遺骨を納めます。通常、施主(遺族代表)やご親族が骨壺を納骨室に安置します。重い石蓋は事前に手配した石材店の方が開閉してくれます。最近では遺族自身で簡単に開閉できる構造のお墓もありますが、多くの場合専門の方に任せます。遺骨を納め終えたら蓋を閉じます。
3.卒塔婆建立・焼香
卒塔婆を建てる場合は、このタイミングでお墓の後方に差し込みます(寺院が用意した卒塔婆に施主が手を添えて立てます)。その後、参列者全員で順に焼香や献花を行い、お墓に手を合わせて拝礼します。
4.閉式・後片付け
式が終わったら祭壇やお供えを片付けます。卒塔婆は立てたままにし、石材店の方や霊園管理者への挨拶も忘れずに。施主は僧侶へのお布施をこの段階で渡します(読経終了後に僧侶に挨拶しながらお布施等の封筒を渡します)。
5.お斎(会食)
法要後に親族や僧侶を交えて会食を行う場合は、近隣の会食所や自宅に移動してお斎となります。僧侶が参加せず御膳料を渡している場合は、遺族・親族だけで故人を偲ぶ食事の席となります。
以上がおおまかな流れです。規模の大きな納骨式でなければ、式自体の所要時間は30分〜1時間程度でしょう(読経や焼香の時間によります)。四十九日法要と同日に行う場合などはもう少しかかることもあります。いずれにせよ、当日は慌ただしいものですから、必要なものを前日までに準備し忘れ物がないようチェックしておきましょう。
お墓以外の新しい供養先:納骨堂・永代供養墓・樹木葬・散骨
近年、伝統的な「お墓(墓石のあるお墓)」以外にも、遺骨の納め先として様々な新しい選択肢が登場し、一般的になってきました。核家族化や少子化に伴い、「後継者を必要としない供養の形」が求められるようになったためです。実際、近年お墓を新規購入・改葬した人の約半数が、従来型のお墓ではなく樹木葬や納骨堂などを含む「永代供養型」のお墓を選んでいます。ここでは代表的な新しい供養先である納骨堂、永代供養墓、樹木葬、散骨について、その特徴と費用感を見てみましょう。
納骨堂(のうこつどう)

納骨堂とは、遺骨(骨壺)を安置するための屋内施設のことです。ビルや寺院の建物内に多数の収蔵スペース(ロッカー状の区画や棚)が用意されており、そこに骨壺を納めます。いわば「屋内のお墓」であり、雨風にさらされず管理も行き届いているのが特徴です。都市部ではビル型の近代的な納骨堂も増えており、カードキーやICチップで参拝ブースに遺骨を自動搬送してくれる施設など、利便性の高いものも登場しています。基本的に屋内なので天候に左右されずお参りでき、遠方にお墓を構えるよりも自宅から通いやすい立地にあることが多い点も魅力です。後継者がいなくても霊園や寺院が管理してくれるプランが用意されていることが多く、継承者不要のお墓として人気が高まっています。
費用は納骨堂の規模や立地、収納できる遺骨の数によって様々ですが、一般的な相場は一区画あたり数十万円程度です。安いものでは10万円前後〜高価なものでは100万円以上する納骨堂もあります。例えば都心の有名寺院が運営する機械式納骨堂では利用料が100万円を超える場合もありますが、地方の小規模な納骨堂なら数十万円で利用できる所もあります。年間管理費が別途かかる施設も多いので、契約前に維持費も含めて確認しましょう。納骨堂は原則として生前契約も可能で、自分で使う分をあらかじめ確保しておく方もいます。「お墓を持つまでの一時的な預け先」として利用し、その後お墓ができたら遺骨を移す、といった柔軟な使い方ができるのも納骨堂の利点です。
永代供養墓(えいたいくようぼ)
永代供養墓とは、霊園や寺院が遺族に代わって永続的に供養・管理してくれるお墓のことです。「永代」といっても霊園によって期間は異なり、たとえば「33回忌まで個別安置し、その後合祀する(合同のお墓に移す)」といったプランが一般的ですが、期間を区切らず最初から合同墓に合祀するタイプもあります。後継者がいなくても無縁仏にならずに寺院が面倒を見てくれるため、昨今需要が急増しています。形態によっていくつか種類がありますが、大きく個別型と合祀型に分けられます。
個別墓タイプ
見た目は従来のお墓(石塔)に近く、一区画ごとに故人を個別に埋葬・供養するタイプです。他の人の遺骨と混ぜずに済む安心感がありますが、墓石を建てる分費用は高めになります。費用相場は約40万〜150万円程度で、墓石代と永代供養料が含まれます。永代供養料には一定期間の管理・供養料が含まれますが、その期間を過ぎると合祀墓へ移されるケースもあります。
集合墓タイプ
一つの大きな納骨室(石室)に複数の骨壺を個別に収納するタイプです。他の方と同じ空間に安置しますが、骨壺単位で区画が確保されています。墓石を建てる必要がないため費用は20万〜60万円程度と個別墓より抑えられます。見た目は大きな石碑や供養塔の地下などに納骨室がある形です。
合祀墓(ごうしぼ)タイプ
最初から他の方の遺骨と一緒に埋葬する共同のお墓です。合同墓、合葬墓とも言われます。多くは石塔やモニュメントの下に大きな納骨室があり、遺骨は袋やカプセルに移し替えてから納められ、他の遺骨と合葬されます。費用は一人あたり5万〜30万円程度と非常に安価なのが特徴です。その代わり、一度合祀すると遺骨を個別に取り出せない場合が多い点は留意しましょう。
永代供養墓は霊園・寺院によって形態やプランがさまざまです。中には樹木葬形式の永代供養墓や、屋内納骨堂タイプで永代供養付きのプランなどもあります。「永代供養墓」と名前についていても必ずしも屋外の合同墓とは限らないので、内容をよく確認して選ぶ必要があります。費用もピンキリですが、合祀型なら数万円台〜、個別型なら数十万〜百数十万円と幅があります。いずれにせよ、後継者がいなくても無縁仏にならない安心感が大きなメリットで、近年では一般墓(従来型のお墓)と並んで検討する人が非常に増えています。
 跡継ぎ不要・管理不要のお墓とは?永代供養と納骨堂のすべて
跡継ぎ不要・管理不要のお墓とは?永代供養と納骨堂のすべて
樹木葬(じゅもくそう)

樹木葬は、墓石の代わりに樹木や花などのシンボルを墓標とするお墓です。自然志向の新しい埋葬スタイルで、公園のようなガーデン墓地や山林の一角など緑に囲まれた区画に遺骨を埋め、代わりに樹や草花を植えたり、その近くにプレートを設置したりします。遺骨は土に還る形で埋葬されることが多く、環境に配慮した方法として注目されています。樹木葬も多くの場合は永代供養付きで、霊園や寺院が管理・供養を行ってくれるため後継者が不要です。「自然に還りたい」「緑の中で眠りたい」という希望を持つ方に選ばれています。
樹木葬にはいくつか種類があります。一人一ヶ所に個別に埋葬し、その場所に小さな樹やプレートを配置するタイプもあれば、家族で一区画を使えるタイプ、複数の遺骨をまとめて一本のシンボルツリーの下に埋葬するタイプ、さらには他の方の遺骨と一緒に合祀するタイプもあります。費用は埋葬方法や区画サイズによって異なり、合祀型なら5万〜20万円、共同区画型で20万〜60万円、家族ごとの個別区画型で50万〜150万円程度が目安とされています。一般のお墓に比べ墓石代が不要な分、比較的費用を抑えやすい傾向にあります。
例えば、周囲を芝生や花壇で整備したガーデニング霊園型の樹木葬では一区画あたり数十万円程度が多いです。一方、共有の樹の下に埋葬するスタイル(合祀型)であれば数万円から利用できるプランもあります。都市部ではおしゃれなガーデン樹木葬が人気で、地方では里山を利用した大規模な樹木葬墓地も広がっています。自然に囲まれた開放的な雰囲気や、従来のお墓のような重圧感がない明るいデザインも、樹木葬の魅力です。樹木葬を選ぶ際は、将来その霊園がちゃんと管理を続けてくれるか(経営母体の安定性)、立地やアクセス、樹木や景観の好みなども含めて検討するとよいでしょう。
 樹木葬とは?お墓の代わりに選ばれる理由と種類・費用まで解説
樹木葬とは?お墓の代わりに選ばれる理由と種類・費用まで解説
散骨(さんこつ)

散骨とは、文字通り遺骨を粉状にして撒く(散布する)供養方法です。主に海洋散骨(海に撒く)や、山林などへの散骨があります。日本では1990年代から徐々に行われるようになり、現在では専門の代行業者も多数存在します。散骨は法律で明確に禁止されてはいません。厚生労働省も「節度を持って行われる限り問題ない」という見解を示しており、公衆衛生上問題のない方法であれば違法ではないと解されています。とはいえ、他人の私有地に撒くことは当然できませんし、海でも岸辺や人が遊泳するような場所での散骨はマナー違反です。実施する際は専門業者に依頼するか、ガイドラインをよく調べて自己責任で行う必要があります。
散骨の最大の特徴は、お墓という形ある場所を持たないことです。遺骨は自然に還りますので、物理的な管理や維持費も不要です。遠方にお墓参りに行かなくても、海や空を見上げて故人を思うことで供養とする——そういった新しいスタイルとも言えます。その反面、「あとで遺骨を手元に戻すことはできない」「遺骨を撒いた場所が特定しづらく、故人を偲ぶ拠り所が無くなる」といった点はデメリットかもしれません。ご家族全員の理解がある場合や、故人の強い希望がある場合に選択されることが多いです。
費用面ですが、散骨は他の埋葬方法に比べ比較的低コストで行えます。例えば海洋散骨の場合、専門業者に依頼すると一組の遺族だけで船をチャーターするプランで20〜40万円前後、他のご家族と乗り合いで合同で散骨するプランなら1組あたり5万〜10万円程度が相場です。最も安価なのは業者に遺骨を預けて代理で散骨してもらう代行散骨で、こちらは数万円〜十数万円ほどの費用で請け負っているところもあります。自分たちで船を手配して散骨することも可能ですが、遺骨をパウダー状に砕く粉骨の手間や当日の安全面を考えると、専門サービスを利用する方が安心でしょう。散骨を行った後、手元には遺骨が残らなくなるため、その代わりとして思い出の品を手元供養したり、散骨海域の緯度経度を記録しておいたりするご家族もいます。
 お墓の代わりに選ぶ「散骨」とは?種類・費用・メリット・デメリット・注意点
お墓の代わりに選ぶ「散骨」とは?種類・費用・メリット・デメリット・注意点
 散骨体験クルーズに参加して分かった、海洋散骨の業者選びのポイント
散骨体験クルーズに参加して分かった、海洋散骨の業者選びのポイント
以上、納骨堂・永代供養墓・樹木葬・散骨といった新しい供養先をご紹介しました。これらは「お墓を持たない」「子や孫に負担をかけない」供養の方法として、特に都市部を中心に利用者が年々増えています。費用面でも従来のお墓より抑えられるケースが多く、各家庭のニーズに合わせて選択できる時代になっています。
卒塔婆とは?〜その意味と宗派ごとの違い

お墓参りや法事の際に、お墓の後ろに立てられる長い木の板を見たことがあるでしょうか。これは卒塔婆(そとば)または板塔婆(いたとうば)といい、故人の供養のために立てる木の供養塔です。卒塔婆という言葉はサンスクリット語の「ストゥーパ(塔)」が語源で、本来お釈迦様の遺骨を納めた塔を意味します。それが転じて、日本ではあの板状の供養具を指すようになりました。
卒塔婆には表面に梵字や経文、戒名などが書かれ、裏面や下部に施主(建立者)名と日付が記されます。梵字は仏教における五大要素(空・風・火・水・地)を表し、これらは宇宙や万物を構成する要素であると同時に人の体を構成する要素ともされています。卒塔婆を立てることには「塔婆供養」という意味があり、故人のために善行(供養)を積むという追善供養の一つです。日々のお参りや年忌法要と同じく、卒塔婆を建立することで故人の冥福を祈る行為になるわけです。初めて卒塔婆を立てるタイミングは、多くの場合四十九日法要や納骨式の際です。以後、お彼岸やお盆、○回忌など節目ごとに新しい卒塔婆を立て、古くなったものはお寺でお焚き上げして処分(供養)してもらいます。
卒塔婆が必要かどうか、何本立てるかは地域や宗派によって異なります。一般的には故人一人につき一本立てるケースが多いですが、お墓の後ろにそんなに沢山立てられない場合は「○○家一同」のように一家で一本にまとめることもあります。一方で、冒頭にも触れたように浄土真宗では「追善供養」の考えがないため卒塔婆供養を行いません。浄土真宗以外でも、お寺や宗派によっては卒塔婆を立てる習慣自体がない場合もあります。ですから、卒塔婆をどうするかは事前に菩提寺に確認しておくことが大切です。菩提寺がない場合は霊園の管理事務所などに相談するとよいでしょう。
卒塔婆を立てる場合、その費用(卒塔婆料)は1本あたりおおむね2,000〜10,000円程度です。料金はお寺があらかじめ定めていることが多く、戒名の長さ(院号が付くと少し高いなど)によって変わることもあります。お布施とは別に封筒に入れて渡す点に注意しましょう。表書きは「卒塔婆料」または「塔婆料」とし、複数本分まとめて一つの封筒に入れて渡すのが一般的です。なお、立てた卒塔婆はずっとそのままではなく、一定期間経ったらお寺で処分してもらいます。木でできているため風雨で傷みますし、法要のたびに増えていくので、お墓に何本も古い塔婆を立てっぱなしにはしません。定期的に古い卒塔婆はお焚き上げ供養して処分する流れになります。お寺によっては一定本数まで立てたら古いものから下げるなどルールがありますので、気になれば菩提寺に尋ねてみましょう。
まとめると、卒塔婆は故人への追善供養として立てるものであり、宗派次第では省略も可能です。必要な場合は本数と費用を把握し、菩提寺に依頼して準備しておきましょう。卒塔婆料は忘れずに別包みで用意すること、そして終了後に古い卒塔婆の処分をお願いする場合はその旨お寺に伝えることも覚えておきたいポイントです。
納骨式にかかる費用:お布施・御膳料・石材店への寸志の相場
納骨式を行う際には、いくつか費用(謝礼)の準備が必要です。ここでは、僧侶へのお布施を中心に、御車代(お車代)・御膳料・石材店への寸志などお金に関するマナーと相場を解説します。
僧侶へのお布施の相場
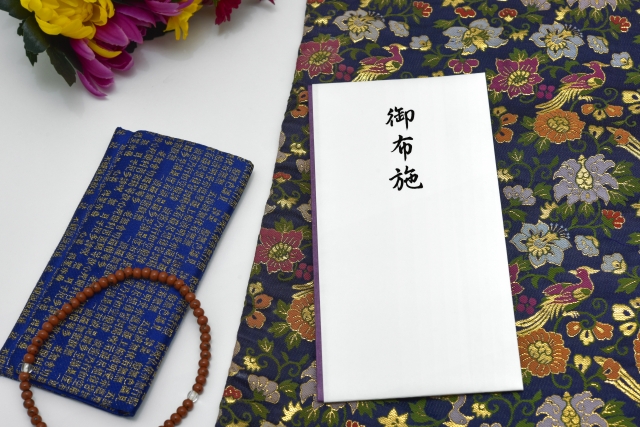
まず、読経や法要をお願いするお布施の金額相場です。お布施は本来「お気持ち」であり定価のないものですが、一般的な目安はあります。納骨式のみを単独で行う場合であれば、僧侶へのお布施は約3万〜5万円程度が相場とされています。これは四十九日などの法要を兼ねない、純粋に納骨のためのお経だけをお願いする場合の目安額です。では、四十九日法要や一周忌法要と同時に納骨式も行う場合はどうなるでしょうか。この場合、その法要分も含めたお布施となりますので、お布施の相場は合計で5万〜10万円程度が目安になります。特に、新しいお墓の開眼供養も同時にお願いする場合には、読経の手間も増えるため通常の1.5倍〜2倍程度を包むケースもあります。具体的な額はお寺とのお付き合いの深さや各家の考え方にもよりますが、「〇〇法要(例:四十九日)+納骨で〇万円包む」という形で調整するとよいでしょう。
昨今では、檀家制度の希薄化もあり、菩提寺がない方がお坊さん紹介サービス(いわゆる「坊さん便」など)を利用して読経を依頼するケースも増えています。その場合でも、相場感は上記と大きく変わりません。一般的に一式〇万円と料金が提示されていることも多く、ひとつの法要につき3万円程度が多いようです。もちろん、菩提寺がありこれまで法事をお願いしてきた場合は、そのお寺での過去のお布施額(例えば〇回忌で包んだ額など)を基準にすると安心です。どうしても判断に迷う場合は、直接お寺に「皆さんどのくらい包まれていますか?」と遠回しに聞いてみるのも一つの方法です。
お布施は本来「僧侶への謝礼」ですが、あくまで宗教的には僧侶への対価ではなく仏教修行として自発的に渡すものとされています。そのため、金額に決まりはありませんが、周囲の相場に大きく外れない範囲で包むのがマナーと言えるでしょう。
 初めての喪主でも安心!『よりそうお坊さん便』徹底ガイド【僧侶手配】
初めての喪主でも安心!『よりそうお坊さん便』徹底ガイド【僧侶手配】
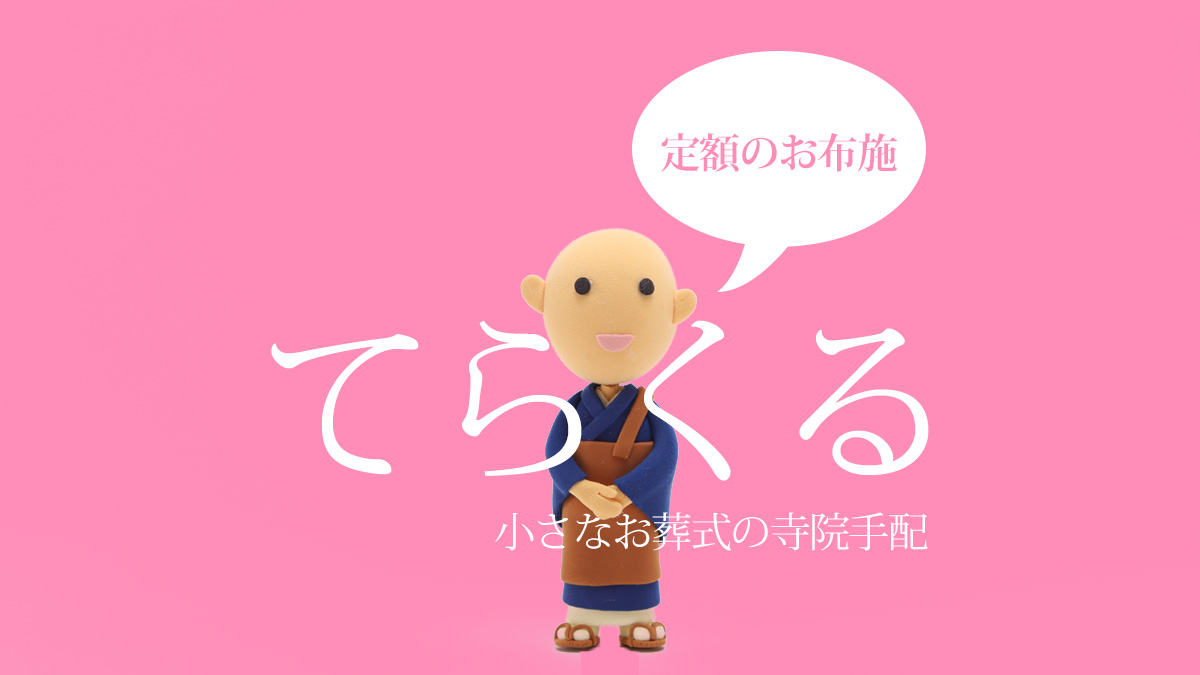 小さなお葬式の寺院手配「てらくる」とは?サービス内容と口コミ・評判を解説
小さなお葬式の寺院手配「てらくる」とは?サービス内容と口コミ・評判を解説
お布施以外に必要な謝礼(御車代・御膳料・寸志)
納骨式ではお布施のほかにもいくつか謝礼として包むお金があります。具体的には「御車代(お車代)」と「御膳料」、そして場合によっては石材店等への寸志です。
御車代(お車代)
お坊さんにお寺以外の場所まで来ていただいた場合の交通費です。例えば、お墓が遠方にあって菩提寺の住職に車で来てもらう場合などに渡します。相場は5,000円前後です。距離によっては1万円包むこともあります。白い封筒に入れ、表書きは「お車代」とします。なお、お布施を郵送で渡す場合や、既にお布施に交通費分を上乗せして多めに包んでいる場合は省略することもあります。
御膳料
本来、法要後にはお坊さんを交えて会食(精進落としのお斎)をする習わしがありますが、近年は住職が辞退されることも多いです。その場合、料理の代わりに渡すのが御膳料です。金額は5,000円程度が目安です(お車代と同程度)。表書きは「御膳料」または「御斎料」とし、別封筒で用意します。お坊さんにお斎を辞退されたら必ず渡すもの、とまではいきませんが、お礼の気持ちとして用意するご家庭が多いです。
石材店への寸志(心づけ)
納骨の作業でお世話になる石材店の作業員の方へのお礼です。当日、重い石の蓋を開けたり閉めたり、墓石の一部を動かしたりといった作業をしていただいた場合、作業後に「今日はありがとうございました」と数千円をお渡しすることがあります。相場は明確ではありませんが、1人あたり2,000〜5,000円程度が多いようです。中には「うちはきっちり支払いをいただいているのでお気持ちだけで十分です」と寸志を辞退される石材店もありますので、状況に応じて渡すとよいでしょう。もちろん、石材店への作業費(開閉料)は別途かかりますので注意してください。石材店の作業料金は地域にもよりますが、納骨室の開閉作業だけなら2万〜3万円程度が一般的です。お墓の中に祭壇を用意したり、お焼香の台などを設置してもらった場合はもう少し費用がかかることもあります。
以上が納骨式に関わる主な費用項目です。このほか、法要後の会食費用(お斎の費用)や、会葬御礼の品を用意すればその費用なども発生しますが、これらはご家族や参列者数によって大きく異なりますので割愛します。基本的にはお布施+お車代+御膳料(+石材店への寸志)の合計額を事前に準備しておくことになります。例えば「納骨式のみで僧侶に読経をお願い、住職は車で来訪、お斎は無し」のケースなら、お布施3万円・お車代5千円・御膳料5千円程度で合計4万円前後というイメージです。地域差や寺院ごとの慣習もありますので、心配な場合は菩提寺や葬儀社などに相場を尋ねてみるのもよいでしょう。
家族構成の変化と宗教観の多様化がもたらす納骨式のあり方
現代では、従来のように「先祖代々のお墓に入る」「菩提寺のお坊さんにお願いして…」という形にとらわれない納骨式も増えてきました。背景には、家族構成やライフスタイルの変化、宗教観の多様化があります。
まず、核家族化・少子化によって「お墓を守る継承者がいない」家庭が珍しくなくなりました。その結果、先述した永代供養墓や樹木葬といった後継者不要の供養を選ぶ人が急増しています。実際、ある調査ではここ5年以内にお墓を求めた人のうち約49.7%が永代供養型のお墓(樹木葬や納骨堂など)を選んだとの結果が出ています。[1] 従来型の「家のお墓」は同じく49.0%で、ほぼ二分する状況です。今やお墓選びの主流は「次世代に負担を残さないこと」にシフトしつつあると言えるでしょう。
また、都市部を中心に檀家離れも進んでいます。先祖代々の菩提寺がない、ご自身が特定の宗教を信仰していない、といった方も多く、無宗教葬や家族葬でお葬式を簡素に済ませる例も増えてきました。そうした場合、納骨式でも必ずしも僧侶を呼ぶとは限りません。実際、公営・民営霊園など寺院管理でない墓地では、僧侶を呼ばず家族だけで納骨式を行うケースも増えています。お経を上げずに、遺族だけで静かに遺骨をお墓に納め、手を合わせるだけのシンプルな納骨式です。「それってアリなの?」と思うかもしれませんが、現代では納骨式を必ず宗教的儀式として行わなければならないわけではないのです。霊園によっては管理者立ち会いのもと、遺族だけで納骨を完了することも可能です。
もちろん、「菩提寺のお坊さんにお願いし、きちんと法要として納骨式を執り行いたい」という方もたくさんおられます。大切なのは、ご家族の信条や状況に合わせた形で納骨式を行うことです。他にも、例えば遠方にお墓があって頻繁にお参りに行けない場合は手元供養を取り入れて分骨し、一部を自宅に安置することで心の拠り所を作る、といった工夫をされる方もいます。
さらに、昨今では先祖代々のお墓を処分して永代供養に切り替える「墓じまい」を行う家庭も増えています。墓じまいとは、墓石を撤去し遺骨を別の供養先に移すことです。「子どもにお墓の管理負担をかけたくない」「遠方でお参りに行けないお墓を整理したい」といった理由で、墓じまいを選択し、遺骨を永代供養墓にまとめたり散骨したりするケースが増加傾向にあります。ある霊園業者によれば、数年前までは年間20件ほどだった墓じまいの相談が、最近ではその10倍近くに増えているとのことです。こうした動きも、「墓にとらわれない供養」の表れと言えるでしょう。
要するに、現代の納骨や供養は非常に多様化しています。大家族が揃って菩提寺で法要をし、お墓に納めるという従来の形式だけではなく、各家庭の事情や価値観に応じたスタイルが許容される時代です。大切なのは、故人を思う気持ちを込めて、遺された家族が納得できる形で供養することでしょう。どの方法にも一長一短がありますので、親族とよく話し合って決めるのが一番です。
オンライン法要から納骨代行まで:最新の供養トレンドとサービス
情報技術やサービス業の発展に伴い、納骨や供養の分野にも新しいトレンドやサービスが登場しています。最後に、2020年代に広がった注目のサービスをいくつかご紹介します。
オンライン法要・オンライン納骨式
新型コロナウイルスの流行を契機に、一気に広がったのがオンライン法要です。直接集まれなくてもインターネット中継を通じて法要に参加できる仕組みで、ZoomやYouTubeライブ配信などを利用します。お寺側でも対応を始めたところが多く、「オンライン法事サービス」の提供が次々と始まっています。例えば、遠方に住む親族がお堂での法要にリモートで参列したり、住職が読経する様子をライブ配信したりといった形です。オンライン法要が増えた一番の理由は言うまでもなく感染症対策ですが、それだけでなく高齢で移動が難しいご親族のためなど、コロナ後の現在でも活用する場面が定着しつつあります。「オンライン法要なんて味気ないのでは?」と思うかもしれませんが、実際に利用した人からは「遠く離れた家族と画面越しでも一緒に故人を偲べて良かった」「移動負担がなく安心して参列できた」など肯定的な声も多いようです。もちろんネット環境や機材の準備は必要ですが、対応する寺院は年々増えていますので、必要に応じて相談してみると良いでしょう。
納骨代行サービス
少子高齢化や人間関係の多様化に伴い、「納骨代行」とも呼べるサービスも登場しています。これは、遺族が納骨に立ち会えない場合に専門業者やNPOが代理で遺骨を埋葬してくれるサービスです。たとえば、故人の子ども世代が遠方に住んでいてお墓まで行けない場合や、継承者がいない独り身の方が生前に依頼契約を結んでおき、自分の死後に納骨を任せるケースなどがあります。特に身寄りが無い方の場合、行政やNPO法人が遺骨を引き取り永代供養墓に納める取り組みもあります。また近年は、人間関係のこじれなどから「親の葬儀や納骨をすべて第三者に任せたい」という依頼が増えているとの報道もあります。実際、とある一般社団法人によれば「親のことを全部任せたい」という子どもからの相談がここ1〜2年で6〜7倍に急増したそうです。背景には様々な事情があるでしょうが、介護から葬儀、納骨、遺品整理に至るまで全てをプロに丸ごと委託するという「終活代行」サービスが登場しているのも事実です。
納骨代行サービスを利用する際は、遺骨の扱いや埋葬先についてきちんと確認し、信頼できる業者や法人に依頼することが重要です。費用は内容にもよりますが、葬儀から納骨まで一式の場合で数十万円〜100万円ほどと報じられています。今後ますます高齢者の「おひとり様」が増える中で、需要が高まるサービスかもしれません。
その他の新サービスあれこれ
上記以外にも、供養に関するユニークなサービスが登場しています。一例を挙げると:
-
お墓参り代行サービス:遠方にあってなかなか行けないお墓を、代行スタッフが清掃・お参りし、写真報告までしてくれるサービスです。忙しい方や高齢で外出が難しい方に利用されています。
-
墓石のリメイク・引越し:先祖代々の墓石を加工して小さく作り直し、新しい霊園に移転するサービスなど、従来の墓石を活かしつつ身軽にする提案も現れています。
このように、時代のニーズに合わせて供養のあり方も柔軟に変化しています。大事なのは、どんな形であれ故人を想う気持ちを絶やさないことでしょう。伝統的な方法に最新サービスを組み合わせることで、ご家族にとってより良い供養の形が実現できるかもしれません。
最後に、納骨や供養について読者の方から寄せられるよくある質問をQ&A形式でまとめました。疑問点を再チェックしてみてください。
よくある質問(Q&A)
納骨のタイミングに決まりや期限はありますか?
決められた期限はありません。法律上、「○日以内に納骨しなければならない」という規定は特にないので、四十九日、一周忌などご家族が行いやすいタイミングで大丈夫です。一般的には四十九日法要に合わせて行うことが多いですが、事情に応じて百箇日や一周忌、三回忌まで延期するケースもあります。極端に長く延期するより三回忌までには済ませる方が多いですが、無理に急ぐ必要はありません。心の準備やお墓の用意が整ってから、遺族が納得できる時期に行いましょう。
納骨式には必ずお坊さんに来てもらわないといけませんか?
必須ではありません。菩提寺のある方は、読経してもらうのが一般的ですが、最近ではお坊さんを呼ばず家族だけで納骨する例も増えています。公営霊園などお寺の管轄でない墓地の場合、宗教儀式は必須ではありません。ただし、寺院墓地の場合や仏式で手厚く供養したい場合は、お坊さんにお願いするのがよいでしょう。無宗教の場合でも、納骨式自体は執り行えます。その際は黙祷や献花だけ行い、形式にとらわれず故人を偲ぶ時間にすると良いでしょう。
お墓がない場合、遺骨はどこに納めればいいですか?
お墓(墓石)がなくても大丈夫です。納骨堂・永代供養墓・樹木葬・散骨など、お墓以外にも遺骨を納める選択肢は豊富にあります。例えば、屋内施設の納骨堂に預けたり、寺院や霊園の永代供養墓に納骨して永続的に供養してもらうことが可能です。自然志向であれば樹木葬を選んで森や庭に埋葬する方法もありますし、管理や維持費を無くしたいなら散骨してお墓そのものを持たないという選択もあります。実際、近年では 樹木葬や納骨堂を含む「永代供養型」のお墓を選ぶ人が非常に増えており、従来のお墓とほぼ同数になっています。ご自身やご家族の希望に合わせて、適切な方法を選んでください。
卒塔婆は必ず建てるものですか?
卒塔婆を建てるかどうかは宗派と菩提寺の方針によります。浄土真宗のように卒塔婆供養の習慣自体が無い宗派もありますし、禅宗や天台宗などでは四十九日やお盆の際に建てるのが一般的です。菩提寺がある場合は事前に住職に確認しましょう。必要な場合でも、故人ごとに一本ずつ建てるか家ごとにまとめるかはお墓のスペースなどで変わります。費用は1本あたり数千円〜1万円程度が相場で、お布施とは別に「卒塔婆料」として包んでお寺に納めます。宗派的に必要なければ無理に建てる必要はありませんが、建てれば供養になるものなので、菩提寺の指示に従うと良いでしょう。
納骨式に参列するときの服装やマナーはどうすればいいですか?
基本的には葬儀や法事と同様の服装・マナーを心がけます。遺族側であれば喪服(男性は黒のスーツに白シャツ・黒ネクタイ、女性は黒のスーツやワンピース)を着用します。参列者側も、なるべく黒や紺など地味な色のスーツやワンピースを着ましょう。平服で、と言われた場合でも華美にならないよう注意します。マナー面では、式中は私語を慎み、携帯電話はマナーモードにするなど一般的な礼儀を守れば問題ありません。焼香の作法やお墓での振る舞いも法事に準じます。屋外で行うため夏場は日傘や帽子で日差しを避けても構いませんが、派手になりすぎないよう配慮してください。要するに、「厳粛な儀式である」という意識を持った身だしなみと態度で臨めば大丈夫です。
遺骨を自宅にずっと置いておくのは良くないですか?
法律上は最終的に埋葬することが望ましいとされていますが、一定期間や一部を手元に置いておく「手元供養」自体は近年増えています。ずっと自宅供養を続ける方もいますが、将来的にご自身が亡くなった後その遺骨をどうするか、という問題が残ります。手元に置く場合でも、故人の分骨を少量手元に残し、本骨は永代供養墓などしかるべき場所に納めておく方が多いです。「ずっと家に置いておきたい」というお気持ちも理解できますが、年月が経つと後の世代では管理が難しくなることも考えられます。一時的に手元に置いて故人を偲び、心の整理がついた段階で改めて納骨する——という流れが現実的には多いようです。どうしても手元供養を続けたい場合は、信頼できる人にその意思を伝えておき、いずれ永代供養してもらえるよう手配(エンディングノートに記載する等)しておくと安心でしょう。
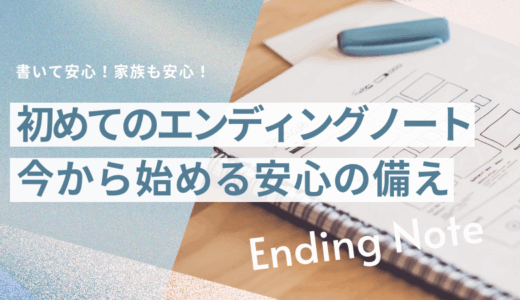 はじめてのエンディングノート〜今から始める安心の備え〜
はじめてのエンディングノート〜今から始める安心の備え〜
まとめ
納骨式に関するポイントを最新事情を踏まえて解説しました。不明点や不安な点がクリアになりましたでしょうか。納骨式は故人との最後の大切なお別れです。形式にとらわれすぎず、かといって準備不足で慌てることのないよう、本記事を参考に心温まる納骨式を執り行っていただければ幸いです。
脚注





