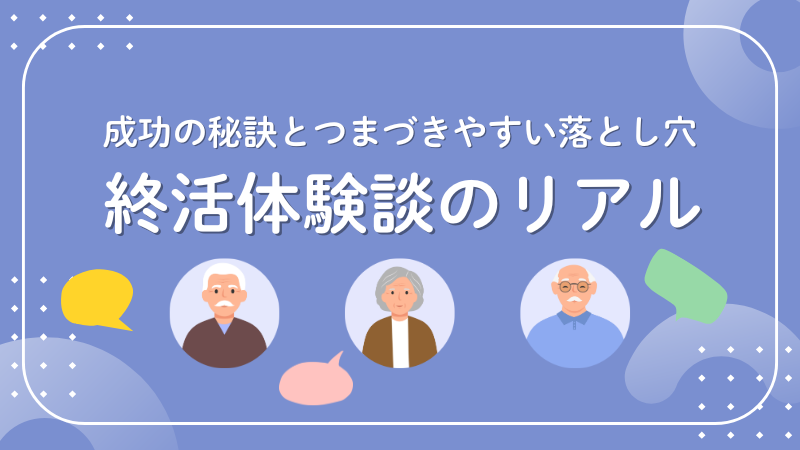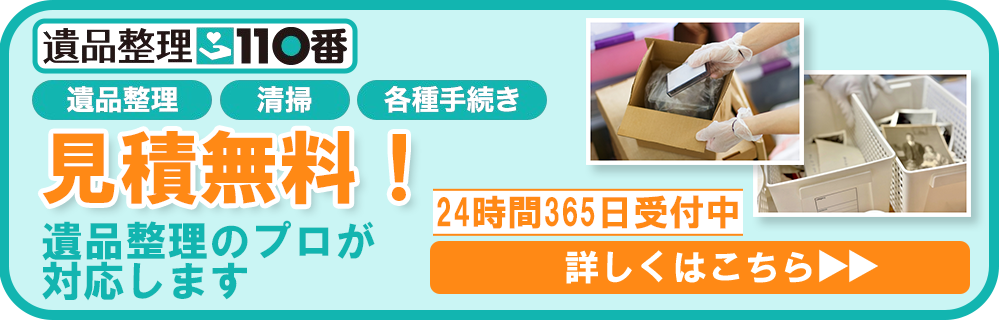終活は「死の準備」ではなく「今を暮らしやすくする工夫」と考える人が増えています。実際に取り組んだ人の中には、安心できたという声もあれば、かえって負担を残してしまったという声もあります。
この記事では、エンディングノートやデジタル遺品、家の片づけ、財産の残し方といったテーマごとに体験談を紹介します。うまくいった例とつまずいた例を両方知ることで、自分らしい終活の形を見つけてください。
エンディングノートに書いた人・書かなかった人
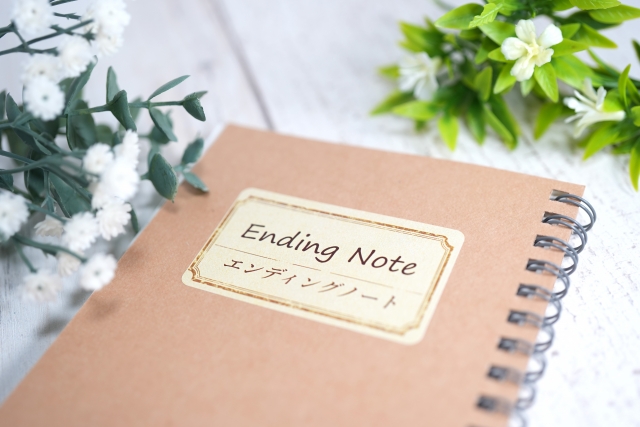
エンディングノートは、思いを整理して家族に伝えるための代表的な道具です。
書いて残した人は会話が増え、安心を得られたといいます。一方で、何も残さなかった家庭では、手続きや相続が長引き、家族が大きな負担を背負いました。一冊のノートで安心が生まれる一方、書き方が不十分だと迷いを残すこともあります。
ここでは、安心につながった人の声と、反対に混乱を招いた事例をあわせて紹介します。
ノートが会話のきっかけになった家庭
![]()
Aさん夫妻は、老後を迎えたタイミングでエンディングノートを手に取りました。ノートには「介護が必要になったときの希望」や「葬儀は小規模で」といった想いを簡単に書きました。
書いた後は、食卓でその内容を話題にすることが増え、夫婦で互いの考えを知る機会になったといいます。数年後、夫が入院した際も家族が迷わず対応できました。
Aさんは「一冊のノートで、終活への心構えができました」と振り返っています。
葬儀の準備が迷わず進んだケース
![]()
Bさんの家族は、エンディングノートに葬儀の希望が丁寧に書かれていたおかげで、大きな迷いなく準備を進められました。
式場の希望、呼んでほしい友人の名前、祭壇に飾る花まで細かく記されており、遺族は「迷ったらノートを見ればいい」と安心できたといいます。
喪主を務めた長男は「悲しみの中でも手順がはっきりしていたので、精神的に支えられました」と振り返りました。
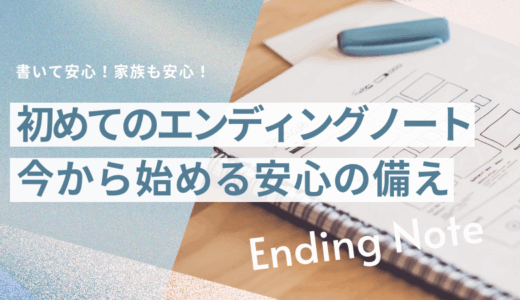 はじめてのエンディングノート〜今から始める安心の備え〜
はじめてのエンディングノート〜今から始める安心の備え〜
葬儀の希望を事前に記録しておくだけで、家族の迷いは大きく減ります。最近では家族葬の広がりから、小さなお葬式の「小さな家族葬」プランような小規模サービスを利用する人も増えています。
料金体系がわかりやすいため、初めての喪主でも安心して準備を進められるのが特徴です。
記録がなく混乱した相続の行方
![]()
Cさんの父は、きちんとした記録を残さないまま急に亡くなりました。
口座や保険の情報がわからず、家族は数週間も探し回ることになりました。遺産の分け方についても、本人の意思が残っていなかったため、兄弟間で話し合いが長引きました。
Bさんは「ほんの数行でも書き残してくれていたら違っていた」と痛感したそうです。
書きかけのノートが残した不安
![]()
Dさんはエンディングノートを書き始めましたが、途中でやめてしまいました。
延命治療については「考え中」とだけ書かれ、財産の欄は空白のまま。残された家族は「本人の意思を尊重したいのに、何も決められていない」と迷いました。結局は家族ごとに解釈が異なり、話し合いが繰り返されることになりました。
中途半端に残されたノートは、逆に混乱の種となってしまったのです。
記録を残す意味を考える
エンディングノートは形式ばった遺言ではなく、家族への気持ちや希望を伝える道具です。成功例にあるように、短い言葉でも対話を生み、家族に安心を与えます。
一方で、残さなければ混乱を招くこともあり、書き方次第で結果が大きく変わります。大切なのは完璧さではなく、「一言でも残す」こと。その小さな一歩が、家族を支える力になります。
デジタル遺品で残る思わぬ壁
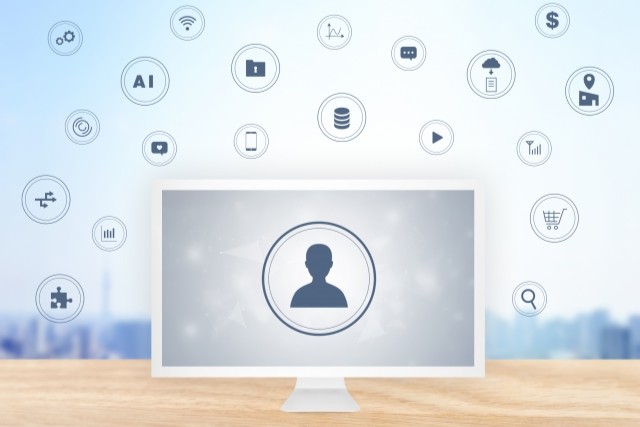
スマホやクラウドのアカウントは、生前は便利でも死後には家族の負担になりがちです。
暗証番号がわからず大切な写真が見られない、解約できない契約が延々と続く。そんな事例は今や珍しくありません。一方で、ほんの少しの準備でスムーズに対応できた例もあります。
この章では、失敗と成功の両面を見ながら、デジタル遺品への備えを考えます。
スマホの暗証番号がわからない
![]()
Eさんの父が亡くなったとき、スマホには家族旅行の写真や動画が残っていました。しかしロック解除の番号がわからず、誰も開けることができません。
通信会社に相談しましたが「契約者本人以外には対応できない」と告げられ、写真は見られないまま。葬儀で遺影を探すときも困り、家族はやり場のない気持ちを抱えました。
解約できず続いたクラウド契約
![]()
Fさんの父は生前に複数のメールアドレスやSNSを使っていました。しかし整理をしていなかったため、どのアドレスが重要なのか家族にはわかりません。
解約すべき契約と残しておくべきものの区別がつかず、何度もログインを試みる日々が続きました。中には料金が発生し続けたサービスもあり、時間も費用も浪費する結果になりました。
Fさんは「もっと早く整理していてほしかった」と振り返っています。
 デジタル終活完全ガイド|SNSやネット口座、そのままで大丈夫?
デジタル終活完全ガイド|SNSやネット口座、そのままで大丈夫?
小さな備えで安心を得た実例
![]()
Gさんは、生前に自分のスマホとパソコンの主要なアカウント情報をノートにまとめ、机の引き出しにしまっておきました。そこには暗証番号や契約しているクラウドサービスの一覧、支払いに使っているカードの情報が整理されていました。
亡くなった後、家族はそのノートを頼りに解約や名義変更をスムーズに進めることができました。
Gさんの子どもたちは「必要な情報がすぐ見つかったので、悲しみの中でも落ち着いて対応できた」と話しており、少しの準備が大きな安心につながったことを実感しました。
デジタル情報を整理する重要性
便利さの裏側には必ず管理の負担が潜んでいます。暗証番号やIDが不明で家族が苦労するケースは少なくありませんが、ほんの小さな工夫で解決できる問題でもあります。
デジタル時代の「残す責任」とは、情報をどう共有するかということ。備えを怠らなければ、大切な思い出や記録を家族につなぐことができます。
家の片づけに取り組んだ終活の記録

家の片づけは、亡くなった後に家族へ大きな負担を残します。
家具や衣類、思い出の品を一気に処分するのは、体力的にも精神的にも大変な作業です。準備不足のまま手を付けた人の中には、必要なものまで捨ててしまうケースもあります。
反対に、生前から計画的に整理を始めている人は暮らしが快適になり、残された家族も安心しています。
ここでは、準備の有無で大きく結果が変わった事例をご紹介します。
大型家具を手放して得た安心
![]()
Hさんは「子どもに迷惑をかけたくない」と考え、リビングに置いていた大きな洋服箪笥を処分しました。リサイクル業者に依頼し、使わない着物や古いスーツも一緒に引き取ってもらったのです。
部屋が広くなったことで転倒の心配も減り、家族からも「暮らしやすくなったね」と喜ばれました。
写真整理で生まれた家族の笑顔
![]()
Iさんは家中に散らばっていた写真を整理し、アルバム数冊にまとめました。アルバムには簡単なコメントを書き添え、「見返すと楽しい」「これなら残してもいい」と家族と笑いながら眺められる形にしました。
亡くなった後、子どもたちは「母がまとめてくれたおかげで迷わず選べた」と、葬儀用の写真をスムーズに決められたそうです。
トランクルーム活用で整理がスムーズに
年配の男性3
残すものが明確になって良かったです コレクション好きだったJさんは、自分でも「全部残すのは無理」と気づきました。そこで、生前のうちに趣味の品をトランクルームに移し、「残すもの」と「処分してよいもの」をリストにまとめておきました。 家族はその指示に従うだけで済み、整理を短期間で終えることができました。 Kさんは「元気なうちに身の回りを減らそう」と思い立ち、大掃除の勢いで家財を大量に処分しました。 しかし、家族の大切な書類や、形見に残したかった時計まで一緒に捨ててしまったのです。残された家族は「相談してほしかった」と複雑な気持ちを抱えました。 Kさんにとっては身軽になったつもりでしたが、家族には逆に負担を残す結果となりました。 生前に片づけを始めた人は、暮らしが軽くなり、家族の負担も減りました。しかし、準備不足のまま一気に処分してしまった人は、必要な物まで失い、家族に不満を残しました。 家の片づけは、時間をかけて「残す物」と「手放す物」を整理することが重要です。仮置きや専門業者の活用など、工夫を取り入れることで、無理なく納得できる形に近づけます。 たとえば「遺品整理110番 財産や遺産の分け方は、家族の関係に大きく影響します。「平等に分ける」と「特定の人に託す」のどちらも正解ですが、準備がないと争いの火種になります。 ここでは、終活の中でも特にトラブルが多い「お金の行き先」をめぐるエピソードを紹介し、備えの重要性を考えます。 Lさんは子どもを授かれなかったことから、「自分の財産を未来の子どもたちのために残したい」と考えるようになりました。終活セミナーで遺贈寄付の仕組みを知り、奨学金事業を支援できることを知ったときに心が動いたといいます。 専門家と相談しながら遺言を作成し、寄付先も具体的に決めました。Jさんは「自分の名前が残らなくても、学ぶ誰かを支えられるのなら十分」と語り、安心した表情を見せていました。 Mさんは若いころ、海外でボランティア活動を経験しました。現地の子どもたちが十分な教育を受けられない姿を目にしたことが、ずっと心に残っていたといいます。 60代になり終活を考え始めたとき、「自分の財産を社会に役立てたい」という思いが再び湧き上がりました。家族にも相談し、賛同を得たうえで、財産の一部を教育団体に寄付する遺言を残しました。 「人生を整理する中で、自分にとって大事なものが改めて見えた」と語っています。 Nさんは当初、エンディングノートに「財産の一部を寄付したい」と書きました。しかし、弁護士に相談したところ「ノートには法的効力がない」と説明されました。 そこで正式な遺言書を作成し、財産の分け方を明確にしました。家族にも内容を伝え、「これなら迷わずにすむ」と安心したそうです。 Lさんは「想いを形にするには、ノートだけでなく法的に効力を持つ手段が必要」と実感したと語っています。 Oさんは財産の一部を寄付したいと考えており、ノートに「〇〇団体に寄付するつもり」と書き残していました。ところが、その記述は正式な遺言ではなかったため、法的効力はなく、寄付先も金額も明確ではありませんでした。 結果として、相続人の間で「本当に寄付すべきか」「どの程度の金額か」で意見が分かれ、話し合いが長引きました。最終的に寄付は実現せず、家族の間にわだかまりが残りました。 Mさんの思いは確かにあったのに、形式を整えていなかったことで希望が叶わなかった例です。 財産の行き先をどう決めるかは、家族にとって避けて通れない課題です。成功例では遺言や話し合いが安心を生み、失敗例では曖昧な記録が混乱を招きました。 大切なのは金額の大小ではなく、本人の意思を形にして残すことです。お金は争いの種にも、安心の礎にもなります。その差を生むのは、備えの有無にほかなりません。 エンディングノート、デジタル遺品、お金の行き先。どのテーマにも共通しているのは、「小さな準備が大きな安心を生む」ということです。 成功した人は、ほんの数行のノートや一覧表を残しただけで家族を支えました。失敗した人は、情報が不足していただけで大きな負担を背負うことになりました。 完璧な準備は難しくても、できる範囲の工夫は誰にでもできます。今日から一歩を踏み出すことが、未来の家族への最大の贈り物になるのです。![]()
無計画な処分が残した後悔
![]()
残す物と手放す物の分け方
![]() 」のように、遺品整理から不用品回収まで幅広く対応してくれる業者を利用するのもおすすめです。遺品整理のプロが丁寧に整理してくれるため、大量の片付け作業もスムーズに進められます。
」のように、遺品整理から不用品回収まで幅広く対応してくれる業者を利用するのもおすすめです。遺品整理のプロが丁寧に整理してくれるため、大量の片付け作業もスムーズに進められます。お金の行き先を決めるという選択

奨学金への遺贈で未来を支援
![]()
人生の振り返りが導いた寄付の決断
![]()
遺言書の作成で得られた安心感
![]()
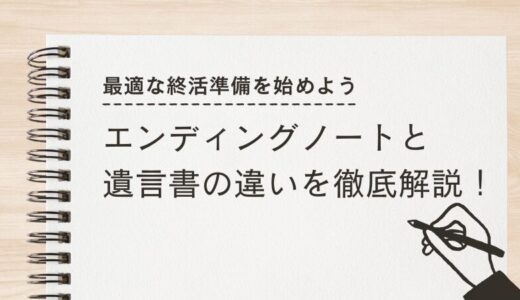 エンディングノートと遺言書の違いを徹底解説!最適な終活準備を始めよう
エンディングノートと遺言書の違いを徹底解説!最適な終活準備を始めよう
曖昧なメモが招いた相続の混乱
![]()
お金の準備から得られる気づき
体験談から見えてくること