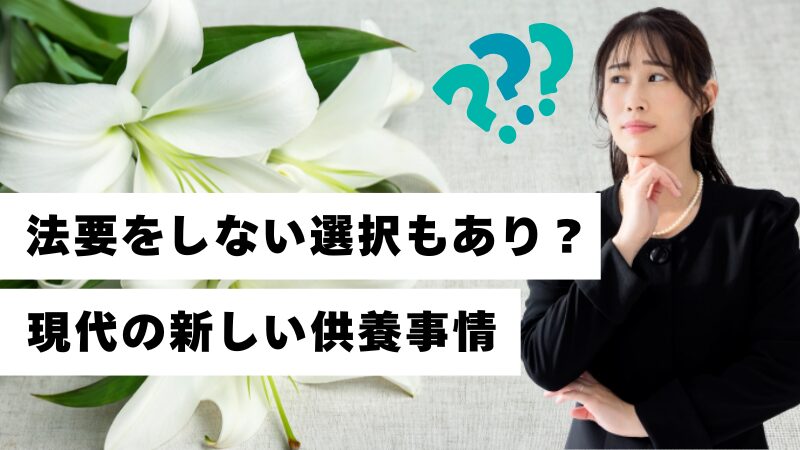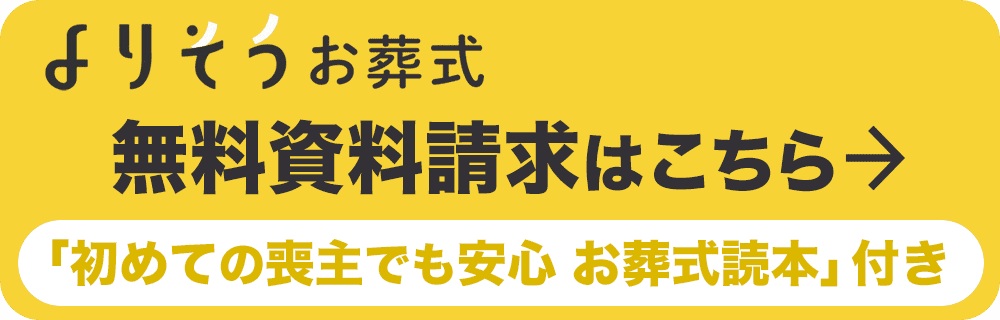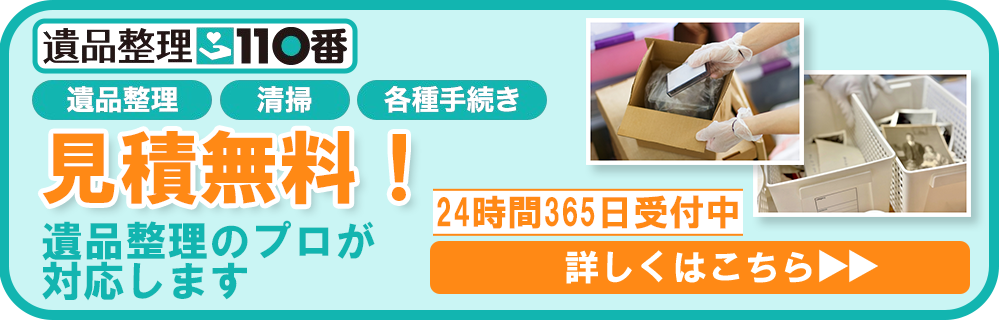近年、「毎年の年忌法要は行わない」という家庭が増えつつあります。その背景には、家族構成や生活様式の変化、高齢化、居住地の分散、さらには費用負担の問題があります。
本記事では、これまでの法要に代わる新しい供養の事例や、法要を行わない決めた際の具体的な手順・注意点について詳しく解説します。さらに、従来の法要と新しい供養方法の費用比較も行い、現代ならではの供養事情を総合的にご紹介します。
法要離れが進む背景

年忌法要など仏事を取り巻く環境は、社会全体の変化とともに大きく様変わりしています。特に核家族化・少子高齢化が進んだ結果、「法要を続けたくても続けられない」家庭が増えているのが実情です。
ここでは、その主な背景をデータとともに整理して解説します。
単身世帯の急増と核家族化
近年、日本の世帯構造は大きく変化しました。厚生労働省の調査[1]によると、2023年時点で一人暮らしの単独世帯は全世帯の34.0%に達し、最も多い世帯形態となりました。2001年に約24%だった割合が20年あまりで1.7倍に増加し、2019年には「夫婦と子の世帯」を上回っています。
反対に、祖父母・親・子が同居する三世代世帯は約4%程度まで減少し(1980年代は15%前後)、大家族で先祖供養をする形態自体が減っているのです。
家族の人数が少なければ、法要を主催・継続する負担を担える人が少なくなるのも自然な流れでしょう。
遠距離家族で薄まる親戚づきあい
核家族化に加え、都市部への人口集中も供養の形を変える要因です。
地方で生まれ育っても就職や進学で都市圏に移り住む人が増え、実家から遠方に暮らすケースが珍しくなくなりました。その結果、故郷に残る墓や菩提寺に親族が集まって交流する機会も減少しています。
例えば以前なら一周忌や三回忌には親戚一同が集まったものですが、昨今はそもそも招待する親族の数自体が少なく、また遠方なら交通の負担も大きいため、欠席するケースも増えています。
こうした状況では、大規模な法要を取り仕切る「本家」的な存在も希薄になり、一家族ごとに簡素化・縮小化した供養が選択されるようになっています。
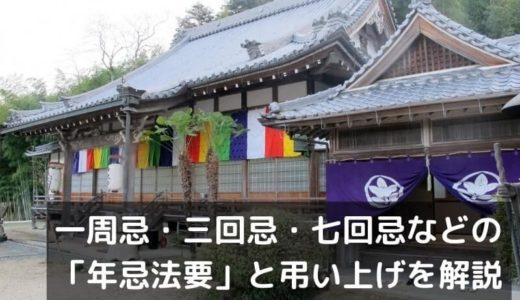 一周忌・三回忌・七回忌…年忌法要と弔い上げをわかりやすく解説
一周忌・三回忌・七回忌…年忌法要と弔い上げをわかりやすく解説
高齢化と負担の増加
日本人の平均寿命は男性81.09歳・女性87.13歳(2024年時点)[2]に達し、法要を主催する側も参列する側も高齢化しています。そのため、法要の準備に追われる主催者だけでなく、高齢の参列者にとっても移動や長時間の会食は大きな負担です。
また子供の数が減った分、一人あたりの金銭的・時間的負担が重くなっていることも見逃せません。「自分たちだけでは手が回らない」「無理をしてまで続けられない」という現実的判断から、年忌法要を行わない・減らす家庭が出てきています。
費用負担の問題

年忌法要には意外と多くの費用がかかります。四十九日法要や一周忌は一般的に約19~37万円程度かかり、三回忌や七回忌も同規模なら同水準です。
主な費用の内訳は次の通りです。
こうした出費の大きさから「そこまでお金をかけなくても……」と感じる人が増えています。
コロナ禍による影響
2020年以降の新型コロナウイルス流行も、法要簡素化の追い風となりました。
「三密」を避けるため大勢が集まる年忌法要を中止・延期する例が相次ぎ、とりわけ2020年春の緊急事態宣言期には一周忌法要の実施件数が前年比63%減、三回忌も前年比-38%と大幅に減少[3]しました。感染不安から最初から計画しない家庭や、法要自体をキャンセルする動きも生まれています。
コロナ禍でやむなく法要をしなかった家庭が、「やらなくても問題なかった」「気持ちだけで十分だった」と感じたケースも多く、コロナ収束後も法要離れが続く一因となっています。
また、コロナ禍を機に一周忌のみを縮小して行い、三回忌以降は行わない選択をした家庭もみられます。
葬儀の小規模化の影響
葬送全体の動向として、葬儀の簡素化・家族葬化が顕著になっています。
鎌倉新書の調査[4]によれば、2024年に行われた葬儀の50.0%が家族葬で行われ、一般葬は30.1%にとどまりました。参列者数も平均38人と過去最少を更新。大規模葬儀の減少で、葬儀費用総額も平均118.5万円と低水準となっています。
家族葬などの小規模な葬儀が増えると、その後の年忌法要も簡素化される傾向があります。一周忌を身内だけで行い、三回忌以降はさらに小規模化または省略する流れが広がっているのです。
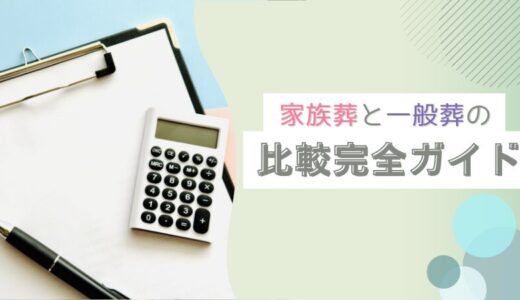 家族葬と一般葬の比較完全ガイド
家族葬と一般葬の比較完全ガイド
このように、家族構成・地理的事情・金銭面・衛生面などの要因が重なり、年忌法要を見直す家庭が増えています。「昔からの習慣だから」と続けるプレッシャーは薄れ、各家庭の状況に合わせて柔軟に供養の形を選ぶ時代になっています。
法要を行わない場合の新しい供養

近年、「形式ばった法要は行わないまでも、故人を偲ぶ気持ちは表したい」という思いから、各家庭で工夫した供養を行う例が増えています。
核家族化や家族が遠方に暮らす現代ならではの、新しい供養方法の一例をご紹介します。いずれも無理なく実践できる方法です。
離れていても思い出を共有する
故人の命日に、離れて暮らす家族や親族同士で電話やメール・SNSを通じて「今日は〇〇さんの命日ですね」と声を掛け合い、思い出話を共有します。
また、家族で共有できるオンラインアルバムを作り、お気に入りの写真や動画、メッセージをアップロードして故人を偲ぶこともできます。
実際に集まれなくても、インターネットを活用して皆で故人への想いを分かち合えるのが利点です。
遠方から供花や弔意を届ける
遠方に住んでいて墓参りに行けない場合、弔電(お悔やみ電報)や供花を手配して故人宅や菩提寺へ届けてもらう方法もあります。
最近はインターネットから弔電・供花を依頼できるサービスも普及しており、直接参列できなくてもお供え物やメッセージで気持ちを伝えることができます。
例えばVERY CARDなら、14時までの申込で弔電を全国即日配達可能(一部地域・商品を除く)です。1,000種類以上ものオリジナル文例を使用できるため、心のこもった弔電をご遺族に届けられます。
 格安弔電で評判!VERY CARDの特徴と使い方、文例、サービス比較(ベリーカード)
格安弔電で評判!VERY CARDの特徴と使い方、文例、サービス比較(ベリーカード)
略式の法要を行う
法要自体を省略・簡略化する例も見られます。菩提寺のお坊さんに協力してもらい、ごく近親者だけでお墓の前で短時間の読経と焼香だけを行う方法です。
正式な会場準備や会食は省き、お布施を渡して必要最低限のお経のみあげてもらう「略式法要」として、負担を軽くしつつ故人を弔うことができます。
お寺や霊園の合同法要に参加する
年に一度など、お寺や霊園で檀家合同の慰霊祭・法要が行われている場合、それに参加して故人を供養するという選択肢もあります。
他の家の故人と一緒にはなりますが、個別に法要を営まなくても読経供養を受けられるため、無理なく供養を続けられます。
法要をまとめて行う
本来は別々に行う初七日や四十九日を、葬儀と同じ日に繰り上げて行う方法です。
葬儀当日に初七日法要も行う「式中初七日」は現在では一般的になりましたが、コロナ禍では感染予防のため四十九日法要まで葬儀当日に行う「式中四十九日」も増加しました。
一度で済ませれば、その分遺族の負担や手間を軽減できます。
形式にとらわれず、「できる範囲で心を尽くす供養」を選ぶ家庭が増えています。大切なのはあくまで故人を想う気持ちであり、僧侶を招いて大勢でお経をあげることだけが供養ではありません。
法要を行わないと決断した場合

「うちはもう毎年の法事はやめよう」と家族で決断した場合でも、円滑に進めるためのポイントがあります。
ここでは親族間の相談から菩提寺への連絡・調整、香典や会食を辞退する際のマナーまで、おさえておきたいポイントを解説します。
近親者で十分に話し合う
まず大切なのは、故人と縁の深い家族・親族内でしっかりと話し合うことです。特にご兄弟姉妹や故人の配偶者など、法要を主催・参加する立場の人たち全員の意向を確認しましょう。
誰か一人でも「やはり形式通りやりたい」という希望があれば、後々しこりを残しかねません。「なぜ法要を行わないのか」「代わりにどう供養するのか」をしっかり話し合い、全員が納得した上で決めることが肝要です。
また故人の遺志も考慮しましょう。故人が生前「形式ばったことはしなくていい」と言っていた場合は尊重すべきですし、反対に「ちゃんと法要してほしい」と望んでいたなら、その気持ちをどう汲むか家族で相談が必要です。
いずれの場合も、身内で事前に十分な対話をしておくことが円満な決定への第一歩です。
菩提寺・お墓の管理者への相談
先祖代々のお墓や菩提寺がある場合、法要を行わない旨をお寺に伝える配慮も必要です。特に檀家としてお世話になっている菩提寺があるなら、「今年の〇回忌法要は家族内で供養することにしました」と事前に伝えておくと良いでしょう。
僧侶側も「今年は法要の依頼がないな」と気にかける場合がありますし、何より無断で済ませると不義理と受け取られかねません。菩提寺によっては「ではお墓で簡単にお経だけあげましょうか」と提案くださるケースもありますし、離檀に発展しないよう配慮することもできます。
寺院がない場合でも、霊園管理者などに年忌法要堂の予約をキャンセルする場合は早めに連絡しましょう。お寺との円満なお付き合いを続けるためにも、法要中止・縮小の旨は一報入れるのがマナーです。
親族や関係者への通知

本来であれば年忌法要に招待していたであろう親戚・知人がいる場合、事後または事前にお知らせを出すことをおすすめします。
近しい親族であれば電話で事情を伝えて了解を得るのも良いでしょう。あまり合わない親戚や故人の友人知人には、ハガキで挨拶状を送る方法が丁寧です。
一般的には一周忌を家族のみで行った後、速やかに「無事一周忌法要を執り行いました」と報告する挨拶状を出すことが多いです。
文章には葬儀の際にお世話になったお礼、一周忌を〇月〇日に家族だけで行った旨、そして「昨今の事情を鑑みご理解ください」という断りとお詫びを記します。
香典・供物・会食の辞退を伝える
法要を開かなくても、香典やお供えを送ろうとしてくださる方も少なくありません。
特にご年配の方などは「たとえ集まりがなくてもお仏前(香典)だけは」と考えることもあります。香典が届いた場合はお返しが必要になるため、負担を減らしたい場合は事前に辞退の旨を知らせます。
あらかじめ案内状や口頭で「お気持ちだけありがたく頂戴しますが、ご香典や供花などは辞退申し上げます」と丁重に伝えましょう。
会食も同様に、「今回は控えさせていただきます」と伝えると親切です。
形だけでも僧侶にお願いしたい場合
「家族だけで供養するけれど、お経だけはあげてほしい」と考える方もいるでしょう。菩提寺が遠方だったり檀家でなかったりする場合は、僧侶派遣サービスを利用する方法があります。
例えば「よりそうお坊さん便」は、ネットで希望の宗派の僧侶を手配できるサービスで、自宅や墓前でのお経のみを依頼することも可能です。
菩提寺がなくても安心して略式法要ができるため、こうしたサービスを活用する家庭が増えています。
 初めての喪主でも安心!『よりそうお坊さん便』徹底ガイド【僧侶手配】
初めての喪主でも安心!『よりそうお坊さん便』徹底ガイド【僧侶手配】
法要を行わないと決めた場合は、知らせるべき相手にきちんと知らせ、礼を尽くすことが大切です。命日にはお墓参りや花を供えるなど、供養を続ける意思を示すと周囲の理解を得やすくなります。
「形式は省いても、故人を偲ぶ気持ちはある」という姿勢が、親族円満の秘訣と言えます。
供養の形を支えるサービスと利用者の声

ここまで見てきたように、現代の供養事情に合わせて様々な支援サービスも登場しています。伝統的な供養に代わる新サービスを知っておくことで、選択肢がぐっと広がるでしょう。
小さなお葬式
小さなお葬式は、葬儀から法要まで低価格で提供する大手葬儀社です。
一日葬や火葬式(直葬)などのシンプルなプランの先駆けで、家族葬プランも充実しています。葬儀後のアフターサービスもしっかりしており、年忌法要の相談にも乗ってくれます。
![]() 長野県・男性
長野県・男性
よりそうお葬式・よりそうお坊さん便
よりそうお葬式![]() は、ネットで葬儀社探しから見積り比較までできるサービス。低価格・明朗会計・24時間サポートが強みで、多宗派対応にも定評があります。
は、ネットで葬儀社探しから見積り比較までできるサービス。低価格・明朗会計・24時間サポートが強みで、多宗派対応にも定評があります。
![]() 千葉県・女性
千葉県・女性
また、「よりそうお坊さん便」は菩提寺がなくても僧侶を手配できるサービスで、定額なので費用面の不安が少ないのが特徴です。
法事・法要のほか、戒名授与にも対応しており、現代のライフスタイルに合った柔軟な供養が可能です。
![]() 東京都・男性
東京都・男性
安心葬儀
安心葬儀は全国対応の葬儀社紹介サイトで、24時間365日サポートが強みです。複数社を一括見積できるので、効率よく希望に合った葬儀社を見つけることができます。
また、終活情報や葬儀・法要の豆知識も多数提供しています。「繰り上げ法要」に関する解説記事など、従来の形式にとらわれない供養方法の情報発信にも力を入れています。
![]() 大阪府・男性
大阪府・男性
VERY CARD|電報サービス
VERY CARDは、弔電・供花のオンライン手配を提供するサービスです。スマホやPCからお悔やみ電報を申し込める手軽さが支持されており、法人向けにも利用されています。
遠方から気持ちを伝える手段として、今後ますます需要が高まりそうです。
![]() 福岡県・女性
福岡県・女性
遺品整理110番

年忌法要を行わない代わりに、故人の遺品整理を丁寧に行って供養とする方もいます。その際に頼りになるのが遺品整理の専門業者です。
「遺品整理110番![]() 」は全国対応の大手サービスで、電話一本で見積もり・作業を依頼できます。遺品の仕分け・不用品の処理・簡易清掃など、遺品整理に必要なサービスはすべて基本プランに含まれています。
」は全国対応の大手サービスで、電話一本で見積もり・作業を依頼できます。遺品の仕分け・不用品の処理・簡易清掃など、遺品整理に必要なサービスはすべて基本プランに含まれています。
また、遺品供養や特殊清掃などのオプションも豊富です。自分だけで作業するのは難しい人や、できるだけ費用を抑えたい人に向いています。
![]() 静岡県・女性
静岡県・女性
![]() 埼玉県・男性
埼玉県・男性
わたしたちの墓じまい
少子化でお墓の継承者がいない、お墓が遠方で維持管理できないといった理由から墓じまいを選ぶ家庭が増えています。
わたしたちの墓じまい![]() は墓じまい専門の代行業者で、離檀交渉から墓石撤去、改葬手続き、遺骨の永代供養先紹介までトータルにサポートしてくれます。
は墓じまい専門の代行業者で、離檀交渉から墓石撤去、改葬手続き、遺骨の永代供養先紹介までトータルにサポートしてくれます。
創業2002年・実績800件以上で、利用者からの評価も高いサービスです。改葬許可などの行政手続きも代行してくれるため、初めてでもスムーズに進められます。
![]() 長野県・男性
長野県・男性
これらのサービスはいずれも、無理のない形で心のこもった供養を実現するための手段です。利用者からは「頼んで良かった」「安心して故人を偲べた」という声が多く聞かれます。
伝統と新しい形式を織り交ぜつつ、自分たちらしい供養スタイルを築くため、必要に応じてプロの力を借りるのも賢い選択肢です。
それぞれの家族に合った供養の形を

現代では核家族化や高齢化、経済的負担などから、毎年の法要を続けるのが難しい家庭が増えています。「法要をしない」という選択も、もはや珍しいことではありません。
大切なのは形式ではなく、故人を想う気持ちです。命日にそっと手を合わせたり、写真を眺めて故人を偲ぶ時間を持ったりするだけでも、きっと故人は喜んでくれるはずです。
現代の供養事情がどう変わろうとも、その本質は変わりません。本記事が、自分たちに合った供養の形を考える際のヒントになれば幸いです。