大切なお子さんを失うことは、ご家族にとって言葉では表せないほどの深い悲しみです。しかし、深い悲しみの中でも葬儀の準備や手続きを進めなければなりません。
本記事では、幼い子どもを亡くした場合の葬儀について、基本的な流れや注意点を解説します。小さな棺や祭壇の準備、火葬の際の工夫、周囲への訃報の伝え方など、実際の手続きに役立つ情報をまとめました。
目次
幼い子を亡くした直後に必要な手続きと準備

幼いお子さんを亡くした直後は、深い悲しみの中でも必要な手続きや準備を進めることが求められます。死亡診断書の受け取りや役所への届出、葬儀社選びなど、やるべきことは多岐にわたります。
この章では、最初に取り組むべき公的手続きと、葬儀に向けた準備について解説します。ご家族だけでは抱えきれない場合は、周囲の助けや専門サービスの利用も検討し、適切に進めていきましょう。
最初に行う届出と連絡
幼いお子さんが亡くなった際には、まず医師から死亡診断書を受け取ります。出生届を出した後に亡くなった場合は7日以内に市区町村役場へ死亡届を提出する必要があります。死産(妊娠12週以降)の場合は死産届を提出しなければなりません。
役所への手続きは、葬儀社に依頼すると代行してもらえることもあります。届け出後に発行される火葬許可証がなければ火葬できないので、注意が必要です。
ご家族は親族や関係者への連絡も行いますが、電話やメールで簡潔に伝えるだけでも問題ありません。深い悲しみで対応が難しい場合は、親戚など信頼できる人に代理連絡をお願いする方法もあります。
葬儀の日程調整も早めに検討します。日本では法律上、死亡後24時間は火葬できません。妊娠24週以降の死産の場合も同様です。したがって通夜や告別式は、ご逝去翌日以降の日程となります。
ご遺体を安置する場所やドライアイスの使用については、葬儀社と相談して決めましょう。
 葬儀の流れを解説 – 臨終から告別式まで、葬儀の準備と流れを徹底解説
葬儀の流れを解説 – 臨終から告別式まで、葬儀の準備と流れを徹底解説
葬儀プランの選択
葬儀の形式は家族葬・一日葬・直葬の中から、心身の負担と参列者の規模に合うものを選びましょう。複数社で見積もりを取り、内容や費用、式場・火葬場までの距離などを比較しましょう。
定額プランのある葬儀社を選べば、調整もスムーズです。予算に合わせて幅広いプランが用意されている「小さなお葬式」なども候補に含め、条件に合うサービスを慎重に選びましょう。
周囲への連絡と学校・職場への対応
訃報は事実を簡潔に伝えます。「家族のみで営む」「参列は辞退」など、方針も最初に添えると問い合わせが減ります。つらいときは、信頼できる人に連絡役をお願いしましょう。
園・学校へは担任や管理職に連絡し、クラスメイトへの知らせ方やお別れの機会をどのように設けるか相談します。兄弟姉妹には、年齢に応じた言葉でお別れを伝えてあげてください。
職場は上長へ連絡し、休暇と復帰の目安のみ共有で十分です。細かな事情まで話す必要はありません。弔意の受け取りが負担なら、辞退の意思を添えると気が楽になります。
一人で抱え込まないで
深い悲しみの中で手続きや準備を進めるのは、ご両親にとって大変な負担です。一人で抱え込まずに、親族や友人、葬儀社のスタッフなど頼れる人には遠慮なく頼りましょう。とくに葬儀社は遺体搬送から手続き代行まで幅広くサポートしてくれるため、困ったことは相談すれば力になってくれます。
幼い子どもの葬儀は通常以上に心身の負担が大きいものです。「悲しみで動けない時は他の人に任せてもいい」——。そのように割り切って、まずは最低限のことを滞りなく進めることを目指しましょう。
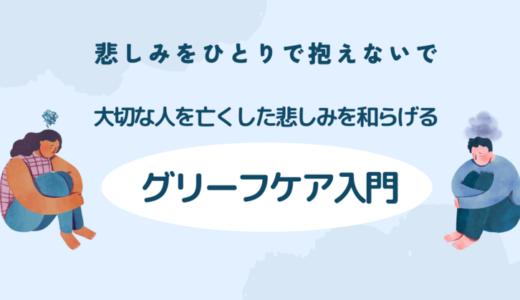 【悲しみをひとりで抱えないで】大切な人を亡くした悲しみを和らげるグリーフケア入門
【悲しみをひとりで抱えないで】大切な人を亡くした悲しみを和らげるグリーフケア入門
子ども用の棺と納棺準備

幼いお子さんには専用の小さな棺が用意されています。一般的な葬儀プランでも小児用の棺がオプションに含まれることが多く、単品手配の相場は数千円〜2万円程度です。
ただし、小さな棺の在庫を持たない葬儀社もあります。葬儀社を選ぶ際には、子ども用の棺の手配が可能か確認しておくと安心です。
祭壇準備のポイント
納棺の際には、生前にお子さんが好きだった服や清潔なベビー服を着せることが一般t系です。おくるみで優しく包む方法もあります。
また、必要に応じてエンゼルメイク(死化粧)や湯灌(お風呂での洗い清め)を依頼することもできます。お子さんのお顔が安らぐよう、葬祭スタッフが丁寧に整えてくれます。
棺に納める際には、ご家族も傍について愛情込めて見守ってあげてください。
葬儀当日に使用する祭壇の準備もポイントです。子どもの祭壇では、故人の好きだった花や色合いで明るく飾ることがあります。白やパステルカラーの花を中心に、天使や星をモチーフにした装飾が施される例も見られます。
遺影写真も、できれば生前に笑顔だった写真を選び、可愛らしい額に入れて飾りましょう。故人が大切にしていた人形を祭壇脇に置いたり、好きだったキャラクターのグッズをそばに添えたりすると、より温かな雰囲気になります。
ただし宗教や式場の方針によっては飾り方の制限もあるため、事前に葬儀社と相談しながら準備を進めてください。
副葬品(棺に入れる品物)の選び方
副葬品とは、故人とともに棺に納める品物のことです。お子さんの葬儀では、親として「これだけは持たせてあげたい」というお気持ちから、お気に入りのものを入れてあげたくなるでしょう。
しかし、棺に入れるものは燃えるものに限るという原則があります。火葬炉で安全に焼却でき、かつお骨に害を与えないものだけを選ぶ必要があります。
- 折り紙で折った鶴や手紙(故人へのメッセージ)
- お気に入りのハンカチやタオル
- 布製の小さなぬいぐるみ
- おむつや衣類
- 紙製の絵本(厚手の本は避ける)
- 写真(数枚まで)
- 金属類(メガネ、腕時計、おもちゃの車など)
火葬炉を傷めたり有害物質が発生する恐れがある - ガラス製品(哺乳瓶など)
破裂の危険がある - 電子機器や電池を含む玩具、厚みのあるプラスチック製品(大型の人形など)
燃え残りや有毒ガスの原因となる
「どうしても〇〇を持たせたい」というお気持ちがある場合は、葬儀担当者と相談しながら最善の形を探してください。副葬品に込めた愛情は、形がどうであれ必ずお子さんに届くことでしょう。
参列者の服装と子どもの喪服マナー

喪主・遺族は一般的な喪服を着用します。ただし、赤ちゃんや小さなお子さんの葬儀では、お母様が平服で参加するケースもあります。出産後間もないお母様の場合、身体への負担や授乳の兼ね合いもあるため無理のない服装を心がけましょう。
状況に応じて、略式でも構わない旨を周囲に伝えておくと安心です。
参列する子ども達の服装について厳格な決まりはありませんが、派手な服装は避けるのがマナーです。小学生以上で制服がある場合は制服が無難です。
小さなお子さんを連れて参列する親御さんは、式の最中に子どもが騒いだ場合は一時退出するなど、周囲への配慮を心がけましょう。しかし、幼い兄弟姉妹が泣いてしまうのは当然のことでもあります。周りの大人も温かく見守り、無理のない範囲で参列させてあげましょう。
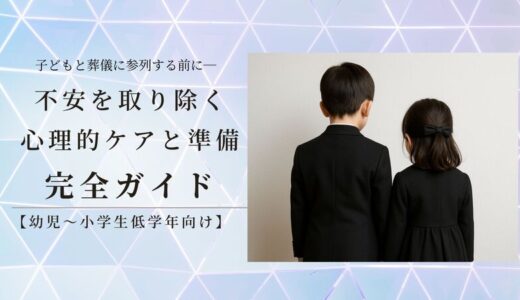 子どもと葬儀に参列する前に―不安を取り除く心理的ケアと準備完全ガイド【幼児~小学生低学年向け】
子どもと葬儀に参列する前に―不安を取り除く心理的ケアと準備完全ガイド【幼児~小学生低学年向け】
小さな安らぎの空間づくり
小さな棺や可愛らしい祭壇は、短い人生を精一杯生きたお子さんへのご家族の愛情の表現です。
準備を進める中で、「もっと〇〇してあげれば良かった」と後悔や自責の念が湧くこともあるでしょう。しかし、ご両親がお子さんを想って選んだ花や服、おもちゃの一つ一つが何よりの供養になります。
お別れの準備が辛く感じられることもありますが、どうか「これがこの子のためにしてあげられる最後の子育てなんだ」という気持ちで取り組んでみてください。
悲しみで手が動かない時は無理をせず、周囲に頼って構いません。小さな棺に託した大きな愛情は、きっと天国のお子さんにも届いていることでしょう。
葬儀当日の流れと見送りの方法

子どもの葬儀当日は大人の葬儀と基本的な流れは同じですが、規模が小さく進行はシンプルになることが一般的です。この章では、通夜から告別式、火葬・収骨までの当日の流れを説明し、子どもの葬儀特有のポイントに触れます。
お子さんを送り出す最後の時間をできるだけ穏やかに過ごせるよう、心構えや当日の留意点を確認しておきましょう。
通夜から告別式までの流れ
葬儀当日の流れは、基本的には通夜→告別式→火葬→収骨という順序になります(※一日葬の場合は通夜を省略)。
子どもの葬儀では参列者が家族・親戚のみのことが多く、形式は柔軟に調整できます。たとえば一日葬を選択すれば、朝から告別式のみを行い、そのまま火葬に向かいます。前夜に通夜を行う場合も、近親者だけで短時間の見送りになることが一般的です。葬儀社が詳細なスケジュールを案内してくれるので、事前に確認しておきましょう。
開式後、僧侶による読経(または神父・牧師による祈祷、無宗教なら黙祷など)、焼香や献花といった儀式を行います。
その後、出棺前にお別れの儀として、参列者全員で棺にお花を手向けます。お子さんの好きだった花や色とりどりの花を棺いっぱいに入れてあげましょう。悲しみが溢れても当然の場面ですので、遠慮せずに想いを伝えてください。
火葬・収骨の際の注意点
出棺は霊柩車が一般的ですが、地域や状況によっては自家用車を利用することもできます。希望があるときは、火葬許可証の携行や安全面を含めて事前に葬儀社へ相談しましょう。送る形は一つではありません。家族が納得できる方法がいちばんです。
小さなご遺体は、炉の状態によってお骨が残りにくいことがあります。経験豊富な技師でも、必ずしもきれいに遺骨を残せるとは限りません。お骨が拾えない可能性も、あらかじめ念頭に置いておきましょう。
火葬が終わったら収骨(骨上げ)です。お子さんのお骨は非常に小さいため、小さな箸やスコップを用いて骨壷へ納めます。お骨が残らなかった場合でも、火葬場によっては焼却炉内の灰の一部を壷に収めてくれることがあります。
収骨後、骨壷は白木の箱に納められ、ご自宅かお墓へ持ち帰ります。小さなお子さんの場合、すぐにお墓に納骨せず自宅供養(手元供養)を選ぶご家庭もあります。心の整理がつくまで、お家でゆっくりお子さんを見守り続けるのも選択肢の一つです。
 手元供養のアイデア徹底解説|自宅で偲ぶ新しい供養スタイル
手元供養のアイデア徹底解説|自宅で偲ぶ新しい供養スタイル
参列者との接し方

葬儀当日は、家族だけでなく近親者や友人が参列することもあります。ご両親はどのように振る舞えば良いか悩むかもしれませんが、無理に気丈に振る舞う必要はありません。
悲しみが深いときは挨拶も簡単で構いませんので、「本日はお忙しい中ありがとうございます」など短くお礼を伝えたあとは、そっとしておいてもらいましょう。周囲もあまり感情をあおるようなことばは避け、静かに見守るのがマナーです。
時には、善意の言葉が重く感じられることもあるでしょう。その場合は席を外す、同席者に橋渡しを頼むなどして、心を落ち着かせましょう。
式後のお礼や香典返しは、落ち着いてからで差し支えありません。今日は「お別れ」に集中して良いのです。
子ども同士の別れ
故人と同年代のお子さんが参列する場合、特に配慮が必要です。兄弟姉妹や仲良しのお友達など、小さな子にとって「死」という概念は理解しにくく、恐怖を感じるかもしれません。
無理にお別れの場に立ち会わせる必要はありませんが、参列する場合は事前に「これは怖い場所ではなく、〇〇ちゃんにさよならを言う大切な場所なんだよ」と優しく説明してあげてください。式後には、「〇〇ちゃんにバイバイできたね」と声をかけ、感じている悲しみや不安を受け止めてあげましょう。
学校のお友達が参列しない場合でも、先生がクラスでお別れや追悼の時間を設けてくれることがあります。後日、お友達からのお手紙や絵を預かることもあるかもしれません。そうした周囲の子ども達の気持ちも大切に受け止め、お子さんが多くの人に愛されていた証として胸に留めておきましょう。
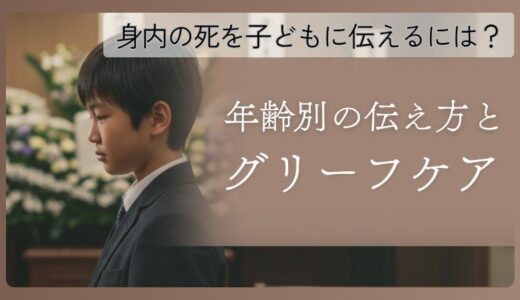 身内の死を子どもに伝えるには?年齢別の伝え方とグリーフケア
身内の死を子どもに伝えるには?年齢別の伝え方とグリーフケア
「最後のお別れ」を悔いなく
葬儀当日は、ご家族にとって「最後の時間」です。深い悲しみと緊張で、後になって「あのときこうすれば良かった」と思うこともあるかもしれません。
しかしご両親が涙ながらにお子さんを想い、抱きしめ、声をかけたその瞬間が何よりの愛情表現です。お別れの儀で手向けたお花や大好きだったぬいぐるみと一緒に旅立つお子さんの姿を心に焼き付け、天国への門出を見送ってあげましょう。
周囲への訃報の伝え方

子どもを亡くしたことを周囲に伝える際には、相手への配慮と自分自身の心の負担軽減を考慮することが大切です。
この章では、訃報を伝える方法、香典や弔電などに対するマナー、葬儀後の支え合い方について説明します。デリケートな状況だからこそ、適切な伝え方とマナーを知っておくことで、不必要な気遣いや誤解を避けることができます。
訃報の伝え方
親族以外の方への訃報は、電話・メール・SNSなど様々な手段がありますが、できるだけ直接伝えることが望ましいとされます。特に親しい友人ほどショックが大きいので、可能であれば電話で伝えます。
伝える内容は簡潔で十分です。「実は◯◯が◯日に息を引き取りました。葬儀は家族のみで執り行います」と、事実と最低限の情報にとどめます。
詳細を尋ねられても、つらい場合は「まだ気持ちの整理がつかなくて…」とだけ伝え、無理に説明しなくて大丈夫です。多くの方はそれ以上詮索せず、そっと見守ってくれるでしょう。
訃報の連絡方法は、状況に応じて負担の少ない手段を選ぶことが大切です。
- 電話:親しい人向け。短く要点のみ。
- 個別メッセージ:範囲を絞って丁寧に。
- お知らせ状:遠方・連絡先不明者に。落ち着いてからでも可。
- SNS:公開範囲を限定。必要以上に広げない。
最後に、参列の可否や辞退の意向を一言添えると、相手も動きやすくなります。
 訃報連絡と案内のマナー|電話・メール・SNSの使い分けと宗教形式別のポイント
訃報連絡と案内のマナー|電話・メール・SNSの使い分けと宗教形式別のポイント
周囲からの言葉に対するの返答例
訃報を伝えた際、よくかけられる言葉にどう返答するか戸惑うこともあります。
たとえば「何とお声をかけてよいか…」と言われた場合には、「お気持ちだけで十分です」と答えればよいでしょう。「お子さんの分まで頑張ってください」と言われたときも、心が追いつかない時は静かに頷くだけでもかまいません。
うまく返さねばと気負わず、その場は「ありがとうございます」とだけ伝え、時間をかけて気持ちを整理していきましょう。
香典への対応
子どもの葬儀でも、基本的なマナーは大人の場合と同じです。親族や知人から香典をいただいた場合は、後日(忌明けの四十九日法要後が一般的)にお礼の品を贈ります。
金額の多少にかかわらず、一律のお菓子やタオルセットを送るケースもあります。もしご自身で手配する余裕がなければ、葬儀社が香典返しの手配サービスを用意していることもあるので利用しましょう。
弔電の受け取り

突然の訃報で時間がない場合、VERY CARDなら14時までの申込みで弔電を当日中に全国配達できます。料金は全国一律1,650円(税込)〜で、オリジナル文例も約1,000種類以上と豊富です。
弔電を受け取ったら、無理のない範囲で後日お礼状を無理のない範囲で送りましょう。香典や供花のお礼状とまとめて出しても差し支えありません。
弔問への向き合い方
葬儀に参加できなかった方から、後日弔問を受けることもあります。忌中(四十九日まで)の期間は、訪問日時を事前に打診された際だけ受け付け、無理な場合は遠慮なくお断りして構いません。
長居されるのが辛い場合は、「まだ落ち着かず失礼をお許しください」と切り上げてもらいましょう。周囲の善意はありがたいものですが、ご自身の心と体が一番大切です。対応できる範囲で礼を尽くし、難しい時には適度に距離を置くことも必要です。
身近な人たちの優しさに包まれて
周囲の厚意は、葬儀を進めるうえで大きな力になります。お手伝いの申し出があれば、負担にならない範囲で頼らせてもらうのもよいでしょう。
お香典や弔電などを受け取っても、すぐに感謝を言葉にできない日もあります。その場合は、香典帳や弔電の控えを整え、落ち着いてからお礼状を送れば失礼には当たりません。
助けを求めることは甘えではありません。必要なときに必要な支えを受け取りましょう。
小さな命と共に生きていく

葬儀が終わっても、気持ちがすぐに落ち着くことはありません。泣きたい日も、何も手につかない日もあるでしょう。できる日は少しだけ、できない日は何もしなくても大丈夫です。その繰り返しが、心の整理を助けてくれます。
記念日や法要は、心の区切りを作る良い機会です。初七日・四十九日・百か日・一周忌など、その都度の供養の方法に正解はありません。自宅で静かに手を合わせる、小さく集まって思い出を話すなど、その時の体調と気力に合わせて選んでください。
眠れない日が続く、食事がとれない、仕事や育児に支障が出ている場合は、地域の相談窓口や医療機関、葬儀社が紹介するグリーフケアの窓口に相談することが大切です。
今日できる一つを大切にしながら、小さな命と一緒にこれからの時間を整えていきましょう。







