事故や災害で、家族を二人以上続けて見送ることがあります。その際、葬儀を一つにまとめるべきか、別々に行うべきか悩むことがあるでしょう。時間や体力、心の負担を考えると、答えはすぐに出せません。
この記事では、判断の基準や葬儀の準備、当日の進行までの流れをわかりやすく解説します。
目次
葬儀の進め方の基本を押さえる
最初に決めたいのは「何を優先するか」です。故人の遺志、家族の気持ち、宗教上の作法、参列しやすさ。どれも大切ですが、全部を同時に満たせない場面もあります。
まずは全体の流れを大まかに決め、家族全員が同じ方向を見られるようにすると迷いが減ります。
合同葬儀か別々かを決める

同じ会場・同じ進行で二人以上を見送るのが合同葬です。通夜から告別式、火葬までの流れを一つにまとめます。
別々に行う場合は、それぞれ個別に祭壇や案内を用意します。どちらが正しいという決まりはありません。遺志・遺族の負担・参列者の環境の三つを軸に、家族でよく話し合いましょう。
- 故人の遺志をどこまで尊重できるか
- 家族の体力と時間に無理はないか
- 参列者の移動や手続きは分かりやすいか
最優先すべきことを決めると、次に何を決めるかが見えてきます。
宗教・宗派の確認は早めに
読経や献花・焼香の作法、戒名や洗礼名の扱いは宗派で異なります。
まず故人の遺志を確かめ、同じ宗派なら共通の進行で整えます。異なる場合は、式の中に共有部分と個別部分を分ける設計が安心です。献花台や掲示の表示も、故人ごとに分かるようにします。
早めに司会者や寺社・教会と打ち合わせを行い、お布施や謝礼の確認もしておくとスムーズです。
事務手続きはまとめて行う
死亡届や火葬許可、火葬場の予約は故人ごとに必要です。位牌・遺影・棺・骨壺・名札・会葬礼状も人数分をそろえます。式が一つでも準備や手続きはは二件分という前提で進めましょう。
死亡届はそれぞれ必要となるので、提出期限や窓口の受付時間を先に確認します。火葬場は続けて利用できる枠があるかを担当者に相談します。
連絡係を決め、印鑑・身分証・委任状などの必要なものはチェック表にまとめて管理するとミスを防げます。
葬儀の進行を共有する
安置から通夜・葬儀・告別式・出棺・火葬・収骨までの大まかな流れを、葬儀社担当者と家族で「当日の進行表」として共有しておくと安心です。
合同葬儀の場合、二人分の弔辞や読経、焼香が加わるぶん、時間が長くなりがちです。高齢の参列者が多い場合は式次第を少し簡潔にし、途中に短い休憩や着席の案内を入れると負担が和らぎます。
変更が生じたときは、その都度スタッフや親族で共有しましょう。予備の時間を少し持たせると当日のゆとりが生まれます。
その中で大切なのは、家族が同じ前提で話せる状態をつくること。状況と気持ちに合う形を、落ち着いて選びましょう。
葬儀を合同で行うか、分けて行うかの判断

葬儀を合同にすると準備や連絡が一本化でき、短い時間で一連の儀式を終えやすくなります。しかし、当日の案内や席順への配慮が欠かせません。
別々に行えば気持ちに寄り添いやすく、宗教や式の希望にも合わせやすいですが、手配は二度必要になります。
判断の参考になるよう、ここでは合同葬儀と別々の葬儀それぞれの特徴を解説します。
合同葬儀のメリット
合同葬儀では会場や進行、案内を一つにまとめられるため、連絡の手間が減ります。また、参列者への案内も回数が少なく、香典や供花の取りまとめも簡単になります。
喪主挨拶や法要の段取りも一枚の計画に収まり、家族の負担が軽くなります。短期間で区切りを付けたいときに選びやすい形です。
- 連絡・調整の回数を最小限にできる
- 宗教者と司会の打合せを一本化できる
- 記録写真や礼状の体裁を統一できる
- 法要の時期や担当を早く決められる
ただし、当日の案内係は多めに配置する必要があります。
合同葬儀の注意点
合同葬儀にする場合、受付や導線が複雑になりやすく、故人ごとの香典や供花の仕分けに工夫が必要です。弔辞や焼香の順番、遺族席の並びも丁寧に決めないと、近楽を起こすことも考えられます。
スタッフや家族で進行内容をしっかりと把握し、役割分担を前日までに固めておきましょう。
- 受付を故人別のレーンに分け、表示を明確にする
- 芳名カードに「どちらへのご弔問か」を記す欄を設ける
- 弔辞・焼香は故人ごとに区切って進行する
- 戒名や洗礼名を見やすい位置に掲示する
これらの準備のほか、当日の案内の声かけを「受付は右手です」「焼香は前列からお願いします」などの短い定型句にそろえると、参列者が迷わず動けます。
合同葬儀を選ぶ目安
宗派が同じで、弔問客の顔ぶれが重なっていると進行を整えやすくなります。また、合同を望む遺志が確認できる、会場に十分な広さがある、スタッフを増員できる、といった条件がそろうと計画が組みやすいです。
家族内の役割が決まっている場合は、式の時間を短めに設計しても安心感が保てます。
葬儀を分けたほうが良い場合
宗派や式の希望が異なる、弔問客が重ならない、長時間の参列が難しい家族がいるなどの状況では、日程や会場を分けたほうが穏やかに進められます。
遺族の悲しみの度合いに差があるときも、時間を分けることで気持ちの負担が和らぎます。どちらの葬儀にも十分な時間を取ることで、家族も送り方に納得しやすくなります。
葬儀の準備と当日の運営のコツ

遺族は突然のことに動揺する暇もなく、多くの準備を行う必要があります。
まずは家族の代表者を決め、判断と連絡の窓口を一本化しましょう。書類や物品はチェック表で一元管理すると、漏れや行き違いを防げます。受付や会計など当日の役割は、親族以外の第三者に任せても良いでしょう。
ここでは、実際の手順の一例を説明します。
最初にやるべきこと
病院や警察での手続き、搬送、安置先の確保、葬儀社への連絡は、あわてず並行して進めましょう。家族の代表者とサブの連絡係を決め、弔問を受ける時間帯も早めに決めておきます。
二人分の手配はどうしても時間がかかります。おおよその所要時間を家族で共有しておくと予定にゆとりが生まれ、無理をせずに進められます。
- 代表者とサブを明確にする
- 宗派・遺志・写真データを確認する
- 会場規模と駐車場の目安を把握する
- 訃報文の雛形を用意する
手続きの流れを先に決めておくことで、抜けややり直しがぐっと減ります。
 葬儀の流れを解説 – 臨終から告別式まで、葬儀の準備と流れを徹底解説
葬儀の流れを解説 – 臨終から告別式まで、葬儀の準備と流れを徹底解説
ChatGPT:
書類と物品の準備
死亡届、火葬許可、火葬場の予約は故人ごとに必要です。位牌名、遺影、棺、骨壺、名札、会葬礼状も人数分を準備します。香典や供花の宛名も分けて整理しましょう。
合同祭壇では遺影の配置や花の色味、名札の見やすさを司会と確認しておくことが大切です。表にして共有すると、漏れを防げます。
物品チェック表(例)
| 区分 | Aさん | Bさん | 備考 |
|---|---|---|---|
| 遺影(四つ切・手札) | □ | □ | 額の色を統一 |
| 位牌・名札 | □ | □ | 読み仮名を確認 |
| 棺・骨壺 | □ | □ | サイズを確認 |
| 会葬礼状 | □ | □ | 両名を記載 |
| 香典仕分け封筒 | □ | □ | 会計簿と連動 |
チェック表は式場のスタッフや受付係と共有し、更新日を記録しておくと安心です。
訃報の出し方と香典の整理
訃報は簡潔に、二人の氏名、葬儀の方法(合同か別か)、会場・時間を記します。高齢の方には電話での連絡も併用しましょう。
受付では、香典や供花を故人別に仕分けできるようにしておくとスムーズです。
- 故人名はフルネームで記載する
- 葬儀の行い方を明記する
- 会場地図と連絡先を添える
- 香典・供花の名義の案内を入れる
短く簡潔な文面でまとめると、混乱を招きづらくなります。
 訃報連絡と案内のマナー|電話・メール・SNSの使い分けと宗教形式別のポイント
訃報連絡と案内のマナー|電話・メール・SNSの使い分けと宗教形式別のポイント
役割分担は前日までに行い、準備を整えて故人をお送りしましょう。
費用の見積もりと葬儀会社の選び方

葬儀の費用は、二人を一つの式で送る場合と日程や会場を分ける場合で配分が変わります。どちらを選んでも、増える項目とまとめられる項目があります。
まずはその仕組みを知り、見積書で確認する順番を決めておくと迷いが減ります。
費用の考え方
費用は大きく「人数で増えるもの」と「式ごとに発生するもの」の2つに分けて考えます。
- 人数で増える例
棺・骨壺・遺影・会葬礼状・安置料 など - 式ごとに発生する例
会場費・司会料・設営撤去・進行関連 など
合同なら後者の費用を一度にまとめやすく、別々なら式ごとに費用がかかります。ただし、同日・同会場で続けて行う場合は、設営費用を共通化できることもあります。
どちらの場合も葬儀社と会場の規定で変わることがあるため、事前に確認してきましょう。
見積書の確認ポイント
見積書を確認する際は、項目ごとに数と単価を分けて見ます。
別々の葬儀にすると増える費用と、合同葬儀にして一本化できる費用に注目し、比較検討しましょう。合同にするか、別々にするかを判断するための参考にもなります。
以下の視点を揃えてから担当者に説明を求めると、判断がぶれにくくなります。
不明点は口頭確認のみにせず、見積書へ注記として記載してもらいましょう。
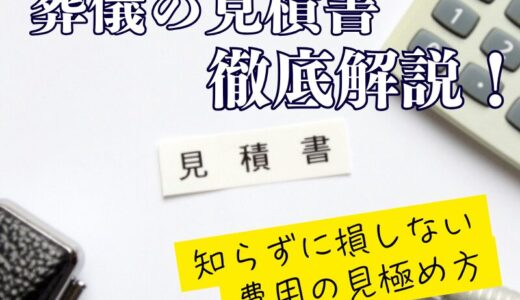 葬儀の見積書を徹底解説|知らずに損しない費用の見極め方
葬儀の見積書を徹底解説|知らずに損しない費用の見極め方
同日に行うか、日を分けるか
葬儀を別にする場合、同日に続けて行うか、別の日に行うかの判断も必要です。
同日で進める場合は、会場の広さ・安置室の空き・火葬場の予約枠がポイントになります。また、霊柩車は二台必要か、読経の時間配分はどうかも要確認です。
別の日に行う場合は故人一人ひとりに対応するため気持ちに寄り添いやすくなりますが、会場費や進行費は式の回数分かかります。安置料の日数や人員配置もあわせて試算しましょう。
葬儀会社を選ぶ基準
葬儀社を選ぶ際のポイントは、説明の分かりやすさと当日の人員体制、そして連絡の速さです。合同葬儀の経験があるか、受付や司会の増員が可能かも確認しておきましょう。
「小さなお葬式」のように家族葬や一日葬のプランが豊富な全国対応サービスなら、同日実施や別日開催の可否を比較しやすい場合があります。複数社で同条件の見積りを取り、担当者の受け答えも含めて見極めましょう。
- 連絡が取りやすいか、返答が速いか
- 見積りの説明が具体的で、注記が残るか
- 当日の人員が十分か、役割の増員が可能か
- 事後の相談窓口や連絡時間帯が明確か
金額だけでなく、担当者への信頼感や相性も重要な判断材料です。数字と担当者の対応、どちらも納得できる葬儀社を選びましょう。
最後の決め手は、担当者の誠実さと連絡の正確さです。悔いなく故人を見送ることができるよう、数字だけにとらわれず、納得できる選択をしましょう。
いつもの暮らしへ戻るために

二人以上の葬儀は、多くの方にとって初めての体験です。合同葬儀にするか別々にするかは、家族の状況と気持ちに応じて決めて問題ありません。
どちらの場合でも、手続きや連絡の方法、日程、会場の動線、役割分担、作法の伝え方を事前に整理しておくと、当日慌てずに済みます。案内文や式次第は表現を統一し、関係者全員で共有すると行き違いを防げます。
自分たちらしい形を選ぶことで、心残りを減らし、日常へ少しずつ戻るための支えとなるでしょう。







