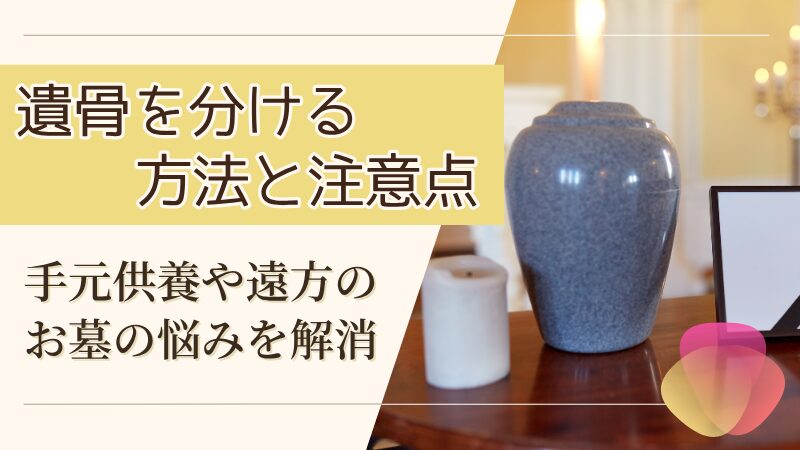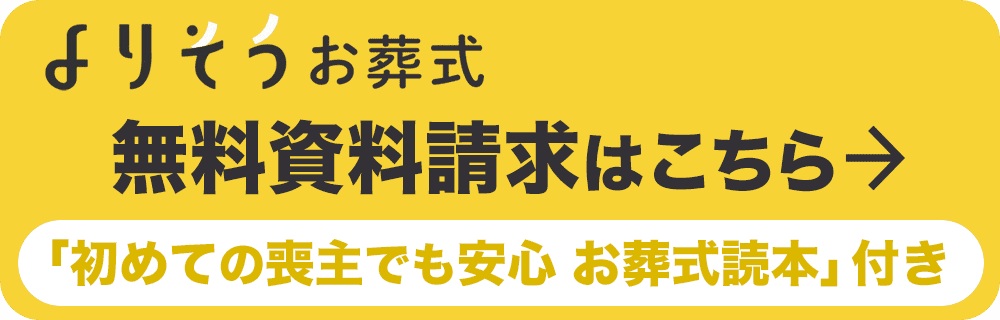お墓が遠方にあってお参りが難しい場合や、「手元供養」として遺骨を自宅に置きたい場合など、遺骨を親族間で分けるニーズが高まっています。分骨は法律的にも問題なく認められた供養方法であり、故人を身近に感じられるメリットがあります。
本記事では、分骨の具体的な手順(分骨証明書の取得方法など)やマナー、さらに自宅で遺骨を保管する際のポイントについてわかりやすくまとめました。公的機関や専門機関の情報も参照しながら解説しますので、分骨を検討している方はぜひ参考にしてください。
分骨の基本と法律

まずは「分骨」とは何か、その目的や法律上の位置づけについて確認しましょう。
遺骨を複数の骨壺に分けて別々の場所で保管・供養することを一般に「分骨」といいます。かつて日本では遺骨は一箇所にまとめて納骨するのが一般的でしたが、近年では様々な事情から分骨を希望する人も増えてきました。
この章では、分骨を選ぶ主な理由やメリット、そして分骨にまつわる法律や宗教上の考え方について解説します。
分骨が選ばれる主な理由
お墓参りや供養の形態が多様化する中、分骨を希望する理由も様々です。
例えば「お墓が遠方にあるので近くにも遺骨を置いて供養したい」というケースがあります。故人のお墓が実家や出生地にあり遠くて頻繁に訪問できない場合、遺骨の一部を手元に置いたり自宅近くの新しいお墓に納めたりすることで、日常的に故人を偲ぶことができます。
また、「親族それぞれが故人の遺骨を分けて手元で供養したい」場合もあります。たとえば兄弟姉妹で遺骨を分け合い、それぞれの家庭で供養することで、各人が故人を身近に感じられるメリットがあります。
最近増えている「手元供養(自宅供養)」も分骨の大きな理由の一つです。遺骨の一部を小さな骨壺に入れて自宅に置いたり、アクセサリーに加工して身に着けたりする手元供養を選ぶ方が増えており、分骨によって故人を常に身近に感じられる心理的な安心感が得られると言われます。
 遺骨を手元供養したい方へ:基礎知識と進め方ガイド
遺骨を手元供養したい方へ:基礎知識と進め方ガイド
分骨の法律上の扱いと注意点
「遺骨を分けるなんて法律的に大丈夫なの?」と不安に思う方もいるかもしれません。結論から言えば、分骨は日本の法律上まったく問題ありません。
厚生労働省所管の「墓地、埋葬等に関する法律施行規則」において遺骨を二箇所以上に分けて埋葬・収蔵する行為(分骨)が認められており、適切な手続きを踏めば違法ではないのです。
ただし法律上の留意点として、遺骨を埋葬できる場所は許可を受けた墓地等に限られるという規定があります。つまり、分骨して遺骨を自宅に置くこと自体は違法ではありませんが、「自宅の庭に新たにお墓を作って遺骨を埋める」ような行為は法律で禁止されています。
自宅供養する場合は遺骨を骨壺や手元供養品に入れて室内で保管する分には問題ありませんが、勝手に自宅敷地内に土葬したりしないよう注意しましょう。
参考
墓地、埋葬等に関する法律施行規則厚生労働省
分骨に対する宗教的・倫理的視点
分骨に対して法律的な問題はありませんが、宗教的・倫理的な面で抵抗を感じる方もいるのも事実です。
例えば「遺骨をバラバラにすると故人が安らかに眠れないのでは」「来世に生まれ変わるとき五体満足にならないのでは」等と心配する声もあります。宗派によって考え方は異なりますが、仏教の例で言えばお釈迦様の遺骨(仏舎利)も弟子たちによって各地に分骨された歴史があり、仏教全体として分骨そのものを否定的に見る考えは一般的ではありません。
むしろ本山納骨(各宗派の本山に遺骨の一部を納める慣習)など、昔から分骨は行われてきました。したがって分骨自体は宗教的にも必ずしもタブーではありません。
ただし感じ方は人それぞれで、特に年配のご親族の中には「縁起が悪い」と考える方もいるかもしれません。分骨を巡って心情的な対立が起きないよう、事前に親族間で十分に話し合い、理解と了承を得ておくことが大切です。
分骨は故人の遺骨を複数に分けてそれぞれ供養する方法で、法律上も問題なく認められた行為です。お墓が遠方にある場合や自宅供養を希望する場合など、分骨には故人を身近に感じられるメリットがあります。一方で宗教的・心理的な抵抗感を持つ方もいるため、親族間で十分話し合い同意を得ることが重要です。
具体的な分骨手順
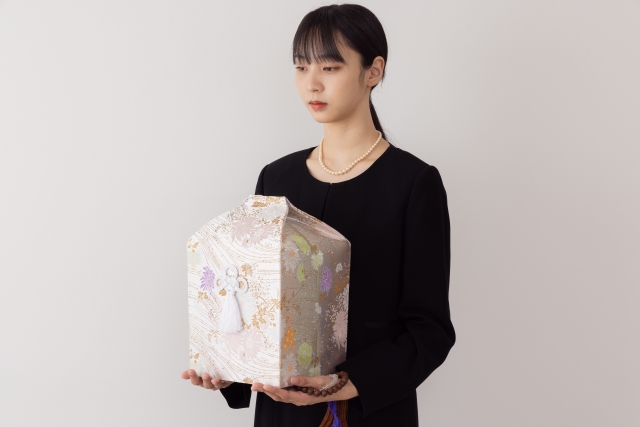
ここでは分骨を実施する具体的な方法と手順を解説します。
分骨はタイミングによって手続きが異なります。大きく分けると、「火葬直後にその場で分骨する場合」と、「既にお墓や納骨堂に納めた遺骨を後から分骨する場合」の二通りがあります。
それぞれのケースで必要な準備や取得すべき書類が違いますので、順を追って説明します。また、分骨に必要となる「分骨証明書」の入手方法や注意点についても併せて紹介します。
火葬時に分骨する場合の手順
火葬後すぐに分骨する場合は、比較的手続きが簡単で負担が少ない方法です。
火葬の前に葬儀社や火葬場の係員に「分骨を希望する」旨を必ず伝えておきましょう。火葬場で遺骨を収骨(拾骨)する際に、必要な数の骨壺に遺骨を分けて納めてもらえます。
具体的な手順は次のとおりです。
1. 骨壺を事前に準備する
分骨する数だけ骨壺が必要になるため、あらかじめ用意しておきます。葬儀社に頼めば火葬場に希望数の骨壺を手配してもらえますし、自分で事前に購入して持ち込むこともできます。
最近ではAmazonや楽天市場などの通販サイトでも手元供養用のミニ骨壺が販売されています。
葬儀社に依頼する場合でも、「小さなお葬式」や「よりそうお葬式」など大手の葬儀サービスでは希望に応じて分骨用の小さな骨壺を追加手配してもらえるので安心です。
2. 火葬場で分骨証明書を発行してもらう
火葬後に遺骨を複数に分ける際は、その場で「分骨証明書」を発行してもらいましょう。
分骨証明書とは「この遺骨は〇〇さんの遺骨の一部である」ということを証明する公的書類で、後々別の墓地に納骨する際に必要になります。火葬場で分骨する旨を伝えておけば、必要な通数の分骨証明書を火葬場の管理者が発行してくれます。
例えば3人で分骨するなら3通の証明書を発行してもらいます。分骨しない主骨の分も含め、必要枚数は葬儀社に相談するとよいでしょう。その際、火葬許可証(役所から交付される「死体埋火葬許可証」)を提出する必要がありますが、通常は葬儀社が手続きを代行してくれます。
火葬場での分骨はこのように骨壺の準備と証明書の発行依頼さえ事前にしておけばスムーズで、遺骨を持ち帰る当日までに証明書も受け取れるケースがほとんどです。
3. 遺骨をそれぞれの骨壺に納める
火葬終了後の収骨の儀において、遺族代表者などが火葬場係員の指示に従い遺骨を骨壺に収めます。通常は一つの骨壺に全ての遺骨を入れますが、分骨の場合はあらかじめ用意した複数の骨壺に遺骨を按分して収めます。
骨壺の大きさは用途に応じて選びます。すべてを納める主骨壺は一般的なサイズにし、分骨用には小さめのミニ骨壺を用意するとよいでしょう。
火葬場によっては予め粉骨(遺骨を粉状に砕くこと)して小さな壺に入れてくれる場合もあります。分骨用の遺骨量は各自の希望によりますが、「手元供養用に喉仏(のどぼとけ)だけ欲しい」というような希望があれば事前に伝えておくと対応してもらえます。
近年は手元供養用のミニ骨壺もデザインや素材が豊富で、インテリアになじむおしゃれなものが数多く市販されています。例えば陶器製や金属製、ガラス製など素材も様々で、カラーやデザインも多彩なミニ骨壺から好みに合ったものを選ぶことができます。
4. 分骨した遺骨の管理
こうして火葬場で無事に分骨が完了したら、それぞれの遺骨を自宅へ持ち帰ります。
火葬場から受け取った分骨証明書は絶対になくさないよう大切に保管してください。証明書を失くしてしまった場合、後日役所で再発行することも可能ですが手間と時間がかかります。将来いつか分骨した遺骨をお墓に納める可能性が少しでもあるなら、分骨証明書は人数分きちんと取得しておき、紛失しないよう管理しましょう。
なお、手元供養で自宅に置いておく間は証明書の提出先はありませんが、万一証明書を紛失しても故人の死亡日や火葬日が分かれば役所で再発行できます。家族にも証明書の保管場所と故人の火葬日時を共有しておくと安心です。
既に納骨済みの場合の分骨方法

既にお墓や納骨堂に納めた遺骨を後から分骨したい場合は、火葬時よりも手順が増えますが対応は可能です。
たとえば「故郷のお墓に納骨した遺骨の一部を、新しく自宅近くにお墓を用意して分けたい」「一度お墓に納めたけれど、やはり一部を手元供養用に取り出したい」といったケースです。
この場合の主な手順は次のとおりです。
1. 墓地の管理者に連絡し、分骨証明書を発行してもらう
まず現在遺骨が納められている墓地・霊園の管理者(寺院や霊園事務所)に分骨したい旨を相談します。
管理者に所定の手続きを経て「分骨証明書」を発行してもらう必要があります。発行機関は墓地の管理主体によりますが、公営霊園なら市区町村役所、寺院墓地ならお寺が窓口になります。
申請には故人の氏名や死亡日時、埋葬日時、火葬場名などを記入する申請書と、申請者の本人確認書類、印鑑などが必要になるケースが多いです。自治体によって申請書様式が異なるため、事前に役所や寺院に確認し、申請書を取り寄せておくとスムーズです。
なお墓地側から、新たに遺骨を移動する受け入れ先(分骨先)の証明書類の提出を求められることもあります。例えば公営霊園では、分骨先の霊園使用許可証のコピー提出を求められる場合がありますので、事前に確認しましょう。
2. 閉眼供養と遺骨の取り出し作業
分骨証明書の発行手続きを進めつつ、実際にお墓から遺骨を取り出す日程を決めます。
お墓から遺骨を取り出す際には、「閉眼供養(魂抜き)」と呼ばれる儀式を行うのが一般的です。閉眼供養とは、そのお墓に宿っている故人の魂を一度抜いてあげる法要で、菩提寺の住職などに読経をお願いして執り行います。
墓石を開ける作業については、自分達でできる場合もありますが、多くは石材店や霊園スタッフに依頼します。墓石の蓋を開けて納骨室から骨壺を取り出し、必要な分だけ遺骨を分けます。取り出した遺骨は新しい骨壺か、あらかじめ用意した分骨用の容器に移しましょう。作業が終わったら墓石を元に戻します。
なお墓石の開閉作業には費用がかかり、相場は2〜5万円程度と言われます。事前に石材店等に見積もりを依頼しておくと安心です。
3. 分骨証明書の受領と遺骨の移送
墓地管理者から発行された分骨証明書を受け取り、分骨した遺骨と共に保管します。分骨先の新しいお墓や納骨堂に遺骨を納める際には、この分骨証明書を先方の管理者に提出する必要があります。
分骨証明書は分骨した遺骨それぞれに対して必要なので、分骨する人数分きちんと発行してもらってください。例えば2箇所目のお墓に一部納め、さらに自宅供養用にも取り出したという場合は、2通の証明書が必要になります。
新しい納骨先には事前に「◯◯から分骨した遺骨を納めたい」旨を伝えておき、受け入れの手続きを確認しておきましょう。
4. 新しい納骨先での納骨と開眼供養

分骨した遺骨を新しいお墓や納骨堂に納める場合、「開眼供養(魂入れ)」を行うのが慣習です。これは新しいお墓に魂を宿らせる儀式で、僧侶に読経してもらいます。
分骨先でも式典を執り行い、遺骨を納骨します。公営霊園などでは納骨の際に分骨証明書の提出と埋葬料の支払いが必要です。これで無事に分骨先への納骨が完了します。
なお、自宅で手元供養する分については納骨の必要はありませんので、自宅で適切に保管してください。
分骨証明書の取得方法
分骨をする際には「分骨証明書」という書類が重要になります。
分骨証明書は火葬場や墓地の管理者が発行する公的書類で、分骨した遺骨の身元を証明するものです。もともと遺骨を埋葬する際には「埋火葬許可証」(死亡届出後に役所から交付される許可証)を墓地に提出して納骨します。
しかし埋火葬許可証は1遺体につき1枚しか発行されずコピーも不可なため、一度提出すると返却されません。そこで、一部の遺骨を別の場所に納骨する場合に使うのが分骨証明書です。分骨証明書があれば、新たな納骨先でも遺骨を正式に受け入れてもらうことができます。逆に言えば、分骨証明書が無いと他の墓地に納骨できない場合があるので注意しましょう。特に将来的に分骨した遺骨をお墓に納める可能性があるなら、手間を惜しまず証明書を取得しておくことを強くおすすめします。
証明書の再発行については、紛失してしまった場合でも火葬場を管轄する自治体で再発行が可能です。例えば〇〇市で火葬したのであれば、その市役所に申請して再発行してもらえます。火葬を行った日付や火葬場名などの情報が必要になりますので、家族にも共有しておくと良いでしょう。再発行には日数がかかる場合がありますので、紛失しないよう気を付けましょう。
火葬時の分骨は比較的簡単で、必要数の骨壺を用意し火葬場で分骨証明書を発行してもらえば、その場で遺骨を分けて持ち帰ることができます。納骨後の分骨では墓地管理者への申請や閉眼供養・石材店による墓石開閉作業などが必要ですが、適切に手続きを踏めば実現可能です。どちらの場合も分骨証明書の取得が重要なポイントであり、将来のために人数分を発行してもらい大切に保管しておきましょう。
分骨のマナーと注意点

分骨を円滑に行うために押さえておきたいマナーや注意点を解説します。
分骨そのものは違法ではありませんが、遺骨の扱いにはデリケートな面も多く、法律や慣習を踏まえた配慮が必要です。また親族間のトラブルを避けるための心得や、自宅で遺骨を保管する際の注意事項もあります。
本章では、分骨にまつわる代表的な注意点を整理します。
親族の理解を得る重要性
分骨を実行する前に、必ず親族間で十分に話し合って同意を得ましょう。 前章でも触れましたが、法律上はお墓の継承者(祭祀承継者)に分骨の決定権があります。しかし権限があるからといって、他の家族に無断で遺骨を分けてしまうのは望ましくありません。分骨に抵抗を感じる方もいるため、勝手に進めると後々親族間のトラブルに発展する恐れがあります。
例えば「勝手に遺骨を持ち出された」と感じる人がいると、深刻な不信や確執を生む可能性があります。実際、「遺骨所有者の承諾が必要です」と多くの葬儀社の案内にも明記されています。
分骨を検討する際は、まず家族・親戚に相談し、理解と了承を得てから手続きを行うようにしましょう。「みんなが納得して気持ちよく供養できる形」を目指すことが大切です。故人を想う気持ちは皆同じですから、話し合いを通じて最善の供養方法を見つけてください。
分骨に伴う費用と手続き上の注意
分骨には多少の費用や手続きの手間がかかる点も理解しておきましょう。 火葬場で分骨証明書を発行してもらう際の手数料は各自治体によりますが、1通あたり数百円(300円程度)が一般的です。例えば一宮市では分骨証明書発行手数料は1件につき300円と定められています。
一方、お墓から取り出す場合は石材店への作業料が数万円程度発生するほか、僧侶へのお布施(閉眼供養・開眼供養)も必要になるでしょう。新しいお墓に納骨する際には墓地使用料や管理料も別途かかります。費用面の負担も考慮し、事前に見積もりを取る・予算を組むことをおすすめします。
また手続き上は、市区町村役所や墓地管理者への申請書類に不備がないよう注意しましょう。特に役所で申請する場合、故人の死亡年月日・火葬日時・火葬場所など細かな情報が求められることがあります。戸籍や火葬許可証の控えを手元に用意して正確に記入することが大切です。
自治体のホームページで申請様式を公開している場合も多いので、事前にダウンロードして必要事項を確認しておくとよいでしょう。墓地や霊園で手続きする場合も、墓地使用者の同意書や分骨後の納骨先に関する情報などが必要となるケースがあります。問い合わせの際に必要書類を確認し、漏れなく準備してください。
参考リンク
宗教儀式やマナーについて
分骨に際しては、宗教的なマナーにも配慮しましょう。お墓から遺骨を取り出す際は閉眼供養を行い、新たに納骨する際は開眼供養を行うのが慣習です。これらは必須の法律行為ではありませんが、故人やご先祖への敬意を示す大切な儀式です。菩提寺がある場合は、分骨の前後でお寺に相談し、適切な法要をお願いすると安心です。
特に田舎の実家のお墓から分骨するような場合、親族や地元の習慣にも配慮して進めましょう。突然遺骨を持ち出すと驚かれることもありますので、菩提寺や墓地管理者には事前連絡をして筋を通すことが大切です。一般に、「〇月〇日に◯◯(故人名)の遺骨の一部を分骨したいと考えています」といった形で連絡すれば、具体的な段取りを教えてもらえます。マナーを守って手続きを行えば、「ご遺骨を大切に思うからこその分骨」であることも理解してもらえるでしょう。
もう一点、分骨後の遺骨の扱いにもマナーがあります。 分骨した遺骨をどこにどのように置くかは人それぞれですが、一般的には仏壇の中や近くに置く方が多いです。リビングや寝室に置く方もいますが、他の人が嫌がらない場所・方法を選ぶ配慮も必要でしょう。遺骨を収納するミニ骨壺や手元供養品はデザイン性の高いものも多く一見して遺骨とは分からないものもありますので、インテリアに馴染む形で供養することも可能です。
どこに置くとしても、清潔かつ丁寧にお祀りすることを心がけましょう。遺骨の入った容器の周囲はホコリを払う、定期的に手を合わせる、といった気持ちで接すれば、故人も安心して側にいてくれるはずです。
自宅で遺骨を保管する際の注意

分骨後、遺骨を自宅で保管・供養する場合には、いくつか注意点があります。法律的には遺骨を自宅に置くこと自体に規制はありませんが、適切な環境で保管しないと遺骨や容器が劣化してしまう恐れがあります。
以下に主なポイントをご紹介します。
湿気に注意する
遺骨は吸湿性があり、環境によってはカビが生えることがあります。実際、「遺骨を長期間保管していたらカビが生えてしまった」という報告もあります。湿度の高い場所は避け、直射日光の当たらない風通しの良い場所に保管しましょう。
特に日本の夏場は湿度が高いので、必要に応じて乾燥剤(シリカゲル等)を骨壺に入れておくと安心です。また急激な温度変化で容器内に結露が生じるとカビの原因になるため、エアコンの風が直接当たる場所も避けた方が無難です。
万一カビが生えてしまった場合は専門業者に相談してください。
衛生管理と定期点検
遺骨そのものは無機物に近い状態ですが、保管環境によっては虫が湧くこともゼロではありません。遺骨や骨壺の周囲は清潔に保ち、定期的に点検しましょう。骨壺のフタが緩んでいないか、ひび割れなど損傷がないかも確認します。
万が一骨壺を倒して遺骨をこぼしてしまった場合は、焦らずに拾い集めて元に戻し、可能であればお線香をあげて手を合わせましょう。普段から安定した場所に置く、耐震マットを敷くなどして転倒・落下防止に努めることも大切です。
保管場所と温度管理
基本的には直射日光の当たらない涼しい場所が適しています。仏壇がある場合は仏壇内が理想ですが、ない場合でも専用のスペースや棚を設けると良いでしょう。
マンション等でスペースが限られる場合、最近は壁掛け型の小型仏壇やインテリア性の高い手元供養台も市販されています。エアコンの温風・冷風が直接当たる場所、キッチンや浴室の近くなど温度・湿度の変化が大きい場所は避けてください。
ペットや小さなお子さんが届かない高めの位置に置くなど、安全面にも配慮しましょう。
将来を見据えた書類の管理
繰り返しになりますが、自宅で保管している間も分骨証明書は大切に保管してください。手元供養していた方が亡くなった後、その遺骨を改めてお墓に納めるケースはよくあります。その際、証明書が無いと納骨できずに困ってしまいます。
ご自身は「生涯手元供養するから大丈夫」と思っていても、環境や継承者の状況が変わる可能性はあります。万が一に備えて証明書を取得・保管し、家族にも所在を知らせておくことをおすすめします。
また、遺骨を加工してアクセサリーにしたり、粉骨・散骨代行を利用したりする場合に、専門業者から証明書の提示を求められるケースがあります。遺骨ペンダントの加工サービスを行っている「ソウルジュエリー」でも、「法律上手元供養に規定は無いが、後々納骨する可能性を考えて証明書は取得しておきましょう」と案内しています。
将来起こり得るシーンを想定して、必要な書類や情報は整えておくのが賢明です。
分骨は、法律面では問題はありませんが、遺骨の埋葬は許可された墓地以外禁止されているなど守るべきルールがあります。また、親族の了承を得てから行うことが円満な分骨の秘訣です。
費用や手続き上の細かな点も事前確認し、菩提寺や関係者への連絡・儀式の実施など慣習面の配慮も怠らないようにしましょう。自宅で遺骨を保管する場合は、湿気や衛生に気を配りつつ丁寧に管理することが大切です。
まとめ

お墓が遠方にある場合や自宅供養をしたい場合に有効な「分骨」について、方法と注意点を詳しく解説しました。分骨は法律上認められた行為であり、正規の手続きを踏めば複数の骨壺に遺骨を分けて保管・埋葬することが可能です。
火葬場で分骨する場合は事前に骨壺を準備し、必要枚数の分骨証明書を発行してもらうことがポイントでした。既に納骨済みの遺骨でも、墓地管理者への申請と閉眼供養などを経て取り出すことができます。
分骨を円滑に行うには、事前に親族の理解と同意を得ておくことが大切です。また、自宅で遺骨を手元供養する際は湿気対策や衛生管理に注意し、遺骨と証明書を適切に管理しましょう。分骨によって故人を身近に感じながら供養することは、現代のニーズに合った新しい供養の形と言えます。